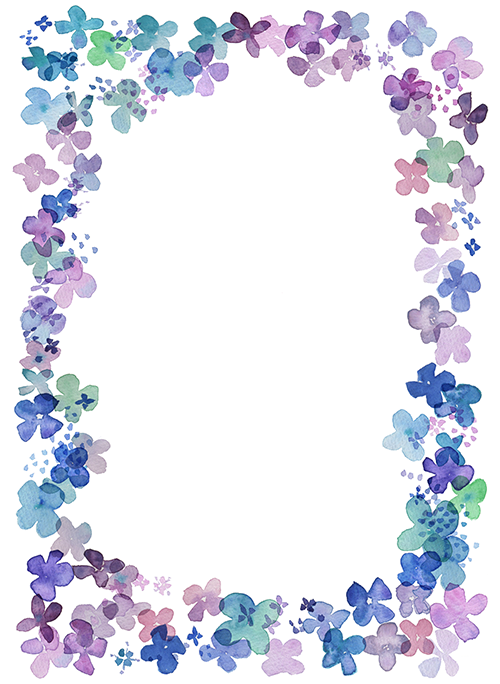君がいなくなってから三度目の夏を迎えた。君が迷惑だと言っていた蝉はもう散りかけの手持ち花火みたいにうるさく、それでいて眩く生きていた。
俺は今、再びあの村に来ている。
「透さぁ、こんなとこに来て一体何がしたいんだよ」
「まぁまぁ」
隣で文句を垂れながらもここまでついてきてくれたのは同期で俳優の横持隼人だった。横持とはあの映画で共演して以来、話すようになり、人嫌いの俺に初めてできた親友だった。スタイルのいい体系はカーゴパンツによって隠れてしまっているが、彼の身長は田舎ではそうそう見ない高さのようですれ違う人の視線が痛い。時折色めき立つ声や黄色い声援、中にはカメラを向けられることもあるが、俺があまりにも気にしない影響か最初はソワソワと落ち着きのなかった彼も人目を気にせずに歩くようになった。
砂利道で足元をとられながらも、俺たちは歩く。目的地はないまま、当てもなくふらついていた。
「なぁ、透。お前変装もなしにこんなに注目されて気持ち悪くねぇの?せめてサングラスとか、マスクとか」
「別にやましいことする訳じゃないし、俺は気にしないよ」
「だったらいいけど……お前って案外神経図太いんだな」
「ネットにあげられて拡散されて散々叩かれてもまた芸能界戻ってくるぐらいにはね」
「……その覚悟にはオレだって脱帽だよ」
時は三年前に遡る。ある夜、『神に捧げる少女』であった者の死体が海辺で、それはとても綺麗に爆ぜた。その後、村の住民は砂浜近辺で泣き崩れてその場でうずくまった男を発見し病院に連れていく。男は病院で俳優の相島透だと判明したが、無断で疾走していたこと、村の禁忌とされる少女と関わっていたことが分かると、一時は相島透の俳優生命は終わったとまで揶揄される事態となった。相島透はその後の調査によって、謎の少女の死に関わっていたものの殺人をした訳ではないということが判明し、無実が認められた。しかしそれに関連し、村の儀式である『神に捧げる少女』が全国に大々的に報道されると各地から残酷すぎるなどの非難囂囂の嵐となり、住民の反対も甲斐もなく儀式は廃止となった。
儀式を失った村は安寧を保てなくなり消滅し、相島透も戻ってこない。
誰もが疑いもせずそう思っていたのだ。
しかし、その一年後相島透は芸能界に何事もなかったかのように復帰する。
まるでその記憶丸ごと忘れてしまったかのように。
更に相島透は元の天然王子様キャラから一変し、完璧スマイルだけではなく様々な表情を見せるようになった。プライベートな話は依然無く、私生活はミステリアスなままだがファンにとってはそれがまた心を擽られるとのことで評判は上々だった。また以前にはなかった孤児や子供を支援するボランティアや寄付活動なども積極的に取り組む姿がネットに掲載されると世界中から多くの称賛を得た。初めこそ視聴者や関係者は戸惑ったものの、帰ってきた相島透は以前より更に神々しくなったと、炎上どころか逆に人気に火が付き、今ではテレビCMにも数多く出演する本物の人気俳優となったのだった。
一方村は、
「ここは変わらないな」
「あぁ、奉納祭なんてやらなくても祟りなんか起きやしないよ。古い伝統を守る言い訳だったのかも、それか神社の利益か」
「罰当たりなこと言うなぁ」
相変わらずの街並みを二人で眺めながらゆっくり息を吐いた。澄んだ空気も、ガードレールの下に根を生やしている彼岸花もそのままで、何も変わらないこの街。言い伝えなんて結局信仰心によって雁字搦めになった倫理観故のものだったのだろう。
「神に捧げる少女」のいなくなった街に大災害は起こることなく、残ったのはただ一人少女が死んだという事実だけだった。
「おー!!」
相島が突然声をあげてふらっと道から外れる。俺が首を傾げると、彼は嬉しそうな表情で振り向いた。
「たません売ってるんだけど!!オレ、たません大好きなんだよね」
「今時珍しいな」
「んね、俺も久々に見たよ。俺らが小さい時には祭りとかの定番だったのに全然見なくなった」
「そうなのか?……じゃあ逆に最近の祭りって何売ってるんだろ」
「んー、いちご飴とかワッフルとか?トッポギとかもたまにあるよね」
これがジェネーレーションギャップというやつか。聞き慣れない単語に目眩がする。変わらないと思っていたが、三年という月日は意外と大きかった。24だった俺は今や27歳になり、今や立派なアラサーという訳だ。これから益々一日一日が短くなって、体も動かなくなって、頭も回らなくなって。
あぁ、考えるだけで憂鬱になる。
「何険しい顔してんだ、お前」
ぽんと肩に手を乗せた横持によって意識が引き戻される。目の前の整った顔は怪訝そうに歪められていた。光を溢れんばかりに取り込んだ瞳には老いへの不安と絶望によって表情管理を忘れたアラサー俳優が映り込んでいる。楽観的に見えて実は何でも知っていそうな相島の前ではこの感情も見透かされてしまいそうだ。
あまりに深すぎるその瞳に、俺の口からは不意にほろりと本音が零れていた。
「俺、年を取るのが怖いよ」
「急だな」
彼はいつの間にか買ったらしいたませんを一つ押し付けてくる。一口齧ると、旨味たっぷりの中濃ソースと白身のぷりっとした食感が口いっぱいに広がった。彼も頬張ると美味いと言って笑った。それから君と歩いたあぜ道を足を踏みしめながら歩いた。踏みしめたのは普通に歩いてしまったら自分の中にある何かが決壊してしまいそうだったからだ。何かというのはまだ分からない。悲しみなのか、怒りなのか、寂しさなのか、苦しみなのか。でも今はまだ気づくべきではないきがして、泣くのを隠すときに唇を噛みしめ、上を向くのと同じように俺は君と歩いたこの道一歩一歩をゆっくりと進む。
君の記憶には全て鍵を掛けた。
「私のことは忘れてください」なんて言葉がなければ俺は君が死んでから一日も欠かすことなく、ボタンのことを思い出しただろう。しかし、あんな約束をしてしまったから無いものにせざるを得なかった。夏のひと時の思い出は熱にやられた幻だったことにして、何事もなかったように俳優活動に専念して、誰かとまた出会って結婚して、晩年はどこか静かな山奥に隠居して死のうと思っていた。
それだというのに、俺は懲りずにまたここに来てしまった。
どこに行っても、何をしていていても、あの夏のことが頭を過るのだ。忘れようとすればするほど、少女の存在は夢だと思い込もうとすればするほど。
しかし、忘れようとする努力をしなくてもいつか、君のことを忘れてしまう日が来るかもしれない。
俺の記憶からいなくなれば、『神に捧げる少女』を覚えている人はいても、ボタンという少女を憶えていられる人はもういないだろう。
ふとそう思ったときに、年を重ねるのが怖いと感じた。馬鹿らしいだろうか、いつか忘れるのは当たり前だというのに。君は忘れることを望んでいたというのに。
彼はそんな俺の考えを悟ってか、母親が子供に向かって優しく叱るときのような、柔らかな微笑を浮かべた。
「老いるから、それでも忘れられないくらいあの子の存在が透に染みついているから、お前は色んな顔をできてるんじゃないの?」
君のことを完璧に忘れていれば、今の相島透はないだろう。
そう諭されて初めて、俺は溢れそうなこの感情が言葉では表すことのできない複雑なものだと気が付いた。
彼は頬にたませんをぱんぱんに詰めたまま突然笑った。
「不老不死まで手に入れたら燃え尽き症候群にでもなってそうだ」
「そうだな」
「まぁでもお前顔がいいから、不老不死になったらファンがありがたがるよ。そのうち神として崇められそうじゃね?」
「そうなったら神社でも作って生計を建てようかな」
「この町でそんなこというなんて度胸ありすぎなんだよ」
横持が笑いを堪えきれず、周りを気にしながら失笑する。ここで某神社の神主とでも鉢合わせたら俺たちはぶっ殺される自信があった。まぁ前提として迷信で金儲けするなんて許されるものではないのだが。
足元に転がっていた石ころを蹴る。遠くに飛んで行ったそれを見つめながら、ふと君と過ごした最後の海を思い出した。
あの時は必死すぎて涙で滲んで碌に思い出すことのできないあの景色をもう一度見れば、この気持ちに整理はつくだろうか。
「横持」
ん?と首を傾げた端正な顔に俺は笑いかける。
突然のことに気味悪がる彼に、俺は更に口角を上げる。
「行きたいところがあるんだ」
彼の目が見開かれた。真っ黒な瞳孔は戸惑うように揺れたあと、蕩けるように形を柔らかく変えて細められた。
「透変わったね」
その声色はどこか嬉しそうだった。きっと彼も彼なりに心配をしてくれていたのだろう。そうだ、彼は憔悴しきって食事もまともに取れなかった俺を、見捨てずに引き上げてくれた男だ。自分の家に連れ帰って食事を取らせて、一日中意味もなく泣きはらしても何も聞かずにただくだらない話をして傍にいてくれた親友なのだ。
俺の瞳がまた一つ、色を取り戻す。
「三年前、初めて自分を変えたいと思えた。もっと自分としての人生を歩みたいと思えた」
月下美人の甘ったるい匂いが風に乗って流れてきた気がした。夜でもないのに、夏風に溶け込んだそれは息を切らしながらそれでも足を止めなかった夏を鮮麗に蘇らせる。
「たった今、変われたような気がする。少しずつだけど、ようやくその一歩を踏み出せた気がするんだ」
夏がまた一つ、香りを憶えた。
俺は今、再びあの村に来ている。
「透さぁ、こんなとこに来て一体何がしたいんだよ」
「まぁまぁ」
隣で文句を垂れながらもここまでついてきてくれたのは同期で俳優の横持隼人だった。横持とはあの映画で共演して以来、話すようになり、人嫌いの俺に初めてできた親友だった。スタイルのいい体系はカーゴパンツによって隠れてしまっているが、彼の身長は田舎ではそうそう見ない高さのようですれ違う人の視線が痛い。時折色めき立つ声や黄色い声援、中にはカメラを向けられることもあるが、俺があまりにも気にしない影響か最初はソワソワと落ち着きのなかった彼も人目を気にせずに歩くようになった。
砂利道で足元をとられながらも、俺たちは歩く。目的地はないまま、当てもなくふらついていた。
「なぁ、透。お前変装もなしにこんなに注目されて気持ち悪くねぇの?せめてサングラスとか、マスクとか」
「別にやましいことする訳じゃないし、俺は気にしないよ」
「だったらいいけど……お前って案外神経図太いんだな」
「ネットにあげられて拡散されて散々叩かれてもまた芸能界戻ってくるぐらいにはね」
「……その覚悟にはオレだって脱帽だよ」
時は三年前に遡る。ある夜、『神に捧げる少女』であった者の死体が海辺で、それはとても綺麗に爆ぜた。その後、村の住民は砂浜近辺で泣き崩れてその場でうずくまった男を発見し病院に連れていく。男は病院で俳優の相島透だと判明したが、無断で疾走していたこと、村の禁忌とされる少女と関わっていたことが分かると、一時は相島透の俳優生命は終わったとまで揶揄される事態となった。相島透はその後の調査によって、謎の少女の死に関わっていたものの殺人をした訳ではないということが判明し、無実が認められた。しかしそれに関連し、村の儀式である『神に捧げる少女』が全国に大々的に報道されると各地から残酷すぎるなどの非難囂囂の嵐となり、住民の反対も甲斐もなく儀式は廃止となった。
儀式を失った村は安寧を保てなくなり消滅し、相島透も戻ってこない。
誰もが疑いもせずそう思っていたのだ。
しかし、その一年後相島透は芸能界に何事もなかったかのように復帰する。
まるでその記憶丸ごと忘れてしまったかのように。
更に相島透は元の天然王子様キャラから一変し、完璧スマイルだけではなく様々な表情を見せるようになった。プライベートな話は依然無く、私生活はミステリアスなままだがファンにとってはそれがまた心を擽られるとのことで評判は上々だった。また以前にはなかった孤児や子供を支援するボランティアや寄付活動なども積極的に取り組む姿がネットに掲載されると世界中から多くの称賛を得た。初めこそ視聴者や関係者は戸惑ったものの、帰ってきた相島透は以前より更に神々しくなったと、炎上どころか逆に人気に火が付き、今ではテレビCMにも数多く出演する本物の人気俳優となったのだった。
一方村は、
「ここは変わらないな」
「あぁ、奉納祭なんてやらなくても祟りなんか起きやしないよ。古い伝統を守る言い訳だったのかも、それか神社の利益か」
「罰当たりなこと言うなぁ」
相変わらずの街並みを二人で眺めながらゆっくり息を吐いた。澄んだ空気も、ガードレールの下に根を生やしている彼岸花もそのままで、何も変わらないこの街。言い伝えなんて結局信仰心によって雁字搦めになった倫理観故のものだったのだろう。
「神に捧げる少女」のいなくなった街に大災害は起こることなく、残ったのはただ一人少女が死んだという事実だけだった。
「おー!!」
相島が突然声をあげてふらっと道から外れる。俺が首を傾げると、彼は嬉しそうな表情で振り向いた。
「たません売ってるんだけど!!オレ、たません大好きなんだよね」
「今時珍しいな」
「んね、俺も久々に見たよ。俺らが小さい時には祭りとかの定番だったのに全然見なくなった」
「そうなのか?……じゃあ逆に最近の祭りって何売ってるんだろ」
「んー、いちご飴とかワッフルとか?トッポギとかもたまにあるよね」
これがジェネーレーションギャップというやつか。聞き慣れない単語に目眩がする。変わらないと思っていたが、三年という月日は意外と大きかった。24だった俺は今や27歳になり、今や立派なアラサーという訳だ。これから益々一日一日が短くなって、体も動かなくなって、頭も回らなくなって。
あぁ、考えるだけで憂鬱になる。
「何険しい顔してんだ、お前」
ぽんと肩に手を乗せた横持によって意識が引き戻される。目の前の整った顔は怪訝そうに歪められていた。光を溢れんばかりに取り込んだ瞳には老いへの不安と絶望によって表情管理を忘れたアラサー俳優が映り込んでいる。楽観的に見えて実は何でも知っていそうな相島の前ではこの感情も見透かされてしまいそうだ。
あまりに深すぎるその瞳に、俺の口からは不意にほろりと本音が零れていた。
「俺、年を取るのが怖いよ」
「急だな」
彼はいつの間にか買ったらしいたませんを一つ押し付けてくる。一口齧ると、旨味たっぷりの中濃ソースと白身のぷりっとした食感が口いっぱいに広がった。彼も頬張ると美味いと言って笑った。それから君と歩いたあぜ道を足を踏みしめながら歩いた。踏みしめたのは普通に歩いてしまったら自分の中にある何かが決壊してしまいそうだったからだ。何かというのはまだ分からない。悲しみなのか、怒りなのか、寂しさなのか、苦しみなのか。でも今はまだ気づくべきではないきがして、泣くのを隠すときに唇を噛みしめ、上を向くのと同じように俺は君と歩いたこの道一歩一歩をゆっくりと進む。
君の記憶には全て鍵を掛けた。
「私のことは忘れてください」なんて言葉がなければ俺は君が死んでから一日も欠かすことなく、ボタンのことを思い出しただろう。しかし、あんな約束をしてしまったから無いものにせざるを得なかった。夏のひと時の思い出は熱にやられた幻だったことにして、何事もなかったように俳優活動に専念して、誰かとまた出会って結婚して、晩年はどこか静かな山奥に隠居して死のうと思っていた。
それだというのに、俺は懲りずにまたここに来てしまった。
どこに行っても、何をしていていても、あの夏のことが頭を過るのだ。忘れようとすればするほど、少女の存在は夢だと思い込もうとすればするほど。
しかし、忘れようとする努力をしなくてもいつか、君のことを忘れてしまう日が来るかもしれない。
俺の記憶からいなくなれば、『神に捧げる少女』を覚えている人はいても、ボタンという少女を憶えていられる人はもういないだろう。
ふとそう思ったときに、年を重ねるのが怖いと感じた。馬鹿らしいだろうか、いつか忘れるのは当たり前だというのに。君は忘れることを望んでいたというのに。
彼はそんな俺の考えを悟ってか、母親が子供に向かって優しく叱るときのような、柔らかな微笑を浮かべた。
「老いるから、それでも忘れられないくらいあの子の存在が透に染みついているから、お前は色んな顔をできてるんじゃないの?」
君のことを完璧に忘れていれば、今の相島透はないだろう。
そう諭されて初めて、俺は溢れそうなこの感情が言葉では表すことのできない複雑なものだと気が付いた。
彼は頬にたませんをぱんぱんに詰めたまま突然笑った。
「不老不死まで手に入れたら燃え尽き症候群にでもなってそうだ」
「そうだな」
「まぁでもお前顔がいいから、不老不死になったらファンがありがたがるよ。そのうち神として崇められそうじゃね?」
「そうなったら神社でも作って生計を建てようかな」
「この町でそんなこというなんて度胸ありすぎなんだよ」
横持が笑いを堪えきれず、周りを気にしながら失笑する。ここで某神社の神主とでも鉢合わせたら俺たちはぶっ殺される自信があった。まぁ前提として迷信で金儲けするなんて許されるものではないのだが。
足元に転がっていた石ころを蹴る。遠くに飛んで行ったそれを見つめながら、ふと君と過ごした最後の海を思い出した。
あの時は必死すぎて涙で滲んで碌に思い出すことのできないあの景色をもう一度見れば、この気持ちに整理はつくだろうか。
「横持」
ん?と首を傾げた端正な顔に俺は笑いかける。
突然のことに気味悪がる彼に、俺は更に口角を上げる。
「行きたいところがあるんだ」
彼の目が見開かれた。真っ黒な瞳孔は戸惑うように揺れたあと、蕩けるように形を柔らかく変えて細められた。
「透変わったね」
その声色はどこか嬉しそうだった。きっと彼も彼なりに心配をしてくれていたのだろう。そうだ、彼は憔悴しきって食事もまともに取れなかった俺を、見捨てずに引き上げてくれた男だ。自分の家に連れ帰って食事を取らせて、一日中意味もなく泣きはらしても何も聞かずにただくだらない話をして傍にいてくれた親友なのだ。
俺の瞳がまた一つ、色を取り戻す。
「三年前、初めて自分を変えたいと思えた。もっと自分としての人生を歩みたいと思えた」
月下美人の甘ったるい匂いが風に乗って流れてきた気がした。夜でもないのに、夏風に溶け込んだそれは息を切らしながらそれでも足を止めなかった夏を鮮麗に蘇らせる。
「たった今、変われたような気がする。少しずつだけど、ようやくその一歩を踏み出せた気がするんだ」
夏がまた一つ、香りを憶えた。