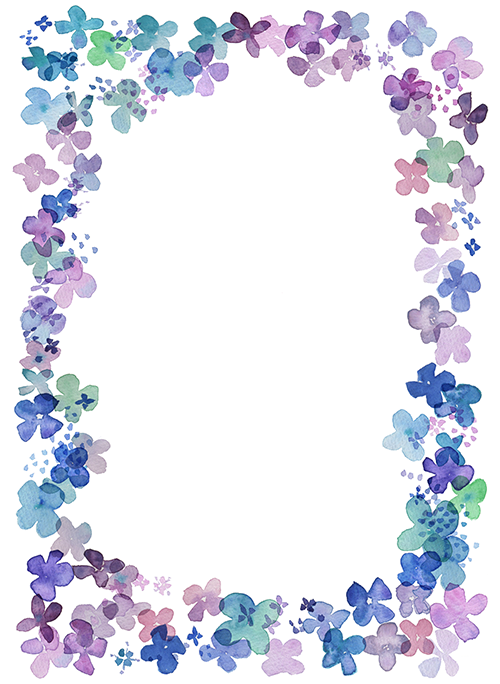月明かりの綺麗な夜だった。腰掛けた堤防は熱帯夜の続く日々にしては珍しく涼しい。背中側から陸風が吹いて、ふっと力を抜けばそのまま真っ黒な海に落ちてしまいそうだった。まぁ今落ちなくても数時間後には沈むんだけど、なんてブラックジョークを言う余裕なんてない。こんな状況でも君なら言いそうだけれど。
「……最期に一度でいいから会いたい」
ふと口にしていた言葉に嫌気がさす。
願ったところで自分から切った縁なのだ、身勝手にも程がある。それに私は透くんさえ幸せになってくれればよかった。先ほどの出来事を思い返す。人気俳優と小さな村の生贄。十人に聞けば十人とも身をわきまえろと頬を叩いてきそうな話だ。神に捧げる少女の歴史はなんと平安時代まで遡るらしい。平安時代の人々もこんな風に悩んだのかな。けれど、源氏物語では身分差も血縁関係もタブーの数々は許されていたもんな。どの時代でも御伽噺ほど甘いものはないだろう。1000年以上前に生きていた人も同じ悩みを抱えていたというのに人は未だに成長できていない。
今更自分の幸せなんて願えなかった。一度は二人で幸せになりたいとも思ったけれど、現実はそう簡単でもなかった。そんなこと今までの人生で十分痛感してきたはずなのに、ここ数日の幸福が飽和量を超えすぎていたから感覚が麻痺してしまったのだろう。結局私の正義なんて、幸せなんて、世間からすれば鼻をかみ終わったティッシュくらいどうでもいいものだった。
「でももしそれが叶っていたらどうだったんだろう」
二人でどこか遠いところに逃げたのだろうか。そこでも世間の目を気にして生活しているのだろうか。生きながらえてしまったことに罪悪感を抱きながら生きているのだろうか。私たちはそれで本当に幸せになれるのだろうか。
漠然と考えて、でもどれだけ考えたところでそれが鮮明になることはなくて、頭が痛くなったところで辞めた。
「やっぱりいいや」
そうだ、これでいい。何処にもぶつけることのできない悔しさを心の奥に押し込める。目を瞑ると、目の前で透くんが笑っていた。出会ったのはたった数日前なのに透くんは確実に私の人生を侵食している。真っ暗な夜でも鮮明に輪郭を、笑い方を、一言発する前に少しだけ漏らす息の音も全部思い出せるくらいには私に強く強く焼き付いていた。あぁ、そんな存在ができるなんて想像することすら許されなかった私が、今ではこんなにも誰かを愛しているという事実に自分自身が一番追いつけていない。
記憶の中の数少ない君の笑顔を最後に私は立ち上がると、ゆっくりと爪先に体重を掛ける。
爆弾はあと1時間後には爆発する。きっとそんなに大掛かりなものではないはずだけど、この村の人たちを巻き込むのは僅かに残された良心が許さなかった。爆破前に海に飛び込めばきっと誰にも迷惑を掛けずに爆ぜることができるだろう。
右足を宙に浮かせた。すぐ下は暗闇だった。ぎゅっと瞼を閉じる。覚悟を決めて肩を前に倒しかけたその時、
「―――ボタン」
貴方の声が、聞えてしまった。
恐る恐る振り返ると、走ってきたのか酸素を貪りながら喘ぐ青年がそこにはいた。月明かりを反射させたその瞳は間違いなく相島透だった。再び会えた嬉しさが爪まで駆け巡った後、すぐに絶望が私を侵食した。
それが表情に出てしまったのか、君は私の顔を見た瞬間に口角を下げて唇を震わせた。
透くん、
透くん、
透くん、
私、間違ってるのかな。どんな顔をすれば正解だったのかな。素直に喜べたら可愛いヒロインになれたのかな。
会いたかったよ、と言いたかった。来てくれてありがとう、と涙を流したかった。
「……透くん」
駄目だよ、と言いかけた私の唇を何かが覆う。視線を下に向けると、ほっそりとした色白な指だった。
驚いて見上げると、綺麗な顔がすぐそこにある。普通の人なら黄色い悲鳴をあげる距離でも透くんという存在にどこかほっとしてしまう。私はこの顔に見慣れてしまった自分に少しの恐怖を抱いた。改めて見れば睫毛がこんなにも長いんだとか、肌のキメが寸分の狂いもなく整っているなぁとかその場の雰囲気にそぐわないことばかり考えてしまって、思わず私も君の唇を人差し指でなぞっていた。
君は微笑を浮かべた後、深い呼吸をしてから私の目を捉える。その瞳があまりに真剣なものだったので私は指先を君の唇に置いてきたまま硬直してしまう。
「どうしてこんなことした?」
指先に唇の震えが伝わった瞬間、端正な顔が歪んだ。そうだよね、あんな置手紙一つで突然いなくなったら当然驚くよね。けれど私はうまい言い訳が思いつかなくて口をもごつかせた。そんな私の姿を見かねてか、彼は悲しそうな表情からまた別の感情で顔を歪ませる。綺麗な二重瞼の淵は赤く染まっていた。
「って聞こうと思ってた。でもやっぱり大事なのはそこじゃないなって思った」
腕をそのまま引き寄せられて私の体は広い肩幅に包み込まれる。何が起きているのか理解できなかった。ただあたたかさに身を委ねていて、脚の感覚なんて当然のようにない。今私は震えているのか、ちゃんと立てているのかすらわからなかった。ただ目の前の真っ暗な海を見つめながら、頭上から頬に注がれた熱い液体を拭う。錆びたロボットのようなぎこちない動きで首を動かすと、痙攣する指先には確かに透明な雫があった。
「ごめん、一人にして」
違う、透くんが謝ることじゃない。首を振った私を無視して君は続ける。
「俺たちは二人で一人だなんて厚かましいこと言いたい訳じゃないんだ。けど、肩先くらいは身を委ねてくれているって勝手に思ってた。実際はこんなところまで一人で抱え込ませてたけど」
「違います、それは透くんの責任じゃなくて私の責任で」
「俺が頼りないせいで、一人で死ぬことを選ばせてしまった」
なんでそれを。驚きで声がでない。
それにいつも世界を俯瞰しているようなその瞳が、今日は酷く幼く見えた。まるで叱られた後の子供みたいに純粋な申し訳なさ、後悔を蓄えながら揺れている。私はそんな君を知らなかったから狼狽して口が開かなかった。
「だから、凄く申し訳なくて」
その言葉が静かな海辺に響いた瞬間、全身が粟立つのを覚えた。私はこのタイミングでようやく自分が計画していたことが失敗に終わったと気づいた。
君を傷つけないように抜け出したのに、こんな顔にさせた私の計画はとっくに失敗していたのだ。
喉から絞り出す声のボリュームは消波ブロックにぶつかった波の音にすら、消されてしまいそうだった。
「……ごめんなさい。私、嘘吐くの下手で」
私は君の手を取ると、掴んだ手ごと腹部に当てた。二つの手にごつごつした人ならぬものが触れた瞬間、君の表情が強張り一歩後ずさりする。
「何、それ」
「私、爆発するんです」
ここまで来てしまったならしょうがない。全てを話す覚悟で君と爆弾を触れさせた。君は私の言ったことに理解が追い付かず、瞳孔を開いたまま遠くを見つめたあと「は?」と腑抜けた声を出した。
「あと一時間で死ぬんです」
「……なんとなく分かってはいた」
「えぇ?!私の嘘、そんなに下手くそでしたか?」
「いいや、君の嘘は立派なものだったよ。とある人に出会わなければ気づかないままだった」
まさか見抜かれていたとは。君が仄めかすとある人が誰だか知りたかったが、表情を見る限り口は堅そうだ。
「それで」
話を切り出す青年の声はとても小さかった。さざ波の音で消されてしまいそうな音量は、私の終わりを半分悟っているのだろうなと思った。
「助かる方法は、もうないのか」
形のよい唇が小刻みに揺れているのが見えて、胸が痛かった。それでも私は告げなければいけない、現実を。抗いきれなかった、運命を。
「はい、この爆弾は小屋を出てから72時間で爆破するものです。初日に病院に行けば助かった可能性は捨てきれませんが、まぁどのみち私は死んでいたでしょう」
ひゅっと風を切る音がして視線を上に向けると、喉を引きつらせた男が必死に酸素を貪っていた。この反応は当然のことだった、しかしそれが貴方だとは思えなかった。今にも死んじゃいそうなくらい苦しそうに息をするこの男が、いつもファンの人の前で微笑みを浮かべていた相島透だとは誰も気づかないだろう。
私は怖くなってシャツの袖を引いた。彼はまた一歩後ずさった。
「なんでもっと早く……」
君は掠れた声で一つ呟く。私は視線を正面から外した。これを言ってしまえば優しい君は更に深い傷を負うだろう。それでも私は理由を伝えなければいけない気がした。傷を、負わせたかった。私にこんな決断をさせたのが貴方だということを知ってほしかった。
「透くんのいない世界で長生きするより、貴方と一緒に知らない公園に行く方が楽しかったからです」
「俺のせいってことか?」
「透くんの責任半分、私の覚悟半分です」
予想通り絶望を体現したような表情をする君。
「じゃあ、俺も死のうか」
まるで今日の晩御飯のメニューを言うようにあっさりと告げられた死に私は慌てて首を振る。
「何言ってるんですか……?」
「もともと覚悟は決まってた。君がここで生きる選択を取るんだったら俳優を辞めて君と都落ちしようとしていたし、死ぬんだったら俺も一緒に死のうって、そう決めてたから」
反射的に骨ばった右手を取る。私はそのまま手汗の滲む掌でぎゅっと力強く握りしめた。
「これ以上透くんが自分自身を責めるなら私は今すぐにここから飛び降ります」
「それは駄目だ!」
「ならちゃんと聞いてください!」
男女の荒げる声が夜の静寂に響く。君は私が海に身を投げるのを止めるために私の左腕を、私は今にも暴走しそうな君の左腕を掴んだ。彼は眉をぴくりとあげて、掴む力を強める。筋肉のない腕には骨に直接ダメージが加わる。私の骨はぎしぎしと鳴って今にも折れてしまいそうだ。私が耐えられずに痛いと声を漏らすと、君ははっとしたように手を広げて一歩引く。自分のしたことが信じられないとばかりに呆然と掌を見つめていた。暫くしても尚、力を込めすぎて白くなったままの自分の指先を見て顔を青くさせた君は、「ごめん」と一言呟いて膝から崩れ落ちた。
「謝らないでください、冷静になれないのはお互い様です」
私の声に首を振り続ける貴方。私は腕ではなく、今度は震える掌を掴んだ。
「まず病院にいったところで爆弾処理なんてしてもらえるはずがありません。それに運よく助かったところで、世間が私を許すとは限りません。世間での私の存在は人気俳優を拐かした村の醜い少女です。退院した後、透くんとまた一緒に過ごすことは愚か再会することも許されないかもしれない」
もし透くんと出会わなかったら生贄として、出会ったとしてもこの鉄と火薬の塊に散り散りにされていた。
私が明日も生きる未来なんてはじめから存在しなかったのだ。それを伝え忘れていたことを今更ながら後悔する。出会った日に私が死ぬことを知っていたら君は今こんなにも沢山のことに縛られていないのに。それでも伝えられなかった自分の弱さと傲慢さに嫌気が差す瞬間もあった。
「考えてみたんです、もしそうなったらどうしようって」
俯いてコンクリートを視界いっぱいに捉えながら想像をする。もし私のせいで彼が笑えなくなってしまったら、私はそっと君の傍を離れて切腹をするだろう。後悔でいっぱいで、もう君に顔向けできないくらいの責任を負うだろう。
大袈裟でもないし、冗談でもない。それほど大切だったのだ。
「貴方がいない人生以上に怖いものはないと思いました」
待ち受ける死を言えなかった一番の理由はこれなのだ。出会ってしまったから、話してしまったから、私が差し伸べられた君の手を取ってしまったから、私は透くんがいない人生がどれほどモノクロだったのか気づいてしまった。
隣に立つ資格がないことは分かっていたけれど、それでも傍にいたいと願ってしまった。
右手から伝わる脈が早まる。驚いてじっと目の前の顔を見つめると、今にも泣きそうな君がちゃんとそこにいた。
「手紙に『私はもうこれ以上君を壊したくありません』と書きましたよね」
君が頷くのが視界の端で見える。
「もう私は今日までにたくさんの人の人生を壊してきました。神主、巫女、この街で豊作を願う人々。それに加えて、今度は貴方までもが私のせいで芸能界で肩身の狭い思いをして、積み上げてきたもの全て私のせいで壊されて、そこまでして私が生きる意味がどうしても見いだせなかったんです」
困り顔で笑う私の手の甲に熱いものが降り注ぐ。その正体に察しはついていたけれど、敢えて「泣いてるの?」なんて聞くことはしなかった。代わりに右手に更に強く力を込めた。
正面から向き合えば、話をすれば、もしかしたら君が病院に口利きして生き延びることも、君とひっそり生きることもできたかもしれない。
でも私は不器用だから、臆病だから、できやしなかった。
ただ愚かな選択をすることしかできなかった。
君の失った心はきっとあの牡丹みたいな一瞬でしか、救えなかったのだ。
ここで今生きていることに意味があって、生き延びた私が君を救える確実な未来なんてどこにもない。
自分の人生より、君の先に待ち受ける現実を選んだ私を神様は嗤うだろうか。
生きることより、幸せを選んだ私を神様は愚か者だと言うだろうか。
そしたら私は笑って返してやろう。
それが私が一番効率悪く生きる方法だったのだ、と。
「一人で死のうとしたことはごめんなさい。それでも君とこの村の人を巻き込まないためにはこうするしかありませんでした」
君が唐突に首筋に手を当てる。涙の膜が張った瞳は痛そうに歪められた。同じところをなぞると、ぼこぼこした炎症が線状に何本もあった。自傷行為に気づかれてしまったようだ、私は首を振り「もうしていませんよ」と答える。
小屋にいたころ、何度自分の首にペーパーナイフを当てただろう。表面の皮膚だけが切れて、頸動脈までは到達しなかった刃先を見て何度絶望しただろう。死ぬことでさえ逃げだというのに、それすらも出来ないなんて、と自己嫌悪を超越した何かに陥っていた。
少量の血液に濡れたナイフを見ながら私はいつも考えていた。
村の豊作を願い、村の人の幸せのために生き、祈り、死ぬ
意味があって生きているはずなのに、時々その意味を忘れてしまいたいと思ってしまう自分は何て醜いのだろう。
君と出会ってその考えは覆された。
正義とは何なのだろう。
代わりに考えるようになったことの一つだった。
君と出会って自分の世界はなんて狭いものだったのだろう、なんて歪んだ正しさだったのだろうと知った。
私は正しいと言われたことは何も疑わずに暮らしてきた。疑ってしまった時点で私の中の正義感は壊れて苦しむと悟っていたから。だから、他人の正しさは自分の正しさとして。不信感は、周りのせいではなく私だけがおかしいのだと一人で背負ってきた。
けれど、透くんは私が疑う気持ちを肯定してくれた。
正義の反対は別の正義と良く言う。表面上ではそんな言葉で片付けられているが、実際は互いに己の正義を押し付け合って傲慢で自分勝手な世界を他人に強要しているだけだ。それならば初めから「正しい」なんて字を使う正義なんてもの、存在しないのかもしれない。
それでも私たちは正義とは何か、考え続けなければいけない。
死ぬほど考え抜いて、時には頭皮から血が出るほど頭を掻きむしって、出た結論はきっと酷く身勝手なものなのだと思う。
貴方の隣で「ボタン」として生きたい。
少なくとも今の私にとっての正義は神に捧げる少女なんかではなく、ボタンとして生きることだった。
誰が文句を言おうと、他の正義を押し付けられようが、揺るがない。
私だけの正義だ。
喉に力を込める。この村の人全員に届くように息を吸って、吸って吸って吸って。
吐き出だした。
「私、生きててよかった」
泣きながら破顔する少女はもう『神に捧げる少女』なんてたいそうな存在ではなかった。
脆くて、臆病で、それでも自分の信念を突き通すことのできる『ボタン』という少女だった。
名前のない少女に名前を贈った青年は気づいているだろうか。
少女を変えたのは自分自身であると。
空虚な私に愛を芽生えさせたのは、君なんだと。
「これは透くんが迎えに来てくれたから気づけたことだよ」
目の前にいる青年もまた、煌めきを纏い常に穏やかな笑みを絶やさない『俳優 相島透』ではなかった。
私の言葉に目頭から大量の雫を零して、顔をあげられないほどに号泣する、不器用で、臆病で、でも誰かの為にこんなにも美しく涙を流せるただの『透くん』だった。
「君に会うまで生きる意味なんて分からなかった。毎日同じ場所で同じことをしていて、それが17年続いたあとに殺されるんだって思いながら生きてきたからさ、貴方がやって来た日は本当に驚いたんだよ」
だからどうか、申し訳ないなんて言わないでほしい。
君が不甲斐ないと思う必要なんて何一つないのだ。
「外の世界に出てから、新しいことをたくさん見れて楽しかった。普通の人が送る普通の生活がどれだけあたたかいのか、どれだけ幸せなのか、普通の日々がどれだけ美しいものなのか知ることができた。けれど同時にそれが守られるために今まで大勢の『神に捧げる少女』が亡くなったことはやっぱり必要なんだと思った」
もしかしたらこれは洗脳なのかもしれない。けれど、もしそうではなく本当に誰かの犠牲の上で幸せが営まれているのだとしたら、と思うと足がすくんだ。
「その職務を放棄した私は後ろめたい気持ちでいっぱいだった。今まで自分が生きてきた意味は誰かの幸せのためだったから、私なんかの幸せのために他の大勢の幸せを犠牲になんて出来ないって寝る前に目をつむると不安に押しつぶされそうだった」
私の手に包まれていた冷たい指先がゆっくりと動く。切り傷のある指先は私の頬を滑る。無造作な前髪から濡羽色の瞳が覗くように見えた。暗くてよく見えなかったけれど、濡れたそれは美しく揺らめいていた。
「けれど、透くんはそんな私も肯定してくれたね」
私は目を瞑ると、そっと顔を寄せた。人生で初めての自分からの接吻だった。柔らかい感触と触れる睫毛のくすぐったさにに幸せを覚える。嗚呼、世界にはまだ私の知らない幸せが沢山あるようだ。
私が照れくささに耐えきれず笑うと、君は信じられないように目を見開きながら私と目を合わせる。
「生きてていいって教えてくれてありがとう。私だけが背負えばいいものを半分背負ってくれてありがとう。自分を犠牲にしてまで私を逃がそうとしてくれてありがとう。花火を一緒にしてくれてありがとう。ここまで迎えに来てくれてありがとう。幸せを願ってくれてありがとう」
また私の目から涙が零れる。言葉一つ一つを噛みしめるように文字を声で縁取っていく。
「私は今この瞬間が幸せで堪らないよ、透くん」
ぐちゃぐちゃだった。顔も声も呂律も全部がぐちゃぐちゃで、到底人に見せられるものではなかった。それでも必死に言葉を紡いだのは全部ぶつけたかったからだ。全部を、私のありったけを、君に知ってほしかった。理解してくれなくていい、ただ君の耳に届くだけでよかった。心を揺さぶらなくていいから、たった一枚の鼓膜を揺らすだけでいい。
「だから死んじゃ駄目だよ、簡単に一緒に死ぬなんて言わないで」
語気が弱まっていくのが自分でも分かる。揺れる声を抑えて何とか最後まで言葉を絞り出す。
「君が願うのと同じように、私も数えきれないほど苦しんできた貴方に幸せになってほしいと願っている。君はまだ生きる権利があるんだから、まだ知らない沢山の幸せに出会えるよきっと」
自分だけ死ぬのはやっぱり卑怯だろうか。そんな言葉を遺して君一人に生きることを託すなんてずるいだろうか。
でもこれだけは譲れなかった。
目の前の青年は私の言葉に肯定も否定もしない。恨めしそうな視線は腹の方に一瞬向けられた後、君は嗚咽交じりの声で泣き崩れた。
潮の匂いよりも花の香りが、夜の月よりも君の後頭部が、瞳に美しく映った。別れが近づいていることがわかった。君が侵食した世界は鳥籠から見えた世界とは何一つ同じではなかった。目に映るものが全て愛おしかった。鼻を擽る君の香りも、掠れた君の声も、触れる指先の冷たさも、全部失いたくなかった。忘れたくなかった。百年後も千年後も生き続けてこの刹那に光り輝く星の瞬きみたいな時を覚えておきたかった。
「俺は、おれは」
君のつむじが持ち上げられる。目が合うと君はもう泣いてはいなかった。
「誰かにこんなに心を揺さぶられるなんて想像したこともなかった」
君が胸のあたりをくしゃりと握りしめる。白いシャツに皺と汚れが付いた。
「俺の全部なんて、少し前の俺ならここで何も言えなかったと思う。全てが空っぽで中身のない自分を全てをあげるなんておこがましくて馬鹿らしいって笑って逃げた。けど、今の俺ならちゃんと向き合える」
君はもう、空っぽではないんだね。よかった、それは……それはよかった。その時、私の大好きな瞳は真っ暗な夜に光を灯した。星よりも煌めきながら、月明かりよりも柔らかく。ほら言っただろう、君はこんなにも綺麗な人間なのだ。私はやっぱり間違えていなかったよ、どれだけ自分で醜いと言い聞かせたところで私には分かるのだ。
青年はくしゃりと笑う。
それは何度も練習した万人受けする笑顔ではない、君が失っていた子供のような笑い方だった。
「ボタンがいてくれてよかった」
時が止まったような感覚に襲われる。流れていく雲は遅くて、海の波は中々打ち消されなくて、先ほどまで鳴いていた蝉も聞こえない。止まった世界では、君だけが一人取り残されたように話続ける。
「ボタンと手を繋いで走ったときに、苦しかったけれど不思議と心は満たされていたんだ。
今までひとりぼっちで走り続けてきた俺にとって、誰かの手を引くなんて有り得なかったから。ただ横を見たときに苦しそうだけれど俺と同じように満足そうに楽しそうに走る君を見て、俺はもう一人じゃないんだって思えたんだ」
「……うん」
「同時にこの人を失いたくないとも思った。永遠なんかないって子供じゃないから分かってるけど、それでもボタンがいつまでも隣にいる未来を何度も想像してしまった」
私もだよ。私もあの日から隣に貴方がいると目の前の日差しが二乗されたように世界が眩しかった。
「俺は正直、まだ明日からこの世にボタンがいないことを受け止めきれてないよ。それに生より俺を選んだ君を許したくない」
整えられた眉がぴくりと震える。私は僅かな変化を見逃すことはできなかった。君が私の手を取る。夏の夜の生ぬるい風が二人の間を通り抜け、私の髪を靡かせる。
「でも、それがボタンが俺にくれた不器用で臆病な愛だから、俺がここまで走って来たことは間違いじゃなかった」
君は笑った。きっとそれは解放を意味していた。空っぽだった君はもうそこにはいない。
私は彼の背中にそっと手を回した。あたたかい、私たちはまだ生きている。お互いがすぐ傍にいる。幸せだ、本当に夢を見ているような現実だった。
視線が噛み合う。彼の右手が頭に左手が腰に回されて強く抱き寄せられた。熱が全身に回る、頬を掠める筋張った首は少し熱い。
「好きだ」
「私も好きです」
「愛してるなんて言葉では伝えきれないくらいに、ボタンのことを想ってる」
その言葉の送り主が透くんだということが幸せで、愛おしくて、愛で溺れて死んでしまいそうだ。
ただ私たちには時間が足りなかっただけなのだ。
それ以外は全てそこにあった。
お互いたくさん傷ついて穴だらけで欠けたものばかりだったけれど、出会ってしまえば欠けていたものはすぐに埋まった。
欠陥があったことすらも忘れてしまうほど、ただ幸せで満たされていた。
これが私たちの出会う意味だったのかもしれない。
この世に神様なんていないかもしれないけれど、運命も永遠も存在しないけれど、
もしそうなら、
それは、凄く幸せなことだと思った。
「……じゃあね」
「うん……またね」
お互い最後の言葉を交わすと、名残惜しさに唇を重ねた。幸せで満たされると同時にこれが最期のキスだと悟った。肺胞全部が二酸化炭素でいっぱいになるまで唇をくっつけて、右頬に感じる睫毛を確かめて、回した腕からの熱を忘れまいとぎゅっと力を込めていた。
酸素が足りなくて私がよろめきかけて、二人の体はようやく離れる。手を繋いだまま顔を見たら気恥ずかしくて思わず笑ってしまった。
笑っているのに涙が止まらなくて、ぼろぼろと雫を零すと彼は愛おしさに満ちた眼差しでまた私を引き寄せた。大丈夫だよと何度も耳元で言ってくれているのにその声も段々と聞こえなくなってくる。不安から私は更に涙腺を緩めて嗚咽した。
「俺はボタンと反対の道を歩かなきゃいけない。頼まれたからには生きて幸せになって、ボタンのことを忘れなきゃいけない」
君の言葉は夢見心地な私を現実に引き戻すには十分だった。君の表情は分からない。君の輪郭は涙の膜でぼやけている。
「真っすぐ前に進もう。もう進みだしたら振り返らない。声も出さないし、泣くのも禁止。ただ前だけを見て歩く」
決意したのは私なのに、この震える足はどうして私のものなのだろう。
揺れる瞳に映る貴方への想いでまだ生きたいと思ってしまうのは罪だろうか。
色々な思いが駆け巡って、それからくっつけられた額との距離は君の長い睫毛を濡らす。
「大丈夫だよ、俺はボタンの強さをもう知ってる」
その言葉をしっかり受け止めてからゆっくりと自分の心に落とし込める。私なら大丈夫、私ならできる。うん、だってもう17年も耐えて生きてきたんだ。きっと、きっと私なら。
目頭をごしごしと擦ると、もう一度真っすぐ澄んだ瞳を見つめた。
「うん、私たちなら大丈夫だ」
私が破顔すると、君は驚いたように目を見開いてから目じりを下げた。
後ろを振り向くとそこはどこにでもいけそうな広い海だった。背後からスニーカーが擦れる音がして君も後ろを向いたことが分かった。一歩、一歩ゆっくりと歩みを進める。
余命残り三十分
私は今、テトラポッドの先まで来ていた。もう君が地面を蹴る音も聞こえない。
苔の生えたコンクリートの塊はとても不安定で、踏みしめていなければ今すぐにでも深海に吸い込まれてしまいそうだった。
深呼吸をして、目を閉じる。私はようやく暗黒に足を踏み入れた。
体が急速に冷やされて力の抜けた体は浮き沈みを繰り返しながら、しかし確実に海底へと引きずり込まれていく。遠のく意識の中、何故だかさっき聞こえなかった君の言葉が段々とボリュームを上げて蘇る。
大丈夫だよ
苦しいのに、辛いのに、もう死んでしまうというのに、私は君の声が脳裏で響く度に微笑みを湛えた。
幸せだったな。
これでいいのだ、これがいいのだ。
四肢に力が入らなくなり、そのうち意識を失った。そうして私は17年の生涯を終えたのだった。
「……最期に一度でいいから会いたい」
ふと口にしていた言葉に嫌気がさす。
願ったところで自分から切った縁なのだ、身勝手にも程がある。それに私は透くんさえ幸せになってくれればよかった。先ほどの出来事を思い返す。人気俳優と小さな村の生贄。十人に聞けば十人とも身をわきまえろと頬を叩いてきそうな話だ。神に捧げる少女の歴史はなんと平安時代まで遡るらしい。平安時代の人々もこんな風に悩んだのかな。けれど、源氏物語では身分差も血縁関係もタブーの数々は許されていたもんな。どの時代でも御伽噺ほど甘いものはないだろう。1000年以上前に生きていた人も同じ悩みを抱えていたというのに人は未だに成長できていない。
今更自分の幸せなんて願えなかった。一度は二人で幸せになりたいとも思ったけれど、現実はそう簡単でもなかった。そんなこと今までの人生で十分痛感してきたはずなのに、ここ数日の幸福が飽和量を超えすぎていたから感覚が麻痺してしまったのだろう。結局私の正義なんて、幸せなんて、世間からすれば鼻をかみ終わったティッシュくらいどうでもいいものだった。
「でももしそれが叶っていたらどうだったんだろう」
二人でどこか遠いところに逃げたのだろうか。そこでも世間の目を気にして生活しているのだろうか。生きながらえてしまったことに罪悪感を抱きながら生きているのだろうか。私たちはそれで本当に幸せになれるのだろうか。
漠然と考えて、でもどれだけ考えたところでそれが鮮明になることはなくて、頭が痛くなったところで辞めた。
「やっぱりいいや」
そうだ、これでいい。何処にもぶつけることのできない悔しさを心の奥に押し込める。目を瞑ると、目の前で透くんが笑っていた。出会ったのはたった数日前なのに透くんは確実に私の人生を侵食している。真っ暗な夜でも鮮明に輪郭を、笑い方を、一言発する前に少しだけ漏らす息の音も全部思い出せるくらいには私に強く強く焼き付いていた。あぁ、そんな存在ができるなんて想像することすら許されなかった私が、今ではこんなにも誰かを愛しているという事実に自分自身が一番追いつけていない。
記憶の中の数少ない君の笑顔を最後に私は立ち上がると、ゆっくりと爪先に体重を掛ける。
爆弾はあと1時間後には爆発する。きっとそんなに大掛かりなものではないはずだけど、この村の人たちを巻き込むのは僅かに残された良心が許さなかった。爆破前に海に飛び込めばきっと誰にも迷惑を掛けずに爆ぜることができるだろう。
右足を宙に浮かせた。すぐ下は暗闇だった。ぎゅっと瞼を閉じる。覚悟を決めて肩を前に倒しかけたその時、
「―――ボタン」
貴方の声が、聞えてしまった。
恐る恐る振り返ると、走ってきたのか酸素を貪りながら喘ぐ青年がそこにはいた。月明かりを反射させたその瞳は間違いなく相島透だった。再び会えた嬉しさが爪まで駆け巡った後、すぐに絶望が私を侵食した。
それが表情に出てしまったのか、君は私の顔を見た瞬間に口角を下げて唇を震わせた。
透くん、
透くん、
透くん、
私、間違ってるのかな。どんな顔をすれば正解だったのかな。素直に喜べたら可愛いヒロインになれたのかな。
会いたかったよ、と言いたかった。来てくれてありがとう、と涙を流したかった。
「……透くん」
駄目だよ、と言いかけた私の唇を何かが覆う。視線を下に向けると、ほっそりとした色白な指だった。
驚いて見上げると、綺麗な顔がすぐそこにある。普通の人なら黄色い悲鳴をあげる距離でも透くんという存在にどこかほっとしてしまう。私はこの顔に見慣れてしまった自分に少しの恐怖を抱いた。改めて見れば睫毛がこんなにも長いんだとか、肌のキメが寸分の狂いもなく整っているなぁとかその場の雰囲気にそぐわないことばかり考えてしまって、思わず私も君の唇を人差し指でなぞっていた。
君は微笑を浮かべた後、深い呼吸をしてから私の目を捉える。その瞳があまりに真剣なものだったので私は指先を君の唇に置いてきたまま硬直してしまう。
「どうしてこんなことした?」
指先に唇の震えが伝わった瞬間、端正な顔が歪んだ。そうだよね、あんな置手紙一つで突然いなくなったら当然驚くよね。けれど私はうまい言い訳が思いつかなくて口をもごつかせた。そんな私の姿を見かねてか、彼は悲しそうな表情からまた別の感情で顔を歪ませる。綺麗な二重瞼の淵は赤く染まっていた。
「って聞こうと思ってた。でもやっぱり大事なのはそこじゃないなって思った」
腕をそのまま引き寄せられて私の体は広い肩幅に包み込まれる。何が起きているのか理解できなかった。ただあたたかさに身を委ねていて、脚の感覚なんて当然のようにない。今私は震えているのか、ちゃんと立てているのかすらわからなかった。ただ目の前の真っ暗な海を見つめながら、頭上から頬に注がれた熱い液体を拭う。錆びたロボットのようなぎこちない動きで首を動かすと、痙攣する指先には確かに透明な雫があった。
「ごめん、一人にして」
違う、透くんが謝ることじゃない。首を振った私を無視して君は続ける。
「俺たちは二人で一人だなんて厚かましいこと言いたい訳じゃないんだ。けど、肩先くらいは身を委ねてくれているって勝手に思ってた。実際はこんなところまで一人で抱え込ませてたけど」
「違います、それは透くんの責任じゃなくて私の責任で」
「俺が頼りないせいで、一人で死ぬことを選ばせてしまった」
なんでそれを。驚きで声がでない。
それにいつも世界を俯瞰しているようなその瞳が、今日は酷く幼く見えた。まるで叱られた後の子供みたいに純粋な申し訳なさ、後悔を蓄えながら揺れている。私はそんな君を知らなかったから狼狽して口が開かなかった。
「だから、凄く申し訳なくて」
その言葉が静かな海辺に響いた瞬間、全身が粟立つのを覚えた。私はこのタイミングでようやく自分が計画していたことが失敗に終わったと気づいた。
君を傷つけないように抜け出したのに、こんな顔にさせた私の計画はとっくに失敗していたのだ。
喉から絞り出す声のボリュームは消波ブロックにぶつかった波の音にすら、消されてしまいそうだった。
「……ごめんなさい。私、嘘吐くの下手で」
私は君の手を取ると、掴んだ手ごと腹部に当てた。二つの手にごつごつした人ならぬものが触れた瞬間、君の表情が強張り一歩後ずさりする。
「何、それ」
「私、爆発するんです」
ここまで来てしまったならしょうがない。全てを話す覚悟で君と爆弾を触れさせた。君は私の言ったことに理解が追い付かず、瞳孔を開いたまま遠くを見つめたあと「は?」と腑抜けた声を出した。
「あと一時間で死ぬんです」
「……なんとなく分かってはいた」
「えぇ?!私の嘘、そんなに下手くそでしたか?」
「いいや、君の嘘は立派なものだったよ。とある人に出会わなければ気づかないままだった」
まさか見抜かれていたとは。君が仄めかすとある人が誰だか知りたかったが、表情を見る限り口は堅そうだ。
「それで」
話を切り出す青年の声はとても小さかった。さざ波の音で消されてしまいそうな音量は、私の終わりを半分悟っているのだろうなと思った。
「助かる方法は、もうないのか」
形のよい唇が小刻みに揺れているのが見えて、胸が痛かった。それでも私は告げなければいけない、現実を。抗いきれなかった、運命を。
「はい、この爆弾は小屋を出てから72時間で爆破するものです。初日に病院に行けば助かった可能性は捨てきれませんが、まぁどのみち私は死んでいたでしょう」
ひゅっと風を切る音がして視線を上に向けると、喉を引きつらせた男が必死に酸素を貪っていた。この反応は当然のことだった、しかしそれが貴方だとは思えなかった。今にも死んじゃいそうなくらい苦しそうに息をするこの男が、いつもファンの人の前で微笑みを浮かべていた相島透だとは誰も気づかないだろう。
私は怖くなってシャツの袖を引いた。彼はまた一歩後ずさった。
「なんでもっと早く……」
君は掠れた声で一つ呟く。私は視線を正面から外した。これを言ってしまえば優しい君は更に深い傷を負うだろう。それでも私は理由を伝えなければいけない気がした。傷を、負わせたかった。私にこんな決断をさせたのが貴方だということを知ってほしかった。
「透くんのいない世界で長生きするより、貴方と一緒に知らない公園に行く方が楽しかったからです」
「俺のせいってことか?」
「透くんの責任半分、私の覚悟半分です」
予想通り絶望を体現したような表情をする君。
「じゃあ、俺も死のうか」
まるで今日の晩御飯のメニューを言うようにあっさりと告げられた死に私は慌てて首を振る。
「何言ってるんですか……?」
「もともと覚悟は決まってた。君がここで生きる選択を取るんだったら俳優を辞めて君と都落ちしようとしていたし、死ぬんだったら俺も一緒に死のうって、そう決めてたから」
反射的に骨ばった右手を取る。私はそのまま手汗の滲む掌でぎゅっと力強く握りしめた。
「これ以上透くんが自分自身を責めるなら私は今すぐにここから飛び降ります」
「それは駄目だ!」
「ならちゃんと聞いてください!」
男女の荒げる声が夜の静寂に響く。君は私が海に身を投げるのを止めるために私の左腕を、私は今にも暴走しそうな君の左腕を掴んだ。彼は眉をぴくりとあげて、掴む力を強める。筋肉のない腕には骨に直接ダメージが加わる。私の骨はぎしぎしと鳴って今にも折れてしまいそうだ。私が耐えられずに痛いと声を漏らすと、君ははっとしたように手を広げて一歩引く。自分のしたことが信じられないとばかりに呆然と掌を見つめていた。暫くしても尚、力を込めすぎて白くなったままの自分の指先を見て顔を青くさせた君は、「ごめん」と一言呟いて膝から崩れ落ちた。
「謝らないでください、冷静になれないのはお互い様です」
私の声に首を振り続ける貴方。私は腕ではなく、今度は震える掌を掴んだ。
「まず病院にいったところで爆弾処理なんてしてもらえるはずがありません。それに運よく助かったところで、世間が私を許すとは限りません。世間での私の存在は人気俳優を拐かした村の醜い少女です。退院した後、透くんとまた一緒に過ごすことは愚か再会することも許されないかもしれない」
もし透くんと出会わなかったら生贄として、出会ったとしてもこの鉄と火薬の塊に散り散りにされていた。
私が明日も生きる未来なんてはじめから存在しなかったのだ。それを伝え忘れていたことを今更ながら後悔する。出会った日に私が死ぬことを知っていたら君は今こんなにも沢山のことに縛られていないのに。それでも伝えられなかった自分の弱さと傲慢さに嫌気が差す瞬間もあった。
「考えてみたんです、もしそうなったらどうしようって」
俯いてコンクリートを視界いっぱいに捉えながら想像をする。もし私のせいで彼が笑えなくなってしまったら、私はそっと君の傍を離れて切腹をするだろう。後悔でいっぱいで、もう君に顔向けできないくらいの責任を負うだろう。
大袈裟でもないし、冗談でもない。それほど大切だったのだ。
「貴方がいない人生以上に怖いものはないと思いました」
待ち受ける死を言えなかった一番の理由はこれなのだ。出会ってしまったから、話してしまったから、私が差し伸べられた君の手を取ってしまったから、私は透くんがいない人生がどれほどモノクロだったのか気づいてしまった。
隣に立つ資格がないことは分かっていたけれど、それでも傍にいたいと願ってしまった。
右手から伝わる脈が早まる。驚いてじっと目の前の顔を見つめると、今にも泣きそうな君がちゃんとそこにいた。
「手紙に『私はもうこれ以上君を壊したくありません』と書きましたよね」
君が頷くのが視界の端で見える。
「もう私は今日までにたくさんの人の人生を壊してきました。神主、巫女、この街で豊作を願う人々。それに加えて、今度は貴方までもが私のせいで芸能界で肩身の狭い思いをして、積み上げてきたもの全て私のせいで壊されて、そこまでして私が生きる意味がどうしても見いだせなかったんです」
困り顔で笑う私の手の甲に熱いものが降り注ぐ。その正体に察しはついていたけれど、敢えて「泣いてるの?」なんて聞くことはしなかった。代わりに右手に更に強く力を込めた。
正面から向き合えば、話をすれば、もしかしたら君が病院に口利きして生き延びることも、君とひっそり生きることもできたかもしれない。
でも私は不器用だから、臆病だから、できやしなかった。
ただ愚かな選択をすることしかできなかった。
君の失った心はきっとあの牡丹みたいな一瞬でしか、救えなかったのだ。
ここで今生きていることに意味があって、生き延びた私が君を救える確実な未来なんてどこにもない。
自分の人生より、君の先に待ち受ける現実を選んだ私を神様は嗤うだろうか。
生きることより、幸せを選んだ私を神様は愚か者だと言うだろうか。
そしたら私は笑って返してやろう。
それが私が一番効率悪く生きる方法だったのだ、と。
「一人で死のうとしたことはごめんなさい。それでも君とこの村の人を巻き込まないためにはこうするしかありませんでした」
君が唐突に首筋に手を当てる。涙の膜が張った瞳は痛そうに歪められた。同じところをなぞると、ぼこぼこした炎症が線状に何本もあった。自傷行為に気づかれてしまったようだ、私は首を振り「もうしていませんよ」と答える。
小屋にいたころ、何度自分の首にペーパーナイフを当てただろう。表面の皮膚だけが切れて、頸動脈までは到達しなかった刃先を見て何度絶望しただろう。死ぬことでさえ逃げだというのに、それすらも出来ないなんて、と自己嫌悪を超越した何かに陥っていた。
少量の血液に濡れたナイフを見ながら私はいつも考えていた。
村の豊作を願い、村の人の幸せのために生き、祈り、死ぬ
意味があって生きているはずなのに、時々その意味を忘れてしまいたいと思ってしまう自分は何て醜いのだろう。
君と出会ってその考えは覆された。
正義とは何なのだろう。
代わりに考えるようになったことの一つだった。
君と出会って自分の世界はなんて狭いものだったのだろう、なんて歪んだ正しさだったのだろうと知った。
私は正しいと言われたことは何も疑わずに暮らしてきた。疑ってしまった時点で私の中の正義感は壊れて苦しむと悟っていたから。だから、他人の正しさは自分の正しさとして。不信感は、周りのせいではなく私だけがおかしいのだと一人で背負ってきた。
けれど、透くんは私が疑う気持ちを肯定してくれた。
正義の反対は別の正義と良く言う。表面上ではそんな言葉で片付けられているが、実際は互いに己の正義を押し付け合って傲慢で自分勝手な世界を他人に強要しているだけだ。それならば初めから「正しい」なんて字を使う正義なんてもの、存在しないのかもしれない。
それでも私たちは正義とは何か、考え続けなければいけない。
死ぬほど考え抜いて、時には頭皮から血が出るほど頭を掻きむしって、出た結論はきっと酷く身勝手なものなのだと思う。
貴方の隣で「ボタン」として生きたい。
少なくとも今の私にとっての正義は神に捧げる少女なんかではなく、ボタンとして生きることだった。
誰が文句を言おうと、他の正義を押し付けられようが、揺るがない。
私だけの正義だ。
喉に力を込める。この村の人全員に届くように息を吸って、吸って吸って吸って。
吐き出だした。
「私、生きててよかった」
泣きながら破顔する少女はもう『神に捧げる少女』なんてたいそうな存在ではなかった。
脆くて、臆病で、それでも自分の信念を突き通すことのできる『ボタン』という少女だった。
名前のない少女に名前を贈った青年は気づいているだろうか。
少女を変えたのは自分自身であると。
空虚な私に愛を芽生えさせたのは、君なんだと。
「これは透くんが迎えに来てくれたから気づけたことだよ」
目の前にいる青年もまた、煌めきを纏い常に穏やかな笑みを絶やさない『俳優 相島透』ではなかった。
私の言葉に目頭から大量の雫を零して、顔をあげられないほどに号泣する、不器用で、臆病で、でも誰かの為にこんなにも美しく涙を流せるただの『透くん』だった。
「君に会うまで生きる意味なんて分からなかった。毎日同じ場所で同じことをしていて、それが17年続いたあとに殺されるんだって思いながら生きてきたからさ、貴方がやって来た日は本当に驚いたんだよ」
だからどうか、申し訳ないなんて言わないでほしい。
君が不甲斐ないと思う必要なんて何一つないのだ。
「外の世界に出てから、新しいことをたくさん見れて楽しかった。普通の人が送る普通の生活がどれだけあたたかいのか、どれだけ幸せなのか、普通の日々がどれだけ美しいものなのか知ることができた。けれど同時にそれが守られるために今まで大勢の『神に捧げる少女』が亡くなったことはやっぱり必要なんだと思った」
もしかしたらこれは洗脳なのかもしれない。けれど、もしそうではなく本当に誰かの犠牲の上で幸せが営まれているのだとしたら、と思うと足がすくんだ。
「その職務を放棄した私は後ろめたい気持ちでいっぱいだった。今まで自分が生きてきた意味は誰かの幸せのためだったから、私なんかの幸せのために他の大勢の幸せを犠牲になんて出来ないって寝る前に目をつむると不安に押しつぶされそうだった」
私の手に包まれていた冷たい指先がゆっくりと動く。切り傷のある指先は私の頬を滑る。無造作な前髪から濡羽色の瞳が覗くように見えた。暗くてよく見えなかったけれど、濡れたそれは美しく揺らめいていた。
「けれど、透くんはそんな私も肯定してくれたね」
私は目を瞑ると、そっと顔を寄せた。人生で初めての自分からの接吻だった。柔らかい感触と触れる睫毛のくすぐったさにに幸せを覚える。嗚呼、世界にはまだ私の知らない幸せが沢山あるようだ。
私が照れくささに耐えきれず笑うと、君は信じられないように目を見開きながら私と目を合わせる。
「生きてていいって教えてくれてありがとう。私だけが背負えばいいものを半分背負ってくれてありがとう。自分を犠牲にしてまで私を逃がそうとしてくれてありがとう。花火を一緒にしてくれてありがとう。ここまで迎えに来てくれてありがとう。幸せを願ってくれてありがとう」
また私の目から涙が零れる。言葉一つ一つを噛みしめるように文字を声で縁取っていく。
「私は今この瞬間が幸せで堪らないよ、透くん」
ぐちゃぐちゃだった。顔も声も呂律も全部がぐちゃぐちゃで、到底人に見せられるものではなかった。それでも必死に言葉を紡いだのは全部ぶつけたかったからだ。全部を、私のありったけを、君に知ってほしかった。理解してくれなくていい、ただ君の耳に届くだけでよかった。心を揺さぶらなくていいから、たった一枚の鼓膜を揺らすだけでいい。
「だから死んじゃ駄目だよ、簡単に一緒に死ぬなんて言わないで」
語気が弱まっていくのが自分でも分かる。揺れる声を抑えて何とか最後まで言葉を絞り出す。
「君が願うのと同じように、私も数えきれないほど苦しんできた貴方に幸せになってほしいと願っている。君はまだ生きる権利があるんだから、まだ知らない沢山の幸せに出会えるよきっと」
自分だけ死ぬのはやっぱり卑怯だろうか。そんな言葉を遺して君一人に生きることを託すなんてずるいだろうか。
でもこれだけは譲れなかった。
目の前の青年は私の言葉に肯定も否定もしない。恨めしそうな視線は腹の方に一瞬向けられた後、君は嗚咽交じりの声で泣き崩れた。
潮の匂いよりも花の香りが、夜の月よりも君の後頭部が、瞳に美しく映った。別れが近づいていることがわかった。君が侵食した世界は鳥籠から見えた世界とは何一つ同じではなかった。目に映るものが全て愛おしかった。鼻を擽る君の香りも、掠れた君の声も、触れる指先の冷たさも、全部失いたくなかった。忘れたくなかった。百年後も千年後も生き続けてこの刹那に光り輝く星の瞬きみたいな時を覚えておきたかった。
「俺は、おれは」
君のつむじが持ち上げられる。目が合うと君はもう泣いてはいなかった。
「誰かにこんなに心を揺さぶられるなんて想像したこともなかった」
君が胸のあたりをくしゃりと握りしめる。白いシャツに皺と汚れが付いた。
「俺の全部なんて、少し前の俺ならここで何も言えなかったと思う。全てが空っぽで中身のない自分を全てをあげるなんておこがましくて馬鹿らしいって笑って逃げた。けど、今の俺ならちゃんと向き合える」
君はもう、空っぽではないんだね。よかった、それは……それはよかった。その時、私の大好きな瞳は真っ暗な夜に光を灯した。星よりも煌めきながら、月明かりよりも柔らかく。ほら言っただろう、君はこんなにも綺麗な人間なのだ。私はやっぱり間違えていなかったよ、どれだけ自分で醜いと言い聞かせたところで私には分かるのだ。
青年はくしゃりと笑う。
それは何度も練習した万人受けする笑顔ではない、君が失っていた子供のような笑い方だった。
「ボタンがいてくれてよかった」
時が止まったような感覚に襲われる。流れていく雲は遅くて、海の波は中々打ち消されなくて、先ほどまで鳴いていた蝉も聞こえない。止まった世界では、君だけが一人取り残されたように話続ける。
「ボタンと手を繋いで走ったときに、苦しかったけれど不思議と心は満たされていたんだ。
今までひとりぼっちで走り続けてきた俺にとって、誰かの手を引くなんて有り得なかったから。ただ横を見たときに苦しそうだけれど俺と同じように満足そうに楽しそうに走る君を見て、俺はもう一人じゃないんだって思えたんだ」
「……うん」
「同時にこの人を失いたくないとも思った。永遠なんかないって子供じゃないから分かってるけど、それでもボタンがいつまでも隣にいる未来を何度も想像してしまった」
私もだよ。私もあの日から隣に貴方がいると目の前の日差しが二乗されたように世界が眩しかった。
「俺は正直、まだ明日からこの世にボタンがいないことを受け止めきれてないよ。それに生より俺を選んだ君を許したくない」
整えられた眉がぴくりと震える。私は僅かな変化を見逃すことはできなかった。君が私の手を取る。夏の夜の生ぬるい風が二人の間を通り抜け、私の髪を靡かせる。
「でも、それがボタンが俺にくれた不器用で臆病な愛だから、俺がここまで走って来たことは間違いじゃなかった」
君は笑った。きっとそれは解放を意味していた。空っぽだった君はもうそこにはいない。
私は彼の背中にそっと手を回した。あたたかい、私たちはまだ生きている。お互いがすぐ傍にいる。幸せだ、本当に夢を見ているような現実だった。
視線が噛み合う。彼の右手が頭に左手が腰に回されて強く抱き寄せられた。熱が全身に回る、頬を掠める筋張った首は少し熱い。
「好きだ」
「私も好きです」
「愛してるなんて言葉では伝えきれないくらいに、ボタンのことを想ってる」
その言葉の送り主が透くんだということが幸せで、愛おしくて、愛で溺れて死んでしまいそうだ。
ただ私たちには時間が足りなかっただけなのだ。
それ以外は全てそこにあった。
お互いたくさん傷ついて穴だらけで欠けたものばかりだったけれど、出会ってしまえば欠けていたものはすぐに埋まった。
欠陥があったことすらも忘れてしまうほど、ただ幸せで満たされていた。
これが私たちの出会う意味だったのかもしれない。
この世に神様なんていないかもしれないけれど、運命も永遠も存在しないけれど、
もしそうなら、
それは、凄く幸せなことだと思った。
「……じゃあね」
「うん……またね」
お互い最後の言葉を交わすと、名残惜しさに唇を重ねた。幸せで満たされると同時にこれが最期のキスだと悟った。肺胞全部が二酸化炭素でいっぱいになるまで唇をくっつけて、右頬に感じる睫毛を確かめて、回した腕からの熱を忘れまいとぎゅっと力を込めていた。
酸素が足りなくて私がよろめきかけて、二人の体はようやく離れる。手を繋いだまま顔を見たら気恥ずかしくて思わず笑ってしまった。
笑っているのに涙が止まらなくて、ぼろぼろと雫を零すと彼は愛おしさに満ちた眼差しでまた私を引き寄せた。大丈夫だよと何度も耳元で言ってくれているのにその声も段々と聞こえなくなってくる。不安から私は更に涙腺を緩めて嗚咽した。
「俺はボタンと反対の道を歩かなきゃいけない。頼まれたからには生きて幸せになって、ボタンのことを忘れなきゃいけない」
君の言葉は夢見心地な私を現実に引き戻すには十分だった。君の表情は分からない。君の輪郭は涙の膜でぼやけている。
「真っすぐ前に進もう。もう進みだしたら振り返らない。声も出さないし、泣くのも禁止。ただ前だけを見て歩く」
決意したのは私なのに、この震える足はどうして私のものなのだろう。
揺れる瞳に映る貴方への想いでまだ生きたいと思ってしまうのは罪だろうか。
色々な思いが駆け巡って、それからくっつけられた額との距離は君の長い睫毛を濡らす。
「大丈夫だよ、俺はボタンの強さをもう知ってる」
その言葉をしっかり受け止めてからゆっくりと自分の心に落とし込める。私なら大丈夫、私ならできる。うん、だってもう17年も耐えて生きてきたんだ。きっと、きっと私なら。
目頭をごしごしと擦ると、もう一度真っすぐ澄んだ瞳を見つめた。
「うん、私たちなら大丈夫だ」
私が破顔すると、君は驚いたように目を見開いてから目じりを下げた。
後ろを振り向くとそこはどこにでもいけそうな広い海だった。背後からスニーカーが擦れる音がして君も後ろを向いたことが分かった。一歩、一歩ゆっくりと歩みを進める。
余命残り三十分
私は今、テトラポッドの先まで来ていた。もう君が地面を蹴る音も聞こえない。
苔の生えたコンクリートの塊はとても不安定で、踏みしめていなければ今すぐにでも深海に吸い込まれてしまいそうだった。
深呼吸をして、目を閉じる。私はようやく暗黒に足を踏み入れた。
体が急速に冷やされて力の抜けた体は浮き沈みを繰り返しながら、しかし確実に海底へと引きずり込まれていく。遠のく意識の中、何故だかさっき聞こえなかった君の言葉が段々とボリュームを上げて蘇る。
大丈夫だよ
苦しいのに、辛いのに、もう死んでしまうというのに、私は君の声が脳裏で響く度に微笑みを湛えた。
幸せだったな。
これでいいのだ、これがいいのだ。
四肢に力が入らなくなり、そのうち意識を失った。そうして私は17年の生涯を終えたのだった。