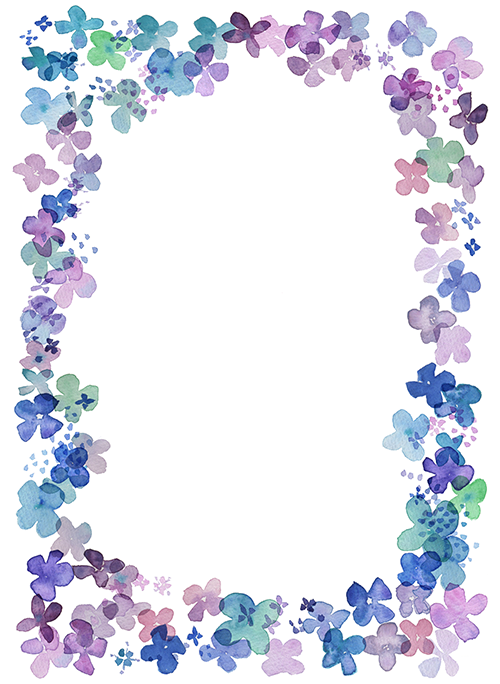拝啓 相島透さまへ
突然いなくなったことを許してください。
この手紙を読むころには貴方は酷く自分を責めているでしょう。何かボタンに嫌な思いをさせてしまっただろうか、と。私が知っている相島透はそんな人のような気がしますが、違うでしょうか。
貴方は初めに「感情のない、ロボットみたいな奴に価値なんてない」と言いましたね。けれどそれは少し違うような気がします。少なくとも貴方は自分で思っているほど冷たくも空っぽでもないと思います。
夏祭りの日、貴方は私を見捨てずに最後まで手を引いてくれました。どこかで捨てれば自分はまた何でもない顔で元の日常に戻れたのに。しかし、君は私を見捨てることが出来なかった。
そんな人がロボットな訳がないでしょう。
君の横顔には確かに愛があったように思えます。
昨日の夜、君は言いたいことがあったはずなのに黙って傍にいてくれました。私に「そのままの君でいて」と言ってくれる人は初めてです。涙が枯れるくらい、嬉しくて幸せでした。
二人でいれば欠けたものが満ちていくのが少しずつ、しかし確かに、感じることができました。
私にとって相島透は世界を広げてくれる人で、貴方にとって私は世界を色づける人。一緒にいればいるほど身に染みて透くんの存在が私の特別になっていきました。
けれども、時間が一分すぎるたびに私は君を触れることを恐れました。一秒すぎる度に君と同じ空間で息をするのが怖くなった。知れば知るほど貴方は綺麗な存在で、人に必要とされる理由がわかったから。私が君の時間を、人生を奪ってはいけない、初めから分かっていたはずなのにあまりの幸せに忘れてしまっていた事実が貴方から優しさを貰う度に痛いほど脳内で警鐘を鳴らした。
私はもう君とは一緒にいることはできません。私はもうこれ以上君を壊したくありません。さようなら、どうかお元気で。
敬具 ボタン
「なぁ……」
全て読み終わったとき、その紙は丸められて破られて文字が読めないほど原形を留めない姿に変化していた。
走って戻ってきた場所に君はいなかった。代わりに新しく白い紙が木に括り付けてあった。俺はうまく動かない手で紙を広げた。白い紙いっぱいに埋め尽くされていたのは、しっかり者の彼女にしては少し乱れた筆跡だった。
なんだよ、この手紙。
嘲笑が漏れる。引きつった口角と三日月に歪んだ目は、到底君の言う愛に溢れた人間ではなかった。
「馬鹿だな、大外れだよ。自分なんて責めてない。俺は自己中な人間だから自分の大切なものを失うのが怖いだけだ。ただ自分の欲望のためにここまで走ってきた、今失いたくないと叫んでいる。全部、君のためじゃない、自分のためだ。これが優しさだというのか、そんなふざけた話ない。俺に愛なんて」
そこまで喚いて、急に体に力が入らなくなってその場にへたり込む。乾いた笑いと、笑いにもならなかった息が体から零れる。
愛ってなんだよ、俺には分からないよ。愛があるって言われたって、俺には見えないんだ。それが何か分からない人間には、理解できないんだ。そこにあるのかすら、それに価値があるのかすら。
『透、欲張っちゃ駄目よ。もし欲張って今まで積み上げたものが全部なくなったら、お母さん透と一緒に死ぬからね』
唐突に母さんの声がして思わず耳をふさいだまましゃがみ込んだ。周りには誰もいないのに頬骨が抉られた感覚がする。頼む、消えろ。しかし、トラウマはフラッシュバックを辞めない。子役時代、現場でやりたくないことをやらされた日の帰り道に母さんに頬をぶたれた記憶が水の波紋のように頭の中に広がっていく。金属を擦り合わせたような声は絶えず俺の脳内で鳴り響いた。
『我儘で幼い自分は押し殺すの。そうすればしっかり者で、非の打ち所がない子役として沢山使ってもらえるからね。ほら笑いたくなくても、笑って。家に帰ったら笑顔の練習をしようね』
『でも、おれつまらないことは笑えな』
『俺、じゃなくて僕ってお母さん言ったよね?俺は下品だからダメって何度も何度も言ってるのにどうして分かってくれないの』
『……ごめんなさい、母さん』
『うんうん、それでいいんだよ。透は素直でいい子だもんね』
透はいい子だもんね。
呪いの言葉のようにそれが何回も何回も何回も何回も何回も何回も、何回も、なんかいも俺の心を侵食する。
「……ごめん。ごめんなさい、母さん」
地面に頭を打ち付ける。こめかみに石がぶつかって血が染み出してくる。あまりの痛さに鼻水を垂らしながら喘いでも、声は消えない。頼む消えてくれよ。もう分かってるから、欲張ったら大事なものが全部なくなるって分かってるから。
記憶の中で俺から感情を奪った人が油汚れみたいな笑顔を向けてくる。粘着質でぎとぎとした肌を歪めて爽やかさと対極の位置にいる笑顔が成人した今も忘れられない。
それでも心のどこかでは恨み切れなくて裏切れなくて、死んでほしくて、でも自分で手を下すのは怖くて。彼女のことを思い出すたびに本当に醜いのは母さんなんかじゃなくて、俺なんじゃないかと思ってしまう。
「俺なんかがボタンの生き方に何か言える権限があるのかな」
そういえばボタンはいつも腹を抑える癖があった。駄菓子屋の老人の話を聞く限り、きっと君はきっとまだ神社の秘密と繋がった鎖に縛られている。目に見えないそれは腹に何か詰められていたのかもしれない。
例えば遅効性の毒であったり、時限爆弾であったり。
そしてタマさんは逃げ出したとしても死ぬことに変わりはないことを分かっていて、あの言葉を呟いたのだ。
君は初め障子を開けることは禁止されていると言っていた。きっと老人と神に捧げる少女の件でその辺りが一層厳しくなったのだろう。孤児が溢れていた過去と違って、現代では簡単に替え玉なんて見つかりやしない。
昔でさえ厳しく、死を免れることはできなかったのに、現在は易しくなっているなんてことあるはずがない。
つまり君は、本当に死んでしまう。
しかしそれに気づいたところで、こんなぽっと出の男が出しゃばって君の死に際に立ち会う権利はあるのだろうか。
君が嘘まで吐いて守ろうとした俺の人生を、自分自身で投げ捨ててもいいのだろうか。
俺は君の苦しみのすべては知らない。一度公園で話したときに、自分よりも俺の方が辛いだろうと言っていたが、それが本当だとは俺は思えなかった。苦しんだ先に出した決断を、こんなに醜い俺が止めに行ってもいいのだろうか。
「わかんないよ、おれ……」
仰向けになって空を見上げた。空は相変わらず美しい。澄んだセレストブルーの端に滲む藍色、薄い雲が太陽の光を透かして地上を淡く照らしつける。俺はそっと瞼を閉じた。美しいものを見ると、目を逸らしたくなる。それは手紙に書かれていた感情と一緒なのかもしれない。
俺たちは臆病だ。
互いが自分を醜いと思って、傷つけることを恐れて、傷を癒そうとしても上手くいかずに空回りして。
「俺が不器用なのはボタンが一番知ってるだろ。……何が正しかったんだよ、どうするのが正解だったんだよ」
こんな時でさえ、責める言葉は相手に届かない。一人取り残されて、君が孤独死を選んだと悟ったとき胸が締め付けられる感覚と共に本当に現実か疑う感情が芽生えた。言葉をまともに受け止めれば傷つきいつか壊れてしまうと分かってから麻痺していった感覚が数十年ぶりに取り戻された予感がする。俺は確かにあの瞬間傷ついた。でも傷つけた本人は臆病だから逃げた。傷つけるなら傷つく覚悟を持つ必要があるのに君は臆病だから逃げた。
ただ臆病と優しさは紙一重だと思う。
そして君は臆病であるけれど、それ以上に人を傷つけるのを嫌う心の綺麗な人間であると俺は知っている。
一度丸めた紙をもう一度引き伸ばした。美しい文字であったけれど、俺の名前を書いたところだけ文字が揺れていた。俺の名前は視線を下にすればするほど歪んでいった。指が震えていたのか、太いところもあれば細いところも、とめはねも雑で、でもボタンの覚悟がひしひしと伝わってくる字だった。
「愚かになる覚悟……」
俺を守るために逃げた君が「さようなら」と書いたとき、どんな気持ちだっただろう。
君には愚者になる覚悟があった。
「でもごめん、俺は一人で死ぬことを選んだボタンを許せないよ」
神に捧げる少女の正しさを否定出来たら、何か変われるのだろうか。
俺は、
俺は最初から神に捧げる少女の言葉なんて聞きたくなかった。
君の心の叫びがずっとずっと聴きたかったんだ。
いつだってお人好しで、自己犠牲の塊みたいな君の、希望を乗せた声がずっと欲しかった。
小屋から出る時にあれほど言ったのに、それでも君の心の中では良心と野性がぶつかり合っていた。
誰かの為に自分の欲を見て見ぬふりする君は馬鹿だと思う。
一人で死ぬなんて間違っていると頬をぶってやりたい。
この衝動に従うのは果たして正義なのか。
「正しいのか正しくないのか、行ってから確かめればいいか」
考えるのはやめた。
『君には愚かにな勇気があるかい?』
あの時、老人の問いかけに俺は少し考えて頷いた。
『大切な人の為なら』
「母さん、ごめんな。俺は醜い人間だから欲望を捨てきることはできなかったよ」
小さく笑う。それはもう自分自身を蔑むものではなかった。こんな状況なのに心が高鳴って、俺は武者震いをする。
人生全部台無しする用意はできた。
きっと次は何にだってなれるだろう。
なら俺は愚者として、君を救いにいきたい。
たった一人の少女ために、人生を捧げたい。
もう辺りは薄暗闇に包まれていた。俺はエネルギーに満ちた体を起こして、山の斜面を駆け抜ける。ここは都会と違って街灯が沢山あるわけではない。まばらに散った光を頼りに俺はボタンがいそうな場所を走った。
関係ない人を巻き込む住宅地はないだろう。山奥はありえないし、村を出ることは多分ない。一銭も持っていない華奢な少女では険しい崖を超えることは難しいと判断した。
「あとは……どこだ」
神社か、ふと赤い鳥居が脳裏を掠める。しかしすぐにそれはないなと思った。彼女はもうけじめはつけたのだから、わざわざ行く必要はない。ならばどこだ、どこにならいる可能性がある。
焦りから普段はかかない変な汗がこめかみにへばりつく。酸欠で脳と視界の所々が欠けている。でもまだ走れる。俺は酸素の足らない頭を必死に回転させる。人に迷惑を掛けずに死ねる場所。山ではなく市街地でもない。となれば、あとこの村に残されたものは一つしかない。
「うみ」
違ったらどうする、朝から消えた君にもう間に合う確証はない。それでも飛び込まないと君に会うことはことはもうない。
戦慄く体は今、人生の舵を切ろうとしていた。それは重く、旋回するかも沈没するかも不確かな運命を決める瞬間であった。
深呼吸をする、深く深く息を吸った。瞼を閉じて、もう一度持ち上げる。
俺は踵を返すと、月明かりで青に照らされたそれを目指した。
君が死を選んだ怒りが、徐々に祈りへと変わっていく。いや怒りが完全に消えたわけではない。
それでも、段々と怒りが祈りへ、祈りが希望へ。塗り重ねられていく。
『この先進む未来が明けない夜でも、止まない雨でも、藻掻いても浮上できない海の底でも、真っ暗で先の見えない道のりでも一緒にいれば何か一つは変われるって俺は確信している』
夏祭りの日、俺を庇う君にそう言っただろう。
「……っ一緒に……いさせてくれよ……」
好きだと言えなくていい。抱きしめられなくてもいい。俳優として芸能界に戻れなくてもいい。生きて朝日を見れなくたっていい。
だから、どうか
どうか、君の息が絶えるそのときまで、傍にいさせてほしい。
夏の夜は比較的明るいはずなのに、その日は神がアイロニーを漂わせるように暗かった。
光がない世界では色は存在しないらしい。光の屈折がどうのこうのという複雑な理屈はいいのだ。光のない、色のない世界で俺はどうやって君を見つければいいのだろう。
いつもの艶のある真っ黒な髪の毛も、銀河系にあるどこかの惑星みたいな瞳も、透くんと綻ばせる表情も、何も分からなくても俺は君をまた見つけられる気がした。不確かで確かな矛盾した確証だった。俺はその確証一つで賭けをしている。
街灯の明かりが消えた道を走る。意地悪するかのように月が雲隠れした夜、頼りにするものは何もなかった。スマホだって充電切れだし、懐中電灯なんてもの持ってやしない。
「ボタン」
貴方の姿は何処にも見当たらない。前後左右全てが黒に包まれた世界を進み続ける。突然何かが足に絡みついて、危うく転びそうになった。靴に絡まったものを解くとごみ捨ての際に被せておくカラス避けだった。擦りむいた膝と手のひらからは血が滲む。しかし興奮からか痛さは全く感じなかった。膝の関節は麻痺することなく、逆に回転数を増やす。
「……そういえば神に捧げる少女、捕まったのかしら」
「そうねぇ、全然話を聞かないから怖いわぁ。あの日以来音沙汰がないみたい」
「だってもう祭りから三日も過ぎているのよ。そろそろ見つからないと、あの神主も顔がたたないんじゃない?」
顔も見えないすれ違う人の声がする。俺はそれを無視して突き進んだ。
俺が探しているのは神に捧げる少女ではない。ボタンという素朴な一人の少女だった。
段々と水平線が近づいてくる。民家の光が届かない目の前は巨大な穴が開いているみたいだった。
ようやく人気がなくなり、視界一面が真っ黒なキャンバスになる。
俺はその中で一つ、光り輝く月明かりに憑りつかれたように導かれる。
綺麗だった。すべてが、現実離れした景色だった。遠くから聞こえる蝉の声、4等星まで肉眼で見える空、無機質なコンクリートに、鼻腔を刺激する磯の香り。
青白いスポットライトの下に君は小さく佇んでいた。
穢れの知らない白いワンピースを纏い、きめの細かい肌で月光を反射させるその姿は月下美人そのものだった。
生きているうちにこんなにも美しいものを見れるのだと胸が焦げるほどに鼓動が高鳴る。気を抜けば、腰が抜けて膝から崩れ落ちてしまいそうだった。
「ボタン」
一番丁寧に君の名前を呼んだ。
ゆっくりと振り向いた君と目が合う。
さぁ答え合わせの時間だ。俺がしたことは本当に正しかったのか、君が教えてくれ。