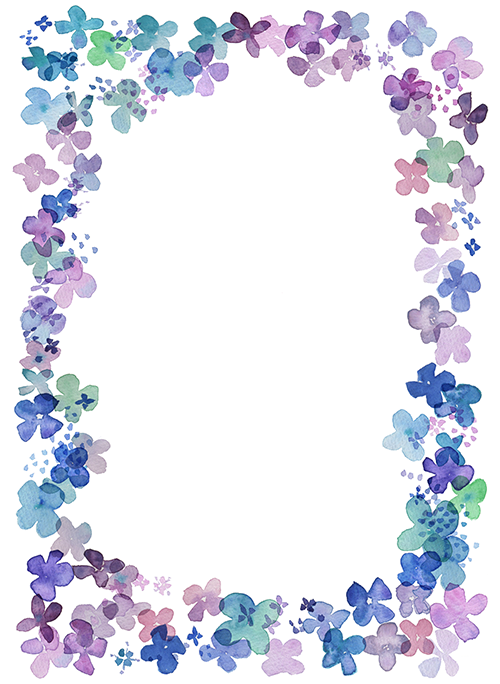その日は雨がしとしとと降る朝だった。瞼を開けると目と鼻の先には今にも消えてしまいそうな儚さを持つ青年がいた。いつの間にか二人とも寝てしまっていたのか。自分の体を触ってみるが、本当に何もされていないようだった。その事実を知ってまた胸が勝手に痛んだ。
「おはようございます」
声を掛けても穏やかな寝息が途切れることはない。きめの細かい肌は触れることも憚られるほどに綺麗で、寝息で揺れる睫毛の一本一本を観察しても飽きないくらい美しい。それはきっと人知を超えた「美しさ」なのだと思った。私は彼を応援する人々の気持ちがようやく理解出来た。子猫とか、赤ちゃんとかと同じなのだ。目の前に差し出されたら可愛いと感嘆の息を漏らし、そっと壊れないように触れて思わず目を細めてしまうのと同じように、彼を見た人々は彼を構成するパーツ全てが信じられないというようにただひたすら瞬きを繰り返して、愛さざるにはいられないのだ。
「……憎いくらいに、本当に綺麗な人」
ただ「美しい」という言葉では言い表しては失礼なほどに相島透は特別だった。例えるなら朝一番の一本の光が透明なガラスにゆっくりゆっくり注ぎ込まれるような、光でいっぱいになったガラスの器で湧き出た天然水を掬う瞬間を切り取ったような、そんな存在だ。
「怖い……」
そして同時にこれ以上近づけば、消えてしまいそうなほど淡くもあった。
私は淡いとか儚いという言葉が好きだ。窓辺に降り注ぐ雪の結晶、水に滲む水彩の青、一晩で散ってしまう花の甘い香り、夏の蛍の光、どれも消えてしまいそうだからこそ名残惜しくて、手に入ったところですぐに消えてしまいそうで愛おしい。しかし、好きだからこそそういうものを直視できない自分もいる。
いつかは消えてしまうから、私はいつまで経っても何も掴めないのか。
大事にしたいものこそ、臆病になって最後には何も残らない。
これは自分だけの弱さなのか、人が皆持つ弱さなのか、分からない。分からないから、逃げたい。
目の前の陶器肌をそっとなぞろうとして、突然君が身をよじった。それが手の気配を察してなのか、単にこの蒸し暑さへの不快感からかは分からないが私はそれ以降君に触れようとはしなかった。
むくりと起き上がり、昨日花火をした川辺まで行って顔を洗う。澄んだ水で夜中に滲んだ脂が幾らかましになったような気がした。河畔をそのまま真っすぐ進むと、煙草の吸殻とひびの入ったボールペンが落ちていた。私は煤に塗れたそれを拾うと、腐りかけの看板に張り付けられていた「熊出没注意」のチラシを無理やり剥がす。背の高い野草に隠れるように座ると、不安定な太ももの上で文字を綴る。
文字を一つ書く度に指が震えて、涙が止まらなかった。書いた文字が滲まないように何度も目を擦るが、涙腺から溢れ出す雨が止むことはなかった。嗚呼、昨夜散々泣いたはずなのにまだこんなにも流せる水分が残っているのか。段々と心の中に掛かっていた不透明な霧が文字に起こす度にはっきりと輪郭をもった。
私は書き終えた手紙を二つ折りにして呆然としたまま目の前の川の流れを見つめる。
朝日を含んだ水は蓄えきれなかった光を零しながら、流れていく。流れる先は曇り空で、下流は光が届かず薄暗い。今私の目の前の光景がどれだけ綺麗でも、流れれば流れるほど零れていく光に私は絶望した。何故だかは自分でもすぐには分からなかった。けれど、流れなければ、そのまま留まっていればその水はいつまでも太陽の下で光を目いっぱい浴びることができたのに、流れるから失う。失った先に光があるのかは誰も分からない。それは抗えない現実と少し似ているような気がした。
「ただいま戻りました」
「お帰り、ボタン。どこに行ってたんだ?」
裏山に戻ると、体を横にしながら目を開けている君がいた。私は目を擦りながらぎこちなく笑う。
「花粉症かもしれなくて、目がかゆい」
「この時期に?」
「はい、この時期に」
春の花粉にしては遅いし、秋の花粉にしては早すぎる時期に君は訝しみながらじっと私の目を見つめてくる。流石仮にでも俳優、深い瞳は簡単には逸らせそうになくて首筋に一筋冷たいものが流れた。それでも尚、口を割らない私に彼は二の句が継げない様子だった。
「嘘へったくそだな」
「すみません……」
肩をすぼませて身を縮こませる私に、彼は呆れた表情は見せるものの何も言わずに立ち上がって川のある方向へ歩き始めた。驚いて思わずズボンの裾を掴むと、もういつもの涼し気な顔に戻っていた彼の口が不満げに歪んだ。
「何か他に隠し事でもあるのか」
「いや……何も言及しないのですか?」
「……どうせ聞いたところで事実が返ってくるとは思ってないからな」
「ぐぬ、それは」
君は言葉を詰まらせる私を「そうだろう?」と言わんばかりの表情で見下ろすと、とっととその場を離れていく。私は姿が見えなくなっても彼の行った方向を見つめ続けていた。
ぼうっとただひたすら目の前を見ていると、突然その方向から声がした。
「おーい」
物静かな彼が珍しく声を張り上げているので私も反射的に返答する。
「何でしょうー?」
「俺はこのまま朝ご飯を調達するけど、ボタンはどうする。ついてくるかー」
私は少し迷ったあと、君はここにいないのについ首を振って答える。
「いえ、ここで留守番しています。まだ体が起ききってないので少し体操をします」
「……そうか」
暫くの沈黙のあと、明らかに落ち込んだ声が聞えてきた。誘えば私は当たり前のようについてくるだろうと思っていたのだろう。しかしボタンにもやらなければいけないことがあった。
芝生を踏みしめる音が段々と遠ざかっていく。私は空を見上げると、風の吹く方向を確認した。幸い雲一つない空には穏やかな夏風が吹いている。私は服の内側から朝書いた手紙を取り出すと、傍にあった木に解けないようしっかりと括りつける。
「頼んだよ」
樹皮をそっと撫でると、まだ君が寄りかかっていたぬくもりが僅かに残っていた。しかし、ごつごつとしたそれに頬を寄せても何も言葉は返ってこないし、繋がれることのない手は手持無沙汰というようにだらりと脱力する。
名残惜しいなんて思ってはいけないのに、私はずっとこのままでいいのにと思ってしまう。
その日、私は彼の傍を離れることにした。
もう君には死ぬまで会わないだろう。
「おはようございます」
声を掛けても穏やかな寝息が途切れることはない。きめの細かい肌は触れることも憚られるほどに綺麗で、寝息で揺れる睫毛の一本一本を観察しても飽きないくらい美しい。それはきっと人知を超えた「美しさ」なのだと思った。私は彼を応援する人々の気持ちがようやく理解出来た。子猫とか、赤ちゃんとかと同じなのだ。目の前に差し出されたら可愛いと感嘆の息を漏らし、そっと壊れないように触れて思わず目を細めてしまうのと同じように、彼を見た人々は彼を構成するパーツ全てが信じられないというようにただひたすら瞬きを繰り返して、愛さざるにはいられないのだ。
「……憎いくらいに、本当に綺麗な人」
ただ「美しい」という言葉では言い表しては失礼なほどに相島透は特別だった。例えるなら朝一番の一本の光が透明なガラスにゆっくりゆっくり注ぎ込まれるような、光でいっぱいになったガラスの器で湧き出た天然水を掬う瞬間を切り取ったような、そんな存在だ。
「怖い……」
そして同時にこれ以上近づけば、消えてしまいそうなほど淡くもあった。
私は淡いとか儚いという言葉が好きだ。窓辺に降り注ぐ雪の結晶、水に滲む水彩の青、一晩で散ってしまう花の甘い香り、夏の蛍の光、どれも消えてしまいそうだからこそ名残惜しくて、手に入ったところですぐに消えてしまいそうで愛おしい。しかし、好きだからこそそういうものを直視できない自分もいる。
いつかは消えてしまうから、私はいつまで経っても何も掴めないのか。
大事にしたいものこそ、臆病になって最後には何も残らない。
これは自分だけの弱さなのか、人が皆持つ弱さなのか、分からない。分からないから、逃げたい。
目の前の陶器肌をそっとなぞろうとして、突然君が身をよじった。それが手の気配を察してなのか、単にこの蒸し暑さへの不快感からかは分からないが私はそれ以降君に触れようとはしなかった。
むくりと起き上がり、昨日花火をした川辺まで行って顔を洗う。澄んだ水で夜中に滲んだ脂が幾らかましになったような気がした。河畔をそのまま真っすぐ進むと、煙草の吸殻とひびの入ったボールペンが落ちていた。私は煤に塗れたそれを拾うと、腐りかけの看板に張り付けられていた「熊出没注意」のチラシを無理やり剥がす。背の高い野草に隠れるように座ると、不安定な太ももの上で文字を綴る。
文字を一つ書く度に指が震えて、涙が止まらなかった。書いた文字が滲まないように何度も目を擦るが、涙腺から溢れ出す雨が止むことはなかった。嗚呼、昨夜散々泣いたはずなのにまだこんなにも流せる水分が残っているのか。段々と心の中に掛かっていた不透明な霧が文字に起こす度にはっきりと輪郭をもった。
私は書き終えた手紙を二つ折りにして呆然としたまま目の前の川の流れを見つめる。
朝日を含んだ水は蓄えきれなかった光を零しながら、流れていく。流れる先は曇り空で、下流は光が届かず薄暗い。今私の目の前の光景がどれだけ綺麗でも、流れれば流れるほど零れていく光に私は絶望した。何故だかは自分でもすぐには分からなかった。けれど、流れなければ、そのまま留まっていればその水はいつまでも太陽の下で光を目いっぱい浴びることができたのに、流れるから失う。失った先に光があるのかは誰も分からない。それは抗えない現実と少し似ているような気がした。
「ただいま戻りました」
「お帰り、ボタン。どこに行ってたんだ?」
裏山に戻ると、体を横にしながら目を開けている君がいた。私は目を擦りながらぎこちなく笑う。
「花粉症かもしれなくて、目がかゆい」
「この時期に?」
「はい、この時期に」
春の花粉にしては遅いし、秋の花粉にしては早すぎる時期に君は訝しみながらじっと私の目を見つめてくる。流石仮にでも俳優、深い瞳は簡単には逸らせそうになくて首筋に一筋冷たいものが流れた。それでも尚、口を割らない私に彼は二の句が継げない様子だった。
「嘘へったくそだな」
「すみません……」
肩をすぼませて身を縮こませる私に、彼は呆れた表情は見せるものの何も言わずに立ち上がって川のある方向へ歩き始めた。驚いて思わずズボンの裾を掴むと、もういつもの涼し気な顔に戻っていた彼の口が不満げに歪んだ。
「何か他に隠し事でもあるのか」
「いや……何も言及しないのですか?」
「……どうせ聞いたところで事実が返ってくるとは思ってないからな」
「ぐぬ、それは」
君は言葉を詰まらせる私を「そうだろう?」と言わんばかりの表情で見下ろすと、とっととその場を離れていく。私は姿が見えなくなっても彼の行った方向を見つめ続けていた。
ぼうっとただひたすら目の前を見ていると、突然その方向から声がした。
「おーい」
物静かな彼が珍しく声を張り上げているので私も反射的に返答する。
「何でしょうー?」
「俺はこのまま朝ご飯を調達するけど、ボタンはどうする。ついてくるかー」
私は少し迷ったあと、君はここにいないのについ首を振って答える。
「いえ、ここで留守番しています。まだ体が起ききってないので少し体操をします」
「……そうか」
暫くの沈黙のあと、明らかに落ち込んだ声が聞えてきた。誘えば私は当たり前のようについてくるだろうと思っていたのだろう。しかしボタンにもやらなければいけないことがあった。
芝生を踏みしめる音が段々と遠ざかっていく。私は空を見上げると、風の吹く方向を確認した。幸い雲一つない空には穏やかな夏風が吹いている。私は服の内側から朝書いた手紙を取り出すと、傍にあった木に解けないようしっかりと括りつける。
「頼んだよ」
樹皮をそっと撫でると、まだ君が寄りかかっていたぬくもりが僅かに残っていた。しかし、ごつごつとしたそれに頬を寄せても何も言葉は返ってこないし、繋がれることのない手は手持無沙汰というようにだらりと脱力する。
名残惜しいなんて思ってはいけないのに、私はずっとこのままでいいのにと思ってしまう。
その日、私は彼の傍を離れることにした。
もう君には死ぬまで会わないだろう。