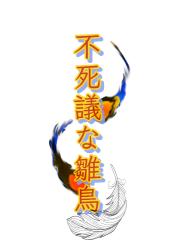* * *
僕は夜、眠れなくなった。
朝起きたら何もかもなくなってしまうのではないか、恐怖と不安で目が血走って眠れない。何度も読み返した本も幼い頃好きだった場所も、僕を想ってくれていた人たちも。跡形もなく無くなってしまうと思うと、寝付くことができない。
医者からはストレスによる不眠症だと言われた。人間の身体の都合上、眠らないことはできないらしい。寝付けなかったり、夜中何度も目が覚めたり、朝早くに目が覚めてしまったり。そのどれもが自分に当てはまった。
気絶するように意識を失い、その度に夢を見る。過ごしてきた土地、身体も動かせず、大地震で崩れていく小さな町をただただ無力に眺めるだけの夢。血の味がするほど叫び、涙をとめどく流し、災禍の絶叫が耳を劈く、そんな夢。変わり果てた荒野に自分だけが残り、幾度も幾度も死にたいと思わせられる。
そんな夢を見るようになって数週間。夜が来るのが怖くなった。だから眠らないように慣れない街を歩く。亡霊のようにフラフラと、歓楽に満ちる街を独りぼっちで。
「……」
東京屈指の歓楽街、新宿という街を宛もなく彷徨う。3月終わりの都内はまだ少し肌寒かった。そんな寒さを吹き飛ばすような、深夜0時を過ぎたころの眩い街明かり。今の僕とはまるで正反対だった。すれ違う華やかな姿をした男女を恨めしそうに視界に入れる。
「…お兄さん、お遊びどうですか?」
声がした方を見る。目の前10時の方向、一人歩くスーツの男にそう声をかける厳つめの男性がいた。スーツの人はそれを無視してスタスタと歩く。
きっとこの人たちも帰れば大切な人がいるんだろう。今の僕にはそんな存在すらいない。僕にはもう何もないし、誰もいない。
声をかけた厳つい男はすぐに諦め、僕の方を見た。
「お兄さん、お遊びどうですか?」
全く同じ言葉を発する。そう言ってこちらに歩みを進め…そのまま通り抜けて僕の後ろを歩いていた男に声をかけた。……僕に向けたものではなかった。
別に声をかけられたかった訳ではない。むしろ煩わしいだけなはずだ。にも関わらず、まるでそこに存在しないかのような扱いに、心に暗い影が落ちた。
明るすぎる歓楽街ですら、誰にも気づかれることはない。今の僕は、天涯孤独。そんな言葉がぴったりと当てはまった。
──
─
「……」
いったいどれほどの時間そんな風に過ごしていただろうか。気がつけば歩き疲れ、駅前のベンチで座り込んでいた。ここまでどうやってきたのかも、記憶に残っていない。俯いた視線に映るのは、噛み終えたガムと消えかけの煙草が落ちているアスファルトの地面だけだった。
「…君、そんなところで何してるの?」
唐突に、項垂れた頭上からそんな声が聞こえた。ゆっくりと顔を擡げる。
「もう深夜も回ってるよ」
「声聞こえてる?」
目に入ったのは、一方はふくよかで、もう一方は筋肉質な男二人組。両方とも青紺の警官服を身にまとっていた。
「……」
かけられた言葉に返すことなく、僕は2人と視線を交差させる。果たして今の僕はどんな顔をしているのだろうか。やっと誰かに声をかけられた安堵の表情か、虚ろな瞳をした覇気のない表情か。どちらにしても情けない表情なのに変わりはないだろうな。
「反応なしですか…先輩、どうします?」
「見たところ高校生か大学生か。どちらにしてもまだ若い。……君、この辺に住んでるの?家に帰れる?」
大学に入って大人になったと思ったが、どうやらまだ自分は子供に見られるようだった。そりゃそうか。成人の年齢は18歳に引き下げられたと言うが、二十歳にもなっていない子など、大人から見れば大差ないだろう。
でもそれは同時に、大人でも子供でもない自分の存在のあやふやさがわかって嫌だった。僕はそう感じたと同時に無視するようにまた俯く。
「…黙ってちゃわからないよ。ご両親も待ってるんじゃないの?」
「…っ」
ご両親も、という言葉にぴくりと反応する。
「……両親はいません」
「いない?」
頭を垂れたままそう言い放つ。
「誰も…いません」
「いないって…そりゃないでしょ」
「ネグレクトですかね?」
「この歳で?一人暮らしの不安とかそういうのじゃないの?俺にもこのくらいの娘いるからわかるよ。初めての一人暮らしって心細いから──」
先輩と呼ばれているふくよかな警官がつらつらと御託を並べ始める。
娘がいるんだ。帰ったらなんだかんだで家族がいるんだな。なにも…なにも知らないくせに。なんにもわからない癖に…。
「とにかく、ほら、帰ろうよ。おうちまで送り届けてあげるから…」
筋肉質な警官の手がぬっと伸びてきた。
「っ!」
怪しい者を見る彼の目。なんとなくその手を取るのが嫌だと思った。
そう思った刹那、体が勝手に動く。僕はベンチから立ち上がって駆け出していた。
「あっ!」
「こら、待ちなさい!」
2人の警官が慌てて僕を追い始める。自分も足はそこまで速くない、いずれ追いつかれるだろう。
「はぁ…はぁ…」
すぐに息が上がる。明らかに運動不足だ。
彼らからすればただの職務質問のつもりだったのだろう。しかし逃げる僕を見て、少し表情が変わっていった。わけも言わず逃げ出すということは後ろめたい何かがあると言っているようなものだ。無論、そんなものあるわけないのだが…今はなんとなく大人の世話になるのが嫌だった。
「うわっ…」
「なに?」
人々から驚嘆の声をぶつけられながら、駅前から歌舞伎町の方へ抜けていく。煉瓦のような石のような地面を蹴り、人混みを縫うように駆けていく。
「はぁ…はぁ…っく」
しかしすぐに信号に足止めされて喉から声が漏れる。歌舞伎町中央通りへと続く、大通りの信号。
「君、待ちなさい!…すみません、どいてください」
「…はぁ…はぁ。どいて、どいてください!」
振り返ると警官がこちらに向かってきている。しかし、人混みを逆走する形で足を取られていた。それにふくよかな警官はそこまで足が速くないようだった。
まずい、まずい。本当に捕まるのも時間の問題だ。
「……はぁ…はぁ。…っ!」
目線を前に戻すとその瞬間、信号が青になった。僕は大慌てで中央通りへ飛び込むように駆け出す。人の間をすり抜けるように走った。
「…はぁ……はぁ……」
中央通りを半分ほど走ったところで、なぜ僕は走り出したのか、なぜ警官の手を取らなかったのだろうか、とそんな考えがふと過ぎる。
「……」
徐々にペースが落ちる。街ゆく人の好奇の目線を感じ取れるほどに、緩やかに。
それはたぶん、ただの反骨心だ。あの時は、なにも助けてくれなかったのに、誰もなにもしてくれなかったのに。今、孤独になったところに手を差し伸べるなんて、そんなの──
「もっと早く…助けて欲しかった……」
思考の終着と共に、そんな言葉が口をついて出た。どれくらい走ったか。中央通りを抜けて新宿東宝ビルを超えた先。僕は足を止めてしまった。
「はぁ…はぁ…。君、突然どこに行くんだ」
「……はぁはぁ。やっと…止まった」
薄暗い路地で警官に追いつかれる。
僕は…別にこの人たちに助けて欲しかったわけではない。むしろこの人たちに限らずこの世の誰にも、どうこうできる問題とも思っていない。
僕から全てを奪った…人知を超えた災禍になど、何人たりとも太刀打ちできるわけないのだから。
「……」
無気力に警官2人を見る。
「黙ってちゃわからないよ。とにかく交番まで行こうか」
筋肉質な警官の手が僕の手首を握った。力なく、引っ張られる。ふくよかな警官はまだ息を整えていた。
もういいや、どうでも。別に逃げる必要もないし。
共に生きてくれる人もいないくせに、天涯孤独になっても僕の見た目や年齢じゃ、独りで生き抜くことさえできない。結局僕という存在を肯定してくれる人や物や居場所なんてどこにも存在しない。こんな全てを受け入れてくれそうな夜の街でさえ、僕の居場所なんてなかったんだ。
「……」
自暴自棄になり、警官に連れられようとされたその刹那──
「あのっ!」
僕らにかかる、柔らかな声が響いた。
「……ん?」
警官が動きを止め、声のほうへ向く。僕も同時に目線をあげると、そこには一人の女性がいた。膝に手をついて息を整えている。
「はぁ…はぁ…。あ、あの!その子、私の連れです!」
たった一言。その一言だけなのに、まるで僕を救い出してくれる天啓のように聞こえた。
荒らげる息を整える彼女を改めて見る。
まるで林檎のような赤を基調とした服装。古き良き喫茶店を彷彿とさせる、ギャルソン風なウェイター服。手にはパンを入れているようなバスケットをぶら下げている。マッチ売りの少女みたい、そんな感想がパッと頭に浮かぶ。格好自体は華やかな夜の街には少しだけ違和感があった。
見た目は僕より1つ2つ上に見える。目鼻立ちはくっきりとしており、高い鼻とまるで雪のような白い肌が特徴的だった。純日本人然とした顔立ちではない。外国の方だろうか。
そしてなによりも目を引いたのはミディアムヘアの美しい黒髪。数メートル離れているこの距離からでさえ、枝毛ひとつ無いであろうとわかる艶やかな髪だ。眩い灯りが照らされて、髪に綺麗なエンジェルリングができている。
まさしく眉目秀麗。およそ現存しているとは思えない…まるで御伽噺から出てきたような美しい人だった。
「……」
「……」
そんな彼女の言葉を聞き、2人の警官が顔を合わせる。
「連れといっても…ねぇ」
「急に現れてそれはちょっと…」
1,2秒のアイコンタクトをしあった後、苦笑いしながら彼女を見定めるようにそう発言した。
「駅前で待ち合わせしてたんです。そしたら突然走っていってしまったので…慌てて追いかけたんですよ?」
警官の訝しげな表情を意に介さず、凛とした様子で彼女はそう答える。
「いやぁ…なら早く声をかけてくれないと…」
「皆さん、足が速いんですもの。追いつくのは到底無理な話ですよ」
コロコロと、嘘をつく。そう、当たり前だが僕はこの人を知らない。
だが、なぜか彼女は僕のことを助けようとしていた。こんなどこの誰とも、何をしたともしれない僕のことを、だ。懐疑的な目か、もしくは誰の目にもとまらなかった僕を助けようとする。そんな優しさに僕自身の存在が肯定されたような気がした。
「とはいえなんの確証もないですから。ひとまず交番まで──」
「い、いや!待ってください!」
とはいえ、感じた優しさは警官の職務とは無縁なもの。無情にも僕を連れていこうとする警官の前に、彼女は今一度通せん坊する。
「ど、どうしたら信じて貰えますか?」
「信じるもなにも、怪しさ満点だし」
「私はその子の姉ですよ?」
「いやどう見ても血筋が…」
「異母姉弟でして…」
「そんな無茶な」
なにやら雲行きが怪しくなってきた。さっきの凛とした態度はどこへやら。目が泳いでお粗末な嘘をつく。
「じゃあこの子、名前なんていうの?」
「え?」
ふくよかな警官が意地の悪い表情でそう質問する。
「そ、それは──」
答えられるわけなど、当然ない。
「……」
僕は黙って彼女を見る。なんて言おうか必死に考えている様子だった。
万事休すなのだが、不思議と心は穏やかだった。純粋に僕のことを助けようとしてくれた、その心が嬉しかったからなのだろう。僕にとってはそれで十分だった。
「わからないんでしょ?そんな嘘をつかないで──」
だけど…だけど願わくば…この世界にいる誰かに僕の存在を肯定してほしかった。その純粋な気にかけのその先、誰かと関わって生きていけるそんな未来を──
「…わかるよ」
そう思った刹那、彼女の優し気な言葉が僕の脳内に響いた。僕を見てそう口にする彼女。その発言は当然警官に対してのものだが、まるでそんな願いに応えるかのようにも聞こえた。
「え?」
「彼の名前、わかりますよ」
彼女へ目を向ける。彼女はまっすぐ僕を見て、また凛とした表情でそう答えた。それはどこか、覚悟の決まった目をしていた。
「ちょっと待っててください」
彼女はさらにそう続け、手持ちのバスケットから1本のペットボトルを取り出した。ラベルには『100%リンゴジュース』と印字されている。よく見る250ml程度の市販のリンゴジュースだ。
「…ふぅ」
彼女は小さな吐息とともに、キャップを外した。何かを込めるように、ペットボトルのリンゴジュースを両手で包み込む。
「……」
なぜこのタイミングで…?僕はそう思った。喉が渇いたのだろうか…それにしてはタイミングがやや変だ。いや、変なことは決してないのだが、少し不思議な行動ではあった。
「……んくっ」
彼女は一つ息を吸い込み、リンゴジュースをゴクリと飲んだ。新宿の街明かりが彼女を照らす。それはどこか神々しく見え、魅入ってしまった。
「…え?」
飲むのにかかった時間は5秒もないだろう。神々しいなと感じた瞬間、彼女に起きたほんの小さな異変を発見し、僕は小さく声を漏らした。
無風な中、彼女の髪がそよ風に撫でられたかのように揺れ…そして、髪に映るエンジェルリングがほんのりと赤色に染まった。反射した紅い光が夜闇に紛れる。一瞬、照らす明かりの色の影響かとも思ったが、彼女の綺麗な黒髪の色が変わっているようにも見えた。
その変化は本当に微かなもので、注視していないとわからないものだったであろう。現に、警官2人は特に気にする様子もない。思わず魅入ってしまっていたからこそ、気が付いたことだった。
「皇…」
ゆっくりと、彼女が口を開く。
「え?」
嘘…いや、本当に彼女とは初対面だ。なのに──
「彼の名前、皇 魁人です」
僕は驚いて目を丸くした。それは…間違いなく僕の名前だった。
「君、名前合ってる?」
静かにこくりと頷く。
「そんな馬鹿な。ちょっと君、身分証出して」
警官に促されるまま、僕はジーンズのポケットから財布を取り出して身分証を見せた。
「皇、魁人…本当だ、あってる」
「他にもわかりますよ。年齢は18、今年度で19歳ですね。出身は長野県の北部の小さな町です。少し前、地震があったところです」
「……」
本当に…全部合っていた。紡がれる僕の情報は寸分違うことはない。彼女とは初めて会ったはずだ。なにせ僕は彼女の名前すら知らない。
ストーカーの類を想像してほんの少しの恐怖も過ったが、自分にそこまでの魅力はない。そんなあるかわからない恐怖よりも、自分を知っているという事実を嬉しいと感じる気持ちのほうがはるかに強かった。自分は独りではないのだと、そう思えることができた。スッと、目が微かに潤むのを感じた。
「私が都内に住んでいるので、少し面倒を見るように言われていて…それで駅前で待ち合わせしていたんですよ。…警官さん、もういいでしょうか?」
警官2人にそう声をかける彼女。もちろん、面倒云々は熟れた林檎のような真っ赤な嘘。
「…ど、どうしますか先輩」
「う、うーん…」
警官2人がひそひそと話す。想定外な出来事が起きて困惑している様子だった。
「必要であれば、他にもいろいろ答えられますけど…」
彼女はそう追撃する。むろん僕は何も言っていないが、今の彼女には何でも答えられるような雰囲気があった。
「わ、わかりました、疑ってすみません」
「…き、君も何も言わずに逃げたら疑っちゃうでしょ。それならそうといってくれないと」
「す、すみません…」
嘘を裏付ける証明の言葉の数々。僕のパーソナルな情報を知っている人間が赤の他人だなんて、警官2人にはわかる由もなかった。
──
─
「それでは、失礼します」
「あまりお姉さんに迷惑かけないように気を付けてね。夜の街は物騒だから」
「は、はい」
その場で簡単な身分調査の後、警官はその場から去っていった。僕の身分証など当然偽りではなかったし、どうやら彼女のものもそうだったようだ。名前の違いなどはあるはずだが割とすんなり開放してくれた。
「…はぁー、なんとかなってよかったぁ」
警官2人の背中が見えなくなったタイミングで、彼女が安堵のため息同時にそう呟いた。力が抜けたように、彼女は張っていた肩肘を緩める。
「……ふぅ」
僕も同じように溜息を吐きながら、警官が去っていった方向を見つめる。そして、今さっき起きた怒涛の出来事を反芻する。
思い返しても不思議なことばかりだった。初めてあった人なのに僕のことをいろいろ知っているなんて。それに、普通はめんどくさがるはずなのだ。僕が周りの人と同じ立場なら、警官に追われているなど人間など助けようなど思わない。好奇の目を向けるだけで、数分後には忘れるだろう。
彼女はどうして僕を助けてくれたのだろうか?単に人助けが好きな人なのかもしれない。もしかしたら本当に僕のことを知っている人なのか。どちらにしてもそんな関わりが、誰との繋がりもなかった僕にとって感謝でしかなかった。
「……」
横目で彼女を盗み見る。改めてみると本当に綺麗な人だ。そういえば、さっき見えた仄かに赤くなっていた髪色は綺麗な黒髪に戻っている。やはり気のせいだったのだろうか。
「さて…君!」
「は、はい」
彼女が突然声をかけてきた。盗み見ていたのがバレたような気がして少し心臓が跳ねる。やましい心は何もないが、不意に目が合うと緊張してしまうというそれだ。
「いや、そっか…魁人くんでいいかな?」
「あ、はい…なんでも大丈夫です」
彼女は口元に手を当て考え込むようなしぐさの後、僕を名前で呼んだ。久々に人に名前を呼ばれた気がする。
「魁人くん、お腹すいてる?」
「え?」
そういう彼女は軽く微笑み──
「よかったらちょっとお話ししない?」
目配せしながらそう提案してきた。
* * *
「あはは…こんなところでごめんね」
「いえ…」
四季の路という不揃いな石畳の遊歩道。そこにある路傍の石の上に並んで座る。小道には木々や草花が生い茂っている。深夜を回っているからか、人通りはそこまで多くない。新宿にもこんなところがあったんだ…と思わされた。そうはいっても深夜の歓楽街近く。ゴミなどが散乱していたり、建物の裏側が剥き出しで見えていたり、とても綺麗とは言い難い場所だった
「走ったら汗かいちゃったね。何か飲み物飲む?」
「…お、お構いなく」
気さくに話しかけてくる彼女。こうやって雑談程度に誰かと話したのは久しぶりだ。
そんなことを考えていた時、ふと嫌な思考が頭をよぎる。
「あ…そういえば…さっき持ってたリンゴジュース飲んじゃったんだった」
「そう…ですね」
「春だけどまだ冷えるよね。寒くない?」
「いえ…全然……くしゅっ」
思わずくしゃみ。3月の終わりとはいえ、まだまだ夜は冷えてる証拠だった。
「…え、ごめん。寒いよね。どっか入ろうか?」
「え!?い、いやっ!」
隣に座る彼女の顔をびっくりして見る。僕は思い切りブンブンと頭を振る。後ろには仄暗いネオンの光が小道に差していた。
「そう?風邪引いちゃうよ?」
「だ、大丈夫です!本当に!!」
「えー、そっか。……でもそんなに嫌がられると傷つくなぁ」
ニッとはにかみながら悪戯っぽくそう言う。や、やっぱりこの人…
「ふふっ、まぁいいや。そういえば、名前まだだったね。私の名前はね──」
「ち、ちょっと待ってください!」
僕は彼女の言葉を遮って立ち上がる。
「ぼ、僕、お金持ってないです!」
「え?」
「怪しいお店とか…つ、美人局とか!本当に持ってないので他の人の方がいいです!!」
彼女に助けられた時は嬉しかった。それは間違いなく本当だ。それこそ思わず瞳が潤むほどに。
だけどこんな状況あまりにも出来すぎていた。こんなに美人な人に助けられて、一緒に夜の街にいるなんて。都会ではそういうのが横行しているという。現にこの眠らない街では、そこかしこに妖艶な雰囲気の男女2人組が星の数ほどいた。
状況だけ見るなら僕は絶好のカモだ。ここではっきり断ってないおかないと大変なことになる。まだ20歳にもなっていないし、お酒の飲めるお店にだっていけない。再度さっきの警官たちのお世話になることになってしまう。僕は酷く脅えていた。
「……」
彼女は立ち上がった僕をキョトンとした様子で見ていた。そして──
「ぷっ、あははっ!」
彼女は可笑しいと言った様子で吹き出した。
「えっ…え?」
「あははっ!そっか、そうだよね!」
そう言ってくくくっとまた笑い、彼女は目に浮かべた笑い涙をしなやかな指で掬った。
「いや、本当にお金持ってないので──」
「大丈夫だよ。安心して。そういうのじゃないから」
ひとしきり笑った後、彼女ははっきりとそう答えた。
「で、でも…」
「考えてもみて?こんなウェイターみたいな格好した人が、そんなことすると思う?」
「あ…いや、そうかもですけど…でもそういうコスプレ的な…」
「さすがにこの街でもそれは居ないってば」
また一つ、クスクスと笑う。
「お金取るとかそういうのしないから。とりあえず座って?ねっ?」
目線を促すように彼女が遊歩道へ視線を移す。人通りが少ないとはいえ、数人の人がこちらを見ていた。
「あっ…す、すみません」
「いーえ。こちらこそごめんね、余計な心配させて」
通行人の注目を軽く集めてしまい、いたたまれなくなって座る。彼女の言葉に嘘はなさそうだった。…まだ騙されているのかもしれないが。
「あー、可笑しい」
雪のような白い肌が少し赤くなるほど、彼女は綺麗に笑っていた。そんな姿に僕の緊張も少し解きほぐれる。
「…でも無理もないよね、ごめんね」
「いえ、こちらこそ失礼なこと言って申し訳ないです」
「いいのいいの。そうね、突然だし、まずは私のことをちゃんと話すとするわ」
彼女は居座りなおした僕を見てうんうんと頷き言葉を続ける。
「私の名前はMarie・W・Schnbellっていうの」
「マリー、ヴァ…イス…?」
「聞き馴染みないよね。ドイツ語なの」
「ドイツの方ですか?」
「えぇ、そうよ」
日本人ではないとは思っていたが、英語圏の方でもなかった。というよりも日本人の血も入っていないようだった。外国といえば、英語が話せる国という漠然としてイメージだったので少し戸惑う。
「すみません、ドイツ語には明るくなくて…」
とはいえ、英語も別に分かるわけではないが。
「全然気にしてないよ」
「…すみません。…あの随分日本語がお上手なのですね」
気になったところを聞いてみる。それくらいには緊張がなくなった。
「ふふっ、ありがと。…まぁ接客業をやってるからかな?すぐに話せるようになったよ」
日本語は他言語に比べて難しいと聞く。すぐに話せたということはこの人は相当頭が良いのか、もしくは相当努力をしたんだろうな…。
「日本に来て長いのですか?」
「3か月ほどかしら」
「…え、それでそこまで話せるのはすごいですね」
「よく言われるわ」
「というか並大抵の努力じゃ難しいと思うのですが…」
「そうかしら?誉め言葉として受け取っておく」
そうして軽くウインク。僕の驚きと有り余るすごさを飄々といなしている感じ。努力云々でどうにかできる期間ではないが…日本に来る前から勉強していたのだろうか。
「まぁ、日本に来てからすぐお店を開いたの。この近くで喫茶店をやってるのよ」
「喫茶店…えっ、というかオーナーなのですか?」
「えぇ、そうよ。だから美人局なんかじゃないわ」
「そ、そのことはもう…」
「ふふふっ、冗談よ。ちなみに実は今も営業中だったりするわ」
「え、お店の方は大丈夫なのですか?というかこんな深夜まで…?」
「お店は大丈夫。深夜だし、お店に来る人もあまりいないから。心配してくれてありがとね」
座っている状態の膝の上、頬杖を突きながら彼女が礼を言う。そんな一挙手一投足すら美しく見えた。それくらい、彼女は綺麗な人だった。
「この辺だと夜やってるお店も珍しくないの。開店してまだまだ日も経ってないし、今は軽く閑古鳥が鳴いている状態ね」
「…そうなのですね」
飲食店経営も大変なんだなと思った。
「私の話はこんなところかな?どう?誤解は解けた?」
「それはもう…1ミリもないです」
「あはは、誤解が解けたようで何より。じゃあ、他に聞きたいことある?」
「聞きたいこと…」
突然振られて少し戸惑う。何を聞こうか…特に聞くこともないなと思考を巡らせたとき、とある疑問がふっと過った。
「…あの、どうして僕の名前がわかったのですか?」
あの時、警官に名前を聞かれたときに彼女は僕の名前をすんなり答えた。しかもそれがドンピシャで当たっていたのを思い出す。それが不思議で仕方なかった。
正直、僕の名前は珍しいと思う。一発で読まれたこともなかなかない。にも関わらず、それを特定したのにはどんなからくりがあるのだろう…。
「あー…それはね」
彼女がまっすぐこちらを見る。そして──
「…っ!」
突然彼女の顔が目と鼻の先までやってきた。それと同時に両手で頬を包み込まれる。甘い香りがふわっと鼻腔を擽った。
「知りたい?」
「……」
その体勢のまま、じっと何かを含みながら見つめてそう言った。色っぽく潤んだ唇、思わず生唾を飲み込む。改めて見ても整った顔立ちに心臓が大きく早鐘を打った。
「……勘!」
「え?」
「当てずっぽうよ!」
しかし、感じていた緊張が吹き飛ぶほどの答えに面を食らった。パッと彼女が離れる。いや…勘って。
「いやさすがに…というか出身とか年齢も当ててたじゃないですか?」
「あれはほら、警官の人が身分証見たときにちらっと見えたからね」
それが本当なら夜に目が効きすぎている気が…。
「名前は本当に勘で当てただけだよ。身分証からわかる情報以外は本当に知らなかったし。だからあれ以上追及されていたら正直まずかったよ…」
「そ、そうですか…」
僕は彼女が離れたのを惜しみつつ、そっぽを向いてそう答えた。なんだか釈然としないが、さっきみたいに近づかれたら心臓が持たない。心臓はまだ早鐘を打っていた。
「そしたら、もう少し君のこと教えてもらっていい?」
「あっ…はい」
こんな風に会話しているものの、僕はまだ自分のことを話していない。当たり前だが初対面なのだ。
なにを聞かれるのだろう…僕は少し身構える。端的に僕の状況を見れば、聞きたいことなどいくらでもあるだろうな。なぜ追われていたのか、とかこんな時間に1人でなにしていたのか、とか。
結局は警官の人に聞かれる内容と同じな気がするが、助けられたのだからある程度は答えよう。恩返しというほどではないけれど、この人ならなんとなく話してもいいかという気持ちになっている。
「それじゃあね──」
「……」
黒い緊張がひた走る。話してもいいとは言ったが、根掘り葉掘り聞かれるのは少し億劫だった。
「好きな食べ物は?」
「……え?」
しかし問われた質問はまたしても拍子抜けするようなものだった。
「あ、私は林檎を使った食べ物が好きなの。ほら、このバスケットの中にもね、私の手作りの──」
そう言って彼女はバスケットの中身を見せてくる。梱包されたアップルパイがあった。
「…ち、ちょっと待ってください」
「ん?」
「いや、え?そんな質問でいいんですか?」
「…ごめん。つまらない話だったかな?」
「いえ、そういうわけではなくて…」
彼女が少し遠慮がちになる。その気持ちにさせたことは申し訳ないが、なんかもっとこう…他にも気になることがあるはずだろう。
「自分で言うのもなんですけど、他に気になることありません?」
「…え、例えば?」
「なんで追われてたのかとか…傍から見ても自分が怪しいの自覚してますし…」
「あー」
言ってて悲しくなるが、深夜に警官に追われる人なんて何かあったに決まってる。そこには一切触れずに、それよりも先に好きな食べ物を聞くのは不思議でしょうがなかった。
「いやぁでも…魁人くん悪い人じゃなさそうだし」
「……」
「それにほら、君自身のことを知りたいしさ。なにがあったの?なんて野暮じゃない?」
「っ」
「私はほら、今会ったばかりだけど、君と…魁人くんと話してるんだしさ」
僕自身を知りたいというその言葉に、僕は強く心を打たれた。同時に、彼女の行動がすべて善意のものだと理解した。
きっと彼女は追われている僕を見て、悪い人ではなさそうだからという1点のみで助けてくれたんだ。だから理由なんてどうでもいいのだと。
嬉しい、そして優しすぎる。荒んでいた心にはそれだけで十分、陳腐ながらそんな感情を抱いた。裏表のない白雪のような純粋さ。それがどれだけ僕の心を掬い上げてくれるか…
「…えっ!?」
「……ぐすっ」
「ご、ごめん、大丈夫!?変なこと言った!?」
気がつけば涙が頬を伝っていた。そんな僕を見て慌てた様子を見せる彼女。
こんなにも人って暖かいものなんだ。ここ幾日か、それを感じることなどなかったからか。涙は感情を乗せて、とめどなく流れる。
「いえ…すみません…」
「ほ、本当に大丈夫?」
「大丈夫です…」
人前で涙を流したのなど久しぶりだ。天涯孤独になった瞬間すら泣かなかった、泣けなかった。だからこそ、恥ずかしいやら情けないやらで、感情がごちゃ混ぜになっている。
でもそれが嫌ではなかった。まるで本当はこういう感情になりたかったんだと、そう思った。
僕は嗚咽交じりに泣いた。彼女に会えてよかったと、そう思った。
──
─
「落ち着いた?」
「…はい」
どれくらいそうしていたか。気がつけば少しだけ夜が濃くなっていた。小道を渡る人も一人もいない、それくらいに夜が更けていた。
僕が泣き止むまで彼女は僕の背をさすってくれていた。心も落ち着き、今は穏やかになったと思う。目元が赤くじんわりと熱を持っているのを感じられるほどに。
「すみません、突然泣いてしまって」
「ううん、大丈夫」
彼女は僕を見て微笑み、またゆっくりと背を撫でてくれる。トントンとときたまあやす様に叩く掌が心地いい。
「…身の上話をしてもいいですか?」
先程の助けられた対価ではない、純粋な気持ちで僕はそう言う。彼女には聞いて欲しい、そう思った。
「…つい数週間前、3月の初めに僕はここに越して来ました」
どこから話すべきか、そう感じながらも成り行きで言葉を紡ぎ始める。
「うん」
「都会の大学に出るためです。長野の北の小さな町から、漠然とした都会への憧れとか、町や家に縛られたくないとか、そんな理由です」
彼女は静かに頷きながら聞いてくれていた。
「両親と大喧嘩して、それでも半ば無理やり上京しました。過ごす家の下見とか、そんな風な理由をつけて。そしたら…」
「……」
「上京していたタイミングで……地元が大震災に見舞われたんです」
僕は少し言い淀みつつ、僕の身にあった出来事を話した。
「…ニュースで見た。東京も大きく揺れたの覚えてる。揺れたのって深夜だよね?3時とか4時とか」
「はい、まさに新居で寝ている間でした」
「たしかかなり大きくて、今も──」
「復興中です。混乱を避けるために被災地へ行くのは止められてます」
「そうよね……あれ?もしかして…」
「はい、帰れてないです。地元には一度も」
彼女はハッと驚いた表情をした。
「え、一度も!?」
「はい。向こうはまだ雪の影響もあって復興に時間もかかってます。…3月は少し天気が荒れ気味になりますから」
声が少し潤んだ。思い返して悲しくなり、涙声になる。
「家族とは連絡が取れていません。両親は、行方不明者として名前があげられていました。兄弟も、縁の近い親戚もいません。友人すら音沙汰なしです。全員いなくなったとは考えられませんが、深夜の大地震だったのでスマホなんて持って逃げなかったのでしょうね」
「……」
彼女の顔が夜の街に陰る。なんと声を掛けたらよいかわからないといったような表情をしていた。
「友人も家族も、朝起きたらなにもかも…僕は一夜にしてすべてを失ってしまいました」
そう言って僕は俯く。一気に言葉にできたのはここまでだった。目からこぼれた大粒の雫が、汚れた石畳に落ちてシミを作った。
「…僕、地震が起きたの気づかなかったんです。熟睡してたんですよ。朝スマホのニュースで知りました。本当に…本当にっ……馬鹿みたいじゃないですかっ…」
怒りやら情けないやらの感情が思い出されて爆発。慟哭にも似た声色。気持ちが溢れる。
「……」
「……」
ボタボタと、大雨のような涙。僕はなにをしていたんだろう、悔やんでも悔やみきれない。東京に来なければ、大学になんて進学しなければ…。失うなんて誰が想像つくのか。全て知っていれば…なんて、夜の数ほど考えた。
「…眠れなくなったんです」
「え?」
「全てを失った後、眠るのが怖くなりました。不眠症だそうです。寝付けないし、眠れてもすぐ起きてしまうし、見る夢は毎日同じ悪夢です。災禍に包まれる地元の町を動けない状態で見るだけ、ただそれだけです」
正しく地獄。何度も死のうと考え、その度にそんな勇気も出ない自分に嫌気がさす。
夢を見た日の朝は震災の行方不明者の事例を調べ尽くした。希望と絶望がないまぜになるだけなのに。不安と焦燥が心も体も思考すら蝕んでいき、そんな日々についに眠れなくなった。
「……」
彼女の方に目を向けると、少し驚いたような表情をしていた。
「驚いた…」
「え?」
「少しだけ、私と似てるなって思って」
そう言って彼女はなにかを思い出すように下を向く。
「別に共感したいとかそういうつもりで言うんじゃないけど、私も眠れないの」
「…本当ですか?」
「うん。だからこうして夜通し働いているの」
思い出したくない過去なのだろうか。苦虫を噛み潰したような表情。
「魁人くんとは少し違った理由だけどね。私も寝るのは怖いんだ」
眠れないつらさがわかるからこそ、僕まで苦しくなり、心がキュッとなる。苦しげな表情をする彼女は、泡沫のように消えてしまうのではと思ってしまうくらい、儚げだった。
「震災が起きる前に母と電話してました。半ば無理矢理上京した僕に、母は最期になにか言おうとしてたんです。それがなにかはわからないままになってしまいました」
そんな寂しさに共鳴するように、言葉を紡ぐ。奇しくも似た境遇を持つ彼女にならこの痛みもつらさもなにもかも理解してくれるような気がした。
彼女は涙ぐみながら僕の頬に触れた。言葉はなかったが、悲しいねと、そう言っているような気がした。
「…魁人くんはさ」
「……はい」
「…どうしたら救われる?」
「……」
押し黙る。つらすぎて考えたこともなかった。どうしたらこの苦しみがなくなるのか。いろいろあるとは思うが、一番はやっぱり──
「家族が見つかるといいと思います。それまでは…せめて、独りじゃないと思いたいです」
「…わかった」
そう言って彼女はバスケットの中のアップルパイを取り出して優しく包み込んだ。
「……」
一瞬、フワッと彼女の髪が靡く。ほんのり髪色が赤く染ったような気がした。
まただ、さっきと同じ。不思議な感覚。僕は視界に映る光景を疑い、目を擦る。
「…今日は一緒にいるよ。夜が明けるまで」
擦った目を開けるとすぐに彼女がそう言った。髪色は麗しい黒一色だった。
「まだまだ夜は長いし、眠れないもの同士楽しいお話をしよっか」
笑う彼女が都会の月明かりに照らされる。春の夜に白雪のような綺麗な肌が映える。綺麗だなと思った。
「…はい」
行きずりでもなんでもいい。この不思議な出会いに感謝しよう。
──
─
「──あっ」
「あ…もうこんな時間なのね」
クスリと彼女が笑った。笑顔が明るく見える。
それもそのはず。四季の路から見えるビルの間の空は少しずつ白み始めていた。スマホを確認すると午前5時半。優しい朝日を感じたのは久々だった。
「…途中から記憶がないんですけど、僕起きてました?」
「えぇ、本当に眠らないで一緒にいた人初めてよ。最後のほうはボーっとしてたけどね」
彼女が朝日と同じ柔らかさで微笑む。
ただひたすらに他愛もない話をしていた。何が好きなのかとか彼女のいた国はどうだったとか。面白みもない話題ばかりだったかもしれない。それでも僕にとっては心地のいい時間だった。
「さてと…それじゃそろそろ戻ろうかな」
「……」
そんな時間にも終わりは来る。これで終わりだと思うと少し惜しい気持ちになった。
「…ほら、そんな顔しないで」
彼女はそう言って立ち上がり、手を差し伸べる。善意でいてくれた彼女に最後まで気を遣わせてしまった。これじゃ駄目だな…。
「すみません…」
差し伸べてくれた手を取り、僕は立ち上がった。
「あっ、そうだ」
すっと手が離れた後、彼女がなにか思い出したような声をあげる。
「これ、受け取って?」
そう言ってバスケットから取り出したのは1つのアップルパイだった。
「えっ、いいんですか?」
「もちろん。…外にいたから少し冷めちゃったけど」
林檎1つ分に満たない重さが掌に乗る。冷えきってはいたが、微かに甘い香りがした。
「魁人くん」
「はい」
「眠れるといいね」
言葉は発さずこくりと頷く。暁に目を細める。彼女の優しさも陽の光も、眩しいと思った。
「…じゃあ、またね!」
そう言って彼女は手を振りながら去っていった。振り返ることなく赤色のウェイター服を揺らして小さくなっていく。それを見えなくなるまで見つめていた。
本当に不思議な時間だった。まるで現実ではないような、夢のような儚さ。こんな夢ならいつまでも見ていたいと思った。
「……」
また会えるだろうか。
そう思いながら貰ったアップルパイを齧る。シナモンのが香り、彼女とした会話の一つ一つが思い起こされる。
「……」
ツーっと涙が頬を伝った。暖かいなと、冷めたアップルパイを頬張りながらそう思った。
僕は夜、眠れなくなった。
朝起きたら何もかもなくなってしまうのではないか、恐怖と不安で目が血走って眠れない。何度も読み返した本も幼い頃好きだった場所も、僕を想ってくれていた人たちも。跡形もなく無くなってしまうと思うと、寝付くことができない。
医者からはストレスによる不眠症だと言われた。人間の身体の都合上、眠らないことはできないらしい。寝付けなかったり、夜中何度も目が覚めたり、朝早くに目が覚めてしまったり。そのどれもが自分に当てはまった。
気絶するように意識を失い、その度に夢を見る。過ごしてきた土地、身体も動かせず、大地震で崩れていく小さな町をただただ無力に眺めるだけの夢。血の味がするほど叫び、涙をとめどく流し、災禍の絶叫が耳を劈く、そんな夢。変わり果てた荒野に自分だけが残り、幾度も幾度も死にたいと思わせられる。
そんな夢を見るようになって数週間。夜が来るのが怖くなった。だから眠らないように慣れない街を歩く。亡霊のようにフラフラと、歓楽に満ちる街を独りぼっちで。
「……」
東京屈指の歓楽街、新宿という街を宛もなく彷徨う。3月終わりの都内はまだ少し肌寒かった。そんな寒さを吹き飛ばすような、深夜0時を過ぎたころの眩い街明かり。今の僕とはまるで正反対だった。すれ違う華やかな姿をした男女を恨めしそうに視界に入れる。
「…お兄さん、お遊びどうですか?」
声がした方を見る。目の前10時の方向、一人歩くスーツの男にそう声をかける厳つめの男性がいた。スーツの人はそれを無視してスタスタと歩く。
きっとこの人たちも帰れば大切な人がいるんだろう。今の僕にはそんな存在すらいない。僕にはもう何もないし、誰もいない。
声をかけた厳つい男はすぐに諦め、僕の方を見た。
「お兄さん、お遊びどうですか?」
全く同じ言葉を発する。そう言ってこちらに歩みを進め…そのまま通り抜けて僕の後ろを歩いていた男に声をかけた。……僕に向けたものではなかった。
別に声をかけられたかった訳ではない。むしろ煩わしいだけなはずだ。にも関わらず、まるでそこに存在しないかのような扱いに、心に暗い影が落ちた。
明るすぎる歓楽街ですら、誰にも気づかれることはない。今の僕は、天涯孤独。そんな言葉がぴったりと当てはまった。
──
─
「……」
いったいどれほどの時間そんな風に過ごしていただろうか。気がつけば歩き疲れ、駅前のベンチで座り込んでいた。ここまでどうやってきたのかも、記憶に残っていない。俯いた視線に映るのは、噛み終えたガムと消えかけの煙草が落ちているアスファルトの地面だけだった。
「…君、そんなところで何してるの?」
唐突に、項垂れた頭上からそんな声が聞こえた。ゆっくりと顔を擡げる。
「もう深夜も回ってるよ」
「声聞こえてる?」
目に入ったのは、一方はふくよかで、もう一方は筋肉質な男二人組。両方とも青紺の警官服を身にまとっていた。
「……」
かけられた言葉に返すことなく、僕は2人と視線を交差させる。果たして今の僕はどんな顔をしているのだろうか。やっと誰かに声をかけられた安堵の表情か、虚ろな瞳をした覇気のない表情か。どちらにしても情けない表情なのに変わりはないだろうな。
「反応なしですか…先輩、どうします?」
「見たところ高校生か大学生か。どちらにしてもまだ若い。……君、この辺に住んでるの?家に帰れる?」
大学に入って大人になったと思ったが、どうやらまだ自分は子供に見られるようだった。そりゃそうか。成人の年齢は18歳に引き下げられたと言うが、二十歳にもなっていない子など、大人から見れば大差ないだろう。
でもそれは同時に、大人でも子供でもない自分の存在のあやふやさがわかって嫌だった。僕はそう感じたと同時に無視するようにまた俯く。
「…黙ってちゃわからないよ。ご両親も待ってるんじゃないの?」
「…っ」
ご両親も、という言葉にぴくりと反応する。
「……両親はいません」
「いない?」
頭を垂れたままそう言い放つ。
「誰も…いません」
「いないって…そりゃないでしょ」
「ネグレクトですかね?」
「この歳で?一人暮らしの不安とかそういうのじゃないの?俺にもこのくらいの娘いるからわかるよ。初めての一人暮らしって心細いから──」
先輩と呼ばれているふくよかな警官がつらつらと御託を並べ始める。
娘がいるんだ。帰ったらなんだかんだで家族がいるんだな。なにも…なにも知らないくせに。なんにもわからない癖に…。
「とにかく、ほら、帰ろうよ。おうちまで送り届けてあげるから…」
筋肉質な警官の手がぬっと伸びてきた。
「っ!」
怪しい者を見る彼の目。なんとなくその手を取るのが嫌だと思った。
そう思った刹那、体が勝手に動く。僕はベンチから立ち上がって駆け出していた。
「あっ!」
「こら、待ちなさい!」
2人の警官が慌てて僕を追い始める。自分も足はそこまで速くない、いずれ追いつかれるだろう。
「はぁ…はぁ…」
すぐに息が上がる。明らかに運動不足だ。
彼らからすればただの職務質問のつもりだったのだろう。しかし逃げる僕を見て、少し表情が変わっていった。わけも言わず逃げ出すということは後ろめたい何かがあると言っているようなものだ。無論、そんなものあるわけないのだが…今はなんとなく大人の世話になるのが嫌だった。
「うわっ…」
「なに?」
人々から驚嘆の声をぶつけられながら、駅前から歌舞伎町の方へ抜けていく。煉瓦のような石のような地面を蹴り、人混みを縫うように駆けていく。
「はぁ…はぁ…っく」
しかしすぐに信号に足止めされて喉から声が漏れる。歌舞伎町中央通りへと続く、大通りの信号。
「君、待ちなさい!…すみません、どいてください」
「…はぁ…はぁ。どいて、どいてください!」
振り返ると警官がこちらに向かってきている。しかし、人混みを逆走する形で足を取られていた。それにふくよかな警官はそこまで足が速くないようだった。
まずい、まずい。本当に捕まるのも時間の問題だ。
「……はぁ…はぁ。…っ!」
目線を前に戻すとその瞬間、信号が青になった。僕は大慌てで中央通りへ飛び込むように駆け出す。人の間をすり抜けるように走った。
「…はぁ……はぁ……」
中央通りを半分ほど走ったところで、なぜ僕は走り出したのか、なぜ警官の手を取らなかったのだろうか、とそんな考えがふと過ぎる。
「……」
徐々にペースが落ちる。街ゆく人の好奇の目線を感じ取れるほどに、緩やかに。
それはたぶん、ただの反骨心だ。あの時は、なにも助けてくれなかったのに、誰もなにもしてくれなかったのに。今、孤独になったところに手を差し伸べるなんて、そんなの──
「もっと早く…助けて欲しかった……」
思考の終着と共に、そんな言葉が口をついて出た。どれくらい走ったか。中央通りを抜けて新宿東宝ビルを超えた先。僕は足を止めてしまった。
「はぁ…はぁ…。君、突然どこに行くんだ」
「……はぁはぁ。やっと…止まった」
薄暗い路地で警官に追いつかれる。
僕は…別にこの人たちに助けて欲しかったわけではない。むしろこの人たちに限らずこの世の誰にも、どうこうできる問題とも思っていない。
僕から全てを奪った…人知を超えた災禍になど、何人たりとも太刀打ちできるわけないのだから。
「……」
無気力に警官2人を見る。
「黙ってちゃわからないよ。とにかく交番まで行こうか」
筋肉質な警官の手が僕の手首を握った。力なく、引っ張られる。ふくよかな警官はまだ息を整えていた。
もういいや、どうでも。別に逃げる必要もないし。
共に生きてくれる人もいないくせに、天涯孤独になっても僕の見た目や年齢じゃ、独りで生き抜くことさえできない。結局僕という存在を肯定してくれる人や物や居場所なんてどこにも存在しない。こんな全てを受け入れてくれそうな夜の街でさえ、僕の居場所なんてなかったんだ。
「……」
自暴自棄になり、警官に連れられようとされたその刹那──
「あのっ!」
僕らにかかる、柔らかな声が響いた。
「……ん?」
警官が動きを止め、声のほうへ向く。僕も同時に目線をあげると、そこには一人の女性がいた。膝に手をついて息を整えている。
「はぁ…はぁ…。あ、あの!その子、私の連れです!」
たった一言。その一言だけなのに、まるで僕を救い出してくれる天啓のように聞こえた。
荒らげる息を整える彼女を改めて見る。
まるで林檎のような赤を基調とした服装。古き良き喫茶店を彷彿とさせる、ギャルソン風なウェイター服。手にはパンを入れているようなバスケットをぶら下げている。マッチ売りの少女みたい、そんな感想がパッと頭に浮かぶ。格好自体は華やかな夜の街には少しだけ違和感があった。
見た目は僕より1つ2つ上に見える。目鼻立ちはくっきりとしており、高い鼻とまるで雪のような白い肌が特徴的だった。純日本人然とした顔立ちではない。外国の方だろうか。
そしてなによりも目を引いたのはミディアムヘアの美しい黒髪。数メートル離れているこの距離からでさえ、枝毛ひとつ無いであろうとわかる艶やかな髪だ。眩い灯りが照らされて、髪に綺麗なエンジェルリングができている。
まさしく眉目秀麗。およそ現存しているとは思えない…まるで御伽噺から出てきたような美しい人だった。
「……」
「……」
そんな彼女の言葉を聞き、2人の警官が顔を合わせる。
「連れといっても…ねぇ」
「急に現れてそれはちょっと…」
1,2秒のアイコンタクトをしあった後、苦笑いしながら彼女を見定めるようにそう発言した。
「駅前で待ち合わせしてたんです。そしたら突然走っていってしまったので…慌てて追いかけたんですよ?」
警官の訝しげな表情を意に介さず、凛とした様子で彼女はそう答える。
「いやぁ…なら早く声をかけてくれないと…」
「皆さん、足が速いんですもの。追いつくのは到底無理な話ですよ」
コロコロと、嘘をつく。そう、当たり前だが僕はこの人を知らない。
だが、なぜか彼女は僕のことを助けようとしていた。こんなどこの誰とも、何をしたともしれない僕のことを、だ。懐疑的な目か、もしくは誰の目にもとまらなかった僕を助けようとする。そんな優しさに僕自身の存在が肯定されたような気がした。
「とはいえなんの確証もないですから。ひとまず交番まで──」
「い、いや!待ってください!」
とはいえ、感じた優しさは警官の職務とは無縁なもの。無情にも僕を連れていこうとする警官の前に、彼女は今一度通せん坊する。
「ど、どうしたら信じて貰えますか?」
「信じるもなにも、怪しさ満点だし」
「私はその子の姉ですよ?」
「いやどう見ても血筋が…」
「異母姉弟でして…」
「そんな無茶な」
なにやら雲行きが怪しくなってきた。さっきの凛とした態度はどこへやら。目が泳いでお粗末な嘘をつく。
「じゃあこの子、名前なんていうの?」
「え?」
ふくよかな警官が意地の悪い表情でそう質問する。
「そ、それは──」
答えられるわけなど、当然ない。
「……」
僕は黙って彼女を見る。なんて言おうか必死に考えている様子だった。
万事休すなのだが、不思議と心は穏やかだった。純粋に僕のことを助けようとしてくれた、その心が嬉しかったからなのだろう。僕にとってはそれで十分だった。
「わからないんでしょ?そんな嘘をつかないで──」
だけど…だけど願わくば…この世界にいる誰かに僕の存在を肯定してほしかった。その純粋な気にかけのその先、誰かと関わって生きていけるそんな未来を──
「…わかるよ」
そう思った刹那、彼女の優し気な言葉が僕の脳内に響いた。僕を見てそう口にする彼女。その発言は当然警官に対してのものだが、まるでそんな願いに応えるかのようにも聞こえた。
「え?」
「彼の名前、わかりますよ」
彼女へ目を向ける。彼女はまっすぐ僕を見て、また凛とした表情でそう答えた。それはどこか、覚悟の決まった目をしていた。
「ちょっと待っててください」
彼女はさらにそう続け、手持ちのバスケットから1本のペットボトルを取り出した。ラベルには『100%リンゴジュース』と印字されている。よく見る250ml程度の市販のリンゴジュースだ。
「…ふぅ」
彼女は小さな吐息とともに、キャップを外した。何かを込めるように、ペットボトルのリンゴジュースを両手で包み込む。
「……」
なぜこのタイミングで…?僕はそう思った。喉が渇いたのだろうか…それにしてはタイミングがやや変だ。いや、変なことは決してないのだが、少し不思議な行動ではあった。
「……んくっ」
彼女は一つ息を吸い込み、リンゴジュースをゴクリと飲んだ。新宿の街明かりが彼女を照らす。それはどこか神々しく見え、魅入ってしまった。
「…え?」
飲むのにかかった時間は5秒もないだろう。神々しいなと感じた瞬間、彼女に起きたほんの小さな異変を発見し、僕は小さく声を漏らした。
無風な中、彼女の髪がそよ風に撫でられたかのように揺れ…そして、髪に映るエンジェルリングがほんのりと赤色に染まった。反射した紅い光が夜闇に紛れる。一瞬、照らす明かりの色の影響かとも思ったが、彼女の綺麗な黒髪の色が変わっているようにも見えた。
その変化は本当に微かなもので、注視していないとわからないものだったであろう。現に、警官2人は特に気にする様子もない。思わず魅入ってしまっていたからこそ、気が付いたことだった。
「皇…」
ゆっくりと、彼女が口を開く。
「え?」
嘘…いや、本当に彼女とは初対面だ。なのに──
「彼の名前、皇 魁人です」
僕は驚いて目を丸くした。それは…間違いなく僕の名前だった。
「君、名前合ってる?」
静かにこくりと頷く。
「そんな馬鹿な。ちょっと君、身分証出して」
警官に促されるまま、僕はジーンズのポケットから財布を取り出して身分証を見せた。
「皇、魁人…本当だ、あってる」
「他にもわかりますよ。年齢は18、今年度で19歳ですね。出身は長野県の北部の小さな町です。少し前、地震があったところです」
「……」
本当に…全部合っていた。紡がれる僕の情報は寸分違うことはない。彼女とは初めて会ったはずだ。なにせ僕は彼女の名前すら知らない。
ストーカーの類を想像してほんの少しの恐怖も過ったが、自分にそこまでの魅力はない。そんなあるかわからない恐怖よりも、自分を知っているという事実を嬉しいと感じる気持ちのほうがはるかに強かった。自分は独りではないのだと、そう思えることができた。スッと、目が微かに潤むのを感じた。
「私が都内に住んでいるので、少し面倒を見るように言われていて…それで駅前で待ち合わせしていたんですよ。…警官さん、もういいでしょうか?」
警官2人にそう声をかける彼女。もちろん、面倒云々は熟れた林檎のような真っ赤な嘘。
「…ど、どうしますか先輩」
「う、うーん…」
警官2人がひそひそと話す。想定外な出来事が起きて困惑している様子だった。
「必要であれば、他にもいろいろ答えられますけど…」
彼女はそう追撃する。むろん僕は何も言っていないが、今の彼女には何でも答えられるような雰囲気があった。
「わ、わかりました、疑ってすみません」
「…き、君も何も言わずに逃げたら疑っちゃうでしょ。それならそうといってくれないと」
「す、すみません…」
嘘を裏付ける証明の言葉の数々。僕のパーソナルな情報を知っている人間が赤の他人だなんて、警官2人にはわかる由もなかった。
──
─
「それでは、失礼します」
「あまりお姉さんに迷惑かけないように気を付けてね。夜の街は物騒だから」
「は、はい」
その場で簡単な身分調査の後、警官はその場から去っていった。僕の身分証など当然偽りではなかったし、どうやら彼女のものもそうだったようだ。名前の違いなどはあるはずだが割とすんなり開放してくれた。
「…はぁー、なんとかなってよかったぁ」
警官2人の背中が見えなくなったタイミングで、彼女が安堵のため息同時にそう呟いた。力が抜けたように、彼女は張っていた肩肘を緩める。
「……ふぅ」
僕も同じように溜息を吐きながら、警官が去っていった方向を見つめる。そして、今さっき起きた怒涛の出来事を反芻する。
思い返しても不思議なことばかりだった。初めてあった人なのに僕のことをいろいろ知っているなんて。それに、普通はめんどくさがるはずなのだ。僕が周りの人と同じ立場なら、警官に追われているなど人間など助けようなど思わない。好奇の目を向けるだけで、数分後には忘れるだろう。
彼女はどうして僕を助けてくれたのだろうか?単に人助けが好きな人なのかもしれない。もしかしたら本当に僕のことを知っている人なのか。どちらにしてもそんな関わりが、誰との繋がりもなかった僕にとって感謝でしかなかった。
「……」
横目で彼女を盗み見る。改めてみると本当に綺麗な人だ。そういえば、さっき見えた仄かに赤くなっていた髪色は綺麗な黒髪に戻っている。やはり気のせいだったのだろうか。
「さて…君!」
「は、はい」
彼女が突然声をかけてきた。盗み見ていたのがバレたような気がして少し心臓が跳ねる。やましい心は何もないが、不意に目が合うと緊張してしまうというそれだ。
「いや、そっか…魁人くんでいいかな?」
「あ、はい…なんでも大丈夫です」
彼女は口元に手を当て考え込むようなしぐさの後、僕を名前で呼んだ。久々に人に名前を呼ばれた気がする。
「魁人くん、お腹すいてる?」
「え?」
そういう彼女は軽く微笑み──
「よかったらちょっとお話ししない?」
目配せしながらそう提案してきた。
* * *
「あはは…こんなところでごめんね」
「いえ…」
四季の路という不揃いな石畳の遊歩道。そこにある路傍の石の上に並んで座る。小道には木々や草花が生い茂っている。深夜を回っているからか、人通りはそこまで多くない。新宿にもこんなところがあったんだ…と思わされた。そうはいっても深夜の歓楽街近く。ゴミなどが散乱していたり、建物の裏側が剥き出しで見えていたり、とても綺麗とは言い難い場所だった
「走ったら汗かいちゃったね。何か飲み物飲む?」
「…お、お構いなく」
気さくに話しかけてくる彼女。こうやって雑談程度に誰かと話したのは久しぶりだ。
そんなことを考えていた時、ふと嫌な思考が頭をよぎる。
「あ…そういえば…さっき持ってたリンゴジュース飲んじゃったんだった」
「そう…ですね」
「春だけどまだ冷えるよね。寒くない?」
「いえ…全然……くしゅっ」
思わずくしゃみ。3月の終わりとはいえ、まだまだ夜は冷えてる証拠だった。
「…え、ごめん。寒いよね。どっか入ろうか?」
「え!?い、いやっ!」
隣に座る彼女の顔をびっくりして見る。僕は思い切りブンブンと頭を振る。後ろには仄暗いネオンの光が小道に差していた。
「そう?風邪引いちゃうよ?」
「だ、大丈夫です!本当に!!」
「えー、そっか。……でもそんなに嫌がられると傷つくなぁ」
ニッとはにかみながら悪戯っぽくそう言う。や、やっぱりこの人…
「ふふっ、まぁいいや。そういえば、名前まだだったね。私の名前はね──」
「ち、ちょっと待ってください!」
僕は彼女の言葉を遮って立ち上がる。
「ぼ、僕、お金持ってないです!」
「え?」
「怪しいお店とか…つ、美人局とか!本当に持ってないので他の人の方がいいです!!」
彼女に助けられた時は嬉しかった。それは間違いなく本当だ。それこそ思わず瞳が潤むほどに。
だけどこんな状況あまりにも出来すぎていた。こんなに美人な人に助けられて、一緒に夜の街にいるなんて。都会ではそういうのが横行しているという。現にこの眠らない街では、そこかしこに妖艶な雰囲気の男女2人組が星の数ほどいた。
状況だけ見るなら僕は絶好のカモだ。ここではっきり断ってないおかないと大変なことになる。まだ20歳にもなっていないし、お酒の飲めるお店にだっていけない。再度さっきの警官たちのお世話になることになってしまう。僕は酷く脅えていた。
「……」
彼女は立ち上がった僕をキョトンとした様子で見ていた。そして──
「ぷっ、あははっ!」
彼女は可笑しいと言った様子で吹き出した。
「えっ…え?」
「あははっ!そっか、そうだよね!」
そう言ってくくくっとまた笑い、彼女は目に浮かべた笑い涙をしなやかな指で掬った。
「いや、本当にお金持ってないので──」
「大丈夫だよ。安心して。そういうのじゃないから」
ひとしきり笑った後、彼女ははっきりとそう答えた。
「で、でも…」
「考えてもみて?こんなウェイターみたいな格好した人が、そんなことすると思う?」
「あ…いや、そうかもですけど…でもそういうコスプレ的な…」
「さすがにこの街でもそれは居ないってば」
また一つ、クスクスと笑う。
「お金取るとかそういうのしないから。とりあえず座って?ねっ?」
目線を促すように彼女が遊歩道へ視線を移す。人通りが少ないとはいえ、数人の人がこちらを見ていた。
「あっ…す、すみません」
「いーえ。こちらこそごめんね、余計な心配させて」
通行人の注目を軽く集めてしまい、いたたまれなくなって座る。彼女の言葉に嘘はなさそうだった。…まだ騙されているのかもしれないが。
「あー、可笑しい」
雪のような白い肌が少し赤くなるほど、彼女は綺麗に笑っていた。そんな姿に僕の緊張も少し解きほぐれる。
「…でも無理もないよね、ごめんね」
「いえ、こちらこそ失礼なこと言って申し訳ないです」
「いいのいいの。そうね、突然だし、まずは私のことをちゃんと話すとするわ」
彼女は居座りなおした僕を見てうんうんと頷き言葉を続ける。
「私の名前はMarie・W・Schnbellっていうの」
「マリー、ヴァ…イス…?」
「聞き馴染みないよね。ドイツ語なの」
「ドイツの方ですか?」
「えぇ、そうよ」
日本人ではないとは思っていたが、英語圏の方でもなかった。というよりも日本人の血も入っていないようだった。外国といえば、英語が話せる国という漠然としてイメージだったので少し戸惑う。
「すみません、ドイツ語には明るくなくて…」
とはいえ、英語も別に分かるわけではないが。
「全然気にしてないよ」
「…すみません。…あの随分日本語がお上手なのですね」
気になったところを聞いてみる。それくらいには緊張がなくなった。
「ふふっ、ありがと。…まぁ接客業をやってるからかな?すぐに話せるようになったよ」
日本語は他言語に比べて難しいと聞く。すぐに話せたということはこの人は相当頭が良いのか、もしくは相当努力をしたんだろうな…。
「日本に来て長いのですか?」
「3か月ほどかしら」
「…え、それでそこまで話せるのはすごいですね」
「よく言われるわ」
「というか並大抵の努力じゃ難しいと思うのですが…」
「そうかしら?誉め言葉として受け取っておく」
そうして軽くウインク。僕の驚きと有り余るすごさを飄々といなしている感じ。努力云々でどうにかできる期間ではないが…日本に来る前から勉強していたのだろうか。
「まぁ、日本に来てからすぐお店を開いたの。この近くで喫茶店をやってるのよ」
「喫茶店…えっ、というかオーナーなのですか?」
「えぇ、そうよ。だから美人局なんかじゃないわ」
「そ、そのことはもう…」
「ふふふっ、冗談よ。ちなみに実は今も営業中だったりするわ」
「え、お店の方は大丈夫なのですか?というかこんな深夜まで…?」
「お店は大丈夫。深夜だし、お店に来る人もあまりいないから。心配してくれてありがとね」
座っている状態の膝の上、頬杖を突きながら彼女が礼を言う。そんな一挙手一投足すら美しく見えた。それくらい、彼女は綺麗な人だった。
「この辺だと夜やってるお店も珍しくないの。開店してまだまだ日も経ってないし、今は軽く閑古鳥が鳴いている状態ね」
「…そうなのですね」
飲食店経営も大変なんだなと思った。
「私の話はこんなところかな?どう?誤解は解けた?」
「それはもう…1ミリもないです」
「あはは、誤解が解けたようで何より。じゃあ、他に聞きたいことある?」
「聞きたいこと…」
突然振られて少し戸惑う。何を聞こうか…特に聞くこともないなと思考を巡らせたとき、とある疑問がふっと過った。
「…あの、どうして僕の名前がわかったのですか?」
あの時、警官に名前を聞かれたときに彼女は僕の名前をすんなり答えた。しかもそれがドンピシャで当たっていたのを思い出す。それが不思議で仕方なかった。
正直、僕の名前は珍しいと思う。一発で読まれたこともなかなかない。にも関わらず、それを特定したのにはどんなからくりがあるのだろう…。
「あー…それはね」
彼女がまっすぐこちらを見る。そして──
「…っ!」
突然彼女の顔が目と鼻の先までやってきた。それと同時に両手で頬を包み込まれる。甘い香りがふわっと鼻腔を擽った。
「知りたい?」
「……」
その体勢のまま、じっと何かを含みながら見つめてそう言った。色っぽく潤んだ唇、思わず生唾を飲み込む。改めて見ても整った顔立ちに心臓が大きく早鐘を打った。
「……勘!」
「え?」
「当てずっぽうよ!」
しかし、感じていた緊張が吹き飛ぶほどの答えに面を食らった。パッと彼女が離れる。いや…勘って。
「いやさすがに…というか出身とか年齢も当ててたじゃないですか?」
「あれはほら、警官の人が身分証見たときにちらっと見えたからね」
それが本当なら夜に目が効きすぎている気が…。
「名前は本当に勘で当てただけだよ。身分証からわかる情報以外は本当に知らなかったし。だからあれ以上追及されていたら正直まずかったよ…」
「そ、そうですか…」
僕は彼女が離れたのを惜しみつつ、そっぽを向いてそう答えた。なんだか釈然としないが、さっきみたいに近づかれたら心臓が持たない。心臓はまだ早鐘を打っていた。
「そしたら、もう少し君のこと教えてもらっていい?」
「あっ…はい」
こんな風に会話しているものの、僕はまだ自分のことを話していない。当たり前だが初対面なのだ。
なにを聞かれるのだろう…僕は少し身構える。端的に僕の状況を見れば、聞きたいことなどいくらでもあるだろうな。なぜ追われていたのか、とかこんな時間に1人でなにしていたのか、とか。
結局は警官の人に聞かれる内容と同じな気がするが、助けられたのだからある程度は答えよう。恩返しというほどではないけれど、この人ならなんとなく話してもいいかという気持ちになっている。
「それじゃあね──」
「……」
黒い緊張がひた走る。話してもいいとは言ったが、根掘り葉掘り聞かれるのは少し億劫だった。
「好きな食べ物は?」
「……え?」
しかし問われた質問はまたしても拍子抜けするようなものだった。
「あ、私は林檎を使った食べ物が好きなの。ほら、このバスケットの中にもね、私の手作りの──」
そう言って彼女はバスケットの中身を見せてくる。梱包されたアップルパイがあった。
「…ち、ちょっと待ってください」
「ん?」
「いや、え?そんな質問でいいんですか?」
「…ごめん。つまらない話だったかな?」
「いえ、そういうわけではなくて…」
彼女が少し遠慮がちになる。その気持ちにさせたことは申し訳ないが、なんかもっとこう…他にも気になることがあるはずだろう。
「自分で言うのもなんですけど、他に気になることありません?」
「…え、例えば?」
「なんで追われてたのかとか…傍から見ても自分が怪しいの自覚してますし…」
「あー」
言ってて悲しくなるが、深夜に警官に追われる人なんて何かあったに決まってる。そこには一切触れずに、それよりも先に好きな食べ物を聞くのは不思議でしょうがなかった。
「いやぁでも…魁人くん悪い人じゃなさそうだし」
「……」
「それにほら、君自身のことを知りたいしさ。なにがあったの?なんて野暮じゃない?」
「っ」
「私はほら、今会ったばかりだけど、君と…魁人くんと話してるんだしさ」
僕自身を知りたいというその言葉に、僕は強く心を打たれた。同時に、彼女の行動がすべて善意のものだと理解した。
きっと彼女は追われている僕を見て、悪い人ではなさそうだからという1点のみで助けてくれたんだ。だから理由なんてどうでもいいのだと。
嬉しい、そして優しすぎる。荒んでいた心にはそれだけで十分、陳腐ながらそんな感情を抱いた。裏表のない白雪のような純粋さ。それがどれだけ僕の心を掬い上げてくれるか…
「…えっ!?」
「……ぐすっ」
「ご、ごめん、大丈夫!?変なこと言った!?」
気がつけば涙が頬を伝っていた。そんな僕を見て慌てた様子を見せる彼女。
こんなにも人って暖かいものなんだ。ここ幾日か、それを感じることなどなかったからか。涙は感情を乗せて、とめどなく流れる。
「いえ…すみません…」
「ほ、本当に大丈夫?」
「大丈夫です…」
人前で涙を流したのなど久しぶりだ。天涯孤独になった瞬間すら泣かなかった、泣けなかった。だからこそ、恥ずかしいやら情けないやらで、感情がごちゃ混ぜになっている。
でもそれが嫌ではなかった。まるで本当はこういう感情になりたかったんだと、そう思った。
僕は嗚咽交じりに泣いた。彼女に会えてよかったと、そう思った。
──
─
「落ち着いた?」
「…はい」
どれくらいそうしていたか。気がつけば少しだけ夜が濃くなっていた。小道を渡る人も一人もいない、それくらいに夜が更けていた。
僕が泣き止むまで彼女は僕の背をさすってくれていた。心も落ち着き、今は穏やかになったと思う。目元が赤くじんわりと熱を持っているのを感じられるほどに。
「すみません、突然泣いてしまって」
「ううん、大丈夫」
彼女は僕を見て微笑み、またゆっくりと背を撫でてくれる。トントンとときたまあやす様に叩く掌が心地いい。
「…身の上話をしてもいいですか?」
先程の助けられた対価ではない、純粋な気持ちで僕はそう言う。彼女には聞いて欲しい、そう思った。
「…つい数週間前、3月の初めに僕はここに越して来ました」
どこから話すべきか、そう感じながらも成り行きで言葉を紡ぎ始める。
「うん」
「都会の大学に出るためです。長野の北の小さな町から、漠然とした都会への憧れとか、町や家に縛られたくないとか、そんな理由です」
彼女は静かに頷きながら聞いてくれていた。
「両親と大喧嘩して、それでも半ば無理やり上京しました。過ごす家の下見とか、そんな風な理由をつけて。そしたら…」
「……」
「上京していたタイミングで……地元が大震災に見舞われたんです」
僕は少し言い淀みつつ、僕の身にあった出来事を話した。
「…ニュースで見た。東京も大きく揺れたの覚えてる。揺れたのって深夜だよね?3時とか4時とか」
「はい、まさに新居で寝ている間でした」
「たしかかなり大きくて、今も──」
「復興中です。混乱を避けるために被災地へ行くのは止められてます」
「そうよね……あれ?もしかして…」
「はい、帰れてないです。地元には一度も」
彼女はハッと驚いた表情をした。
「え、一度も!?」
「はい。向こうはまだ雪の影響もあって復興に時間もかかってます。…3月は少し天気が荒れ気味になりますから」
声が少し潤んだ。思い返して悲しくなり、涙声になる。
「家族とは連絡が取れていません。両親は、行方不明者として名前があげられていました。兄弟も、縁の近い親戚もいません。友人すら音沙汰なしです。全員いなくなったとは考えられませんが、深夜の大地震だったのでスマホなんて持って逃げなかったのでしょうね」
「……」
彼女の顔が夜の街に陰る。なんと声を掛けたらよいかわからないといったような表情をしていた。
「友人も家族も、朝起きたらなにもかも…僕は一夜にしてすべてを失ってしまいました」
そう言って僕は俯く。一気に言葉にできたのはここまでだった。目からこぼれた大粒の雫が、汚れた石畳に落ちてシミを作った。
「…僕、地震が起きたの気づかなかったんです。熟睡してたんですよ。朝スマホのニュースで知りました。本当に…本当にっ……馬鹿みたいじゃないですかっ…」
怒りやら情けないやらの感情が思い出されて爆発。慟哭にも似た声色。気持ちが溢れる。
「……」
「……」
ボタボタと、大雨のような涙。僕はなにをしていたんだろう、悔やんでも悔やみきれない。東京に来なければ、大学になんて進学しなければ…。失うなんて誰が想像つくのか。全て知っていれば…なんて、夜の数ほど考えた。
「…眠れなくなったんです」
「え?」
「全てを失った後、眠るのが怖くなりました。不眠症だそうです。寝付けないし、眠れてもすぐ起きてしまうし、見る夢は毎日同じ悪夢です。災禍に包まれる地元の町を動けない状態で見るだけ、ただそれだけです」
正しく地獄。何度も死のうと考え、その度にそんな勇気も出ない自分に嫌気がさす。
夢を見た日の朝は震災の行方不明者の事例を調べ尽くした。希望と絶望がないまぜになるだけなのに。不安と焦燥が心も体も思考すら蝕んでいき、そんな日々についに眠れなくなった。
「……」
彼女の方に目を向けると、少し驚いたような表情をしていた。
「驚いた…」
「え?」
「少しだけ、私と似てるなって思って」
そう言って彼女はなにかを思い出すように下を向く。
「別に共感したいとかそういうつもりで言うんじゃないけど、私も眠れないの」
「…本当ですか?」
「うん。だからこうして夜通し働いているの」
思い出したくない過去なのだろうか。苦虫を噛み潰したような表情。
「魁人くんとは少し違った理由だけどね。私も寝るのは怖いんだ」
眠れないつらさがわかるからこそ、僕まで苦しくなり、心がキュッとなる。苦しげな表情をする彼女は、泡沫のように消えてしまうのではと思ってしまうくらい、儚げだった。
「震災が起きる前に母と電話してました。半ば無理矢理上京した僕に、母は最期になにか言おうとしてたんです。それがなにかはわからないままになってしまいました」
そんな寂しさに共鳴するように、言葉を紡ぐ。奇しくも似た境遇を持つ彼女にならこの痛みもつらさもなにもかも理解してくれるような気がした。
彼女は涙ぐみながら僕の頬に触れた。言葉はなかったが、悲しいねと、そう言っているような気がした。
「…魁人くんはさ」
「……はい」
「…どうしたら救われる?」
「……」
押し黙る。つらすぎて考えたこともなかった。どうしたらこの苦しみがなくなるのか。いろいろあるとは思うが、一番はやっぱり──
「家族が見つかるといいと思います。それまでは…せめて、独りじゃないと思いたいです」
「…わかった」
そう言って彼女はバスケットの中のアップルパイを取り出して優しく包み込んだ。
「……」
一瞬、フワッと彼女の髪が靡く。ほんのり髪色が赤く染ったような気がした。
まただ、さっきと同じ。不思議な感覚。僕は視界に映る光景を疑い、目を擦る。
「…今日は一緒にいるよ。夜が明けるまで」
擦った目を開けるとすぐに彼女がそう言った。髪色は麗しい黒一色だった。
「まだまだ夜は長いし、眠れないもの同士楽しいお話をしよっか」
笑う彼女が都会の月明かりに照らされる。春の夜に白雪のような綺麗な肌が映える。綺麗だなと思った。
「…はい」
行きずりでもなんでもいい。この不思議な出会いに感謝しよう。
──
─
「──あっ」
「あ…もうこんな時間なのね」
クスリと彼女が笑った。笑顔が明るく見える。
それもそのはず。四季の路から見えるビルの間の空は少しずつ白み始めていた。スマホを確認すると午前5時半。優しい朝日を感じたのは久々だった。
「…途中から記憶がないんですけど、僕起きてました?」
「えぇ、本当に眠らないで一緒にいた人初めてよ。最後のほうはボーっとしてたけどね」
彼女が朝日と同じ柔らかさで微笑む。
ただひたすらに他愛もない話をしていた。何が好きなのかとか彼女のいた国はどうだったとか。面白みもない話題ばかりだったかもしれない。それでも僕にとっては心地のいい時間だった。
「さてと…それじゃそろそろ戻ろうかな」
「……」
そんな時間にも終わりは来る。これで終わりだと思うと少し惜しい気持ちになった。
「…ほら、そんな顔しないで」
彼女はそう言って立ち上がり、手を差し伸べる。善意でいてくれた彼女に最後まで気を遣わせてしまった。これじゃ駄目だな…。
「すみません…」
差し伸べてくれた手を取り、僕は立ち上がった。
「あっ、そうだ」
すっと手が離れた後、彼女がなにか思い出したような声をあげる。
「これ、受け取って?」
そう言ってバスケットから取り出したのは1つのアップルパイだった。
「えっ、いいんですか?」
「もちろん。…外にいたから少し冷めちゃったけど」
林檎1つ分に満たない重さが掌に乗る。冷えきってはいたが、微かに甘い香りがした。
「魁人くん」
「はい」
「眠れるといいね」
言葉は発さずこくりと頷く。暁に目を細める。彼女の優しさも陽の光も、眩しいと思った。
「…じゃあ、またね!」
そう言って彼女は手を振りながら去っていった。振り返ることなく赤色のウェイター服を揺らして小さくなっていく。それを見えなくなるまで見つめていた。
本当に不思議な時間だった。まるで現実ではないような、夢のような儚さ。こんな夢ならいつまでも見ていたいと思った。
「……」
また会えるだろうか。
そう思いながら貰ったアップルパイを齧る。シナモンのが香り、彼女とした会話の一つ一つが思い起こされる。
「……」
ツーっと涙が頬を伝った。暖かいなと、冷めたアップルパイを頬張りながらそう思った。