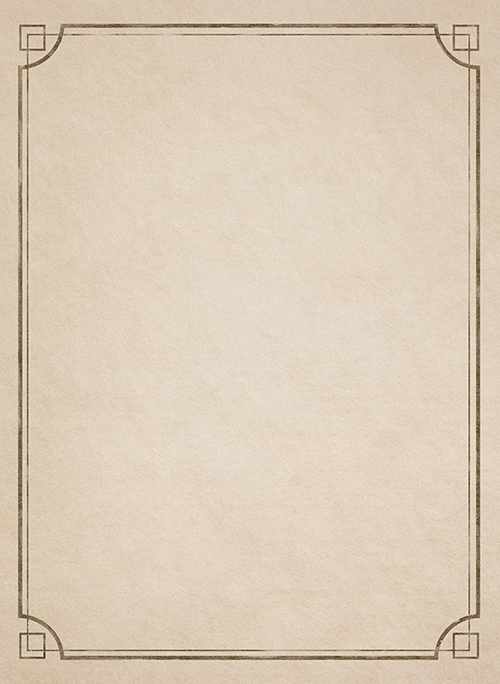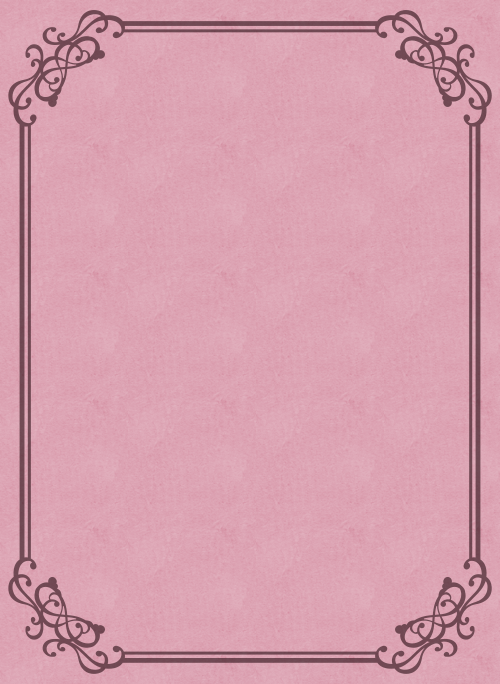部活も他に何かをやっているわけでない俺は、休みは家にいる。
今日は休日だ。
例のごとく、俺は自宅にいた。
だけども今日は、例外的に家には居たくなかった。
母親から、例の傘の件について問い詰められたのだ。
俺の母親も父親も、基本的に家にはいない。
そのため、俺とは会話をすることがない。
もし、会話をする場合は、問題が起きた時だけだ。
つまり、今日のような。
災厄の土曜日だ。
俺は、母親に説明をしたが。
そこから傘の話から成績や将来の話へと話が広がっていく。
…これだから、女性の話は嫌いだ。
非論理的な話。
感情的で、なんに得ることがない。
俺は、母親の話を耳から垂れ流しながら、そう思った。
とはいえ、俺も馬鹿ではない。
申し訳なさそうに、神妙な感じで話を聞き。
そして、時折、謝罪も忘れない。
彼女は俺を予備校へ通わせたいらしい。
実のところ、俺は通っても成績は上がらない、と思った。
なにせ、やる気がないのだ。
とはいえ、そこで反対するほど馬鹿ではない。
俺は、賛成しながら、話を聞く。
そんな技法を駆使しても、母親の話は終わらない。
はぁ、まいったな。
俺は、母親の愚痴なのか、不安なのかよく分からない話を聞きながら、どうするかと考えた。
それから、数時間は話をしていたと思う。
たぶん、俺は夏休み中に予備校に通うらしい。
そして、傘の件は女子へ謝るべきらしい。
結局、話は何も纏まらなかった。
俺は、母親との話が終わった隙を見計らって外に出ることにした。
もちろん、理由はあった。
母親が選んだ、この予備校に行く。
そして、そこでお話を聞きに行く、という大義名分だ。
俺は、母親から貰ったパンフレットをカバンに突っ込んで、家を出た。
自転車へ跨って、俺は出かけていく。
行先はもちろん、予備校などではない。
俺は自転車のペダルを漕ぎながら、行き先を決めていなかった。
とりあえず、家から遠くにいくことに専念していた。
気がつくと、俺が住んでいる住宅地から外れた川辺に来ていた。
ここなら誰にも会わないだろう。
まあ、俺には友人も恋人もいない。
俺の両親に、俺がどこにいたかを報告するのは学校の先生くらいだろう。
しかし、念を入れる必要はあるのだ。
いや?
予備校に母親が電話をするかも?
でも、まだ予備校に所属していない生徒の確認なんて予備校がやるだろうか?
そんなことを考えつつ。
とりあえず、俺は自転車を止めた。
周囲に座れる場所を探す。
川沿いの遊歩道。
その周囲は、コンクリートブロックで舗装されている。
そして、その川に掛かっている橋。
その橋桁の下は影になっている。
俺は、陰になっている場所に腰を掛けることにした。
ちょうどコンクリートブロックが段差になっており、座りやすい。
ポケットから取り出した予備校のパンフレットを眺める。
正直、行く気はまったくない。
しかし、両親に予備校へ行ったという風に見せることは大事だ。
さて、どうやって予備校に行かずに行ったように見せるか?
パラパラと予備校の情報を見ながら、考えていた。
考えていると、だんだんと眠気が襲ってくる。
つい、ウトウトとしていた時だった。
自分の肩が叩かれた。
誰だ?
まさか、母親か?
俺は、さっと血の気が引いた気がした。
瞬時に肩を叩かれた方へと振り返った。
肩まで伸びた茶色がかった髪が風に揺れていた。
優しげな目元に、大きな瞳。
小さな鼻と柔らかそうな唇が印象的な、整った顔立ち。
あいつだ。
白のTシャツに黄色のパンツ。
スリムな体型には変わらない。
背が伸びたみたいだ。
それ以外は相変わらずだ。
「あのー、すいません?…あっ!やっぱり、雄太君だ!」
彼女はそう言って、笑っている。
立山麻衣(たてやま まい)。
立山は、中学時代に一緒だった。
妙に俺に絡んでくる不思議な女子だった。
一緒にスマホゲームをやったり、ゲームをやったり。休みにゲームをしたり。
…ゲームしかやってないな。
違う高校へ進学したので、もう一生会うことはないと俺は思っていた。
そういえば、卒業前。
彼女は強引に俺は、彼女の連絡先を押し付けられた。
すぐに連絡しろとか言っていた。
それからしばらくは、彼女から頻繁にメッセージやら、連絡が来ていたようだった。
しかし、面倒だったので、俺は一切応じなかった。
というより、すぐにブロックと着信拒否に設定した。
今どうなっているのか、よく分からない。
「酷い!雄太君。私の連絡に応じないなんて!」
「え?ああ、うん……」
俺は言葉を濁した。
正直、どう対応すればいいか分からなかった。
「もう!せっかく連絡先教えたのに!私、毎日メッセージ送ってたんだよ?」
立山は、俺の腕を掴んで揺さぶってきた。
相変わらず、スキンシップが多い奴だ。
「悪い。携帯、壊れてて……」
とっさに俺は嘘をついた。
しかし、立山は納得していないようだった。
「嘘だー!絶対嘘!雄太君のゲームアカウントはログインされてたもん!」
くそ。ゲームのことを忘れていた。
「まあ、いいや。久しぶりに会えたんだし!」
立山はニッコリと笑って、そう言った。
「それにしても、雄太君がこんなところで何してたの?」
立山は俺の隣に座り、首を傾げた。
「別に…」
俺は曖昧に答えたが、立山の鋭い目が俺の手元に向けられた。
「あれ?それ予備校のパンフレット?」
「ああ…まあな。」
逃げられないと悟り、俺は素直に認めた。
今後の展開が俺には読めた。
「へぇー!雄太君も予備校行くんだ!どこ?」
立山は興味津々の様子で、俺の手からパンフレットを奪い取った。
「おい。返せよ、それ。」
「えーと…あ!これってさ、私が通ってる予備校だよ!」
立山の目が輝いた。
「そうか。」
「うん!間違いない!ねえねえ、雄太君もここに決めたの?」
「まあ、行かざるをないだろうな。」
俺は事実をいった。
「そっかー。でも、ここいいよ!先生たちも優しいし、授業も分かりやすいし!」
立山は熱心に説明し始めた。
俺はその様子を横目で見ながら、川面を眺めていた。
「それに、私がいるからさ!絶対楽しいよ!」
「そうだな。」
俺はどうしようかと、考えていた。
立山と一緒にゲームをするのは悪くない。
でも、当初の目論見である、予備校に行かない、に黄色信号が灯っていた。
「もう!失礼な反応!今の高校でも、美少女でモテるのに!」
立山は頬を膨らませた。
まあ、顔は可愛い。
それは認めよう。
でも、俺は一人になりたかったのだ。
「雄太君が来てくれるなんて、嬉しいな…」
立山の声のトーンが少し下がった。
俺の考えと、彼女の思考が、まったく被っていないようだ。
「そうか。しかしな、俺が行っても。」
「違うよ!雄太君が来てくれたら、私、すっごく嬉しい!」
立山は真剣な眼差しで俺を見つめた。
「なんでだよ。」
「だって…中学の時から、雄太君のこと気になってたから…」
立山の頬が少し赤くなった。
俺は何と言っていいか分からなくなった。
「あー…そう…。」
かろうじて俺は、そう言った。
気まずい空気が流れた。
俺は唐変木ではないので、立山が俺を好きなことは分かった。
しかし、彼女が見ている俺の姿が全く分からない。
俺のどこがいいのか、まったく分からない。
立山は俺の手を握りしめた。
立山は顔を真っ赤にしながら、じっとこっちを見ている。
「雄太君。私のこと好き?」
立山はそんなことを聞いてきた。
たしかに、これまで彼女から告白されたことはなかった。
なんとなく察したことはあったが。
「うーん。俺は恋人や友達は作らないんだ。」
本心を言った。
俺は、面倒な人間関係が何よりも嫌なのだ。
立山は俺の答えが気に入らない様子で、俺をじっと睨みつけてきた。
「私のこと嫌い?それとも他に好きな人がいるの?」
彼女は必至なご様子だ。
その気迫に気圧されながら俺は、答えた。
「いない。」
俺の答えを聞いて、立山は口元を緩ませた。
「じゃあ、私と付き合おうよ!雄太君!」
立山は、さらに俺へ迫ってきた。
「えっと、な。」
「なんでよ!いいじゃん!ね?私、可愛いし、頭もいいし!予備校も一緒で!それに、雄太君のゲームアカウントも知ってるし!」
立山の押しは強い。
それに、俺のゲームアカウントは関係あるのか?
「いや、その…。」
「何?雄太君は、私じゃ嫌なの?」
潤んだ瞳で、立山は俺を見つめる。
非常に拒否しずらい雰囲気を出している。
「いや、そういうわけじゃないが……」
「じゃあ、何?」
俺は、どう答えればいいのか分からなかった。
いや、そもそも俺は、男女交際なんてしたくないのだ。
「なあ、俺はさ。」
「うん。」
「恋愛とか興味ないんだわ。」
俺は、正直に答えた。
「なんでよ!いいじゃん!私が彼女で!」
彼女はそう言った。
表情がコロコロと変わる。
「そうは言われてもな。一人が楽だしな。」
俺は、繰り返し同じ主張をする。
別の表現で。
「雄太君ってモテるの?」
立山はそんなことを聞いてくる。
「いや、モテない。」
「じゃあ、私でいいじゃん!」
立山は、さらに俺に迫ってきた。
「えっと……」
俺は、何か適当に言葉を続けようとした。
「雄太君、もう決まりです!今日から私たちは恋人ね?」
立山は、俺の手を握りしめて、そう言った。
「あー、そうだ。予備校の体験入学へ行かないと。」
俺は、適当なことを言った。
そして、とにかくこの場を離れることにした。
「まあ、これから予備校で会うだろ?今日はじゃあな。」
「あ!ちょっと雄太君!待ってよ!」
そんな立山の言葉を無視して、俺は立ち上がった。
「悪いな。」
「あ!ちょっと!」
立山は俺を追いかけてきた。
俺はそれを振り切るようにして、自転車に跨った。
「雄太君!」
後ろから聞こえる立山の声を聞きながら、俺は自転車で走りだした。
さて、これからどこへ行くべきなのか。
俺は考えながら、速やかに河辺から離脱していった。
今日は休日だ。
例のごとく、俺は自宅にいた。
だけども今日は、例外的に家には居たくなかった。
母親から、例の傘の件について問い詰められたのだ。
俺の母親も父親も、基本的に家にはいない。
そのため、俺とは会話をすることがない。
もし、会話をする場合は、問題が起きた時だけだ。
つまり、今日のような。
災厄の土曜日だ。
俺は、母親に説明をしたが。
そこから傘の話から成績や将来の話へと話が広がっていく。
…これだから、女性の話は嫌いだ。
非論理的な話。
感情的で、なんに得ることがない。
俺は、母親の話を耳から垂れ流しながら、そう思った。
とはいえ、俺も馬鹿ではない。
申し訳なさそうに、神妙な感じで話を聞き。
そして、時折、謝罪も忘れない。
彼女は俺を予備校へ通わせたいらしい。
実のところ、俺は通っても成績は上がらない、と思った。
なにせ、やる気がないのだ。
とはいえ、そこで反対するほど馬鹿ではない。
俺は、賛成しながら、話を聞く。
そんな技法を駆使しても、母親の話は終わらない。
はぁ、まいったな。
俺は、母親の愚痴なのか、不安なのかよく分からない話を聞きながら、どうするかと考えた。
それから、数時間は話をしていたと思う。
たぶん、俺は夏休み中に予備校に通うらしい。
そして、傘の件は女子へ謝るべきらしい。
結局、話は何も纏まらなかった。
俺は、母親との話が終わった隙を見計らって外に出ることにした。
もちろん、理由はあった。
母親が選んだ、この予備校に行く。
そして、そこでお話を聞きに行く、という大義名分だ。
俺は、母親から貰ったパンフレットをカバンに突っ込んで、家を出た。
自転車へ跨って、俺は出かけていく。
行先はもちろん、予備校などではない。
俺は自転車のペダルを漕ぎながら、行き先を決めていなかった。
とりあえず、家から遠くにいくことに専念していた。
気がつくと、俺が住んでいる住宅地から外れた川辺に来ていた。
ここなら誰にも会わないだろう。
まあ、俺には友人も恋人もいない。
俺の両親に、俺がどこにいたかを報告するのは学校の先生くらいだろう。
しかし、念を入れる必要はあるのだ。
いや?
予備校に母親が電話をするかも?
でも、まだ予備校に所属していない生徒の確認なんて予備校がやるだろうか?
そんなことを考えつつ。
とりあえず、俺は自転車を止めた。
周囲に座れる場所を探す。
川沿いの遊歩道。
その周囲は、コンクリートブロックで舗装されている。
そして、その川に掛かっている橋。
その橋桁の下は影になっている。
俺は、陰になっている場所に腰を掛けることにした。
ちょうどコンクリートブロックが段差になっており、座りやすい。
ポケットから取り出した予備校のパンフレットを眺める。
正直、行く気はまったくない。
しかし、両親に予備校へ行ったという風に見せることは大事だ。
さて、どうやって予備校に行かずに行ったように見せるか?
パラパラと予備校の情報を見ながら、考えていた。
考えていると、だんだんと眠気が襲ってくる。
つい、ウトウトとしていた時だった。
自分の肩が叩かれた。
誰だ?
まさか、母親か?
俺は、さっと血の気が引いた気がした。
瞬時に肩を叩かれた方へと振り返った。
肩まで伸びた茶色がかった髪が風に揺れていた。
優しげな目元に、大きな瞳。
小さな鼻と柔らかそうな唇が印象的な、整った顔立ち。
あいつだ。
白のTシャツに黄色のパンツ。
スリムな体型には変わらない。
背が伸びたみたいだ。
それ以外は相変わらずだ。
「あのー、すいません?…あっ!やっぱり、雄太君だ!」
彼女はそう言って、笑っている。
立山麻衣(たてやま まい)。
立山は、中学時代に一緒だった。
妙に俺に絡んでくる不思議な女子だった。
一緒にスマホゲームをやったり、ゲームをやったり。休みにゲームをしたり。
…ゲームしかやってないな。
違う高校へ進学したので、もう一生会うことはないと俺は思っていた。
そういえば、卒業前。
彼女は強引に俺は、彼女の連絡先を押し付けられた。
すぐに連絡しろとか言っていた。
それからしばらくは、彼女から頻繁にメッセージやら、連絡が来ていたようだった。
しかし、面倒だったので、俺は一切応じなかった。
というより、すぐにブロックと着信拒否に設定した。
今どうなっているのか、よく分からない。
「酷い!雄太君。私の連絡に応じないなんて!」
「え?ああ、うん……」
俺は言葉を濁した。
正直、どう対応すればいいか分からなかった。
「もう!せっかく連絡先教えたのに!私、毎日メッセージ送ってたんだよ?」
立山は、俺の腕を掴んで揺さぶってきた。
相変わらず、スキンシップが多い奴だ。
「悪い。携帯、壊れてて……」
とっさに俺は嘘をついた。
しかし、立山は納得していないようだった。
「嘘だー!絶対嘘!雄太君のゲームアカウントはログインされてたもん!」
くそ。ゲームのことを忘れていた。
「まあ、いいや。久しぶりに会えたんだし!」
立山はニッコリと笑って、そう言った。
「それにしても、雄太君がこんなところで何してたの?」
立山は俺の隣に座り、首を傾げた。
「別に…」
俺は曖昧に答えたが、立山の鋭い目が俺の手元に向けられた。
「あれ?それ予備校のパンフレット?」
「ああ…まあな。」
逃げられないと悟り、俺は素直に認めた。
今後の展開が俺には読めた。
「へぇー!雄太君も予備校行くんだ!どこ?」
立山は興味津々の様子で、俺の手からパンフレットを奪い取った。
「おい。返せよ、それ。」
「えーと…あ!これってさ、私が通ってる予備校だよ!」
立山の目が輝いた。
「そうか。」
「うん!間違いない!ねえねえ、雄太君もここに決めたの?」
「まあ、行かざるをないだろうな。」
俺は事実をいった。
「そっかー。でも、ここいいよ!先生たちも優しいし、授業も分かりやすいし!」
立山は熱心に説明し始めた。
俺はその様子を横目で見ながら、川面を眺めていた。
「それに、私がいるからさ!絶対楽しいよ!」
「そうだな。」
俺はどうしようかと、考えていた。
立山と一緒にゲームをするのは悪くない。
でも、当初の目論見である、予備校に行かない、に黄色信号が灯っていた。
「もう!失礼な反応!今の高校でも、美少女でモテるのに!」
立山は頬を膨らませた。
まあ、顔は可愛い。
それは認めよう。
でも、俺は一人になりたかったのだ。
「雄太君が来てくれるなんて、嬉しいな…」
立山の声のトーンが少し下がった。
俺の考えと、彼女の思考が、まったく被っていないようだ。
「そうか。しかしな、俺が行っても。」
「違うよ!雄太君が来てくれたら、私、すっごく嬉しい!」
立山は真剣な眼差しで俺を見つめた。
「なんでだよ。」
「だって…中学の時から、雄太君のこと気になってたから…」
立山の頬が少し赤くなった。
俺は何と言っていいか分からなくなった。
「あー…そう…。」
かろうじて俺は、そう言った。
気まずい空気が流れた。
俺は唐変木ではないので、立山が俺を好きなことは分かった。
しかし、彼女が見ている俺の姿が全く分からない。
俺のどこがいいのか、まったく分からない。
立山は俺の手を握りしめた。
立山は顔を真っ赤にしながら、じっとこっちを見ている。
「雄太君。私のこと好き?」
立山はそんなことを聞いてきた。
たしかに、これまで彼女から告白されたことはなかった。
なんとなく察したことはあったが。
「うーん。俺は恋人や友達は作らないんだ。」
本心を言った。
俺は、面倒な人間関係が何よりも嫌なのだ。
立山は俺の答えが気に入らない様子で、俺をじっと睨みつけてきた。
「私のこと嫌い?それとも他に好きな人がいるの?」
彼女は必至なご様子だ。
その気迫に気圧されながら俺は、答えた。
「いない。」
俺の答えを聞いて、立山は口元を緩ませた。
「じゃあ、私と付き合おうよ!雄太君!」
立山は、さらに俺へ迫ってきた。
「えっと、な。」
「なんでよ!いいじゃん!ね?私、可愛いし、頭もいいし!予備校も一緒で!それに、雄太君のゲームアカウントも知ってるし!」
立山の押しは強い。
それに、俺のゲームアカウントは関係あるのか?
「いや、その…。」
「何?雄太君は、私じゃ嫌なの?」
潤んだ瞳で、立山は俺を見つめる。
非常に拒否しずらい雰囲気を出している。
「いや、そういうわけじゃないが……」
「じゃあ、何?」
俺は、どう答えればいいのか分からなかった。
いや、そもそも俺は、男女交際なんてしたくないのだ。
「なあ、俺はさ。」
「うん。」
「恋愛とか興味ないんだわ。」
俺は、正直に答えた。
「なんでよ!いいじゃん!私が彼女で!」
彼女はそう言った。
表情がコロコロと変わる。
「そうは言われてもな。一人が楽だしな。」
俺は、繰り返し同じ主張をする。
別の表現で。
「雄太君ってモテるの?」
立山はそんなことを聞いてくる。
「いや、モテない。」
「じゃあ、私でいいじゃん!」
立山は、さらに俺に迫ってきた。
「えっと……」
俺は、何か適当に言葉を続けようとした。
「雄太君、もう決まりです!今日から私たちは恋人ね?」
立山は、俺の手を握りしめて、そう言った。
「あー、そうだ。予備校の体験入学へ行かないと。」
俺は、適当なことを言った。
そして、とにかくこの場を離れることにした。
「まあ、これから予備校で会うだろ?今日はじゃあな。」
「あ!ちょっと雄太君!待ってよ!」
そんな立山の言葉を無視して、俺は立ち上がった。
「悪いな。」
「あ!ちょっと!」
立山は俺を追いかけてきた。
俺はそれを振り切るようにして、自転車に跨った。
「雄太君!」
後ろから聞こえる立山の声を聞きながら、俺は自転車で走りだした。
さて、これからどこへ行くべきなのか。
俺は考えながら、速やかに河辺から離脱していった。