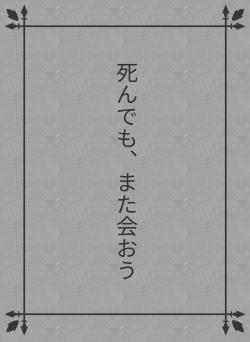最初は、ただの憧れだった。私にない物を全て持っていて、なんでも完璧にこなす君は美しく輝いて見えた。惚れたのは間違いないあの時だ。
私は、しがない学級委員長。やる人がいなくて押し付けられた。泣く泣く始めた学級委員長。誰も、私の話など聞かない。先生も助けてくれない。そんな中、君だけだった。目を見て意見をして、任意のアンケートに答えてくれて。そっと助け舟を出してくれる。もうその時点で私の心は君に奪われていたのかもね。
恋心を、自覚したのは、私の体調不良に気づいてくれた時だ。お腹が痛いのを我慢しながら、文化祭の企画を進めていた。他の文化祭実行委員は気づかない。私自身も上手く隠している……つもりだった。
「希帆。お前。」
「はい、なんでしょう。」
「さては、体調悪いな?」
「え…………。なんで……?」
「俺は魔法が使えるからな。ここは、任せて保健室にでも行って来い。」
「ぁ…………ありがとう。佐熊くん。」
必要以上に高鳴る胸と踊る心。間違いないこれは恋。私の直感がそう告げた。同時に叶わないと思った。佐熊くんには、親しげな女性がいて叶わぬ恋だと思った。けれど、抑えられない恋心。気づいたら、告白していて。気づいたら恋人になっていた。
私は、しがない学級委員長。やる人がいなくて押し付けられた。泣く泣く始めた学級委員長。誰も、私の話など聞かない。先生も助けてくれない。そんな中、君だけだった。目を見て意見をして、任意のアンケートに答えてくれて。そっと助け舟を出してくれる。もうその時点で私の心は君に奪われていたのかもね。
恋心を、自覚したのは、私の体調不良に気づいてくれた時だ。お腹が痛いのを我慢しながら、文化祭の企画を進めていた。他の文化祭実行委員は気づかない。私自身も上手く隠している……つもりだった。
「希帆。お前。」
「はい、なんでしょう。」
「さては、体調悪いな?」
「え…………。なんで……?」
「俺は魔法が使えるからな。ここは、任せて保健室にでも行って来い。」
「ぁ…………ありがとう。佐熊くん。」
必要以上に高鳴る胸と踊る心。間違いないこれは恋。私の直感がそう告げた。同時に叶わないと思った。佐熊くんには、親しげな女性がいて叶わぬ恋だと思った。けれど、抑えられない恋心。気づいたら、告白していて。気づいたら恋人になっていた。