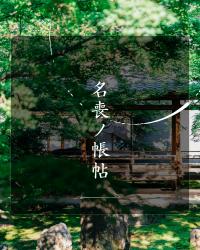もう何年もずっと前から貴女だけを追っていた。
気づいていなくたっていいから。
だから今から意識してほしい。
僕の好きの気持ちを込めて伝えるから。
迷惑かもしれないけれど。
ただの自己満だって言われればおしまいだけど。
それでも知ってほしかったから────。
今思えば彼女が好きだと気づいたのはきっと5歳の頃。
幼いながらも好きな人嫌いな人が目に見えてわかる年齢。
今だったら嫌いな人とでもあたり障りなく会話をする。
けれど幼い頃は嫌いな人は徹底して無視。
相手に泣かれてなだめに入った幼稚園の先生に『どうして仲良くできないの?』と聞かれると『だって嫌いなんだもん』と言われる。
この経験を僕はしたことがある。
僕は嫌われる側だった。
そんな僕に近所の女の子は優しく接してくれた。
一緒に遊んでくれ、ひらがな・カタカナ・漢字、足し算・引き算・かけ算九九も教えてくれた。
当時はよくわかっていなかったけれど彼女と遊んで勉強する時間が楽しくて、懐くのに時間なんてかからなかった。
園に行けば窓から見える彼女が通っている近くの小学校の校舎を眺める毎日。
お迎えが来て家に帰ると手洗いうがいをしっかりした後に彼女の家のインターホンを押しに行く。
そんな日々。
彼女とは3歳差で園で会えることはなかった。
けれど卒園して入学すれば同じ小学校へ通えると知ったときにはとても嬉しかったことを今でも覚えている。
けれどいざ入学すると彼女と校舎内で会えることは少なかった。
小学1年生と小学4年生。
教室も階も違うのは当たり前のこと。
学校も帰った後までも一緒だとずっと思っていたから衝撃を受けた。
彼女と一緒なのは登下校の時間だけ。
20分休みや昼休憩に上の学年に混ざって仲間に入れてもらえば彼女とも遊べたけれど僕にはできなかった。
下校した後に宿題を教えてもらうようになっていた。
彼女の卒業式では大泣きした。
僕が卒業するわけでもないのに卒業生と同じくらい泣いた。
僕の知る限り在校生の中で泣いていたのは僕だけだったと思う。
中学校へ入学したときにはもう彼女は高校生になっていて、『何で中学は3年しかないんだよ』とひとり心の中で毒づいていた。
彼女は、1-G・2-D・3-Aだったらしい。
僕らの学年は人数が少なかった関係で6組、つまりFまでしかなかった。
だから僕は2-D・3-Aになれますようにと祈っていた。
その願いが叶ったのは2年生の頃。
残念ながら3年ではAにならなかった。
丁度この頃、2年の頃から成績が悪くなっていった。
せめて5教科くらいはなんとかしたくて母親に相談してみた。
すると次の日、家に帰ると彼女が家にいた。
家庭教師として彼女は僕に勉強を教えてくれることになったらしい。
そんな彼女の家庭教師は僕が高校2年生になった今でも続いている。
「あれ、圭くん。こんなところで何してるの?」
川べり、橋の陰で暑さをしのぎながら参考書を開いていた。
貴女を待ってましたなんて言えない。
言えるわけない。
太陽の光を反射してキラキラと光る川の流れ。
青い空に浮かぶ白い雲。
反対岸にはつづく緑と街並。
このまま通り過ぎることだってできたのに下りくると僕の隣に腰かけた。
夏風に揺れる彼女の髪。
小鹿の毛並みみたいなフォーン色。
白いブラウスに黄色いパンツ。
ヒールのあるベージュの靴。名前は確か......パンプス?
「好きだ」『かわいい』
「へ?」
彼女の慌てた、それでいて驚いた表情が目に映る。
僕は今何て言った?
顔に熱が集中していくのがわかる。
想っていたことが口をついて出てしまった。
伝えてしまったものは取り消しができない。
言い訳もできない。
彼女には断られるだろう。
拒否されるだろうことはあらかじめ想定していた。
嫌われる時期が少し早まっただけだ。
周りはエリートだらけの男子大学生に僕なんかが勝てるわけがない。
「圭くん、ちょっとごめんね」
そう言って立ち上がった彼女。
できれば意識してもらいたかったけれどそれも無理そうだった。
無計画に告白してしまったせいで、この後のかてきょーでどんな顔で合えばいいのかわからない。
「圭くん、これとりあえず飲みなよ」
戻ってきた彼女の手には天然水。
自販機で買うために離れたんだとわかってその水を受け取った。
でもまだ油断は禁物だ。
水を口に含ませてごくりと飲み下す。
「まり姉......」
「圭くん、まり姉はもう禁止ね?私の名前は日葵だよ?」
微笑む彼女の頬は少し赤らんでいるように見えて、期待してしまう僕はいけないだろうか
「圭くん、かてきょーの前に時間ある?」
「あ、るけど。」
「なら圭くんの部屋で後の話はしようか」
ほら立ってと立ち上がって僕に手を伸ばすその手のひらをつかんだ。
僕が立ち上がって離そうと手を緩めると彼女はなぜか柔く僕の手を握り返す。
「あ、ごめんね。これだと圭くん自転車押せなくなっちゃうね」
パッと離された彼女の手。
僕の右手には彼女のぬくもりがまだ残っていて、隣を歩く彼女と僕の影の肩が触れている。
くらくら、陽炎が揺れる。
『好き』の言葉を伝えた夏。
この先の答えなんてわからないけど、僕たちの未来が交差して続いていくといいなと思いをはせた。
気づいていなくたっていいから。
だから今から意識してほしい。
僕の好きの気持ちを込めて伝えるから。
迷惑かもしれないけれど。
ただの自己満だって言われればおしまいだけど。
それでも知ってほしかったから────。
今思えば彼女が好きだと気づいたのはきっと5歳の頃。
幼いながらも好きな人嫌いな人が目に見えてわかる年齢。
今だったら嫌いな人とでもあたり障りなく会話をする。
けれど幼い頃は嫌いな人は徹底して無視。
相手に泣かれてなだめに入った幼稚園の先生に『どうして仲良くできないの?』と聞かれると『だって嫌いなんだもん』と言われる。
この経験を僕はしたことがある。
僕は嫌われる側だった。
そんな僕に近所の女の子は優しく接してくれた。
一緒に遊んでくれ、ひらがな・カタカナ・漢字、足し算・引き算・かけ算九九も教えてくれた。
当時はよくわかっていなかったけれど彼女と遊んで勉強する時間が楽しくて、懐くのに時間なんてかからなかった。
園に行けば窓から見える彼女が通っている近くの小学校の校舎を眺める毎日。
お迎えが来て家に帰ると手洗いうがいをしっかりした後に彼女の家のインターホンを押しに行く。
そんな日々。
彼女とは3歳差で園で会えることはなかった。
けれど卒園して入学すれば同じ小学校へ通えると知ったときにはとても嬉しかったことを今でも覚えている。
けれどいざ入学すると彼女と校舎内で会えることは少なかった。
小学1年生と小学4年生。
教室も階も違うのは当たり前のこと。
学校も帰った後までも一緒だとずっと思っていたから衝撃を受けた。
彼女と一緒なのは登下校の時間だけ。
20分休みや昼休憩に上の学年に混ざって仲間に入れてもらえば彼女とも遊べたけれど僕にはできなかった。
下校した後に宿題を教えてもらうようになっていた。
彼女の卒業式では大泣きした。
僕が卒業するわけでもないのに卒業生と同じくらい泣いた。
僕の知る限り在校生の中で泣いていたのは僕だけだったと思う。
中学校へ入学したときにはもう彼女は高校生になっていて、『何で中学は3年しかないんだよ』とひとり心の中で毒づいていた。
彼女は、1-G・2-D・3-Aだったらしい。
僕らの学年は人数が少なかった関係で6組、つまりFまでしかなかった。
だから僕は2-D・3-Aになれますようにと祈っていた。
その願いが叶ったのは2年生の頃。
残念ながら3年ではAにならなかった。
丁度この頃、2年の頃から成績が悪くなっていった。
せめて5教科くらいはなんとかしたくて母親に相談してみた。
すると次の日、家に帰ると彼女が家にいた。
家庭教師として彼女は僕に勉強を教えてくれることになったらしい。
そんな彼女の家庭教師は僕が高校2年生になった今でも続いている。
「あれ、圭くん。こんなところで何してるの?」
川べり、橋の陰で暑さをしのぎながら参考書を開いていた。
貴女を待ってましたなんて言えない。
言えるわけない。
太陽の光を反射してキラキラと光る川の流れ。
青い空に浮かぶ白い雲。
反対岸にはつづく緑と街並。
このまま通り過ぎることだってできたのに下りくると僕の隣に腰かけた。
夏風に揺れる彼女の髪。
小鹿の毛並みみたいなフォーン色。
白いブラウスに黄色いパンツ。
ヒールのあるベージュの靴。名前は確か......パンプス?
「好きだ」『かわいい』
「へ?」
彼女の慌てた、それでいて驚いた表情が目に映る。
僕は今何て言った?
顔に熱が集中していくのがわかる。
想っていたことが口をついて出てしまった。
伝えてしまったものは取り消しができない。
言い訳もできない。
彼女には断られるだろう。
拒否されるだろうことはあらかじめ想定していた。
嫌われる時期が少し早まっただけだ。
周りはエリートだらけの男子大学生に僕なんかが勝てるわけがない。
「圭くん、ちょっとごめんね」
そう言って立ち上がった彼女。
できれば意識してもらいたかったけれどそれも無理そうだった。
無計画に告白してしまったせいで、この後のかてきょーでどんな顔で合えばいいのかわからない。
「圭くん、これとりあえず飲みなよ」
戻ってきた彼女の手には天然水。
自販機で買うために離れたんだとわかってその水を受け取った。
でもまだ油断は禁物だ。
水を口に含ませてごくりと飲み下す。
「まり姉......」
「圭くん、まり姉はもう禁止ね?私の名前は日葵だよ?」
微笑む彼女の頬は少し赤らんでいるように見えて、期待してしまう僕はいけないだろうか
「圭くん、かてきょーの前に時間ある?」
「あ、るけど。」
「なら圭くんの部屋で後の話はしようか」
ほら立ってと立ち上がって僕に手を伸ばすその手のひらをつかんだ。
僕が立ち上がって離そうと手を緩めると彼女はなぜか柔く僕の手を握り返す。
「あ、ごめんね。これだと圭くん自転車押せなくなっちゃうね」
パッと離された彼女の手。
僕の右手には彼女のぬくもりがまだ残っていて、隣を歩く彼女と僕の影の肩が触れている。
くらくら、陽炎が揺れる。
『好き』の言葉を伝えた夏。
この先の答えなんてわからないけど、僕たちの未来が交差して続いていくといいなと思いをはせた。