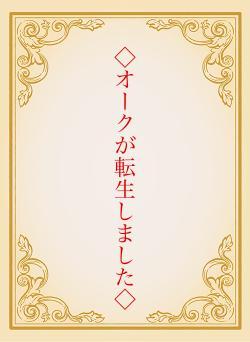「あら。どうかなすったんですか?」
お庭で洗濯干しに勤しんでいましたら、縁側を挟んだ先の書斎にうんうん唸る良庵せんせのお姿が。
今日もあちこちに跳ねる髪を後ろで結え、机に置いた本を食い入る様に見詰めていたんですよ。
「それがさ、ここの所がどう描いてあったのかよく分からないんです」
良庵せんせがお顔をくっつける様にして読んでいるのは、幼い頃から愛読している『野巫三才図絵』です。
『世界でただ一つのこの本に、野巫の全てが記されている』
と冒頭で謳う眉唾ものの一冊ですけど、これが強ち間違いでもありません。
天・地・人、の三部に分かれ――題名の『三才』はこの『三部』を意味しています――、その『人の部』を良庵せんせはお小さい頃から繰り返し読んでいらっしゃるんですよ。
天と地の部については只の人が読むには難解です。まず第一に巫戟の力を理解できねば読んでもちんぷんかんぷんの筈ですから。
「どこですか?」
「ここのところなんですけど」
良庵せんせが指差すところを覗き込むと、
『加齢に伴う節々の痛みにはうんぬんかんぬん――』
ははぁ。昨日お見えになられた熊五郎棟梁の女将さん用ですか。しかし確かにこれは読めませんねぇ。
解説は読めますけれど、肝心の呪符の図柄の細かい所が良庵せんせの手汗のせいか滲んで潰れちまってますね。
「うーん……ちょいと筆と紙を貸して頂けますか?」
「よしきた」
この手の事に勘が良い、良庵せんせは私の事をそう思ってくれていますから、立ち上がって文机の前を私に譲ってくださいました。
ストンと腰を落ち着けて、先ずはじっくり三才図絵の図柄を見詰め、うーん、と小首を傾げる素振りも忘れぬ様に付け加えてから、スラスラサラリンと筆を走らせました。
「こんな感じに見えましたけど、どうです?」
図柄は文字と四角に三角やら丸の模様をがちゃがちゃ混ぜ合わせたもの。
私が描いた図柄を眼鏡を掛けて見、眼鏡を上げて見、さらには角度を変えて凝視する良庵せんせ。
「ふーむ……確かこんな形だったように思えてきました」
良庵せんせはどうにも図形の形を覚えるのが得意でないんですよ。
「ほんとですか?」
「ほんとほんと。きっとこれで合ってる。いやぁ助かりました」
あら可愛らしい。
私に向けてにっこり微笑んだ良庵せんせがとっても可愛らしくてキュンとしちまいました。
良い歳して恥ずかしいですねぇ。
文机を良庵せんせにお返しして、私はお洗濯の続きを、良庵せんせは丁寧に呪符作りを再開です。
お互いにキリのいいところで切り上げて、早目に軽く昼食を済ませて良庵せんせを誘って一つのお布団で一緒に少し微睡んで、そして起きたらちょうど熊五郎棟梁と女将さんが見えられました。
「ほれ、とろとろ歩いてんじゃねぇや」
「この馬鹿! 膝が痛えって言ってるじゃないのさ!」
罵り合っていますけど、ここらじゃ仲良し夫婦で有名なんですよ。
現に女将さんの小荷物を棟梁が持ってあげての道行ですもの。
「相変わらず仲睦まじいお二人ですねぇ」
「僕らもああなれたら良いですね」
門から道場へと歩んでくる二人を、良庵せんせと並んで見ながらそう溢したら、
「お葉ちゃんも先生も何言ってやんでぇ!」
「このヤドロクと仲良くなんてありゃしませんよ!」
熊五郎夫妻にも聞こえてしまってましたが、照れ隠しの仕方までそっくりで、やっぱりちょっと可愛らしくて微笑んでしまいますね。
診察室にお通しして、良庵せんせが女将さんの膝をサスサス触って曲げ伸ばし。
やはり外傷もありませんし、腱や筋肉に損傷もないようです。
「ふむ。やはり棟梁と同じ呪符ではダメだった様だ」
ヒビの入った骨を治すには、元々備わっている元に戻る力を促進させるだけで効果がありますが、加齢による膝痛ではそんな、元に戻る力がまず存在しやしませんからね。
「膝のお皿にズレもない。恐らくは軟い骨の摩耗、すり減りが原因だ」
「軟い骨? なんですそりゃ?」
「膝の骨と骨の間にあるんだよ」
良庵せんせが両手をグーにして縦に並べ、こことここの間、と説明します。
こういった触診は得意な方ですから、ここまではやぶ医者っぽさはないんですよね。
「そこでこの……、あれ?」
袂を弄った良庵せんせでしたが、どうやらお目当てのものがないらしいです。
「まだ文机の上なのではございません?」
「ああそうだ。墨を乾かしていたのでした」
取りに立とうとする良庵せんせを私が参りますと押し留め、これ幸いと書斎へと足早に向かいます。
そして誰もいない書斎で、良庵せんせが丁寧に仕上げた三枚の呪符を恭しく取り上げて、私も丁寧に一枚ずつ巫戟の力を籠めていきます。
巫戟の巫は『かんなぎ』、神を招くを語源とする言葉。
巫戟の戟は、そのまま『げき』、三叉の矛のこと。
巫戟の力で怪我も病魔も、さらには妖魔も退治が可能なんですよ。
って、妖魔の私が手前で言ってちゃ可笑しいですね。
そして何食わぬ顔で戻って良庵せんせに手渡しました。
「ありがとうお葉さん」
優しい良庵せんせはそう言って、女将さんの膝へ一枚の呪符を薄布で巻き付けます。丸一日ほどで次の呪符へ、さらに翌日に最後の呪符へと交換する様にと申し付けました。
「大体丸一日で呪符の墨が急激に薄くなる。それが替え時だから」
さらに付け加えます。
「墨の薄くなった呪符、持ってきて欲しいんだ」
「まだなにかに使えるんで?」
「いや、ちゃんと薄くなるのか知りたいんだ。なにせ初めて試す呪符だからさ」
熊五郎夫妻が微妙に不安そうな顔をした事に、良庵せんせだけが気付かなかったようでした。
きっと大丈夫だと思いますよ。
私の巫戟の力もありますけど、せんせの呪符もばっちり仕上がっていましたから。