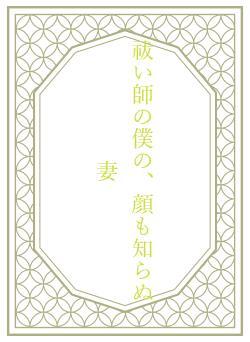「…あの、私たちが、こ、恋人ってことは私は駿ちゃんに告白をした、のかな?」
「してくれたよ。耳まで真っ赤になりながらね。すごく可愛かった」
「っあ、やっぱり、そうなんだ…」
やはり自分は決意した通り、告白を決行したらしい。
全く覚えていないけど。
「それで、ここはどこなの?」
「ここは二人で借りてるマンションだよ」
「ど、同棲してるってこと…?」
「うん。ずっと一緒に居たくて、数年前から一緒に暮らしてる」
まさか恋人になっただけでなく、同棲までしているとは。
私たちは家が近いこともあって、幼稚園から高校までずっと一緒に仲良しな幼なじみとして過ごしてきた。
私からしたら急に同棲カップルにまでスキップした気分だ。
「私は、大学とかは行ってたの?今25歳ってことは働いてるのかな?」
「大学は行けなかったんだけど、今は家で出来る仕事をしてるよ」
「そうなんだ…。まぁ、記憶がないのに勉強なんかできないか」
私が自虐的なことを言うと、駿ちゃんは目線を落として申し訳なさそうな顔になる。
「僕も、サポートできることはしたかったんだけど…。大学だって、一緒のところに行こうって約束してたのに」
「仕方ないよ。それに、きっとこうして毎日、状況説明してくれてるんでしょ?それだけで十分だよ」
駿ちゃんは慣れた様子で私が理解しやすいように話してくれた。
それは記憶がない7年間、毎日してくれているからだと思う。