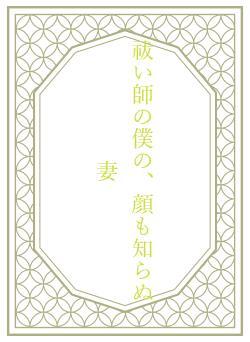「…先生が言うには、これ以上昔の記憶を失くさないようにするのが精一杯だって」
「…」
「脳は特に繊細で、謎の部分が多いみたいで。原因が分かったとしても下手に手術とかをしようとすると、むしろ悪化しかねないんだって」
「うん…、そっか」
仕方ないことだとは分かってる。
でも、自分だけ駿ちゃんとの思い出も何もかもを忘れていってしまうことが、どうしようもなく悲しい。
18歳の頃で止まったまま、一人取り残されてしまうのが怖い。
駿ちゃんの視線が背中に刺さる。
そのまま、何も言わず後ろから優しく抱きしめられた。
「大丈夫、花菜ちゃんを置いていったりなんかしないよ。ずっと、僕が傍にいる」
まるで私の心の声が聞こえたかのような言葉に、苦笑が漏れる。
「やっぱり、何でもお見通しなんだね」
「ずっと、花菜ちゃんだけを見てきたから」