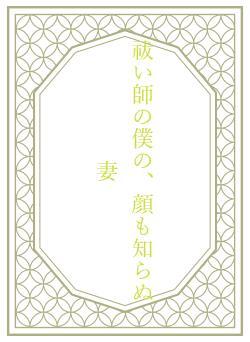資料の内容は半分は分からないものだったけど、私は打ち込むだけでいいので集中出来た。
しばらくリビングにはキーボードを叩く音だけが流れ、二人とも一言も話さなかった。
元々私たちは口数が多い方ではなく、ただ隣にいるだけで時間が過ぎたとしても苦痛には感じない。
幼いころから一緒に居たからこそ、相手が何を考えているのか、何をしてほしいのか、何も言わなくても伝わることが多かったのもあるもしれない。
でも今は、駿ちゃんは出来るだけちゃんと言葉にしてくれているのだと思う。
私には、今日しかないから。
「ねぇ、駿ちゃん」
「なぁに?」
振り返らずに名前を呼ぶと、優しく答えてくれる。
そんな駿ちゃんに、こんなことを聞くのは酷だと思う。
でも、聞かずにはいられなかった。
「…私の記憶は、もう戻らないのかな?」
事故から7年も経っているようだし、きっと治療法もないのだろう。
頭では分かっているのに、少しの希望に縋りたくなってしまった。
もしかしたら時間が掛かるだけでいずれは…、なんて。