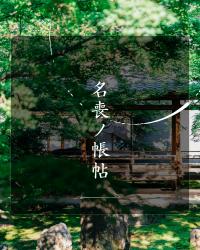きっともうずっと前から気づいてた
なのに、気づかないフリして本当ばかみたいだった
今でも引きずっている過去の苦い記憶
朝起きておはようって
そんな些細な幸せさえ叶わない
いつになったら私の幸せは得られるんだろう
こんな願いすら叶わないなら、もしかしたら私は幸せになってはいけない人なのかもしれない
こんな弱音を吐いたって無意味でしかないのは百も承知
だから泣くのは一人の時だけ
どれだけ悔しくても、不安で苦しくても
人前で涙を見せてはいけない
泣いたらダメなの
それは"自分は弱いです"って私自身が認めているようなものだから
見た目だけでも強くいないと
強がりってバレないように
でも夜になるたびに元彼を思い出して、叶わないのならば消えてしまいたい
…なんてこぼしてしまう
そんなことばも闇夜に紛れて溶けた
──────今宵もまた夜が始まりを告げる
🫧
─『来週、拓真の家行くね』
そう送ったメッセージに返信はまだない
今まではすぐに返事があった
遅くても数時間後かその日中
それがだんだん遅くなっていって今では1週間も未読スルー
返事おそいだけですぐ嫌われたかなって不安になるから
だから嫌いじゃないよって言って欲しい
ただ私が安心したいだけっていわれたらそれまでだけど
─ピンポン
合鍵はまだ渡せてもらえてない
いつか信用される女性になったら渡してくれるかな
「あぁ、美波。来てたんだ」
「メッセージ見てない?」
「あー、、、」
出てきた彼はなんだか少し焦ってる?
頭をクシャリとかくのは彼が何か隠し事をしているときの癖
「もしかして部屋散らかしてるんじゃない?」
「そ。散らかってっからまた今度来てくれよ、な?」
今思えば必死に隠してたんだと思う
そんなこと知りもしない私は何かと理由をつけて彼の家に上がってしまった
最初に気づいたのは玄関にあった女性ものの靴
それがまたヒールの高い靴で"まさか"と勘ぐってしまった
テーブルには飲み口部分に口紅であろうものがついているコップが
ふすまを開けようと手を伸ばすと"おいっ"と肩をつかまれた
けれど振り払って開けてしまう
どうか、どうか私の思い違いでありますようにと祈りながら
でも私の目に入ってきたのは布団にくるまっどうしてか彼のベッドの上でツンとしていた女性
その女性はなんて言ったらいいのか…
はっきり言えば、そう、服を全部着ていなかった
怒りなのか悲しみなのか私の握りしめた拳が震えていた
心臓は強く脈打っているのに自分が今どこでどうやって立っているのかわからなくなるほど頭が混乱して、手足が熱を失っていくがわかる
3人の中で一番初めに声を発したのは私
きっと今まで出したことないくらい冷たい声だったと思う
「拓真、別れよっか」
「え~!たっくんへの気持ちってその程度だっだったんだぁ~なら遠慮なくうちがもらうねっ!幸せになろ?ね?」
語尾にハートが付きそうな口調の女性は
さっきまでそっぽを向いていたのに態度を一変させた
拓真は終始目線を泳がせて"えっと…"と続く言葉を濁すだけ
「拓真、お願いだから何か言って」
「たっくんのこと呼び捨てにしないでよ~。もう赤の他人なんだしっ!」
私は拓真から聞きたいのに横やりを入れてくる彼女
自分に非はないと思っているのか強く出すぎではないだろうか
「ねぇ、聞いてるの~?早く出て行ってよっ!!」
終いには自分の手元にあった枕を投げてよこしたのだ
顔にこそ当たらなかったものの立っているのがやっとだった私にはこたえてふらついてしまう
「悪い」
やっと口を開いたと思ったらたった3文字で、悪いとも思ってないのが手に取るようにわかる
ベッドにいる女性の方しか気にしていないのは丸わかり
私が好きだったはずの拓真はどこに行ったんだろう
まやかしだったのかな
私がもっとちゃんと彼の事を知ろうとしていれば今とは違ったのかな
「そう。じゃぁ仕方ないね」
彼にではなく私自身に言い聞かせるためにこぼしたこの言葉
真意をきっと彼はくみ取ることができないだろう
ぱたりと扉を閉じた向こうで起きていることなどもう私には一切関係ないことがとても寂しかった
🫧
あんなことがあったせいか寂しい夜は嫌い
不安になって辛くなる
もう二度と人生が交わることがない
会うこともない彼を思い出すから
振ったのは私なのに
そのはずなのに振られたって思ってしまってどうしても次の恋愛に臆病になってしまう
何年も引きずってしまうなんて思わなかった
知られたくないし踏み込まれたくもない
だけど理解してもらいたいし必要だって言われたい
そんな矛盾がいつもいつも苦しくて
こんなことを考えている自分に一番嫌気がさす
どうせ遠い人になってしまうのなら
最初から付き合わない方がいいんだって言聞かせて
好きなんて言わなくていいから
独りにならないように温もりを求めて
満たされたくて、夜に溺れた─────
────はずだった
このまま行けるところまで堕ちてしまえばいいとすら思っていたのに...
なのに私は服のままベッドに横になっていて、形跡はどこにもない
どこかのホテルだろうなということはわかる
人肌が恋しくてどうとでもなれと半ば勢いで声をかけてきた誰かについていったところまでは覚えているから
ガチャと音がした方に首をひねると女性関係には困ることなんてなさそうな男性がバスローブを着て立っていた
この人が私に声をかけてきた・・・の?ありえない
「やっと起きたか。とりあえず飲め」
差し出されたのはお水
おずおず受け取って飲みほした
どうやら体は水分を欲していたみたい
「で、お前は生に執着がないってことでいいんだろうな」
さっきこぼしていただろうとつづけた彼
えぇ、もしかして口に出していたんだろうか
だとしたらどこからどこまで口にしていて、聞かれたのはどのあたりだろう
「消えたいって思ったのは本当です。でもそれは願いが叶わなければの話で…」
「ならお前の願いは何だ?」
「朝起きたら誰かにおはようって言えることです」
ちっぽけな願いだなと鼻で笑われるか一蹴されるかだと思っていたのに
予想の斜め上を上回る言葉が返ってきた
「お前の願い叶えてやる。だから俺のものになれ。」
こんなところに来るやつはたいてい朝にはもういねえからな
その点俺に拾われたお前は相当な運の持ち主だよ
と続けた彼に目が点になる
数時間前に初めて会っただけの人同士が恋人って過程を吹っ飛ばして夫婦だなんて聞いたこともない
理解が追いつかないことが表情に出ていたんだろう
「理解なんて後からでも遅くない。なんてったってまだ夜は長い」
覚悟はいいかと聞かれるや否やベッドへ沈みこんだ私の身体
まだ何も言っていないのにと思う反面、やっと願いが叶うのなら目の前の男性についていくのも悪くないのではないかと思った
彼がどうして幸の薄そうな顔だちの私を選ぶのか皆目見当はつかないけれど
今はそんなこと考えていられない
身体を這う舌に指に思考がかき乱されて正常な判断なんて、もう
なのに、気づかないフリして本当ばかみたいだった
今でも引きずっている過去の苦い記憶
朝起きておはようって
そんな些細な幸せさえ叶わない
いつになったら私の幸せは得られるんだろう
こんな願いすら叶わないなら、もしかしたら私は幸せになってはいけない人なのかもしれない
こんな弱音を吐いたって無意味でしかないのは百も承知
だから泣くのは一人の時だけ
どれだけ悔しくても、不安で苦しくても
人前で涙を見せてはいけない
泣いたらダメなの
それは"自分は弱いです"って私自身が認めているようなものだから
見た目だけでも強くいないと
強がりってバレないように
でも夜になるたびに元彼を思い出して、叶わないのならば消えてしまいたい
…なんてこぼしてしまう
そんなことばも闇夜に紛れて溶けた
──────今宵もまた夜が始まりを告げる
🫧
─『来週、拓真の家行くね』
そう送ったメッセージに返信はまだない
今まではすぐに返事があった
遅くても数時間後かその日中
それがだんだん遅くなっていって今では1週間も未読スルー
返事おそいだけですぐ嫌われたかなって不安になるから
だから嫌いじゃないよって言って欲しい
ただ私が安心したいだけっていわれたらそれまでだけど
─ピンポン
合鍵はまだ渡せてもらえてない
いつか信用される女性になったら渡してくれるかな
「あぁ、美波。来てたんだ」
「メッセージ見てない?」
「あー、、、」
出てきた彼はなんだか少し焦ってる?
頭をクシャリとかくのは彼が何か隠し事をしているときの癖
「もしかして部屋散らかしてるんじゃない?」
「そ。散らかってっからまた今度来てくれよ、な?」
今思えば必死に隠してたんだと思う
そんなこと知りもしない私は何かと理由をつけて彼の家に上がってしまった
最初に気づいたのは玄関にあった女性ものの靴
それがまたヒールの高い靴で"まさか"と勘ぐってしまった
テーブルには飲み口部分に口紅であろうものがついているコップが
ふすまを開けようと手を伸ばすと"おいっ"と肩をつかまれた
けれど振り払って開けてしまう
どうか、どうか私の思い違いでありますようにと祈りながら
でも私の目に入ってきたのは布団にくるまっどうしてか彼のベッドの上でツンとしていた女性
その女性はなんて言ったらいいのか…
はっきり言えば、そう、服を全部着ていなかった
怒りなのか悲しみなのか私の握りしめた拳が震えていた
心臓は強く脈打っているのに自分が今どこでどうやって立っているのかわからなくなるほど頭が混乱して、手足が熱を失っていくがわかる
3人の中で一番初めに声を発したのは私
きっと今まで出したことないくらい冷たい声だったと思う
「拓真、別れよっか」
「え~!たっくんへの気持ちってその程度だっだったんだぁ~なら遠慮なくうちがもらうねっ!幸せになろ?ね?」
語尾にハートが付きそうな口調の女性は
さっきまでそっぽを向いていたのに態度を一変させた
拓真は終始目線を泳がせて"えっと…"と続く言葉を濁すだけ
「拓真、お願いだから何か言って」
「たっくんのこと呼び捨てにしないでよ~。もう赤の他人なんだしっ!」
私は拓真から聞きたいのに横やりを入れてくる彼女
自分に非はないと思っているのか強く出すぎではないだろうか
「ねぇ、聞いてるの~?早く出て行ってよっ!!」
終いには自分の手元にあった枕を投げてよこしたのだ
顔にこそ当たらなかったものの立っているのがやっとだった私にはこたえてふらついてしまう
「悪い」
やっと口を開いたと思ったらたった3文字で、悪いとも思ってないのが手に取るようにわかる
ベッドにいる女性の方しか気にしていないのは丸わかり
私が好きだったはずの拓真はどこに行ったんだろう
まやかしだったのかな
私がもっとちゃんと彼の事を知ろうとしていれば今とは違ったのかな
「そう。じゃぁ仕方ないね」
彼にではなく私自身に言い聞かせるためにこぼしたこの言葉
真意をきっと彼はくみ取ることができないだろう
ぱたりと扉を閉じた向こうで起きていることなどもう私には一切関係ないことがとても寂しかった
🫧
あんなことがあったせいか寂しい夜は嫌い
不安になって辛くなる
もう二度と人生が交わることがない
会うこともない彼を思い出すから
振ったのは私なのに
そのはずなのに振られたって思ってしまってどうしても次の恋愛に臆病になってしまう
何年も引きずってしまうなんて思わなかった
知られたくないし踏み込まれたくもない
だけど理解してもらいたいし必要だって言われたい
そんな矛盾がいつもいつも苦しくて
こんなことを考えている自分に一番嫌気がさす
どうせ遠い人になってしまうのなら
最初から付き合わない方がいいんだって言聞かせて
好きなんて言わなくていいから
独りにならないように温もりを求めて
満たされたくて、夜に溺れた─────
────はずだった
このまま行けるところまで堕ちてしまえばいいとすら思っていたのに...
なのに私は服のままベッドに横になっていて、形跡はどこにもない
どこかのホテルだろうなということはわかる
人肌が恋しくてどうとでもなれと半ば勢いで声をかけてきた誰かについていったところまでは覚えているから
ガチャと音がした方に首をひねると女性関係には困ることなんてなさそうな男性がバスローブを着て立っていた
この人が私に声をかけてきた・・・の?ありえない
「やっと起きたか。とりあえず飲め」
差し出されたのはお水
おずおず受け取って飲みほした
どうやら体は水分を欲していたみたい
「で、お前は生に執着がないってことでいいんだろうな」
さっきこぼしていただろうとつづけた彼
えぇ、もしかして口に出していたんだろうか
だとしたらどこからどこまで口にしていて、聞かれたのはどのあたりだろう
「消えたいって思ったのは本当です。でもそれは願いが叶わなければの話で…」
「ならお前の願いは何だ?」
「朝起きたら誰かにおはようって言えることです」
ちっぽけな願いだなと鼻で笑われるか一蹴されるかだと思っていたのに
予想の斜め上を上回る言葉が返ってきた
「お前の願い叶えてやる。だから俺のものになれ。」
こんなところに来るやつはたいてい朝にはもういねえからな
その点俺に拾われたお前は相当な運の持ち主だよ
と続けた彼に目が点になる
数時間前に初めて会っただけの人同士が恋人って過程を吹っ飛ばして夫婦だなんて聞いたこともない
理解が追いつかないことが表情に出ていたんだろう
「理解なんて後からでも遅くない。なんてったってまだ夜は長い」
覚悟はいいかと聞かれるや否やベッドへ沈みこんだ私の身体
まだ何も言っていないのにと思う反面、やっと願いが叶うのなら目の前の男性についていくのも悪くないのではないかと思った
彼がどうして幸の薄そうな顔だちの私を選ぶのか皆目見当はつかないけれど
今はそんなこと考えていられない
身体を這う舌に指に思考がかき乱されて正常な判断なんて、もう