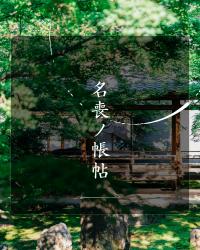「もう忘れなきゃ」
何度も繰り返したことば
自分に言い聞かせるようにつぶやいている
それでも彼の声も顔も仕草も全部ぜんぶ忘れることなんてできない
わすれるどころか鮮明に今でも思い出すことができる
先日、恋人の櫂から2回目の告白をされた
「『好きです。これからは結婚を前提にお付き合いを続けてくれませんか』だもんね」
といっても結婚式はまだ先でお互い大学を卒業して仕事にも慣れた後
まずは半同棲から始めようとのことだった
プロポーズはいつかしてくれるらしいんだけど、、、、
彼には秘密にしていたけれど、私には忘れることができない人がいる
私の幸せはあの人と一緒じゃなきゃ、なんて
今は背伸びしてもどれだけ手を伸ばしたところで届かない今でも大切な人
晶
彼への思いもあり、返事を先延ばしにしている
でも早く伝えないと櫂に悪い
そう悩みながら眠りについた
ღ
「朝だよ、おはよう」
誰かの声が聞こえて目を覚ます
そこにはあのころと変わらない晶がいてこれは夢だと気づいた
もうこの世にはいない変わらず大切な人
これは私の夢描いていた幻の世界
人は声から忘れ、香りを最後まで覚えている
なんて、どこかでそんなこと聞いたことがある
永遠だと信じていたかった元恋人
そんなあなたを私は忘れることなんて到底できない
できるはずもない
「おは......っぅ」
ちゃんと"おはよう"って言いたいのに言葉がつかえて涙が溢れてしまう
「莉那?」
心配そうに私を呼ぶその声
どうすればいいのか迷った末におずおずと私に腕を回して包んでくれる
何もかもが愛おしくて涙は余計に止まらなかった
夢の中なはずなのにしっかり触れることができる
彼がそこにいる
ただそれだけで涙があふれる
どうやら今日は休日で私も彼もオフの日らしい
彼が作ってくれていた朝ご飯は私が泣いてしまっていたせいで少し冷めていた
「せっかく温かいご飯だったのにごめんね」
「莉那が泣いていた理由はやっぱり話せない?」
「うん...」
だって言えるはずもない
貴方はもう亡くなっていて、これは私が作り上げた空想の世界なんだよなんて
「なら、ご飯温めなおして食べよう」
食べればきっと元気になれるよ
そう言って置いてくれた卵焼きに白米、そして味噌汁
凝った料理なんかじゃないけどホッとするこの味
もう味わえる機会なんてないと思っていた
「……しぃ、、、おいひいよぉ」
さっきもう枯れてしまったと思っていた涙が勝手に頬を伝って落ちる
「莉那?!今日は泣き虫だね」
そう言いながらティッシュを渡してくれた
味わいながら噛みしめようと思ったのに涙で味覚がわからなくなる
ふと朝日が降り注ぐ窓から外を見るとカラリと晴れたいい天気
私を気にしていた彼がポツリとこぼした
「外、行くか」
行きたい
彼と久しぶりのデート
だけど外に出た瞬間この夢が覚めちゃうんじゃないかって
そう思ったらこのまま外出せずに家の中で
なんて考えてしまったけれど頭を振ってその考えを振り払う
「いいね。私準備してくるね」
食べ終わった2人の食器を洗い、外行の服に着替えて化粧を施していく
起きたときと食時中に泣いて腫れた目をなんとかするのに時間がかかってしまった
お出かけするなら少しでも可愛いって思ってもらいたいから念入りにチェックしたあと、彼のもとまで急ぐ
「ごめんね、時間かかっちゃって」
「今日はどうする?」
「車以外がいい」
クルマの鍵を持っている彼の手から鍵を取って私の手を絡める
車を運転していた時に事故にあった彼
交通ルールを守っていたのにも関わらず、違反をしていた加害者の運転していた車にぶつかられての事故だった
「歩いて駅まで行こうか」
そんな私の思いを知ってか知らずか目の前の彼は私の手を握り返すと歩幅を合わせて歩いてくれた
電車に揺られているときはつり革を持っている彼の服を掴んでバランスを保つ
学生の頃は移動手段は徒歩もしくは自転車か電車かだったから懐かしい記憶に思いを馳せた
たどり着いた先は近くの大型ショッピングモール
晶との思い出がいっぱいつまった場所だから櫂とのデートでは1度もきたことがない場所
いつもここ以外がいいと我が儘を言ったっけ
きっと面倒な彼女だったはずなのにいつもたくさんのプランを考えてくれていた
なにも聞かないでここはどうかあそこはどうかと提案してくれた
「莉那?どうかした?」
「ううん、なんでもないよ。回ろっか」
足が止まってしまった私を不思議がる彼になんでもないと首を振って行こうと促す
何にも買わなくても彼と2人ならんで歩くこの時間は私にとってかげがえのないもの
付き合うと手をつないで隣にいることが多かったけれど私は彼の半歩後ろを歩くことが好きだった
あっという間に過ぎていく時間が恨めしくてこのまま時が止まればいいのにとさえ思うほど
あと何秒?何分?何時間?
一緒にいられるタイムリミットはきっと刻一刻と近づいてきているはずだから
現実の私がこのまま覚めなければいいのに
帰り道、彼に聞いてみたお夕飯のリクエスト
「オムレツ!」
間髪入れずに即答したのは彼の好きな物
私は彼の作る卵焼きが大好きで、彼は私の作るオムレツが好き
彼が好きだからオムレツづくりの練習をしたことなんて絶対教えない
ふわトロになるまで卵をたくさん使って練習していた
そのせいで食卓に卵料理が多かったことなんてしょっちゅう
お墓参りのときにも必ず作ってお供えしているから腕は鈍っていないはず
今までで一番のオムレツを食べてもらいたい一心で料理に取り掛かった
コトン
彼の前に置いたのは彼の好物詰め合わせの一品
肉じゃがとチーズを卵で包んだふわトロな具だくさんオムレツ
「莉那ありがとう。俺これすげぇ好き」
すぐに完食してくれて、美味しい美味しいっていっぱい伝えてくれる
私が食べ終わるまでずっと食卓にいてくれたし、朝は莉那がしてくれたから夜はするよと食器を洗ってくれた
その間にお風呂の準備を終わらせる
今日は私がしてみたくて、でもできなかったことをして驚かせたいと思う
「晶~洗い終わったら先お風呂入ってね」
「今日は莉那先に入らなくていいの?」
「いいのいいの!」
ほら、入った入ったと脱衣所に彼を押しやる
どうしたと慌てる彼に秘密だよと含み笑い返す
怪しみながらも風呂場に入った音を聞いて私も準備をする
1度深呼吸をして頬をパシンと叩いた
「よし」と呟いてお風呂場の扉開けた
「晶~!今日は私が背中流すよって──わ?!」
私が入ったことに驚いた彼がシャワーを落とし、シャワーヘッドが上向きになったせいで放物線を描いて私に降り注いだ
グッショリ濡れてしまった服が肌に張り付いてくる
雨のなか走って屋根のあるところで雨宿りしたあの頃を思い出した
「莉那?!ごめん!えっとほら先入って」
目ぇ瞑ってるからと言われてちょっとふて腐れ気味な私
だってさ、、、恥ずかしさ我慢して入ったのに彼の背中すら洗えなかったんだもん
「脱がなきゃかぁ」
ため息と共に呟くとクルリと後ろを向いた晶
その瞳は私を捕らえて離さない
「莉那、早くしないと俺が脱がしちゃうけど?」
いいの?とでも言う風にズイッと近づいてキャミの紐に指をかける
彼だってさっきまでシャワーを浴びてたんだから濡れているのは当たり前で、余計に色っぽい
ポタリと雫が滴り落ちた
「...ん」
今までで一番勇気を出したかもしれない
彼に聞こえたかは分からないけれどこれが私の精一杯の答え
「へぇ」
ニヤリと妖艶に笑った彼は意図も容易く私の服を脱がしていき、一糸纏わぬ姿になってしまう
やっぱり答えるんじゃなかったかもしれない羞恥心で沸騰しそう
「早く、入ろ...」
そういうと余裕そうな笑みを浮かべて、まずは洗わないとななんて手に泡をつけて私の肌を撫でる
指先、手のひらはゆっくり動いていて、これは焦らしているにちがいない
お風呂場は声が響くし、近所の人が聞いているかもしれないし、晶はカッコいいしてでもう頭はぐちゃぐちゃ
やっとつかれた湯槽では、彼が動く度にちゃぽんと揺れる水面に耐えきれなくて早々にあがってしまった
リタイアしたお風呂のリベンジをしようと寝室で晶を待つ
あの日、本当は私の言うことなんでも聞いてくれるって日だった
いっぱい普段はしないおねだりもしてみようかと思っていた
甘えてみたかった1つくらい叶えてみたかった
戻ってきた彼はコップを2つ水を注いで持ってきてくれていた
けれどお水なんてあと
おもいっきり勢いをつけて彼に抱きつく
こぼれた水はあとで拭くから
だから今だけは私を見てよ
そんな思いで彼にキスをした
目を見張り驚いたような顔をした彼はすぐに悲しそうに眉を下げた
そして諦めたように笑った彼は私をやんわり断った
「莉那、もう寝な」
水を置いて晶はベッドに転び、隣をポスポス叩く
なんで、なんで、抑えきれない想いはせきを切って涙と一緒にぶつけてしまう
「好きだよ、あきらぁ。好きなの。お願いだからいなくならないで。私のとなりにずっといてよ」
このまま晶が消えちゃいそうで
引き留めておきたくて
ありったけの好きを伝える
今日は朝から夜まで本当に泣きっぱなしの私
泣き虫だと思われていいから
私には晶が必要なの
「大切にしなよ結婚するんでしょ?俺のことは忘れればいいんだよ。莉那を幸せにできない男なんてさ。」
きっと初めから晶は晶だったんだ
私が夢の中で作り出した彼ではなく、本当の
私がきっと悩んでいたから伝えにきてくれたんだと気づいた
「わかった。でもキスはしたいよ」
きゅっと唇を噛んで涙がこれ以上こぼれないように我慢して、お願いしてみる
私が寝るまでいっぱいと付け足すと仕方ないねとクスリと笑う彼と重ねた
唇から、繋いだ手から、回した腕から、背中から彼の体温を感じながら眠りについた
まどろむ意識の中覚えているのはそう、晶が私の左薬指に触れたか触れていないか分からないくらい優しくて軽いキスをしたこと
ღ
目が覚めると泣いていて無性に電話したくなった
櫂は朝早いのにもかかわらずでてくれた
「待っていてくれてありがとう、話したいことがあるの。それを聞いた上で櫂が私をゆるしてくれるのなら、こんな私をもらってください」
鼻声の私を心配しながらも喜んでいる彼
『 』
朝の風にのって声が聞こえた気がした
今の私がいるのはあなたのおかげだから
だから、忘れないよ
この想いを嚙みしめたまま、私は幸せになるよ
それでも良いでしょう?
窓辺に活けてあるミモザは風にその白と黄の花を揺らした
何度も繰り返したことば
自分に言い聞かせるようにつぶやいている
それでも彼の声も顔も仕草も全部ぜんぶ忘れることなんてできない
わすれるどころか鮮明に今でも思い出すことができる
先日、恋人の櫂から2回目の告白をされた
「『好きです。これからは結婚を前提にお付き合いを続けてくれませんか』だもんね」
といっても結婚式はまだ先でお互い大学を卒業して仕事にも慣れた後
まずは半同棲から始めようとのことだった
プロポーズはいつかしてくれるらしいんだけど、、、、
彼には秘密にしていたけれど、私には忘れることができない人がいる
私の幸せはあの人と一緒じゃなきゃ、なんて
今は背伸びしてもどれだけ手を伸ばしたところで届かない今でも大切な人
晶
彼への思いもあり、返事を先延ばしにしている
でも早く伝えないと櫂に悪い
そう悩みながら眠りについた
ღ
「朝だよ、おはよう」
誰かの声が聞こえて目を覚ます
そこにはあのころと変わらない晶がいてこれは夢だと気づいた
もうこの世にはいない変わらず大切な人
これは私の夢描いていた幻の世界
人は声から忘れ、香りを最後まで覚えている
なんて、どこかでそんなこと聞いたことがある
永遠だと信じていたかった元恋人
そんなあなたを私は忘れることなんて到底できない
できるはずもない
「おは......っぅ」
ちゃんと"おはよう"って言いたいのに言葉がつかえて涙が溢れてしまう
「莉那?」
心配そうに私を呼ぶその声
どうすればいいのか迷った末におずおずと私に腕を回して包んでくれる
何もかもが愛おしくて涙は余計に止まらなかった
夢の中なはずなのにしっかり触れることができる
彼がそこにいる
ただそれだけで涙があふれる
どうやら今日は休日で私も彼もオフの日らしい
彼が作ってくれていた朝ご飯は私が泣いてしまっていたせいで少し冷めていた
「せっかく温かいご飯だったのにごめんね」
「莉那が泣いていた理由はやっぱり話せない?」
「うん...」
だって言えるはずもない
貴方はもう亡くなっていて、これは私が作り上げた空想の世界なんだよなんて
「なら、ご飯温めなおして食べよう」
食べればきっと元気になれるよ
そう言って置いてくれた卵焼きに白米、そして味噌汁
凝った料理なんかじゃないけどホッとするこの味
もう味わえる機会なんてないと思っていた
「……しぃ、、、おいひいよぉ」
さっきもう枯れてしまったと思っていた涙が勝手に頬を伝って落ちる
「莉那?!今日は泣き虫だね」
そう言いながらティッシュを渡してくれた
味わいながら噛みしめようと思ったのに涙で味覚がわからなくなる
ふと朝日が降り注ぐ窓から外を見るとカラリと晴れたいい天気
私を気にしていた彼がポツリとこぼした
「外、行くか」
行きたい
彼と久しぶりのデート
だけど外に出た瞬間この夢が覚めちゃうんじゃないかって
そう思ったらこのまま外出せずに家の中で
なんて考えてしまったけれど頭を振ってその考えを振り払う
「いいね。私準備してくるね」
食べ終わった2人の食器を洗い、外行の服に着替えて化粧を施していく
起きたときと食時中に泣いて腫れた目をなんとかするのに時間がかかってしまった
お出かけするなら少しでも可愛いって思ってもらいたいから念入りにチェックしたあと、彼のもとまで急ぐ
「ごめんね、時間かかっちゃって」
「今日はどうする?」
「車以外がいい」
クルマの鍵を持っている彼の手から鍵を取って私の手を絡める
車を運転していた時に事故にあった彼
交通ルールを守っていたのにも関わらず、違反をしていた加害者の運転していた車にぶつかられての事故だった
「歩いて駅まで行こうか」
そんな私の思いを知ってか知らずか目の前の彼は私の手を握り返すと歩幅を合わせて歩いてくれた
電車に揺られているときはつり革を持っている彼の服を掴んでバランスを保つ
学生の頃は移動手段は徒歩もしくは自転車か電車かだったから懐かしい記憶に思いを馳せた
たどり着いた先は近くの大型ショッピングモール
晶との思い出がいっぱいつまった場所だから櫂とのデートでは1度もきたことがない場所
いつもここ以外がいいと我が儘を言ったっけ
きっと面倒な彼女だったはずなのにいつもたくさんのプランを考えてくれていた
なにも聞かないでここはどうかあそこはどうかと提案してくれた
「莉那?どうかした?」
「ううん、なんでもないよ。回ろっか」
足が止まってしまった私を不思議がる彼になんでもないと首を振って行こうと促す
何にも買わなくても彼と2人ならんで歩くこの時間は私にとってかげがえのないもの
付き合うと手をつないで隣にいることが多かったけれど私は彼の半歩後ろを歩くことが好きだった
あっという間に過ぎていく時間が恨めしくてこのまま時が止まればいいのにとさえ思うほど
あと何秒?何分?何時間?
一緒にいられるタイムリミットはきっと刻一刻と近づいてきているはずだから
現実の私がこのまま覚めなければいいのに
帰り道、彼に聞いてみたお夕飯のリクエスト
「オムレツ!」
間髪入れずに即答したのは彼の好きな物
私は彼の作る卵焼きが大好きで、彼は私の作るオムレツが好き
彼が好きだからオムレツづくりの練習をしたことなんて絶対教えない
ふわトロになるまで卵をたくさん使って練習していた
そのせいで食卓に卵料理が多かったことなんてしょっちゅう
お墓参りのときにも必ず作ってお供えしているから腕は鈍っていないはず
今までで一番のオムレツを食べてもらいたい一心で料理に取り掛かった
コトン
彼の前に置いたのは彼の好物詰め合わせの一品
肉じゃがとチーズを卵で包んだふわトロな具だくさんオムレツ
「莉那ありがとう。俺これすげぇ好き」
すぐに完食してくれて、美味しい美味しいっていっぱい伝えてくれる
私が食べ終わるまでずっと食卓にいてくれたし、朝は莉那がしてくれたから夜はするよと食器を洗ってくれた
その間にお風呂の準備を終わらせる
今日は私がしてみたくて、でもできなかったことをして驚かせたいと思う
「晶~洗い終わったら先お風呂入ってね」
「今日は莉那先に入らなくていいの?」
「いいのいいの!」
ほら、入った入ったと脱衣所に彼を押しやる
どうしたと慌てる彼に秘密だよと含み笑い返す
怪しみながらも風呂場に入った音を聞いて私も準備をする
1度深呼吸をして頬をパシンと叩いた
「よし」と呟いてお風呂場の扉開けた
「晶~!今日は私が背中流すよって──わ?!」
私が入ったことに驚いた彼がシャワーを落とし、シャワーヘッドが上向きになったせいで放物線を描いて私に降り注いだ
グッショリ濡れてしまった服が肌に張り付いてくる
雨のなか走って屋根のあるところで雨宿りしたあの頃を思い出した
「莉那?!ごめん!えっとほら先入って」
目ぇ瞑ってるからと言われてちょっとふて腐れ気味な私
だってさ、、、恥ずかしさ我慢して入ったのに彼の背中すら洗えなかったんだもん
「脱がなきゃかぁ」
ため息と共に呟くとクルリと後ろを向いた晶
その瞳は私を捕らえて離さない
「莉那、早くしないと俺が脱がしちゃうけど?」
いいの?とでも言う風にズイッと近づいてキャミの紐に指をかける
彼だってさっきまでシャワーを浴びてたんだから濡れているのは当たり前で、余計に色っぽい
ポタリと雫が滴り落ちた
「...ん」
今までで一番勇気を出したかもしれない
彼に聞こえたかは分からないけれどこれが私の精一杯の答え
「へぇ」
ニヤリと妖艶に笑った彼は意図も容易く私の服を脱がしていき、一糸纏わぬ姿になってしまう
やっぱり答えるんじゃなかったかもしれない羞恥心で沸騰しそう
「早く、入ろ...」
そういうと余裕そうな笑みを浮かべて、まずは洗わないとななんて手に泡をつけて私の肌を撫でる
指先、手のひらはゆっくり動いていて、これは焦らしているにちがいない
お風呂場は声が響くし、近所の人が聞いているかもしれないし、晶はカッコいいしてでもう頭はぐちゃぐちゃ
やっとつかれた湯槽では、彼が動く度にちゃぽんと揺れる水面に耐えきれなくて早々にあがってしまった
リタイアしたお風呂のリベンジをしようと寝室で晶を待つ
あの日、本当は私の言うことなんでも聞いてくれるって日だった
いっぱい普段はしないおねだりもしてみようかと思っていた
甘えてみたかった1つくらい叶えてみたかった
戻ってきた彼はコップを2つ水を注いで持ってきてくれていた
けれどお水なんてあと
おもいっきり勢いをつけて彼に抱きつく
こぼれた水はあとで拭くから
だから今だけは私を見てよ
そんな思いで彼にキスをした
目を見張り驚いたような顔をした彼はすぐに悲しそうに眉を下げた
そして諦めたように笑った彼は私をやんわり断った
「莉那、もう寝な」
水を置いて晶はベッドに転び、隣をポスポス叩く
なんで、なんで、抑えきれない想いはせきを切って涙と一緒にぶつけてしまう
「好きだよ、あきらぁ。好きなの。お願いだからいなくならないで。私のとなりにずっといてよ」
このまま晶が消えちゃいそうで
引き留めておきたくて
ありったけの好きを伝える
今日は朝から夜まで本当に泣きっぱなしの私
泣き虫だと思われていいから
私には晶が必要なの
「大切にしなよ結婚するんでしょ?俺のことは忘れればいいんだよ。莉那を幸せにできない男なんてさ。」
きっと初めから晶は晶だったんだ
私が夢の中で作り出した彼ではなく、本当の
私がきっと悩んでいたから伝えにきてくれたんだと気づいた
「わかった。でもキスはしたいよ」
きゅっと唇を噛んで涙がこれ以上こぼれないように我慢して、お願いしてみる
私が寝るまでいっぱいと付け足すと仕方ないねとクスリと笑う彼と重ねた
唇から、繋いだ手から、回した腕から、背中から彼の体温を感じながら眠りについた
まどろむ意識の中覚えているのはそう、晶が私の左薬指に触れたか触れていないか分からないくらい優しくて軽いキスをしたこと
ღ
目が覚めると泣いていて無性に電話したくなった
櫂は朝早いのにもかかわらずでてくれた
「待っていてくれてありがとう、話したいことがあるの。それを聞いた上で櫂が私をゆるしてくれるのなら、こんな私をもらってください」
鼻声の私を心配しながらも喜んでいる彼
『 』
朝の風にのって声が聞こえた気がした
今の私がいるのはあなたのおかげだから
だから、忘れないよ
この想いを嚙みしめたまま、私は幸せになるよ
それでも良いでしょう?
窓辺に活けてあるミモザは風にその白と黄の花を揺らした