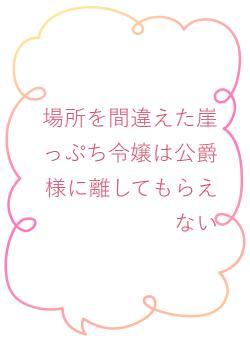その日は雨だった。
寒い冬の日ではあったけれど、いつもとさほど変わらない、ありふれた日常。当たり前みたいにやってきた今日と、その中を生きる自分と、同じような明日を予感させる街の景色。
少し濡れてしまったスカートの裾を気にしながら、急ぐ帰り道。
……約束は破られた。
今日が来るのを指折り数えて待っていたのは、私だけだったようだ。
これで何度目だろう。
今日は二人にとって、大切な日だったはずなのに……。
『ごめん、急用が入った』
簡単な言葉ですべてを否定され、冷たい雨と相まって、私の心は冷え切っていた。
きっともう、終わるのだ。
彼の心は、もう私を向いてはいない。
*****
赤信号で立ち止まった私は、ふと、携帯に手を伸ばす。SNSでは、最近よくやり取りをするMIYAさんが、今日も「何気ない日常」を呟いていた。
MIYAさんを知ったのは、彼が書いたWeb小説の紹介を見て、私がそれを読みに行ったのが切っ掛けだった。
「生と死だけが、我々に残された唯一の『平等』である」
その書き出しを読んで、私はすっかり彼の文章の虜になってしまったのだ。
感想などを伝えるうち、なんとなくお互いを知り、彼がバツイチであること、小説を書くのが趣味であること、昼は都内で会社員として働いていることなどを知った。やり取りを重ねていくうちに、彼からの淡い好意にも…気付いた。
けれど、MIYAさんは私に恋人がいることも、勿論知っていた。だから、私たちは小さな箱の中の知人でしかない。
私はずるいかもしれない。
MIYAさんの好意を知りながら、彼を試すような書き込みをしたのだから。
『約束なんかしなきゃよかった。希望なんか、どこにもなくなった。……私は、独りだ』
信号が青に変わる。
雨の中、私はゆっくりと歩き出した。
メッセージはすぐに返ってきた。
『今、どこ?』
『大丈夫?』
『俺でよければ、話聞くよ?』
思った通りだ。
私は言いようのない罪悪感と共に、安堵の息を漏らす。
『大丈夫じゃ……ないです』
送信ボタンを押す指は、一瞬だけ躊躇したけれど、結局は押してしまう。
卑怯者。
『場所、教えて。迎えに行くから』
いけないことだとわかっている。
こんなこと、すべきではないと。
それでも、私は独りが嫌だった。
*****
MIYAさんと会うのは初めてだ。
だから、お互い顔も知らない。
会った途端、幻滅するかもしれないし、幻滅されるかもしれない。それならそれで、構わなかった。
「……オル……ちゃん?」
紺色の傘を差した長身の男性。少し不安そうに、私の顔を覗き込んだ。私はにっこり笑って、応える。
「初めまして、MIYAさん」
MIYAさんは自分のことを「おっさん」だと書いていたが、私が抱くおっさんのイメージはあまりなかった。年齢は四十代前半くらいだろうか? 私だってもうすぐ三十路なのだから、見る人が見れば立派におばさんだろう。
「とりあえず、中、入ろう」
MIYAさんとの待ち合わせは、繁華街から少し離れた、大人の雰囲気漂うバーだった。とはいえ、かしこまりすぎてもなく、派手すぎもせず、ゆっくりとした時間が流れているような、落ち着いた雰囲気がある。
「大丈夫? 寒かったろ」
私を気遣ってくれるMIYAさんは、SNSでやり取りしているときと変わらず穏やかで優しかった。何より、ここまで来てくれたことで、私は少し浮かれてしまっていたかもしれない。
「呼び出すみたいなことしちゃってごめんなさい。お仕事、大丈夫だったんですか?」
「ああ、今日は残業なしで終われたんだ。ちょうど帰るところだったし」
そう言ってネクタイを緩める。
「……で、どうしたの?」
少し寂しそうな顔をして、私を見つめる。
「……まぁ、ちょっと…ええ、」
言い淀む私にそれ以上のことは聞かず、MIYAさんは飲み物とおつまみをオーダーしてくれた。私が何のお酒が好きで、何の食べ物が好きかを、彼は知っている。出てくる料理は、どれも美味しかった。
MIYAさんは他愛もない話を私に投げかけた。私も他愛のない返事をした。MIYAさんの話はとても楽しくて、あっという間に時が過ぎる。アルコールの効果もあってか、その心地よさに、いつしか私も饒舌になっていった。
「終わりそうなんですよね、彼と」
ついに、口に出してしまう。
MIYAさんは一瞬ハッとした顔をし、それから口を歪ませる。
「オルちゃんを泣かせるなんて、信じられないな、そいつ」
「仕方ないですよ。『男と女なんて、所詮は交わることなんか出来ない異星人同士』なんですから」
かつて読んだ彼の小説の一文を持ち出す。
「あー、それを言うか」
ばつが悪そうに頭を搔く。
「でも本当に、異星人なんですよ、きっと」
いっそ、そうであってほしかった。私と言葉が通じないのは、違う星の住人だから。私と一緒にいられないのは、星に帰らなきゃいけないから。
不意に黙り込んだ私の手を、MIYAさんがそっと撫でた。
「……交われないのかな、俺たちも」
じっと私の目を見つめてくるMIYAさんの目はとても真剣で、とても必死に見えた。
「どうなんでしょうね」
私はまた、曖昧に返す。
MIYAさんは少し複雑な表情を浮かべ、けれど小さく首を振ると、消え入りそうな声で、
「出ようか」
と言って立ち上がった。
*****
外は相変わらず冷たい雨。
パタパタと傘を鳴らす水音と雑踏。
私はMIYAさんの少し後をついて歩く。
彼がどこに向かっているかは、考える必要もなかった。
「傷心中の女の子の隙に付け込む悪い男だってわかってるけど、このまま帰したくない。理由としてはとても邪なんだけど、同じくらい、真剣なんだ」
言い訳なのか告白なのかわからないような言い回しで、私に向き直るMIYAさんを、なんだか可愛いと思ってしまう。
「大丈夫です」
何が大丈夫なのかわからないが、私は私で、罪悪感と背徳感に満たされていたのだ。
誘われるまま、ホテルへと。
そして私は、MIYAさんに身を委ねる……。
「私、わかっちゃいました」
MIYAさんの腕の中で、呟く。
「なにが?」
「男女間の愛って、ないんですね」
何度目かの恋愛。
年齢的にも、未来を描きながら彼と時を過ごしてきたつもりだ。実際、そんな話も出ていた。いや、出ていたのではなく、私が出したのか。そしてその頃から、彼の態度が変わり始めたのだ。
「ない……のか」
MIYAさんは寂しそうに繰り返す。
「ないんです、きっと。だって、MIYAさんだってバツイチですよね?」
「まぁ、それはそうなんだけど……、」
「恋愛って、最初はすごくきれいな泉みたいなんです。でも湧き上がる透明なキラキラした水は、時を経るごとに段々濁っていく。いつの間にか足元には泥が溜まって、抜け出そうと、もがけばもがくほど沈んでいって、そのうち溺れて死ぬんだわ」
「オルちゃん……、」
感情的になる私の頭を撫でつけ、MIYAさんが困った顔をする。
「MIYAさんの小説……、」
「ん?」
「生と死だけが、我々に残された唯一の平等だ、って」
「ああ、うん」
「あれ、その通りだと思うんです。愛情って、人によって濃さというか、重さというか、思いの丈って違いますよね。なのに恋愛するとお互いのバランスなんか考えもせず、二人は両思いだと勘違いするでしょ? でも本当は違う。どちらかが重いから、片方は浮くんです。シーソーみたいに。平等なんか、どこにもない」
そうだ。
きっと彼は浮いているんだ。
私が泥に沈んで溺れかけているとき、彼は水面から見える遠くの景色を見ていたんだ。
「俺が引っ張り出してやるよ。泥の中から」
MIYAさんが切なそうに、言った。
ああ、優しい人ね。
だけど、同じことだわ。
この世界にあるのは刹那の欲と、その場限りの安らぎと、嘘っぱちの約束ばかり。
「引っ張り出して、それからどうするんですか?」
「そうだな……もう水辺には近寄らせないようにする」
「なにそれ」
くすっと笑みをこぼした私を見て、MIYAさんも笑う。
「俺は、オルちゃんを泣かせたりしない」
私の頭を胸に押し付けるように抱きしめ、MIYAさんが囁いた。
嘘つき。
言葉は水面を揺らすけれど、響きはしない……。
私が泥から這い上がっても、MIYAさんが新しい泉となる。時が経てば同じように、どちらかが沈んでゆくのだ。
そもそも、有限の中にあって、無限を求めること自体、間違っているのだろう。
最初からそんなものなかったのだから、最後まで見つかる筈がない。
わかっている。
それでも私は、探してしまう。変わらない想いを。不変の愛を。
そんなものはないと知りながら。
誰か、私をドロドロに溶かしてよ。
カケラひとつ、残らないくらいに。
遠くから雨の音が聞こえる。
あの雨も、流れて、流れて、いつか深くて濁った大きな水溜りになるのだ。
誰かを水底へと沈めようとほくそ笑む、大きくて濁った水溜りに。
――雨は、止むことなく降り続けていた。
寒い冬の日ではあったけれど、いつもとさほど変わらない、ありふれた日常。当たり前みたいにやってきた今日と、その中を生きる自分と、同じような明日を予感させる街の景色。
少し濡れてしまったスカートの裾を気にしながら、急ぐ帰り道。
……約束は破られた。
今日が来るのを指折り数えて待っていたのは、私だけだったようだ。
これで何度目だろう。
今日は二人にとって、大切な日だったはずなのに……。
『ごめん、急用が入った』
簡単な言葉ですべてを否定され、冷たい雨と相まって、私の心は冷え切っていた。
きっともう、終わるのだ。
彼の心は、もう私を向いてはいない。
*****
赤信号で立ち止まった私は、ふと、携帯に手を伸ばす。SNSでは、最近よくやり取りをするMIYAさんが、今日も「何気ない日常」を呟いていた。
MIYAさんを知ったのは、彼が書いたWeb小説の紹介を見て、私がそれを読みに行ったのが切っ掛けだった。
「生と死だけが、我々に残された唯一の『平等』である」
その書き出しを読んで、私はすっかり彼の文章の虜になってしまったのだ。
感想などを伝えるうち、なんとなくお互いを知り、彼がバツイチであること、小説を書くのが趣味であること、昼は都内で会社員として働いていることなどを知った。やり取りを重ねていくうちに、彼からの淡い好意にも…気付いた。
けれど、MIYAさんは私に恋人がいることも、勿論知っていた。だから、私たちは小さな箱の中の知人でしかない。
私はずるいかもしれない。
MIYAさんの好意を知りながら、彼を試すような書き込みをしたのだから。
『約束なんかしなきゃよかった。希望なんか、どこにもなくなった。……私は、独りだ』
信号が青に変わる。
雨の中、私はゆっくりと歩き出した。
メッセージはすぐに返ってきた。
『今、どこ?』
『大丈夫?』
『俺でよければ、話聞くよ?』
思った通りだ。
私は言いようのない罪悪感と共に、安堵の息を漏らす。
『大丈夫じゃ……ないです』
送信ボタンを押す指は、一瞬だけ躊躇したけれど、結局は押してしまう。
卑怯者。
『場所、教えて。迎えに行くから』
いけないことだとわかっている。
こんなこと、すべきではないと。
それでも、私は独りが嫌だった。
*****
MIYAさんと会うのは初めてだ。
だから、お互い顔も知らない。
会った途端、幻滅するかもしれないし、幻滅されるかもしれない。それならそれで、構わなかった。
「……オル……ちゃん?」
紺色の傘を差した長身の男性。少し不安そうに、私の顔を覗き込んだ。私はにっこり笑って、応える。
「初めまして、MIYAさん」
MIYAさんは自分のことを「おっさん」だと書いていたが、私が抱くおっさんのイメージはあまりなかった。年齢は四十代前半くらいだろうか? 私だってもうすぐ三十路なのだから、見る人が見れば立派におばさんだろう。
「とりあえず、中、入ろう」
MIYAさんとの待ち合わせは、繁華街から少し離れた、大人の雰囲気漂うバーだった。とはいえ、かしこまりすぎてもなく、派手すぎもせず、ゆっくりとした時間が流れているような、落ち着いた雰囲気がある。
「大丈夫? 寒かったろ」
私を気遣ってくれるMIYAさんは、SNSでやり取りしているときと変わらず穏やかで優しかった。何より、ここまで来てくれたことで、私は少し浮かれてしまっていたかもしれない。
「呼び出すみたいなことしちゃってごめんなさい。お仕事、大丈夫だったんですか?」
「ああ、今日は残業なしで終われたんだ。ちょうど帰るところだったし」
そう言ってネクタイを緩める。
「……で、どうしたの?」
少し寂しそうな顔をして、私を見つめる。
「……まぁ、ちょっと…ええ、」
言い淀む私にそれ以上のことは聞かず、MIYAさんは飲み物とおつまみをオーダーしてくれた。私が何のお酒が好きで、何の食べ物が好きかを、彼は知っている。出てくる料理は、どれも美味しかった。
MIYAさんは他愛もない話を私に投げかけた。私も他愛のない返事をした。MIYAさんの話はとても楽しくて、あっという間に時が過ぎる。アルコールの効果もあってか、その心地よさに、いつしか私も饒舌になっていった。
「終わりそうなんですよね、彼と」
ついに、口に出してしまう。
MIYAさんは一瞬ハッとした顔をし、それから口を歪ませる。
「オルちゃんを泣かせるなんて、信じられないな、そいつ」
「仕方ないですよ。『男と女なんて、所詮は交わることなんか出来ない異星人同士』なんですから」
かつて読んだ彼の小説の一文を持ち出す。
「あー、それを言うか」
ばつが悪そうに頭を搔く。
「でも本当に、異星人なんですよ、きっと」
いっそ、そうであってほしかった。私と言葉が通じないのは、違う星の住人だから。私と一緒にいられないのは、星に帰らなきゃいけないから。
不意に黙り込んだ私の手を、MIYAさんがそっと撫でた。
「……交われないのかな、俺たちも」
じっと私の目を見つめてくるMIYAさんの目はとても真剣で、とても必死に見えた。
「どうなんでしょうね」
私はまた、曖昧に返す。
MIYAさんは少し複雑な表情を浮かべ、けれど小さく首を振ると、消え入りそうな声で、
「出ようか」
と言って立ち上がった。
*****
外は相変わらず冷たい雨。
パタパタと傘を鳴らす水音と雑踏。
私はMIYAさんの少し後をついて歩く。
彼がどこに向かっているかは、考える必要もなかった。
「傷心中の女の子の隙に付け込む悪い男だってわかってるけど、このまま帰したくない。理由としてはとても邪なんだけど、同じくらい、真剣なんだ」
言い訳なのか告白なのかわからないような言い回しで、私に向き直るMIYAさんを、なんだか可愛いと思ってしまう。
「大丈夫です」
何が大丈夫なのかわからないが、私は私で、罪悪感と背徳感に満たされていたのだ。
誘われるまま、ホテルへと。
そして私は、MIYAさんに身を委ねる……。
「私、わかっちゃいました」
MIYAさんの腕の中で、呟く。
「なにが?」
「男女間の愛って、ないんですね」
何度目かの恋愛。
年齢的にも、未来を描きながら彼と時を過ごしてきたつもりだ。実際、そんな話も出ていた。いや、出ていたのではなく、私が出したのか。そしてその頃から、彼の態度が変わり始めたのだ。
「ない……のか」
MIYAさんは寂しそうに繰り返す。
「ないんです、きっと。だって、MIYAさんだってバツイチですよね?」
「まぁ、それはそうなんだけど……、」
「恋愛って、最初はすごくきれいな泉みたいなんです。でも湧き上がる透明なキラキラした水は、時を経るごとに段々濁っていく。いつの間にか足元には泥が溜まって、抜け出そうと、もがけばもがくほど沈んでいって、そのうち溺れて死ぬんだわ」
「オルちゃん……、」
感情的になる私の頭を撫でつけ、MIYAさんが困った顔をする。
「MIYAさんの小説……、」
「ん?」
「生と死だけが、我々に残された唯一の平等だ、って」
「ああ、うん」
「あれ、その通りだと思うんです。愛情って、人によって濃さというか、重さというか、思いの丈って違いますよね。なのに恋愛するとお互いのバランスなんか考えもせず、二人は両思いだと勘違いするでしょ? でも本当は違う。どちらかが重いから、片方は浮くんです。シーソーみたいに。平等なんか、どこにもない」
そうだ。
きっと彼は浮いているんだ。
私が泥に沈んで溺れかけているとき、彼は水面から見える遠くの景色を見ていたんだ。
「俺が引っ張り出してやるよ。泥の中から」
MIYAさんが切なそうに、言った。
ああ、優しい人ね。
だけど、同じことだわ。
この世界にあるのは刹那の欲と、その場限りの安らぎと、嘘っぱちの約束ばかり。
「引っ張り出して、それからどうするんですか?」
「そうだな……もう水辺には近寄らせないようにする」
「なにそれ」
くすっと笑みをこぼした私を見て、MIYAさんも笑う。
「俺は、オルちゃんを泣かせたりしない」
私の頭を胸に押し付けるように抱きしめ、MIYAさんが囁いた。
嘘つき。
言葉は水面を揺らすけれど、響きはしない……。
私が泥から這い上がっても、MIYAさんが新しい泉となる。時が経てば同じように、どちらかが沈んでゆくのだ。
そもそも、有限の中にあって、無限を求めること自体、間違っているのだろう。
最初からそんなものなかったのだから、最後まで見つかる筈がない。
わかっている。
それでも私は、探してしまう。変わらない想いを。不変の愛を。
そんなものはないと知りながら。
誰か、私をドロドロに溶かしてよ。
カケラひとつ、残らないくらいに。
遠くから雨の音が聞こえる。
あの雨も、流れて、流れて、いつか深くて濁った大きな水溜りになるのだ。
誰かを水底へと沈めようとほくそ笑む、大きくて濁った水溜りに。
――雨は、止むことなく降り続けていた。