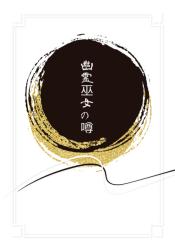真奈美の指示で皆、巫女さんを呼び出す儀式の準備をする。儀式自体は至って簡単でシンプルなものだ。
まず、どこでもいいので、一箇所だけ窓を開けてカーテンを閉め、部屋を暗くする。後々、儀式に参加する面々で手を繋ぐので、皆円形に座る。その中心に赤いペンや筆で大きな鳥居とその中に五芒星を描いた和紙を置く。今回は真奈美が用意してくれた赤いボールペンを使って書いた物を用意した。その横に刃物を一本用意する。これは巫女さんと契約する者が、自分の指を少し切って拇印を押す為の物だ。真奈美の呪文が終わるのと同時に、和紙に血判を押さなければならない。血判を押せば、巫女さんとの契約は完了し、悪霊を祓ってくれるというのが一連の流れだと真奈美は淡々と説明した。
「ここまでは大丈夫?」
「途中で手、放してもいいのか?」
「うん。呪文が終われば、見えないけど、巫女さんは近くにいるみたいだから」
「間違って親指切るなよ、涼佑」
「そんな間抜けなことするか」
「あ、大丈夫。意外と親指切っちゃう人多いから、その時は反対の親指で押してね」
「お、おう」
そう聞いて、少々心配になったのか、ちらりと涼佑はテーブルに置かれたカッターナイフを見つめる。唯一、気を付けるべきことは深く切らないことだけだ。しかし、そこで一つ疑問が持ち上がる。
「青谷、さっき巫女さんの分って言ってたやつは? 置かなくていいのか?」
「うん。今はまだ呼び出してないから、これは巫女さんが来てから使うの」
座っている真奈美の傍には、さっき取っておいた大福と麦茶が置かれている。一切手を付けられていない様は何かお供え物みたいだなと涼佑は思った。
「じゃあ、始めよっか。……あ、言っとくけど、新條。絶対怖がっちゃダメだからね」
「は? 怖がる訳無いだろ」
準備が整い、絢の一言で皆はお互いに手を繋ぐ。涼佑が直樹の方をちらりと見ると、左隣の真奈美と手を繋いでいることを分かりやすく意識していた。右にいる涼佑のことなんて、眼中に無い様子に彼は少しだけ腹を立てた。自分は至って真剣なのだがと言ってやりたい気分になる。静かになったところで、折りを見た真奈美が滔々と呪文を唱え始めた。
「巫女さん、巫女さん。彼方よりお出で下さい。此方にお迎え致します」
ふわ、と開いた窓から弱い風が入ってきて、カーテンを捲り上げる。偶然の筈なのに、涼佑の背筋にぞくりと寒気とも怖気とも分からないものが駆け上がってきた。そうしているうちにも真奈美の声は続く。
「彼方よりお越しくだされば、貴方様の依代をお約束致します」
ざわざわと身体中の毛が逆立つのが分かった。これは窓が開いてるから、風が入ってきて少し肌寒いせいだ。心霊的なものじゃない。そう自分に言い聞かせる涼佑。そろそろ血判の準備をしようとカッターナイフを取って刃を親指に当てそうになり、慌てて別の指にしようとして、手が滑った。スパッ、と小指側の掌側面を切ってしまい、血が滴る。一瞬、止めようと真奈美の言葉が詰まったが、「続けろ!」という涼佑の声に覚悟を決めたようで続行された。右手の親指に血を付けていつでも押せるようにしておく。
「此度、貴方様と契りを交わすは新條涼佑なる人。どうか、その体にお入りください」
呪文が終わったと同時に、涼佑は和紙に血塗れの親指を押し付ける。無事、拇印が押されると、風が止み、皆少し疲れた溜息を吐いた。
「これで、終わり?」
「ううん、まだ。後は新條君の周りで何かが起きるのを待つ」
集中していたせいか、緊張の糸が切れると、何だかどっと疲れが出て涼佑は体の力を抜く。これで儀式は終わったと肩の荷が下りたような心地でいると、ずり、ずり、と何かが這ってくるような音がする。その音に誘われるようにして何気なくドアの方を見た。いつの間にか部屋のドアは開いていて、そこから階段の降り口が少しだけ見える。どうやら、音は階段を上がってくるようだった。嫌な予感を覚え、奥歯を噛み締めるが、それ以外にできることは無く、階段の降り口からぬっと現れたのは長い黒髪を引きずるようにして上ってきた四つん這いの女の顔だった。
「うわぁああああああああっ!!?」
瞬間、涼佑は他人の家にいるということも忘れて叫んだ。恐怖で心の底から叫び、怯えた。咄嗟に逃げようとしたが、カーペットか何かで滑って立ち上がることすらできない。彼の叫び声ですぐさま真奈美が動き、何故か涼佑の肩を押さえて動きを止めようとする。
「怖がらないで! 巫女さんはあなたの前に現れるけど、その姿は大抵普通の霊と変わらないの! 彼女を受け入れないと、悪霊は祓えない!」
涼佑は真奈美の話を聞いているのか、いないのか、傍目から見て判断はできない。それ程、今の彼は怯えて錯乱状態になっていた。残念ながら真奈美達の目には、涼佑が見ているものは映っていない。彼が何を見て怯えているのか正確なことは分からないが、その反応から真奈美は巫女さんが現れたと確信できた。
女はじっとそこから動かない。まるでこっちの様子を窺っているみたいだった。一気に近付いて来られるのも怖いが、じっとそこに居られるのも怖いと涼佑はどうにもならない凝り固まった恐怖と必死に戦っていた。涼佑が女と睨み合っている間も、真奈美は彼に落ち着くよう声を掛け続ける。
「大丈夫、落ち着いて。巫女さんはこっちが何かしない限り、近付いては来ないから。深呼吸して、ちゃんと彼女を見るの」
そのままどのくらいの時間が経ったのかは分からない。けれど、真奈美の声かけが功を奏したのか、何とか落ち着き始めた涼佑は少し冷静さも取り戻した。確かに真奈美の言った通り、女は一向に近付いて来ない。だが、依然としてそこにいるのは変わらなかった。
それから数分が経ち、一歩も近付いてこない女の姿に少し見慣れると、涼佑の恐怖は段々と融解して先程の叫び散らかしている状態からは脱し、いくらか冷静に周りを見ることができるようになってきた。それを好機と見た真奈美が静かに語りかける。
「ねぇ、新條君。巫女さんは今どこにいるの?」
「どこって……見えないのか?」
涼佑の問いに真奈美は頷く。巫女さんの姿が見えるのは、契約した本人だけだと彼女が説明すると、涼佑はもう堪らないという顔で頭を抱えた。「何だよそれ、そんなん聞いてねぇよ……」と零された言葉に真奈美が淡々と返す。
「言ってなかったからね。それに、巫女さんの姿は見る人によって違うの。さっきは大抵、普通の幽霊の姿って言ったけど、稀にそれとは違う姿の巫女さんを見る人もいるみたい。新條君はどうなのか、分からなかったから」
「……階段のとこ。四つん這いで、こっち見てる」
「今の巫女さんはどんな風に見える?」と訊いた真奈美の様子があまりにも落ち着いていて、涼佑は自分の周囲を観察できるまでになった。直樹達も真奈美同様に巫女さんが見えないらしく、不安げに涼佑と階段を交互に見ている。周りの様子を見る余裕が生まれると、自分一人が心底怖がっているのが間違っているのかもとすら思えてきた涼佑は、もう一度、階段の方を見る――
「やっぱ、いるじゃん……」
やっぱ、いるのである。こっちをじっと見つめていて動かない。いや、あっちも動けないと言った方が正しいか。こちらの様子をずっと窺っている。見えるありのままの様子を涙声で涼佑が報告すると、真奈美はうんうんと頷き、厭に優しく次の手順を教えてくれた。
「じゃあ、巫女さんの前にこれを置いて、『お供え物です。どうぞ』って言ってくれない? それで正式な契約は果たされるの」
「死ねって言ってる?」
どう聞いてもそう言っているとしか思えない。それ程までに彼にとって、この任務は荷が重い。「だめ?」と小首を傾げて訊いてくる真奈美に、涼佑は絶望するしかない。
「巫女さんもあのままじゃ可哀想だよ? 都市伝説では私達と同い年くらいの女の子って聞いてるんだけど」
「え、そうなんだ」
同い年の女の子と聞いて、何か複雑な感情を抱いた涼佑はもう一度巫女さんを見た。ちらりと階段の陰から覗いている顔は確かに大人というよりは幼いが、かといって子供とも違うように見える。それに、よくよく見れば、別にこっちを恨みがましく見ている訳じゃない。どちらかというと、こっちにいつ近寄っていいものか、少し戸惑っているようにも見えた。しかし、それを差し引いても涼佑にとっては存在自体が怖い。さっきまで何もいなかった場所に何の前兆も無く、いきなり現れたのだから当然だろう。誰だって怖がるに決まってる。現れるなら、もう少し普通に現れて欲しいと彼は思った。それこそ、ゲームのヒロインみたいに一陣の風が起きて、その中から神々しい巫女服着た女の子が現れても良いと思う、と切実に文句を言いたい気持ちになってしまう。それが何故、四つん這いで階段を這い上ってくるという手段に出たのか、心底理解できない。そんなことを考えていたのが顔に出ていた涼佑に、真奈美が釘を刺すように言ってきた。
「先に言っておくとね、巫女さんの姿は契約する人の感情や思い込みによって変わるって言われてるの。新條君、儀式の間、不安だったんじゃないかな」
「そんなつもりは……無かったんだけど……」
尻すぼみになっていく言葉。自分ではそんなこと思っていなかったけど、無意識では違っていたのかと自分の感情が分からなくなってしまう涼佑。それを確かめようと、また巫女さんを見た。今度は顔がはっきり見える。別に彼女の位置が変わった訳じゃない。ただ顔の半分を隠していた黒髪が分けられて顔が全部見えるようになっただけだ。でも、それだけで涼佑の目にはだいぶ普通の女の子に見えた。顔は傷一つ無く、綺麗な肌をしていて、可愛らしい顔立ちをしていた。その状態の彼女を見て、彼は直感した。
ああ、そうか。ずっと不安で怖かったんだと納得できた。巫女さんを喚んでも、同じ事が起こったらどうしようだとか、更に悪化したらどうしようだとか、先が見えない不安でいっぱいだった。それが彼女の姿に表れていたのかと涼佑は自分の恐怖を受け入れることができた。
その気持ちに応えるように、いつの間にか巫女さんは普通に立っていて、階段を上りきっている。所々汚れてはいるが、白い着物に身を包んだ巫女さんは存外、小さな少女だった。随分、小柄な彼女は目の前まで来ると、儚げに微笑む。その笑顔を見ると、自然と体が動いて涼佑は真奈美の手から離れた。彼女に言われた通りに大福と麦茶を巫女さんへ差し出し、唱える。
「巫女さん、お供え物です。どうぞ」
差し出されたそれに巫女さんが触れると、大福と麦茶から半透明な像が浮かび上がる。実体の方ではなく、像の方を手にすると巫女さんは半透明の大福を食べ、麦茶を飲んだ。
その瞬間、それまで典型的な幽霊少女の姿はかき消え、代わりに巫女服を着たポニーテールの少女がそこに立っていた。巫女服の上に薄く白い上着のような着物を着て、腰には刀を携えている。少女の小柄な体に似合わない、少々大振りの物だ。それに左手をかけて巫女さんは不敵に口端を上げた。
「漸く私を受け入れたか。遅いぞ、涼佑」
さっきまでのしおらしい雰囲気はどこへやら、やや偉そうな態度で巫女さんはふん、と鼻を鳴らした。涼佑が無事お供え物をあげることができ、契約が完了したので、真奈美はほっと胸を撫で下ろして「これで大丈夫」と零す。
「どう? 新條くん。巫女さんはちゃんと傍にいる?」
「やっぱ、オレ以外には見えないのか?」
「彼女はちょっと特殊な守護霊で、見える人には見える守護霊とは違うの。契約した人にだけ見える都市伝説の巫女さん」
「ああ、そうそう。その都市伝説ってどういう話なんだ?」
少し前から訊こうと思っていたことを漸く訊くと、真奈美は「始める前に話しておけば、良かった?」と逆に質問してくる。
「ん~……いや、よく訊かなかったのはオレの方だからなぁ」
「じゃあ、話しておくね」
真奈美から聞いた話はこんな話だった。
昔、ある女子高生が非常にたちの悪い悪霊に取り憑かれてしまったが、周囲に相談できないので、一人で巫女さんの儀式をした。巫女さんが彼女に憑依してからは悪霊はどこかへ去り、彼女と悪霊の縁を巫女さんが断ち切ってくれたお陰で、その女子高生はもう二度と霊に悩まされることは無くなったという話。
他にも巫女さんに関する有り難い話はあるが、丁度タイムリーな話の方が良いと思って話したと言う真奈美。傍らに立つ巫女さんに本当の話か訊くと「ああ、まぁな」とだけ返ってきた。どうやら、彼女の口調は元々男勝りなもののようだ。
「さて、新條君に巫女さんも憑いたことだし、ご飯にしましょうか」
『ご飯』という単語に急に現実に引き戻されたような感覚があって、思わず涼佑は「へ?」と間抜けな声を出してしまう。念を押すように直樹が訊いた。
「いや、飯の準備は良いんだけど、もう涼佑に危険は無いのか?」
「うん。ちゃんと新條君には巫女さんの姿が見えてるし、お供え物をあげたから守ってくれるよ」
真奈美の手に巫女さんに差し出した大福と麦茶があるのに気付いて、何となく見つめていると、巫女さんはにやりと笑って言った。
「食ってみるか? かなり不味くなってるがな」
「いや、いいよ。というか、巫女さんっていつもそういう口調なのか?」
ついさっき涼佑が思ったことを質問としてぶつけると、彼女は些か不愉快そうに眉を顰め、「なんだ、お前。女がこういう口調なのが許せないタイプか? 今、西暦何年だ? 令和だろ?」と嫌味っぽく言ってくる。そういう意図は全く無いと言った上で、涼佑は思ったことを正直に言った。
「そうじゃなくて、その、幽霊でもこういうことに巻き込まれてばっかりいたりしたから、自然とそういう口調になったのかなって。もちろん、巫女さんにも今まで色々あっただろうし、詮索する気は、無いけど」
「……まぁ、私達、ついさっき会ったばっかりだしな。お互いに知らないだろ」
「でも、お前がちょっとだけ話の分かる奴だってのは、分かった」と巫女さんはニカッと笑った。
まず、どこでもいいので、一箇所だけ窓を開けてカーテンを閉め、部屋を暗くする。後々、儀式に参加する面々で手を繋ぐので、皆円形に座る。その中心に赤いペンや筆で大きな鳥居とその中に五芒星を描いた和紙を置く。今回は真奈美が用意してくれた赤いボールペンを使って書いた物を用意した。その横に刃物を一本用意する。これは巫女さんと契約する者が、自分の指を少し切って拇印を押す為の物だ。真奈美の呪文が終わるのと同時に、和紙に血判を押さなければならない。血判を押せば、巫女さんとの契約は完了し、悪霊を祓ってくれるというのが一連の流れだと真奈美は淡々と説明した。
「ここまでは大丈夫?」
「途中で手、放してもいいのか?」
「うん。呪文が終われば、見えないけど、巫女さんは近くにいるみたいだから」
「間違って親指切るなよ、涼佑」
「そんな間抜けなことするか」
「あ、大丈夫。意外と親指切っちゃう人多いから、その時は反対の親指で押してね」
「お、おう」
そう聞いて、少々心配になったのか、ちらりと涼佑はテーブルに置かれたカッターナイフを見つめる。唯一、気を付けるべきことは深く切らないことだけだ。しかし、そこで一つ疑問が持ち上がる。
「青谷、さっき巫女さんの分って言ってたやつは? 置かなくていいのか?」
「うん。今はまだ呼び出してないから、これは巫女さんが来てから使うの」
座っている真奈美の傍には、さっき取っておいた大福と麦茶が置かれている。一切手を付けられていない様は何かお供え物みたいだなと涼佑は思った。
「じゃあ、始めよっか。……あ、言っとくけど、新條。絶対怖がっちゃダメだからね」
「は? 怖がる訳無いだろ」
準備が整い、絢の一言で皆はお互いに手を繋ぐ。涼佑が直樹の方をちらりと見ると、左隣の真奈美と手を繋いでいることを分かりやすく意識していた。右にいる涼佑のことなんて、眼中に無い様子に彼は少しだけ腹を立てた。自分は至って真剣なのだがと言ってやりたい気分になる。静かになったところで、折りを見た真奈美が滔々と呪文を唱え始めた。
「巫女さん、巫女さん。彼方よりお出で下さい。此方にお迎え致します」
ふわ、と開いた窓から弱い風が入ってきて、カーテンを捲り上げる。偶然の筈なのに、涼佑の背筋にぞくりと寒気とも怖気とも分からないものが駆け上がってきた。そうしているうちにも真奈美の声は続く。
「彼方よりお越しくだされば、貴方様の依代をお約束致します」
ざわざわと身体中の毛が逆立つのが分かった。これは窓が開いてるから、風が入ってきて少し肌寒いせいだ。心霊的なものじゃない。そう自分に言い聞かせる涼佑。そろそろ血判の準備をしようとカッターナイフを取って刃を親指に当てそうになり、慌てて別の指にしようとして、手が滑った。スパッ、と小指側の掌側面を切ってしまい、血が滴る。一瞬、止めようと真奈美の言葉が詰まったが、「続けろ!」という涼佑の声に覚悟を決めたようで続行された。右手の親指に血を付けていつでも押せるようにしておく。
「此度、貴方様と契りを交わすは新條涼佑なる人。どうか、その体にお入りください」
呪文が終わったと同時に、涼佑は和紙に血塗れの親指を押し付ける。無事、拇印が押されると、風が止み、皆少し疲れた溜息を吐いた。
「これで、終わり?」
「ううん、まだ。後は新條君の周りで何かが起きるのを待つ」
集中していたせいか、緊張の糸が切れると、何だかどっと疲れが出て涼佑は体の力を抜く。これで儀式は終わったと肩の荷が下りたような心地でいると、ずり、ずり、と何かが這ってくるような音がする。その音に誘われるようにして何気なくドアの方を見た。いつの間にか部屋のドアは開いていて、そこから階段の降り口が少しだけ見える。どうやら、音は階段を上がってくるようだった。嫌な予感を覚え、奥歯を噛み締めるが、それ以外にできることは無く、階段の降り口からぬっと現れたのは長い黒髪を引きずるようにして上ってきた四つん這いの女の顔だった。
「うわぁああああああああっ!!?」
瞬間、涼佑は他人の家にいるということも忘れて叫んだ。恐怖で心の底から叫び、怯えた。咄嗟に逃げようとしたが、カーペットか何かで滑って立ち上がることすらできない。彼の叫び声ですぐさま真奈美が動き、何故か涼佑の肩を押さえて動きを止めようとする。
「怖がらないで! 巫女さんはあなたの前に現れるけど、その姿は大抵普通の霊と変わらないの! 彼女を受け入れないと、悪霊は祓えない!」
涼佑は真奈美の話を聞いているのか、いないのか、傍目から見て判断はできない。それ程、今の彼は怯えて錯乱状態になっていた。残念ながら真奈美達の目には、涼佑が見ているものは映っていない。彼が何を見て怯えているのか正確なことは分からないが、その反応から真奈美は巫女さんが現れたと確信できた。
女はじっとそこから動かない。まるでこっちの様子を窺っているみたいだった。一気に近付いて来られるのも怖いが、じっとそこに居られるのも怖いと涼佑はどうにもならない凝り固まった恐怖と必死に戦っていた。涼佑が女と睨み合っている間も、真奈美は彼に落ち着くよう声を掛け続ける。
「大丈夫、落ち着いて。巫女さんはこっちが何かしない限り、近付いては来ないから。深呼吸して、ちゃんと彼女を見るの」
そのままどのくらいの時間が経ったのかは分からない。けれど、真奈美の声かけが功を奏したのか、何とか落ち着き始めた涼佑は少し冷静さも取り戻した。確かに真奈美の言った通り、女は一向に近付いて来ない。だが、依然としてそこにいるのは変わらなかった。
それから数分が経ち、一歩も近付いてこない女の姿に少し見慣れると、涼佑の恐怖は段々と融解して先程の叫び散らかしている状態からは脱し、いくらか冷静に周りを見ることができるようになってきた。それを好機と見た真奈美が静かに語りかける。
「ねぇ、新條君。巫女さんは今どこにいるの?」
「どこって……見えないのか?」
涼佑の問いに真奈美は頷く。巫女さんの姿が見えるのは、契約した本人だけだと彼女が説明すると、涼佑はもう堪らないという顔で頭を抱えた。「何だよそれ、そんなん聞いてねぇよ……」と零された言葉に真奈美が淡々と返す。
「言ってなかったからね。それに、巫女さんの姿は見る人によって違うの。さっきは大抵、普通の幽霊の姿って言ったけど、稀にそれとは違う姿の巫女さんを見る人もいるみたい。新條君はどうなのか、分からなかったから」
「……階段のとこ。四つん這いで、こっち見てる」
「今の巫女さんはどんな風に見える?」と訊いた真奈美の様子があまりにも落ち着いていて、涼佑は自分の周囲を観察できるまでになった。直樹達も真奈美同様に巫女さんが見えないらしく、不安げに涼佑と階段を交互に見ている。周りの様子を見る余裕が生まれると、自分一人が心底怖がっているのが間違っているのかもとすら思えてきた涼佑は、もう一度、階段の方を見る――
「やっぱ、いるじゃん……」
やっぱ、いるのである。こっちをじっと見つめていて動かない。いや、あっちも動けないと言った方が正しいか。こちらの様子をずっと窺っている。見えるありのままの様子を涙声で涼佑が報告すると、真奈美はうんうんと頷き、厭に優しく次の手順を教えてくれた。
「じゃあ、巫女さんの前にこれを置いて、『お供え物です。どうぞ』って言ってくれない? それで正式な契約は果たされるの」
「死ねって言ってる?」
どう聞いてもそう言っているとしか思えない。それ程までに彼にとって、この任務は荷が重い。「だめ?」と小首を傾げて訊いてくる真奈美に、涼佑は絶望するしかない。
「巫女さんもあのままじゃ可哀想だよ? 都市伝説では私達と同い年くらいの女の子って聞いてるんだけど」
「え、そうなんだ」
同い年の女の子と聞いて、何か複雑な感情を抱いた涼佑はもう一度巫女さんを見た。ちらりと階段の陰から覗いている顔は確かに大人というよりは幼いが、かといって子供とも違うように見える。それに、よくよく見れば、別にこっちを恨みがましく見ている訳じゃない。どちらかというと、こっちにいつ近寄っていいものか、少し戸惑っているようにも見えた。しかし、それを差し引いても涼佑にとっては存在自体が怖い。さっきまで何もいなかった場所に何の前兆も無く、いきなり現れたのだから当然だろう。誰だって怖がるに決まってる。現れるなら、もう少し普通に現れて欲しいと彼は思った。それこそ、ゲームのヒロインみたいに一陣の風が起きて、その中から神々しい巫女服着た女の子が現れても良いと思う、と切実に文句を言いたい気持ちになってしまう。それが何故、四つん這いで階段を這い上ってくるという手段に出たのか、心底理解できない。そんなことを考えていたのが顔に出ていた涼佑に、真奈美が釘を刺すように言ってきた。
「先に言っておくとね、巫女さんの姿は契約する人の感情や思い込みによって変わるって言われてるの。新條君、儀式の間、不安だったんじゃないかな」
「そんなつもりは……無かったんだけど……」
尻すぼみになっていく言葉。自分ではそんなこと思っていなかったけど、無意識では違っていたのかと自分の感情が分からなくなってしまう涼佑。それを確かめようと、また巫女さんを見た。今度は顔がはっきり見える。別に彼女の位置が変わった訳じゃない。ただ顔の半分を隠していた黒髪が分けられて顔が全部見えるようになっただけだ。でも、それだけで涼佑の目にはだいぶ普通の女の子に見えた。顔は傷一つ無く、綺麗な肌をしていて、可愛らしい顔立ちをしていた。その状態の彼女を見て、彼は直感した。
ああ、そうか。ずっと不安で怖かったんだと納得できた。巫女さんを喚んでも、同じ事が起こったらどうしようだとか、更に悪化したらどうしようだとか、先が見えない不安でいっぱいだった。それが彼女の姿に表れていたのかと涼佑は自分の恐怖を受け入れることができた。
その気持ちに応えるように、いつの間にか巫女さんは普通に立っていて、階段を上りきっている。所々汚れてはいるが、白い着物に身を包んだ巫女さんは存外、小さな少女だった。随分、小柄な彼女は目の前まで来ると、儚げに微笑む。その笑顔を見ると、自然と体が動いて涼佑は真奈美の手から離れた。彼女に言われた通りに大福と麦茶を巫女さんへ差し出し、唱える。
「巫女さん、お供え物です。どうぞ」
差し出されたそれに巫女さんが触れると、大福と麦茶から半透明な像が浮かび上がる。実体の方ではなく、像の方を手にすると巫女さんは半透明の大福を食べ、麦茶を飲んだ。
その瞬間、それまで典型的な幽霊少女の姿はかき消え、代わりに巫女服を着たポニーテールの少女がそこに立っていた。巫女服の上に薄く白い上着のような着物を着て、腰には刀を携えている。少女の小柄な体に似合わない、少々大振りの物だ。それに左手をかけて巫女さんは不敵に口端を上げた。
「漸く私を受け入れたか。遅いぞ、涼佑」
さっきまでのしおらしい雰囲気はどこへやら、やや偉そうな態度で巫女さんはふん、と鼻を鳴らした。涼佑が無事お供え物をあげることができ、契約が完了したので、真奈美はほっと胸を撫で下ろして「これで大丈夫」と零す。
「どう? 新條くん。巫女さんはちゃんと傍にいる?」
「やっぱ、オレ以外には見えないのか?」
「彼女はちょっと特殊な守護霊で、見える人には見える守護霊とは違うの。契約した人にだけ見える都市伝説の巫女さん」
「ああ、そうそう。その都市伝説ってどういう話なんだ?」
少し前から訊こうと思っていたことを漸く訊くと、真奈美は「始める前に話しておけば、良かった?」と逆に質問してくる。
「ん~……いや、よく訊かなかったのはオレの方だからなぁ」
「じゃあ、話しておくね」
真奈美から聞いた話はこんな話だった。
昔、ある女子高生が非常にたちの悪い悪霊に取り憑かれてしまったが、周囲に相談できないので、一人で巫女さんの儀式をした。巫女さんが彼女に憑依してからは悪霊はどこかへ去り、彼女と悪霊の縁を巫女さんが断ち切ってくれたお陰で、その女子高生はもう二度と霊に悩まされることは無くなったという話。
他にも巫女さんに関する有り難い話はあるが、丁度タイムリーな話の方が良いと思って話したと言う真奈美。傍らに立つ巫女さんに本当の話か訊くと「ああ、まぁな」とだけ返ってきた。どうやら、彼女の口調は元々男勝りなもののようだ。
「さて、新條君に巫女さんも憑いたことだし、ご飯にしましょうか」
『ご飯』という単語に急に現実に引き戻されたような感覚があって、思わず涼佑は「へ?」と間抜けな声を出してしまう。念を押すように直樹が訊いた。
「いや、飯の準備は良いんだけど、もう涼佑に危険は無いのか?」
「うん。ちゃんと新條君には巫女さんの姿が見えてるし、お供え物をあげたから守ってくれるよ」
真奈美の手に巫女さんに差し出した大福と麦茶があるのに気付いて、何となく見つめていると、巫女さんはにやりと笑って言った。
「食ってみるか? かなり不味くなってるがな」
「いや、いいよ。というか、巫女さんっていつもそういう口調なのか?」
ついさっき涼佑が思ったことを質問としてぶつけると、彼女は些か不愉快そうに眉を顰め、「なんだ、お前。女がこういう口調なのが許せないタイプか? 今、西暦何年だ? 令和だろ?」と嫌味っぽく言ってくる。そういう意図は全く無いと言った上で、涼佑は思ったことを正直に言った。
「そうじゃなくて、その、幽霊でもこういうことに巻き込まれてばっかりいたりしたから、自然とそういう口調になったのかなって。もちろん、巫女さんにも今まで色々あっただろうし、詮索する気は、無いけど」
「……まぁ、私達、ついさっき会ったばっかりだしな。お互いに知らないだろ」
「でも、お前がちょっとだけ話の分かる奴だってのは、分かった」と巫女さんはニカッと笑った。