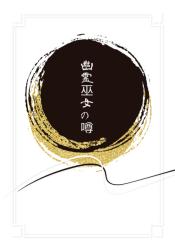今後のことを話し合う中、一番の懸念はみくの存在だろうという話になった。小さな子を連れたまま、この村を探索するのは少々無謀だとは思った涼佑だが、この民家に置いて行く訳にもいかない。ここの住民が絶対に襲って来ないという保証も無い。万が一、道連れにでもされたら堪ったものではないと思った涼佑は、取り敢えず、村の奥に行ってみようと話し合っている真奈美達に近付き、誰に話そうかと考え、やはり真奈美にこっそりと話し掛けた。
「あの、さ、真奈美」
「どうしたの? 涼佑くん」
さて、どう切り出したものかと涼佑は考える。勿論、第一に優先すべきは自分達やみくの命だ。この村が本当に『転んだら死ぬ村』である以上、最終目標は生きたまま皆で帰る。この一点に尽きる。しかし、その過程を考えると、どうしても涼佑の頭をある考えが過ってしまうのも事実だ。じゃあ、もし、それができなかったら? と。一度そう考えてしまうと、どうしてもそれを口にすることは憚られた。
それ以上、何も言えずに口ごもってしまう涼佑を真奈美は不思議そうに見返す。そんな二人に「涼佑、近いんですけどぉ」と軽口を叩きながら直樹が近寄って来て、涼佑の肩に腕を回す。そのまま真奈美からぐいぐいと離され、玄関の隅に連れて来られた涼佑は「何だよ?」と怪訝そうな顔をする。そんな彼に直樹はこしょこしょと内緒話をした。
「お前、さっき何て言おうとした?」
「え? 何って、万が一、生きて帰れなかったらって話を――」
「バッカ。お前、そんな話すんな。生きて帰れなかったらなんて話、聞きたくもねぇよ! ……その場合、お前どうするつもり?」
「――オレから巫女さんを何とか切り離して……」
「却下。そんな案、案じゃねぇよ。却下過ぎるわ。その場合はおれだろ」
とても怖がりの直樹から出た案とは思えずに涼佑は、瞠目したまま彼を見る。直樹はへへんと得意気な笑みを浮かべて自分の胸を親指で叩いた。
「……本気か?」
「今んとこ、このメンバーで言ったらおれが足手まといだし。何より転ぶ自信しかねぇ。それにさ、ここでもし、おれが真奈美を庇って死んだらかっこいいじゃん。それこそ伝説になるだろ?」
口ではそんな冗談を言っているが、体は僅かに震えている。額を伝う冷や汗に気付かない振りをして、涼佑は「ばぁか」と直樹を小突いた。「痛って!?」と小突かれた頭を大袈裟に擦る直樹に涼佑は失笑を交えつつ、話を流す。
「お前みたいなビビりがそんなことできる訳ないだろ」
「はぁ? シンガイなんですけどぉ!」
直樹から離れ、涼佑は真奈美に「何でもない」と微笑むと、真奈美はやはり読めない無表情で「そう」とだけ言って、絢達の傍に戻った。存外、身近な者から自らを犠牲にしろと言われるのは思ったよりずっと心が痛いものだなと思いつつ、涼佑は震える手を奮い立たせるようにぎゅっと握った。怖くない、なんて嘘だ。でも、この村にいる間は友人達を守れたら、と考えずにはいられないのだった。
取り敢えず、まずは情報収集をしようということになり、ある程度の範囲を決めて、その範囲内で二手に分かれることになった。真奈美達と巫女さんの女子組にはみくの面倒も見てもらうことになり、涼佑と直樹は男子組として調査しようとそれぞれ民家を出た。多少、霧が出ているが、先が分からなくなる程ではない。別れても大丈夫だろうと判断した一同は、この民家を集合場所として互いに反対方向の道へ歩いて行く。みくは絢とずっと手を繋いでいるようなので、転ぶ心配はあまり無いかと、ちら、と女子組を見ていた涼佑は転ばないように前を向いた。
直樹達と合流する前、巫女さんに言われたことを思い出した涼佑は、「そういえばさ」という切り口で直樹に話す。
「直樹達と合流する前、巫女さんに言われたんだけど、今オレらは魂だけの存在だから、体重が凄く軽いんだってよ」
「ほーん……んで?」
「万が一、オレか直樹が転びそうになった時に引っ張れば、体勢直るんじゃね? って思って。今のうちに試したいんだけど」
そう言った瞬間、直樹はずさっと後ろに下がって涼佑から少し距離を取った。その顔は不信そのものだ。
「なんだよ」
「いや、涼佑君。誰が、何を試すって……?」
「いや、どっちかがどっちかのことを持ち上げたりできないかなって――」
最後まで言えずに涼佑は、ぎゅんっと迫ってきた直樹の鬼気迫る表情に「うわっ」と驚いた。直樹はそんな彼に構わず、ごく真剣な表情と若干血走った目で言い募る。
「いやいやいやいや! ここでっ!? 試すっ!? 転んだら死ぬって聞いてんのにっ!? わざわざ自分から転びに行くの!? なんで!? お前バカなの!? 世界バカ選手権第一位でも目指してんのっ!?」
「目指してねぇし、そんな選手権ねーよ」
直樹のあまりの言い草に苛立った涼佑は「もういい。岡島チキンめ」と言い残してそのまま先へ進もうとしたが、直樹は「別にビビってないですけどぉ?」と強がりながら付いて来る。ここで直樹と喧嘩しても仕方がないと思った涼佑は、後で隙を見て彼をちょっと持ち上げてみようと心に決めた。
民家から出て畦道を歩いていると、二つ目の田んぼの中に麦わら帽子を被った男が一人、何やら農作業をしていた。よく見ると田植えをしているようで、脇に苗がたくさん入った段ボール箱を抱えている。涼佑と直樹は少し「変だな」と思った。霧が出ているのに田植えをするというイメージが二人の中に無かったからだ。しかし、そこは「ここが夢の中なのだから」ということである程度、現実と違いがあるのだろうと納得し、直樹はその男の背中へ声を掛けてみた。ここからでは少し距離があるので、両手を筒代わりにする。
「すいませーん。ちょっとお話聞いて良いっすかぁ~?」
人当たりの良い直樹の声に男はすぐに気付いたようで、こちらへ振り向くと、返事をするように片手を挙げる。直樹がもう一度、少し話せないかと伺うと、男はにこやかにこちらへ近付いて来た。泥に足を少し取られながらも、こちらに来るその様子は快活そうで好感が持てる。男は思ったよりまだ若く、四十代に見えた。長年農作業をしているのか、日に焼けた肌が健康そうだ。歩きながら男が訊いてきた。
「どうしたの? 迷った?」
「すいません、お仕事中に。そうなんすよ、おれら迷っちゃって。帰り道知りませんかぁ?」
呑気に答える直樹を見て涼佑は内心「話し掛けて良かったのか?」と不安に思ったが、彼の心配とは裏腹に男はにこやかに「ああ、そっかぁ。大変だねぇ」と相槌を打つ。脇に抱えていた苗が入った箱を雑草の上に置いて、男は「帰り道はねぇ……」と指そうとしたのか、田んぼの中からこちらへ出ようとした。
「おっ……と!」
「あ」
男が泥の中から足を抜こうとした途端、そのまま足を取られて男はべしゃりと転んで倒れてしまった。つい直樹が「大丈夫っすか?」と声を掛けるも、男からの返答は無い。思わず、直樹が男に近付こうとしたが、涼佑は彼の服の裾を掴んで止めた。
「何だよ、涼佑。起こしてやんなきゃ――」
「近付くな! 死んでるよ、その人……!」
「え?」
見ると、涼佑の言った通り、みるみるうちに男の全身に青紫の痣が広がる。この村に来てから、涼佑が一度見た、直樹は初めて光景だ。村人らしき人はいたし、襲っては来ない。むしろ、現実のように友好的だ。だが、それ以上に強烈な恐怖と罪悪感を覚えてしまう。もうそれ以上、ピクリとも動かない男を見ていられなくて、二人は青い顔のまま畦道を進んで行った。
「あの、さ、真奈美」
「どうしたの? 涼佑くん」
さて、どう切り出したものかと涼佑は考える。勿論、第一に優先すべきは自分達やみくの命だ。この村が本当に『転んだら死ぬ村』である以上、最終目標は生きたまま皆で帰る。この一点に尽きる。しかし、その過程を考えると、どうしても涼佑の頭をある考えが過ってしまうのも事実だ。じゃあ、もし、それができなかったら? と。一度そう考えてしまうと、どうしてもそれを口にすることは憚られた。
それ以上、何も言えずに口ごもってしまう涼佑を真奈美は不思議そうに見返す。そんな二人に「涼佑、近いんですけどぉ」と軽口を叩きながら直樹が近寄って来て、涼佑の肩に腕を回す。そのまま真奈美からぐいぐいと離され、玄関の隅に連れて来られた涼佑は「何だよ?」と怪訝そうな顔をする。そんな彼に直樹はこしょこしょと内緒話をした。
「お前、さっき何て言おうとした?」
「え? 何って、万が一、生きて帰れなかったらって話を――」
「バッカ。お前、そんな話すんな。生きて帰れなかったらなんて話、聞きたくもねぇよ! ……その場合、お前どうするつもり?」
「――オレから巫女さんを何とか切り離して……」
「却下。そんな案、案じゃねぇよ。却下過ぎるわ。その場合はおれだろ」
とても怖がりの直樹から出た案とは思えずに涼佑は、瞠目したまま彼を見る。直樹はへへんと得意気な笑みを浮かべて自分の胸を親指で叩いた。
「……本気か?」
「今んとこ、このメンバーで言ったらおれが足手まといだし。何より転ぶ自信しかねぇ。それにさ、ここでもし、おれが真奈美を庇って死んだらかっこいいじゃん。それこそ伝説になるだろ?」
口ではそんな冗談を言っているが、体は僅かに震えている。額を伝う冷や汗に気付かない振りをして、涼佑は「ばぁか」と直樹を小突いた。「痛って!?」と小突かれた頭を大袈裟に擦る直樹に涼佑は失笑を交えつつ、話を流す。
「お前みたいなビビりがそんなことできる訳ないだろ」
「はぁ? シンガイなんですけどぉ!」
直樹から離れ、涼佑は真奈美に「何でもない」と微笑むと、真奈美はやはり読めない無表情で「そう」とだけ言って、絢達の傍に戻った。存外、身近な者から自らを犠牲にしろと言われるのは思ったよりずっと心が痛いものだなと思いつつ、涼佑は震える手を奮い立たせるようにぎゅっと握った。怖くない、なんて嘘だ。でも、この村にいる間は友人達を守れたら、と考えずにはいられないのだった。
取り敢えず、まずは情報収集をしようということになり、ある程度の範囲を決めて、その範囲内で二手に分かれることになった。真奈美達と巫女さんの女子組にはみくの面倒も見てもらうことになり、涼佑と直樹は男子組として調査しようとそれぞれ民家を出た。多少、霧が出ているが、先が分からなくなる程ではない。別れても大丈夫だろうと判断した一同は、この民家を集合場所として互いに反対方向の道へ歩いて行く。みくは絢とずっと手を繋いでいるようなので、転ぶ心配はあまり無いかと、ちら、と女子組を見ていた涼佑は転ばないように前を向いた。
直樹達と合流する前、巫女さんに言われたことを思い出した涼佑は、「そういえばさ」という切り口で直樹に話す。
「直樹達と合流する前、巫女さんに言われたんだけど、今オレらは魂だけの存在だから、体重が凄く軽いんだってよ」
「ほーん……んで?」
「万が一、オレか直樹が転びそうになった時に引っ張れば、体勢直るんじゃね? って思って。今のうちに試したいんだけど」
そう言った瞬間、直樹はずさっと後ろに下がって涼佑から少し距離を取った。その顔は不信そのものだ。
「なんだよ」
「いや、涼佑君。誰が、何を試すって……?」
「いや、どっちかがどっちかのことを持ち上げたりできないかなって――」
最後まで言えずに涼佑は、ぎゅんっと迫ってきた直樹の鬼気迫る表情に「うわっ」と驚いた。直樹はそんな彼に構わず、ごく真剣な表情と若干血走った目で言い募る。
「いやいやいやいや! ここでっ!? 試すっ!? 転んだら死ぬって聞いてんのにっ!? わざわざ自分から転びに行くの!? なんで!? お前バカなの!? 世界バカ選手権第一位でも目指してんのっ!?」
「目指してねぇし、そんな選手権ねーよ」
直樹のあまりの言い草に苛立った涼佑は「もういい。岡島チキンめ」と言い残してそのまま先へ進もうとしたが、直樹は「別にビビってないですけどぉ?」と強がりながら付いて来る。ここで直樹と喧嘩しても仕方がないと思った涼佑は、後で隙を見て彼をちょっと持ち上げてみようと心に決めた。
民家から出て畦道を歩いていると、二つ目の田んぼの中に麦わら帽子を被った男が一人、何やら農作業をしていた。よく見ると田植えをしているようで、脇に苗がたくさん入った段ボール箱を抱えている。涼佑と直樹は少し「変だな」と思った。霧が出ているのに田植えをするというイメージが二人の中に無かったからだ。しかし、そこは「ここが夢の中なのだから」ということである程度、現実と違いがあるのだろうと納得し、直樹はその男の背中へ声を掛けてみた。ここからでは少し距離があるので、両手を筒代わりにする。
「すいませーん。ちょっとお話聞いて良いっすかぁ~?」
人当たりの良い直樹の声に男はすぐに気付いたようで、こちらへ振り向くと、返事をするように片手を挙げる。直樹がもう一度、少し話せないかと伺うと、男はにこやかにこちらへ近付いて来た。泥に足を少し取られながらも、こちらに来るその様子は快活そうで好感が持てる。男は思ったよりまだ若く、四十代に見えた。長年農作業をしているのか、日に焼けた肌が健康そうだ。歩きながら男が訊いてきた。
「どうしたの? 迷った?」
「すいません、お仕事中に。そうなんすよ、おれら迷っちゃって。帰り道知りませんかぁ?」
呑気に答える直樹を見て涼佑は内心「話し掛けて良かったのか?」と不安に思ったが、彼の心配とは裏腹に男はにこやかに「ああ、そっかぁ。大変だねぇ」と相槌を打つ。脇に抱えていた苗が入った箱を雑草の上に置いて、男は「帰り道はねぇ……」と指そうとしたのか、田んぼの中からこちらへ出ようとした。
「おっ……と!」
「あ」
男が泥の中から足を抜こうとした途端、そのまま足を取られて男はべしゃりと転んで倒れてしまった。つい直樹が「大丈夫っすか?」と声を掛けるも、男からの返答は無い。思わず、直樹が男に近付こうとしたが、涼佑は彼の服の裾を掴んで止めた。
「何だよ、涼佑。起こしてやんなきゃ――」
「近付くな! 死んでるよ、その人……!」
「え?」
見ると、涼佑の言った通り、みるみるうちに男の全身に青紫の痣が広がる。この村に来てから、涼佑が一度見た、直樹は初めて光景だ。村人らしき人はいたし、襲っては来ない。むしろ、現実のように友好的だ。だが、それ以上に強烈な恐怖と罪悪感を覚えてしまう。もうそれ以上、ピクリとも動かない男を見ていられなくて、二人は青い顔のまま畦道を進んで行った。