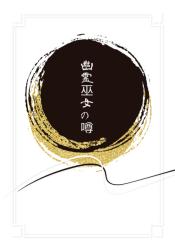「ここにっ……! 今ここにスマホがあったら!」といつになく興奮している真奈美に皆、呆気に取られる。先程まで泣いていた絢ですら、真奈美の様子を見てぽかんとした後、何やら微笑ましそうな顔をしていた。
平時は殆ど表情が変わらない彼女にしては珍しく、本当に心の底から後悔しているようだった。暗い顔で沈んでいる真奈美に、直樹が恐る恐る「そんなにか?」と訊くと、彼女は「だって、巫女さんだよ!?」と声を荒らげる。
「彼女は普通の守護霊と違って、普段は宿主の涼佑くんにしか見えないし、聞こえないのっ! そんな彼女がここにこうして現れてるってすっごく! すっごく貴重な体験なんだからねっ!? 私、私……」
興奮のままに直樹に迫る真奈美に「お、おぅ」としか返せなくなりながら聞いていた直樹だが、その様子を見て我に返った真奈美は、恥ずかしそうに両手で自分の頬を叩くように押さえ、「見たこと無いの……」と蚊の鳴くような声で呟いた。しょもしょもと先程までの勢いを無くしてしまった真奈美は、今更込み上げてきた羞恥でいたたまれなくなったのか、そのまま玄関に座り込んでしまい、「見ないで……」と赤くなった顔を隠してしまった。そんな彼女を何とか励まそうと直樹が「いや、気にすんなよ。真奈美、こういうの好きだもんな」と声を掛けるも、萎んでしまった真奈美は微かに「ごめん」と謝るだけだ。
先程までの緊張が解け、いくらか場が和んだその時。がたり、と真奈美の背後で物音がした。瞬間、弾かれたように一同は物音がした方へ目を向け、巫女さんは皆より一歩前へ出て、いつでも抜けるよう刀に手を添える。物音がしたのは広い玄関よりもう少し奥の方、真奈美が座っているくれ縁よりもう一段上がって畳敷きの居間に置かれた棚からだ。衣装棚のようで、物音はその中から聞こえた。咄嗟のことだったので、巫女さんは靴も脱がずにそのままの体勢で鋭く声を掛けた。
「誰だ。出て来なければ、斬るぞ」
警告と予備動作も兼ねて鯉口を切る彼女を制止するように、棚の中から焦ったような、それでいて少しか細い少女の声がした。
「ま、待ってくださいっ。わたっ……私、私も迷い込んじゃったんですっ」
怯えたような言葉が終わると、衣装棚はゆっくりと遠慮がちに開き、中から小さな少女が顔を覗かせた。涼佑達より随分幼い少女のようで、長い黒髪を三つ編みにしている。巫女さんに脅されたのが怖いのか、不安げな顔でこちらを覗くように見つめていた。
相手が幼い少女だと分かると、絢が巫女さんに「巫女さん、刀しまって!」と訴える。絢の言葉は聞こえている筈だが、一向に彼女は刀から手を放す素振りは無い。見兼ねた絢が彼女と少女の間に入り、少女を守るように巫女さんと対面した。
「相手はこんな小さい子なんだよ!? 斬る必要なんて無い!」
「退け、絢。それを判断するのはお前達じゃない」
「巫女さん、オレからもお願い。その子は無関係……でも無さそうだけど、一回話聞こう」
もし、少女が何らかの怪異だとしたら、前回の鹿島さんのように凶暴性のあるものではないと涼佑は判断した。鹿島さんのような者であれば、巫女さんを見たらすぐにでも襲いかかって来るだろう。彼がそう説得すると、逡巡した巫女さんは漸く少し警戒を解き、刀から手を放した。チン、と刀身を戻した彼女は絢と少女から少し離れ、壁際まで下がる。
「何か妙な兆候・動きがあれば、即斬るからな」
巫女さんには涼佑との契約上、彼と彼の友人達を守り、無事に帰すという責任がある。その契約を果たそうとしてくれたのだろうと思った涼佑は、こちらの言葉を聞き入れてくれた彼女に「ありがとう、巫女さん」と礼を言った。先程まで張り詰めた緊張の中にいたせいか、空気がいくらか緩むと、直樹がひそひそと涼佑に耳打ちする。
「すげぇじゃん、涼佑。巫女さんのこと飼い慣らしてる感じ?」
「怒られるぞ」
「そこ、聞こえてるぞ」
「はいっ、すいませんっ!」
悟られないよう小声で話していた直樹と涼佑だったが、狭い民家の中なので、巫女さんにはしっかり聞こえていたようだ。彼女の鋭い声が飛んで来ると、直樹は叱られた犬のようにびくっと肩を震わせ、しょもしょもと萎む。何分、巫女さんは帯刀しているので、無闇に逆らったり、迂闊な発言は慎んだ方が良さそうだ。彼女に危害を加える意思は無くとも、怒らせたら怖いからだ。
巫女さんが退いてくれたと分かると、絢はほっと胸を撫で下ろし、少女の方へ向き直り、努めて優しく声を掛けた。
「もう大丈夫……って言っても、私達も迷い込んじゃっただけなんだけど。あなたも友達とかから話を聞いて来ちゃったってこと?」
「は、はい……」
「もう怖い人はいないから大丈夫」と言う絢に対して、巫女さんが不満げに唇を尖らせ、ぼそりと「誰が怖い人だ」と呟いた。少女は彼らの雰囲気にいくらか安心したのか、そっと衣装棚から出てきてぺこりとお辞儀をした。年は十歳くらいで、襟に可愛らしい花の刺繍が入っている白いブラウスに紺色のチュニックを履いている。小花柄の靴下に不安げな視線を落としている姿は女生徒達の庇護欲を掻き立てるのか、絢と友香里は小さく「かわいい」と零した。絢と友香里は単純に妹のような可愛らしい存在に、真奈美は年上という責任感から少女を安心させようとそれぞれ話し掛けてみる。
「あなた、名前は?」
「いちはし、みく……です」
「かわいい~。何歳なの?」
「十一歳、です……」
「一人で怖かったでしょ? ここに隠れてたのは偉かったね」
友香里の言葉に少女みくは噛み締めるようにきゅっと口を引き結び、その目に涙を浮かべる。彼女の予想通り、こんな小さな少女がたった一人で死の恐怖に耐えていたのは余程怖かったようで、涙声で「うん」と頷く健気な姿に心を打たれた絢は、何か無いかと自分のポケットを探る。そういえば、何故か自分達は学校の制服を着ているなと涼佑はそこで気が付いた。生憎と彼女のポケットにはハンカチ以外何も入っていなかったのか、少々残念そうな顔をしながらも、絢は取り出したクリーム色のハンカチで涙を拭ってやる。角にスマイリーマークが刺繍されたもので、彼女のお気に入りだ。
「頑張ったね、偉い偉い」
ハンカチの柔らかな感触と頭を撫でる絢の手に安心したようで、今度こそみくは嗚咽し始める。そんな彼女を絢はぎゅっと抱き締め、「怖かったね、もう大丈夫だからね」とぷるぷる震えている背中を摩った。
一頻り泣いた後、漸く落ち着いてきたみくはすっかり絢に懐いたようで、くすんくすんと未だ少し鼻を啜りながらも彼女のハンカチと手を放さない。絢も子供好きらしく、懐かれて悪い気はしないのか、どことなく嬉しそうだ。みくが泣いている間に絢が彼女をくれ縁まで連れてきて、今は絢と友香里の間にみくが座っており、友香里の左隣に真奈美という女子三人に囲まれているような状態だ。不安から解放されたせいか、もう真奈美達を警戒している様子は無い。絢と手を繋いだままのみくと目線を合わせるように屈んだ涼佑と直樹は、自己紹介し始める。
「みくちゃん……だっけ? おれは岡島直樹。そっちは新條涼佑。おれの親友で同じクラス。みくちゃんは小学……何年生?」
「十一歳ってことは五年生くらいだろ」
「へぇええ? もう幼児じゃん」
「あんた何言ってんの?」
相変わらずの直樹に最早恒例と化した絢の冷めた目を向けられる。またいつものように絢に突っかかろうとした直樹を真奈美が止め、その一連の会話を聞いたみくがくすくすとおかしそうに笑う。そんな光景を一歩引いたところで、巫女さんはただじっと見つめていた。
平時は殆ど表情が変わらない彼女にしては珍しく、本当に心の底から後悔しているようだった。暗い顔で沈んでいる真奈美に、直樹が恐る恐る「そんなにか?」と訊くと、彼女は「だって、巫女さんだよ!?」と声を荒らげる。
「彼女は普通の守護霊と違って、普段は宿主の涼佑くんにしか見えないし、聞こえないのっ! そんな彼女がここにこうして現れてるってすっごく! すっごく貴重な体験なんだからねっ!? 私、私……」
興奮のままに直樹に迫る真奈美に「お、おぅ」としか返せなくなりながら聞いていた直樹だが、その様子を見て我に返った真奈美は、恥ずかしそうに両手で自分の頬を叩くように押さえ、「見たこと無いの……」と蚊の鳴くような声で呟いた。しょもしょもと先程までの勢いを無くしてしまった真奈美は、今更込み上げてきた羞恥でいたたまれなくなったのか、そのまま玄関に座り込んでしまい、「見ないで……」と赤くなった顔を隠してしまった。そんな彼女を何とか励まそうと直樹が「いや、気にすんなよ。真奈美、こういうの好きだもんな」と声を掛けるも、萎んでしまった真奈美は微かに「ごめん」と謝るだけだ。
先程までの緊張が解け、いくらか場が和んだその時。がたり、と真奈美の背後で物音がした。瞬間、弾かれたように一同は物音がした方へ目を向け、巫女さんは皆より一歩前へ出て、いつでも抜けるよう刀に手を添える。物音がしたのは広い玄関よりもう少し奥の方、真奈美が座っているくれ縁よりもう一段上がって畳敷きの居間に置かれた棚からだ。衣装棚のようで、物音はその中から聞こえた。咄嗟のことだったので、巫女さんは靴も脱がずにそのままの体勢で鋭く声を掛けた。
「誰だ。出て来なければ、斬るぞ」
警告と予備動作も兼ねて鯉口を切る彼女を制止するように、棚の中から焦ったような、それでいて少しか細い少女の声がした。
「ま、待ってくださいっ。わたっ……私、私も迷い込んじゃったんですっ」
怯えたような言葉が終わると、衣装棚はゆっくりと遠慮がちに開き、中から小さな少女が顔を覗かせた。涼佑達より随分幼い少女のようで、長い黒髪を三つ編みにしている。巫女さんに脅されたのが怖いのか、不安げな顔でこちらを覗くように見つめていた。
相手が幼い少女だと分かると、絢が巫女さんに「巫女さん、刀しまって!」と訴える。絢の言葉は聞こえている筈だが、一向に彼女は刀から手を放す素振りは無い。見兼ねた絢が彼女と少女の間に入り、少女を守るように巫女さんと対面した。
「相手はこんな小さい子なんだよ!? 斬る必要なんて無い!」
「退け、絢。それを判断するのはお前達じゃない」
「巫女さん、オレからもお願い。その子は無関係……でも無さそうだけど、一回話聞こう」
もし、少女が何らかの怪異だとしたら、前回の鹿島さんのように凶暴性のあるものではないと涼佑は判断した。鹿島さんのような者であれば、巫女さんを見たらすぐにでも襲いかかって来るだろう。彼がそう説得すると、逡巡した巫女さんは漸く少し警戒を解き、刀から手を放した。チン、と刀身を戻した彼女は絢と少女から少し離れ、壁際まで下がる。
「何か妙な兆候・動きがあれば、即斬るからな」
巫女さんには涼佑との契約上、彼と彼の友人達を守り、無事に帰すという責任がある。その契約を果たそうとしてくれたのだろうと思った涼佑は、こちらの言葉を聞き入れてくれた彼女に「ありがとう、巫女さん」と礼を言った。先程まで張り詰めた緊張の中にいたせいか、空気がいくらか緩むと、直樹がひそひそと涼佑に耳打ちする。
「すげぇじゃん、涼佑。巫女さんのこと飼い慣らしてる感じ?」
「怒られるぞ」
「そこ、聞こえてるぞ」
「はいっ、すいませんっ!」
悟られないよう小声で話していた直樹と涼佑だったが、狭い民家の中なので、巫女さんにはしっかり聞こえていたようだ。彼女の鋭い声が飛んで来ると、直樹は叱られた犬のようにびくっと肩を震わせ、しょもしょもと萎む。何分、巫女さんは帯刀しているので、無闇に逆らったり、迂闊な発言は慎んだ方が良さそうだ。彼女に危害を加える意思は無くとも、怒らせたら怖いからだ。
巫女さんが退いてくれたと分かると、絢はほっと胸を撫で下ろし、少女の方へ向き直り、努めて優しく声を掛けた。
「もう大丈夫……って言っても、私達も迷い込んじゃっただけなんだけど。あなたも友達とかから話を聞いて来ちゃったってこと?」
「は、はい……」
「もう怖い人はいないから大丈夫」と言う絢に対して、巫女さんが不満げに唇を尖らせ、ぼそりと「誰が怖い人だ」と呟いた。少女は彼らの雰囲気にいくらか安心したのか、そっと衣装棚から出てきてぺこりとお辞儀をした。年は十歳くらいで、襟に可愛らしい花の刺繍が入っている白いブラウスに紺色のチュニックを履いている。小花柄の靴下に不安げな視線を落としている姿は女生徒達の庇護欲を掻き立てるのか、絢と友香里は小さく「かわいい」と零した。絢と友香里は単純に妹のような可愛らしい存在に、真奈美は年上という責任感から少女を安心させようとそれぞれ話し掛けてみる。
「あなた、名前は?」
「いちはし、みく……です」
「かわいい~。何歳なの?」
「十一歳、です……」
「一人で怖かったでしょ? ここに隠れてたのは偉かったね」
友香里の言葉に少女みくは噛み締めるようにきゅっと口を引き結び、その目に涙を浮かべる。彼女の予想通り、こんな小さな少女がたった一人で死の恐怖に耐えていたのは余程怖かったようで、涙声で「うん」と頷く健気な姿に心を打たれた絢は、何か無いかと自分のポケットを探る。そういえば、何故か自分達は学校の制服を着ているなと涼佑はそこで気が付いた。生憎と彼女のポケットにはハンカチ以外何も入っていなかったのか、少々残念そうな顔をしながらも、絢は取り出したクリーム色のハンカチで涙を拭ってやる。角にスマイリーマークが刺繍されたもので、彼女のお気に入りだ。
「頑張ったね、偉い偉い」
ハンカチの柔らかな感触と頭を撫でる絢の手に安心したようで、今度こそみくは嗚咽し始める。そんな彼女を絢はぎゅっと抱き締め、「怖かったね、もう大丈夫だからね」とぷるぷる震えている背中を摩った。
一頻り泣いた後、漸く落ち着いてきたみくはすっかり絢に懐いたようで、くすんくすんと未だ少し鼻を啜りながらも彼女のハンカチと手を放さない。絢も子供好きらしく、懐かれて悪い気はしないのか、どことなく嬉しそうだ。みくが泣いている間に絢が彼女をくれ縁まで連れてきて、今は絢と友香里の間にみくが座っており、友香里の左隣に真奈美という女子三人に囲まれているような状態だ。不安から解放されたせいか、もう真奈美達を警戒している様子は無い。絢と手を繋いだままのみくと目線を合わせるように屈んだ涼佑と直樹は、自己紹介し始める。
「みくちゃん……だっけ? おれは岡島直樹。そっちは新條涼佑。おれの親友で同じクラス。みくちゃんは小学……何年生?」
「十一歳ってことは五年生くらいだろ」
「へぇええ? もう幼児じゃん」
「あんた何言ってんの?」
相変わらずの直樹に最早恒例と化した絢の冷めた目を向けられる。またいつものように絢に突っかかろうとした直樹を真奈美が止め、その一連の会話を聞いたみくがくすくすとおかしそうに笑う。そんな光景を一歩引いたところで、巫女さんはただじっと見つめていた。