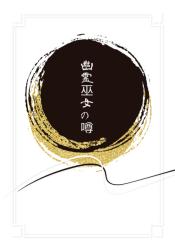「あ、そういえば」
真奈美が何か思い出したような声を上げて皆の顔を見回す。夏神がそれを察して「どうしたの?」と訊くと、彼女は少々バツが悪そうな顔でぽつりと言った。
「この話、聞いた人のところに来るんだって忘れてた」
その一言で絶望したのは、直樹だ。みるみるうちに青ざめて泣きそうな顔になる。真奈美に近寄り、彼女の肩を掴んで「なんでぇっ!?」と驚愕と怯えの声を上げた。そんな彼に対しては特に抵抗せずに真奈美はやはり無表情のままで答える。
「なんでぇっ!? なんでそういう大事なこと忘れちゃうのぉ!? 真奈美ぃっ……!」
「ん~、ごめんね?」
こてん、と目の前で小首を傾げられた直樹は、半泣きで「許すよぉ~!」と言うしかない。しかし、そんな二人の間に割って入ったのが夏神だった。直樹の手を掴んで真奈美から放させると、彼から守るように間に入る。
「止めなよ、岡島君。そんな風に他人の体に無闇に触るものじゃないよ」
「…………は?」
「大丈夫? 青谷さん」
「え? うん」
「別に真奈美は嫌がってねぇし、いいだろ。なぁ?」
直樹の言葉に真奈美は特に気分を害した様子も無く、頷く。しかし、それでも夏神は渋い顔で首を左右に振った。
「青谷さんが嫌がってないからって、女性の体に無闇に触れるのはいけないと思うんだ。友達だからって、ちょっと気安過ぎるんじゃないかな」
「は、はあ? なんでお前にそんなこと言われなくちゃいけないんだよ!?」
「友達なのだから、親交を深める目的として少々のスキンシップは仕方ない」と主張する直樹に対して、夏神は「たとえ友達でも異性の体に触れたりするのはよろしくない。そういうことが苦手な子もいる」と注意する夏神。傍から聞いている涼佑はどちらの意見も分かるし、共感できるが、直樹ほど熱くなる理由も無いので、事の成り行きを傍観することに決めた。あまり第三者が間に入る必要も無いと判断したせいもある。そのまま傍観を続けていると、理性的な夏神の言い様に怒りを誘われたのか、直樹が食ってかかる。
「なんだよ、ちょっと女子にモテるからって調子に乗りやがって! これだから甘やかされてるお坊ちゃんは困るよなぁ!」
「――誰がっ……!!」
その言葉の何が彼の怒りに触れたのかは涼佑達には分からない。けれど、明らかに夏神の表情が変わり、冷ややかな目つきになって直樹の胸倉を掴んだ。いつも爽やか優等生な彼にしては乱暴な行動に、それまで止まることを知らなかった直樹の口も閉ざされる。殴られるのかと直樹が無意識に身を固くするも、夏神ははっと我に返って直樹のシャツを放した。
「……ごめん」
しおらしくなった夏神に一瞬怒りが萎えた様子の直樹だったが、それまで味わった悔しさからだろうか、尚も食い下がって喧嘩を売る。
「いいよな、イケメンは。そうやってしおらしくしてりゃあ、周りから持て囃されるんだからさ」
「ちょっと直樹! あんた、いい加減にしなさいよっ!」
「絢は黙ってろよ。よし、じゃあさ、『鹿島さん』が話聞いた奴らのとこに来るってんなら、それはおれらも例外じゃない訳じゃん? だったら、どっちが先に遭遇するか勝負しようぜ。んで、退治できた方の勝ちな!」
「は? あんた、何言ってんの?」
「何を言ってるんだ。付き合い切れないね」
心底困り果てたと言いたげな夏神に、直樹はびしっと彼を指してもう一度荒唐無稽な宣言をする。
「いいか? 夏神。これは男同士の勝負だ。どっちが先に『鹿島さん』を見付けて退治できるか。おれが勝ったら、もうおれと真奈美のことでいちいち文句付けてくんなよ!」
「文句じゃないし、どうして僕が君の勝負なんかに付き合わなきゃいけないのかな。しかも、僕に何のメリットも無いじゃないか」
気分を害した夏神は呆れた溜息を吐いて、手早く広げた昼食を再びコンビニ袋に入れてその場から立ち去ろうとする。その背中に直樹は尚も挑発の言葉を投げた。
「おっ、逃げんのかっ? おいおい、意気地無しかよ。流石は八坂神社のお坊ちゃん! 『僕ぅ、そんな怖いことできませーん!』ってか?」
おちょくる調子で挑発する直樹を、こちらへ振り返った夏神は今度こそ冷酷な目で睨み付けてきた。冷え切ったその表情に、その場にいた誰もが息を呑む。今度こそ殴られるかもしれないと思った直樹だったが、彼の意に反して夏神はまた前を向き直って言った。
「そんなに勝負したいんなら、良いよ。僕も男だからね。そこまで言われて退く訳にはいかないから、受けるよ。その勝負」
予想外の返答に提案した本人の直樹ですら驚く。そんな一同に構わず、夏神は続けた。
「但し、僕が勝ったら――僕の言うこと、何でも一つ聞くっていうのはどう?」
感情の読めない、無に近い表情でそんなことを言い出す夏神。何を考えているのか分からないが、それでも直樹は退かなかった。「ああ、いいぞ」と彼が勝手に許可を出すと、夏神は「約束だからね」と言い残して校舎へ戻っていった。
『鹿島さん』を退治した方が勝負に勝つ。こんな勝手なことを言い出した直樹はこの時、涼佑と巫女さんに責められるのかもしれないとは微塵も頭に無かった。だから、昼休みが終わり、段々冷静になってきた彼の頭にある恐ろしい考えが浮かんでくるのは、時間の問題だったのだ。
放課後、自分の机に突っ伏したまま「無理」と呟く直樹を涼佑と巫女さんは心底呆れた表情で見下した。
「なんだよ、今更」
「無理ぃ……っ! よく考えたら、おれ、無理じゃんっ! 『鹿島さん』なんかに会ったら、死ぬぅ!」
「死ね」
涼佑の傍らにいた巫女さんが直樹に直接守護霊らしかぬことを言うが、もちろん彼には見えていないし、聞こえていない。どうせこんなことだろうと思っていた涼佑は、その頭にチョップを入れる。
「いてっ」
「しょうがないから、協力してやる」
その言葉に突っ伏していた顔を上げてぱあっと表情を明るくさせる直樹だったが、「但し、終わったら何か奢れよ」の一言でまた撃沈する。涼佑としては勝手に勝負に巻き込まれたという前提があるので、このくらいは当然だと思っていたので、直樹の反応に少々怒りすら湧いてくるのだった。
「なんでぇ……涼ちゃん、なんでぇ……」
「当たり前だろ、アホ。退治するって、自分で出来もしないことを勝負にするんじゃねぇよ」
「ぐぐぐぅ……ド正論過ぎてぐうの音しか出ない」
「まぁ、今回のこのバカの勝負は使える。涼佑、一応後で真奈美にもう少し詳しい話を聞きに行ってくれ。もう少し情報が欲しい」
「使える、って?」
「後で説明してやる」
今回の直樹の言動には心底呆れ返って深い溜息を吐く涼佑と巫女さんだったが、かと言って見捨てる訳にもいかない。どちらにせよ、巫女さんは『鹿島さん』に何か用があるらしいので、涼佑は手早く帰り支度を済ませ、直樹を伴って隣のクラスへ急いだ。
隣のクラスへ顔を出すと、真奈美達は彼女の席周辺に固まっていて、涼佑達を待っていたようだった。二人が現れると、真奈美は分かっていたかのように近付き、涼佑の手を取る。
「へ? え、真奈美?」
「『鹿島さん』について、知りたいんでしょう? ここじゃ上手く説明できないから私の家に来て」
それだけ言うと、ぐいぐい引っ張って階下へ行こうとする真奈美に連れられて、いつもの面子は校舎を出た。真奈美の誘い方に涼佑の隣にいた直樹は、何故かほんのり頬を染めて口元に手を当て、ドキドキする胸を押さえながら付いて来た様が気色悪かったので、涼佑と巫女さんの中でやたら印象に残ることとなった。
真奈美が何か思い出したような声を上げて皆の顔を見回す。夏神がそれを察して「どうしたの?」と訊くと、彼女は少々バツが悪そうな顔でぽつりと言った。
「この話、聞いた人のところに来るんだって忘れてた」
その一言で絶望したのは、直樹だ。みるみるうちに青ざめて泣きそうな顔になる。真奈美に近寄り、彼女の肩を掴んで「なんでぇっ!?」と驚愕と怯えの声を上げた。そんな彼に対しては特に抵抗せずに真奈美はやはり無表情のままで答える。
「なんでぇっ!? なんでそういう大事なこと忘れちゃうのぉ!? 真奈美ぃっ……!」
「ん~、ごめんね?」
こてん、と目の前で小首を傾げられた直樹は、半泣きで「許すよぉ~!」と言うしかない。しかし、そんな二人の間に割って入ったのが夏神だった。直樹の手を掴んで真奈美から放させると、彼から守るように間に入る。
「止めなよ、岡島君。そんな風に他人の体に無闇に触るものじゃないよ」
「…………は?」
「大丈夫? 青谷さん」
「え? うん」
「別に真奈美は嫌がってねぇし、いいだろ。なぁ?」
直樹の言葉に真奈美は特に気分を害した様子も無く、頷く。しかし、それでも夏神は渋い顔で首を左右に振った。
「青谷さんが嫌がってないからって、女性の体に無闇に触れるのはいけないと思うんだ。友達だからって、ちょっと気安過ぎるんじゃないかな」
「は、はあ? なんでお前にそんなこと言われなくちゃいけないんだよ!?」
「友達なのだから、親交を深める目的として少々のスキンシップは仕方ない」と主張する直樹に対して、夏神は「たとえ友達でも異性の体に触れたりするのはよろしくない。そういうことが苦手な子もいる」と注意する夏神。傍から聞いている涼佑はどちらの意見も分かるし、共感できるが、直樹ほど熱くなる理由も無いので、事の成り行きを傍観することに決めた。あまり第三者が間に入る必要も無いと判断したせいもある。そのまま傍観を続けていると、理性的な夏神の言い様に怒りを誘われたのか、直樹が食ってかかる。
「なんだよ、ちょっと女子にモテるからって調子に乗りやがって! これだから甘やかされてるお坊ちゃんは困るよなぁ!」
「――誰がっ……!!」
その言葉の何が彼の怒りに触れたのかは涼佑達には分からない。けれど、明らかに夏神の表情が変わり、冷ややかな目つきになって直樹の胸倉を掴んだ。いつも爽やか優等生な彼にしては乱暴な行動に、それまで止まることを知らなかった直樹の口も閉ざされる。殴られるのかと直樹が無意識に身を固くするも、夏神ははっと我に返って直樹のシャツを放した。
「……ごめん」
しおらしくなった夏神に一瞬怒りが萎えた様子の直樹だったが、それまで味わった悔しさからだろうか、尚も食い下がって喧嘩を売る。
「いいよな、イケメンは。そうやってしおらしくしてりゃあ、周りから持て囃されるんだからさ」
「ちょっと直樹! あんた、いい加減にしなさいよっ!」
「絢は黙ってろよ。よし、じゃあさ、『鹿島さん』が話聞いた奴らのとこに来るってんなら、それはおれらも例外じゃない訳じゃん? だったら、どっちが先に遭遇するか勝負しようぜ。んで、退治できた方の勝ちな!」
「は? あんた、何言ってんの?」
「何を言ってるんだ。付き合い切れないね」
心底困り果てたと言いたげな夏神に、直樹はびしっと彼を指してもう一度荒唐無稽な宣言をする。
「いいか? 夏神。これは男同士の勝負だ。どっちが先に『鹿島さん』を見付けて退治できるか。おれが勝ったら、もうおれと真奈美のことでいちいち文句付けてくんなよ!」
「文句じゃないし、どうして僕が君の勝負なんかに付き合わなきゃいけないのかな。しかも、僕に何のメリットも無いじゃないか」
気分を害した夏神は呆れた溜息を吐いて、手早く広げた昼食を再びコンビニ袋に入れてその場から立ち去ろうとする。その背中に直樹は尚も挑発の言葉を投げた。
「おっ、逃げんのかっ? おいおい、意気地無しかよ。流石は八坂神社のお坊ちゃん! 『僕ぅ、そんな怖いことできませーん!』ってか?」
おちょくる調子で挑発する直樹を、こちらへ振り返った夏神は今度こそ冷酷な目で睨み付けてきた。冷え切ったその表情に、その場にいた誰もが息を呑む。今度こそ殴られるかもしれないと思った直樹だったが、彼の意に反して夏神はまた前を向き直って言った。
「そんなに勝負したいんなら、良いよ。僕も男だからね。そこまで言われて退く訳にはいかないから、受けるよ。その勝負」
予想外の返答に提案した本人の直樹ですら驚く。そんな一同に構わず、夏神は続けた。
「但し、僕が勝ったら――僕の言うこと、何でも一つ聞くっていうのはどう?」
感情の読めない、無に近い表情でそんなことを言い出す夏神。何を考えているのか分からないが、それでも直樹は退かなかった。「ああ、いいぞ」と彼が勝手に許可を出すと、夏神は「約束だからね」と言い残して校舎へ戻っていった。
『鹿島さん』を退治した方が勝負に勝つ。こんな勝手なことを言い出した直樹はこの時、涼佑と巫女さんに責められるのかもしれないとは微塵も頭に無かった。だから、昼休みが終わり、段々冷静になってきた彼の頭にある恐ろしい考えが浮かんでくるのは、時間の問題だったのだ。
放課後、自分の机に突っ伏したまま「無理」と呟く直樹を涼佑と巫女さんは心底呆れた表情で見下した。
「なんだよ、今更」
「無理ぃ……っ! よく考えたら、おれ、無理じゃんっ! 『鹿島さん』なんかに会ったら、死ぬぅ!」
「死ね」
涼佑の傍らにいた巫女さんが直樹に直接守護霊らしかぬことを言うが、もちろん彼には見えていないし、聞こえていない。どうせこんなことだろうと思っていた涼佑は、その頭にチョップを入れる。
「いてっ」
「しょうがないから、協力してやる」
その言葉に突っ伏していた顔を上げてぱあっと表情を明るくさせる直樹だったが、「但し、終わったら何か奢れよ」の一言でまた撃沈する。涼佑としては勝手に勝負に巻き込まれたという前提があるので、このくらいは当然だと思っていたので、直樹の反応に少々怒りすら湧いてくるのだった。
「なんでぇ……涼ちゃん、なんでぇ……」
「当たり前だろ、アホ。退治するって、自分で出来もしないことを勝負にするんじゃねぇよ」
「ぐぐぐぅ……ド正論過ぎてぐうの音しか出ない」
「まぁ、今回のこのバカの勝負は使える。涼佑、一応後で真奈美にもう少し詳しい話を聞きに行ってくれ。もう少し情報が欲しい」
「使える、って?」
「後で説明してやる」
今回の直樹の言動には心底呆れ返って深い溜息を吐く涼佑と巫女さんだったが、かと言って見捨てる訳にもいかない。どちらにせよ、巫女さんは『鹿島さん』に何か用があるらしいので、涼佑は手早く帰り支度を済ませ、直樹を伴って隣のクラスへ急いだ。
隣のクラスへ顔を出すと、真奈美達は彼女の席周辺に固まっていて、涼佑達を待っていたようだった。二人が現れると、真奈美は分かっていたかのように近付き、涼佑の手を取る。
「へ? え、真奈美?」
「『鹿島さん』について、知りたいんでしょう? ここじゃ上手く説明できないから私の家に来て」
それだけ言うと、ぐいぐい引っ張って階下へ行こうとする真奈美に連れられて、いつもの面子は校舎を出た。真奈美の誘い方に涼佑の隣にいた直樹は、何故かほんのり頬を染めて口元に手を当て、ドキドキする胸を押さえながら付いて来た様が気色悪かったので、涼佑と巫女さんの中でやたら印象に残ることとなった。