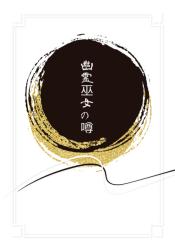閑静な夜の住宅街の中を男が一人、必死の形相で走り抜けて行く。駅からずっと走りっぱなしのせいで通勤用のスーツだというのに、全身汗まみれで髪はぐちゃぐちゃ。革靴の片方はどこかに置き去り、それでも何とか鞄だけは抱えたまま、家を目指して走っている。どうしてこんなことになってしまったのか、男は駅で見てはいけないものを見てしまったことを大いに後悔していた。
それを見付けたのは偶然だった。仕事が終わって、男は郊外にある自宅へ帰ろうと駅のホームで電車が来るのを待っていた。今日もあちこち回って何件か契約を取り、会社に帰って報告と見積りを依頼する。そんな仕事をこなし、疲れたなと自販機で買った缶コーヒー片手にホームの硬い椅子に腰掛ける。男は夕方に飲むコーヒーは微糖が好きだったが、間違えてブラックを買ってしまった。仕方ないかと缶を開けて、そのまま口に運ぶ。疲れた体を癒してくれる優しい甘さは無く、きりりとした飲み口のそれをこの時間に飲むのは、やはりあまり好きじゃない。苦味にやや顔を顰めながら、彼は何となく目の前に敷かれた線路を見ていた。向こう側のホームを見、その手前の線路を見た時、彼はおや、と思った。向こう側に敷かれた線路の上に何か落ちている。辺りは薄暗いが、ホームの天井から降り注ぐ電灯の光で駅周辺だけは明るい。しかし、落し物の全体像はよく掴めなかった。白い楕円のような形をして僅かに光を反射しているのか、所々てらてらと光っている。あれは何だろうと、彼はよく目を凝らしてみようとしたが、それより早くこちら側のホームに入ってきた電車に隠されてしまった。
目的の電車だ。缶コーヒーと鞄を持ち直した男は、目の前で開いた車両に乗り込む。そんなに混んではいないし、もしかしたらさっきの落し物が何なのか分かるかもしれない。そんな考えもあって、男は乗り込んですぐ傍にある席に座った。
まだ発車まで少し余裕がある。その間に落し物をもう一度見ようと、男はポケットからスマホを取り出しつつ、窓の向こうを見た。落し物はまだあった。先程と同じ位置、同じ向きでそこにある。電車に乗り込んだことで、先程より落し物に近付いたが、やはりそれが何なのか分からない。ただ、思ったより大きそうなことだけは分かる。それだけ分かれば十分だと元々それ程興味を惹かれていなかった男は、手元のスマホに視線を落とした。目的の駅までは三駅過ぎてからだ。それまで男はスマホを弄りつつ、缶コーヒーをちびちび飲みながら時間が過ぎるのを待った。
やがて、次に降りる駅名が聞こえてきたので、固まった姿勢を伸ばそうと、男は顔を上げた。向かいの座席に何か座っている。一瞬、男はそれが何か分からなかった。初めは精巧な人形に見えた。真っ白を通り越して青白い滑らかなプラスチックの胴体に首と手足に当たる部分は赤い切断面が覗いている、悪趣味な人形だと思った。ゆっくり周囲を見回してみる。いつの間にか殆ど客は乗っていない。後方の車両へ続くドアに程近い席で居眠りをしている老人が一人いるくらいだ。
もう一度、男は自分の向かいの座席へ視線を戻す。切断面と見られる傷口からはつう、と赤い雫が伝い、すぐ下のなだらかな双丘の間をとろりと流れていく。途端に思い出したように濃い鉄の匂いが鼻孔を掠めていった。その濡れた光の当たり方と相まって、漸くそれが首と手足の付け根から切断された女の胴体だと理解した男は言葉にならない悲鳴を上げて後退ろうとし、背後の窓ガラスに思い切り後頭部をぶつけた。その衝撃が伝わったのか、それとも偶然か。向かいの座席に鎮座していた女の胴体はぐらりとバランスを崩したかと思うと、どう、と床に倒れた。ぴっと血が床へ舞う。胴体との距離が更に縮んだことで男は益々、パニックに陥る。最早、後頭部の痛みなどすっかり忘れて男は少しでも距離を取ろうと窓沿いに手を付いたまま、抜けた腰を引きずるようにして前の車両へ近付く。視界が段々真っ赤に染まり、自分が何をしているのか、周りの状況すらも認識できなくなっていく。その感覚にまた恐怖を感じて、男は縋るように出入り口のドアにへばりついた。
すぐにドアが開き、這々の体で電車から降り、駅のホームに入ると漸く抜けた腰が持ち上がり、何とか立ち上がることができた。すぐ近くにあった自販機にまた縋るようにして寄りかかり、さっきまで自分が乗っていた電車を見て、今度こそ男は悲鳴を上げた。
這って来ている。首も無い、手足も無い女の胴体がずるり、ずるりと血の跡を残しながらゆっくりこちらに這って来ていた。男の悲鳴を聞きつけたのか、駅員が駆けつけて来たが、それどころではない。あの胴体は自分を追って来たのだと分かると、男は身を捻るようにして自販機から離れ、無意識に自宅へ逃げようと連絡通路への階段を駆け上がって行った。後に残された駅員は男の後ろ姿を見送りつつ、不思議そうな顔で首を捻っていた。
ひいひいと喉から込み上げる悲鳴を抑えることもできないまま、男は駅を出ていつもの帰り道をひた走る。目の前の横断歩道の信号が丁度、青になっていたのでそのまま突っ切り、いつも夕食を買うコンビニを通り過ぎ、暗い住宅街へ入る。
冒頭に戻り、その間にも何度か後ろを振り返って男はその度、非現実的な現実に打ちひしがれていた。付いて来ている。ずるり、ずるりとあの引きずるような、這うような不気味な音を立てて胴体はまだ男を追って来ていた。追って来ているといっても、男の背後だけではなく、ある時は行く先に、ある時はすぐ横に突然現れる。その度に男はあらん限りの声で絶叫し、夜道を駆け抜けていく。やがて、自分の部屋がある古いアパートに辿り着いた男は、無我夢中で階段を駆け上り、自分の部屋へ逃げ込んだ。靴を乱雑に脱ぎ捨て、そのまま部屋中のカーテンを閉め切り、頭から布団を被ってがたがた震えることしかできない。一瞬、自宅に帰って来たのは失敗だったかと思った彼だったが、今更遅い。もう外に出て行く勇気も度胸も無く、そのまま震えていることを選んだ。
どのくらい経っただろう。あれだけ追って来ていた不気味な音はいつの間にか聞こえてこない。それどころか、あの胴体は男を見失ってくれたのか、外からはいつもの車が通り過ぎていく音が遠くから聞こえてくるだけだ。もう大丈夫なのかと思いはする彼だが、極度の緊張と警戒心から電気を点ける訳にはいかないと、もう今日は着替えてそのまま寝ることにした。あまり物音を立てないように寝間着代わりのスウェットに着替え、ベッドに潜り込む。恐怖から眠れないだろうと思っていたが、走って疲れたのか、そのまま男はすぐ眠りに就いた。
目を開けると、そこには女が一人いた。真っ暗な空間にセーラー服姿のどう見ても成人しているであろう女性。そのあまりの突飛さに男はすぐ「あ、これ夢だ」と理解した。女は恨めしげに男を見つめていたかと思うと、音も無く近付いて耳元でこう言った。
「手を寄越せ」
「……え?」
何と言ったのか聞き取れなかった男は思わず、聞き返したが、その直後に左腕が何かに引っ張られるような感覚がしたので、そちらを見た。腕が千切れていた。無理矢理引っ張って千切られた肩口からはぼたぼたと血が滴り、吐き気がする程の鉄の匂いすら感じる。痛みは無い。痛みだけが無いのが却って不気味で、男は「なんて夢見てんだっ……!?」と自分の精神が心配になった。いや、それより千切られた腕はどこへ行ったと思い、男は女の方へ視線を戻す。男の腕は女の手に大事そうに握られていた。まるで子供の頃に無くしたぬいぐるみを取られまいとするかのようにぎゅっと抱き締めている。そして、女は自分の腕をもう片方の手で掴んだかと思うと、当然のように引き抜いた。血は一切出ない。引き抜かれたそこに男の腕をくっつけようと宛がって押し込まれる。ぐちゃりと鈍く嫌な音がした。女が手を放すと、男の腕だった物がそこに不格好に付いている。
「おい、何してんだよ……」
左肩から夥しい量の血を流し、呆然としている男を放って初めはきゃっきゃと子供のように喜んでいた女だったが、次第に笑い声は消え、無表情になっていく。やがて、怒りを露わにすると、途端に女は甲高い悲鳴なのか奇声なのか、分からない声を上げ、「違う! 違う! 違う!」と半狂乱になって頭を振り乱した。そして、何も言葉らしい言葉を発さず今度は男の右腕を?ぐ。右腕も左腕と同じように付け替えた女だったが、何が気に入らないのか癇癪を起こした子供のように悲鳴を上げてまたそれも放り出す。間髪入れず、女は男にもう一度迫った。
「足を寄越せ」
男が何か言おうと口を開くが、それより先に女は男の足に噛み付き、あっという間に両足を?いだ。どさっと体が地面だろうか床だろうか、それに相当する場所に倒れて初めて男は両足を取られたと分かった。
「なん、なんで……?」
「違う! 違う! 違う! 違う! 違う! 違う! 違う! 違ぅうううっ!」
血溜まりの中に沈む男を、女は付け替えたばかりの歪な両足でしゃがみ込み、その顔を覗き込む。そして、これが最後と言うように付け替えた歪な手で男の髪の毛を鷲掴んで持ち上げ、言った。
「この話、誰から聞いた?」
「なん、で……なんで……」
男は自分の両手両足が失われてしまったことに心を囚われ、質問に答えない。元より彼の答えなんて聞く気が無いのか、女はその頭に両手を添え、喜色満面で思い切り引っ張った。
カーテンの隙間から朝日が差し込む。サッサとした陽光は部屋の様相を薄闇の中に浮かび上がらせる。もう男にとっての脅威は何も無い。彼の恐怖心の代わりに部屋の中に残されていたのは、血塗れのベッドと布団の中で首と四肢を引き抜かれ、追ってきていたあの胴体と同じになった男の死体だけが静かに横たわっていた。
それを見付けたのは偶然だった。仕事が終わって、男は郊外にある自宅へ帰ろうと駅のホームで電車が来るのを待っていた。今日もあちこち回って何件か契約を取り、会社に帰って報告と見積りを依頼する。そんな仕事をこなし、疲れたなと自販機で買った缶コーヒー片手にホームの硬い椅子に腰掛ける。男は夕方に飲むコーヒーは微糖が好きだったが、間違えてブラックを買ってしまった。仕方ないかと缶を開けて、そのまま口に運ぶ。疲れた体を癒してくれる優しい甘さは無く、きりりとした飲み口のそれをこの時間に飲むのは、やはりあまり好きじゃない。苦味にやや顔を顰めながら、彼は何となく目の前に敷かれた線路を見ていた。向こう側のホームを見、その手前の線路を見た時、彼はおや、と思った。向こう側に敷かれた線路の上に何か落ちている。辺りは薄暗いが、ホームの天井から降り注ぐ電灯の光で駅周辺だけは明るい。しかし、落し物の全体像はよく掴めなかった。白い楕円のような形をして僅かに光を反射しているのか、所々てらてらと光っている。あれは何だろうと、彼はよく目を凝らしてみようとしたが、それより早くこちら側のホームに入ってきた電車に隠されてしまった。
目的の電車だ。缶コーヒーと鞄を持ち直した男は、目の前で開いた車両に乗り込む。そんなに混んではいないし、もしかしたらさっきの落し物が何なのか分かるかもしれない。そんな考えもあって、男は乗り込んですぐ傍にある席に座った。
まだ発車まで少し余裕がある。その間に落し物をもう一度見ようと、男はポケットからスマホを取り出しつつ、窓の向こうを見た。落し物はまだあった。先程と同じ位置、同じ向きでそこにある。電車に乗り込んだことで、先程より落し物に近付いたが、やはりそれが何なのか分からない。ただ、思ったより大きそうなことだけは分かる。それだけ分かれば十分だと元々それ程興味を惹かれていなかった男は、手元のスマホに視線を落とした。目的の駅までは三駅過ぎてからだ。それまで男はスマホを弄りつつ、缶コーヒーをちびちび飲みながら時間が過ぎるのを待った。
やがて、次に降りる駅名が聞こえてきたので、固まった姿勢を伸ばそうと、男は顔を上げた。向かいの座席に何か座っている。一瞬、男はそれが何か分からなかった。初めは精巧な人形に見えた。真っ白を通り越して青白い滑らかなプラスチックの胴体に首と手足に当たる部分は赤い切断面が覗いている、悪趣味な人形だと思った。ゆっくり周囲を見回してみる。いつの間にか殆ど客は乗っていない。後方の車両へ続くドアに程近い席で居眠りをしている老人が一人いるくらいだ。
もう一度、男は自分の向かいの座席へ視線を戻す。切断面と見られる傷口からはつう、と赤い雫が伝い、すぐ下のなだらかな双丘の間をとろりと流れていく。途端に思い出したように濃い鉄の匂いが鼻孔を掠めていった。その濡れた光の当たり方と相まって、漸くそれが首と手足の付け根から切断された女の胴体だと理解した男は言葉にならない悲鳴を上げて後退ろうとし、背後の窓ガラスに思い切り後頭部をぶつけた。その衝撃が伝わったのか、それとも偶然か。向かいの座席に鎮座していた女の胴体はぐらりとバランスを崩したかと思うと、どう、と床に倒れた。ぴっと血が床へ舞う。胴体との距離が更に縮んだことで男は益々、パニックに陥る。最早、後頭部の痛みなどすっかり忘れて男は少しでも距離を取ろうと窓沿いに手を付いたまま、抜けた腰を引きずるようにして前の車両へ近付く。視界が段々真っ赤に染まり、自分が何をしているのか、周りの状況すらも認識できなくなっていく。その感覚にまた恐怖を感じて、男は縋るように出入り口のドアにへばりついた。
すぐにドアが開き、這々の体で電車から降り、駅のホームに入ると漸く抜けた腰が持ち上がり、何とか立ち上がることができた。すぐ近くにあった自販機にまた縋るようにして寄りかかり、さっきまで自分が乗っていた電車を見て、今度こそ男は悲鳴を上げた。
這って来ている。首も無い、手足も無い女の胴体がずるり、ずるりと血の跡を残しながらゆっくりこちらに這って来ていた。男の悲鳴を聞きつけたのか、駅員が駆けつけて来たが、それどころではない。あの胴体は自分を追って来たのだと分かると、男は身を捻るようにして自販機から離れ、無意識に自宅へ逃げようと連絡通路への階段を駆け上がって行った。後に残された駅員は男の後ろ姿を見送りつつ、不思議そうな顔で首を捻っていた。
ひいひいと喉から込み上げる悲鳴を抑えることもできないまま、男は駅を出ていつもの帰り道をひた走る。目の前の横断歩道の信号が丁度、青になっていたのでそのまま突っ切り、いつも夕食を買うコンビニを通り過ぎ、暗い住宅街へ入る。
冒頭に戻り、その間にも何度か後ろを振り返って男はその度、非現実的な現実に打ちひしがれていた。付いて来ている。ずるり、ずるりとあの引きずるような、這うような不気味な音を立てて胴体はまだ男を追って来ていた。追って来ているといっても、男の背後だけではなく、ある時は行く先に、ある時はすぐ横に突然現れる。その度に男はあらん限りの声で絶叫し、夜道を駆け抜けていく。やがて、自分の部屋がある古いアパートに辿り着いた男は、無我夢中で階段を駆け上り、自分の部屋へ逃げ込んだ。靴を乱雑に脱ぎ捨て、そのまま部屋中のカーテンを閉め切り、頭から布団を被ってがたがた震えることしかできない。一瞬、自宅に帰って来たのは失敗だったかと思った彼だったが、今更遅い。もう外に出て行く勇気も度胸も無く、そのまま震えていることを選んだ。
どのくらい経っただろう。あれだけ追って来ていた不気味な音はいつの間にか聞こえてこない。それどころか、あの胴体は男を見失ってくれたのか、外からはいつもの車が通り過ぎていく音が遠くから聞こえてくるだけだ。もう大丈夫なのかと思いはする彼だが、極度の緊張と警戒心から電気を点ける訳にはいかないと、もう今日は着替えてそのまま寝ることにした。あまり物音を立てないように寝間着代わりのスウェットに着替え、ベッドに潜り込む。恐怖から眠れないだろうと思っていたが、走って疲れたのか、そのまま男はすぐ眠りに就いた。
目を開けると、そこには女が一人いた。真っ暗な空間にセーラー服姿のどう見ても成人しているであろう女性。そのあまりの突飛さに男はすぐ「あ、これ夢だ」と理解した。女は恨めしげに男を見つめていたかと思うと、音も無く近付いて耳元でこう言った。
「手を寄越せ」
「……え?」
何と言ったのか聞き取れなかった男は思わず、聞き返したが、その直後に左腕が何かに引っ張られるような感覚がしたので、そちらを見た。腕が千切れていた。無理矢理引っ張って千切られた肩口からはぼたぼたと血が滴り、吐き気がする程の鉄の匂いすら感じる。痛みは無い。痛みだけが無いのが却って不気味で、男は「なんて夢見てんだっ……!?」と自分の精神が心配になった。いや、それより千切られた腕はどこへ行ったと思い、男は女の方へ視線を戻す。男の腕は女の手に大事そうに握られていた。まるで子供の頃に無くしたぬいぐるみを取られまいとするかのようにぎゅっと抱き締めている。そして、女は自分の腕をもう片方の手で掴んだかと思うと、当然のように引き抜いた。血は一切出ない。引き抜かれたそこに男の腕をくっつけようと宛がって押し込まれる。ぐちゃりと鈍く嫌な音がした。女が手を放すと、男の腕だった物がそこに不格好に付いている。
「おい、何してんだよ……」
左肩から夥しい量の血を流し、呆然としている男を放って初めはきゃっきゃと子供のように喜んでいた女だったが、次第に笑い声は消え、無表情になっていく。やがて、怒りを露わにすると、途端に女は甲高い悲鳴なのか奇声なのか、分からない声を上げ、「違う! 違う! 違う!」と半狂乱になって頭を振り乱した。そして、何も言葉らしい言葉を発さず今度は男の右腕を?ぐ。右腕も左腕と同じように付け替えた女だったが、何が気に入らないのか癇癪を起こした子供のように悲鳴を上げてまたそれも放り出す。間髪入れず、女は男にもう一度迫った。
「足を寄越せ」
男が何か言おうと口を開くが、それより先に女は男の足に噛み付き、あっという間に両足を?いだ。どさっと体が地面だろうか床だろうか、それに相当する場所に倒れて初めて男は両足を取られたと分かった。
「なん、なんで……?」
「違う! 違う! 違う! 違う! 違う! 違う! 違う! 違ぅうううっ!」
血溜まりの中に沈む男を、女は付け替えたばかりの歪な両足でしゃがみ込み、その顔を覗き込む。そして、これが最後と言うように付け替えた歪な手で男の髪の毛を鷲掴んで持ち上げ、言った。
「この話、誰から聞いた?」
「なん、で……なんで……」
男は自分の両手両足が失われてしまったことに心を囚われ、質問に答えない。元より彼の答えなんて聞く気が無いのか、女はその頭に両手を添え、喜色満面で思い切り引っ張った。
カーテンの隙間から朝日が差し込む。サッサとした陽光は部屋の様相を薄闇の中に浮かび上がらせる。もう男にとっての脅威は何も無い。彼の恐怖心の代わりに部屋の中に残されていたのは、血塗れのベッドと布団の中で首と四肢を引き抜かれ、追ってきていたあの胴体と同じになった男の死体だけが静かに横たわっていた。