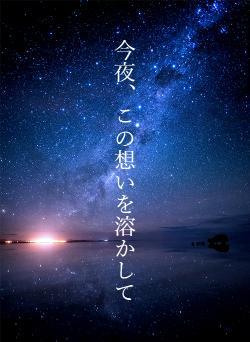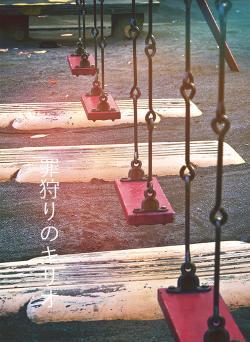大学へは奨学生として入学した。
僕が入学した大学は、広大な敷地に周りの景観を損なわないように、上手く馴染んでいた。さすが、美術学部が併設されている大学だと感じた。絵画棟は、正門から五つの建物を越えた場所に、悠然とそびえ立っている。絵画棟までの時間は空を見つめながら歩くのが日課になっている。
空は不思議な存在だ。場所によって様々な形に姿を変える。都会では定規で引いたような線で縁どられ、田舎ではパノラマのように雄大な広がりを見せる。時には心そのものを表すときだってある。
身近にあり、いつも見守ってくれているような存在でもある。
そう、両親のようだ。
でも、僕は父の温もりを知らない。
大学に入学してから、明らかに絵に対する価値観が変わってきた。芸術とは一種の自己満足の極みかもしれないが、上手く描きたいというよりも、上手く人に伝えたいという気持ちが芽生えてきた。
そう感じたのは、同じ学部の彼女の絵を観てからだ。
繊細な筆運びながら、どこか力強くて、でも一瞬で消え去りそうな儚さも持ち合わせている。
一目で虜になった。こんな絵を描ける人物に、興味を抱かない理由はなかった。
それが僕と彼女の始まりだった。
僕が入学した大学は、広大な敷地に周りの景観を損なわないように、上手く馴染んでいた。さすが、美術学部が併設されている大学だと感じた。絵画棟は、正門から五つの建物を越えた場所に、悠然とそびえ立っている。絵画棟までの時間は空を見つめながら歩くのが日課になっている。
空は不思議な存在だ。場所によって様々な形に姿を変える。都会では定規で引いたような線で縁どられ、田舎ではパノラマのように雄大な広がりを見せる。時には心そのものを表すときだってある。
身近にあり、いつも見守ってくれているような存在でもある。
そう、両親のようだ。
でも、僕は父の温もりを知らない。
大学に入学してから、明らかに絵に対する価値観が変わってきた。芸術とは一種の自己満足の極みかもしれないが、上手く描きたいというよりも、上手く人に伝えたいという気持ちが芽生えてきた。
そう感じたのは、同じ学部の彼女の絵を観てからだ。
繊細な筆運びながら、どこか力強くて、でも一瞬で消え去りそうな儚さも持ち合わせている。
一目で虜になった。こんな絵を描ける人物に、興味を抱かない理由はなかった。
それが僕と彼女の始まりだった。