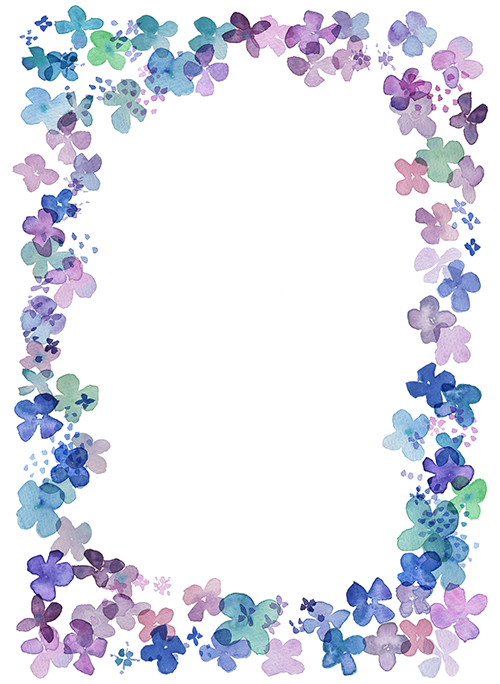じとりと背中が濡れる。暑さのせいではない、嫌な生ぬるい汗が肌を伝り、べったりと髪を頬に絡みつけた。
嫌だ。
機械音が鳴って、今にも壊れそうな古びた電車のドアが半端に閉められる。濁ったガラス越しに青年は手を振った。だから私も笑いながら振り返す、目尻を濡らす涙がばれてしまわないように目を細めた。
電車は進む。
キイキイと不安定に揺れながら加速していく。
その時、辺りに突然破裂音が響いた。驚いて線路の向こうに目をやると電車はもう宙に浮いていた。レールから外れた電車はそのまま崖を直進して空へと進んでいく。
あまりにも突然のことであった。
崖の下の海と空、どちらの青にも吸い込まれそうなその車体は上昇することなく、静かに落下していった。
ビー玉の軽い音が手元で鳴った。共鳴するように私たちを囲む森から蝉が体を震わせた。苔の生い茂る坂道を上れば、私たちはもうお別れだ。小さな駅から君は大都会へ一歩先に進むのだ。それは嬉しく、少し寂しいことでもあった。
「次は半年後?」
振り返りそう尋ねる。大型のキャリーケースを苦も無く片手で引き上げる彼は「そうだな」と頷いた。思えば十八年間いつだって彼と一緒にいた気がする。同じ町で育ち、同じ小学校に行って。裏山へ探検もしたし、時には港まで行って真冬の海に飛び込んだりもした。右手で音を立てるガラス瓶も、底を透かして見える世界は青色に染まって綺麗だった。私はラムネ瓶越しに見える君の笑顔が一番好きだった。
「意外とすぐじゃん。あーあ、なんか寂しくなって損したわ~」
「寂しさを無駄遣いに言うんじゃねぇよ」
そんな言葉、虚勢に決まってるだろう。本当は置いて行かれるのが堪らなく怖いのだ。
あぁ、もう駅が見えてきた。寂れた無人駅、それが私たちの分岐点だった。その場所に近づいていくのが怖い。大学進学を決めた君と、地元の町役場で就職を決めた私。今までずっと一緒にいたからと言って心も体も一緒な訳がないのに、もし君がこの電車に乗ってしまえばもう二度と会えないんじゃないか。言葉では形容し難いそんな不安を抱いているのは私だけだろうか。
「うっし、着いたな」
「疲れた~、体の老いを感じる~」
「小学生の頃はここまで走って登るの、よく競争したよな」
「あの時は私が勝ってたよ!」
「今競争したらお前途中で倒れそうだけどな」
「うるさい!」
駅のホームにある一つしかないベンチに腰掛ける。隣の彼は笑いながらも瞳は遠くの電車の来る方に向いていた。
もうお別れなんだ。本当に君は東京に行ってしまうんだ。
認めたくない醜い感情がこの期に及んで湧き上がる。駄目だと思い深呼吸すると、木造建築のかび臭い匂いが肺を満たす。その瞬間ジジジッと擦り切れたカセットテープのように何かの映像が脳内で再生される。
途切れ途切れで、朧気で、ほとんど分からない。しかし、満たした息を吐きだすと同時に電車に乗り込む君の姿が見えたような気がした。
「これは何……?」
「ん?どうした?」
私がぼそりと独り言を呟くとボストンバッグ一つ分隣にはまだ電車に乗り込んでいない君が心配そうにこちらを覗き込んでいた。私は彼の顔を見た途端、何故か目頭が焦げるほど熱くなる。理性では制御できない「何か」が確実に働いていた。きっと何かの記憶ときっと混ざりあっているのだろう。しかし、胸を満たす嫌な予感は何度息を吐きだしたって、わだかまって、こびりついて、無くなることはなかった。
暫くすると「まもなく、電車が参ります。ご注意ください」と掠れたアナウンスが鳴り響いた。眉毛を震わせた君は立ち上がると再びボストンバックを肩に掛け、重そうなキャリーケースを引きずると黄色い線の一歩外側に立つ。
「じゃあ、またね」
私が小さく手を振る。うまく笑えている自信がなかった。本音を言えば私はずっと君と一緒にいたかった。これからも、この辺鄙で小さな町に君と二人で思い出を紡ぎあげて、いつかは胸に秘める想いを伝えられたらいいな。なんて安易で幼稚で、けれどきっとどんなに道を踏み外したって不幸じゃないと言い切れる未来が欲しかった。
けれど、だからといって二手に分かれた私たちの未来を潰したいわけじゃない。
君には幸せになってもらいたい。
だから精一杯笑うのだ。また会える日まで、私のことを忘れられないくらい強く強く記憶に焼き付けてやるのだ。
「……また」
そんな私を見かねてか君も笑う。こんなにも顔をくしゃくしゃにさせて笑う青年の姿を見たのはいつぶりだろう。懐かしい感情が込み上げて溢れて、止まらなかった。
あぁ、愛おしいなぁ。
自分を雁字搦めにしていた気持ちが腑に落ちたと同時に右手のガラス瓶がまたカランと音を立てる。
やっぱり私は君のことが好きだ。
彼の体が電車に吸い込まれていく。機械音がして、歪んだ電車のドアが閉じられた。
その時、再びカセットテープが再生される。今度は進みゆく車体のガラスから手を振る君の姿が次の瞬間空中に放り出され、落下していく景色だった。段々と息が浅くなっていくのが自分でも分かる。思い出した、これは今朝見た夢だ。
きっとこれから起こることを表した夢だったのだ。
プーっと音をたて、車体は加速していく。笑顔で汚れた窓越しに手を振る君に私は絶叫した。
「嫌だいやだいやだ」
神様
どうか私を一人にしないでください。君だけ死んで私だけ取り残されたら私はどうやって息をすればいいのか分かりません。
君が助からない未来なんて嫌だ。
けれど、痛くて苦しくて孤独なまま君が死んでしまうなんて、もっとずっと嫌だ。
風鈴と手から滑り落ちたガラス瓶が砕けた音が合図だった。
私は後先考えずに走り出した。十メートル先を走る電車に追いつけるように必死に手を、足を振った。千切れてしまうんじゃないかと思うくらいにひらすら走って、絡まる足を前に進める。
ふと顔をあげると、君は驚いたようにこちらを凝視していた。何か怒鳴りながら窓を叩く姿も見える。
ごめんね、勝手なことして。
けど、やっぱり許せなかったよ。
私が息を吸った刹那、電車はスピードを緩めないまま残酷な音を残し崖から飛び出した。
不安定だったドアが外れ、君の身は宙に投げ出される。
一面青の世界、淡い白のシャツだけが浮かびあがっていた。
私はそれめがけて崖から飛び出す。それは即ち死を意味していた。覚悟はできていたもののやはり怖くて思わずぎゅっと目を固く閉じてしまう。
瞬間、伸ばした腕は何か柔らかいものによって引っ張られた。
「……っおい!!」
叫ぶような声で私は再びこわごわと瞼を持ち上げる。青の世界に浮かんでいたのは綿雲と、涙ぐむ君だった。
君は怒ったような困ったようなどうしたらいいのか分からないというように百面相をする。
落下する体は下から殴られたように痛い。けれど君の顔を見たら安堵してしまった自分もいた。
頬に手が添えられる。
覚悟を決めたような瞳はもう先ほどとは違い、穏やかだった。
「わらって」
君の口がそう動く。二人分の空気抵抗は相当なものらしい。風の切る音で声なんか聞こえやしない。けれど確かに君はそう言った。私は言葉通り笑って、君の手を引く。柔らかい視線が自然と絡んだ。どちらがともなく自然と唇を寄せ合う。
十八年間ずっと待ち焦がれていた君とのキスだった。
互いに覚悟はできていた。君がいれば何も怖いものなんてなかった。思い返せば一人ではきっと探検できない山も海も町も冒険しようと思えたのは、どんなときだって優しく手を引いてくれたのは、君だった。
ねぇ
また生まれ変わって、どこかで出会えたら私の名前を呼んでほしい。
それから恋に落ちて、また夏の空の青い日、キスをしよう。
何も覚えていなくたって私たちはまたきっと出会える。またきっと好きになってしまう。
だから大丈夫
「好きだよ」
零れた言葉が最後、白い飛沫をあげた水面と沈みゆく体。君の左手のラムネの瓶が光を反射して煌めいた。ガラスの破片越しに見えた最後の景色は愛おしい君だった。
嫌だ。
機械音が鳴って、今にも壊れそうな古びた電車のドアが半端に閉められる。濁ったガラス越しに青年は手を振った。だから私も笑いながら振り返す、目尻を濡らす涙がばれてしまわないように目を細めた。
電車は進む。
キイキイと不安定に揺れながら加速していく。
その時、辺りに突然破裂音が響いた。驚いて線路の向こうに目をやると電車はもう宙に浮いていた。レールから外れた電車はそのまま崖を直進して空へと進んでいく。
あまりにも突然のことであった。
崖の下の海と空、どちらの青にも吸い込まれそうなその車体は上昇することなく、静かに落下していった。
ビー玉の軽い音が手元で鳴った。共鳴するように私たちを囲む森から蝉が体を震わせた。苔の生い茂る坂道を上れば、私たちはもうお別れだ。小さな駅から君は大都会へ一歩先に進むのだ。それは嬉しく、少し寂しいことでもあった。
「次は半年後?」
振り返りそう尋ねる。大型のキャリーケースを苦も無く片手で引き上げる彼は「そうだな」と頷いた。思えば十八年間いつだって彼と一緒にいた気がする。同じ町で育ち、同じ小学校に行って。裏山へ探検もしたし、時には港まで行って真冬の海に飛び込んだりもした。右手で音を立てるガラス瓶も、底を透かして見える世界は青色に染まって綺麗だった。私はラムネ瓶越しに見える君の笑顔が一番好きだった。
「意外とすぐじゃん。あーあ、なんか寂しくなって損したわ~」
「寂しさを無駄遣いに言うんじゃねぇよ」
そんな言葉、虚勢に決まってるだろう。本当は置いて行かれるのが堪らなく怖いのだ。
あぁ、もう駅が見えてきた。寂れた無人駅、それが私たちの分岐点だった。その場所に近づいていくのが怖い。大学進学を決めた君と、地元の町役場で就職を決めた私。今までずっと一緒にいたからと言って心も体も一緒な訳がないのに、もし君がこの電車に乗ってしまえばもう二度と会えないんじゃないか。言葉では形容し難いそんな不安を抱いているのは私だけだろうか。
「うっし、着いたな」
「疲れた~、体の老いを感じる~」
「小学生の頃はここまで走って登るの、よく競争したよな」
「あの時は私が勝ってたよ!」
「今競争したらお前途中で倒れそうだけどな」
「うるさい!」
駅のホームにある一つしかないベンチに腰掛ける。隣の彼は笑いながらも瞳は遠くの電車の来る方に向いていた。
もうお別れなんだ。本当に君は東京に行ってしまうんだ。
認めたくない醜い感情がこの期に及んで湧き上がる。駄目だと思い深呼吸すると、木造建築のかび臭い匂いが肺を満たす。その瞬間ジジジッと擦り切れたカセットテープのように何かの映像が脳内で再生される。
途切れ途切れで、朧気で、ほとんど分からない。しかし、満たした息を吐きだすと同時に電車に乗り込む君の姿が見えたような気がした。
「これは何……?」
「ん?どうした?」
私がぼそりと独り言を呟くとボストンバッグ一つ分隣にはまだ電車に乗り込んでいない君が心配そうにこちらを覗き込んでいた。私は彼の顔を見た途端、何故か目頭が焦げるほど熱くなる。理性では制御できない「何か」が確実に働いていた。きっと何かの記憶ときっと混ざりあっているのだろう。しかし、胸を満たす嫌な予感は何度息を吐きだしたって、わだかまって、こびりついて、無くなることはなかった。
暫くすると「まもなく、電車が参ります。ご注意ください」と掠れたアナウンスが鳴り響いた。眉毛を震わせた君は立ち上がると再びボストンバックを肩に掛け、重そうなキャリーケースを引きずると黄色い線の一歩外側に立つ。
「じゃあ、またね」
私が小さく手を振る。うまく笑えている自信がなかった。本音を言えば私はずっと君と一緒にいたかった。これからも、この辺鄙で小さな町に君と二人で思い出を紡ぎあげて、いつかは胸に秘める想いを伝えられたらいいな。なんて安易で幼稚で、けれどきっとどんなに道を踏み外したって不幸じゃないと言い切れる未来が欲しかった。
けれど、だからといって二手に分かれた私たちの未来を潰したいわけじゃない。
君には幸せになってもらいたい。
だから精一杯笑うのだ。また会える日まで、私のことを忘れられないくらい強く強く記憶に焼き付けてやるのだ。
「……また」
そんな私を見かねてか君も笑う。こんなにも顔をくしゃくしゃにさせて笑う青年の姿を見たのはいつぶりだろう。懐かしい感情が込み上げて溢れて、止まらなかった。
あぁ、愛おしいなぁ。
自分を雁字搦めにしていた気持ちが腑に落ちたと同時に右手のガラス瓶がまたカランと音を立てる。
やっぱり私は君のことが好きだ。
彼の体が電車に吸い込まれていく。機械音がして、歪んだ電車のドアが閉じられた。
その時、再びカセットテープが再生される。今度は進みゆく車体のガラスから手を振る君の姿が次の瞬間空中に放り出され、落下していく景色だった。段々と息が浅くなっていくのが自分でも分かる。思い出した、これは今朝見た夢だ。
きっとこれから起こることを表した夢だったのだ。
プーっと音をたて、車体は加速していく。笑顔で汚れた窓越しに手を振る君に私は絶叫した。
「嫌だいやだいやだ」
神様
どうか私を一人にしないでください。君だけ死んで私だけ取り残されたら私はどうやって息をすればいいのか分かりません。
君が助からない未来なんて嫌だ。
けれど、痛くて苦しくて孤独なまま君が死んでしまうなんて、もっとずっと嫌だ。
風鈴と手から滑り落ちたガラス瓶が砕けた音が合図だった。
私は後先考えずに走り出した。十メートル先を走る電車に追いつけるように必死に手を、足を振った。千切れてしまうんじゃないかと思うくらいにひらすら走って、絡まる足を前に進める。
ふと顔をあげると、君は驚いたようにこちらを凝視していた。何か怒鳴りながら窓を叩く姿も見える。
ごめんね、勝手なことして。
けど、やっぱり許せなかったよ。
私が息を吸った刹那、電車はスピードを緩めないまま残酷な音を残し崖から飛び出した。
不安定だったドアが外れ、君の身は宙に投げ出される。
一面青の世界、淡い白のシャツだけが浮かびあがっていた。
私はそれめがけて崖から飛び出す。それは即ち死を意味していた。覚悟はできていたもののやはり怖くて思わずぎゅっと目を固く閉じてしまう。
瞬間、伸ばした腕は何か柔らかいものによって引っ張られた。
「……っおい!!」
叫ぶような声で私は再びこわごわと瞼を持ち上げる。青の世界に浮かんでいたのは綿雲と、涙ぐむ君だった。
君は怒ったような困ったようなどうしたらいいのか分からないというように百面相をする。
落下する体は下から殴られたように痛い。けれど君の顔を見たら安堵してしまった自分もいた。
頬に手が添えられる。
覚悟を決めたような瞳はもう先ほどとは違い、穏やかだった。
「わらって」
君の口がそう動く。二人分の空気抵抗は相当なものらしい。風の切る音で声なんか聞こえやしない。けれど確かに君はそう言った。私は言葉通り笑って、君の手を引く。柔らかい視線が自然と絡んだ。どちらがともなく自然と唇を寄せ合う。
十八年間ずっと待ち焦がれていた君とのキスだった。
互いに覚悟はできていた。君がいれば何も怖いものなんてなかった。思い返せば一人ではきっと探検できない山も海も町も冒険しようと思えたのは、どんなときだって優しく手を引いてくれたのは、君だった。
ねぇ
また生まれ変わって、どこかで出会えたら私の名前を呼んでほしい。
それから恋に落ちて、また夏の空の青い日、キスをしよう。
何も覚えていなくたって私たちはまたきっと出会える。またきっと好きになってしまう。
だから大丈夫
「好きだよ」
零れた言葉が最後、白い飛沫をあげた水面と沈みゆく体。君の左手のラムネの瓶が光を反射して煌めいた。ガラスの破片越しに見えた最後の景色は愛おしい君だった。