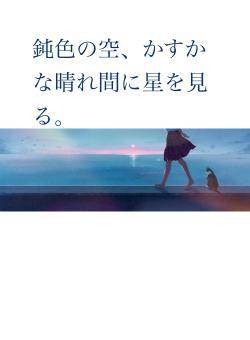九条の家は、人里離れた京都の山の奥深くにある。
実家へ帰りながら、彩葉は両親や礼葉と家族になったときのことを思い出していた。
今から約十年前、まだ名前も持たなかった頃の話だ。
母親と生き別れた子狐時代、彩葉は九条九郎という男に出会った。
当時彩葉は人間に化けて街中に潜み、ときに悪事を働いて生きる、小悪党のあやかしだった。
親を亡くし、ひとりぼっちだった子狐は、人間の子供に化けて必死に食べ物を探していた。数日水しか口にしていなかった子狐の体力は、既に限界を越えていた。
大人に化ける余裕も、木の葉を金に変える力すら残っていなかった。
野良の子狐は毎日、子供に化けて物乞いをした。
しかし、どこへ行っても食べ物を恵んでくれる店はない。我慢の限界を迎え、子狐は露店で売られていた団子をひとつ盗んだ。
しかし、運悪く店の店主らしき男に盗んだ瞬間を見られてしまった。
男は怒り心頭で、子狐は何度も何度も殴られた。とうとう体力がなくなり、子供の変化が解けてしまった。子狐の正体を見て、男は驚いた。
「忌々しい妖狐め! 殺してやる!」
このままじゃ殴り殺される、と死を覚悟したとき、だれかが男の手を掴んだ。
見知らぬ老父だった。
老父は「うちの娘がいたずらをして申し訳ない」と言って、丁寧に頭を下げた。
うちの娘、と言った老父に、子狐は首を傾げた。
まったく見覚えがない。
戸惑う子狐をよそに、老父は詫びだと言って子狐が見たこともないくらいの大金を男に与えた。
男は目の前の金にすっかり気をよくして、子狐を解放してくれた。
しかし店を出るとき、ものすごい剣幕で怒鳴られた子狐は震え上がって、その場から脱兎のごとく逃げ出した。
人気のない森の中の神社まで逃げて一息ついていると、あの老父がやってきた。
あからさまに怯える子狐に、老父はあの店の団子を差し出した。
子狐は老父を警戒しながらも空腹に勝てず、そろそろと手を伸ばして、その団子を受け取った。
受け取った途端、頬いっぱいに団子を頬張る子狐を見て、老父は微笑みながら言った。
「君、親はいないのかい?」
子狐は咀嚼をやめ、老父をじっと睨みつける。そして、小さく答えた。
「いない。死んだ」
「……そうか。なら、うちの子になるかい?」
「え……?」
子狐はじっと老父を見つめる。
老父は境内にちょんと座っていた子狐のとなりに腰を下ろすと、しっとりと話し出した。
「うちにもね、君と同じくらいの娘がいるんだ。歳がいってようやく授かった子だった。だけど、娘は生まれたときから身体が弱くてね……。よかったら、うちの子の姉妹になってくれないかな」
「おじさんの娘に?」
「見てのとおり、僕はおじさんだ。もう先も長くない。この先、娘がひとりになってしまうことだけが僕は気がかりなんだ」
「おじさんの娘もひとりぼっちなの? 私と一緒だね」
あどけない声で言う子狐に、老父は微笑む。
「そうだ。だから、僕たちがいなくなったあと、ふたりが力を合わせて生きていってくれたら、おじさんはすごく嬉しいんだ。どうかな?」
「おじさんの子になったら、私、ひとりぼっちじゃなくなる? おなかいっぱいになれる?」
「もちろん。家族になるんだからね」
子狐は、パッと表情を明るくする。しかし、その表情はすぐに翳った。
「……でも、私はあやかしだよ。妖狐は、悪いヤツだってみんな言うよ。今日だって……」
「君はただ一生懸命に生きているだけだ。悪いことなんてなにもしていないよ。君、名前はなんと言うんだ?」
「……ない。あったのかもしれないけど、知らない」
「そうか。なら、僕がつけてもいいだろうか」
老父は子狐に優しい眼差しを向けた。
「僕の娘はね、礼葉というんだ。どうせならうちの子と似た名前がいいな。……そうだ、彩葉というのはどうだろう?」
「いろは……ねぇ、それってどういう意味?」
「彩というのは、鮮やかで美しいことをいうんだよ。それから、いろんな色の組み合わせを言う。礼葉と良い関係になってほしいという気持ちを込めてみたんだ」
「彩葉……?」
名前を呟く。名前というものに慣れていない子狐は、そわそわとした。
「どうかな? 彩葉」
「可愛い名前だね」
「そうか」
「おじさんの名前はなんて言うの?」
「九郎だよ。九条九郎だ」
「……九郎おじさん。私、おじさんの子になりたい。おじさんの娘、守るよ。私が」
そうして、子狐は老父――九郎の娘となったのだ。
***
礼葉が亡くなったのは、彩葉が実家へ帰ってすぐのことだった。両親と同じ流行病に罹患してしまったのだ。
最愛の姉の死に、彩葉の心にはぽっかりと大きな穴が空いてしまった。しばらくなにをする気にもならず、彩葉は姉の亡骸に寄り添い続けた。
礼葉が亡くなったその日の夜、彩葉は夢を見た。
彩葉が天月家に嫁ぐことが決まった日の夜の夢だ。
だれより心配症である礼葉は、じぶんと入れ替わって結婚する彩葉のことをすこぶる心配していた。
結婚前夜、布団に横になりながら、彩葉は言った。
「――いい? 礼葉。今日から私は礼葉として、あなたは彩葉として生きるの。私たちが入れ替わってるってことは、ぜったいに天月家には秘密なんだからね」
礼葉が彩葉のほうへ寝返りを打つ。
「ねぇ彩葉、本当にお嫁に行くの? 身代わりなんて無茶だよ。もしバレたら、妖狐であるあなたは殺されちゃうかもしれない。やっぱり私が……」
「大丈夫よ! もしバレそうになったら、そのときは逃げるわ。私、逃げ足だけはとっても早いのよ。なにせ、妖狐ですから」
ぽんっ! と変化を解き、狐の耳としっぽをあらわにした彩葉を見て、礼葉がくすくすと笑う。
「私は、お父さまとお母さまの本当の子じゃないけれど、それでも愛情だけは礼葉にだって負けてないつもりよ」
「もちろん、それは分かってるわ。でも、天月家の次期当主は、気難しいかただと聞いたわ。彩葉は素直だから、ちゃんと上手くやっていけるのか心配なの」
「大丈夫! 上手くやるわよ!」
「本当かなぁ」
「とにかく、私はふたりに恩返しをしたいの。分かってよ、礼葉」
「うん……」
それでもまだ苦い顔をする礼葉の手を、彩葉がぎゅっと握る。
「大丈夫。嫁いだって家族は家族。私たちの心はずっと一緒よ。それに、もしお父さまとお母さまになにかあったら、すぐに戻る。礼葉がひとりになるときは、必ず帰ってくる」
「本当?」
「もちろん。礼葉はとにかく、今は病を治すことを考えて。それから、お母さまとお父さまをよろしくね。あまり無理させないように」
「うん、分かった」
礼葉と彩葉は、血が一滴も繋がっていない仮初の姉妹だったけれど、それでもふたりは本物の姉妹よりもずっと深い絆で繋がっていた。
目が覚めると、枕が濡れていた。目元を拭いながら起き上がると、がらんとした殺風景な空間が目に入る。どことなく、色褪せているような気がした。
……色も、温度も、音すらない部屋。
少し前まで、どんな場所よりあたたかかったのに。
目が覚めた途端に襲ってくる不安感に、彩葉は打ちのめされた。
「礼葉……お父さま、お母さま……会いたい」
彩葉の呟きは、だれもいない空間に寂しく溶けていく。
実家に戻ってから、数週間が経った。
涙も枯れ果てた頃、彩葉はようやく部屋を片付け始めた。家のあちこちに、両親や礼葉の生活の跡が残っている。礼葉が作っていた押し花や、父親の趣味の木彫りの鳥。台所に行くと、今でも母親の背中が見えるような気がしてしまう。
がらんとした部屋を見るたび、枯れたはずの涙があふれ出してくる。
涙を拭いながら遺品の整理をしていると、不意にほとほとと玄関の戸が鳴った。
「礼葉、いるか?」
聞こえてきたのは、楊の声だった。もしや、礼葉を連れ戻しに来たのだろうか。一瞬出るか迷ったが、彩葉はそろそろと立ち上がり、玄関に向かった。
戸を開けると、そこに立っていたのはやはり楊だった。
「礼葉。彩葉さんの具合はどうだ?」
彩葉は楊を呆然と見上げる。
そうか。そういえば、まだ姉が亡くなった報せを出していなかったのだった、と彩葉は今さらになって気付く。
楊は続ける。
「実は、京の山には大蛇がいるんだが、その大蛇の鱗は万能薬なんだそうだ。時間がかかってしまったが、ようやく手に入れたんだ。すりおろして飲ませるといい」
言いながら、楊は彩葉の手に紙袋をのせる。
「それから……この前は、無理に引き止めて悪かった」
楊はそれから、さめざめとした様子で言った。
「たったひとりの妹を大切に思うのは当たり前のことなのに、俺はあまりに身勝手だった。ごめん」
「…………」
ふと、黙り込んだままの彩葉に、楊が首を傾げる。
「礼葉? どうした?」
「……ました」
「ん?」
「死にました、昨日」
「…………」
楊は黙り込んだまま、何度か瞬きを繰り返す。そして、ひそやかな声で言った。
「……そうか。それは……残念だった」
「……いえ。せっかく持ってきていただいたのに申し訳ありませんが、これはお返しします。もう、必要なくなってしまったので」
そう言って、彩葉は紙袋を楊へそっと押し返す。戸を閉めようとすると、「待て」と楊が戸を押さえた。
「礼葉、少しだけ中に入れてもらえないか。彩葉さんをちゃんと悼みたいし……それに礼葉、少し痩せたんじゃないか? ちゃんと食べているのか? 握り飯くらいなら俺も作れる。よかったら……」
「すみません。まだ、いろいろと整理がつかなくて。今日はお帰りください」
彩葉は楊の声に被せるようにして言った。
「礼葉」
彩葉は引き止める楊を無視して、無理やり戸を閉めると、鍵を閉めた。そのまま、戸に背中をつけ座り込む。
彩葉の両目の端から、再び大粒の涙があふれた。
どれくらい、そうしていたのだろう。いつの間にか眠ってしまっていたらしかった。
また、夢を見た。
満開の藤の木の下に、大好きなひとが立っている。礼葉だ。
礼葉は見たことのない着物を着ていた。きれいな藤色の着物だ。それに、白い袴。まるで藤の花の精霊のようだと彩葉は思った。
「礼葉……!」
彩葉は思わず駆け出し、礼葉に抱きついた。勢いよく飛びついた彩葉を、礼葉は優しく抱きとめる。
「礼葉、会いたかった!」
しかし、抱き締めながら、彩葉は違和感を感じた。
感触がないのだ。礼葉を抱き締めているのに、ぬくもりがない。礼葉の背中へ腕を回しても、力が入らない。
礼葉はどことなく悲しげな眼差しのまま、彩葉を見つめた。青白い顔をしている。
「礼葉?」
困惑したまま、彩葉は礼葉を見つめる。
「彩葉、ごめんね。せっかく帰ってきてくれたのに、ひとりにしちゃって」
礼葉はそっと目を伏せ、彩葉から離れた。
「私、あなたには迷惑かけてばかり。あなたから、いろんなものを奪ってばかりだった」
「そんなことない!」
「でもね、彩葉、私、今はとてもすっきりしてるのよ」
「……どうして?」
「あなたにとってなにより大切な名前を返せた。それから、自由も」
どうしようもないくらい、悲しくなる。どうしてそんなことを言うのだろう。それではまるで……。
「なによそれ。死んでよかったみたいなこと、言わないでよ」
「彩葉とのお別れは寂しい。だけど、身体が軽いの。呼吸が楽なの。こんなの初めてよ」
礼葉はそう言って、その場でくるりと回転して見せた。その動きは、たしかに羽のように軽く見える。
「彩葉。私はただ、これ以上あなたに悲しんでほしくないだけ」
「そんなこと言ったって……」
無理だ。最愛の家族を一度に亡くして、それを悲しまないなんて。
「私ね、彩葉にお願いがあるの。最後の最後まで頼みごとばかりで申し訳ないのだけど。だけど、これは私だけじゃなくて、お父さまとお母さまのお願いでもあるから、言うわね」
礼葉は一度言葉を切ってから、言った。
「彩葉は、今までずっと私たち家族のために生きてきてくれたでしょ。だから、これからはじぶんのために生きて。彩葉の人生を生きるのよ」
思いもよらないことを言われ、彩葉は困惑する。
「ねぇ、よく考えてみて。あなたにはまだ、大切なひとがいるじゃない」
「大切なひと? いないよ、そんなの」
首を振る彩葉を、礼葉は優しく見つめる。
「いるわ。楊さまよ」
彩葉はハッとした。
「楊……さま?」
「そうよ。今の彩葉の家族は、楊さまでしょう?」
「そ、それは違うわ。お父さまやお母さまが死んで、私はあの家にいる理由がなくなった。私はもう、楊さまとは離縁するの。他人になるの」
「まだよ。まだ愛は残ってるでしょう」
「愛……?」
「そうよ。彩葉はまだ楊さまを愛しているし、楊さまも彩葉を愛してる。でなきゃ、離縁した妻のために、九条の実家までわざわざ妙薬を届けになんてきてくれないわ」
「そ、それは礼葉のためであって……」
「違うわ。彩葉を取り戻したいからよ。私が元気になれば、きっと彩葉は安心して戻ってきてくれると思ったのよ。楊さまって、とっても可愛いところがあるのね。噂では冷酷なひとだと聞いていたけれど、ぜんぜん違うみたい」
「……楊さまは優しいわ。でも……」
ふと、ふたりを囲んでいた藤の花が淡く輝き出した。ぽうぽうと光るそれは、消えそうで消えない。次第に、礼葉の身体も輝き出した。
「もうそろそろ、時間みたい。行かなきゃ」
礼葉が言う。
「行くって、どこへ?」
「お父さまとお母さまのところよ」
「そんな……お願い、待って。もう少しそばにいて」
思わず手を伸ばすが、彩葉の手はもはや、礼葉に触れることはできなかった。まるで煙に映る幻に手を伸ばしているかのように、掴もうとすればふっと消えてしまう。
「彩葉、最後にひとつ忠告よ。楊さまを追いかけて」
「え?」
「彼、私の病を治す薬を手に入れるために、かなりの無茶をしたみたい。もし今あやかしに襲われたら、間違いなく死んでしまうわ」
ハッとする。そういえば、家に訪ねてきたときの楊は、どことなくやつれていた。心に余裕がなく、気遣いの言葉ひとつかけてやれなかった。
「今楊さまを守れるのは、彩葉だけよ」
「私には……無理だよ」
よろよろと首を振る彩葉に、礼葉は姉の慈愛がこもった眼差しを向ける。
「彩葉、大切なものというのは、失ってから気付いても遅いの。あなたはそのことをだれよりよく分かっているはずよ。今ならまだ間に合う。だから急いで、お願い」
次の瞬間、ふたりを包んでいた光がふっと消えた。
彩葉は目を開けた。静かに瞬きをする。
彩葉は、じぶんの手のひらを見つめた。
『楊さまを追いかけて』
脳内で礼葉の声が木霊し、心臓がざわめき出す。
今の夢はなんだったのだろう。むしのしらせというもの?
もしかして、楊になにかある?
妙な胸騒ぎがして、いてもたってもいられなくなった。彩葉は急いで家を出た。