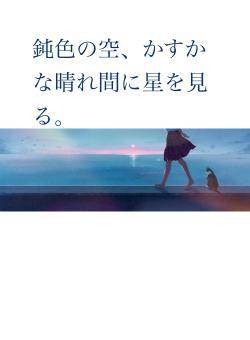屋敷の裏山の奥、山桜の樹洞の中で、彩葉は騒々しく脈を打つ心臓を押さえた。
先ほど包丁で切ってしまった指先を見る。傷口はもう完全に塞がっていた。きれいな皮膚を見て、彩葉は呟く。
「バケモノめ……」
怪我をするたび、鏡を見るたびに彩葉はじぶんがあやかしであることを思い出す。思い出しては、ひとでないことに絶望していた。
礼葉や両親といた頃は、妖狐として生まれたことを気にしたことなんてなかった。そんなことを気にする必要がないくらい、深く愛されていたから。
けれど、今は違う。
近頃彩葉は、じぶんがあやかしであることに後ろめたさと焦燥を感じるようになった。
なぜだろう。
楊が祓い屋の当主だからか。
いや、それだけではきっとない。
今、時代は変わりつつある。
天月家は都会から多少離れたところにあるが、とはいえ京都にも少しづつ都会の大衆文化やモダニズムが波及しつつある。
この先あやかしは、どんどん棲家を奪われていくだろう。
それは、妖狐である彩葉も例外ではない。いつまでも人間のそばに留まるべきではない。
最初から彩葉は、楊とは相容れない存在だったのだ。
しかしそれについて寂しさを感じていることが、彩葉にとっては予想外だった。
いつからこんなに、楊の存在が大きくなっていたのだろう。
「結婚当初は、いやな人だと思っていたのにな」
彩葉はひとりごちる。
かつて、楊は彩葉にこう言い放った。
――結婚などただの見せかけだ。俺には不必要にかかわるな。
楊のひとぎらいは、家庭環境にあるようだった。女中たちの話によると、楊の死んだ父親は、女癖が悪く、ろくでもないひとだったらしい。
おかげで、出会った頃の楊は極度の女ぎらいだった。
触れることはおろか、目が合っただけで怒鳴られたこともある。
しかし、彩葉はどれだけ楊に傷付けられても逃げ帰るわけにはいかなかった。
両親をがっかりさせないためにも、離縁されるわけにはいかなかったのだ。
嫁いでから彩葉は、楊とせめてふつうに会話ができるくらいに好かれようと奮闘した。苦戦したが、今はなんとかふつうに近い関係にはなれたと思っている。
すべては両親のためだった。
でも、その両親はもういない。すべて終わったのだ。
彩葉が楊へどんな想いを抱いていようと、楊がたとえ行くなと言おうと、お芝居はおしまいなのだ。
彩葉は大嘘つきのバケモノ。楊とは釣り合わない。
山桜の木の上から、彩葉は眼下、山桜に囲まれた天月屋敷を見下ろした。
彩葉は家を出ようと決意した。