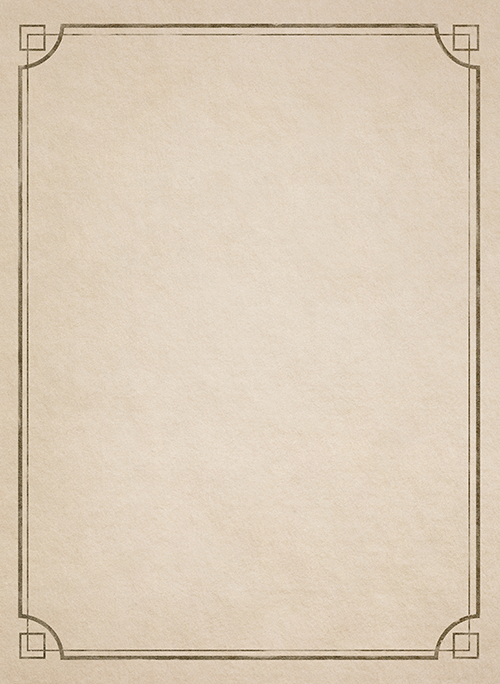○令和三年 三月某日
「これは私の友達の話なんだけどね。
赫碧症として生まれたその子はそれだけで邪険にされたり嫌われたりするから、『じゃあこの力を困っている人たちのために使おう』って前向きに捉えたの。
褒めてもらいたくて、認めてもらいたくて、危険な場面でも構わず立ち向かって、何度も碧眼になって。
でもその先に待ってたのは余りにも早すぎる最期だった。悪いことしようとしたわけじゃなかったのにね」
友人のことを想っていたのか、それとも本当は自分自身の過去を思っていたのか。問いただそうとはせず、忍はただ黙って聞いていた。
「だからあんたも長生きしたかったら、誰かに褒めてもらおうとか認められようとか承認欲求拗らせてないで、あまり多くを求めず慎ましく生きなさい。
……それでも欲張りしたいなら……せめて特別な人一人のためだけにしなさい。
大勢を助けなくても、誰か一人救えただけで人生……御の字なんだから…………」
◇◇◇
「……有島さん、赫碧症だったんですね。それに碧眼がそんなに恐ろしいものだったなんて……。
あの、もしかして『書き置き残して』って言うのは本当は……?」
「いや、本当に最後は書き置き残して失踪したよ。夜逃げかと思ったけど、荷物は殆ど残してった」
◇◇◇
死期を悟った猫がある日忽然といなくなる。
そんなはずはない。猫じゃないんだから。
だいたい死ぬとしても葬式ぐらい挙げてやるんだから――――。
そこで気づいた。
彼女の家族構成、そして今どこに住んでいるのかを自分が全く知らなかったことに。
一ヶ月後の四月。有島が去ってすぐ探偵業変更届出書を警察署に提出する。一人で仕事に追われながらも、いつかは帰ってくるだろうと楽観視していた。彼女の人徳のおかげか、熊谷をはじめとした探偵事務所の所長達の手助けでなんとかやってこれた。
半年後。蒼樹が有島を訪ねにやってきた。それでも有島は戻ってこなくて、二人でなんとか事務所を回した。
一年後。蒼樹が去り、一人でまた仕事に追われる日々が戻ってきた。まだあと一年あると、それまで事務所を守らなければという義務感だけが支えだった。
二年後。有島は戻らなかった。
そして契約書の通り屋号を変えた。
◇◇◇
「契約書……? そんなもの事前に用意してたんですか?」
「その契約書がね、ガバガバすぎて笑っちゃうから。明日学校から帰ったら見せてあげる」
「約束ですよ?」
柊が控えめな笑顔を作ったかと思えば少し悲しそうな声で尋ねる。
「有島さんが突然いなくなった時は悲しかったですか?」
「それが全然。あんな弱ってるところ見てたくせに『絶対どこかでしぶとく生きてるだろ』って思い込んでたから。最悪の可能性は考えたくなかった」
「重い病気だとしても、なぜ急にいなくなったのか心当たりってありましたか?」
「うん……殆ど俺の妄想なんだけど。葬式で、自分の家族来ないとこを皆に……俺に見せたくなかったんじゃないかな……」
忍の瞬きの回数が急に増え出したのを見て焦った柊は「もう大丈夫です」と言った。
「なんかしんみりした話になって悪いな」
「そんなことないです。不謹慎かもしれませんけど……感動しました」
「有島さんも草葉の陰で喜んでるよ」
「勝手に殺さないでください。……もう」
冗談めかした流れになったかと思いきや、「柊」と忍が真摯な顔で彼女をじっと見つめた。そんな彼の視線に柊はどぎまぎした様子だ。
「有島さんのこと、あまり思い出さないようにしてたから、なんか懐かしくなってきたよ。聞いてくれてありがとう」
「と、とんでもないです」
そこで忍が目を伏せ
「――――有島さんはな。他人が幸せになる権利踏みにじるようなマネだけは絶対しなかった。あの人も赫碧症だったから……ってワケじゃなくて。ポリシーだったんだ。俺も有島さんみたいになりたかったけど、たった三年で人ってこんなに変わるもんなんだな」
と、自嘲気味に言った。自分が薄汚いマネをしていると彼は自覚していたから、今まで有島のことを極力思い出さないようにしていた。
「……でも。でも、所長はあの人達を幸せにしようと考えて行動したじゃないですか」
二人は釣り場駐車場での出来事を思い出す。結果は失敗に終わり、依頼人と男性は破局してしまった。
「所長はあの日から生まれ変わったんです。だから有島さんみたいな立派な所長になれますよ。何事にも遅すぎることなんてありません。
所長ならきっと、赫碧症の方も、そうじゃない方もみんなが幸せになる方法を見つけてくれるはずです」
それを聞いた忍は「責任重大だな」と苦笑した。
こうして有島の話も終わり、暫し二人は口を閉ざす。先に沈黙を破ったのは柊だった。
「あの。添い寝をお願いしましたけども、本当に好きにしてくださって構いませんから」
「鈍いから聞いちゃうけど、本当は添い寝以上のことをして欲しいか」
と、忍が至って真面目に聞いてきた。そんな直球で聞いてくるとは思わなかったのか、柊は少し照れながら返答に迷った末、「どっちでも嬉しいです」と答える。
「どうしようか。実は自覚が無いだけな赫碧症者で、明日朝起きたら離婚届だけ置いて出ていかれたら」
「構いません。私、もし所長がそうでも、やっぱり離婚したくないです」
忍が茶化しながら言うと、仰向けになっていた柊が彼と向き合うように横向きになる。
「でも、怖いって言ってたじゃないか」
「すみません。あんなこと言っておいて自分でも面の皮が厚いと思ってるんですが」
柊は一旦そこで区切り、
「本当は私、赫碧症なんです。ずっと黙っててごめんなさい」
悔いるように、忍に告白する。
忍は初めて彼女と会った――落ちた植木鉢を追ってビルの屋上から飛び降りた――時、彼女の眼に美しい碧色が宿っていたのを思い出していた。
「……そうか。初めて会った時、碧っぽく見えたのはやっぱ気のせいじゃなかったか」
「はい。だから、男の人とそういうことしたら、赫くなると思います」
もじもじしながら彼女は「多分」と付け加えた。そして忍の胸に恐る恐る手を当て、上目遣いでねだるように見つめ、
「もし所長さえ良ければ、今晩、初夜にしませんか」
などと、柊はついに爆弾発言をしてしまった。
恥ずかしさで縮こまる彼女を見て、忍は無性に悲しい気分を覚えた。彼女にそんな気持ちを悟られぬよう、すぐに穏やかな笑みを浮かべた。
「在学中は無責任な真似はしないって先生たちに約束しちゃったからな」
「律儀ですね。どうせわかりっこないですよ」
柊は忍の胸に顔を擦り付けるようにぐりぐりする。忍は、今日送り届けた犬がこんなふうに飼い主の体にすり寄っていたな、と思い出す。
彼の心臓の鼓動を聞いて落ち着いてるらしい。
幼子を持つ親とはこんな気分なのだろうかと、忍は柊が愛おしくなって彼女の細い髪の感触を確かめるように指で掬いつつ、頭を何度か撫でた。
人恋しかったのは、自分の方だったのかもしれない。
●五月二十日(月曜)
翌日、忍が先に目を覚ます。
いつの間にか立場が逆転していたらしく、起きると忍の頭は緩く柊の腕に抱かれ、やや謙虚な膨らみに顔を埋めていた。ちょっとした感触でノーブラだと気づいてしまった。
「これはイカン」
彼女を起こさないよう忍は慎重にベッドから脱出して静かに寝室を去る。
やましいことなど何もしていないのに、なぜか罪悪感が襲ってきた。
二人で添い寝をしたせいだろうか。
今まで彼女が夢に出たことなど一度もなかったのに、朧げに柊からキスをされる夢を見たせいで忍は落ち着かなかった。
「これは私の友達の話なんだけどね。
赫碧症として生まれたその子はそれだけで邪険にされたり嫌われたりするから、『じゃあこの力を困っている人たちのために使おう』って前向きに捉えたの。
褒めてもらいたくて、認めてもらいたくて、危険な場面でも構わず立ち向かって、何度も碧眼になって。
でもその先に待ってたのは余りにも早すぎる最期だった。悪いことしようとしたわけじゃなかったのにね」
友人のことを想っていたのか、それとも本当は自分自身の過去を思っていたのか。問いただそうとはせず、忍はただ黙って聞いていた。
「だからあんたも長生きしたかったら、誰かに褒めてもらおうとか認められようとか承認欲求拗らせてないで、あまり多くを求めず慎ましく生きなさい。
……それでも欲張りしたいなら……せめて特別な人一人のためだけにしなさい。
大勢を助けなくても、誰か一人救えただけで人生……御の字なんだから…………」
◇◇◇
「……有島さん、赫碧症だったんですね。それに碧眼がそんなに恐ろしいものだったなんて……。
あの、もしかして『書き置き残して』って言うのは本当は……?」
「いや、本当に最後は書き置き残して失踪したよ。夜逃げかと思ったけど、荷物は殆ど残してった」
◇◇◇
死期を悟った猫がある日忽然といなくなる。
そんなはずはない。猫じゃないんだから。
だいたい死ぬとしても葬式ぐらい挙げてやるんだから――――。
そこで気づいた。
彼女の家族構成、そして今どこに住んでいるのかを自分が全く知らなかったことに。
一ヶ月後の四月。有島が去ってすぐ探偵業変更届出書を警察署に提出する。一人で仕事に追われながらも、いつかは帰ってくるだろうと楽観視していた。彼女の人徳のおかげか、熊谷をはじめとした探偵事務所の所長達の手助けでなんとかやってこれた。
半年後。蒼樹が有島を訪ねにやってきた。それでも有島は戻ってこなくて、二人でなんとか事務所を回した。
一年後。蒼樹が去り、一人でまた仕事に追われる日々が戻ってきた。まだあと一年あると、それまで事務所を守らなければという義務感だけが支えだった。
二年後。有島は戻らなかった。
そして契約書の通り屋号を変えた。
◇◇◇
「契約書……? そんなもの事前に用意してたんですか?」
「その契約書がね、ガバガバすぎて笑っちゃうから。明日学校から帰ったら見せてあげる」
「約束ですよ?」
柊が控えめな笑顔を作ったかと思えば少し悲しそうな声で尋ねる。
「有島さんが突然いなくなった時は悲しかったですか?」
「それが全然。あんな弱ってるところ見てたくせに『絶対どこかでしぶとく生きてるだろ』って思い込んでたから。最悪の可能性は考えたくなかった」
「重い病気だとしても、なぜ急にいなくなったのか心当たりってありましたか?」
「うん……殆ど俺の妄想なんだけど。葬式で、自分の家族来ないとこを皆に……俺に見せたくなかったんじゃないかな……」
忍の瞬きの回数が急に増え出したのを見て焦った柊は「もう大丈夫です」と言った。
「なんかしんみりした話になって悪いな」
「そんなことないです。不謹慎かもしれませんけど……感動しました」
「有島さんも草葉の陰で喜んでるよ」
「勝手に殺さないでください。……もう」
冗談めかした流れになったかと思いきや、「柊」と忍が真摯な顔で彼女をじっと見つめた。そんな彼の視線に柊はどぎまぎした様子だ。
「有島さんのこと、あまり思い出さないようにしてたから、なんか懐かしくなってきたよ。聞いてくれてありがとう」
「と、とんでもないです」
そこで忍が目を伏せ
「――――有島さんはな。他人が幸せになる権利踏みにじるようなマネだけは絶対しなかった。あの人も赫碧症だったから……ってワケじゃなくて。ポリシーだったんだ。俺も有島さんみたいになりたかったけど、たった三年で人ってこんなに変わるもんなんだな」
と、自嘲気味に言った。自分が薄汚いマネをしていると彼は自覚していたから、今まで有島のことを極力思い出さないようにしていた。
「……でも。でも、所長はあの人達を幸せにしようと考えて行動したじゃないですか」
二人は釣り場駐車場での出来事を思い出す。結果は失敗に終わり、依頼人と男性は破局してしまった。
「所長はあの日から生まれ変わったんです。だから有島さんみたいな立派な所長になれますよ。何事にも遅すぎることなんてありません。
所長ならきっと、赫碧症の方も、そうじゃない方もみんなが幸せになる方法を見つけてくれるはずです」
それを聞いた忍は「責任重大だな」と苦笑した。
こうして有島の話も終わり、暫し二人は口を閉ざす。先に沈黙を破ったのは柊だった。
「あの。添い寝をお願いしましたけども、本当に好きにしてくださって構いませんから」
「鈍いから聞いちゃうけど、本当は添い寝以上のことをして欲しいか」
と、忍が至って真面目に聞いてきた。そんな直球で聞いてくるとは思わなかったのか、柊は少し照れながら返答に迷った末、「どっちでも嬉しいです」と答える。
「どうしようか。実は自覚が無いだけな赫碧症者で、明日朝起きたら離婚届だけ置いて出ていかれたら」
「構いません。私、もし所長がそうでも、やっぱり離婚したくないです」
忍が茶化しながら言うと、仰向けになっていた柊が彼と向き合うように横向きになる。
「でも、怖いって言ってたじゃないか」
「すみません。あんなこと言っておいて自分でも面の皮が厚いと思ってるんですが」
柊は一旦そこで区切り、
「本当は私、赫碧症なんです。ずっと黙っててごめんなさい」
悔いるように、忍に告白する。
忍は初めて彼女と会った――落ちた植木鉢を追ってビルの屋上から飛び降りた――時、彼女の眼に美しい碧色が宿っていたのを思い出していた。
「……そうか。初めて会った時、碧っぽく見えたのはやっぱ気のせいじゃなかったか」
「はい。だから、男の人とそういうことしたら、赫くなると思います」
もじもじしながら彼女は「多分」と付け加えた。そして忍の胸に恐る恐る手を当て、上目遣いでねだるように見つめ、
「もし所長さえ良ければ、今晩、初夜にしませんか」
などと、柊はついに爆弾発言をしてしまった。
恥ずかしさで縮こまる彼女を見て、忍は無性に悲しい気分を覚えた。彼女にそんな気持ちを悟られぬよう、すぐに穏やかな笑みを浮かべた。
「在学中は無責任な真似はしないって先生たちに約束しちゃったからな」
「律儀ですね。どうせわかりっこないですよ」
柊は忍の胸に顔を擦り付けるようにぐりぐりする。忍は、今日送り届けた犬がこんなふうに飼い主の体にすり寄っていたな、と思い出す。
彼の心臓の鼓動を聞いて落ち着いてるらしい。
幼子を持つ親とはこんな気分なのだろうかと、忍は柊が愛おしくなって彼女の細い髪の感触を確かめるように指で掬いつつ、頭を何度か撫でた。
人恋しかったのは、自分の方だったのかもしれない。
●五月二十日(月曜)
翌日、忍が先に目を覚ます。
いつの間にか立場が逆転していたらしく、起きると忍の頭は緩く柊の腕に抱かれ、やや謙虚な膨らみに顔を埋めていた。ちょっとした感触でノーブラだと気づいてしまった。
「これはイカン」
彼女を起こさないよう忍は慎重にベッドから脱出して静かに寝室を去る。
やましいことなど何もしていないのに、なぜか罪悪感が襲ってきた。
二人で添い寝をしたせいだろうか。
今まで彼女が夢に出たことなど一度もなかったのに、朧げに柊からキスをされる夢を見たせいで忍は落ち着かなかった。