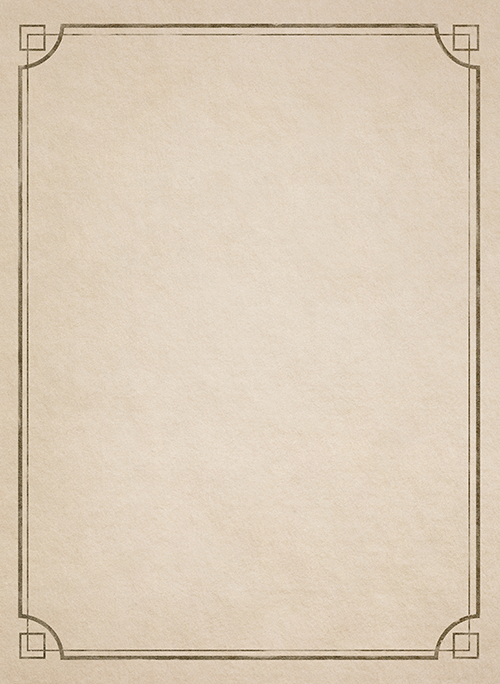○平成二十八年 某月某日
ある日、有島の介入に対する報復に訪れたヤクザが事務所のドアのガラスなどを盛大にブチ壊して押し入ってきた。
有島も忍もその場に居合せ、男たちは近接武器を持参して襲いかかってきたものの、忍は思いの外すんなりと碧眼して襲ってきた大人五人をコテンパンにしてしまった。当時忍はまだ中学二年である。
碧眼というのは任意のタイミングでなろうと思ってなれるものではない。それは今の忍でも同じ話である。
しかし「差し迫った状況」――これを脳が認識するかどうか、そしてその速さは人それぞれであり、「碧眼になった時はもう手遅れでした」というパターンも珍しくない。
だが一部の人間、例えば彼のように危機察知能力が高すぎる人間ほど、早い段階で碧眼状態に入りやすくなってしまうのである。
赫碧症の自分が初めて人を守るために役に立った。
それが誇らしくて、後ろにいた有島に「今の見てた⁉︎」と嬉しそうに振り向いた瞬間。
熱い平手打ちを喰らった。
「碧眼状態は脳に負担がかかる。心理福祉課で習わなかったの」
「……習ったけどっ! ほんの一瞬だったじゃんかっ! 十秒もなかった! たったそれくらいどうってことないだろ!」
「どうってことがあるから引っ叩いてんのよ!」
有島はもう片方の頬を平手打ちした。
「碧眼になれるからって自惚れるんじゃないんだからね。そんなの才能でもなんでもないんだから」
そんなことを言われるために戦ったわけでも、碧眼になったわけでもないのに。
忍は既に転がっていた観葉植物のプランターを思い切り蹴り上げ、怒りに任せて走り去る。
そのままとある河川敷に駆け込み一人不貞腐れていた。
いつぞや有島に見つけてもらい、そしてある記念日を迎えた、彼にとって思い出の場所とも言える。
しかし数時間経っても有島は現れず、忍も時間が経ったおかげで頭が冷えて、事務所へ戻ることにした。
事務所はまだ警察の実況見分が終わっておらず、有島もそばで立ち会っている。
なんだ、探しにこなかったのは警察に拘束されてたせいなのか。
少し考えれば分かりそうなことだったのに、有島が来なかった理由が別にあったと知って安堵する自分がいることに忍は気づかない。
裏口からそっと入って二階に上がり、軽い罪滅ぼしとして有島が比較的好んだ鉄板目玉焼きのせナポリタンを用意した。
実況見分から解放されたのかちょうど調理し終えた頃に有島が現れたが、料理にちっとも関心を示さず一人で部屋に戻ろうとする。
それがどうしてもどうしてもどうしても腹立たしくて――――。
「……め……眼。眼が赫くなってる」
ほんの一瞬だけだったが、意識が飛んでいた。言われるまで赫眼になっていたことにも気づかなかった。いつのまにか食卓テーブルがひっくり返って、用意したはずのナポリタンはカーペットの上でぐちゃぐちゃになっている。
「あーもうただでさえ事務所もめちゃくちゃなのにダイニングまで……カーペット汚れちゃったじゃん。気に入ってたのに。
……それと癇癪起こして赫眼になるのが許されるのは小学校低学年までだから。あんた今何年生? 中二でしょ。そんなんじゃ高校生活やっていけないわよ」
「……じゃあいいよ! 義務教育じゃないんだから高校は通わなくてもいいんだろ‼︎」
「あっそう。じゃあ親元に帰れば? 中卒の探偵助手なんていらないから」
有島は冷たく吐き捨てて、彼を無視して部屋の中へ消えてしまう。
忍は最初片付けも何もかも放り投げて一度は部屋――現在の物置部屋――でふて寝したものの、一時間ほどしてすぐにダイニングに戻り、散らかった料理を片付け、手洗い表示のカーペットを風呂場で足踏みして洗うもナポリタンのケチャップの跡は消えそうになく、ある程度のところで諦めた。
翌日には予備のカーペットを敷いて、忍は努めていつものように過ごす。有島は気怠げそうだった。日によって気分が変わるのはこの人にはよくあることだと言い聞かせた。
結局この件のはなあなあになり、直接和解があったわけではないがお互い喧嘩していたことなどなかったかのように振る舞った。
◇◇◇
「――丈夫だけが取り柄みたいな人だったんだけど、事務所出てく半年前くらいから体調崩して、毎週水曜定休日にしてずっと寝込んでた。この部屋で」
◇◇◇
○令和二年 十月某日
忍が十八になってほどなく、有島の調子がおかしくなりはじめた。
そして高校三年の三学期。忍の卒業まであと三ヶ月のことだった。
相変わらず寝室で横になっていた有島を見かねた忍はお粥を作り、ただの飾りと化したアンティーク椅子の上にお粥が入った食器とレンゲを乗せたお盆を置く。
「所長、もう三ヶ月近く水曜は横になりますね」
「女の子はね、週に一回、こうして寝込みたくなるくらい辛いことがあるの……」
「……………………」
「おい、今せっかくツッコミポイント二箇所ほど用意してやったろ」
「こんな時に人の気遣いなんてしてる場合じゃないでしょう。病院行きましょ、せっかく免許取ったのに」
「病院行く前に事故って死ぬ……」
「部下をもっと信用してくださいよ! そりゃあの、車にガードレールちょっぴり擦った記憶があるようなないような気がしますけど」
◇◇◇
「気丈な方なんですね、有島さんって」
「うん。横になってる時点で弱み見せまくってるんだけど、本人的には弱みを見せてないつもりっぽい。それがまた面白いのなんの」
――また、柊には以下のやりとりを伏せた。
◇◇◇
しまった、またいつもの調子で話してしまった。今の有島に必要なのは安息と休息、そして病院へ向かうことだと、忍はスマートフォンを取り出した。
「タクシー呼びましょ。病院行ったことない自慢とかしてる場合じゃないですよ。それか救急車――――」
スマートフォンを操作する手を弱々しくも有島が制した。「所長?」と困ったように尋ねると、すぐに有島は腕をだらりと下げる。
「あんた……碧眼になりやすいからってあんまホイホイ使うんじゃないわよ……。
私の知り合いで赫碧症の人がいてね……危険な土地で、危険な仕事して……何度も死線潜り抜ける度に碧眼になりやすくなって、だんだん脳に負担がかかって、ある日突然脳死しちゃった……。
その人、まだ二十六だった……」
「あ…………所長、もしかして、そんな」
「だから、これは女の子の週一のイベントっつってん……でしょうが…………」
「……所長……。女の子って、何歳まで女の子なんでしょうか…………週一って、そんな頻度高いですっけ…………」
「そうそう……そのツッコミ…………待って…………」
嬉しそうにそう言いかけて有島は眠りにつく。
冷めると思って食器に蓋にして、数時間後にまた戻ってきたら有島がまだお粥に手をつけていないことに気づいた。
――彼女が自分と同じ赫碧症だと、この日初めて知った。
それでも次の日にはいつものように起きていつものように仕事する。傍目には元気そうにしか見えない。
元気そうにしか見えないだけに、水曜の憔悴しきった彼女とは別人のような気がしてならなかった。
◇◇◇
「一ヶ月後に週一のイベントは週二のイベントになった。新規の依頼は受けないことにした。熊谷さん、他の探偵事務所に案件の引き継ぎをお願いしに回った」
ある日、有島の介入に対する報復に訪れたヤクザが事務所のドアのガラスなどを盛大にブチ壊して押し入ってきた。
有島も忍もその場に居合せ、男たちは近接武器を持参して襲いかかってきたものの、忍は思いの外すんなりと碧眼して襲ってきた大人五人をコテンパンにしてしまった。当時忍はまだ中学二年である。
碧眼というのは任意のタイミングでなろうと思ってなれるものではない。それは今の忍でも同じ話である。
しかし「差し迫った状況」――これを脳が認識するかどうか、そしてその速さは人それぞれであり、「碧眼になった時はもう手遅れでした」というパターンも珍しくない。
だが一部の人間、例えば彼のように危機察知能力が高すぎる人間ほど、早い段階で碧眼状態に入りやすくなってしまうのである。
赫碧症の自分が初めて人を守るために役に立った。
それが誇らしくて、後ろにいた有島に「今の見てた⁉︎」と嬉しそうに振り向いた瞬間。
熱い平手打ちを喰らった。
「碧眼状態は脳に負担がかかる。心理福祉課で習わなかったの」
「……習ったけどっ! ほんの一瞬だったじゃんかっ! 十秒もなかった! たったそれくらいどうってことないだろ!」
「どうってことがあるから引っ叩いてんのよ!」
有島はもう片方の頬を平手打ちした。
「碧眼になれるからって自惚れるんじゃないんだからね。そんなの才能でもなんでもないんだから」
そんなことを言われるために戦ったわけでも、碧眼になったわけでもないのに。
忍は既に転がっていた観葉植物のプランターを思い切り蹴り上げ、怒りに任せて走り去る。
そのままとある河川敷に駆け込み一人不貞腐れていた。
いつぞや有島に見つけてもらい、そしてある記念日を迎えた、彼にとって思い出の場所とも言える。
しかし数時間経っても有島は現れず、忍も時間が経ったおかげで頭が冷えて、事務所へ戻ることにした。
事務所はまだ警察の実況見分が終わっておらず、有島もそばで立ち会っている。
なんだ、探しにこなかったのは警察に拘束されてたせいなのか。
少し考えれば分かりそうなことだったのに、有島が来なかった理由が別にあったと知って安堵する自分がいることに忍は気づかない。
裏口からそっと入って二階に上がり、軽い罪滅ぼしとして有島が比較的好んだ鉄板目玉焼きのせナポリタンを用意した。
実況見分から解放されたのかちょうど調理し終えた頃に有島が現れたが、料理にちっとも関心を示さず一人で部屋に戻ろうとする。
それがどうしてもどうしてもどうしても腹立たしくて――――。
「……め……眼。眼が赫くなってる」
ほんの一瞬だけだったが、意識が飛んでいた。言われるまで赫眼になっていたことにも気づかなかった。いつのまにか食卓テーブルがひっくり返って、用意したはずのナポリタンはカーペットの上でぐちゃぐちゃになっている。
「あーもうただでさえ事務所もめちゃくちゃなのにダイニングまで……カーペット汚れちゃったじゃん。気に入ってたのに。
……それと癇癪起こして赫眼になるのが許されるのは小学校低学年までだから。あんた今何年生? 中二でしょ。そんなんじゃ高校生活やっていけないわよ」
「……じゃあいいよ! 義務教育じゃないんだから高校は通わなくてもいいんだろ‼︎」
「あっそう。じゃあ親元に帰れば? 中卒の探偵助手なんていらないから」
有島は冷たく吐き捨てて、彼を無視して部屋の中へ消えてしまう。
忍は最初片付けも何もかも放り投げて一度は部屋――現在の物置部屋――でふて寝したものの、一時間ほどしてすぐにダイニングに戻り、散らかった料理を片付け、手洗い表示のカーペットを風呂場で足踏みして洗うもナポリタンのケチャップの跡は消えそうになく、ある程度のところで諦めた。
翌日には予備のカーペットを敷いて、忍は努めていつものように過ごす。有島は気怠げそうだった。日によって気分が変わるのはこの人にはよくあることだと言い聞かせた。
結局この件のはなあなあになり、直接和解があったわけではないがお互い喧嘩していたことなどなかったかのように振る舞った。
◇◇◇
「――丈夫だけが取り柄みたいな人だったんだけど、事務所出てく半年前くらいから体調崩して、毎週水曜定休日にしてずっと寝込んでた。この部屋で」
◇◇◇
○令和二年 十月某日
忍が十八になってほどなく、有島の調子がおかしくなりはじめた。
そして高校三年の三学期。忍の卒業まであと三ヶ月のことだった。
相変わらず寝室で横になっていた有島を見かねた忍はお粥を作り、ただの飾りと化したアンティーク椅子の上にお粥が入った食器とレンゲを乗せたお盆を置く。
「所長、もう三ヶ月近く水曜は横になりますね」
「女の子はね、週に一回、こうして寝込みたくなるくらい辛いことがあるの……」
「……………………」
「おい、今せっかくツッコミポイント二箇所ほど用意してやったろ」
「こんな時に人の気遣いなんてしてる場合じゃないでしょう。病院行きましょ、せっかく免許取ったのに」
「病院行く前に事故って死ぬ……」
「部下をもっと信用してくださいよ! そりゃあの、車にガードレールちょっぴり擦った記憶があるようなないような気がしますけど」
◇◇◇
「気丈な方なんですね、有島さんって」
「うん。横になってる時点で弱み見せまくってるんだけど、本人的には弱みを見せてないつもりっぽい。それがまた面白いのなんの」
――また、柊には以下のやりとりを伏せた。
◇◇◇
しまった、またいつもの調子で話してしまった。今の有島に必要なのは安息と休息、そして病院へ向かうことだと、忍はスマートフォンを取り出した。
「タクシー呼びましょ。病院行ったことない自慢とかしてる場合じゃないですよ。それか救急車――――」
スマートフォンを操作する手を弱々しくも有島が制した。「所長?」と困ったように尋ねると、すぐに有島は腕をだらりと下げる。
「あんた……碧眼になりやすいからってあんまホイホイ使うんじゃないわよ……。
私の知り合いで赫碧症の人がいてね……危険な土地で、危険な仕事して……何度も死線潜り抜ける度に碧眼になりやすくなって、だんだん脳に負担がかかって、ある日突然脳死しちゃった……。
その人、まだ二十六だった……」
「あ…………所長、もしかして、そんな」
「だから、これは女の子の週一のイベントっつってん……でしょうが…………」
「……所長……。女の子って、何歳まで女の子なんでしょうか…………週一って、そんな頻度高いですっけ…………」
「そうそう……そのツッコミ…………待って…………」
嬉しそうにそう言いかけて有島は眠りにつく。
冷めると思って食器に蓋にして、数時間後にまた戻ってきたら有島がまだお粥に手をつけていないことに気づいた。
――彼女が自分と同じ赫碧症だと、この日初めて知った。
それでも次の日にはいつものように起きていつものように仕事する。傍目には元気そうにしか見えない。
元気そうにしか見えないだけに、水曜の憔悴しきった彼女とは別人のような気がしてならなかった。
◇◇◇
「一ヶ月後に週一のイベントは週二のイベントになった。新規の依頼は受けないことにした。熊谷さん、他の探偵事務所に案件の引き継ぎをお願いしに回った」