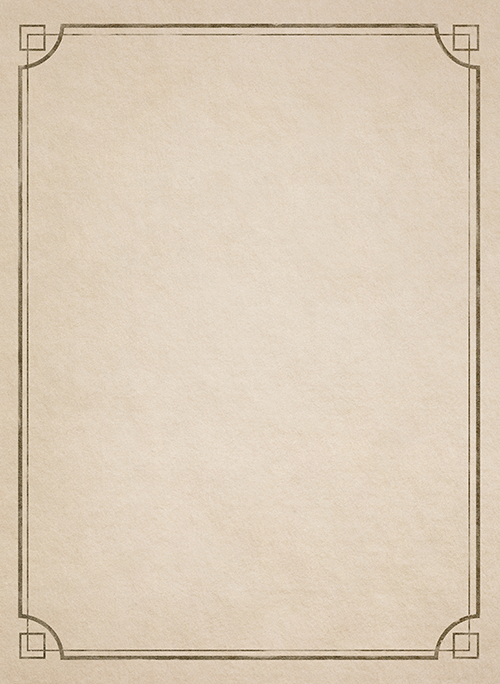●五月十四日(火曜)
「この度はありがとうございました」
孝子が会社の帰りに依頼料を支払いに来所した。
忍はお札の枚数を数え終わると「確かに」と言って封筒に戻し、予め用意していた複写式の領収書の一枚目の方を依頼人に手渡す。
「また何かお困りのことがあればいつでも相談にいらしてください」
「いえ……多分もう、大丈夫です」
孝子は忍に顔を、というより目を合わせづらそうに言う。
「そうですか。では、この度はご利用ありがとうございました」
ありがとうございました、と柊も続け、孝子は事務所を去って行った。
「……あのあと結局どうなったのか、話しませんでしたね」
「まあ良い報告があったら言うだろ。言わなかったらそういうことだろ」
「男性の方は気の毒でしたね。今までずっと気をつけて生活して、それでも赫眼になるのをいとわずに助けてくださったのに」
「そうだな」
「もう、恋愛はしたくないって思いますかね」
「そうかもな。
……まあしんみりしてもしょうがねーって! どうせ男女なんて別れるときゃ別れるんだから」
忍はソファから立ち上がってオフィスチェアに戻り、アームレストに肘をついて楽にする。
「晦さんの両親だって離婚してるんだろ。所詮血の繋がってない恋人なんて体とか、夫婦なら紙切れだけで繋がってるんだって」
柊は「あの」とおずおずと忍に声をかけた。
「海外に住んでるっていう父の話なんですが。本当は実の父じゃなくて、叔父なんです。
両親が死んで、叔父の養子になったんです。
――両親が、殺されたから」
忍がびっくりしたようなリアクションを――
――取ろうとして、やめた。
その代わり「あのさ」と申し訳なさそうに重く口を開く。
「実は晦さんの戸籍謄本が必要になった時、もう養子だって知ってたんだ。前は『樫井柊』って言うんだよな。
それで実の両親の名前……見覚えがあったから調べた。ごめん」
「あはは……そっか。戸籍謄本で全部バレちゃうんですね。うっかりしてました」
「じゃあ、やっぱり君は……」
「そうです。九年前のクリスマスイヴに起きた未解決事件――『樫井夫妻殺害事件』。その殺された被害者の娘が私です」
忍はただの書類置きと化していた丸椅子から書類を机の上にまとめて置いて、自分の前に動かして柊に「座りなよ」と促す。二人は座って向かい合う形になった。
「犯人が少年、それに殺されたのが赫保《かくほ》……赫碧症人権保障機関のトップ、そしてクリスマスイヴということもあって当時センセーショナルに取り上げられました。覚えてますよね、やっぱり」
「うんまあ……目撃された犯人と同世代だったから、心穏やかではなかったね」
「それで、その日犯人と鉢合わせになったことがあったんです。私が目撃者でした」
「よく無事だったな……」
「犯人は真夜中に庭の木を上って二階のガラスの窓を割って入ってきて、私の部屋も二階だったから聞こえたんです。
それに人の足音が聞こえて、怖くて……。
最初は布団かぶって、机の下に逃げて、足音が怖くて耳を塞ぐのに必死で……。
突然誰かが部屋に入ってきて微かにゴソゴソした音が聴こえて、その時は本当に生きた心地がしなくて……。
でも私に気づかなかったのかすぐに出て行ったんです。
それで数分して耳を塞ぐのをやめたら足音も聞こえなくなってて、もういなくなったんじゃないかと思って、すぐにでも両親の元へ行かなきゃって……」
「柊……」
「……それで両親の元へ急いで向かったら、二人はもう変わり果てた姿でした。
横たわった両親に駆け寄った私を部屋の外から犯人が見ていて、目が合ったらすぐにその場を離れたんです。
そうして一人取り残されて、玄関が閉まる音を聞くと糸が切れたように失神して、気づいたら警察署で……」
「柊、もうよせ……」
「そのあと、二階を物色した痕跡はあったようですが結局何も取られていなかったことを知りました。
それで犯人について世間に公表された内容は少年であることと身体的特徴だけだったんですけど、ひとつだけ伏せられたことがあったんです。赫保には都合の悪い内容でしたから。
――――どういうことか、お分かりですよね」
「……犯人は赫碧症で、お前が見た時赫眼してたんだな」
柊は「所長」と毅然とした態度で言う。彼女が心からの主張をぶつける前触れだった。
「あの人のこと、心のどこかで軽蔑してるでしょう。
でもみんながみんな、唯一依頼をキャンセルした人みたいにはなれないんです。あの人の反応の方が普通なんです」
忍は柊をじっと見る。心なしか彼女の目が潤んでいる気がした。
「私も、彼女の気持ちが痛いほど分かります。
……怖いんです。赫碧症の、しかも男の人がみんな両親の仇に見えてしまって。
もし好きな人が赫碧症だったら私、耐えられません」
「例えば俺がそうだとしても?」
「そうだとしても、です」
「あの依頼人みたいに、即離婚する?」
柊は俯いてその質問には答えようとはしなかった。
「でも、彼は何も悪いことをしてなかったんだ。愛する人を守ろうとしただけだったんだよ」
なのにあまりにも理不尽じゃないか。そんな彼のやるせなさを感じ取った柊は「じゃあ、所長」と話しかけ、「なに?」と忍も耳を傾ける。
「もし所長があの男性と同じ立場で、私が危ない目に遭いそうな時、嫌われるかもしれないと分かっていても、あの人みたいに迷わず助けに来てくれますか?」
実年齢よりちょっと年上に見られる彼だが、この時だけは少年を思わせる屈託のない笑顔で答えた。
「伴侶だからな」
「この度はありがとうございました」
孝子が会社の帰りに依頼料を支払いに来所した。
忍はお札の枚数を数え終わると「確かに」と言って封筒に戻し、予め用意していた複写式の領収書の一枚目の方を依頼人に手渡す。
「また何かお困りのことがあればいつでも相談にいらしてください」
「いえ……多分もう、大丈夫です」
孝子は忍に顔を、というより目を合わせづらそうに言う。
「そうですか。では、この度はご利用ありがとうございました」
ありがとうございました、と柊も続け、孝子は事務所を去って行った。
「……あのあと結局どうなったのか、話しませんでしたね」
「まあ良い報告があったら言うだろ。言わなかったらそういうことだろ」
「男性の方は気の毒でしたね。今までずっと気をつけて生活して、それでも赫眼になるのをいとわずに助けてくださったのに」
「そうだな」
「もう、恋愛はしたくないって思いますかね」
「そうかもな。
……まあしんみりしてもしょうがねーって! どうせ男女なんて別れるときゃ別れるんだから」
忍はソファから立ち上がってオフィスチェアに戻り、アームレストに肘をついて楽にする。
「晦さんの両親だって離婚してるんだろ。所詮血の繋がってない恋人なんて体とか、夫婦なら紙切れだけで繋がってるんだって」
柊は「あの」とおずおずと忍に声をかけた。
「海外に住んでるっていう父の話なんですが。本当は実の父じゃなくて、叔父なんです。
両親が死んで、叔父の養子になったんです。
――両親が、殺されたから」
忍がびっくりしたようなリアクションを――
――取ろうとして、やめた。
その代わり「あのさ」と申し訳なさそうに重く口を開く。
「実は晦さんの戸籍謄本が必要になった時、もう養子だって知ってたんだ。前は『樫井柊』って言うんだよな。
それで実の両親の名前……見覚えがあったから調べた。ごめん」
「あはは……そっか。戸籍謄本で全部バレちゃうんですね。うっかりしてました」
「じゃあ、やっぱり君は……」
「そうです。九年前のクリスマスイヴに起きた未解決事件――『樫井夫妻殺害事件』。その殺された被害者の娘が私です」
忍はただの書類置きと化していた丸椅子から書類を机の上にまとめて置いて、自分の前に動かして柊に「座りなよ」と促す。二人は座って向かい合う形になった。
「犯人が少年、それに殺されたのが赫保《かくほ》……赫碧症人権保障機関のトップ、そしてクリスマスイヴということもあって当時センセーショナルに取り上げられました。覚えてますよね、やっぱり」
「うんまあ……目撃された犯人と同世代だったから、心穏やかではなかったね」
「それで、その日犯人と鉢合わせになったことがあったんです。私が目撃者でした」
「よく無事だったな……」
「犯人は真夜中に庭の木を上って二階のガラスの窓を割って入ってきて、私の部屋も二階だったから聞こえたんです。
それに人の足音が聞こえて、怖くて……。
最初は布団かぶって、机の下に逃げて、足音が怖くて耳を塞ぐのに必死で……。
突然誰かが部屋に入ってきて微かにゴソゴソした音が聴こえて、その時は本当に生きた心地がしなくて……。
でも私に気づかなかったのかすぐに出て行ったんです。
それで数分して耳を塞ぐのをやめたら足音も聞こえなくなってて、もういなくなったんじゃないかと思って、すぐにでも両親の元へ行かなきゃって……」
「柊……」
「……それで両親の元へ急いで向かったら、二人はもう変わり果てた姿でした。
横たわった両親に駆け寄った私を部屋の外から犯人が見ていて、目が合ったらすぐにその場を離れたんです。
そうして一人取り残されて、玄関が閉まる音を聞くと糸が切れたように失神して、気づいたら警察署で……」
「柊、もうよせ……」
「そのあと、二階を物色した痕跡はあったようですが結局何も取られていなかったことを知りました。
それで犯人について世間に公表された内容は少年であることと身体的特徴だけだったんですけど、ひとつだけ伏せられたことがあったんです。赫保には都合の悪い内容でしたから。
――――どういうことか、お分かりですよね」
「……犯人は赫碧症で、お前が見た時赫眼してたんだな」
柊は「所長」と毅然とした態度で言う。彼女が心からの主張をぶつける前触れだった。
「あの人のこと、心のどこかで軽蔑してるでしょう。
でもみんながみんな、唯一依頼をキャンセルした人みたいにはなれないんです。あの人の反応の方が普通なんです」
忍は柊をじっと見る。心なしか彼女の目が潤んでいる気がした。
「私も、彼女の気持ちが痛いほど分かります。
……怖いんです。赫碧症の、しかも男の人がみんな両親の仇に見えてしまって。
もし好きな人が赫碧症だったら私、耐えられません」
「例えば俺がそうだとしても?」
「そうだとしても、です」
「あの依頼人みたいに、即離婚する?」
柊は俯いてその質問には答えようとはしなかった。
「でも、彼は何も悪いことをしてなかったんだ。愛する人を守ろうとしただけだったんだよ」
なのにあまりにも理不尽じゃないか。そんな彼のやるせなさを感じ取った柊は「じゃあ、所長」と話しかけ、「なに?」と忍も耳を傾ける。
「もし所長があの男性と同じ立場で、私が危ない目に遭いそうな時、嫌われるかもしれないと分かっていても、あの人みたいに迷わず助けに来てくれますか?」
実年齢よりちょっと年上に見られる彼だが、この時だけは少年を思わせる屈託のない笑顔で答えた。
「伴侶だからな」