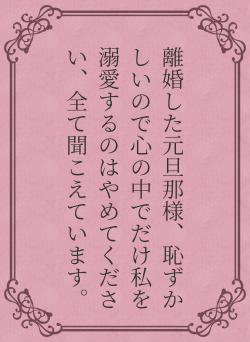ロスロズや他のバンドのライブ以外で、初めて二人で出掛けないかとの主旨のラインを、スマホ片手にうんうん唸りながら何とか文章にし、送信した。
すると大友にしては珍しい速さで、『どこに』と一言。。
大友の好きなところでいいと返すと、『ない』と弾丸のような速さで返信があった。
本当に二人で出掛ける気があるのかと不安になる。
僕の選んだところでいいかとの問いには『いい』。
これ以上大友から言葉を引き出すのは不可能だと悟った僕は「次の日曜日、午前十一時、例の喫茶店の前で」『了解』これだけのやりとりで終わらせた。
改めて大友のコミュニケーション能力の低さを痛感する。
僕やロスロズのメンバー以外に送ったら誤解を招きそうだ。
☆☆☆
率直に僕は、待ち合わせ場所に現れた大友に目を奪われていた。
裾に白いレースがあしらわれた黒を基調としたミニスカートに秋らしい細身のブーツを履いてポンチョみたいな形の白い上着を羽織っている。
ライブに行く時よりは抑え目だが、ゴシックな雰囲気は変わらない。
そんなお洒落な大友の横にいると、僕はいかにもファッションに無頓着な大学生という感じだった。
二人並んで歩き出すと、おもむろに一冊の文庫本を取り出して、大友は「これ」と僕に見せた。
「あ、それ」
「本屋で偶然見付けて買ったんだから」
それは僕も参加した、数人の作家が原稿を寄せた短編集だった。
新作がリリースされると必ず大友に渡すのがいつからかの習慣になっていた。
本好きの大友は、発売前の作品を読めると喜んでいた。
「忘れてた。次からは気を付けるよ」
バッグに本をしまいながら大友は少し怒ったようだった。
僕は小さく肩を竦める。
相変わらず大友の地雷はよくわからない。
「で、どこ行くの?」
溜飲を下げたのか、大友はぶっきらぼうに僕に聞いた。
「水族館。好きだろ」
「好きだけど。なんで」
知っているのか、と言いたいんだろう。
いつも通り言葉が足りない。
「創さんにリサーチ済み」
僕は小さく胸を張って言った。
「大友の歌詞全部読ませてもらったけど、空とか水とかよく出てくるよな。青好きなの?」
「好き」
「高校の頃よく空見てたもんな、屋上で」
「あれは暇だったからだけど・・・」
大友は付けていたネックレスのチャームを僕に見せると、「誕生石も青だし」と付け足した。
そのネックレスは亡くなったお父さんからの、最後のプレゼントらしい。
透き通った綺麗な青色の宝石だった。
「誕生日いつだっけ?」
「三月」
そんな知っていて当たり前の情報すら、僕たちは交わしたことがなかった。
「寺田は?」
「六月。
どっちももう過ぎちゃったな」
誕生日、か。
いつの間にか僕たちは大人になっていた。
初めて出会ったあの頃から何度誕生日を重ねただろう。
もう誕生日が無邪気に楽しみな年は過ぎてしまったのかも知れない。
「次の誕生日は一緒にいたいな」
ごく自然にぽろりと出た僕の言葉に、大友は僕を凝視し、少し俯くと「そうだね」と呟いた。
僕は心の底の歓喜を何とか押し留め、にやけそうになる唇に力を込めた。
「嬉しかったの」
俯いたまま大友は更に呟く。
「家族以外で自分のことをこんなに考えてくれる人がいるんだって感激したの」
僕はすぐにそれが、僕と一緒に流したあの涙の理由だと理解した。
同時に大友が、より深く心を開いてくれた気配がした。
あの時告げられなかった涙の理由を、今ならば、と。
感動に打ち震えているうちに、電車がやって来て、僕らは乗り込んだ。
座席に座ると、隣に僕がいるというのに、大友は先程の本を読み始めた。
ここまで空気が読めないともう個性だというしかない。
少し肌寒くなり始めた秋の澄んだ空気。
甘い金木犀の香りが鼻をくすぐる並木道を、並んで歩いた。
僕は、無防備な大友の左手をそっと握った。
寒さに反して緊張で熱くなった自分の右手で。
大友は拒絶反応を示さなかった。
僕は安心してその手に力を込める。
ちら、と眺めると大友の頬に朱が差し、恥ずかしそうに俯いている。
繋いだ手を、大友がぎゅっと力強く握り返してくる。
彼女も、僕と同じ気持ちでいてくれたら・・・これ以上嬉しいことはない。
ゆっくりたっぷり時間をかけて、僕らは同じ速度で歩いて行こう。
夢に破れても、現実に打ちのめされても二人で。
離れずにずっと。
こんな僕でいいのなら。
「茨」
勇気を出してそう口にすると、一拍置いて、満面の笑みで大友が笑った。