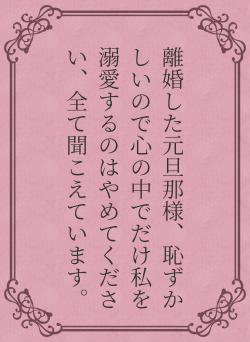卒業式も終わり、同級生たちが進学するのを多少は意識しながらも、僕が知らないうちに春が去って、窓から射す太陽光は狂暴なものに変わっていた。
あらゆる出版社の新人賞に応募するために次々と新たな物語を紡いでいく。
高揚感が常に僕を動かしていたと思う。
そんな中、大友から瑠奈さんがバンドに復帰したとの連絡を受けて喫茶店に向かった。
久し振りに会うロスロズのメンバー。
工事現場でバイトをしている創さんは健康的に焼けていて、光さんは変わらず中性的な美貌をしている。
大友は、勿論いない。
瑠奈さんは昔よりも濃いメイクにパンクファッションをしており、ピンクがかった髪をくるくると弄んでいた。
僕が席に着くと少しバツの悪い表情になった。
大学生になったはずだが、一体どんな心境の変化があったのだろう。
瑠奈さんは苦笑いしながら話し出した。
「いやあ、大学でうっかり軽音サークルに入っちゃってさ。
そしたら周りプロ目指してる人ばっかりで、感化されちゃって」
高校の時と変わらない朗らかで愛嬌のあるキャラクターに、僕たちは毒気を抜かれてしまって彼女を強く責める気にはなれなかった。
「久々に連絡したら創と光はまだバンド続けてるって言うからさ。戻れないかなーなんて」
「俺たちが断らないことくらいわかってたんだろうが」
溜息混じりの創さんに瑠奈さんが小さく舌を出して笑った。
「バレてた?
まあね、中学からの仲だからさ。
復帰させてくれるだろうなとは思ってた。
でもね」
そこで言葉を切ると、瑠奈さんは急に真面目な顔付きになった。
「大学もバンドもやり切ってみせる。
夢だけを追って大学辞めたんじゃロスロズ辞めた時と変わらないもん」
瑠奈さんは「そういえば」と、鞄からクリアファイルを取り出した。
「これ茨から参考にってもらった資料。
今度からあたしが作詞することにしたから」
資料というよりは、メモ書きに近いが、紙の束はそれなりの厚さがあった。
プリントアウトした用紙には、規則性のない言葉がずらりと並び、中には適当な表現が見付からなかったのか、もどかしく文章で綴られているものもあった。
「お前バンドのこと茨に言ってんのか?
酷じゃねぇ?」
光さんが言うと、「茨は友達だもん。バンドのことも知りたがってるし」と瑠奈さんはあっけらかんと言い返した。
僕は用紙を何枚か眺めて、閃くものがあった。
これは使えるかもしれない。
この資料にある言葉を使っていいか尋ねると、「全然大丈夫」と力強く言ってもらえた。
「ロスロズの復活をまずは知ってもらうためにチラシ刷ろうよ 」
「経費がかかるな」
「いいじゃん。あんたたちバイトしてるんでしょ」
その夏、地元でも有数の人気があったロックバンド、ロスト・ローズは正式に復活を果たした。
ドラムの居ない路上ライブも再開された。
ロスロズの夏はドラム探しと曲作りに明け暮れた。
大友にも動きがあった。
デモテープを作るために、創さんが大友にドラムを叩いてくれないかと持ち掛け、了承してもらったという。
瑠奈さんによると、大友は通勤電車の中で曲を覚えてレコーディングに臨むという。
大友のスケジュールに合わせてスタジオを予約し、録音することとなった。
「寺田くん、無料で配るデモテープとチラシ配り手伝ってくれない?
お礼はするからさ。
そうだ!レコーディングに遊びに来なよ!」
という瑠奈さんの一声で、僕もスタジオに入らせてもらうことになった。
大友はTシャツにミニスカートという出で立ちで、相変わらず綺麗な黒髪で、少し疲れたような顔でやって来た。
バンド時代のような溌剌とした表情はもう見られないのかもしれない。
それは、一足先に大友が大人になるということでもあった。
少し寂しくて僕は感傷的になる。
しかし大友は、久し振りに触る楽器を念入りにチューニングすると、まるで昔のように、髪を振り乱して力強く叩き始めた。
腹に刺さる低音。
五回ほど通して叩くと、ブースの外から納得したように創さんがOKを出した。
ブランクを感じさせないプレイ。
大友はスティックを置くと息を切らしていた。
その時、僕は見てしまった。
大友がいとおしそうにドラムに触れて、微笑む柔らかな横顔を。
恐らく、一生忘れないだろう大好きな人の美しい笑みを。
☆☆☆
レコーディングに立ち会ったあの日を最後に、ロスロズのメンバーや大友と会うことはなくなった。
焦っていないとは言えない時期を迎え、壁からカレンダーを外した。
食事と寝る時間以外はまるで受験生の頃に戻ったかのように執筆に没頭した。
時が経つのは本当に早く、僕の夢の集大成が近付いているのを肌で感じていた。
秋も終盤になった頃、机の上のスマホがうなり声をあげた。
見たことがない番号からの着信だった。
「英文社の元木と申します」
聞いたことがない男性の声だった。
電話の内容を纏めるとこうだ。
春先に応募した作品が、コンテストの最終選考まで残り、受賞は逃したものの、編集者の元木さんの目に留まった。
大幅な加筆や修正は必要だが、僕の作品を本にして出したいという。
僕はすぐに飛び付いた。
のちに、秋に応募した作品が短編賞を受賞していたこともわかった。
大友の書いたメモに刺激されて書いた作品だった。
僕はついに夢を叶えたのだ。
まだ全然実感は沸かないが、ただ純粋に文章だけの力で、顔も知らない誰かに、僕という人間の存在意義を認めてもらえた気がした。
承認欲求が満たされる。
この嬉しい気持ちを、何を差し置いても伝えたい人がいた。
大友。
勤務中であろう大友に、ラインで事の次第を書きつづって送る。
しばらくすると、「おめでとう」という簡素な言葉と、週末に会いたいという、珍しい大友からの誘いが書かれていた。
僕は初めての経験に、世界が変わる予感を覚えていた。
好転する。
努力は報われる。
決して裏切ったりなどしない。
大友に、会いたかった。
すぐに返信した。
☆☆☆
いつもの喫茶店で待ち合わせると、大友は僕に小ぶりな箱を差し出した。
僕は不思議に思いながら受け取ってラッピングを解いていく。
中身はブルーライトカットの眼鏡だった。
「寺田、いつもパソコン見ながら目が痛いって言ってたから。
仕事帰りに買って来たの。
ショボいけど出版記念」
忙しさにかまけて買いに行くのを先延ばしにしていたものだった。
「どう?自分の本が出る感想は」
僕は頭を掻きながら、「まだ実感ないよ」と返すしかなかった。
そう。
ネガティブにも僕は夢の実現を信じ切れず、まだどこか他人事のような気分になっていた。
「おめでとう」
僕の目を真っ直ぐ見て、大友は笑った。
思わず、彼女を抱き締めてしまいそうになる。
僕は目をそらし、暫し迷いながらも、勇気を振り絞って尋ねた。
「大友は、もう音楽はやらないの?」
すると大友は、少し寂しげに小さく笑った。
「現実を見ちゃうとね・・・難しいと思う、続けていくのは」
そして「それに」と続けて軽く肩を竦めて見せた。
「熱が冷めたんだと思う。
創たちみたいにメジャー目指すっていうエネルギーが削られたっていうのかな。
あたしはもうあんな風に熱中出来ないよ。
デモテープ聴きながら、これで最後のプレイにしようと考えてた。プレイヤーではなく、いちリスナーに戻ろうって」
不意に思い出した。
レコーディングの時にドラムに触れていた横顔。
あれは、音楽をこれからも続けようという笑みなのではなく、最後を決意した惜別の笑みだったというのか。
僕は喫茶店で二人で過ごした時間を思い出していた。
彼女がいなければ出来なかったかも知れない物語。
「そんな・・・そんなの不公平だ」
大友だけが夢への熱を奪われるなんて。
不覚にも、僕はボロボロと涙を溢していた。
「夢を叶えたあんたが何で泣くのよ」
大友が苦笑いしながらハンカチを差し出した。
涙を拭こうと顔を上げると、大友が泣いていた。
本人も驚いたようで、不思議そうに頬を拭っていた。
「寺田のバカ」
大友は小さく呟いたが、その意味は教えてくれなかった。
☆☆☆
僕が一年遅れの大学生活を迎えた頃、『ドラムが決まった』という一行だけのラインが届いた。
大友が戻る場所は正式になくなった。
僕は創さんにスケジュールを訊いて、出来る限り大友を誘ってライブに足を運んだ。
元々、地元で人気のあったロスロズは、新ドラムが加入して二ヶ月でワンマンライブを行い、僕や大友は見届けられなかったけれど、それから半年が経つ頃には、メジャーから声が掛かった。
僕も大友も忙しくなり、ラインや電話で連絡を取り合うことしかしなかったけれど、ライブに行っては瑠奈さんの甲高いシャウトと腹にズシリと来るバンドサウンドに乗せられて、汗をかくくらいジャンプしたり大声で歌ったりと特別な非日常を満喫していた。
ロスロズは夢へと順調に漕ぎ出していた。
☆☆☆
僕の大学生活も折り返しを少し過ぎた頃、ロスロズはメジャーで結果を出せず、解散の道を選んだ。
メンバーのその後については、僕はよく知らない。
ただ、彼らのリリースしたシングルやアルバムを聴く度に、やるせなさが残った。
こんなに格好良い音を奏でるバンドなのに、契約を打ち切ったレコード会社はわかっていない、と一人憤慨する。
僕は新作の題材を、バンドを結成し様々な壁や困難にぶち当たりながらもメジャーデビューし、人気バンドにのし上がった音楽に懸けた女の子を主人公にした小説を書いた。
主人公のドラムは、とびきりの美人にした。
少し青臭くて幼稚かな、とは思っていたが、その本は書店員が推薦する書籍を選ぶコンテストの賞を受賞した。
タイトルはロスト・ローズだ。
せめて本の中でだけでも、彼らには成功してほしかった。
そばにいた僕にしか書けない彼らの眩しい青春。
その貴重な日々を形あるものに刻み付けたい。
もう戻らないひたすらに夢を追い掛けたあの頃を絶対に忘れたりしないように。