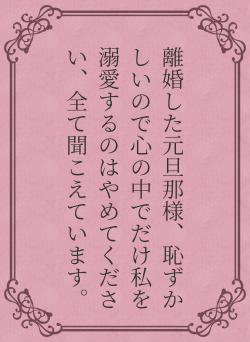高二になってしばらくすると、大友の欠席が目立つようになった。
クラス替えで、僕と大友は同じクラスに、大友健が別のクラスになったので、屋上まで大友を迎えに行くこともなくなった。
あの頃より大友とは親しくなったけど、もう戻らないあのひりひりした関係を、一方で恋しくも思う。
大友は、学校を休んで三つバイトを掛け持ちしているという。
お父さんが病に倒れて入院しているため、その入院費と生活費を賄うために大友が働くしかないという話だった。
お母さんは、体が弱く家事をこなすだけで精一杯らしい。
そんなことを、久々に登校した疲れた顔の本人に聞いた。
それでも、バンドの練習には顔を出しているという。
創さんが見つけてきたサポートギターの手を借りてロスロズは何とか存続していた。
☆☆☆
桜はとうに散り終わり、辺りはむせ返るほどの眩しい緑に包まれていた。
鼻で感じる日光の温かさ。
そして、夏の暑さを予告するような直射日光に澄んだ空。
衣替えの直前。
もうすぐ、僕とロスロズが出会って一年が経とうとしていた。
一年前と違うのは、本気で夢を掴もうと、執筆活動を本格化したこと。
眩しいロスロズのメンバーに触発されて、僕の足はもつれながらも進み出した。
相変わらず成績は良いようで、教師陣は何も言わないが、大友の欠席は問題視されつつあった。
☆☆☆
絡み付くような蒸し暑さが始まる頃。
大友がぱったりと学校に来なくなった。
初めのうちは、お父さんの病気が悪化したのかもしれないと心配していたが、一週間、二週間と経つ内、嫌な予感が胸中で膨らんだ。
僕は職員室に向かった。
担任の広間先生のところだ。
広間先生はまだ若い男性の先生だった。
僕は、やや声を落として言った。
「先生、大友のことなんですけど」
「ああ、大友な」
広間先生は眉をしかめて僕を見た。
「ずっと休んでるようですけど、何かあったんですか」
「何だ、知らないのか」
先生は声を低くして言った。
「大友なら退学したよ」
僕の背中を、身体を、全神経に衝撃が走った。
「何でも親父さんが亡くなって高校どころじゃなくなったとか」
お父さんが亡くなって、お母さんが働けなくて、大友ひとりに背負いきれるものなのだろうか。
いつだって颯爽と前を向いていた大友。
そんな大友の姿を思い浮かべたら、何故だか自然と涙が出て来た。
何だか、無性に悔しかった。
☆☆☆
その姿を探すように、僕は連日ある場所へ通い詰めた。
やがてようやくその黒髪に辿り着いた。
いつもの喫茶店。
ただ憂いを帯びた眼差しでストローをくわえている大友は、それだけでモデルのように様になっていた。
大友は店に入って来た僕に気が付くと、気まずそうに下を向いた。
テーブルには、数冊の本が積まれている。
「大友」
声を掛けると、大友はのろのろと顔を上げた。
「寺田・・・」
大友は、制服姿の僕を懐かしそうに見つめ目を細めた。
「この店、まだ使ってたんだ」
「ここにいるとね、ドラムの音や歓声が時々聞こえてくるの」
僕は正面に座りながら本類に目を落とした。
久々に大友に会えたことへの興奮を押し隠しながら冷静を装って言った。
「資格の勉強?」
「そう。正社員になるためのね」
「バイトだけで大変なんじゃないの。そんなに働かないといけないの」
「あたし一人ならどうとでもなるんだけど二人じゃあね。
あたしがまだ高校にいた頃、お母さんお弁当の仕出しの仕事始めたんだけど、二週間で倒れちゃって。
肺炎になって入院して大変だったんだ。
その時は貯金があったけど、ずっと貯金を切り崩して食べて行けるほど裕福じゃないし。
何の資格もない高校中退じゃ時給の安いバイトしか雇ってもらえないし」
カラン、と音を立てて汗をかいたグラスの中で氷が溶ける。
「学校、辞めちゃったんだね」
「仕方ないよ。
これもなんかの運命なんだろうし。
でもね、資格取ったら親戚の会社で雇ってくれることになってるの。
そうすればバイトの掛け持ちも必要ないし。
その点は恵まれてると思う」
僕はどう返したらいいものか悩みながらそれでも口にした。
「ロスロズは、続けるんだよね?」
「まあね。今のところは。ただ就職したらどうか分からない」
飄々とした調子で不確実な将来を語る大友を、何故だか不安定だと感じた。
一瞬訪れた沈黙を慌てて埋めるように、僕は前から聞いてみたかった事を口にした。
「大友は、何でドラムを始めようと思ったの?」
すると、大友は頬を紅潮させ、初めて見る表情で饒舌に喋り出した。
「父親の影響でね、小さい頃から色んなジャンルの音楽を聴いてたの。
その中で一番惹かれたのがロックで。
病んだ時、救ってくれる音楽って詞のことかと思ってたけどメロディも凄く大事で。 ギターに憧れて楽器店に行ったんだけど、展示されてたドラムセットに一目惚れしちゃったんだよね。
カッコ良くない?
自分でカスタムできて要塞みたいで。
メロディを支える縁の下の力持ちっぽくてさ。
でも音楽を支配してるみたいな。
小四の頃からドラム教室に通わせてもらって。
うち、お金なかったからそれが唯一の習い事。
中学になってからは音楽室のドラム貸してもらうようになって、CD貸してくれる軽音部の友達も出来て。
それが今のメンバーなんだけど」
一息に喋った大友は、クールダウンするようにアイスティーを一口含んだ。
僕は、初めて知った彼女の一面に、何故か妙な敗北感を味わっていた。
これだけ一緒に過ごしていても、僕は大友のことを全く知らなかったのだ。
「寺田は?」
「え?」
呆けていると、意識の外から質問が投げ掛けられた。
「寺田の将来の夢」
将来の夢。
何て幼稚な言葉だろうと思った。
僕は目を逸らしつつ。
「笑わない?」
「笑うような夢なの?」
真剣な表情になって大友は言った。
「作家になりたいんだ。
無理だってのはわかってるんだけど」
すると大友は苦笑いをして告げた。
「メジャーになりたいなんて夢を恥ずかしげもなく目標にしてるあたしたちが、笑えるわけないでしょ」
大友は、僕の夢を聞いても笑わなかった。
肯定さえしてくれた。
意外なほど恥ずかしさは感じなかった。
大友なら、おおらかに受け入れてくれるような気がしていたのだ。
それにしても、大友はつまらなそうに屋上で寝転んでいた時には考えられないほどに表情豊かでとっつきやすかった。
どうして、学校でこの表情をしなかったのか。
そうすれば、敬遠されることもなく、友達だって出来ただろうに。
途方もなく実現不可能に限りなく近く、あるいは失笑を買ってしまうような夢みがちな目標。
でも大友は、頭ごなしに否定したりはしなかった。
僕の夢も、自分の夢も叶うと信じている。
だからこそ大友は、こんなにも眩しいのだ。
誤解させられてしまうほどに。
この日を境に、僕は時間を作っては喫茶店に通い、勉強する大友の正面で執筆活動に勤しむようになった。
ロスロズに引っ張られるように、僕は自分を信じてみようと思った。
ロスロズは僕の夢の指針だった。
☆☆☆
大友のいない夏休みが始まろうとしていた。
僕は、一日の休みもない夏期講習に連日追われていた。
そのくらいしなければ、受かる脈のない大学を志願していたからだ。
味気のない日々に辟易していると、アドレスを交換して以来一度も連絡がなかった瑠奈さんからラインが届いた。
ロスロズについて重大な話があるから、立ち会って欲しいという。
バンドと関係がない僕が行っていいものか悩んだが、無下にするわけにもいかず、いつもの喫茶店へと向かった。
店内にはすでに、メンバーが揃って僕の到着を待っていた。
こほん、と一つ咳払いをすると、髪を真っ黒に染めた瑠奈さんは、ガバッと突然頭を下げた。
「本当ごめん!バンド辞めたいんだ」
余りのことに僕が呆然としていると、瑠奈さんは早口に喋り始めた。
「親にはずっとバンドは反対されてたんだよね。
そんなので食べて行けるわけないって。
あたしも意地になってたんだけど、もう高二だし、将来のことを考えると、バンドで売れるのは難しいかなって」
「プロになるって言ってたじゃねえかよ」
バンドのお兄さん的存在の創さんが静かに、でも隠しきれない怒りを滲ませた口調で瑠奈さんを責めた。
大友は、人形のように無表情だった。
「本当ごめんね。じゃあ」
と言って、瑠奈さんは有無を言わせぬ迫力で店を出て行った。
カランカランと扉の開閉を知らせるベルが鳴る中、僕は瑠奈さんはズルいと思っていた。
バンドと関係ない僕がいる手前、大友と創さんは瑠奈さんを強く責められない。
「新しいボーカルとギターを探せばいい」
ぼそっと大友が呟いた。
それに対して創さんは棘のある口調で言った。
「お前だってバイトで全然、練習来ねえじゃねえか」
「週末は空けておくよ。あんたが目をつけたギターに会いに行く」
創さんは苛立たしげに髪をかきむしると、「もういい」と伝票を手に取り会計を済ませて店を出て行ってしまった。
☆☆☆
迷い、だろうか。
その秋、僕の成績は教師が心配するほど、トップクラスから大幅にランクを落とした。
それを知った両親の憤怒は並みではなかった。
仕事から帰って来た父親は、成績表を見ると、「何があった?」と静かな怒気を孕んだ声で問うてきた。
「最近帰りも遅いし悪い友達でも出来たんじゃないの?」
と、母親は困惑気味に言った。
悪い友達・・・大友たちは悪い友達なんだろうか。
確かに、最近の僕は塾の帰りにあの喫茶店に足を運んでいる。
そこに行けば誰かしらがいたからだ。
けれど、成績低下の原因に大友を関わらせたくない。
僕は鞄からプリントアウトした用紙を取り出し父親に手渡した。
手が震えた。
羞恥と恐怖心とで。
「小説大賞?こんなものを書いているのか」
母親も父親の手元を覗き込んでヒステリックに叫んだ。
「小説家になんてなれるわけないでしょう!
高二にもなってそんなこともわからないの?」
「昇、お前が目指しているのは難関校だな。
こんな成績で受かると本気で思っているのか」
思ってなど、いない。
本来ならば、椅子に身体を縛りつけて、寝ないで勉強しなければ、僕ごときが、到底受かる大学ではない。
僕は、天才じゃない。
人一倍努力しなければ志望校には受からない。
僕は不器用だった。
ふたつのことを同時には出来なかったのだ。
自覚はなかったが、小説にのめり込むあまり勉強が疎かになっていた。
肝心の夢のほうは、推敲に推敲を重ねた原稿を手当たり次第賞に応募したのだが、結果は落選続きだった。
僕の夢もまた遠ざかった。
気合いを入れ直し、まずは志望校に合格するために猛勉強を始めた。
☆☆☆
いつもの喫茶店で、執筆に代わり勉強をしていると、向かいの席で頬杖を付いて窓の外を眺めていた創さんがぼそりと言った。
「寺田は特別なんだな」
「え?」
僕は勉強の手を止めて、目の前に座る彼を見た。
「茨だよ。
あいつ友達いないだろ。
昔俺に、人付き合いは面倒だってはっきり言ったことがあるんだよ。
俺たちとは音楽の趣味が合ったから喋るけど・・・。
寺田には心を開いている気がする」
正直、物凄く嬉しかった。
頬が緩むのがわかった。
その時の僕には、それが何の感情なのか、良くわからなかったけれど。
しかし、喜びを顔に出すのが不謹慎なほど、創さんの顔はしかめられていた。
「終わりかもな、俺たちはもう」
そんな最後通告のような言葉に戸惑った数時間後、大友からラインが届いた。
『ロスロズ解散』
衝撃と諦めがない交ぜになった心地で返信をためらった。
どんな言葉をかければいいのか、全くわからなかった。
そしてそれは、僕に返信を迷わせないための、たった一行の半ば突き放すような物言いなのだと気付いた。
返信は必要ないのだと。
大友なりの優しさだったのだろうと思う。
夢半ばで挫折したロスロズ。
いつだって僕の夢は彼らとともにあった。
ロスロズが混迷した時、僕の夢も迷子になった。
ロスロズが、大友茨がいない。
消えてしまった。
僕はどうすればいい?選ぶ道を、誰が決めてくれるというのだろう。