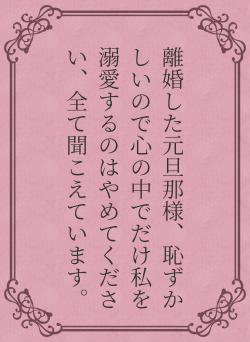「井上・・・上原・・・大友」
教室はしん、と静まり返った。
鞄が置かれた空席を一瞥すると、担任の教師は僕をちらりと見やった。
僕はそれを合図に立ち上がると教室を出る。
廊下を歩きながら何の気なしに他のクラスの様子を横目に見て、向かうのは屋上だ。
固い扉を押し開けると、衣替えした太陽が容赦なく降り注いでいた。
「大友」
日光浴でもするようにそこに寝転んでいた少女が顔を上げた。
黒くて艶のある長い髪、開けられたブラウスのボタン。
高校に入学して約二ヶ月。
僕が屋上に出向いて、彼女を教室に呼び戻しに訪れることが日課となっていた。
朝の暴力的な白い光に包まれながら、大友の大きな黒目がちの瞳が僕を捉える。
「大友、出欠終わったよ」
「わかった」
伸びをして立ち上がると、制服についた砂ぼこりを払い、僕の横をすり抜けて階段を降りていく。
彼女の短いスカートが揺れるたびにドキリとして、僕は思わず目を逸らした。
色濃く残る昨夜の雨の匂いと、ここぞとばかりに萌える緑が溢れるグラウンドを見下ろす。
まだ梅雨が始まったばかりだというのにお構いなしに照り付ける朝陽にほんの一瞬目眩をさせられる。
猫みたいだ、とこれもほんの一瞬彼女のことをそんなふうに思った。
僕のクラスには、高橋姓が二人、大友姓が二人いる。
全員に血縁関係はなく、偶然同じクラスになっただけのようだ。
一人は大友健という男子生徒で、もう一人が僕が出迎えるのが日課となっている少女、大友茨である。
一度、彼女に何故ホームルームの時間だけ教室にいないのか尋ねたら、彼女は「自分の名前が大嫌いだから」と言った。
大友健と区別するためフルネームで呼ばれるのが耐えられないという。
大友の名前嫌いは徹底していて、授業中、自分をフルネームで呼んだ先生に指されても、絶対に答えない。
噂では、大友は成績は良いらしく、多少の生活態度の悪さは許容され、その頑なな姿勢に教師陣も大友を指さなくなったほどだった。
やがて大友の行動パターンが読めてきた。
大友は登校して鞄を机に置くと、屋上に行く。
僕の知る限り友達はいない。
昼休みになると弁当箱を片手に図書館の隅でヘッドフォンを装着して目を閉じている。
寝ているのかどうかは分からない。
放課後は校舎を徘徊している。
様々な部活を見学したり、一度僕が生徒会の仕事で遅くなったとき、教室の窓からグラウンドを見つめる大友に遭遇した。
彼女は何も言わず僕を一瞥すると視線を戻した。
そんな猫のような変人、大友に対して、僕は絵に描いたような優等生だ。
持ち前の真面目さでクラス委員長に満場一致で選ばれた。
しかし、僕の心中は穏やかではなかった。
僕、寺田昇という人間はつまらないと言われているようなものだったからだ。
銀行員の父親に元教師の母親に公務員になることを望まれている。
しかし、僕には諦められない夢があった。
作家になること。
その夢に向かって何でも吸収するため勉強も苦ではない。
塾にも行かせてもらっているし、大学にも行くつもりだ。
でも、その先は・・・。
僕は自分の書いたものだけで食べて行きたいと思っている。
無謀で非現実なこの夢を、僕は両親に言い出せずにいる。