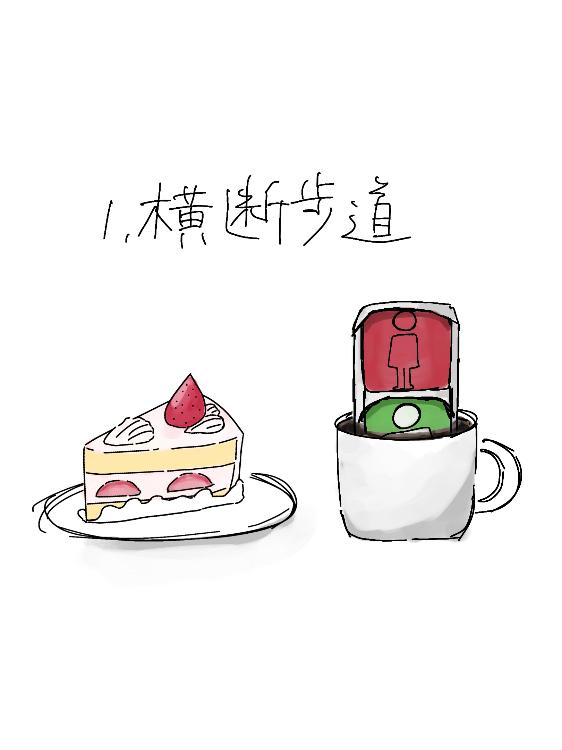横断歩道
「私はね、小さい頃からずっと横断歩道が怖いの」
彼女はそう語る。彼女の行きつけの個人経営の喫茶店でコーヒーを啜りながら彼女の話を聞いていた。
「ずっと、ずっと怖かったの。なんでかは分からない。けどね、私が持ってる一番昔の記憶も横断歩道を怖がっている記憶なの」
彼女の話を流しながらコーヒーに砂糖と少し入れとく。あまりにも苦かったからだ。それを見て彼女も自分のコーヒーに砂糖を入れた。
「国道にあるような長い横断歩道は勿論のこと、幅の狭い道に適当に引かれた3歩歩けば渡れちゃうような横断歩道だって怖い」
まだ苦い。こんな事なら調子乗ってブラックコーヒーを頼むんじゃなかった。後悔先に立たずだ。
「一緒に渡る人が多かろうとも少なかろうとも変わらない。何かずっと嫌な予感がするの」
「ご注文のショートケーキです」
店員さんがショートケーキの二切れ持って来てくれる。礼をしながら店員さんが立ち去るのを待つ。そして。彼女の所にもショートケーキを置き食べ始める。
「どんな感じなんだろ……口では説明しにくいんだけどね……。そうだ、夏の怪談話ってな感じかな。和風な怖さ。」
ショートケーキの苺は最後に食べる派であるがどうやら彼女は先に食べる派だそうだ。
「だからいっつも回り道してどうにか歩道橋がある場所を探すんだけど中々無いよね。だから向こう側に行けないの……。さながら陸の孤島に取り残された可哀想な美女ね。」
ショートケーキのホイップがふわふわで口の中に溶けていく。小さい頃に雪を食べた感覚と似ている気がする。まぁ、その後お腹を壊して高熱を出してで散々だったけれども……
「けど、やっぱり怖いばっか言ってないで渡らなきゃ行けない時が人生あるじゃない?そんな時は目を瞑って息を止めるの。そうずれば誰にも見つからないんじゃ無いかなって。けど、長い横断歩道じゃおすすめしないよ。死ぬかと思った。」
ショートケーキは乗っていた皿はすっかりケーキ敷紙とフィルムしか残っていなかった。本当はもう一つ食べたい所だが意外と値段は張るし彼女の奢りなので控えておく。彼女の方のショートケーキもチラ見したが同じような状況だった。
「何か原因分かる?……ってかちゃんと聞いてた?」
「聞いてたよ。えっと、コーヒーが苦くてショートケーキをおかわりしたい。って話でしょ?」
「全然違う!!横断歩道が怖いって話だよ!!!」
「ああ、そんな事も言ってたっけ……?。う〜ん……それって音楽のせいじゃない?」
「音楽……?」
「ほら、最近だと鳥の鳴き声のものが増えて来ている気がするけどたまに『通りゃんせ』が流れる信号があるじゃん?その歌が少し怖いからそのイメージが付いたんじゃ無い?」
彼女は何か考え込むようにして窓から見える横断歩道を見つめる。その横断歩道が丁度青になってメロディが流れそれが店内にも小さいながらも聞こえてくる。
「ほんとだ。この感じ、めっちゃ怖い。これかぁ〜……なんかスッキリしたよありがとう。」
「どう致しまして〜奢ってくれたからね。お礼みたいなもんだよ」
「覚えてたの!?……まぁ、そうだよね……うぅ……二人分となると結構値段張るなぁ……」
「そんな日もあるよ」
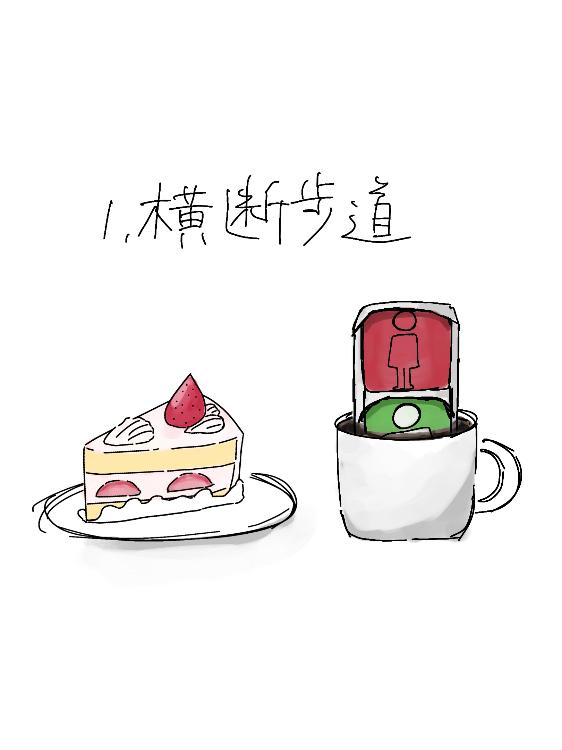
「私はね、小さい頃からずっと横断歩道が怖いの」
彼女はそう語る。彼女の行きつけの個人経営の喫茶店でコーヒーを啜りながら彼女の話を聞いていた。
「ずっと、ずっと怖かったの。なんでかは分からない。けどね、私が持ってる一番昔の記憶も横断歩道を怖がっている記憶なの」
彼女の話を流しながらコーヒーに砂糖と少し入れとく。あまりにも苦かったからだ。それを見て彼女も自分のコーヒーに砂糖を入れた。
「国道にあるような長い横断歩道は勿論のこと、幅の狭い道に適当に引かれた3歩歩けば渡れちゃうような横断歩道だって怖い」
まだ苦い。こんな事なら調子乗ってブラックコーヒーを頼むんじゃなかった。後悔先に立たずだ。
「一緒に渡る人が多かろうとも少なかろうとも変わらない。何かずっと嫌な予感がするの」
「ご注文のショートケーキです」
店員さんがショートケーキの二切れ持って来てくれる。礼をしながら店員さんが立ち去るのを待つ。そして。彼女の所にもショートケーキを置き食べ始める。
「どんな感じなんだろ……口では説明しにくいんだけどね……。そうだ、夏の怪談話ってな感じかな。和風な怖さ。」
ショートケーキの苺は最後に食べる派であるがどうやら彼女は先に食べる派だそうだ。
「だからいっつも回り道してどうにか歩道橋がある場所を探すんだけど中々無いよね。だから向こう側に行けないの……。さながら陸の孤島に取り残された可哀想な美女ね。」
ショートケーキのホイップがふわふわで口の中に溶けていく。小さい頃に雪を食べた感覚と似ている気がする。まぁ、その後お腹を壊して高熱を出してで散々だったけれども……
「けど、やっぱり怖いばっか言ってないで渡らなきゃ行けない時が人生あるじゃない?そんな時は目を瞑って息を止めるの。そうずれば誰にも見つからないんじゃ無いかなって。けど、長い横断歩道じゃおすすめしないよ。死ぬかと思った。」
ショートケーキは乗っていた皿はすっかりケーキ敷紙とフィルムしか残っていなかった。本当はもう一つ食べたい所だが意外と値段は張るし彼女の奢りなので控えておく。彼女の方のショートケーキもチラ見したが同じような状況だった。
「何か原因分かる?……ってかちゃんと聞いてた?」
「聞いてたよ。えっと、コーヒーが苦くてショートケーキをおかわりしたい。って話でしょ?」
「全然違う!!横断歩道が怖いって話だよ!!!」
「ああ、そんな事も言ってたっけ……?。う〜ん……それって音楽のせいじゃない?」
「音楽……?」
「ほら、最近だと鳥の鳴き声のものが増えて来ている気がするけどたまに『通りゃんせ』が流れる信号があるじゃん?その歌が少し怖いからそのイメージが付いたんじゃ無い?」
彼女は何か考え込むようにして窓から見える横断歩道を見つめる。その横断歩道が丁度青になってメロディが流れそれが店内にも小さいながらも聞こえてくる。
「ほんとだ。この感じ、めっちゃ怖い。これかぁ〜……なんかスッキリしたよありがとう。」
「どう致しまして〜奢ってくれたからね。お礼みたいなもんだよ」
「覚えてたの!?……まぁ、そうだよね……うぅ……二人分となると結構値段張るなぁ……」
「そんな日もあるよ」