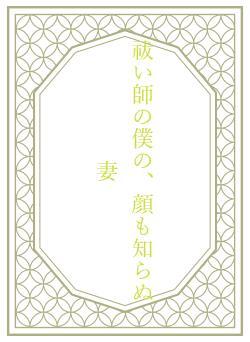カーテンの隙間から入り込んできた朝日が目に掛かり、起きろと急かして来る。
尤も、カーテンには所々穴が開いていて、その役割はあまり果たしていないが。
目を開けると、隙間から入り込んだ光に沿って部屋に舞った埃が強調される。
掃除も碌にしないので、部屋の隅には蜘蛛の巣が張り巡らされ、
床板も虫に食われたのか、穴が開いて下から風が入ってくる。
更に足を乗せれば軋んで、ギシギシと音を立てる。
ベッドも動くたびにギシギシと音を奏でるので、起きるときや寝るときは特に軋みの大合唱である。
それなりの大音量なので、朝は目覚まし時計代わりになってちょうどいいかもしれない。
今日も軋む音を聞きながら、部屋に三つあるドアの内の一つを開けて入る。
そこにはシャワーと洗面台が取り付けられている。
どちらも、これまた年季が入っていて、変な所から水が出ることがある。
そして、古いからか、それとも後付けの物だからか、今日のような極寒の冬場でも冷たい水しか出ない。
最初の頃は凍えそうになったものだが、今では慣れた。
顔を洗って、掛けてあったタオルで軽く拭く。
そのタオルもザッと水を通して、太陽の光がよく入る場所に置いておく。
そんな感じで、匂いも汚れもさほど取れず、タオルはいつも生乾き状態だが、生憎と洗濯物の洗剤は持ち合わせていないのだ。
頼めば支給してくれるだろうが、“あの人たち”との交流はなるべく避けたい。
ベッドが置かれている部屋に戻ってしばらくすると、シャワー室とは別のドアの向こうからベルの音がした。
けれどすぐには開けず、ドアに耳を当てて、人の気配がなくなってから静かに素早くカートを中に入れる。
二段あるカートの一番上は今日の朝食、二番目は諸々の消耗品・日用品が置かれていた。
取り敢えず、朝食を頂くことにする。
大小さまざまなお皿が乗ったトレーを持って、ベッドのヘッドボードの方にある台形出窓に行く。
ベッドと同じ高さに揃えられた出窓ベンチは、数段上って、ゆったり座れる広さがある。
この部屋で唯一のお気に入りの場所。
ボロボロのカーテンを少しだけ開けて、朝日を浴びながらご飯を食べるのが日課だ。
正座した膝の上にトレーを置いて、いただきますと手を合わせる。
フォークを手に取って、まずはサラダを口に運ぶ。
レタスがシャキシャキと音を立てて、その新鮮さを伝えてくる。
次はスプーンを持って、湯気を上げた豆スープを口に含む。
冷えた体に、温かさが染みわたっていく。
「おいしい…」
思わずそう声を発してしまうほど、温かいスープは冬に重宝する。
声を出したのは数日ぶりだ。
ずっとこの部屋に籠っていて話し相手もいないし、今のように無意識に出なければ独り言もほとんどない。
子供特有の少し高めな声は、比較する相手がいないので、少し掠れていることに本人は気づいていない。
埃と乾燥、さらに声帯を使わないことの結果である。
八歳にしては達観した目つきと、少々コケた頬。
体も、決して健康とは言えない。
けれど、ここに籠っているのは自分の意思だ。
閉じ込められているわけではない。
むしろ部屋の外へ連れ出そうと“あの人たち”は今も思っているはずだ。
四歳の時に籠るようになってから、早四年。
もう、ここを去る時が近づいている。
そろそろ妹が生まれる頃だ。
私、ダイフェリ・ウィルウェルは由緒正しき公爵家の令嬢である。
父譲りのエメラルドの瞳と、母譲りのプラチナブロンドの髪。
だが、瞳には光がなく、髪は碌な手入れをしていないので燻んでしまっているが。
本来なら、今の年頃ならお茶会に招かれたり招いたり、子供なりに着飾って街中に繰り出したりするもの。
決してお金に困っているわけではない。
ウィルウェル家は国内でも有数の資産家。
一生遊んで暮らせるほどの財力は持ち合わせている。
更に、私には優秀な兄が二人いる。
長男は、ガイジス・ウィルウェル(12歳)。
恵まれた頑丈な体躯、毎日のように剣を振り、最近では騎士たちと共に魔物狩りに勤しんでいるよう。