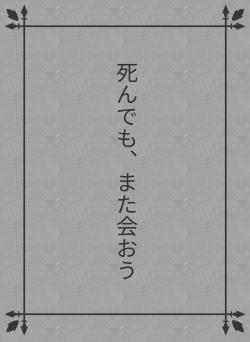その日、私は憎しみに潰されそうになっていた。特に何があった訳でもない。しかし、過去に私を追い詰めた人たちがどうしようもなく憎くなってしまった。
私にイジワルしたあの女が高校を退学したと聞いて、内心穏やかでは居られない。私を目の敵にするのなら、最後までそれを貫き通して欲しかった。
彼女が隣の高校に受かったと聞いた時は、絶望にくれたものだ。駅で見た願書提出時のあの蔑んだ目は、これからも忘れる事は無いだろう。昨日まであんなに澄んでいた心もすっかり淀んでしまった。
次の日、私は哀しみに支配されていた。家で彼氏が欲しいとボヤいていたら母に、髪型をどうにかしないと出来るものも出来ないと言われてしまった。
私はツーブロックのセンターパートだ。一応生物学上、女性だが《カッコいい》と言われるのが嬉しくて、ツーブロックにした。母は、未だに私を。私の心の性別を認めていないので、平気でそんな事が言えるのだ。父も隣でニコニコしていた。《男らしく》ありたいのがそんなにもいけない事だろうか?
きっかけは、こんなにも些細な事だった。なのに。なのに、私には光が見えなくなってしまった。今の生活には、何ら不満はない。しかし私の心に影を落とすのには、十分過ぎる理由だった。
それから数日間は、いつもの明るい気持ちを灯せる様に張り切っていた。けれど、いとも簡単に私の心には闇が支配し続ける。どうやって息をしていたのか忘れる程に、自分で自分の首を閉めていく。
辛い。
苦しい。
死にたい。
その気持ちが頭を周りそれ以外考えられない。渡り廊下から、身を投げてしまえばどんなに楽だろうか。そんな事ばかり考えていたら、雨に降っている事に気ずかなかった。髪から雫が落ちる。もう辞めよう。こんな世界にいても意味が無い。ただ、ただそう思った。正常な思考など、とっくのとうに置いてきた。これで楽になる。柵に足をかけた時、声がした。
「はい。タオル。」
「ヘ?」
「だから、タオル。」
「あっはい」
「僕が使ったから、ちょっと湿ってるけど」
「どうも」
「シャツも透けてるよ。これじゃ、下着視えちゃう。僕の上着、着ていいよ」
「でも、濡れちゃう」
「僕の上着なんかより、そっちのほうが大事でしょ」
「ありがとうございます。私は、《アマネ》です。貴方は?」
「あっ僕?《ヒイロ》だよ~。とりあえず、室内に入ろ〜!」
私にイジワルしたあの女が高校を退学したと聞いて、内心穏やかでは居られない。私を目の敵にするのなら、最後までそれを貫き通して欲しかった。
彼女が隣の高校に受かったと聞いた時は、絶望にくれたものだ。駅で見た願書提出時のあの蔑んだ目は、これからも忘れる事は無いだろう。昨日まであんなに澄んでいた心もすっかり淀んでしまった。
次の日、私は哀しみに支配されていた。家で彼氏が欲しいとボヤいていたら母に、髪型をどうにかしないと出来るものも出来ないと言われてしまった。
私はツーブロックのセンターパートだ。一応生物学上、女性だが《カッコいい》と言われるのが嬉しくて、ツーブロックにした。母は、未だに私を。私の心の性別を認めていないので、平気でそんな事が言えるのだ。父も隣でニコニコしていた。《男らしく》ありたいのがそんなにもいけない事だろうか?
きっかけは、こんなにも些細な事だった。なのに。なのに、私には光が見えなくなってしまった。今の生活には、何ら不満はない。しかし私の心に影を落とすのには、十分過ぎる理由だった。
それから数日間は、いつもの明るい気持ちを灯せる様に張り切っていた。けれど、いとも簡単に私の心には闇が支配し続ける。どうやって息をしていたのか忘れる程に、自分で自分の首を閉めていく。
辛い。
苦しい。
死にたい。
その気持ちが頭を周りそれ以外考えられない。渡り廊下から、身を投げてしまえばどんなに楽だろうか。そんな事ばかり考えていたら、雨に降っている事に気ずかなかった。髪から雫が落ちる。もう辞めよう。こんな世界にいても意味が無い。ただ、ただそう思った。正常な思考など、とっくのとうに置いてきた。これで楽になる。柵に足をかけた時、声がした。
「はい。タオル。」
「ヘ?」
「だから、タオル。」
「あっはい」
「僕が使ったから、ちょっと湿ってるけど」
「どうも」
「シャツも透けてるよ。これじゃ、下着視えちゃう。僕の上着、着ていいよ」
「でも、濡れちゃう」
「僕の上着なんかより、そっちのほうが大事でしょ」
「ありがとうございます。私は、《アマネ》です。貴方は?」
「あっ僕?《ヒイロ》だよ~。とりあえず、室内に入ろ〜!」