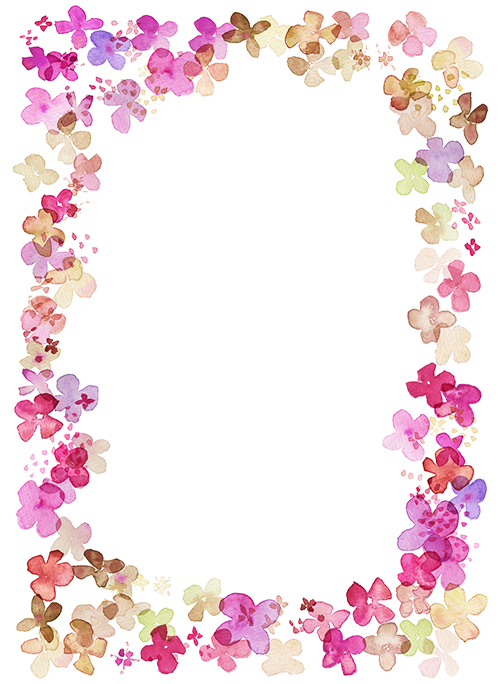怪我の手当てをした後一昼夜昏々と眠り続けて、私は兄に電話をかけた。
兄は言葉少なくそれを聞いて、約束すると告げた。
起きている実感がないまま目覚めて、私は街へ歩き出す。
なじんだ振動を耳ではなく全身で感じ取って、私は目を開く。
視界に映るのは白けた光に照らされた吊り広告と、鈍色に輝く窓枠の向こうに広がる漆黒の闇だった。
私以外誰もいない夜の車両。それを確認して、私はたった今まで自分がうたたねをしていたことに気づいた。
――東京駅に、迎えに来て。
どうして兄に、そんなことを電話したのかはわからない。
とにかく足早に、何かに憑かれたように駅に向かって、電車に乗った。
クリスマスイブの夜だからか、終電近くなのに車両はどこも満員だった。何度か乗り換えながら、私はぼんやりと壁際に立って外を眺めていた。
もしかしたら同じ駅を、何度も回ったかもしれない。そんな無意味なことをしていた。
特別なダイヤで回っていたらしく、途切れることなく列車は繋がっていた。どこまでも行きそうで、大して広くない街をぐるぐると走り続けた。
最初は人に押しつぶされそうに壁際で、その内に大きな駅で人がどっと流れ出てからはシートの近くで、やがて空いてきたのを見計らって席に腰を下ろした。
……後は、記憶にない。
列車は揺れる。濁った黄色の光で満ちた車両が、右へ左へ。
「何してんの」
ぼんやりと呟いても、聞いてくれる人はいない。
しばらく私は鞄を抱えたまま、座席に身を沈めたままうずくまっていた。何を考えるということもなく、鞄を手で弄ぶ。
何だか熱いなと気づいて顔を上げた。暖房が効きすぎているのかと思って辺りを見回すけど、それと同時に背筋をすっと指先で撫でるような悪寒を感じる。
体の外側は火にかけられたように熱いのに、体の芯にはべったりと氷を貼り付けているような感触だった。
どうも熱があるらしい。だから意味不明な電話をしたのだろう。私は脱力しながら思う。
私はその携帯を手の上に乗せて、また外をみつめる。
朦朧とする意識の中、私は呆けたように座り込んでいた。ただ人形のように列車の振動に揺られ続ける。
どれくらい時間が経っただろう。
私は岩のように固まっていた瞼をゆっくりとこじ開けて、漆黒の車窓を目に映した。
アナウンスが聞こえて、ブレーキが掛かる。どうやらずいぶんと長い間走っていたらしいこの列車も、そろそろ止まる時が来たようだ。
列車がゆっくりとスピードを落としていく。人の姿もまばらな、そんな駅へと入っていく。
「あ……」
その停車の動きの中で、私は喉を引きつらせていた。
駅名が書かれたプレートの下で、柱にもたれながら腕組みをして立っていた誰かが、列車の中にいる私を確かに目で捉える。
スローモーションのように、私はその光景に目を見開いた。
甲高い音を上げて、ブレーキが掛かる。それで一瞬見えたはずのその人の姿は視界から外れて、列車は数十メートル進んだところで止まる。
『東京ー、東京ー』
けだるいアナウンスが、車内に反響する。
私はまだ座っていた。立ち上がることができなかった。
ちょうどホームの柱に立つ時計が、深夜零時を指した時だった。
その人が静かに列車の出口に現れる。
私は信じられないものを見る思いで、呆然と出口に立つ彼をみつめた。
彼は無言でそこに立っていた。中に踏み込むことはなく、ただその灰色の瞳でじっと私をみつめる。
「沙世」
その呼び方は、たった一人だけのもの。
「降りてこい。迎えに来たから」
そう言えるのは、私にとって唯一の存在。
兄は身動き一つ取らなかった。表情を変えることも、中へ踏み込んでくることもなく、ただ入り口で私を待つ。
「降りるしかねぇんだよ。ここは終点だ」
ふわっと彼の口から白い息が出た。
……無意識に、私は席を立っていた。
ふと駅名のプレートを眺める。そこには「東京」と、シンプルなレタリングで書かれている。
東京駅は、過去たった一度だけ来た。
私が初めて上京してきた時。やはり、兄が迎えにきてくれた駅。
……私の一年の、始まりの場所だ。
数メートルの距離が、永遠のように感じた。私は、揺れてもいないのによろめきながら、黒いコートの方へと歩み寄る。つまずきそうになりながら、それでも近づく。
兄は趣味が悪いし、品もないし。そのくせ何でもできて、私が必死で努力したことを平気で飛び越していく。
……そして家族としての立場を崩して、私を抱こうとして。
それってだめなことじゃん? そう、彼を責めたい気持ちに駆られる。
「……にいちゃん」
それでも私は、気づけば電車を降りて彼の胸にすがり付いていた。
苦いタバコの匂いと微かな汗の匂いが染み付いたコートに頬をすり寄せながら、私は力いっぱい彼の服を両手で掴む。
熱のせいだろうか。それとも、寒さのせいなのか。
私の精一杯の力で、とにかく彼にしがみついた。
「沙世」
囁くような小さな声が、頭上で響いた。
ぐいとコートの内側に押し込められる。それだけで、私の体は簡単に彼の腕の中に取り込まれてしまっていた。
彼の匂いと温もりが直に伝わってくる。それに、私は涙がぼろぼろと零れ落ちてきた。
「にいちゃ……私」
何、泣いてるんだろう。悲しいわけじゃないのに、どうして。
「かわいく、ないよね……馬鹿だよね……こんな妹、ほしく、なかったよね……」
つまらないことを、自虐的なことを、どうして口にしているんだろう。
兄にいったい、何を言ってほしいと願っているんだろう。
「私なんか……」
「お前を可愛いなんて思ったことは、俺は一度もねぇよ」
兄は私に言葉を続けさせなかった。
ぐずぐずと泣きじゃくる私を、彼は抱えるようにして連れて行く。そのまま静かにベンチに腰掛けて、けれど私は変わらず彼の腕の中にいた。
「お前と初めて会ったときを、俺は覚えちゃいないが」
髪に兄の顎が触れる。硬くて、それは温かく私の頭の上に置かれていた。
「けど、チビだったらしい。いつも入院ばかりして、泣き虫で、弱かったと。それを俺はせっせと世話を焼いていたんだと」
親父に聞いたんだと、兄は言葉を続ける。
「いくらお前を可愛がってたと親父たちが言っても、知るわけねぇだろ、そんなガキの頃の話。いくら毎日のように病院に様子を見に行っていたと教えられても、ただの好奇心じゃないと誰が言い切れる?」
私を抱え込む腕に力は入っていない。けれど、私はそこから抜け出ることができるとは到底思えなかった。
「小汚いガキじゃねぇか。しかもすぐにでも死にそうな、握ったら潰れそうな生き物なんて、誰が好きになれるか」
兄はつまらなそうに、けれど確かな意思を持って言葉を紡ぐ。
「可愛くも、何かの役にたつわけでもない。面倒なだけの荷物だよ、お前は」
頑丈な檻のような、そんな両腕で彼は私の全身をすっぽりと包んでしまう。
「だから、嫌いだよ。大っ嫌いな……いつまでだって、ただの妹だ」
きゅっと私は彼のコートの端を掴む。小さな子どもが、置き去りにされないよう精一杯しがみつくように。
「……ありがとう」
兄がくれたそれは、きっとどんな愛の言葉より甘い嘘。
ふいに体を離して、兄は膝の上の私を見下ろす。みっともなく目と鼻を真っ赤にして、まだぐすぐすと鼻をすすっている不細工な私を。
兄はそれに目を細めて、懐かしむような素振りを見せた。光もほとんど失われた夜の中で、その灰色の瞳は優しかった。
「沙世。実家に帰れ」
兄はさとすように私に告げて、私を背負っていた。
「大嫌いなもんはここに全部捨てていけ。お前の大好きな世界に帰ればいい」
ホームの隅から少しずつ、人の声のする方へと兄は歩き出す。私はその背中にぐったりと張り付いて、熱さと寒さの中をさまよっていた。
「……うん。そうするよ、兄ちゃん」
それが、今から五年前の話。
私は兄に言われた通り、都会の生活を捨てて故郷に帰った。実家の両親と懐かしい友達に囲まれながら、穏やかな生活を送っている。
私はその後、東京で働く兄とは電話で話すだけになった。
兄は何をどうしたのか、今は東京で弁護士をしているらしい。多少危ない仕事もしているらしいが、時々聞く兄の声は明るい。
今も冗談交じりに、二人であの日のことを話す。ぼろぼろ泣いていた私を、兄は可笑しそうにからかう。私は、兄ちゃんだってやけに真面目なこと言ってたじゃんと文句をつける。
私たちは、あの日の東京駅で確かに離れてしまったけれど。
今も「大嫌い」な兄妹同士として、電話越しに笑い合っている。
兄は言葉少なくそれを聞いて、約束すると告げた。
起きている実感がないまま目覚めて、私は街へ歩き出す。
なじんだ振動を耳ではなく全身で感じ取って、私は目を開く。
視界に映るのは白けた光に照らされた吊り広告と、鈍色に輝く窓枠の向こうに広がる漆黒の闇だった。
私以外誰もいない夜の車両。それを確認して、私はたった今まで自分がうたたねをしていたことに気づいた。
――東京駅に、迎えに来て。
どうして兄に、そんなことを電話したのかはわからない。
とにかく足早に、何かに憑かれたように駅に向かって、電車に乗った。
クリスマスイブの夜だからか、終電近くなのに車両はどこも満員だった。何度か乗り換えながら、私はぼんやりと壁際に立って外を眺めていた。
もしかしたら同じ駅を、何度も回ったかもしれない。そんな無意味なことをしていた。
特別なダイヤで回っていたらしく、途切れることなく列車は繋がっていた。どこまでも行きそうで、大して広くない街をぐるぐると走り続けた。
最初は人に押しつぶされそうに壁際で、その内に大きな駅で人がどっと流れ出てからはシートの近くで、やがて空いてきたのを見計らって席に腰を下ろした。
……後は、記憶にない。
列車は揺れる。濁った黄色の光で満ちた車両が、右へ左へ。
「何してんの」
ぼんやりと呟いても、聞いてくれる人はいない。
しばらく私は鞄を抱えたまま、座席に身を沈めたままうずくまっていた。何を考えるということもなく、鞄を手で弄ぶ。
何だか熱いなと気づいて顔を上げた。暖房が効きすぎているのかと思って辺りを見回すけど、それと同時に背筋をすっと指先で撫でるような悪寒を感じる。
体の外側は火にかけられたように熱いのに、体の芯にはべったりと氷を貼り付けているような感触だった。
どうも熱があるらしい。だから意味不明な電話をしたのだろう。私は脱力しながら思う。
私はその携帯を手の上に乗せて、また外をみつめる。
朦朧とする意識の中、私は呆けたように座り込んでいた。ただ人形のように列車の振動に揺られ続ける。
どれくらい時間が経っただろう。
私は岩のように固まっていた瞼をゆっくりとこじ開けて、漆黒の車窓を目に映した。
アナウンスが聞こえて、ブレーキが掛かる。どうやらずいぶんと長い間走っていたらしいこの列車も、そろそろ止まる時が来たようだ。
列車がゆっくりとスピードを落としていく。人の姿もまばらな、そんな駅へと入っていく。
「あ……」
その停車の動きの中で、私は喉を引きつらせていた。
駅名が書かれたプレートの下で、柱にもたれながら腕組みをして立っていた誰かが、列車の中にいる私を確かに目で捉える。
スローモーションのように、私はその光景に目を見開いた。
甲高い音を上げて、ブレーキが掛かる。それで一瞬見えたはずのその人の姿は視界から外れて、列車は数十メートル進んだところで止まる。
『東京ー、東京ー』
けだるいアナウンスが、車内に反響する。
私はまだ座っていた。立ち上がることができなかった。
ちょうどホームの柱に立つ時計が、深夜零時を指した時だった。
その人が静かに列車の出口に現れる。
私は信じられないものを見る思いで、呆然と出口に立つ彼をみつめた。
彼は無言でそこに立っていた。中に踏み込むことはなく、ただその灰色の瞳でじっと私をみつめる。
「沙世」
その呼び方は、たった一人だけのもの。
「降りてこい。迎えに来たから」
そう言えるのは、私にとって唯一の存在。
兄は身動き一つ取らなかった。表情を変えることも、中へ踏み込んでくることもなく、ただ入り口で私を待つ。
「降りるしかねぇんだよ。ここは終点だ」
ふわっと彼の口から白い息が出た。
……無意識に、私は席を立っていた。
ふと駅名のプレートを眺める。そこには「東京」と、シンプルなレタリングで書かれている。
東京駅は、過去たった一度だけ来た。
私が初めて上京してきた時。やはり、兄が迎えにきてくれた駅。
……私の一年の、始まりの場所だ。
数メートルの距離が、永遠のように感じた。私は、揺れてもいないのによろめきながら、黒いコートの方へと歩み寄る。つまずきそうになりながら、それでも近づく。
兄は趣味が悪いし、品もないし。そのくせ何でもできて、私が必死で努力したことを平気で飛び越していく。
……そして家族としての立場を崩して、私を抱こうとして。
それってだめなことじゃん? そう、彼を責めたい気持ちに駆られる。
「……にいちゃん」
それでも私は、気づけば電車を降りて彼の胸にすがり付いていた。
苦いタバコの匂いと微かな汗の匂いが染み付いたコートに頬をすり寄せながら、私は力いっぱい彼の服を両手で掴む。
熱のせいだろうか。それとも、寒さのせいなのか。
私の精一杯の力で、とにかく彼にしがみついた。
「沙世」
囁くような小さな声が、頭上で響いた。
ぐいとコートの内側に押し込められる。それだけで、私の体は簡単に彼の腕の中に取り込まれてしまっていた。
彼の匂いと温もりが直に伝わってくる。それに、私は涙がぼろぼろと零れ落ちてきた。
「にいちゃ……私」
何、泣いてるんだろう。悲しいわけじゃないのに、どうして。
「かわいく、ないよね……馬鹿だよね……こんな妹、ほしく、なかったよね……」
つまらないことを、自虐的なことを、どうして口にしているんだろう。
兄にいったい、何を言ってほしいと願っているんだろう。
「私なんか……」
「お前を可愛いなんて思ったことは、俺は一度もねぇよ」
兄は私に言葉を続けさせなかった。
ぐずぐずと泣きじゃくる私を、彼は抱えるようにして連れて行く。そのまま静かにベンチに腰掛けて、けれど私は変わらず彼の腕の中にいた。
「お前と初めて会ったときを、俺は覚えちゃいないが」
髪に兄の顎が触れる。硬くて、それは温かく私の頭の上に置かれていた。
「けど、チビだったらしい。いつも入院ばかりして、泣き虫で、弱かったと。それを俺はせっせと世話を焼いていたんだと」
親父に聞いたんだと、兄は言葉を続ける。
「いくらお前を可愛がってたと親父たちが言っても、知るわけねぇだろ、そんなガキの頃の話。いくら毎日のように病院に様子を見に行っていたと教えられても、ただの好奇心じゃないと誰が言い切れる?」
私を抱え込む腕に力は入っていない。けれど、私はそこから抜け出ることができるとは到底思えなかった。
「小汚いガキじゃねぇか。しかもすぐにでも死にそうな、握ったら潰れそうな生き物なんて、誰が好きになれるか」
兄はつまらなそうに、けれど確かな意思を持って言葉を紡ぐ。
「可愛くも、何かの役にたつわけでもない。面倒なだけの荷物だよ、お前は」
頑丈な檻のような、そんな両腕で彼は私の全身をすっぽりと包んでしまう。
「だから、嫌いだよ。大っ嫌いな……いつまでだって、ただの妹だ」
きゅっと私は彼のコートの端を掴む。小さな子どもが、置き去りにされないよう精一杯しがみつくように。
「……ありがとう」
兄がくれたそれは、きっとどんな愛の言葉より甘い嘘。
ふいに体を離して、兄は膝の上の私を見下ろす。みっともなく目と鼻を真っ赤にして、まだぐすぐすと鼻をすすっている不細工な私を。
兄はそれに目を細めて、懐かしむような素振りを見せた。光もほとんど失われた夜の中で、その灰色の瞳は優しかった。
「沙世。実家に帰れ」
兄はさとすように私に告げて、私を背負っていた。
「大嫌いなもんはここに全部捨てていけ。お前の大好きな世界に帰ればいい」
ホームの隅から少しずつ、人の声のする方へと兄は歩き出す。私はその背中にぐったりと張り付いて、熱さと寒さの中をさまよっていた。
「……うん。そうするよ、兄ちゃん」
それが、今から五年前の話。
私は兄に言われた通り、都会の生活を捨てて故郷に帰った。実家の両親と懐かしい友達に囲まれながら、穏やかな生活を送っている。
私はその後、東京で働く兄とは電話で話すだけになった。
兄は何をどうしたのか、今は東京で弁護士をしているらしい。多少危ない仕事もしているらしいが、時々聞く兄の声は明るい。
今も冗談交じりに、二人であの日のことを話す。ぼろぼろ泣いていた私を、兄は可笑しそうにからかう。私は、兄ちゃんだってやけに真面目なこと言ってたじゃんと文句をつける。
私たちは、あの日の東京駅で確かに離れてしまったけれど。
今も「大嫌い」な兄妹同士として、電話越しに笑い合っている。