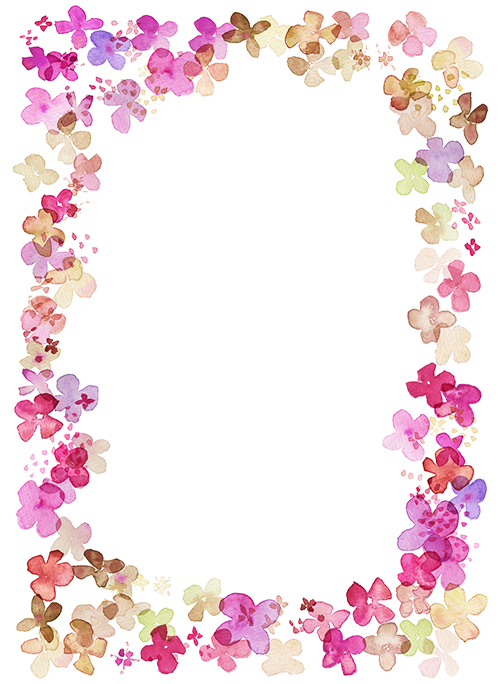一悶着起こした後ではさすがに居づらくて、私は早々に帰宅することにした。
兄のバイクの後部座席で、ぼんやりと考えに沈む。あんな騒ぎを起こすくらいならもう兄にくっついて行くのはやめようか、それともまだ決めるのは早すぎるのか。
上目遣いで前に座る兄を窺う。駆け抜ける風とテールランプの中、彼はいつものように黙って前を見据えていた。振り返る素振りも、何か言葉を発する気配もない。
パーッと、車のクラクションがうるさい。渋滞に引っかかって停車すると空気もぬるくて、疾走感の快さが一瞬で消える。
「おい」
なんとなく身を捩ると、兄がだるそうに振り返って言った。
「寝るなよ。落ちるぞ」
たぶん兄もじっとりした夜気がうっとうしくて、何かしゃべるのも億劫だったのだと思う。
でも、それだけだった。
馬鹿でガキで面倒な妹を責める言葉は、それ以外何一つ口にすることがなかった。
兄のアパートでシャワーを浴びた後、私はそのまま畳の上で仰向けに寝転がった。
「畳が濡れるだろ。頭拭け、頭」
あぐらをかいてテレビを見ていた兄は、伸びている私を見て顔をしかめる。
「もう拭いたよ」
「起きろ。水滴ってるっつーの」
軽く髪を掴まれて、私は渋々ながら体を起こす。ぶつくさと文句を零しつつも風呂場からタオルを取ってきて、ぞんざいにそれで頭を拭った。
「ほれ、ドライヤー」
「ありがと」
部屋の隅に転がっていたドライヤーを、兄が滑らせてよこす。
私はそれをコンセントに差し込み、温風を出したところで……ふと手を止めて兄を見た。
「兄ちゃん」
「あ?」
返事かどうかもわからない声を聞いて、一言問う。
「兄ちゃんって彼女いるの?」
実は兄に訊くのは生まれて初めての質問だった。噂でならたくさんあったけれど、私は一度も兄の口から「彼女」という言葉を聞いたことはない。
それに、訊く必要もないと思っていた。知ったところで、私には関係ないと信じていたかった。
「ほら、ドライヤーなんて兄ちゃんが自分で買うわけないし」
兄はテレビを眺めていた。特に面白くもなさそうなバラエティー番組で、画面から漏れ出す黄色の光が目にチカチカする。
わぁっとテレビから溢れる笑い声と、緩いドライヤーの電動音が重なる。その中で私たち兄妹の間にだけ、一瞬の沈黙が流れた。
「沙世。耳はどうなった」
普段通りの顔で兄が振り返り、私の右耳を掴んだ。少し乱暴に親指と人差し指でそれを挟み込み、耳の裏側を覗き込む。
「やっぱ切れてるな。何か貼っとくか?」
顔をしかめる兄に、私は適当な答えを返す。
「痛くないよ。要らない」
「消毒液どこだったか」
兄は座ったまま畳の上を滑るようにして移動する。
言い終わらない内から傍の棚で消毒液を探している、この行動の早さは何なのだろう。
「動くなよ。目に入るぞ」
そうするのが当たり前のように私を座らせ、消毒液を染み込ませたガーゼを押し当てているのも、この年の妹にするのはいささか過保護な気がしてならない。
何かと転んだりして兄に世話を焼かせた私に、原因があるのはわかってる。人見知りの激しかった私は兄に対してはとことんわがままで、そして兄はそれを叱りながらも甘んじて受けてきた。
「深くは切れてない」
独り言のように呟く兄と、怪我が大したものでないとわかる度にあからさまに安堵した、幼い頃の彼の声色が重なる。
「別に。耳の後ろなんて気にもならないよ」
横目で窺った浅黒い腕には、細かいものからスパッと切れた刃物のような傷まで大小様々だ。誰に付けられたかなんて、たぶん本人すら覚えていないのだろう。
兄の腕は太く、筋肉もしっかりついてる。スポーツや喧嘩に耐えてきただけあって、いくら私だって彼が強い人間であるのは疑ったことがない。
同年代どころか年上の男にも簡単には負けない。だけど自他共にそう認められている兄は、意外だけどめったに自分から手を出すことはなかった。
それは兄の余裕の証であり、同時に人からも慕われる理由になっているのだと、今でも信じている。
けど、幼い頃から兄は私が怪我を負うことを異常なほど気にする。それこそ自分は腕を血まみれにしてもせせら笑って帰ってくるくせに、小さな私が転んで膝を擦りむいて泣くと本気で痛そうな顔をする。
私は手当てから解放されると、再び仰向けに寝転びながら考える。
私は幼い頃ひどく体が弱かった。病気もたくさんしたし、チビだったし、めそめそとよく泣く内気な子供だった。両親に手を上げられたこともないし、同年代の誰より立派な体格と気の強さを持っていた兄とは、まったく同じ生き物には見えなかった。
たぶん一番そばで私を見ていた兄が、誰よりもそう思っていた。
タンクトップの上からでも筋肉の動きがわかる背中をみつめながら私は納得して、そして息苦しくなる。
……私はずっと、兄とどこも似ていない生き物でいていいのか。
拓磨の妹だからと、大抵のことは大目に見てもらえる。ダンスもできない、軽いおしゃべりも楽しめない、変に生真面目で堅い私のままでも。
「ねぇ、兄ちゃん」
そもそも違う世界の人間として、ただ珍しがられるだけの私。
救急箱を棚に押し込んでいた兄が、何だよ、といい加減に返事をした時だった。
「私もピアスしてみたい」
……よそ者は嫌だ、仲間はずれは嫌だと、そんな縋るような幼い思いで口にした言葉だった。
「は?」
私の言動がよほど意外だったのか、兄は棚を閉めるのも忘れて振り返る。
「何だよ。お前、ピアスは趣味悪いって言ってただろ」
「確かに言ったよ。でも」
口元を歪めて、私は拗ねたように言う。
「なんとなく、やってみたくなった。それだけ」
言葉を紡いでから理由を考えた。
たぶん私は、兄のいる世界に溶け込みたい。全然違う、ただ守ってやらなきゃいけない弱い生き物じゃなくて、そこに元から受け入れてもらえるものになりたい。
「ダメって言ってもするからね。もう決めたんだから」
ただその世界へ入りたい理由が、兄の側に自然に居られて、守ってもらえて安心だからという、ひどく矛盾したものでしかないけど。
「沙世」
「やだ」
駄々っ子のように兄の言葉を遮って、私は寝転んだまま彼をにらみつける。
証が欲しいと純粋に思った。たとえそれが趣味の悪いものでも、決して私が好きになりそうにないものでも、確かに目に映る形が欲しいと。
「ピアスがいい。イヤリングじゃなくて」
そしてそれは、はっきりと後に残るものでなければいけなかった。兄が決して私に許さなかった、私の体に傷をつけてしまうもの。
心が急いている。落ち着けと内部で止める声も聞こえる。たかがアクセサリーだけど、それがどれだけ今までの私を否定するのかも、頭の冷静な部分では理解している。
それでも私は、困惑顔の兄から一度も目を逸らすことができなかった。兄はやめろという意思を表情から隠しもせず、無意識に自分のピアスを弾いていた。
だけど先に顔を背けたのは兄で、短くため息をついたのも兄の方だった。
「しょうがねぇな」
棚を元通りに閉めて、兄は私の真横に座りなおす。その拍子に、耳に下がるピアスが一斉に揺れ動いた。
「小せぇのにしろよ。親父が泣くぞ」
「兄ちゃんに言われたくない」
「あと」
兄は軽く屈みこんで私の右耳を指先で挟み込む。先ほどと違って、それは奇妙に優しい動作だった。
「俺にやらせろよ。穴あけんのは」
一瞬、ぞくりとした。
耳に触れる冷たい指先と、どこか楽しげな兄の表情が、まったく他人のもののように感じた。
……それはまるで、性を孕んだ誘惑のようなもので。
頭に鳴り響く警鐘と、包み込まれるようなぬるい安堵感。かつてない緊張感と、心に染み渡る熱さ。
「うん、そうして」
その狭間で、私は目を細めて深く頷いた。
天井からぶら下がる電球が眩しい。背中に当たる畳は柔らかすぎて肩が沈む。洗濯ロープに掛かった色の抜けたジーンズは小汚くて、安物の冷蔵庫が立てる電動音は耳障りで仕方ない。
「兄ちゃん」
「ん?」
でも、ここが本来私のあるべき場所だと思うのだ。
「私、彼氏とうまくいってないんだ」
何気なくつぶやいた私に、兄は眉一つ動かさずに頷く。
「じゃ、他のをみつけろ」
あっさりした答えだった。
だけどそれを、私はずっと兄に言ってもらいたかったに違いない。
「穴あけんのはこの怪我が治ってからだな」
次の瞬間にはもう、耳の話に戻っている。私もそれを望んでいた。
私は目を伏せて、変わらず耳を掴んだままの兄の指先を感じながら言う。冷たくも熱くもない、心地よい体温だった。
「彼女いるの? 兄ちゃん」
気負いなく呟いた言葉だったから、口調も淡白なものでしかない。
「皮膚薄いな、お前。血管透けてるし」
だから兄が何も答えなくても、私は苛立つことはなかった。
「怒るんじゃないの? いつも馬鹿で面倒な妹の面倒ばっかりみてちゃ」
「お前くらいのガキにも合いそうなピアス、見つけといてやるよ」
会話はまるで噛み合ってなかった。
それでも、兄との距離が急速に縮まっていくのを、私は心の中の冷静な部分で感じ取っていた。
兄のバイクの後部座席で、ぼんやりと考えに沈む。あんな騒ぎを起こすくらいならもう兄にくっついて行くのはやめようか、それともまだ決めるのは早すぎるのか。
上目遣いで前に座る兄を窺う。駆け抜ける風とテールランプの中、彼はいつものように黙って前を見据えていた。振り返る素振りも、何か言葉を発する気配もない。
パーッと、車のクラクションがうるさい。渋滞に引っかかって停車すると空気もぬるくて、疾走感の快さが一瞬で消える。
「おい」
なんとなく身を捩ると、兄がだるそうに振り返って言った。
「寝るなよ。落ちるぞ」
たぶん兄もじっとりした夜気がうっとうしくて、何かしゃべるのも億劫だったのだと思う。
でも、それだけだった。
馬鹿でガキで面倒な妹を責める言葉は、それ以外何一つ口にすることがなかった。
兄のアパートでシャワーを浴びた後、私はそのまま畳の上で仰向けに寝転がった。
「畳が濡れるだろ。頭拭け、頭」
あぐらをかいてテレビを見ていた兄は、伸びている私を見て顔をしかめる。
「もう拭いたよ」
「起きろ。水滴ってるっつーの」
軽く髪を掴まれて、私は渋々ながら体を起こす。ぶつくさと文句を零しつつも風呂場からタオルを取ってきて、ぞんざいにそれで頭を拭った。
「ほれ、ドライヤー」
「ありがと」
部屋の隅に転がっていたドライヤーを、兄が滑らせてよこす。
私はそれをコンセントに差し込み、温風を出したところで……ふと手を止めて兄を見た。
「兄ちゃん」
「あ?」
返事かどうかもわからない声を聞いて、一言問う。
「兄ちゃんって彼女いるの?」
実は兄に訊くのは生まれて初めての質問だった。噂でならたくさんあったけれど、私は一度も兄の口から「彼女」という言葉を聞いたことはない。
それに、訊く必要もないと思っていた。知ったところで、私には関係ないと信じていたかった。
「ほら、ドライヤーなんて兄ちゃんが自分で買うわけないし」
兄はテレビを眺めていた。特に面白くもなさそうなバラエティー番組で、画面から漏れ出す黄色の光が目にチカチカする。
わぁっとテレビから溢れる笑い声と、緩いドライヤーの電動音が重なる。その中で私たち兄妹の間にだけ、一瞬の沈黙が流れた。
「沙世。耳はどうなった」
普段通りの顔で兄が振り返り、私の右耳を掴んだ。少し乱暴に親指と人差し指でそれを挟み込み、耳の裏側を覗き込む。
「やっぱ切れてるな。何か貼っとくか?」
顔をしかめる兄に、私は適当な答えを返す。
「痛くないよ。要らない」
「消毒液どこだったか」
兄は座ったまま畳の上を滑るようにして移動する。
言い終わらない内から傍の棚で消毒液を探している、この行動の早さは何なのだろう。
「動くなよ。目に入るぞ」
そうするのが当たり前のように私を座らせ、消毒液を染み込ませたガーゼを押し当てているのも、この年の妹にするのはいささか過保護な気がしてならない。
何かと転んだりして兄に世話を焼かせた私に、原因があるのはわかってる。人見知りの激しかった私は兄に対してはとことんわがままで、そして兄はそれを叱りながらも甘んじて受けてきた。
「深くは切れてない」
独り言のように呟く兄と、怪我が大したものでないとわかる度にあからさまに安堵した、幼い頃の彼の声色が重なる。
「別に。耳の後ろなんて気にもならないよ」
横目で窺った浅黒い腕には、細かいものからスパッと切れた刃物のような傷まで大小様々だ。誰に付けられたかなんて、たぶん本人すら覚えていないのだろう。
兄の腕は太く、筋肉もしっかりついてる。スポーツや喧嘩に耐えてきただけあって、いくら私だって彼が強い人間であるのは疑ったことがない。
同年代どころか年上の男にも簡単には負けない。だけど自他共にそう認められている兄は、意外だけどめったに自分から手を出すことはなかった。
それは兄の余裕の証であり、同時に人からも慕われる理由になっているのだと、今でも信じている。
けど、幼い頃から兄は私が怪我を負うことを異常なほど気にする。それこそ自分は腕を血まみれにしてもせせら笑って帰ってくるくせに、小さな私が転んで膝を擦りむいて泣くと本気で痛そうな顔をする。
私は手当てから解放されると、再び仰向けに寝転びながら考える。
私は幼い頃ひどく体が弱かった。病気もたくさんしたし、チビだったし、めそめそとよく泣く内気な子供だった。両親に手を上げられたこともないし、同年代の誰より立派な体格と気の強さを持っていた兄とは、まったく同じ生き物には見えなかった。
たぶん一番そばで私を見ていた兄が、誰よりもそう思っていた。
タンクトップの上からでも筋肉の動きがわかる背中をみつめながら私は納得して、そして息苦しくなる。
……私はずっと、兄とどこも似ていない生き物でいていいのか。
拓磨の妹だからと、大抵のことは大目に見てもらえる。ダンスもできない、軽いおしゃべりも楽しめない、変に生真面目で堅い私のままでも。
「ねぇ、兄ちゃん」
そもそも違う世界の人間として、ただ珍しがられるだけの私。
救急箱を棚に押し込んでいた兄が、何だよ、といい加減に返事をした時だった。
「私もピアスしてみたい」
……よそ者は嫌だ、仲間はずれは嫌だと、そんな縋るような幼い思いで口にした言葉だった。
「は?」
私の言動がよほど意外だったのか、兄は棚を閉めるのも忘れて振り返る。
「何だよ。お前、ピアスは趣味悪いって言ってただろ」
「確かに言ったよ。でも」
口元を歪めて、私は拗ねたように言う。
「なんとなく、やってみたくなった。それだけ」
言葉を紡いでから理由を考えた。
たぶん私は、兄のいる世界に溶け込みたい。全然違う、ただ守ってやらなきゃいけない弱い生き物じゃなくて、そこに元から受け入れてもらえるものになりたい。
「ダメって言ってもするからね。もう決めたんだから」
ただその世界へ入りたい理由が、兄の側に自然に居られて、守ってもらえて安心だからという、ひどく矛盾したものでしかないけど。
「沙世」
「やだ」
駄々っ子のように兄の言葉を遮って、私は寝転んだまま彼をにらみつける。
証が欲しいと純粋に思った。たとえそれが趣味の悪いものでも、決して私が好きになりそうにないものでも、確かに目に映る形が欲しいと。
「ピアスがいい。イヤリングじゃなくて」
そしてそれは、はっきりと後に残るものでなければいけなかった。兄が決して私に許さなかった、私の体に傷をつけてしまうもの。
心が急いている。落ち着けと内部で止める声も聞こえる。たかがアクセサリーだけど、それがどれだけ今までの私を否定するのかも、頭の冷静な部分では理解している。
それでも私は、困惑顔の兄から一度も目を逸らすことができなかった。兄はやめろという意思を表情から隠しもせず、無意識に自分のピアスを弾いていた。
だけど先に顔を背けたのは兄で、短くため息をついたのも兄の方だった。
「しょうがねぇな」
棚を元通りに閉めて、兄は私の真横に座りなおす。その拍子に、耳に下がるピアスが一斉に揺れ動いた。
「小せぇのにしろよ。親父が泣くぞ」
「兄ちゃんに言われたくない」
「あと」
兄は軽く屈みこんで私の右耳を指先で挟み込む。先ほどと違って、それは奇妙に優しい動作だった。
「俺にやらせろよ。穴あけんのは」
一瞬、ぞくりとした。
耳に触れる冷たい指先と、どこか楽しげな兄の表情が、まったく他人のもののように感じた。
……それはまるで、性を孕んだ誘惑のようなもので。
頭に鳴り響く警鐘と、包み込まれるようなぬるい安堵感。かつてない緊張感と、心に染み渡る熱さ。
「うん、そうして」
その狭間で、私は目を細めて深く頷いた。
天井からぶら下がる電球が眩しい。背中に当たる畳は柔らかすぎて肩が沈む。洗濯ロープに掛かった色の抜けたジーンズは小汚くて、安物の冷蔵庫が立てる電動音は耳障りで仕方ない。
「兄ちゃん」
「ん?」
でも、ここが本来私のあるべき場所だと思うのだ。
「私、彼氏とうまくいってないんだ」
何気なくつぶやいた私に、兄は眉一つ動かさずに頷く。
「じゃ、他のをみつけろ」
あっさりした答えだった。
だけどそれを、私はずっと兄に言ってもらいたかったに違いない。
「穴あけんのはこの怪我が治ってからだな」
次の瞬間にはもう、耳の話に戻っている。私もそれを望んでいた。
私は目を伏せて、変わらず耳を掴んだままの兄の指先を感じながら言う。冷たくも熱くもない、心地よい体温だった。
「彼女いるの? 兄ちゃん」
気負いなく呟いた言葉だったから、口調も淡白なものでしかない。
「皮膚薄いな、お前。血管透けてるし」
だから兄が何も答えなくても、私は苛立つことはなかった。
「怒るんじゃないの? いつも馬鹿で面倒な妹の面倒ばっかりみてちゃ」
「お前くらいのガキにも合いそうなピアス、見つけといてやるよ」
会話はまるで噛み合ってなかった。
それでも、兄との距離が急速に縮まっていくのを、私は心の中の冷静な部分で感じ取っていた。