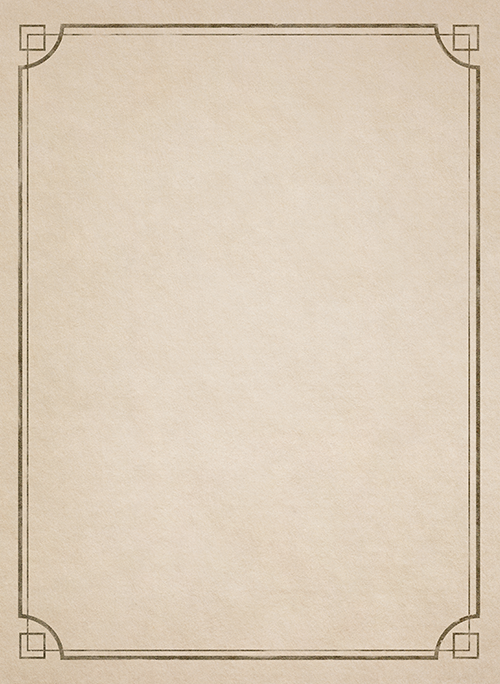「はい。これで大丈夫ですヨ」
「助かったぞリフェル。ありがとう」
リフェルの治癒魔法によってタヌキの傷がどんどん治っていく。傷も塞がり、さっきまでの荒々しい呼吸も落ち着いてきた様子だ。
「これタヌキ……だよな?」
「多分」
「タヌキって羽生えてたか?」
「タヌキに羽なんてあるわけないでしょ。それに羽と言うより鳥の翼みたいだけど」
「確かに……って、どっちにしても可笑しいだろ。タヌキなんだから。こういう種族なのかな」
「いや、こんな種族は存在しない筈だ」
「私もアクルと同じ意見でス。私のデータに存在しませン」
「じゃあこれは一体……」
話しをしていると、意識が戻ったのかタヌキが動き出した。
そしてこれが、この島で起こる俺達の物語の始まりだった――。
「……」
「お、動いたぞ。何はともあれ大丈夫そうだな。羽の生えたタヌキなんて初めて見た。ほら、元気になったなら森へ戻りな」
「――“動物扱いされてもな”」
「ん?……何か言ったか?」
声が聞こえた俺はリフェル達を見た。だが誰も言葉を発しない。3人共不思議そうに互いの顔を見た後、再び俺を見てきた。
「いや。オラ達じゃないぞ……」
「え? だって今何か喋っただろ?」
「私ではないでス」
「私も」
ん……? 皆困惑した表情を浮かべている。ふざけている……訳じゃないよな?
でも今確かに誰かッ……「――“俺だよ旦那”」
また声がした。
俺はリフェル達を見たが全員首を振っている。訳が分からねぇ。皆も無意識の内に辺りをキョロキョロ見渡していた。
気のせいではなく確かに聞こえる。でも俺達じゃない。
なら一体これは誰のッ……「――“お~い、こっちこっち! ここだよ”」
「「――⁉⁉」」
俺は……じゃなく、全員が目を疑った。
「良かった良かった。やっと気が付いてくれたみたいだな」
おいおいおい……どうなってんだこれは……。
「いや~、危ない所を助けてもらってマジで感謝! もうダメかと思ってたんよ」
これまでの人生でも目を疑う様な事はそれなりにあった。だがその中でもコレはまた異様――。
「ありがとう! 旦那達のお陰で助かったぜ」
俺達が今見ているものが夢でなければ、この世界の誰が信じてくれるだろうか。
ついさっきまで大怪我をして力尽きそうだったタヌキが、何故か羽を生やしている挙句にこちらに向かって“喋っている”なんて。
一体何処の誰が信じてくれようか――。
「な、なッ……何なんだお前はぁぁぁ⁉⁉」
ヘクセンリーパーという悪名高き魔女の島にいる事を忘れ、俺は思わず大声で叫んでしまった。でもこれはしょうがねぇ。
だってあろう事かタヌキが喋っているんだからな!
しかも流暢に。しかも人間みたいに2本足で立ってるし。
「まぁまぁまぁ。驚くのは分かるけどさ、取り敢えず深呼吸して落ち着きなよ。話はそれから」
まだ現実を受け止めきれていない上に、俺は今ひょっとしてタヌキに気遣われている?
アクルとエマも驚いているのか、タヌキを見て珍しく呆然としている様だ。しかもこんな摩訶不思議な状況にも関わらず、流石と言うべきなのかリフェルが1番最初に言葉を返した。
「アナタは何者ですか?」
「お、お姉さんすげー美人だね。 ラッキー! こんな美女に助けてもらったのか俺は。名前は?」
「私の質問が先ですヨ」
「これは失礼。助けてもらったのに自己紹介がまだだった。改めて……危ない所を助けてくれてサンキューな。俺の名前は“ルルカ・ヴィクラム・デーヴィ”。信じられないと思うけど、これでもれっきとした人間なんよ。それと一応盗賊やってるんで宜しく!」
「はい。分かりましタ」
「軽ッ! お姉さん面白いね。ヒャハハ」
ルルカと名乗った羽つきタヌキ。 見れば見るほど不思議でならん。
「もしかして……“デーヴィ盗賊団”?」
そう口にしたのはエマであった。
「ん? 俺らの事知ってるのか、獣人族のお嬢ちゃん」
「私のデータからも抽出されましタ。ルルカ・ヴィクラム・デーヴィ。年齢21歳。男。女好きで軽い人間ですが、盗賊としての才能は折り紙付き。彼が10代で結成したデーヴィ盗賊団はその界隈で一躍名を轟かせていますネ」
このタヌキが盗賊団の頭? それも名のある……つか、その前に人間ってどういう事? 情報が渋滞してやがる。
「はぁ~、これは驚いた。お嬢ちゃんもお姉さんも知ってるなんて、俺も随分有名になってるなぁ。お姉さんなんて最早俺のファンだよね」
「あり得ませン。ただアナタの情報を申し上げているだけでス」
清々しいまでの一刀両断。お調子者の彼も流石に戸惑ったみたいだな。
一旦会話が止まった所で今度は俺が彼に聞いた。
「なぁタヌキ。お前が人間ってどういう事だ」
「今度は旦那が質問ね。それにその答えは話すとまぁ長いんよ……。でも噓ではない。お姉さんが言った様に俺は盗賊団の頭であり、ルルカという1人の人間だ。今は“魔女の呪い”によってこんな姿だけどよ」
疑いたくもなるが、そう語るルルカというタヌキの瞳は真剣だった。
「魔女の呪いって……もしかしてこの島にいるヘクセンリーパーか?」
「そうさ。俺が言うのも変だけど、旦那達こそ何者なんよ? こんな所にいて。まさか奴の友達とかじゃないよね」
「まさか。友達どころか見た事もねぇ。何なら名前もさっき知ったばっかりだ。俺達はその魔女にちょっと聞きたいことがあってな」
「へぇ……。まぁ旦那達があの魔女に何の用があるか知らないけど、それは無理かもしれんよ」
「何故だ?」
「何故って……ヘクセンリーパーは俺が“殺す”から」
今までの軽い雰囲気からは一転。
彼の最後の一言からはとてつもない殺意と覚悟の重さを感じた――。
「助かったぞリフェル。ありがとう」
リフェルの治癒魔法によってタヌキの傷がどんどん治っていく。傷も塞がり、さっきまでの荒々しい呼吸も落ち着いてきた様子だ。
「これタヌキ……だよな?」
「多分」
「タヌキって羽生えてたか?」
「タヌキに羽なんてあるわけないでしょ。それに羽と言うより鳥の翼みたいだけど」
「確かに……って、どっちにしても可笑しいだろ。タヌキなんだから。こういう種族なのかな」
「いや、こんな種族は存在しない筈だ」
「私もアクルと同じ意見でス。私のデータに存在しませン」
「じゃあこれは一体……」
話しをしていると、意識が戻ったのかタヌキが動き出した。
そしてこれが、この島で起こる俺達の物語の始まりだった――。
「……」
「お、動いたぞ。何はともあれ大丈夫そうだな。羽の生えたタヌキなんて初めて見た。ほら、元気になったなら森へ戻りな」
「――“動物扱いされてもな”」
「ん?……何か言ったか?」
声が聞こえた俺はリフェル達を見た。だが誰も言葉を発しない。3人共不思議そうに互いの顔を見た後、再び俺を見てきた。
「いや。オラ達じゃないぞ……」
「え? だって今何か喋っただろ?」
「私ではないでス」
「私も」
ん……? 皆困惑した表情を浮かべている。ふざけている……訳じゃないよな?
でも今確かに誰かッ……「――“俺だよ旦那”」
また声がした。
俺はリフェル達を見たが全員首を振っている。訳が分からねぇ。皆も無意識の内に辺りをキョロキョロ見渡していた。
気のせいではなく確かに聞こえる。でも俺達じゃない。
なら一体これは誰のッ……「――“お~い、こっちこっち! ここだよ”」
「「――⁉⁉」」
俺は……じゃなく、全員が目を疑った。
「良かった良かった。やっと気が付いてくれたみたいだな」
おいおいおい……どうなってんだこれは……。
「いや~、危ない所を助けてもらってマジで感謝! もうダメかと思ってたんよ」
これまでの人生でも目を疑う様な事はそれなりにあった。だがその中でもコレはまた異様――。
「ありがとう! 旦那達のお陰で助かったぜ」
俺達が今見ているものが夢でなければ、この世界の誰が信じてくれるだろうか。
ついさっきまで大怪我をして力尽きそうだったタヌキが、何故か羽を生やしている挙句にこちらに向かって“喋っている”なんて。
一体何処の誰が信じてくれようか――。
「な、なッ……何なんだお前はぁぁぁ⁉⁉」
ヘクセンリーパーという悪名高き魔女の島にいる事を忘れ、俺は思わず大声で叫んでしまった。でもこれはしょうがねぇ。
だってあろう事かタヌキが喋っているんだからな!
しかも流暢に。しかも人間みたいに2本足で立ってるし。
「まぁまぁまぁ。驚くのは分かるけどさ、取り敢えず深呼吸して落ち着きなよ。話はそれから」
まだ現実を受け止めきれていない上に、俺は今ひょっとしてタヌキに気遣われている?
アクルとエマも驚いているのか、タヌキを見て珍しく呆然としている様だ。しかもこんな摩訶不思議な状況にも関わらず、流石と言うべきなのかリフェルが1番最初に言葉を返した。
「アナタは何者ですか?」
「お、お姉さんすげー美人だね。 ラッキー! こんな美女に助けてもらったのか俺は。名前は?」
「私の質問が先ですヨ」
「これは失礼。助けてもらったのに自己紹介がまだだった。改めて……危ない所を助けてくれてサンキューな。俺の名前は“ルルカ・ヴィクラム・デーヴィ”。信じられないと思うけど、これでもれっきとした人間なんよ。それと一応盗賊やってるんで宜しく!」
「はい。分かりましタ」
「軽ッ! お姉さん面白いね。ヒャハハ」
ルルカと名乗った羽つきタヌキ。 見れば見るほど不思議でならん。
「もしかして……“デーヴィ盗賊団”?」
そう口にしたのはエマであった。
「ん? 俺らの事知ってるのか、獣人族のお嬢ちゃん」
「私のデータからも抽出されましタ。ルルカ・ヴィクラム・デーヴィ。年齢21歳。男。女好きで軽い人間ですが、盗賊としての才能は折り紙付き。彼が10代で結成したデーヴィ盗賊団はその界隈で一躍名を轟かせていますネ」
このタヌキが盗賊団の頭? それも名のある……つか、その前に人間ってどういう事? 情報が渋滞してやがる。
「はぁ~、これは驚いた。お嬢ちゃんもお姉さんも知ってるなんて、俺も随分有名になってるなぁ。お姉さんなんて最早俺のファンだよね」
「あり得ませン。ただアナタの情報を申し上げているだけでス」
清々しいまでの一刀両断。お調子者の彼も流石に戸惑ったみたいだな。
一旦会話が止まった所で今度は俺が彼に聞いた。
「なぁタヌキ。お前が人間ってどういう事だ」
「今度は旦那が質問ね。それにその答えは話すとまぁ長いんよ……。でも噓ではない。お姉さんが言った様に俺は盗賊団の頭であり、ルルカという1人の人間だ。今は“魔女の呪い”によってこんな姿だけどよ」
疑いたくもなるが、そう語るルルカというタヌキの瞳は真剣だった。
「魔女の呪いって……もしかしてこの島にいるヘクセンリーパーか?」
「そうさ。俺が言うのも変だけど、旦那達こそ何者なんよ? こんな所にいて。まさか奴の友達とかじゃないよね」
「まさか。友達どころか見た事もねぇ。何なら名前もさっき知ったばっかりだ。俺達はその魔女にちょっと聞きたいことがあってな」
「へぇ……。まぁ旦那達があの魔女に何の用があるか知らないけど、それは無理かもしれんよ」
「何故だ?」
「何故って……ヘクセンリーパーは俺が“殺す”から」
今までの軽い雰囲気からは一転。
彼の最後の一言からはとてつもない殺意と覚悟の重さを感じた――。