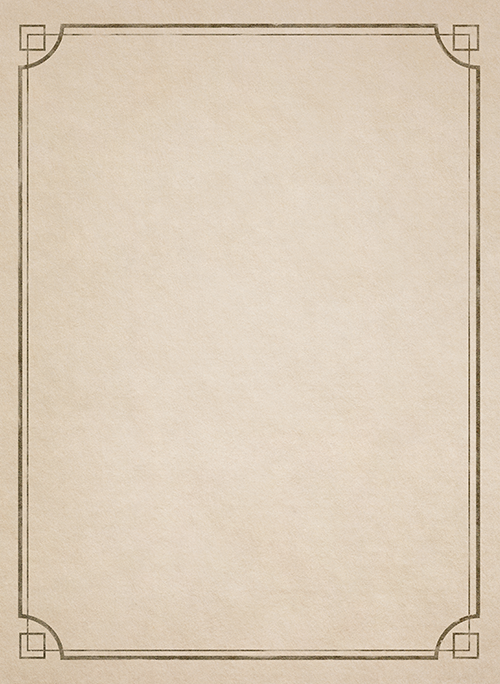時は遡ること小1時間前――。
俺達はこの世界でも“水の都”として有名な、ワーホルム王国を訪れていた。
この王国はその名の通り、王国の実に35%以上が運河である大小13の島々が集まって出来た水の王国である。その美しい街並みから訪れる人も多い世界屈指の観光スポットだ。
「流石ワーホルム王国、壮観だな」
「景色より満月龍よ」
「そうでス。観光に来たのではありませんからネ」
「いつも言ってるが、そんな張り詰めていたら身が持たんぞ」
例え機械とは言えど、リフェルとエマを何気に気に掛けているアクルは面倒見が良い。見た目とは正反対に。
「アクルもジンフリーも毎度呑気な事ばかり言っているからトラブルに巻き込まれるのでス。満月龍を探しているともっと自覚を持ちなさイ」
「全くだわ」
この暫しの旅で、リフェルとエマが思いの外意見が合うという事を俺は知った。
「はいはい。……で、今回は何でワーホルム王国に来たんだ?」
俺の問いかけに答えたのはアクルだった。
旅での行き先はいつもリフェルかアクルが決めている。初めは何故か張り合っていた(リフェルが一方的に)が、探している相手が相手なだけに、最近では協力して少しでも満月龍に辿り着けそうな手掛かりを探ってくれている。
何でも、アクルによるとここのワーホルム王国に、ある1人の“魔女”がいるらしい。これまでの旅の中で、その魔女がどうやら重要な手掛かり掴んでいるらしい。リフェルのデータとアクルの知識、そして旅で得た僅かな繋がりから導き出された様だが、結論この情報も実際に確かめてみないと分からない。それがワーホルム王国に来た理由だそうだ。
唯一その魔女について分かる情報があるとすれば、彼女が“ヘクセンリーパー”と呼ばれる残虐非道な悪名高い魔女であるという事。
そして、そんな彼女の本名が……エル・ヨハネス・“シンラ―”。
そう。
かつてバン・ショウ・ドミナトルと共に紅鏡龍を倒した、ローゼン・シンラ―の末裔である――。
「世間は狭いな」
「まさかヘクセンリーパーがあのローゼンの末裔だとは。流石に本名までは知らなかった。今回の手掛かりは大きいかも知れない」
「兎に角行ってみようぜ。その魔女のところによ」
「勿論行きたいが、そこがまた問題だ」
ワーホルム王国は観光客も多く訪れる治安の良い平和な王国。
だが、そんなワーホルム王国の中でもある1つの島が特別禁止区域に指定されている。特別禁止区域は一般人では出入り出来ない場所。危険なモンスターが生息していたり歴史的価値のある場所だったりと理由は様々だが、ワーホルム王国がその島だけを特別禁止区域に指定した理由が紛れもない、ヘクセンリーパーが住んでいるからである。
「入れない?」
「普通じゃまず無理だ。会うどころか奴は島自体に結界を張っているらしい。魔女の魔力は極めて高い上に、相手があのヘクセンリーパーだからな。もしこの結界とやらが魔術によるものならば強行突破も難しいだろう」
「リフェル、お前の魔法でいけるか?」
「愚問ですネ。まだ私を舐めているのですか。早く行きますヨ」
こうして俺達はリフェルの魔法で、特別禁止区域に指定されているヘクセンリーパーの島へと降り立った。
♢♦♢
~ワーホルム王国・特別禁止区域~
綺麗な街並みが続いていたワーホルム王国とは一変。とても同じ王国内とは思えない程、“この島”だけは異質な空気が漂っている。
見渡す限りの密林。日中にも関わらず何故かこの島だけ暗く、霧がかっているせいで視界もあまり良くない。
「ここが魔女のいる島か?」
「恐らくね」
どうやらリフェルの魔法によって俺達はヘクセンリーパーへの島へと入れた様だが、何故か俺の目の前にはエマしかいなかった。
「はぐれたみたいだな」
「でもこの島にはいるみたい。微かに魔力を感知出来たから」
「そうか。よく分からねぇが取り敢えず2人を探そう」
「はぁ。また面倒が起こりそうね……」
エマがそう静かに呟やいた。だがそれも仕方ない。だってそこら辺にモンスターの気配感じるもん。1体1体大した強さではないが何分数が多い。
「――来るぞ」
「これもきっとオヤジのせいよ」
そう会話した直後、木々の茂みからモンスターが現れた。
「グオォォ!」
――ザシュ!
俺が飛び掛かってきたモンスターを斬り倒すと、それが合図かの如く次から次へと俺達目掛けて襲い掛かってきた。
「全部相手にしてられねぇ。撒くぞ」
俺とエマは向かってくるモンスターを倒しつつ、その場を離れてリフェルとアクルを探した。
「2人の位置は?」
「リフェルは東、アクルは西」
「アイツらは一緒じゃねぇのか。しかも真逆」
「2人とは別に、島の中心でも物凄い魔力を感じるわ」
「そりゃ間違いなくヘクセンリーパーだ。恐らく俺達が島に入った事も気付いているぞ。殺気がビンビン伝わってきてるからな」
話しを聞きに来ただけのつもりだったが、そんな穏便に済みそうもねぇな。
「オヤジ、あれ」
徐にエマが上空を指差す。その方向へ視線を移すと、そこには1つの赤い煙が立ち上っていた。
何だあれ。
そう思ったのも束の間。モクモクと立ち上った煙が上空で突如動き始め、見る見るうちに形を変えていく煙は“集合!”という文字を現した。
「リフェルだな……」
というかそれ以外あり得ない。発想も手段も口調も。まぁセンスは疑うが結界オーライ。これなら全員集まれる。俺とエマは頷き、立ち上る煙の元へと向かった。
そして……。
「――来ましたねジンフリー、エマ。私の合図が助けになったでしょウ」
煙の元まで辿り着くと、何とも言えないドヤ顔で立っているリフェルがいた。
確かに機転を利かせた判断だが、こうも偉そうにされると素直に礼を言いたくないと思う俺は幼稚なのだろうか。
「無事だったか? アクルは?」
「心配無用でス。もうそこまで来ていますヨ」
リフェルの言った通り、俺とエマが着いた数十秒後にアクルも現れた。
「おぉアクル、お前も大丈夫だッ……?」
皆まで言わずそこで止まった。
取り敢えずアクルは見た感じ大丈夫そうなので何より。
それよりも、俺が目に留まったのは“そこ”ではない。きっとリフェルとエマも同じ事を思っている筈。こちらに向かってくるアクルが、何故か心配そうな表情をしながら自分の両手を見ているから。まるでそっと“何か”を持っているかの様に。
「皆無事だったか」
「お前もな大丈夫そうだな。それより、何持ってるんだそれ」
「ああ、実はな……」
アクルはゆっくりとその大きな両手を俺達に見せたきた。
するとそこには、怪我をして血を流しているタヌキの姿があった。
血を流している事にも弱っている事にも勿論驚いたが、何より1番驚いたのは、その横たわるタヌキの背中から何故か鳥の様な“羽”が生えていたから――。
俺達はこの世界でも“水の都”として有名な、ワーホルム王国を訪れていた。
この王国はその名の通り、王国の実に35%以上が運河である大小13の島々が集まって出来た水の王国である。その美しい街並みから訪れる人も多い世界屈指の観光スポットだ。
「流石ワーホルム王国、壮観だな」
「景色より満月龍よ」
「そうでス。観光に来たのではありませんからネ」
「いつも言ってるが、そんな張り詰めていたら身が持たんぞ」
例え機械とは言えど、リフェルとエマを何気に気に掛けているアクルは面倒見が良い。見た目とは正反対に。
「アクルもジンフリーも毎度呑気な事ばかり言っているからトラブルに巻き込まれるのでス。満月龍を探しているともっと自覚を持ちなさイ」
「全くだわ」
この暫しの旅で、リフェルとエマが思いの外意見が合うという事を俺は知った。
「はいはい。……で、今回は何でワーホルム王国に来たんだ?」
俺の問いかけに答えたのはアクルだった。
旅での行き先はいつもリフェルかアクルが決めている。初めは何故か張り合っていた(リフェルが一方的に)が、探している相手が相手なだけに、最近では協力して少しでも満月龍に辿り着けそうな手掛かりを探ってくれている。
何でも、アクルによるとここのワーホルム王国に、ある1人の“魔女”がいるらしい。これまでの旅の中で、その魔女がどうやら重要な手掛かり掴んでいるらしい。リフェルのデータとアクルの知識、そして旅で得た僅かな繋がりから導き出された様だが、結論この情報も実際に確かめてみないと分からない。それがワーホルム王国に来た理由だそうだ。
唯一その魔女について分かる情報があるとすれば、彼女が“ヘクセンリーパー”と呼ばれる残虐非道な悪名高い魔女であるという事。
そして、そんな彼女の本名が……エル・ヨハネス・“シンラ―”。
そう。
かつてバン・ショウ・ドミナトルと共に紅鏡龍を倒した、ローゼン・シンラ―の末裔である――。
「世間は狭いな」
「まさかヘクセンリーパーがあのローゼンの末裔だとは。流石に本名までは知らなかった。今回の手掛かりは大きいかも知れない」
「兎に角行ってみようぜ。その魔女のところによ」
「勿論行きたいが、そこがまた問題だ」
ワーホルム王国は観光客も多く訪れる治安の良い平和な王国。
だが、そんなワーホルム王国の中でもある1つの島が特別禁止区域に指定されている。特別禁止区域は一般人では出入り出来ない場所。危険なモンスターが生息していたり歴史的価値のある場所だったりと理由は様々だが、ワーホルム王国がその島だけを特別禁止区域に指定した理由が紛れもない、ヘクセンリーパーが住んでいるからである。
「入れない?」
「普通じゃまず無理だ。会うどころか奴は島自体に結界を張っているらしい。魔女の魔力は極めて高い上に、相手があのヘクセンリーパーだからな。もしこの結界とやらが魔術によるものならば強行突破も難しいだろう」
「リフェル、お前の魔法でいけるか?」
「愚問ですネ。まだ私を舐めているのですか。早く行きますヨ」
こうして俺達はリフェルの魔法で、特別禁止区域に指定されているヘクセンリーパーの島へと降り立った。
♢♦♢
~ワーホルム王国・特別禁止区域~
綺麗な街並みが続いていたワーホルム王国とは一変。とても同じ王国内とは思えない程、“この島”だけは異質な空気が漂っている。
見渡す限りの密林。日中にも関わらず何故かこの島だけ暗く、霧がかっているせいで視界もあまり良くない。
「ここが魔女のいる島か?」
「恐らくね」
どうやらリフェルの魔法によって俺達はヘクセンリーパーへの島へと入れた様だが、何故か俺の目の前にはエマしかいなかった。
「はぐれたみたいだな」
「でもこの島にはいるみたい。微かに魔力を感知出来たから」
「そうか。よく分からねぇが取り敢えず2人を探そう」
「はぁ。また面倒が起こりそうね……」
エマがそう静かに呟やいた。だがそれも仕方ない。だってそこら辺にモンスターの気配感じるもん。1体1体大した強さではないが何分数が多い。
「――来るぞ」
「これもきっとオヤジのせいよ」
そう会話した直後、木々の茂みからモンスターが現れた。
「グオォォ!」
――ザシュ!
俺が飛び掛かってきたモンスターを斬り倒すと、それが合図かの如く次から次へと俺達目掛けて襲い掛かってきた。
「全部相手にしてられねぇ。撒くぞ」
俺とエマは向かってくるモンスターを倒しつつ、その場を離れてリフェルとアクルを探した。
「2人の位置は?」
「リフェルは東、アクルは西」
「アイツらは一緒じゃねぇのか。しかも真逆」
「2人とは別に、島の中心でも物凄い魔力を感じるわ」
「そりゃ間違いなくヘクセンリーパーだ。恐らく俺達が島に入った事も気付いているぞ。殺気がビンビン伝わってきてるからな」
話しを聞きに来ただけのつもりだったが、そんな穏便に済みそうもねぇな。
「オヤジ、あれ」
徐にエマが上空を指差す。その方向へ視線を移すと、そこには1つの赤い煙が立ち上っていた。
何だあれ。
そう思ったのも束の間。モクモクと立ち上った煙が上空で突如動き始め、見る見るうちに形を変えていく煙は“集合!”という文字を現した。
「リフェルだな……」
というかそれ以外あり得ない。発想も手段も口調も。まぁセンスは疑うが結界オーライ。これなら全員集まれる。俺とエマは頷き、立ち上る煙の元へと向かった。
そして……。
「――来ましたねジンフリー、エマ。私の合図が助けになったでしょウ」
煙の元まで辿り着くと、何とも言えないドヤ顔で立っているリフェルがいた。
確かに機転を利かせた判断だが、こうも偉そうにされると素直に礼を言いたくないと思う俺は幼稚なのだろうか。
「無事だったか? アクルは?」
「心配無用でス。もうそこまで来ていますヨ」
リフェルの言った通り、俺とエマが着いた数十秒後にアクルも現れた。
「おぉアクル、お前も大丈夫だッ……?」
皆まで言わずそこで止まった。
取り敢えずアクルは見た感じ大丈夫そうなので何より。
それよりも、俺が目に留まったのは“そこ”ではない。きっとリフェルとエマも同じ事を思っている筈。こちらに向かってくるアクルが、何故か心配そうな表情をしながら自分の両手を見ているから。まるでそっと“何か”を持っているかの様に。
「皆無事だったか」
「お前もな大丈夫そうだな。それより、何持ってるんだそれ」
「ああ、実はな……」
アクルはゆっくりとその大きな両手を俺達に見せたきた。
するとそこには、怪我をして血を流しているタヌキの姿があった。
血を流している事にも弱っている事にも勿論驚いたが、何より1番驚いたのは、その横たわるタヌキの背中から何故か鳥の様な“羽”が生えていたから――。