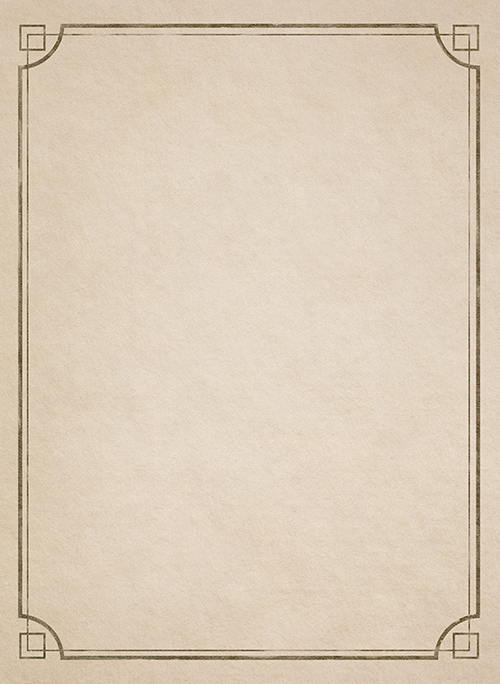「何をしている」
「アクル……」
暴れてクールダウンした様子のアクルが俺達の元へ来た。
「その獣人族の子供は……」
「ハイ。ピノキラーです」
その名を聞いたアクルも少し驚いていた。
「ピノキラーの正体がまさかこんな子供だったとは。それにしても、何故コイツだけ残っている? さっきお前が魔法で全員飛ばしたのだろう?」
「言っておきマスが決して私のミスではありマセン」
「だったらどうしてこの子供だけ……」
「私ガ使った魔法は強制移動ノ魔法。対象者ヲ“元の場所”ヘト飛ばすのデス。人間ヤ獣人族なら家、動物やモンスターなら住処とイッタ様に、魔法の対象とナッタ者が無意識に1番身近だと思ってイル場所へと。
つまり、原因とシテはピノキラー本人にとって、自らがソウ思う、そうダト感じられる“場所がない”ト言う事でショウ。
どんな生物デモ本能的に存在シ得る場所なのデスがね。存在する己の場所がナイ等、とても稀デ珍しい存在デスよピノキラーは。
まぁ満月龍の存在ヨリ遥かに現実的な数値デスが」
リフェルの言葉によって彼女に対する辛さが増してしまった。彼女の感情が元からこうなのか暗殺一家に育てられた結果なのかは分からない。そして今の俺達にはそれを知る由もないのだから。
「リフェル。彼女の鎖を取って檻から出してやってくれ」
「それは危険だろ。見た目は子供でもあのピノゾディ家の殺人兵器だぞ」
「その心配はないでショウ。彼女は“私と同じ”優秀な出来デス。私ノ持つ情報ではピノキラーが独断デ動く事はまずあり得マセン。彼女はピノゾディ家の者と、オークションで競り落とし主とナッタ者の命令シカ聞かないのデス。しかも殺しの命令以外ハ一切反応しない様デスよ」
聞くだけでまたも苛立ちが込み上げてくる。
俺が1人苛立った所でどうしようもないし、そもそも筋違いかもしれない。
こんな事言ったらアレだが……百歩譲って目の前にいる彼女が自分の意志で殺しの道を歩んでいるのなら、それはそれで構わねぇ。他人がどうこう言う問題じゃねぇからな。
でも、これは明らかに違うだろ。子供がする顔じゃねぇ。ピノゾディとか言う奴らも彼女を扱った奴らも、一体どういう神経してやがる。
「さっさと開けろ」
俺はそう言い、リフェルに彼女を解放させた。
そして良くも悪くもリフェルの情報が正しかったのか、静かに檻から出てきた彼女は黙ったまままるで動こうとする気配が無かった。
「名前は?」
「そんなの無い。強いて言えばピノキラーかNo.444。今回の主人はアナタか。誰を殺せばいい?」
彼女の一挙手一投足に、誰かに胸の奥をグッと掴まれている様な感覚を覚える。
「とんでもない子供だ。オラが出会った中で1番悍ましい雰囲気を感じる」
「私達は主人デハありマセン。オークションは潰れマシタ」
「誰も殺す必要はねぇ」
俺達がそう言うや否や、動く気配が無かった彼女が突如踵を返して歩き出した。
「お、おい、ちょっと待て。何処行くんだよ」
反射的に彼女を呼び止めた。だがそれと同時にこうも思った。
彼女を呼び止めてどうすると――。
「何処って、アナタ達が主人でないなら私は帰るだけ」
俺の呼びかけに彼女はそう答えた。そして一瞬足は止めたものの、そのまま振り向きもせずにまた歩いて行った。
“無関係”。
今の俺と彼女に合う言葉はこれ以上無い。
ついさっきまで互いの存在すら知らなかったのに、俺は何故彼女を引き留めているのだろう。自分でも何がしたいのか全く分からないが、無意識に動いていた俺の体が彼女の腕を掴んで止めていた。
「なぁ、ちょっと待ってくれって」
「……?」
「帰る場所なんてあるのか?」
「何言ってるのアナタ。ここでする事がない以上、私は“ノエ様”の元に戻る」
「ノエ様……?」
聞き覚えの無い名に首を傾げると、間髪入れずリフェルのうんちくが飛び込んできた。
「彼女ノ言ったノエ様とは恐らくノエ・ピノゾディ。言ワズもがなコノ世界で1番有名ナ暗殺一家、ピノゾディ家の主デス。
彼の残した伝説は数知れず。初めて彼ガ暗殺をシタとされる6歳の頃カラ現在マデ、約90年以上経った今でも彼は現役だと言われていマス。
その長い歴史の中で、彼に関して分かる情報と言エバ名前と性別と数々の殺しのみ。顔はオロカ、実際に彼ヲ見たという者は片手デ収まる程度だと語らレルぐらい謎二包まれた存在デス。残念なガラ私でも分かりマセン。
デスがそんな彼ニハ、噓か誠か多額の懸賞金ガ賭けられおり、コレまでに様々な裏稼業の者達ヤ腕に自信のアル冒険者達が彼ヲ仕留めようとしマシタが……結果は言うマデもありマセン」
「へぇ、そんな奴がいるのか」
「ノエ・ピノゾディは人間だが、昔からオラも聞いた事がある」
そんな事を話していると、彼女は見事な身のこなしで掴んでいた俺の腕から抜け出した。
「おッ⁉ 何だ今のは……って何で直ぐ行こうとするんだよ」
俺の問いかけに全く反応することなく彼女はまたスタスタと歩いて行く。会ったばかりの彼女を何故こんなに引き留めるのか自分でも本当に理解出来ない。だがこれは理屈じゃなく感覚。
俺の直感が、この子を助けたいと言っているんだ――。
「……分かった。だったら俺がお前の“主人”になる」
「「は?」」
咄嗟に出た言葉だった。
ポカンと口を開けたまま固まっているリフェルとアクルは無視。
今は何より、全く反応を示さなかった彼女が振り返っているという事が重要。
「アナタが……?」
「ああ。お前の最低相場が66,600,000Gなんだろ? だったら俺が買うぜ。他に競り合う奴がいねぇから落札で決まりだ」
「――!」
俺は彼女を落札した。
「アクル……」
暴れてクールダウンした様子のアクルが俺達の元へ来た。
「その獣人族の子供は……」
「ハイ。ピノキラーです」
その名を聞いたアクルも少し驚いていた。
「ピノキラーの正体がまさかこんな子供だったとは。それにしても、何故コイツだけ残っている? さっきお前が魔法で全員飛ばしたのだろう?」
「言っておきマスが決して私のミスではありマセン」
「だったらどうしてこの子供だけ……」
「私ガ使った魔法は強制移動ノ魔法。対象者ヲ“元の場所”ヘト飛ばすのデス。人間ヤ獣人族なら家、動物やモンスターなら住処とイッタ様に、魔法の対象とナッタ者が無意識に1番身近だと思ってイル場所へと。
つまり、原因とシテはピノキラー本人にとって、自らがソウ思う、そうダト感じられる“場所がない”ト言う事でショウ。
どんな生物デモ本能的に存在シ得る場所なのデスがね。存在する己の場所がナイ等、とても稀デ珍しい存在デスよピノキラーは。
まぁ満月龍の存在ヨリ遥かに現実的な数値デスが」
リフェルの言葉によって彼女に対する辛さが増してしまった。彼女の感情が元からこうなのか暗殺一家に育てられた結果なのかは分からない。そして今の俺達にはそれを知る由もないのだから。
「リフェル。彼女の鎖を取って檻から出してやってくれ」
「それは危険だろ。見た目は子供でもあのピノゾディ家の殺人兵器だぞ」
「その心配はないでショウ。彼女は“私と同じ”優秀な出来デス。私ノ持つ情報ではピノキラーが独断デ動く事はまずあり得マセン。彼女はピノゾディ家の者と、オークションで競り落とし主とナッタ者の命令シカ聞かないのデス。しかも殺しの命令以外ハ一切反応しない様デスよ」
聞くだけでまたも苛立ちが込み上げてくる。
俺が1人苛立った所でどうしようもないし、そもそも筋違いかもしれない。
こんな事言ったらアレだが……百歩譲って目の前にいる彼女が自分の意志で殺しの道を歩んでいるのなら、それはそれで構わねぇ。他人がどうこう言う問題じゃねぇからな。
でも、これは明らかに違うだろ。子供がする顔じゃねぇ。ピノゾディとか言う奴らも彼女を扱った奴らも、一体どういう神経してやがる。
「さっさと開けろ」
俺はそう言い、リフェルに彼女を解放させた。
そして良くも悪くもリフェルの情報が正しかったのか、静かに檻から出てきた彼女は黙ったまままるで動こうとする気配が無かった。
「名前は?」
「そんなの無い。強いて言えばピノキラーかNo.444。今回の主人はアナタか。誰を殺せばいい?」
彼女の一挙手一投足に、誰かに胸の奥をグッと掴まれている様な感覚を覚える。
「とんでもない子供だ。オラが出会った中で1番悍ましい雰囲気を感じる」
「私達は主人デハありマセン。オークションは潰れマシタ」
「誰も殺す必要はねぇ」
俺達がそう言うや否や、動く気配が無かった彼女が突如踵を返して歩き出した。
「お、おい、ちょっと待て。何処行くんだよ」
反射的に彼女を呼び止めた。だがそれと同時にこうも思った。
彼女を呼び止めてどうすると――。
「何処って、アナタ達が主人でないなら私は帰るだけ」
俺の呼びかけに彼女はそう答えた。そして一瞬足は止めたものの、そのまま振り向きもせずにまた歩いて行った。
“無関係”。
今の俺と彼女に合う言葉はこれ以上無い。
ついさっきまで互いの存在すら知らなかったのに、俺は何故彼女を引き留めているのだろう。自分でも何がしたいのか全く分からないが、無意識に動いていた俺の体が彼女の腕を掴んで止めていた。
「なぁ、ちょっと待ってくれって」
「……?」
「帰る場所なんてあるのか?」
「何言ってるのアナタ。ここでする事がない以上、私は“ノエ様”の元に戻る」
「ノエ様……?」
聞き覚えの無い名に首を傾げると、間髪入れずリフェルのうんちくが飛び込んできた。
「彼女ノ言ったノエ様とは恐らくノエ・ピノゾディ。言ワズもがなコノ世界で1番有名ナ暗殺一家、ピノゾディ家の主デス。
彼の残した伝説は数知れず。初めて彼ガ暗殺をシタとされる6歳の頃カラ現在マデ、約90年以上経った今でも彼は現役だと言われていマス。
その長い歴史の中で、彼に関して分かる情報と言エバ名前と性別と数々の殺しのみ。顔はオロカ、実際に彼ヲ見たという者は片手デ収まる程度だと語らレルぐらい謎二包まれた存在デス。残念なガラ私でも分かりマセン。
デスがそんな彼ニハ、噓か誠か多額の懸賞金ガ賭けられおり、コレまでに様々な裏稼業の者達ヤ腕に自信のアル冒険者達が彼ヲ仕留めようとしマシタが……結果は言うマデもありマセン」
「へぇ、そんな奴がいるのか」
「ノエ・ピノゾディは人間だが、昔からオラも聞いた事がある」
そんな事を話していると、彼女は見事な身のこなしで掴んでいた俺の腕から抜け出した。
「おッ⁉ 何だ今のは……って何で直ぐ行こうとするんだよ」
俺の問いかけに全く反応することなく彼女はまたスタスタと歩いて行く。会ったばかりの彼女を何故こんなに引き留めるのか自分でも本当に理解出来ない。だがこれは理屈じゃなく感覚。
俺の直感が、この子を助けたいと言っているんだ――。
「……分かった。だったら俺がお前の“主人”になる」
「「は?」」
咄嗟に出た言葉だった。
ポカンと口を開けたまま固まっているリフェルとアクルは無視。
今は何より、全く反応を示さなかった彼女が振り返っているという事が重要。
「アナタが……?」
「ああ。お前の最低相場が66,600,000Gなんだろ? だったら俺が買うぜ。他に競り合う奴がいねぇから落札で決まりだ」
「――!」
俺は彼女を落札した。