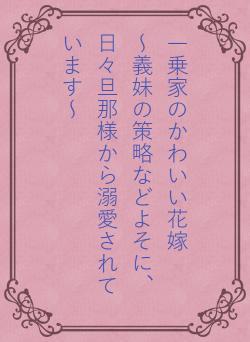1
――花御寮にするのなら、この娘がいいと思ったんだ。
人間を妻とすることは生まれながらに決まっていた。しかも、相手の人間は自分では選べない。界背村が送った人間をそのまま妻とするのが決まりだった。
そんな淡泊な流れで、夫婦らしい何かが芽生えるというのか。
少なくとも自分は、芽生えたという過去の例を、ひとつも知らない。
それが黒王の役目だと言われれば、そうなのだろう。目的は嫁取りというより、次代の黒王を残すことなのだから。
何が花御寮だ。
何が夫婦だ。
全て嘘ではないか。
だから、黒王になると分かった時、密かに界背村を見に行った。多分、ささやかな抵抗だったのだと思う。自分で選ぶことができないのなら、せいぜい全員を見て『どれが来ても変わらんな』と自分を納得させたかったのだと思う。
郷の皆が寝静まった後、一羽の烏姿に転化しひっそりと鳥居を抜け村を飛んで見回った。
現世を訪ねたのは、それが初めてではない。
昔はよく灰墨と一緒に郷を抜け出し、現世をふらりと跳び回っていた。それで、鳥居をくぐって帰ったところでいつもそれぞれの父親に捕まって、げんこつと雷をもらったものだ。
あの時は現世に行くのが楽しかったのに、この時は憂鬱で仕方なかった。
この村のどこかに、自分の妻になる者がいる。
とはいっても夜中だし、見ることができても寝顔だけで、性格も何も分かったものじゃないが。
そんなことを考えながら飛んでいたせいか、それとも転化が久しぶりだったからか。雑木林に入ったところで羽を引っ掛け、墜落してしまった。
しこたま地面に身体を打ち付け、『しくじった』と己の馬鹿さ加減を後悔していれば、カサッ、と何者かが近付いてくる音がしたのだ。慌てて飛び立とうとするも、やはり片羽はまだ動かせず、地面をのたうちまわるだけ。
そうこうしているうちに、声が聞こえた。
若い女の声だった。
ただですらうっそうとして暗い雑木林に、しかもこんな深夜になぜ……。
しかし、人間にここで遭うわけにはいかない。
人間が烏を良く思っていないのは前々から知っていた。妖の姿なら人間など赤子も一緒の存在だが、この姿でしかも怪我までしている今は不利だ。
しかし間に合わず、木の向こうからひょこっと娘の顔が覗いた。
どんな仕打ちを受けるのかと半ば覚悟した時、彼女は驚きの行動に出た。なんと、ためらいもなく己の着物を引き裂き、怪我をしている羽に巻き付けたのだ。すっかり拍子抜けして警戒も解けてしまった。
しかも、呆気にとられていれば、顔をまじまじと覗き込んできて――。
『あなた、珍しい色の羽根と目をしているのね』
『とっても綺麗な色だわ』
と言ってのけたのだ。
しまいには、怪我で飛べないからと、木の実まで口先に並べていった。
なんだこの娘は――と、帰っていく娘の背から、しばらく目が離せなかった。
翌日、郷に戻っても彼女の突飛な行動が信じられなくて、再びこっそりと村を訪ねた。
その日も深夜にやってきた彼女は、寒さに耐えるかのように、膝を抱いて丸く小さくなっていた。
気付けば、彼女の前に降り立っていた。本来なら、自分から人間に近付くなどあり得ない。
顔を上げた彼女は、懐から木の実や干し柿を差し出した。正直、昨夜もだが、腹など減っていない。それにただの烏と違い、木の実など好んで食べたりするものか。
しかし、向けられた弱々しい笑みが、自分のために懸命に笑ってくれているかのようで、気付いたら赤い実をひとつ口にしていた。
『ありがとう、優しいのね』
心臓が止まったと思った。
こんな人間がいるのかと。
その後、『ひとりぼっち』だと言って小さな嗚咽を上げ続ける彼女を、今すぐに抱きしめたいと思ったものだ。
――俺はあの夜からずっと、彼女に心を奪われたままだ。
◆
あふ、と黒王は口元を隠した手の下で、噛み殺せないほど大きなあくびをした。
昨夜は、レイカは何が好きか、何を贈ったら喜ぶかなど、彼女のことを考えていたらすっかり寝付くのが遅くなってしまった。
――何が『古柴レイカはワガママで高飛車』なんだか。灰墨の言葉も当てにならんな。
猫を被っているかもと指摘もされ、初めはそうかもと思っていたが、どう見ても何も被っていない。自分が出会ったあの夜の彼女そのものだった。
しかし、そうなると今度は灰墨の言葉が気になる。
――あいつは、どこでそんな噂を拾ってきたんだ?
大方、同じ名前の別人の噂を間違えて聞いた、といったところか。昔から灰墨にはおっちょこちょいなところがあるし、そう考えるのが自然だ。
そんなことをぼんやりと考えていると、隣から横腹を突かれた。
「――と各里からの報告は以上なのですが……大丈夫ですか、黒王様?」
「ん、ああ。それじゃあ少し休憩を挟もうか」
今、部屋では重役達と共に、各里の定例報告と婚儀の進行についての話し合いが行われていた。半分は上の空だったが、定例報告については事前の報告が上がってきた段階で、全て目を通して把握しているため問題ない。
正直、今すぐにでもレイカに会いに行きたかった。
重役達の厳めしい顔を見るよりも、レイカと桜を眺めながら茶をすすりたい。彼女が隣にいてくれるだけで、陽だまりの中に立つように胸の内側が温かくなるのだ。
しかし、そうも言っていられない。
まだ自分は黒王になって日が浅いのだ。
ここに集った重役達は各里を束ねてくれている者達であり、彼らの力を借りなければならないことも多い。
『黒王』が血統によって継がれることに異議をとなえる者はいない。
黒王が黒王である理由は、鴉一族の中で圧倒的な力を持つからである。
妖と呼ばれる者達は、多かれ少なかれ皆『妖力』を持つ。
それによって様々な術を使えるのだが、黒王は術の規模、精度、強度、どれをとっても他の鴉とは一線画す力を持っていた。
それを可能にしているのが、界背村の娘――花御寮の血である。
界背村の者達の身には、祓魔の力が宿っている。
元をたどれば妖力だが、長い時を経て今や完全に別物となっている。より彼らの世界に馴染むようにと独自の進化をとげ、また、村内婚姻を重ねて力が凝縮されているのだ。
それは大木のごとしで、根は同じだが成長し枝先がのびるにつれ、どんどんと力の性質が離れていった。
そして、性質の異なる力を掛け合わせてきたことで、黒王の血統は抜きん出た力を持つようになった。もし、他の鴉が真似をして界背村の娘に子を産ませても、何代にも渡って力を重ねてきた黒王の力には到底及ばない。
だから皆、黒王が自分より若輩者であろうと『黒王』として敬うのだ。力によって立場が決められる妖の世界では、強さとは崇敬するものであった。
ただ、時には崇敬とは別の感情を抱く者も中にはいる。
「各里変わりないようで何よりだ。そうだ、南嶺。奥方の調子はどうだ? 寝込んでいると聞いていたが」
「おおっ、お気遣いありがとうございます、黒王様! しかし心配はいりませんよ。ただの食あたりですから」
「ははっ、ならば一安心だ」
「いえ、もう本当、うちの妻は食い気がすごくて。しかも寒いと尚更とか言って……今度黒王様からも食べ過ぎるなと言ってやってくださいよ」
「では今度、南嶺の里へと邪魔するかな」
「黒王様が来てくださるのなら、里の者達も喜びます」
こうした何気ない会話で相手の様子を窺うのも重要なのだ。
休憩ということで、皆それぞれの里の様子や、自分の子や孫のことなどの会話に花を咲かせていた。
そこで、「では」と老爺のかすれた声が場をまとめる。
「次は、黒王様の婚儀についてですが。ここからは儀式を取り仕切る私が、話し合いの進行もいたしましょう」
灰墨が老爺――玄泰の目配せに浅く頷く。
さすがに先々代、先代と続けて婚儀を仕切ってきた玄泰は、婚儀までに行われる儀礼についてしっかりと把握している。それに対する段取りにも抜けがない。
「――そして、婚儀の前日ですが、黒王様と花御寮様はそれぞれに潔斎に入っていただきます。黒王様は北の霊泉で、花御寮様は南の霊泉でそれぞれ沐浴していただき、その日から婚儀まで、二人の接触は一切禁じられます」
「一切か……」
たった数時間の会議の間でも会いたくて仕方ないのに、一日も我慢できるか我ながら心配になってきた。
「その後は、祝詞奏上と三献の儀、誓詞奉読と……まあ一般的な婚儀の流れと同じです」
「であれば気をつけるのはやはり前日だな。うっかり東棟に足を運んでしまいそうだ」
悩ましげに前髪を掻き上げながら呟く黒王に、南嶺が愉快そうに目を細める。
「そういえば、黒王様は足繁く東棟に通われているとのこと。お二人の仲がよろしいのであれば、これ以上幸いなことはありませんな」
周囲も南嶺の言葉を聞いて、「それはそれは」と表情をほころばせていた。
しかし、灰墨ともうひとり――玄泰だけは口を引き結んでいる。
「はてさて、それがいつまで続くやら……」
温まっていた場の空気が、一瞬にして凍りついた。
「その花御寮様の仮面が、どこまでもつのかが問題ですな」
「俺の花御寮は仮面など被っているようには見えんがな? とても美しく可憐な容貌だぞ」
玄泰の皮肉に皮肉で返せば、彼ははっと鼻で一笑し、腰をゆっくりと上げる。
「私は、そろそろこの花御寮という習わしを、やめてもいいと思っておりますがね」
「俺のことよりも、郷の外の妖はどうした? 自分から名乗りを上げたんだ。しっかりと対処できているのだろうな」
「もちろんですよ。里の若手もいましたし、私も黒王様のような力は持たずとも、これでも長年里長を任されてきた身でしてね」
少し曲がった腰で手を結び、玄泰は足で畳を擦るようにして部屋を出て行く。しかし、廊下に出たところで「そうそう」と歩みを止めて、黒王へと首を返した。
「女官達が、花御寮様は未だに湯殿や着替えの手伝いをさせてくれぬから、暇になってしまうと嘆いておられましたぞ。やはり花御寮様は妖に触れられるのを、心の中では嫌悪されているのかもしれませんなあ」
黒王の目がじわりと見開く。
玄泰は黒王の表情を目の端に捉えると、猿のように皺だらけになった口元を笑ませて、去って行った。
「気になさいますな、黒王様。玄泰殿は二代にわたって花御寮様と接してこられ、色々とその……苦労されてきたようですから」
他の重役からの慰めの言葉に、黒王はチッと口の中で舌打ちした。
――王が憐れまれてどうする。
「……分かっているさ」
本当、食えない爺だ。
◆
「レイカ、いるか!」
いつものように菊が広間で若葉や女官と談笑していると、入り口が開くなり荒っぽい声を飛んできた。
「あら、黒王様。こんにちは」
しかし、誰が入ってきたか分かっている菊達は特に驚くこともなく、黒王ににこやかな挨拶を向ける。
彼は広間に入るなり荒々しい足取りで一直線に向かってきて、菊の左隣でぴたっと肩をくっつけるようにして座った。いつも、いつ来たか分からないくらい静かに入ってくるのに、今日はまたどうしたことか。
「まあまあ、黒王様ったら。それでは花御寮様が動けないじゃありませんか」
若葉は黒王に場を譲るように菊の傍から一歩分さがり、女官達は微笑ましい者を見るような顔をして、ほほと袂を口に当てながら部屋を出て行く。
「黒王様、何かありました? ご様子がいつもと違うように思うのですが」
「んー……別に。レイカの顔を見たら良くなった」
低く抑揚のない声で言われても、説得力がないのだが。
しかも肩はくっついているのに、黒王はそっぽを向いているから、菊からは様子が見えない。顔を覗き込もうと、菊がそうっと身体を傾けて前から回り込もうとするも、気付いた黒王に「見るな」とばかりに、床についていた左手を握られてしまった。
「ふふ、今日の黒王様は、ご機嫌なななめなんですね」
「…………」
また手をぎゅっと握りしめられる。
どうやら、もうしばらくはこのままのほうが良さそうだ。
「若葉さん、すみませんが文机を」
「かしこまりました」
若葉は分かったように立ち上がると、文机と一緒に墨や筆が入った硯箱も持ってきて、菊の前に整えた。
左手は黒王に握られたままで動かすのははばかられ、筆を持った右手だけで文字の練習をしていく。暇さえあれば本の書き取りをしてきたためか、今では平仮名であれば全て、漢字も簡単なものであればいくつかは書けるようになっていた。
若葉が紙を押さえ、菊が書いていく。
紙をめくる音と筆が滑る音だけが部屋に響く、穏やかな時間が過ぎていく。
「……何を書いてるんだ」
少し落ち着いたのか、黒王の顔がようやく菊の方を向いた。
「色々ですよ。今は、若葉さんや女官の皆さんの名前を書いてます」
平仮名ですけどね、と筆先を上げて、書いた文字を黒王から見えやすくする。
紙には、上手いとは言いがたいひょろりとした文字で「わかば」や「こうづき」「ももせ」などと書いてあり、黒王が首を伸ばしてまじまじと覗き込んでくる。
てっきり「まだまだ下手だな」などと笑ってくれるかと思っていたのだが、なぜか黒王の口はみるみるへの字になっていく。
「え、え!? あ、あの、黒王様!? 私何か失礼を……!?」
戸惑いにおどおどする菊だったが、その隣でなぜか若葉が吹きだした。
「え、若葉さん?」
「…………若葉」
黒王が、ぼそりと非難めいた声で若葉をたしなめる。
「……っし、失礼……っふふ」
顔を袖で隠していても、全身が小刻みに揺れているせいで、笑っているのがばればれである。というより、黒王はなぜ難しい顔になり、若葉は笑いをこらえているのか。
「若葉っ」
しかし、黒王には若葉が笑っている理由が分かるらしく、また若葉を、今度は先ほどよりも強い声でたしなめていた。
――なんで分かるのかしら。
菊には二人の表情の意味が分からないのに。
二人の間で顔を往復させていた菊は、無意識に己の胸元にカリッと爪を立てていた。
「ふっ……はいはい。それでは怒られてしまいましたし、わたくしはこれで失礼いたしましょうかね。黒王様、言いたいことは口になさならないと伝わりませんよ」
「――っ若葉!」
とうとう声を上げた黒王などなんのその。若葉は「ほほほー」と満足げな笑声を響かせながら、パタンと扉の向こうへと消えていった。
はぁ、と大きな溜息と共に前髪を乱暴に掻く黒王は、菊が初めて見るもので、珍しい粗野な姿に思わず見とれてしまう。
「ったく、あいつは昔っから……」
しかし、彼が呟いた言葉で、瞬く間に菊の高揚は醒め、それと共に顔まで俯く。
「どうしたんだ、レイカ?」
二人は言葉を交わさずともわかり合っていた。
しかし、自分は口にされないと分からないらしい。
それがなんだか、少し悔しくて、もやっとするのだ。
――なんなのかしら、これ……。
「……昔から黒王様と若葉さんは、そのように仲がよろしかったのですか?」
隣で黒王が笑う気配がした。
顔を上げれば、黒王がくつくつと喉を鳴らして笑っている。楽しそうに頬を緩め、こちらを見ているではないか。
しかし、なぜ彼が笑っているのか、菊にはまた分からない。
「安心しろ、若葉とは幼馴染みなだけだ」
「あ……そう……なんです、ね」
すーっと胸にわだかまっていた何かが晴れる心地がした。
ニヤニヤと揶揄い顔を黒王が近づけてくる。
「妬いたのか?」
「妬く?」
「俺と若葉の関係に嫉妬したのかと聞いているんだ」
「……分かりませんが……それは、この胸のあたりが、もやっとしたことを言うのでしょうか?」
こてん、と菊が首を傾げてみせれば、黒王は口をぽかんと開けたまま一歩後ずさった。
「どうされたのです、黒王様?」
顔が真っ赤だ。
「――っ無自覚か!?」
何がだろうか。
「婚儀までまだ数日あるのに、勘弁してくれ……っ」
「それよりも、黒王様こそ、先ほどのへの字口はなんだったのですか?」
「それよりもとは……」
きょとんとして本気で分からないといった顔をする菊に、黒王は明後日の見つめながら、後頭部をがしがしと乱していた。
「あれは、その……若葉や女官達の名前ばかり書いていたから……」
「しかし、黒王様のお名前を私はまだ聞かされておりませんから」
そこで菊は、はた、と気付く。
「もしや、お名前が『黒王』というわけではありませんよね?」
「……筆を貸せ」
言うが早いか、黒王は菊の手から筆を抜き取ると、さらさらと筆を走らせ文字を書いた。
「俺の名だ」
菊にも分かる達筆さなのだが、漢字で書かれているため読めず、読み方を聞こうとしたら、それよりも早く黒王の口が菊の耳元で囁いた。
「――――」
聞いた名を呟こうとして、人差し指を口に乗せられてしまう。
「決して他人に知られてはならない名だ。だから、レイカにだけ教えた。二人きりの……特別な時にだけ呼んでくれ」
菊は紙に書かれた二つの漢字をじっと眺め、音を伴わず呟いた。
すると、水が湧き出るように胸の中で何かがこみ上げてきて、何度も何度も口に馴染ませるように、刻み込むかのように、菊はひとり呟き続ける。
「それにしても、レイカは十九だろう。今まで嫉妬したりなかったのか? 村で想いを寄せた者や、寄せられた者くらいいただろう? ああ、いや……俺としてはとても嬉しいことなんだが……」
菊は苦笑した。
「村にどのような者がいるのかすら私は知りませんでしたから……誰かに特別な感情を覚えるというのもなかったんですよ」
「そう……か」
「はい」と微笑んだ菊と、黒王はその日も若葉に「そろそろ夕食の時間ですので」と言われるまで、並んで春風を共に感じていた。
「…………」
母屋へと戻る廊下の半ばで、ふと黒王は足を止めた。
「……灰墨」
ぼそりと呟けば、一羽の烏が飛来し横の欄干に着地する。
名前を呼べば、彼はすぐにやって来る。たとえそれが独り言の大きさでもだ。それが近侍である。
「何か」
「調べてほしいことがある」
「どのような」
「界背村へ行け。そして〝古柴レイカ〟についてもう一度調べてきてくれ」
「花御寮様について? 今更ですか?」
「同じことでもなんでもいい。とにかく彼女に関すること全てを持ってこい」
「かしこまりました」
2
――なんだか、村にいたのがもう随分昔のことのようだわ。
実際はまだひと月も経っていないというのに。
今日は、昼から仕事があるからと、彼は朝早くからやって来た。
忙しいのなら無理して訪ねてこなくても大丈夫だと伝えたのだが、彼は「俺が会いたいだけだから」と言って頬を撫でてくれた。彼の名前を書けるようになったと報告すれば、頭を撫でてくれた。
――なんなのかしら……この気持ち……。
彼に撫でられた頬の感触を思い出しただけで、顔が熱くなる。
最初は、伸ばされた彼の手を怖いと思った。
でも、今では彼に触れてほしいと、自ら頬を差し出しそうになる。
もっと、もっとたくさん、色々なところを彼に触れてほしい。
「――っああ、私ったらなんてことを……っ!? はしたないわ……」
耳の奥まで沸騰したように熱くなった顔を、自らの両手で包んで冷やす。
「良かった……若葉さん達がいない時で……」
こんな顔を見られたら、病気かと騒ぎになるところだった。
若葉達は今、それぞれの持ち受けた仕事で、広間の外に出ている。特に今は、婚儀を目前にして衣装の準備や、用具の確認などで忙しいようだ。しかし、声を掛ければ、誰かしらがすぐにやって来てくれるため、困ることはない。
「本当……どうしたのかしら、私……」
菊は風でも浴びようと広庇へと出て、庭に面した欄干に身体をもたれさせた。
眼下では、桜の薄紅だけでなく、すみれの紫やたんぽぽの黄色、名を知らない小花の水色や桃色が咲き誇っている。
「あ、あの桜の木は……」
たくさんの桜の木が植わっているのだが、桜の花々で隠された庭の奥にある一本は、かつて黒王と共に腰を下ろして眺めた桜ではないだろうか。
あの日に誓った――凍えていた彼を温めようと。彼が、ずっと笑っていられるように。
――私はずっと彼の傍にはいれないから……。
「少しでも彼の心が癒えてると良いんだけど」
傷は簡単に癒えない。
しかし、花御寮としてここで過ごすようになって、確かに菊の中の傷は癒えていっていた。そして癒えた場所に、別の何かが芽吹き始めているような気がする。
それがなんなのかは分からない。
ここでもまた、生まれて初めてを経験していた。
「何かしらね」
桜の麓を眺め続けていると、ふと背中を支えてくれていた、彼の大きな手の逞しさを思い出してしまった。
たちまち耳まで熱くなる。
「……もうっ」
手でパタパタを顔を扇ぐ。花の香りを含んだ風が、ちょうど良い冷たさで心地よい。
花御寮になってからというもの、菊が得る感情は未知のものばかりで、毎日が大忙しった。
胸が躍るようなことから、締め付けられるようなこと。凪ぐような時もあれば、毛が逆立つような時もあった。
「そういえば、昨日のあれはなんだったのかしら」
胸の内側が、なんというか不愉快だった。しかし、今こうして指でカリカリと掻いてみても何も感じない。昨日は掻いても消えないもやもやをもどかしく思っていたのに。
「嫉妬……なのかしら? でも、どうして……」
菊は振り返り、正面にある広間の入り口を眺めた。
扉はぴったりと閉まっており、うんともすんとも開く気配がない。
「……仕事って言っていたもの。来ないわよね」
そこで菊は、今あの扉が開いて彼が顔を出してくれないかと、自分が願っていることに気付いた。
「そういえば、いつからかしら」
彼が来るのが待ち遠しく感じたり、帰っていく背中を寂しく思い始めたのは。
最初は、彼が来れば恐ろしく、帰ればほっとしていたというのに。
「…………」
菊は、入り口を眺めながら、欄干に引っ掛けた腕に頭を乗せた。
自分の頬が、ほのかに温かくなっていくのを感じる。胸の内側がむずむずとする。でも、爪を立てたくなるような不快感はない。
「なんなのかしら……」
答えは出ない。
しかし、この感情は決して悪いものではないのだろう。
◆
東棟を訪ねれば、彼女は青草の爽やかさが香るような笑みで迎えてくれる。
今日は朝から訪ねたのだが、若葉達が部屋を出て二人きりになった途端、耳元に顔を寄せてきて。
『お名前、書けるようになりました』
と、囁かれた。
それが嬉しくて嬉しくて、ニヤける口元を隠すのに大変だった。
口を押さえて言葉を発せなかったため、代わりに頭を撫でてやれば、彼女は照れたように「ふふ」と笑った。
その穏やかさがまた可愛くて、たまらなくて。
彼女が自分のことをどう思っているのかは分からない。
ただ、どのように思われていようと、暖かな陽だまりのような彼女の隣にいれるだけで、心地よくて、幸せだった。
傍にいてくれるだけで……良かったのだ。
しかし、名残惜しさを感じながらも、午後からの仕事があるため早々に母屋へと戻ってきたのだが、それどころではなくなってしまった。
「――デタラメを言うなっ!!」
三日ぶりに帰ってきた灰墨の報告を聞いて、黒王は母屋中に響き渡るほどの怒号を落とした。
「しばしお待ちを」
しかし、灰墨は少しも臆することなく座を立つと、閉まっていた障子を開け、外の様子をきょろきょろと窺い戻ってくる。
「黒王様、もう少し声を落としてください。人払いをお願いしましたが、あまりにもですと女官達が駆けつけてくるかもしれません」
「……なるほど。このための人払いだったか……」
怒号と一緒に落とした拳により、脇息が半ばから綺麗に折れていた。
「花御寮が嫌いだからと、適当なことを言っているんじゃないだろうな、灰墨」
「そんなことしないのは、黒王様が一番分かってますよね」
「…………悪い」
灰墨が折れた脇息を手際よく片付けていく。
黒王は置き所のなくなった手で顔を覆った。
「レイカが……っ身ごもっているだと……」
灰墨は当初、既に嫁入った者のことなど誰が噂するというのだろうと、きっと大した情報は得られないなと期待していなかった。
しかし、界背村に入り自分の認識を改めた。
村の者達は、あちらこちらでヒソヒソと『古柴家の娘』や『レイカ』という言葉を口にしていたのだ。
何をそんなに彼女のことで話すことがあるのか、と聞き耳を立てれば、村人達はどうやらひとつの話題ばかりをはなしている様子だった。
『さすがレイカだわぁ。私だったら万が一を考えてそんなことできないわよ』
『古柴家だからって、結構彼女だけ色々と許されてたもんね』
『でも、だからってまさか、妊娠してたなんて』
灰墨は耳を疑った。
冗談だろう、と。
もしかして、村にはレイカという名前の女が他にいて、そちらの者のことだろうと。しかし、それから隅々まで村を跳び回って村人達の声を集めたが、〝古柴レイカ〟どころか〝レイカ〟という名前の女はひとりしかいないという裏付けにしかならなかった。
そして、彼女が身ごもっていたということも。
「村はその噂で持ちきりでした」
「……村人達はどうやってレイカの身ごもりを知ったんだ」
「花御寮様には元々恋人がいたそうです。本来村の掟では、花御寮候補者はその期間が過ぎるまで、異性と深い仲になることを禁じられているそうです。が、彼女の場合は相手の男含め、村の有力家だったようで、清い関係であればと大目に見られていたようです」
「清い関係な……」
どうやら村の大人達の譲歩は、見事に裏目に出たようだ。
「深い仲の恋人がいたのは分かった。だが、どうして今さら噂になっているんだ」
「どうやらその男、長らく仕事で村の外に出ていたようで。古柴レイカが花御寮に選ばれたことも、嫁入りしたことも知らなかったらしく。仕事を終え村に戻ってきた時、他の村人から聞いて『レイカの腹には俺の子がいるんだぞ!』と随分と騒いだようです」
「なるほどな。それでその男と……古柴家はどうしている」
「まず古柴家の方ですが、嫁入り以降火が消えたように静からしいです。使用人も、娘が花御寮となってから入れていないようですし」
「娘がいなくなったショックか」
「男の方はしばらく騒いでいたようですが、今は落ち着いているみたいですね。ただ、それでも内容が内容なので噂は未だ……という感じです」
正しく状況を把握するために、なんとか冷静に話を聞くことはできたが、こうして座っていても頭がクラクラする。胸の内側は焼けるように熱いのに、頭の中は凍ってしまったかのように、恐ろしいほど冷えていた。
――レイカの腹の中には、既に別の男との子が宿っている……?
この紫色を、綺麗だと微笑んでくれた彼女の中に?
嘘を吐かないと、小指を差し出してくれた彼女の中に?
自分の真名を記憶するために、何度もあの愛らしい唇で口ずさんでいた彼女の中に?
「…………っ!」
前髪を握りこんだ手の中で、ブチブチと髪が切れる感覚があった。しかし、痛みは感じない。
黒王の憤る姿に、灰墨の目も悲しそうに眇められていた。
「そりゃ人間は嫌いですし、花御寮制度なんかなくなれって思ってますけど……でも、黒王様が笑われる姿が増えて、良かったとは思ってたんです。だから……その笑顔がなくなるようなこと、本当は持ち帰りたくなくて……」
以前、古柴レイカを調べると言って村へ行った時は、灰墨は一日で帰ってきた。今回三日もかかったのは、噂が間違いであることを突き止めようと、頑張ってくれたからだろう。
「分かっている……余計な苦労をかけたな、灰墨」
ありがとう、と労ってやりたいのに上手く言葉が出なかった。
正直に言うと、聞きたくなかった。
しかし、彼女に関する情報を全て持ってこいと言ったのは自分だ。灰墨は何も悪くない。悪いのは、彼女の一言に違和感を覚えてしまった自分なのだから。
彼女に関しては、以前からちょこちょこ、と首を傾げたくなるようなことはあった。
たとえば、聞いていた性格と違うとか、文字の読み書きができないとか。しかし、性格に関しては、相手によって評価も変わるだろうし、読み書きは、得手不得手があるだろうと、さして疑問は抱かなかった。
しかし、『村にどのような者がいるのかすら私は知りませんでしたから』という言い方には引っかかりを覚えた。
村人に噂される程度の関わりはあるのに、『知らない』などということがあり得るのだろうかと。
その些細な引っかかりを解消しようとした結果――。
「……ますますレイカが分からなくなった」
――俺があの夜に出会った彼女と今の彼女、そして噂の彼女……どれがいったい本物なんだ。
すると、もじもじと灰墨が視線を送っているのに気付く。
「どうした、灰墨」
灰墨が、ためらいがちに口を開いた。
「黒王様……花御寮様って確か、女官達に湯殿や着替えの手伝いをさせないって話でしたよね」
ハッとした。
「それって、膨らんだ腹を見られないようにするためじゃ……」
「……下がれ……灰墨。このことは他言無用だ……」
「黒王様! 花御寮様を村へ送り返してやりましょうよ!? 別の花御寮でも良いじゃないですか! だって下手したら、見知らぬ人間の男との子を育てるはめになってた――!」
「下がれ、灰墨っ!!」
もう何も聞きたくない。
黒王は意思表示をするように、瞼を閉じ顔を俯けた。
「黒王様……っ」
憐れみと悔しさを滲ませた声で灰墨が呼ぶが、これ以上は何も考えたくないのだ。
「下がれ…………」
喉から絞り出した声は、自分でも聞いたことないような悲壮感が漂っていた。
灰墨が立ち上がる衣擦れの音がした後、すーっと障子が開いて、また閉められる音がした。
トン、トン、と足音が部屋から遠ざかっていく。
部屋に落ちる静けさが耳に痛かった。
いや、耳よりももっと別のところが、掻きむしりたくなるほどに痛かった。
「それでも俺は……っ」
瞼の裏では、彼女が『黒王様』と呼んで笑っていた。
いつも扉を開けると、春陽が降りそそぐ明るい広間で、彼女はちょこんと座っている。そしてこちらに気付くと彼女は、ふっ、と顔をほころばせるのだ。
桜色に頬を染めながら。
「っああ……こんな時に好きなものを知るとはな……」
彼女の桜色に染まる頬が好きだ。
彼女の小鳥がさえずるような愛らしい声が好きだ。
彼女の「黒王様」と言う小さな口が好きだ。
彼女の穏やかに下がった眉と、猫のように少し跳ねた目元が好きだ。
彼女の真っ直ぐに見つめてくる、烏の色と同じ真っ黒な瞳が好きだ。
すっぽりと握れてしまう小さな手も、懸命に後をついてくる狭い歩幅も、景色を見るたびにうっとりとした息を漏らすところも……。
「――――っ!」
何もかも。
全部。
彼女が狂おしいほどに好きなんだ。
「もう……俺には彼女を手放すことなど……っ」
たとえ、別の男の子を身ごもっていようと――。
3
桜も八分咲きとなり、風が吹けば淡い花びらを広間に散らすようになった。
広間と続きになった広庇から見える景色は、夕日を浴び薄紅色の花びらが茜色に染まり、圧巻の一言だ。
しかし、そんな美しい景色の中、菊は先ほどからずっとチラチラと部屋の入り口を気にして、若葉の話も上の空という感じだった。
「花御寮様、気になりますか?」
「えっ、何がですか」
「何がですか、じゃないですよ。昼過ぎからずっと入り口ばかり気にして。分かりやすすぎです」
若葉が目も口も弧にして、隣へとにじり寄ってくる。「もうっ」と肩をグイグイと押され、なぜだか気恥ずかしくなった。
「私、そんなに分かりやすかったですか?」
そりゃあもう、と若葉は大げさに頷く。
「黒王様をお待ちなんでしょう?」
「……はい」
返事した菊の声は、消え入りそうなほど小さかった。
「確かに、今日はどうしたことでしょうか。もう夕刻だというのに、黒王様がまだお見えにならないとは……」
「お仕事でしょうか」
「そうかも知れませんね。婚儀も近いですから」
「婚儀……」
その日を迎えれば、全てが明らかになる。
――そうしたら、私はどうなるのかしら。
少なくとも、もうここにはいられない。
この美しい景色とも、暖かな陽射しとも、優しい女官とも、姉のような若葉とも、お別れだ。そして……。
――彼とも……。
傾く夕日のせいだろうか、心がきゅうと締め付けられ、なぜだか虚しくなった。
「大丈夫ですよ。皆、花御寮様が黒王様の正妻になられるのを心待ちにしているのですから。慣れないことも多いでしょうが、その都度わたくし達がお助けしますから」
押し黙ってしまった菊の肩を、若葉がゆるりと撫でた。婚儀を間近に控えて不安に思っていると、勘違いされたようだ。
菊は、曖昧に笑った。
「そういえば、若葉さんは黒王様と幼馴染みだとか。よければ黒王様について聞かせてくれませんか」
「うふ、花御寮様も黒王様のことが好きなのですねぇ。おふたりに仕えるわたくしにとっては、喜ばしいことです」
「え、好き……?」
これ以上婚儀のことは考えたくなくて、別の話題を探してふっと出てきたのが彼だったというだけで、『好きだから』などとは考えなかったのだが。
――しかも、『花御寮様も』ってことは……。
まさか、黒王は自分のことを好きなのか。
確かに彼は優しいし、よく微笑みかけてくれる。
でも、それはそういう優しい性格の人だと、自分の花御寮だから気遣っているのだと思っていた。以前、若葉も彼はとても優しい人だと言っていたし。
悩む菊を置き去りに、若葉は嬉しそうに「小さい頃の黒王様は……」などと、さっそく語り始めている。
「まあまあ、それはそれはやんちゃでしたよ」
「え、あの黒王様がですか!? とても落ち着いた方ですが……」
「猫かぶりです。花御寮様に格好よく思われたくて、一生懸命につくろっているんですよ。わたくしの方が、えっと……三つ年上なのですが、もうそれは昔っから随分と手を焼かされたものですよ。わたくしの母が先代の花御寮様に仕えていたのもあり、よくわたくしもお屋敷に連れてこられていまして」
「ああ、それで幼馴染みなんですね」
「ええ、年が近くてちょうど良いからと、黒王様と、乳母兄弟の灰墨という者がいるんですけど、いつの間にかそのふたりのお世話係にされてましたね。花御寮様は灰墨をご存知で?」
「い、以前、母屋に行った時にチラッと……」
菊が困ったように笑ったのを見て、若葉は「あー」と理由を察する。
「灰墨は昔から黒王様に憧れてましたからね。だからその黒王様が……」
その先を言いにくそうに若葉が言葉を濁す。
「ええ、黒王様から聞いてます。そんなことがあれば、誰だって人間が嫌いなって当たり前ですよ」
なるべく直接的には言わず知っているということを伝えれば、たちまち若葉の涼しげな両目が大きく、眦が裂けんばかりに見開かれた。
「え、あ……ま、まさか聞かれたんですか? 黒王様から先代花御寮様のことを」
そんなに驚くことだろうか。
素直に菊が頷くと、若葉は今度は目を細め、はぁと吐く息を震わせていた。
「良かった……っ本当に……あなた様が花御寮になってくださって。あの件で、彼は心を閉ざしてしまい、ほとんどの感情を失っていました。以降、決して誰にも先代花御寮様の話や、その件について口にはしませんでしたから」
「感情を失う……分かる気がします」
村にいた時の自分も、感情など苦しいと悲しいくらいしかなかったものだ。それが当たり前になりすぎて、他の感情があることもすっかり忘れていた。
考えると絶望に打ちのめされそうになるから、どうでもいいと無心で生きるしかなかった。
「でも今、黒王様は信じられないくらいに穏やかに笑われます。帰られる時も、とても名残惜しそうに広間を何度も振り返りながら」
「知らなかった……です」
――私だけじゃなかったのね……。
閉まった扉に名残惜しさを感じていたのは。
きょとんとしてこぼせば、若葉は眉を垂らして「そうでしょうとも」と肩を揺らした。嬉しくて仕方ないといった様子で、目尻を濡らしている。
「まるで幼い頃のあの子を見ているようで……感情豊かに、日々を楽しんでいるあの頃に戻ったようで、わたくしはとても嬉しかったのですよ」
握りしめた菊の手に、若葉は敬うように額をあてがう。
「彼の心を取り戻してくださって、ありがとうございます。侍女の若葉ではなく、彼の幼馴染みとして心より感謝しております」
彼女の手は小刻みに震えていた。どれだけ彼女が彼のことを気に掛けていたのか伝わってきて、菊も思わず目頭が熱くなる。
――誰かが喜ぶのが、こんなにも嬉しいことだなんて。
「私、黒王様の花御寮になれて良かったです」
心からの言葉だった。
しかし、自分がその名前で呼ばれるのもあと数日。瞬間、胸の奥が痛いほどに締め付けられる。しかし、菊はその感情を見ないふりした。
その代わり、痛みを誤魔化すように菊はチラッと横目で入り口を窺った。
「黒王様もそう思ってくださってたら嬉しいんですけど……」
なぜだか泣きたくなった顔に、無理矢理笑みを貼り付ける。
「大丈夫ですよ。きっと明日は訪ねてこられます。たくさん文字を練習して、驚かせましょう!」
「そうですね」
若葉はちゃんと騙されてくれたようで安心した。
まだ自分はしっかりと花御寮をできている。
◆
しかし、次の日も、そのまた次の日も、彼は姿を現さなかった。
病気なのではと心配になり、若葉に様子を尋ねたりもしたが、彼女は病気ではないと首を横に振った。
「仕事が詰まっているのかとも思いましたが、今の黒王様でしたら、一瞬でも手すきの時間があれば飛んできそうなものですのに」
「あの、私から黒王様を訪ねてはいけませんか?」
あと僅かな限られた時間は、少しでも多く彼と過ごしたかった。
菊の提案に、若葉がパンッと手を打つ。
「そうですよ。待っている必要なんかありませんものね! 花御寮様は母屋でも他の棟でも、ご自由に歩かれて良いんですよ」
どうやら今までの花御寮は、東棟からは絶対に出ようとしなかったとかで、若葉もすっかり忘れていたらしい。
確かに、嫁入りを泣き叫ぶほど嫌がっていたのなら、わざわざ東棟を出て人の多い母屋へと行こうとは思わないだろう。
「では、若葉さん。供をお願いします」
こうして菊は、東棟を出て母屋へと向かったのだった。
母屋には以前黒王に手を引かれて一度来たきりだったが、若葉がいてくれたおかげで迷いはしなかった。そして、黒王の行動範囲を把握している若葉によって、あっという間に彼は見つかった。
「こんにちは、黒王様」
「レ、イカ……ッ!?」
なんのことはない。黒王は彼の私室にいた。
若葉が訪ねて来ただけと思ったのだろう。若葉の入室を請う言葉に「んー」と気のない返事をした黒王は、現れた菊を見て、飲んでいた茶を吹きだしていた。
「いつも黒王様に来ていただくばかりでしたので、今日は私から訪ねてみました」
「どうやらお仕事中ではなさそうですし、ちょうど良かったですね、花御寮様」
「ええ、ありがとうございます、若葉さん」
「では、黒王様、花御寮様。どうぞごゆっくりぃ。あ、帰りは黒王様が東棟まで送って差し上げてくださいね」
「え、あ、おい! 若葉っ」
言いたいことだけ言うと、若葉は黒王に口を挟ませる暇もなく部屋を去って行った。
てっきり、いつものように笑みを向けてもらえると思ったのだが、黒王の顔は菊を向いていなかった。口元の茶を袖で拭きながら、どこか気まずそうに視線を下げている。
「すみません、突然。お仕事の休憩中だったでしょうか?」
「ああ、いやまあ……そうだな。この後は少し……郷の外を見回るつもりだ」
「黒王様自ら見回りなどされるのですね」
「ここ数ヶ月、他のあやかしが近くをうろついていてな。結界を張っているから中までは入って来ることはないし、もう片付いたようだが。一応念のためにな」
「それは大変ですね。そんな時にすみません。黒王様のお姿が最近見えなかったもので、気になって……」
「――ッ本当か!」
逸らされていた黒王の顔が、勢いよく菊へと向けられた。あまりの勢いの良さに、菊のほうが驚いて一歩下がってしまう。
部屋に入って初めて交わった視線。
その表情はパッと花が咲いたように晴れやかなもので、紫色の瞳の中では星がぱちぱちと瞬いていた。
「あ、いや……なんでもない」
しかしそれも、一度強く瞼を閉じ、再び開けた時にはもう消えていた。
視線も逸らされたままで、部屋にもどかしい気まずさが漂う。
菊はまだ部屋の入り口に立ったままであった。普段の彼ならば、部屋に菊が来た時点で手招きでもしそうなのだが、やはり今日は最初からどこか様子がおかしい。
「レイカ……聞きたいことがあるんだが……」
「はい、なんなりと」
いつも隣で会話していたから、今のふたりの距離もそうだが、菊が立って黒王が座っているという妙な距離に違和感がある。
「その……体調は悪くはないか。腹が痛いとか……」
「ええ、おかげさまで。お料理は美味しいですし、若葉さん達皆さん優しいですし、差し込む太陽は暖かですし、一面の桜も美しいですから。村にいた時よりも健康的ですよ」
「そ、それならば良いが」
またしても奇妙な空気が流れる。
――何かしら? 言いたいことを我慢してるような……。
彼は言葉を飲み込むように、何度も喉を上下させていた。
「もう、鴉の郷には慣れたか」
「はい、とても素敵なところです」
「では、そろそろ女官達に湯殿や着替えの手伝いをさせてはどうだ。仕事がないと困っているぞ」
どくん、と心臓が痛いくらいに跳ねた。まるで内側から胸を殴られたようだ。
「い、あの、それはまだ慣れないと言いますか……その……見られるのが恥ずかしいので……」
気付けば、先ほどまで視線を逸らしていた黒王がこちらを向いていた。
吸い込まれそうなほどに深い紫が、射抜くような強さでまっすぐに見つめてくる。
「……っ」
もしかして、入れ替わりがばれたのか。それとも、この身体を誰かに見られたのか。
菊の踵がトンとぶつかった。
「あっ!?」
振り返れば、いつの間にか背後にある障子まで後ずさっていたようだ。これでは、何かやましいことがあると言っているも同然だ。
「どうした、そんなに慌てて」
近くで彼の声が聞こえ、驚きと共に顔を正面へと戻した次の瞬間、菊は息をのんだ。
黒王が目の前に立っていた。
思わず体勢を崩してしまい、よろりと今度は踵だけでなく背中まで障子にぶつかってしまう。ガタガタと障子がうるさく揺れた。
「俺に言えないことでもあるのか?」
「そ、そのようなことは……」
カタン、と顔の両側から乾いた音がした。菊の逃げ道を塞ぐように、黒王が障子の格子に手を掛けていた。黒王が高い位置から菊を見下ろす姿は、黒い着物を着ていることもあり、まるで大きな烏が小さな菊に覆い被さっているようだ。
影が落ちた顔の中で、紫の双眸が不穏にギラついている。
「なあ、レイカ。嘘は吐かないと桜の木の下で約束してくれたよな」
「嘘など……ついていません」
そう言っている今も自分は嘘を重ねている。
――お願い。もうそれ以上踏み込んでこないで。
嘘を吐く口は震え、逸らさないと決めた視線は伏せられ、膝が今にも抜けそうだった。
いつかはばれると覚悟していたが、せめてぎりぎりまでは彼の花御寮でいたいのだ。
「見られるのが恥ずかしいから、な」
「あの、こ、黒王様……」
「本当は、身体を見せられない理由でもあるんじゃないのか?」
「――っ!!」
心臓が胸を突き破ったのかと思うほど、身体の中心が激しく脈打った。嫌な汗が背中をじっとりと濡らす。
彼は何をどこまで知っているのか。
「恥ずかしいならば慣れてしまえばいい。俺達はもうすぐで夫婦になる関係だ。俺にならば見られても構わないだろう?」
言い終わらぬうちに、黒王の手が胸元の合わせからするりと入り込んできた。
「え、あっ!? お、お待ちください、黒王様!」
「待たない」
菊が必死に制止の声を上げるも、黒王は強引に手を進め続ける。彼の手は胸元の輪郭をなぞりながら肩へとのぼり、到着すると撫でるようにして着物を脱がせはじめた。
「いやっ、黒王様!」
身をよじって黒王の手から逃れようとした菊だったが、障子に突っ張っていた彼の腕に引っかかり体勢を崩してしまう。
「きゃっ!?」
「レイカ!」
ぐらりと大きく傾いた菊の身体をすんでのところで黒王が抱きとめるが、既に半分以上倒れていたこともあり、二人してもつれるように畳へと転がった。
ドスンという大きな音の割りに菊の身体に痛みがなかったのは、黒王の腕が代わりに下敷きになってくれたからだろう。
脇から頭へ、背中から腰へと回された腕は、確かな力で守るように菊を抱きしめていた。
耳元で「痛っ」と言う黒王の声が聞こえた次の瞬間、彼はガバッと身を起こし、不安そうな顔でこちらを見下ろしていた。
「大丈夫か、レイカ!?」
彼の顔には焦燥が浮かんでいる。
「大丈夫です」と答えようとしたのだが、口を開けば言葉よりも先に嗚咽が漏れた。
彼は自分の嘘に気付いているのに、それでもこうして心配してくれる。
――私には、彼に心配してもらえる資格なんかないのに……っ。
すると、黒王の顔が苦しそうにしかめられた。
「頼む……泣かないでくれ」
言われて初めて、菊は自分が泣いているのだと気付いた。
目尻からぬるい雫がこめかみへと流れ落ち、畳に広がった髪を濡らしていく。一旦認識してしまうと、次々と涙があふれて止まらなくなってしまう。
「泣かせたいわけじゃないんだ。お前が大切だから全てを知りたいんだ」
見ている方が痛々しくなるほどの悲痛な顔で、絞り出すように言った黒王は、畳に広がった菊の波打つ長い髪を、壊れ物に触れるような手つきで丁寧に梳き続けた。
それはまるで『もう触れないから』と言っているようで、ますます菊の胸は締め付けられ嗚咽が止まらなくなる。
「……っ見な……で……」
ごめんなさい、嘘を吐いて。
ごめんなさい、何も言えなくて。
ごめんなさい、あなたにそんな顔をさせて。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
「こく……お、様……っ、お願……ッ……し……」
偽物なのに、あなたの傍にずっといたいと願ってしまって、ごめんなさい。
顔を両手で覆い見ないでと懇願する菊を、しばらく黒王は唇を噛んで見つめていたが、視線を切ると一緒に、自らの羽織をはだけて露わになっていた菊の胸元に掛けた。
え、と菊が思った瞬間、羽織で身体を包むようにして、抱き起こされる。
突然の予期せぬことに菊の涙も止まったが、それも一瞬。
「好きだ」
肩口に顔をうずめ、羽織の上からきつく抱きしめながら呟いた黒王の言葉に、止まっていた涙が再び流れだす。
〝好き〟という言葉が、これほどに感情を切なくするものだとは知らなかった。そして、同時に胸を高鳴らせるものだということも。
「黒王……様」
「どうした」
互いに顔を見ずに声だけを交わす。
「もう少しだけ……っ、こうしていて、くださいますか……」
途端に、グッと彼の抱きしめる力が増した。隙間がないほどにくっつき、互いの体温だけでなく鼓動すらも伝わってくる。
「もちろんだ、レイカ」
彼の腕の中にいるのは自分なのに、彼が呼ぶ名前は自分ではなかった。
しかし、だからこそ彼の腕の中にいられるのだ。
レイカを羨ましく思ったことなど一度もなかったのに、彼に名前を呼んでもらえる今だけは羨ましくて仕方なかった。
――ずっとは願いませんから、だからどうかあと少しだけ、彼を私にください。
今、菊はやっと初めてこの感情の名を知った。
これは間違いなく〝恋〟だった。
障子を通した柔らかな薄光に包まれ、部屋の色が白から茜になるまで、ふたりが離れることはなかった。
4
「昨日は驚きましたよ。花御寮様ったら、黒王様に抱えられて戻ってこられるんですもの。しかも、すやすやと心地よさそうな寝息を立てられて」
「そ、それは本当、なんと言って良いのやら……」
恥ずかしそうに菊が袖で顔を隠せば、若葉だけでなく女官達からもクスクスと笑いが漏れる。
今朝、目が覚めたら自分の布団で寝ていた。どうやらあの後、自分は彼の腕の中で眠ってしまっていたらしい。しかも、東棟に帰ってきたのが日も暮れた頃と聞かされ、どれだけ長時間、彼を枕にしてしまったのかと申し訳なさでいっぱいだった。
それに加え、昨日の一件が気掛かりでしょうがない。
彼は今日どのような顔をして来るのか。どのような顔をして会えば良いのか。もう一度聞かれた時、はたして自分は嘘をついていないと言えるのだろうか。
言いようのない不安に、じわじわと胸を蝕まれているようだった。
「そんな落ち込まないでくださいな。わたくし達は黒王様の腕の中で眠られている花御寮様を見て、嬉しかったんですから」
どうやら若葉は、菊の表情が暗くなったのを寝入ってしまったからと思ったようだ。
「若葉さん達が嬉しい、ですか?」
菊は首をコテンと横に倒す。
「ほら、人間はわたくし共を怖がるでしょう? でも、花御寮様は眠られるほど心を開いてくださっているのだなと思いまして」
頬を緩めて「くふふ」と変な笑いを漏らす若葉は、本当に嬉しそうだった。
「若葉さん達は、今までの花御寮に色々と辛い思いをさせられてきたのに、どうしてそう私に最初から優しいんですか?」
「弱い者が強い者を怖がるのは自然の摂理ですから」
にっこりと微笑まれ、姿形は一緒でも彼女達は常世に住む〝あやかし〟なのだと思い知らされ、少しだけ背中が冷たくなった。余裕が感じられる笑みは、絶対的な強者だという自負からきているのだろう。
「それに最初に言いましたように、来てくださっただけでありがたいんですから。邪険にすることなどあり得ませんよ。まあ、それ以上に、わたくし共が純粋に花御寮様を好きだからですけどね」
ねー、と若葉と女官達は、少女のように声と首の角度を合わせて楽しそうに笑っていた。
「ですから、明後日の婚儀が楽しみで楽しみで仕方ないんです!」
「若葉殿ったら、まあ張り切っちゃって」
「本当に。こんなに張り切る若葉殿は珍しいんですよ、花御寮様」
「明後日……」
外に目を向ければ、桜は満開に咲き誇っていた。
風に吹かれ、さやさやと揺れた花が、広庇に薄紅色の雨を降らせている。
そう、婚儀は明後日だ。
今はそのために、当日着る衣装の最終調整をしているところである。
村から嫁入りするときにも白無垢は着た。その時は、こんな上等なものは後にも先にもこれきりだろうなと思ったものだが、目の前の衣紋掛けに掛かっている白無垢や色打ち掛けはその比ではない。
ただの白かと思えば、同じ白糸で模様が入れられており、光の加減で裾には流水文様が、胸元には桜と扇文様が浮かび上がる。下に着る着物――掛下にも透かしが入り、帯は七宝文様。末広には金箔が巻かれ、頭を飾る簪の飾りにも見たことない美しい石がちりばめられている。
溜息が漏れるほどに美しいとは、このことだろう。
「でも、その前にまずは明日の潔斎ですけどね」
調整を終え、出した小物をてきぱきと片付けていく若葉達。
「禊ぎ、でしたっけ。それはどこでするんですか? 郷の外でしょうか」
「いえいえ、ご安心ください。郷の中ですから」
「安心?」
菊は首を傾げた。
「最近までどこかのあやかしが、郷の外をウロチョロしていたようでして」
「そういえば、黒王様もそんなことを言っていたような」
「雑魚あやかしのようですから、そこまで心配する必要はありませんが。玄泰様が黒王様の命で対処されたようですし、もう大丈夫ですよ。大丈夫です、婚儀にはなんの支障もありません」
はは、と菊はなんとも言えず、曖昧な笑みで話を躱す。
「それに、万が一があっても黒王様は強いですから。なんとかしてくれます!」
若葉が力強く拳を握っていた。
「あやかしにも、強い弱いがあるんですか?」
あやかしはあやかしとしか捉えていなかったが、その中にもやはり序列があるのだろうか。
人間社会にも序列はあった。たとえば貴族には帝都貴族と地方貴族があり、平民にも商人や農民、職人など、さまざまな身分が存在した。当然、平民より貴族のほうが上であり、貴族の中では地方よりも帝都貴族のほうが序列は上だ。
その中で、界背村は『祓魔師』と呼ばれるのだが、少々特殊で平民のくくりには入らなず序列から独立した地位にあった。しかし、村の中しか知らない菊がそれを体感することはなかったが。
「あやかしの序列は当然ありますよ」
腕組みした若葉が、深く頷きながら教えてくれた。
まず、水神や龍といった神と呼ばれる者達がいて、その次に、鬼や天狗、大蛇など人間にも伝承されるような者達、そして、烏や狐などの現世の自然界にも存在する者達がいて、最後に魑魅魍魎といった群れにならない小さな者達の順が基本なのだとか。
「だから我ら鴉は群れを作るのです。ひとりひとりの力は弱いですが、数は他のものとは圧倒的な差がありますからね。それと、実は黒王様はこの序列の限りではないんですよ。鬼か、下手したら龍にも並ぶほどの妖力をお持ちなんですから」
「え、でも黒王様も烏のあやかしですよね」
「ふふ、だから黒王様は我らの長であれるんですよ」
若葉は、目と口元に意味深な弧を描いていた。
◆
夜、菊は寝所を抜けだし、いつもの広間にひとり佇んでいた。
時刻はそろそろ日付が変わろうとする頃、辺りはひっそりと静まりかえっている。菊が歩くたびにギィと板張りの床が鳴き、もの悲しさをかもしだしていた。
ほぼ満月の月が、手燭もいらないくらいに全てを明るく照らし出す。
とうとう今日、彼は来なかった。
どんな顔をして会えば良いのか分からなかったから、少しだけホッとしたが、それよりも寂しさのほうが大きかった。
明後日はとうとう婚儀の日だ。
『婚儀』という言葉を聞く度に、胸が苦しくなって息ができなくなる。
「最初から分かっていたことじゃない」
しかし、最初はこのようになるとは思わなかったのだ。
黒王は恐ろしいあやかしで、人間を食べると思っていた。たとえ食べられなくとも、ひどい扱いを受けるのだろうと覚悟していた。
菊は見上げた月に向かって手を伸ばした。
「一度で良いから……菊って呼んでほしかったわ……」
彼の、低く穏やかな声で。
「……っ……ぅ」
菊は痛みに耐えるように身体をくの字に曲げ、自らの手で自身を抱きしめた。
なぜ涙が出るのか。
今までにも涙くらい、いくらでも流してきた。たくさん殴られた夜にも、空腹で寒くて凍えそうな朝にも、手を伸ばして誰にも見向きもされなかった日にも。
でも、これはそんな悲しいだけのものとは違う。
こうして涙が出る理由を、菊は昨日、彼に強く抱かれた腕の中で知った。
「好き……」
これは愛おしさだ。
彼に恋をして芽生えた、甘くて、もどかしくて、痛い感情。
「好きです……黒王様……っ」
狂おしいほどに、離れがたいほどに、彼を愛してしまった。
――だから、これ以上は駄目。
彼も好きだと言ってくれた。
しかし、その言葉には応えられない。たとえ自分も同じ気持ちだとしても。
菊は濡れた瞳を袖で拭い、まばゆいばかりに輝く月を見上げた。
「このままじゃいけないのよ、菊」
このまま、彼と婚儀を挙げるわけにはいかなかった。
「私が花御寮に相応しくないって分かった時に婚儀を終えてしまっていたら、村がもうひとり別の娘を寄越すとは考えられないもの」
ただでさえ、どこの家も花御寮を出し渋っているというのに。契約通りひとり出したのだからもう良いだろうと拒否するはずだ。
しかし婚儀前ならば、黒王達も新たな花御寮をと押し通せるだろう。
「私の役目もこれでおしまい」
言った後で、くっと口角が下に引っ張られる。
「元々私は偽物なのよ。良かったじゃない、偽物のくせにこんなに贅沢な時間を与えてもらって。あのまま村にいるより幸せだったのよ」
自分に言い聞かせるように、菊はこれで良いのだと言い続けた。
「きっと黒王様なら、新しい花御寮にも優しくしてくださるわ。とっても素敵な方ですもの、新しい花御寮もすぐに彼を好きになるわ」
彼と婚儀を挙げ口づけを交わし、名前を呼ばれながら肌を重ね、彼との子供をその両手に抱くのだろう。
「――っ!」
両手で顔を覆った指の隙間から、一度は止めたはずの雫がまたぽたぽたと滴っていく。
「そんなのいや……っ」
しかし、どうしようもない。
自分は忌み子だ。生まれた時から彼と結ばれる運命になかっただけだ。
しかし別れるのなら、せめて彼に好かれたまま別れたかった。
「こんな汚れた身体、彼には見られたくないもの」
何も知られず、彼の記憶には綺麗なまま残りたかった。
「全ては、明日の潔斎まで」
潔斎は身を清めるため、全てひとりで行わなければならないと聞いた。
ひとりになったら密かに郷を出よう。郷の外のあやかしも片付いたと言っていたし、きっと大丈夫。それに、花御寮自らが逃げたとなればあやかし側に責任はない。
菊は、広間の隅に置かれたいくつもの唐櫃に目を向けた。その中のひとつから硯箱を取り出し、筆をとったのだった。
◆
眩しいほどの月明かりが、部屋の畳に障子の格子模様を落とす。
黒王は酒杯を傾けながら、斜めに歪んだ格子を視界に映しているのだが、頭の中はまったく別のことを考えていた。
レイカは羽根のように軽かった。
彼女を手に抱いたのは、あれで二度目だ。
一度目は必死にしがみついてきて、それが猫のようで愛らしく、重さなど気にする余裕もなかった。
二度目は、自分の腕の中で眠っていた。少し赤く腫れた目元と、頬に残った涙の跡を愛おしく思ったものだ。東棟になど戻さず、このまま腕の中に閉じ込めて、彼女が目覚めるその瞬間まで寄り添っていたかった。
「腹の中に子がなあ……」
昨日の彼女の反応を考えると、おそらくほぼ間違いはない。
しかし幸いにも、灰墨以外レイカが身ごもっていることは誰にも知られていなかった。
彼女が身ごもっていると知ってから、しばらく東棟へは足が遠のいた。どう接したら良いのか分からず、頭もぐちゃぐちゃで、彼女を見たら思ってもないことを口走ってしまいそうだったから。
嘘を吐かないと誓ってくれたのにと憎む気持ちと、それでも彼女には傍にいてほしいと渇望する気持ちとが何度も衝突して、この先どうすればいいのか、ずっと答えが出せないままでいた。
しかし、突然『気になって』と言ってレイカが部屋にやって来た。
正直、嬉しかった。彼女が自分を気に掛けて会いたいと思ってくれたことに、震えるほどの喜びを感じた。
そんな優しい彼女が身ごもっているはずがないと、確信がほしくて様子を窺ってみたのだが、彼女の反応を目の当たりにして、頭から血の気が引いていった。
明らかに、彼女は動揺し何かを隠していた。
驚くほど頭が冷えていた。いや頭だけでなく、まるで氷塊を飲まされたように身体の真中心が痛いほどに冷たくなった。
気がついたら、自分は彼女を襲おうとしていた。このまま婚儀を待たず、自分のものにしてしまおうかとも考えていた。
しかし、彼女が倒れそうになったのを見た瞬間、そんな考えはどこかへ飛んでいった。レイカだけでなく腹の子も守らねばと思い、抱き留めていた。
「悩むだけ無駄だったな」
やはり自分は、彼女が身ごもっていても手放せないらしい。
『見ないで』と、泣きじゃくりながら哀願する彼女すら愛おしく思った。
『もう少しだけ』と抱擁を求める彼女を、誰が拒めるだろうか。
そのまま腕の中で眠ってしまった彼女の額に、密かに口づけた。本当は唇にしたかったが、婚儀まではと我慢したものだ。
今日が婚儀の前に彼女に会える最後の日だった。
本当は会いたくて堪らなかった。
しかし、運悪く玄泰やその他の里長、灰墨にまで捕まり、明日に控えた潔斎や明後日の婚儀について、段取りの確認や郷の者達への振る舞いなどを話し合っていたら、あっという間に日が傾いていた。
明日のこともあるし、きっと緊張しているだろうから、さすがに夜に訪ねるのは憚られた。次に会えるのは婚儀の時だ。
「ははっ、まったく……どれだけ彼女のことを考えているんだか」
思わず苦笑が漏れた。
会っていても離れていても、常に脳裏には彼女の姿があった。
「自分でもどうしようもないくらい、彼女に惚れているんだろうな」
たとえ嘘を吐いていようとも、その嘘ごと愛せるくらいに。
おそらくレイカの身ごもりがばれたら、里長達は新しい花御寮をと騒ぐだろう。
「奪われて堪るか」
自分から彼女を引き離そうとする者は、誰であっても許さない。
彼女以外、花御寮はありえない。
黒王は酒杯を床に置くと、障子を開けに立った。
滑りの良い障子はすーっと静かに開き、夜の虫の音を邪魔することはない。廊下に出て見上げれば、ほとんどまん丸の月が夜闇に浮かんでいた。
次に会えるのは婚儀の日。
「俺がほしいのは、花御寮じゃなくて彼女なんだ」
――花御寮にするのなら、この娘がいいと思ったんだ。
人間を妻とすることは生まれながらに決まっていた。しかも、相手の人間は自分では選べない。界背村が送った人間をそのまま妻とするのが決まりだった。
そんな淡泊な流れで、夫婦らしい何かが芽生えるというのか。
少なくとも自分は、芽生えたという過去の例を、ひとつも知らない。
それが黒王の役目だと言われれば、そうなのだろう。目的は嫁取りというより、次代の黒王を残すことなのだから。
何が花御寮だ。
何が夫婦だ。
全て嘘ではないか。
だから、黒王になると分かった時、密かに界背村を見に行った。多分、ささやかな抵抗だったのだと思う。自分で選ぶことができないのなら、せいぜい全員を見て『どれが来ても変わらんな』と自分を納得させたかったのだと思う。
郷の皆が寝静まった後、一羽の烏姿に転化しひっそりと鳥居を抜け村を飛んで見回った。
現世を訪ねたのは、それが初めてではない。
昔はよく灰墨と一緒に郷を抜け出し、現世をふらりと跳び回っていた。それで、鳥居をくぐって帰ったところでいつもそれぞれの父親に捕まって、げんこつと雷をもらったものだ。
あの時は現世に行くのが楽しかったのに、この時は憂鬱で仕方なかった。
この村のどこかに、自分の妻になる者がいる。
とはいっても夜中だし、見ることができても寝顔だけで、性格も何も分かったものじゃないが。
そんなことを考えながら飛んでいたせいか、それとも転化が久しぶりだったからか。雑木林に入ったところで羽を引っ掛け、墜落してしまった。
しこたま地面に身体を打ち付け、『しくじった』と己の馬鹿さ加減を後悔していれば、カサッ、と何者かが近付いてくる音がしたのだ。慌てて飛び立とうとするも、やはり片羽はまだ動かせず、地面をのたうちまわるだけ。
そうこうしているうちに、声が聞こえた。
若い女の声だった。
ただですらうっそうとして暗い雑木林に、しかもこんな深夜になぜ……。
しかし、人間にここで遭うわけにはいかない。
人間が烏を良く思っていないのは前々から知っていた。妖の姿なら人間など赤子も一緒の存在だが、この姿でしかも怪我までしている今は不利だ。
しかし間に合わず、木の向こうからひょこっと娘の顔が覗いた。
どんな仕打ちを受けるのかと半ば覚悟した時、彼女は驚きの行動に出た。なんと、ためらいもなく己の着物を引き裂き、怪我をしている羽に巻き付けたのだ。すっかり拍子抜けして警戒も解けてしまった。
しかも、呆気にとられていれば、顔をまじまじと覗き込んできて――。
『あなた、珍しい色の羽根と目をしているのね』
『とっても綺麗な色だわ』
と言ってのけたのだ。
しまいには、怪我で飛べないからと、木の実まで口先に並べていった。
なんだこの娘は――と、帰っていく娘の背から、しばらく目が離せなかった。
翌日、郷に戻っても彼女の突飛な行動が信じられなくて、再びこっそりと村を訪ねた。
その日も深夜にやってきた彼女は、寒さに耐えるかのように、膝を抱いて丸く小さくなっていた。
気付けば、彼女の前に降り立っていた。本来なら、自分から人間に近付くなどあり得ない。
顔を上げた彼女は、懐から木の実や干し柿を差し出した。正直、昨夜もだが、腹など減っていない。それにただの烏と違い、木の実など好んで食べたりするものか。
しかし、向けられた弱々しい笑みが、自分のために懸命に笑ってくれているかのようで、気付いたら赤い実をひとつ口にしていた。
『ありがとう、優しいのね』
心臓が止まったと思った。
こんな人間がいるのかと。
その後、『ひとりぼっち』だと言って小さな嗚咽を上げ続ける彼女を、今すぐに抱きしめたいと思ったものだ。
――俺はあの夜からずっと、彼女に心を奪われたままだ。
◆
あふ、と黒王は口元を隠した手の下で、噛み殺せないほど大きなあくびをした。
昨夜は、レイカは何が好きか、何を贈ったら喜ぶかなど、彼女のことを考えていたらすっかり寝付くのが遅くなってしまった。
――何が『古柴レイカはワガママで高飛車』なんだか。灰墨の言葉も当てにならんな。
猫を被っているかもと指摘もされ、初めはそうかもと思っていたが、どう見ても何も被っていない。自分が出会ったあの夜の彼女そのものだった。
しかし、そうなると今度は灰墨の言葉が気になる。
――あいつは、どこでそんな噂を拾ってきたんだ?
大方、同じ名前の別人の噂を間違えて聞いた、といったところか。昔から灰墨にはおっちょこちょいなところがあるし、そう考えるのが自然だ。
そんなことをぼんやりと考えていると、隣から横腹を突かれた。
「――と各里からの報告は以上なのですが……大丈夫ですか、黒王様?」
「ん、ああ。それじゃあ少し休憩を挟もうか」
今、部屋では重役達と共に、各里の定例報告と婚儀の進行についての話し合いが行われていた。半分は上の空だったが、定例報告については事前の報告が上がってきた段階で、全て目を通して把握しているため問題ない。
正直、今すぐにでもレイカに会いに行きたかった。
重役達の厳めしい顔を見るよりも、レイカと桜を眺めながら茶をすすりたい。彼女が隣にいてくれるだけで、陽だまりの中に立つように胸の内側が温かくなるのだ。
しかし、そうも言っていられない。
まだ自分は黒王になって日が浅いのだ。
ここに集った重役達は各里を束ねてくれている者達であり、彼らの力を借りなければならないことも多い。
『黒王』が血統によって継がれることに異議をとなえる者はいない。
黒王が黒王である理由は、鴉一族の中で圧倒的な力を持つからである。
妖と呼ばれる者達は、多かれ少なかれ皆『妖力』を持つ。
それによって様々な術を使えるのだが、黒王は術の規模、精度、強度、どれをとっても他の鴉とは一線画す力を持っていた。
それを可能にしているのが、界背村の娘――花御寮の血である。
界背村の者達の身には、祓魔の力が宿っている。
元をたどれば妖力だが、長い時を経て今や完全に別物となっている。より彼らの世界に馴染むようにと独自の進化をとげ、また、村内婚姻を重ねて力が凝縮されているのだ。
それは大木のごとしで、根は同じだが成長し枝先がのびるにつれ、どんどんと力の性質が離れていった。
そして、性質の異なる力を掛け合わせてきたことで、黒王の血統は抜きん出た力を持つようになった。もし、他の鴉が真似をして界背村の娘に子を産ませても、何代にも渡って力を重ねてきた黒王の力には到底及ばない。
だから皆、黒王が自分より若輩者であろうと『黒王』として敬うのだ。力によって立場が決められる妖の世界では、強さとは崇敬するものであった。
ただ、時には崇敬とは別の感情を抱く者も中にはいる。
「各里変わりないようで何よりだ。そうだ、南嶺。奥方の調子はどうだ? 寝込んでいると聞いていたが」
「おおっ、お気遣いありがとうございます、黒王様! しかし心配はいりませんよ。ただの食あたりですから」
「ははっ、ならば一安心だ」
「いえ、もう本当、うちの妻は食い気がすごくて。しかも寒いと尚更とか言って……今度黒王様からも食べ過ぎるなと言ってやってくださいよ」
「では今度、南嶺の里へと邪魔するかな」
「黒王様が来てくださるのなら、里の者達も喜びます」
こうした何気ない会話で相手の様子を窺うのも重要なのだ。
休憩ということで、皆それぞれの里の様子や、自分の子や孫のことなどの会話に花を咲かせていた。
そこで、「では」と老爺のかすれた声が場をまとめる。
「次は、黒王様の婚儀についてですが。ここからは儀式を取り仕切る私が、話し合いの進行もいたしましょう」
灰墨が老爺――玄泰の目配せに浅く頷く。
さすがに先々代、先代と続けて婚儀を仕切ってきた玄泰は、婚儀までに行われる儀礼についてしっかりと把握している。それに対する段取りにも抜けがない。
「――そして、婚儀の前日ですが、黒王様と花御寮様はそれぞれに潔斎に入っていただきます。黒王様は北の霊泉で、花御寮様は南の霊泉でそれぞれ沐浴していただき、その日から婚儀まで、二人の接触は一切禁じられます」
「一切か……」
たった数時間の会議の間でも会いたくて仕方ないのに、一日も我慢できるか我ながら心配になってきた。
「その後は、祝詞奏上と三献の儀、誓詞奉読と……まあ一般的な婚儀の流れと同じです」
「であれば気をつけるのはやはり前日だな。うっかり東棟に足を運んでしまいそうだ」
悩ましげに前髪を掻き上げながら呟く黒王に、南嶺が愉快そうに目を細める。
「そういえば、黒王様は足繁く東棟に通われているとのこと。お二人の仲がよろしいのであれば、これ以上幸いなことはありませんな」
周囲も南嶺の言葉を聞いて、「それはそれは」と表情をほころばせていた。
しかし、灰墨ともうひとり――玄泰だけは口を引き結んでいる。
「はてさて、それがいつまで続くやら……」
温まっていた場の空気が、一瞬にして凍りついた。
「その花御寮様の仮面が、どこまでもつのかが問題ですな」
「俺の花御寮は仮面など被っているようには見えんがな? とても美しく可憐な容貌だぞ」
玄泰の皮肉に皮肉で返せば、彼ははっと鼻で一笑し、腰をゆっくりと上げる。
「私は、そろそろこの花御寮という習わしを、やめてもいいと思っておりますがね」
「俺のことよりも、郷の外の妖はどうした? 自分から名乗りを上げたんだ。しっかりと対処できているのだろうな」
「もちろんですよ。里の若手もいましたし、私も黒王様のような力は持たずとも、これでも長年里長を任されてきた身でしてね」
少し曲がった腰で手を結び、玄泰は足で畳を擦るようにして部屋を出て行く。しかし、廊下に出たところで「そうそう」と歩みを止めて、黒王へと首を返した。
「女官達が、花御寮様は未だに湯殿や着替えの手伝いをさせてくれぬから、暇になってしまうと嘆いておられましたぞ。やはり花御寮様は妖に触れられるのを、心の中では嫌悪されているのかもしれませんなあ」
黒王の目がじわりと見開く。
玄泰は黒王の表情を目の端に捉えると、猿のように皺だらけになった口元を笑ませて、去って行った。
「気になさいますな、黒王様。玄泰殿は二代にわたって花御寮様と接してこられ、色々とその……苦労されてきたようですから」
他の重役からの慰めの言葉に、黒王はチッと口の中で舌打ちした。
――王が憐れまれてどうする。
「……分かっているさ」
本当、食えない爺だ。
◆
「レイカ、いるか!」
いつものように菊が広間で若葉や女官と談笑していると、入り口が開くなり荒っぽい声を飛んできた。
「あら、黒王様。こんにちは」
しかし、誰が入ってきたか分かっている菊達は特に驚くこともなく、黒王ににこやかな挨拶を向ける。
彼は広間に入るなり荒々しい足取りで一直線に向かってきて、菊の左隣でぴたっと肩をくっつけるようにして座った。いつも、いつ来たか分からないくらい静かに入ってくるのに、今日はまたどうしたことか。
「まあまあ、黒王様ったら。それでは花御寮様が動けないじゃありませんか」
若葉は黒王に場を譲るように菊の傍から一歩分さがり、女官達は微笑ましい者を見るような顔をして、ほほと袂を口に当てながら部屋を出て行く。
「黒王様、何かありました? ご様子がいつもと違うように思うのですが」
「んー……別に。レイカの顔を見たら良くなった」
低く抑揚のない声で言われても、説得力がないのだが。
しかも肩はくっついているのに、黒王はそっぽを向いているから、菊からは様子が見えない。顔を覗き込もうと、菊がそうっと身体を傾けて前から回り込もうとするも、気付いた黒王に「見るな」とばかりに、床についていた左手を握られてしまった。
「ふふ、今日の黒王様は、ご機嫌なななめなんですね」
「…………」
また手をぎゅっと握りしめられる。
どうやら、もうしばらくはこのままのほうが良さそうだ。
「若葉さん、すみませんが文机を」
「かしこまりました」
若葉は分かったように立ち上がると、文机と一緒に墨や筆が入った硯箱も持ってきて、菊の前に整えた。
左手は黒王に握られたままで動かすのははばかられ、筆を持った右手だけで文字の練習をしていく。暇さえあれば本の書き取りをしてきたためか、今では平仮名であれば全て、漢字も簡単なものであればいくつかは書けるようになっていた。
若葉が紙を押さえ、菊が書いていく。
紙をめくる音と筆が滑る音だけが部屋に響く、穏やかな時間が過ぎていく。
「……何を書いてるんだ」
少し落ち着いたのか、黒王の顔がようやく菊の方を向いた。
「色々ですよ。今は、若葉さんや女官の皆さんの名前を書いてます」
平仮名ですけどね、と筆先を上げて、書いた文字を黒王から見えやすくする。
紙には、上手いとは言いがたいひょろりとした文字で「わかば」や「こうづき」「ももせ」などと書いてあり、黒王が首を伸ばしてまじまじと覗き込んでくる。
てっきり「まだまだ下手だな」などと笑ってくれるかと思っていたのだが、なぜか黒王の口はみるみるへの字になっていく。
「え、え!? あ、あの、黒王様!? 私何か失礼を……!?」
戸惑いにおどおどする菊だったが、その隣でなぜか若葉が吹きだした。
「え、若葉さん?」
「…………若葉」
黒王が、ぼそりと非難めいた声で若葉をたしなめる。
「……っし、失礼……っふふ」
顔を袖で隠していても、全身が小刻みに揺れているせいで、笑っているのがばればれである。というより、黒王はなぜ難しい顔になり、若葉は笑いをこらえているのか。
「若葉っ」
しかし、黒王には若葉が笑っている理由が分かるらしく、また若葉を、今度は先ほどよりも強い声でたしなめていた。
――なんで分かるのかしら。
菊には二人の表情の意味が分からないのに。
二人の間で顔を往復させていた菊は、無意識に己の胸元にカリッと爪を立てていた。
「ふっ……はいはい。それでは怒られてしまいましたし、わたくしはこれで失礼いたしましょうかね。黒王様、言いたいことは口になさならないと伝わりませんよ」
「――っ若葉!」
とうとう声を上げた黒王などなんのその。若葉は「ほほほー」と満足げな笑声を響かせながら、パタンと扉の向こうへと消えていった。
はぁ、と大きな溜息と共に前髪を乱暴に掻く黒王は、菊が初めて見るもので、珍しい粗野な姿に思わず見とれてしまう。
「ったく、あいつは昔っから……」
しかし、彼が呟いた言葉で、瞬く間に菊の高揚は醒め、それと共に顔まで俯く。
「どうしたんだ、レイカ?」
二人は言葉を交わさずともわかり合っていた。
しかし、自分は口にされないと分からないらしい。
それがなんだか、少し悔しくて、もやっとするのだ。
――なんなのかしら、これ……。
「……昔から黒王様と若葉さんは、そのように仲がよろしかったのですか?」
隣で黒王が笑う気配がした。
顔を上げれば、黒王がくつくつと喉を鳴らして笑っている。楽しそうに頬を緩め、こちらを見ているではないか。
しかし、なぜ彼が笑っているのか、菊にはまた分からない。
「安心しろ、若葉とは幼馴染みなだけだ」
「あ……そう……なんです、ね」
すーっと胸にわだかまっていた何かが晴れる心地がした。
ニヤニヤと揶揄い顔を黒王が近づけてくる。
「妬いたのか?」
「妬く?」
「俺と若葉の関係に嫉妬したのかと聞いているんだ」
「……分かりませんが……それは、この胸のあたりが、もやっとしたことを言うのでしょうか?」
こてん、と菊が首を傾げてみせれば、黒王は口をぽかんと開けたまま一歩後ずさった。
「どうされたのです、黒王様?」
顔が真っ赤だ。
「――っ無自覚か!?」
何がだろうか。
「婚儀までまだ数日あるのに、勘弁してくれ……っ」
「それよりも、黒王様こそ、先ほどのへの字口はなんだったのですか?」
「それよりもとは……」
きょとんとして本気で分からないといった顔をする菊に、黒王は明後日の見つめながら、後頭部をがしがしと乱していた。
「あれは、その……若葉や女官達の名前ばかり書いていたから……」
「しかし、黒王様のお名前を私はまだ聞かされておりませんから」
そこで菊は、はた、と気付く。
「もしや、お名前が『黒王』というわけではありませんよね?」
「……筆を貸せ」
言うが早いか、黒王は菊の手から筆を抜き取ると、さらさらと筆を走らせ文字を書いた。
「俺の名だ」
菊にも分かる達筆さなのだが、漢字で書かれているため読めず、読み方を聞こうとしたら、それよりも早く黒王の口が菊の耳元で囁いた。
「――――」
聞いた名を呟こうとして、人差し指を口に乗せられてしまう。
「決して他人に知られてはならない名だ。だから、レイカにだけ教えた。二人きりの……特別な時にだけ呼んでくれ」
菊は紙に書かれた二つの漢字をじっと眺め、音を伴わず呟いた。
すると、水が湧き出るように胸の中で何かがこみ上げてきて、何度も何度も口に馴染ませるように、刻み込むかのように、菊はひとり呟き続ける。
「それにしても、レイカは十九だろう。今まで嫉妬したりなかったのか? 村で想いを寄せた者や、寄せられた者くらいいただろう? ああ、いや……俺としてはとても嬉しいことなんだが……」
菊は苦笑した。
「村にどのような者がいるのかすら私は知りませんでしたから……誰かに特別な感情を覚えるというのもなかったんですよ」
「そう……か」
「はい」と微笑んだ菊と、黒王はその日も若葉に「そろそろ夕食の時間ですので」と言われるまで、並んで春風を共に感じていた。
「…………」
母屋へと戻る廊下の半ばで、ふと黒王は足を止めた。
「……灰墨」
ぼそりと呟けば、一羽の烏が飛来し横の欄干に着地する。
名前を呼べば、彼はすぐにやって来る。たとえそれが独り言の大きさでもだ。それが近侍である。
「何か」
「調べてほしいことがある」
「どのような」
「界背村へ行け。そして〝古柴レイカ〟についてもう一度調べてきてくれ」
「花御寮様について? 今更ですか?」
「同じことでもなんでもいい。とにかく彼女に関すること全てを持ってこい」
「かしこまりました」
2
――なんだか、村にいたのがもう随分昔のことのようだわ。
実際はまだひと月も経っていないというのに。
今日は、昼から仕事があるからと、彼は朝早くからやって来た。
忙しいのなら無理して訪ねてこなくても大丈夫だと伝えたのだが、彼は「俺が会いたいだけだから」と言って頬を撫でてくれた。彼の名前を書けるようになったと報告すれば、頭を撫でてくれた。
――なんなのかしら……この気持ち……。
彼に撫でられた頬の感触を思い出しただけで、顔が熱くなる。
最初は、伸ばされた彼の手を怖いと思った。
でも、今では彼に触れてほしいと、自ら頬を差し出しそうになる。
もっと、もっとたくさん、色々なところを彼に触れてほしい。
「――っああ、私ったらなんてことを……っ!? はしたないわ……」
耳の奥まで沸騰したように熱くなった顔を、自らの両手で包んで冷やす。
「良かった……若葉さん達がいない時で……」
こんな顔を見られたら、病気かと騒ぎになるところだった。
若葉達は今、それぞれの持ち受けた仕事で、広間の外に出ている。特に今は、婚儀を目前にして衣装の準備や、用具の確認などで忙しいようだ。しかし、声を掛ければ、誰かしらがすぐにやって来てくれるため、困ることはない。
「本当……どうしたのかしら、私……」
菊は風でも浴びようと広庇へと出て、庭に面した欄干に身体をもたれさせた。
眼下では、桜の薄紅だけでなく、すみれの紫やたんぽぽの黄色、名を知らない小花の水色や桃色が咲き誇っている。
「あ、あの桜の木は……」
たくさんの桜の木が植わっているのだが、桜の花々で隠された庭の奥にある一本は、かつて黒王と共に腰を下ろして眺めた桜ではないだろうか。
あの日に誓った――凍えていた彼を温めようと。彼が、ずっと笑っていられるように。
――私はずっと彼の傍にはいれないから……。
「少しでも彼の心が癒えてると良いんだけど」
傷は簡単に癒えない。
しかし、花御寮としてここで過ごすようになって、確かに菊の中の傷は癒えていっていた。そして癒えた場所に、別の何かが芽吹き始めているような気がする。
それがなんなのかは分からない。
ここでもまた、生まれて初めてを経験していた。
「何かしらね」
桜の麓を眺め続けていると、ふと背中を支えてくれていた、彼の大きな手の逞しさを思い出してしまった。
たちまち耳まで熱くなる。
「……もうっ」
手でパタパタを顔を扇ぐ。花の香りを含んだ風が、ちょうど良い冷たさで心地よい。
花御寮になってからというもの、菊が得る感情は未知のものばかりで、毎日が大忙しった。
胸が躍るようなことから、締め付けられるようなこと。凪ぐような時もあれば、毛が逆立つような時もあった。
「そういえば、昨日のあれはなんだったのかしら」
胸の内側が、なんというか不愉快だった。しかし、今こうして指でカリカリと掻いてみても何も感じない。昨日は掻いても消えないもやもやをもどかしく思っていたのに。
「嫉妬……なのかしら? でも、どうして……」
菊は振り返り、正面にある広間の入り口を眺めた。
扉はぴったりと閉まっており、うんともすんとも開く気配がない。
「……仕事って言っていたもの。来ないわよね」
そこで菊は、今あの扉が開いて彼が顔を出してくれないかと、自分が願っていることに気付いた。
「そういえば、いつからかしら」
彼が来るのが待ち遠しく感じたり、帰っていく背中を寂しく思い始めたのは。
最初は、彼が来れば恐ろしく、帰ればほっとしていたというのに。
「…………」
菊は、入り口を眺めながら、欄干に引っ掛けた腕に頭を乗せた。
自分の頬が、ほのかに温かくなっていくのを感じる。胸の内側がむずむずとする。でも、爪を立てたくなるような不快感はない。
「なんなのかしら……」
答えは出ない。
しかし、この感情は決して悪いものではないのだろう。
◆
東棟を訪ねれば、彼女は青草の爽やかさが香るような笑みで迎えてくれる。
今日は朝から訪ねたのだが、若葉達が部屋を出て二人きりになった途端、耳元に顔を寄せてきて。
『お名前、書けるようになりました』
と、囁かれた。
それが嬉しくて嬉しくて、ニヤける口元を隠すのに大変だった。
口を押さえて言葉を発せなかったため、代わりに頭を撫でてやれば、彼女は照れたように「ふふ」と笑った。
その穏やかさがまた可愛くて、たまらなくて。
彼女が自分のことをどう思っているのかは分からない。
ただ、どのように思われていようと、暖かな陽だまりのような彼女の隣にいれるだけで、心地よくて、幸せだった。
傍にいてくれるだけで……良かったのだ。
しかし、名残惜しさを感じながらも、午後からの仕事があるため早々に母屋へと戻ってきたのだが、それどころではなくなってしまった。
「――デタラメを言うなっ!!」
三日ぶりに帰ってきた灰墨の報告を聞いて、黒王は母屋中に響き渡るほどの怒号を落とした。
「しばしお待ちを」
しかし、灰墨は少しも臆することなく座を立つと、閉まっていた障子を開け、外の様子をきょろきょろと窺い戻ってくる。
「黒王様、もう少し声を落としてください。人払いをお願いしましたが、あまりにもですと女官達が駆けつけてくるかもしれません」
「……なるほど。このための人払いだったか……」
怒号と一緒に落とした拳により、脇息が半ばから綺麗に折れていた。
「花御寮が嫌いだからと、適当なことを言っているんじゃないだろうな、灰墨」
「そんなことしないのは、黒王様が一番分かってますよね」
「…………悪い」
灰墨が折れた脇息を手際よく片付けていく。
黒王は置き所のなくなった手で顔を覆った。
「レイカが……っ身ごもっているだと……」
灰墨は当初、既に嫁入った者のことなど誰が噂するというのだろうと、きっと大した情報は得られないなと期待していなかった。
しかし、界背村に入り自分の認識を改めた。
村の者達は、あちらこちらでヒソヒソと『古柴家の娘』や『レイカ』という言葉を口にしていたのだ。
何をそんなに彼女のことで話すことがあるのか、と聞き耳を立てれば、村人達はどうやらひとつの話題ばかりをはなしている様子だった。
『さすがレイカだわぁ。私だったら万が一を考えてそんなことできないわよ』
『古柴家だからって、結構彼女だけ色々と許されてたもんね』
『でも、だからってまさか、妊娠してたなんて』
灰墨は耳を疑った。
冗談だろう、と。
もしかして、村にはレイカという名前の女が他にいて、そちらの者のことだろうと。しかし、それから隅々まで村を跳び回って村人達の声を集めたが、〝古柴レイカ〟どころか〝レイカ〟という名前の女はひとりしかいないという裏付けにしかならなかった。
そして、彼女が身ごもっていたということも。
「村はその噂で持ちきりでした」
「……村人達はどうやってレイカの身ごもりを知ったんだ」
「花御寮様には元々恋人がいたそうです。本来村の掟では、花御寮候補者はその期間が過ぎるまで、異性と深い仲になることを禁じられているそうです。が、彼女の場合は相手の男含め、村の有力家だったようで、清い関係であればと大目に見られていたようです」
「清い関係な……」
どうやら村の大人達の譲歩は、見事に裏目に出たようだ。
「深い仲の恋人がいたのは分かった。だが、どうして今さら噂になっているんだ」
「どうやらその男、長らく仕事で村の外に出ていたようで。古柴レイカが花御寮に選ばれたことも、嫁入りしたことも知らなかったらしく。仕事を終え村に戻ってきた時、他の村人から聞いて『レイカの腹には俺の子がいるんだぞ!』と随分と騒いだようです」
「なるほどな。それでその男と……古柴家はどうしている」
「まず古柴家の方ですが、嫁入り以降火が消えたように静からしいです。使用人も、娘が花御寮となってから入れていないようですし」
「娘がいなくなったショックか」
「男の方はしばらく騒いでいたようですが、今は落ち着いているみたいですね。ただ、それでも内容が内容なので噂は未だ……という感じです」
正しく状況を把握するために、なんとか冷静に話を聞くことはできたが、こうして座っていても頭がクラクラする。胸の内側は焼けるように熱いのに、頭の中は凍ってしまったかのように、恐ろしいほど冷えていた。
――レイカの腹の中には、既に別の男との子が宿っている……?
この紫色を、綺麗だと微笑んでくれた彼女の中に?
嘘を吐かないと、小指を差し出してくれた彼女の中に?
自分の真名を記憶するために、何度もあの愛らしい唇で口ずさんでいた彼女の中に?
「…………っ!」
前髪を握りこんだ手の中で、ブチブチと髪が切れる感覚があった。しかし、痛みは感じない。
黒王の憤る姿に、灰墨の目も悲しそうに眇められていた。
「そりゃ人間は嫌いですし、花御寮制度なんかなくなれって思ってますけど……でも、黒王様が笑われる姿が増えて、良かったとは思ってたんです。だから……その笑顔がなくなるようなこと、本当は持ち帰りたくなくて……」
以前、古柴レイカを調べると言って村へ行った時は、灰墨は一日で帰ってきた。今回三日もかかったのは、噂が間違いであることを突き止めようと、頑張ってくれたからだろう。
「分かっている……余計な苦労をかけたな、灰墨」
ありがとう、と労ってやりたいのに上手く言葉が出なかった。
正直に言うと、聞きたくなかった。
しかし、彼女に関する情報を全て持ってこいと言ったのは自分だ。灰墨は何も悪くない。悪いのは、彼女の一言に違和感を覚えてしまった自分なのだから。
彼女に関しては、以前からちょこちょこ、と首を傾げたくなるようなことはあった。
たとえば、聞いていた性格と違うとか、文字の読み書きができないとか。しかし、性格に関しては、相手によって評価も変わるだろうし、読み書きは、得手不得手があるだろうと、さして疑問は抱かなかった。
しかし、『村にどのような者がいるのかすら私は知りませんでしたから』という言い方には引っかかりを覚えた。
村人に噂される程度の関わりはあるのに、『知らない』などということがあり得るのだろうかと。
その些細な引っかかりを解消しようとした結果――。
「……ますますレイカが分からなくなった」
――俺があの夜に出会った彼女と今の彼女、そして噂の彼女……どれがいったい本物なんだ。
すると、もじもじと灰墨が視線を送っているのに気付く。
「どうした、灰墨」
灰墨が、ためらいがちに口を開いた。
「黒王様……花御寮様って確か、女官達に湯殿や着替えの手伝いをさせないって話でしたよね」
ハッとした。
「それって、膨らんだ腹を見られないようにするためじゃ……」
「……下がれ……灰墨。このことは他言無用だ……」
「黒王様! 花御寮様を村へ送り返してやりましょうよ!? 別の花御寮でも良いじゃないですか! だって下手したら、見知らぬ人間の男との子を育てるはめになってた――!」
「下がれ、灰墨っ!!」
もう何も聞きたくない。
黒王は意思表示をするように、瞼を閉じ顔を俯けた。
「黒王様……っ」
憐れみと悔しさを滲ませた声で灰墨が呼ぶが、これ以上は何も考えたくないのだ。
「下がれ…………」
喉から絞り出した声は、自分でも聞いたことないような悲壮感が漂っていた。
灰墨が立ち上がる衣擦れの音がした後、すーっと障子が開いて、また閉められる音がした。
トン、トン、と足音が部屋から遠ざかっていく。
部屋に落ちる静けさが耳に痛かった。
いや、耳よりももっと別のところが、掻きむしりたくなるほどに痛かった。
「それでも俺は……っ」
瞼の裏では、彼女が『黒王様』と呼んで笑っていた。
いつも扉を開けると、春陽が降りそそぐ明るい広間で、彼女はちょこんと座っている。そしてこちらに気付くと彼女は、ふっ、と顔をほころばせるのだ。
桜色に頬を染めながら。
「っああ……こんな時に好きなものを知るとはな……」
彼女の桜色に染まる頬が好きだ。
彼女の小鳥がさえずるような愛らしい声が好きだ。
彼女の「黒王様」と言う小さな口が好きだ。
彼女の穏やかに下がった眉と、猫のように少し跳ねた目元が好きだ。
彼女の真っ直ぐに見つめてくる、烏の色と同じ真っ黒な瞳が好きだ。
すっぽりと握れてしまう小さな手も、懸命に後をついてくる狭い歩幅も、景色を見るたびにうっとりとした息を漏らすところも……。
「――――っ!」
何もかも。
全部。
彼女が狂おしいほどに好きなんだ。
「もう……俺には彼女を手放すことなど……っ」
たとえ、別の男の子を身ごもっていようと――。
3
桜も八分咲きとなり、風が吹けば淡い花びらを広間に散らすようになった。
広間と続きになった広庇から見える景色は、夕日を浴び薄紅色の花びらが茜色に染まり、圧巻の一言だ。
しかし、そんな美しい景色の中、菊は先ほどからずっとチラチラと部屋の入り口を気にして、若葉の話も上の空という感じだった。
「花御寮様、気になりますか?」
「えっ、何がですか」
「何がですか、じゃないですよ。昼過ぎからずっと入り口ばかり気にして。分かりやすすぎです」
若葉が目も口も弧にして、隣へとにじり寄ってくる。「もうっ」と肩をグイグイと押され、なぜだか気恥ずかしくなった。
「私、そんなに分かりやすかったですか?」
そりゃあもう、と若葉は大げさに頷く。
「黒王様をお待ちなんでしょう?」
「……はい」
返事した菊の声は、消え入りそうなほど小さかった。
「確かに、今日はどうしたことでしょうか。もう夕刻だというのに、黒王様がまだお見えにならないとは……」
「お仕事でしょうか」
「そうかも知れませんね。婚儀も近いですから」
「婚儀……」
その日を迎えれば、全てが明らかになる。
――そうしたら、私はどうなるのかしら。
少なくとも、もうここにはいられない。
この美しい景色とも、暖かな陽射しとも、優しい女官とも、姉のような若葉とも、お別れだ。そして……。
――彼とも……。
傾く夕日のせいだろうか、心がきゅうと締め付けられ、なぜだか虚しくなった。
「大丈夫ですよ。皆、花御寮様が黒王様の正妻になられるのを心待ちにしているのですから。慣れないことも多いでしょうが、その都度わたくし達がお助けしますから」
押し黙ってしまった菊の肩を、若葉がゆるりと撫でた。婚儀を間近に控えて不安に思っていると、勘違いされたようだ。
菊は、曖昧に笑った。
「そういえば、若葉さんは黒王様と幼馴染みだとか。よければ黒王様について聞かせてくれませんか」
「うふ、花御寮様も黒王様のことが好きなのですねぇ。おふたりに仕えるわたくしにとっては、喜ばしいことです」
「え、好き……?」
これ以上婚儀のことは考えたくなくて、別の話題を探してふっと出てきたのが彼だったというだけで、『好きだから』などとは考えなかったのだが。
――しかも、『花御寮様も』ってことは……。
まさか、黒王は自分のことを好きなのか。
確かに彼は優しいし、よく微笑みかけてくれる。
でも、それはそういう優しい性格の人だと、自分の花御寮だから気遣っているのだと思っていた。以前、若葉も彼はとても優しい人だと言っていたし。
悩む菊を置き去りに、若葉は嬉しそうに「小さい頃の黒王様は……」などと、さっそく語り始めている。
「まあまあ、それはそれはやんちゃでしたよ」
「え、あの黒王様がですか!? とても落ち着いた方ですが……」
「猫かぶりです。花御寮様に格好よく思われたくて、一生懸命につくろっているんですよ。わたくしの方が、えっと……三つ年上なのですが、もうそれは昔っから随分と手を焼かされたものですよ。わたくしの母が先代の花御寮様に仕えていたのもあり、よくわたくしもお屋敷に連れてこられていまして」
「ああ、それで幼馴染みなんですね」
「ええ、年が近くてちょうど良いからと、黒王様と、乳母兄弟の灰墨という者がいるんですけど、いつの間にかそのふたりのお世話係にされてましたね。花御寮様は灰墨をご存知で?」
「い、以前、母屋に行った時にチラッと……」
菊が困ったように笑ったのを見て、若葉は「あー」と理由を察する。
「灰墨は昔から黒王様に憧れてましたからね。だからその黒王様が……」
その先を言いにくそうに若葉が言葉を濁す。
「ええ、黒王様から聞いてます。そんなことがあれば、誰だって人間が嫌いなって当たり前ですよ」
なるべく直接的には言わず知っているということを伝えれば、たちまち若葉の涼しげな両目が大きく、眦が裂けんばかりに見開かれた。
「え、あ……ま、まさか聞かれたんですか? 黒王様から先代花御寮様のことを」
そんなに驚くことだろうか。
素直に菊が頷くと、若葉は今度は目を細め、はぁと吐く息を震わせていた。
「良かった……っ本当に……あなた様が花御寮になってくださって。あの件で、彼は心を閉ざしてしまい、ほとんどの感情を失っていました。以降、決して誰にも先代花御寮様の話や、その件について口にはしませんでしたから」
「感情を失う……分かる気がします」
村にいた時の自分も、感情など苦しいと悲しいくらいしかなかったものだ。それが当たり前になりすぎて、他の感情があることもすっかり忘れていた。
考えると絶望に打ちのめされそうになるから、どうでもいいと無心で生きるしかなかった。
「でも今、黒王様は信じられないくらいに穏やかに笑われます。帰られる時も、とても名残惜しそうに広間を何度も振り返りながら」
「知らなかった……です」
――私だけじゃなかったのね……。
閉まった扉に名残惜しさを感じていたのは。
きょとんとしてこぼせば、若葉は眉を垂らして「そうでしょうとも」と肩を揺らした。嬉しくて仕方ないといった様子で、目尻を濡らしている。
「まるで幼い頃のあの子を見ているようで……感情豊かに、日々を楽しんでいるあの頃に戻ったようで、わたくしはとても嬉しかったのですよ」
握りしめた菊の手に、若葉は敬うように額をあてがう。
「彼の心を取り戻してくださって、ありがとうございます。侍女の若葉ではなく、彼の幼馴染みとして心より感謝しております」
彼女の手は小刻みに震えていた。どれだけ彼女が彼のことを気に掛けていたのか伝わってきて、菊も思わず目頭が熱くなる。
――誰かが喜ぶのが、こんなにも嬉しいことだなんて。
「私、黒王様の花御寮になれて良かったです」
心からの言葉だった。
しかし、自分がその名前で呼ばれるのもあと数日。瞬間、胸の奥が痛いほどに締め付けられる。しかし、菊はその感情を見ないふりした。
その代わり、痛みを誤魔化すように菊はチラッと横目で入り口を窺った。
「黒王様もそう思ってくださってたら嬉しいんですけど……」
なぜだか泣きたくなった顔に、無理矢理笑みを貼り付ける。
「大丈夫ですよ。きっと明日は訪ねてこられます。たくさん文字を練習して、驚かせましょう!」
「そうですね」
若葉はちゃんと騙されてくれたようで安心した。
まだ自分はしっかりと花御寮をできている。
◆
しかし、次の日も、そのまた次の日も、彼は姿を現さなかった。
病気なのではと心配になり、若葉に様子を尋ねたりもしたが、彼女は病気ではないと首を横に振った。
「仕事が詰まっているのかとも思いましたが、今の黒王様でしたら、一瞬でも手すきの時間があれば飛んできそうなものですのに」
「あの、私から黒王様を訪ねてはいけませんか?」
あと僅かな限られた時間は、少しでも多く彼と過ごしたかった。
菊の提案に、若葉がパンッと手を打つ。
「そうですよ。待っている必要なんかありませんものね! 花御寮様は母屋でも他の棟でも、ご自由に歩かれて良いんですよ」
どうやら今までの花御寮は、東棟からは絶対に出ようとしなかったとかで、若葉もすっかり忘れていたらしい。
確かに、嫁入りを泣き叫ぶほど嫌がっていたのなら、わざわざ東棟を出て人の多い母屋へと行こうとは思わないだろう。
「では、若葉さん。供をお願いします」
こうして菊は、東棟を出て母屋へと向かったのだった。
母屋には以前黒王に手を引かれて一度来たきりだったが、若葉がいてくれたおかげで迷いはしなかった。そして、黒王の行動範囲を把握している若葉によって、あっという間に彼は見つかった。
「こんにちは、黒王様」
「レ、イカ……ッ!?」
なんのことはない。黒王は彼の私室にいた。
若葉が訪ねて来ただけと思ったのだろう。若葉の入室を請う言葉に「んー」と気のない返事をした黒王は、現れた菊を見て、飲んでいた茶を吹きだしていた。
「いつも黒王様に来ていただくばかりでしたので、今日は私から訪ねてみました」
「どうやらお仕事中ではなさそうですし、ちょうど良かったですね、花御寮様」
「ええ、ありがとうございます、若葉さん」
「では、黒王様、花御寮様。どうぞごゆっくりぃ。あ、帰りは黒王様が東棟まで送って差し上げてくださいね」
「え、あ、おい! 若葉っ」
言いたいことだけ言うと、若葉は黒王に口を挟ませる暇もなく部屋を去って行った。
てっきり、いつものように笑みを向けてもらえると思ったのだが、黒王の顔は菊を向いていなかった。口元の茶を袖で拭きながら、どこか気まずそうに視線を下げている。
「すみません、突然。お仕事の休憩中だったでしょうか?」
「ああ、いやまあ……そうだな。この後は少し……郷の外を見回るつもりだ」
「黒王様自ら見回りなどされるのですね」
「ここ数ヶ月、他のあやかしが近くをうろついていてな。結界を張っているから中までは入って来ることはないし、もう片付いたようだが。一応念のためにな」
「それは大変ですね。そんな時にすみません。黒王様のお姿が最近見えなかったもので、気になって……」
「――ッ本当か!」
逸らされていた黒王の顔が、勢いよく菊へと向けられた。あまりの勢いの良さに、菊のほうが驚いて一歩下がってしまう。
部屋に入って初めて交わった視線。
その表情はパッと花が咲いたように晴れやかなもので、紫色の瞳の中では星がぱちぱちと瞬いていた。
「あ、いや……なんでもない」
しかしそれも、一度強く瞼を閉じ、再び開けた時にはもう消えていた。
視線も逸らされたままで、部屋にもどかしい気まずさが漂う。
菊はまだ部屋の入り口に立ったままであった。普段の彼ならば、部屋に菊が来た時点で手招きでもしそうなのだが、やはり今日は最初からどこか様子がおかしい。
「レイカ……聞きたいことがあるんだが……」
「はい、なんなりと」
いつも隣で会話していたから、今のふたりの距離もそうだが、菊が立って黒王が座っているという妙な距離に違和感がある。
「その……体調は悪くはないか。腹が痛いとか……」
「ええ、おかげさまで。お料理は美味しいですし、若葉さん達皆さん優しいですし、差し込む太陽は暖かですし、一面の桜も美しいですから。村にいた時よりも健康的ですよ」
「そ、それならば良いが」
またしても奇妙な空気が流れる。
――何かしら? 言いたいことを我慢してるような……。
彼は言葉を飲み込むように、何度も喉を上下させていた。
「もう、鴉の郷には慣れたか」
「はい、とても素敵なところです」
「では、そろそろ女官達に湯殿や着替えの手伝いをさせてはどうだ。仕事がないと困っているぞ」
どくん、と心臓が痛いくらいに跳ねた。まるで内側から胸を殴られたようだ。
「い、あの、それはまだ慣れないと言いますか……その……見られるのが恥ずかしいので……」
気付けば、先ほどまで視線を逸らしていた黒王がこちらを向いていた。
吸い込まれそうなほどに深い紫が、射抜くような強さでまっすぐに見つめてくる。
「……っ」
もしかして、入れ替わりがばれたのか。それとも、この身体を誰かに見られたのか。
菊の踵がトンとぶつかった。
「あっ!?」
振り返れば、いつの間にか背後にある障子まで後ずさっていたようだ。これでは、何かやましいことがあると言っているも同然だ。
「どうした、そんなに慌てて」
近くで彼の声が聞こえ、驚きと共に顔を正面へと戻した次の瞬間、菊は息をのんだ。
黒王が目の前に立っていた。
思わず体勢を崩してしまい、よろりと今度は踵だけでなく背中まで障子にぶつかってしまう。ガタガタと障子がうるさく揺れた。
「俺に言えないことでもあるのか?」
「そ、そのようなことは……」
カタン、と顔の両側から乾いた音がした。菊の逃げ道を塞ぐように、黒王が障子の格子に手を掛けていた。黒王が高い位置から菊を見下ろす姿は、黒い着物を着ていることもあり、まるで大きな烏が小さな菊に覆い被さっているようだ。
影が落ちた顔の中で、紫の双眸が不穏にギラついている。
「なあ、レイカ。嘘は吐かないと桜の木の下で約束してくれたよな」
「嘘など……ついていません」
そう言っている今も自分は嘘を重ねている。
――お願い。もうそれ以上踏み込んでこないで。
嘘を吐く口は震え、逸らさないと決めた視線は伏せられ、膝が今にも抜けそうだった。
いつかはばれると覚悟していたが、せめてぎりぎりまでは彼の花御寮でいたいのだ。
「見られるのが恥ずかしいから、な」
「あの、こ、黒王様……」
「本当は、身体を見せられない理由でもあるんじゃないのか?」
「――っ!!」
心臓が胸を突き破ったのかと思うほど、身体の中心が激しく脈打った。嫌な汗が背中をじっとりと濡らす。
彼は何をどこまで知っているのか。
「恥ずかしいならば慣れてしまえばいい。俺達はもうすぐで夫婦になる関係だ。俺にならば見られても構わないだろう?」
言い終わらぬうちに、黒王の手が胸元の合わせからするりと入り込んできた。
「え、あっ!? お、お待ちください、黒王様!」
「待たない」
菊が必死に制止の声を上げるも、黒王は強引に手を進め続ける。彼の手は胸元の輪郭をなぞりながら肩へとのぼり、到着すると撫でるようにして着物を脱がせはじめた。
「いやっ、黒王様!」
身をよじって黒王の手から逃れようとした菊だったが、障子に突っ張っていた彼の腕に引っかかり体勢を崩してしまう。
「きゃっ!?」
「レイカ!」
ぐらりと大きく傾いた菊の身体をすんでのところで黒王が抱きとめるが、既に半分以上倒れていたこともあり、二人してもつれるように畳へと転がった。
ドスンという大きな音の割りに菊の身体に痛みがなかったのは、黒王の腕が代わりに下敷きになってくれたからだろう。
脇から頭へ、背中から腰へと回された腕は、確かな力で守るように菊を抱きしめていた。
耳元で「痛っ」と言う黒王の声が聞こえた次の瞬間、彼はガバッと身を起こし、不安そうな顔でこちらを見下ろしていた。
「大丈夫か、レイカ!?」
彼の顔には焦燥が浮かんでいる。
「大丈夫です」と答えようとしたのだが、口を開けば言葉よりも先に嗚咽が漏れた。
彼は自分の嘘に気付いているのに、それでもこうして心配してくれる。
――私には、彼に心配してもらえる資格なんかないのに……っ。
すると、黒王の顔が苦しそうにしかめられた。
「頼む……泣かないでくれ」
言われて初めて、菊は自分が泣いているのだと気付いた。
目尻からぬるい雫がこめかみへと流れ落ち、畳に広がった髪を濡らしていく。一旦認識してしまうと、次々と涙があふれて止まらなくなってしまう。
「泣かせたいわけじゃないんだ。お前が大切だから全てを知りたいんだ」
見ている方が痛々しくなるほどの悲痛な顔で、絞り出すように言った黒王は、畳に広がった菊の波打つ長い髪を、壊れ物に触れるような手つきで丁寧に梳き続けた。
それはまるで『もう触れないから』と言っているようで、ますます菊の胸は締め付けられ嗚咽が止まらなくなる。
「……っ見な……で……」
ごめんなさい、嘘を吐いて。
ごめんなさい、何も言えなくて。
ごめんなさい、あなたにそんな顔をさせて。
ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
「こく……お、様……っ、お願……ッ……し……」
偽物なのに、あなたの傍にずっといたいと願ってしまって、ごめんなさい。
顔を両手で覆い見ないでと懇願する菊を、しばらく黒王は唇を噛んで見つめていたが、視線を切ると一緒に、自らの羽織をはだけて露わになっていた菊の胸元に掛けた。
え、と菊が思った瞬間、羽織で身体を包むようにして、抱き起こされる。
突然の予期せぬことに菊の涙も止まったが、それも一瞬。
「好きだ」
肩口に顔をうずめ、羽織の上からきつく抱きしめながら呟いた黒王の言葉に、止まっていた涙が再び流れだす。
〝好き〟という言葉が、これほどに感情を切なくするものだとは知らなかった。そして、同時に胸を高鳴らせるものだということも。
「黒王……様」
「どうした」
互いに顔を見ずに声だけを交わす。
「もう少しだけ……っ、こうしていて、くださいますか……」
途端に、グッと彼の抱きしめる力が増した。隙間がないほどにくっつき、互いの体温だけでなく鼓動すらも伝わってくる。
「もちろんだ、レイカ」
彼の腕の中にいるのは自分なのに、彼が呼ぶ名前は自分ではなかった。
しかし、だからこそ彼の腕の中にいられるのだ。
レイカを羨ましく思ったことなど一度もなかったのに、彼に名前を呼んでもらえる今だけは羨ましくて仕方なかった。
――ずっとは願いませんから、だからどうかあと少しだけ、彼を私にください。
今、菊はやっと初めてこの感情の名を知った。
これは間違いなく〝恋〟だった。
障子を通した柔らかな薄光に包まれ、部屋の色が白から茜になるまで、ふたりが離れることはなかった。
4
「昨日は驚きましたよ。花御寮様ったら、黒王様に抱えられて戻ってこられるんですもの。しかも、すやすやと心地よさそうな寝息を立てられて」
「そ、それは本当、なんと言って良いのやら……」
恥ずかしそうに菊が袖で顔を隠せば、若葉だけでなく女官達からもクスクスと笑いが漏れる。
今朝、目が覚めたら自分の布団で寝ていた。どうやらあの後、自分は彼の腕の中で眠ってしまっていたらしい。しかも、東棟に帰ってきたのが日も暮れた頃と聞かされ、どれだけ長時間、彼を枕にしてしまったのかと申し訳なさでいっぱいだった。
それに加え、昨日の一件が気掛かりでしょうがない。
彼は今日どのような顔をして来るのか。どのような顔をして会えば良いのか。もう一度聞かれた時、はたして自分は嘘をついていないと言えるのだろうか。
言いようのない不安に、じわじわと胸を蝕まれているようだった。
「そんな落ち込まないでくださいな。わたくし達は黒王様の腕の中で眠られている花御寮様を見て、嬉しかったんですから」
どうやら若葉は、菊の表情が暗くなったのを寝入ってしまったからと思ったようだ。
「若葉さん達が嬉しい、ですか?」
菊は首をコテンと横に倒す。
「ほら、人間はわたくし共を怖がるでしょう? でも、花御寮様は眠られるほど心を開いてくださっているのだなと思いまして」
頬を緩めて「くふふ」と変な笑いを漏らす若葉は、本当に嬉しそうだった。
「若葉さん達は、今までの花御寮に色々と辛い思いをさせられてきたのに、どうしてそう私に最初から優しいんですか?」
「弱い者が強い者を怖がるのは自然の摂理ですから」
にっこりと微笑まれ、姿形は一緒でも彼女達は常世に住む〝あやかし〟なのだと思い知らされ、少しだけ背中が冷たくなった。余裕が感じられる笑みは、絶対的な強者だという自負からきているのだろう。
「それに最初に言いましたように、来てくださっただけでありがたいんですから。邪険にすることなどあり得ませんよ。まあ、それ以上に、わたくし共が純粋に花御寮様を好きだからですけどね」
ねー、と若葉と女官達は、少女のように声と首の角度を合わせて楽しそうに笑っていた。
「ですから、明後日の婚儀が楽しみで楽しみで仕方ないんです!」
「若葉殿ったら、まあ張り切っちゃって」
「本当に。こんなに張り切る若葉殿は珍しいんですよ、花御寮様」
「明後日……」
外に目を向ければ、桜は満開に咲き誇っていた。
風に吹かれ、さやさやと揺れた花が、広庇に薄紅色の雨を降らせている。
そう、婚儀は明後日だ。
今はそのために、当日着る衣装の最終調整をしているところである。
村から嫁入りするときにも白無垢は着た。その時は、こんな上等なものは後にも先にもこれきりだろうなと思ったものだが、目の前の衣紋掛けに掛かっている白無垢や色打ち掛けはその比ではない。
ただの白かと思えば、同じ白糸で模様が入れられており、光の加減で裾には流水文様が、胸元には桜と扇文様が浮かび上がる。下に着る着物――掛下にも透かしが入り、帯は七宝文様。末広には金箔が巻かれ、頭を飾る簪の飾りにも見たことない美しい石がちりばめられている。
溜息が漏れるほどに美しいとは、このことだろう。
「でも、その前にまずは明日の潔斎ですけどね」
調整を終え、出した小物をてきぱきと片付けていく若葉達。
「禊ぎ、でしたっけ。それはどこでするんですか? 郷の外でしょうか」
「いえいえ、ご安心ください。郷の中ですから」
「安心?」
菊は首を傾げた。
「最近までどこかのあやかしが、郷の外をウロチョロしていたようでして」
「そういえば、黒王様もそんなことを言っていたような」
「雑魚あやかしのようですから、そこまで心配する必要はありませんが。玄泰様が黒王様の命で対処されたようですし、もう大丈夫ですよ。大丈夫です、婚儀にはなんの支障もありません」
はは、と菊はなんとも言えず、曖昧な笑みで話を躱す。
「それに、万が一があっても黒王様は強いですから。なんとかしてくれます!」
若葉が力強く拳を握っていた。
「あやかしにも、強い弱いがあるんですか?」
あやかしはあやかしとしか捉えていなかったが、その中にもやはり序列があるのだろうか。
人間社会にも序列はあった。たとえば貴族には帝都貴族と地方貴族があり、平民にも商人や農民、職人など、さまざまな身分が存在した。当然、平民より貴族のほうが上であり、貴族の中では地方よりも帝都貴族のほうが序列は上だ。
その中で、界背村は『祓魔師』と呼ばれるのだが、少々特殊で平民のくくりには入らなず序列から独立した地位にあった。しかし、村の中しか知らない菊がそれを体感することはなかったが。
「あやかしの序列は当然ありますよ」
腕組みした若葉が、深く頷きながら教えてくれた。
まず、水神や龍といった神と呼ばれる者達がいて、その次に、鬼や天狗、大蛇など人間にも伝承されるような者達、そして、烏や狐などの現世の自然界にも存在する者達がいて、最後に魑魅魍魎といった群れにならない小さな者達の順が基本なのだとか。
「だから我ら鴉は群れを作るのです。ひとりひとりの力は弱いですが、数は他のものとは圧倒的な差がありますからね。それと、実は黒王様はこの序列の限りではないんですよ。鬼か、下手したら龍にも並ぶほどの妖力をお持ちなんですから」
「え、でも黒王様も烏のあやかしですよね」
「ふふ、だから黒王様は我らの長であれるんですよ」
若葉は、目と口元に意味深な弧を描いていた。
◆
夜、菊は寝所を抜けだし、いつもの広間にひとり佇んでいた。
時刻はそろそろ日付が変わろうとする頃、辺りはひっそりと静まりかえっている。菊が歩くたびにギィと板張りの床が鳴き、もの悲しさをかもしだしていた。
ほぼ満月の月が、手燭もいらないくらいに全てを明るく照らし出す。
とうとう今日、彼は来なかった。
どんな顔をして会えば良いのか分からなかったから、少しだけホッとしたが、それよりも寂しさのほうが大きかった。
明後日はとうとう婚儀の日だ。
『婚儀』という言葉を聞く度に、胸が苦しくなって息ができなくなる。
「最初から分かっていたことじゃない」
しかし、最初はこのようになるとは思わなかったのだ。
黒王は恐ろしいあやかしで、人間を食べると思っていた。たとえ食べられなくとも、ひどい扱いを受けるのだろうと覚悟していた。
菊は見上げた月に向かって手を伸ばした。
「一度で良いから……菊って呼んでほしかったわ……」
彼の、低く穏やかな声で。
「……っ……ぅ」
菊は痛みに耐えるように身体をくの字に曲げ、自らの手で自身を抱きしめた。
なぜ涙が出るのか。
今までにも涙くらい、いくらでも流してきた。たくさん殴られた夜にも、空腹で寒くて凍えそうな朝にも、手を伸ばして誰にも見向きもされなかった日にも。
でも、これはそんな悲しいだけのものとは違う。
こうして涙が出る理由を、菊は昨日、彼に強く抱かれた腕の中で知った。
「好き……」
これは愛おしさだ。
彼に恋をして芽生えた、甘くて、もどかしくて、痛い感情。
「好きです……黒王様……っ」
狂おしいほどに、離れがたいほどに、彼を愛してしまった。
――だから、これ以上は駄目。
彼も好きだと言ってくれた。
しかし、その言葉には応えられない。たとえ自分も同じ気持ちだとしても。
菊は濡れた瞳を袖で拭い、まばゆいばかりに輝く月を見上げた。
「このままじゃいけないのよ、菊」
このまま、彼と婚儀を挙げるわけにはいかなかった。
「私が花御寮に相応しくないって分かった時に婚儀を終えてしまっていたら、村がもうひとり別の娘を寄越すとは考えられないもの」
ただでさえ、どこの家も花御寮を出し渋っているというのに。契約通りひとり出したのだからもう良いだろうと拒否するはずだ。
しかし婚儀前ならば、黒王達も新たな花御寮をと押し通せるだろう。
「私の役目もこれでおしまい」
言った後で、くっと口角が下に引っ張られる。
「元々私は偽物なのよ。良かったじゃない、偽物のくせにこんなに贅沢な時間を与えてもらって。あのまま村にいるより幸せだったのよ」
自分に言い聞かせるように、菊はこれで良いのだと言い続けた。
「きっと黒王様なら、新しい花御寮にも優しくしてくださるわ。とっても素敵な方ですもの、新しい花御寮もすぐに彼を好きになるわ」
彼と婚儀を挙げ口づけを交わし、名前を呼ばれながら肌を重ね、彼との子供をその両手に抱くのだろう。
「――っ!」
両手で顔を覆った指の隙間から、一度は止めたはずの雫がまたぽたぽたと滴っていく。
「そんなのいや……っ」
しかし、どうしようもない。
自分は忌み子だ。生まれた時から彼と結ばれる運命になかっただけだ。
しかし別れるのなら、せめて彼に好かれたまま別れたかった。
「こんな汚れた身体、彼には見られたくないもの」
何も知られず、彼の記憶には綺麗なまま残りたかった。
「全ては、明日の潔斎まで」
潔斎は身を清めるため、全てひとりで行わなければならないと聞いた。
ひとりになったら密かに郷を出よう。郷の外のあやかしも片付いたと言っていたし、きっと大丈夫。それに、花御寮自らが逃げたとなればあやかし側に責任はない。
菊は、広間の隅に置かれたいくつもの唐櫃に目を向けた。その中のひとつから硯箱を取り出し、筆をとったのだった。
◆
眩しいほどの月明かりが、部屋の畳に障子の格子模様を落とす。
黒王は酒杯を傾けながら、斜めに歪んだ格子を視界に映しているのだが、頭の中はまったく別のことを考えていた。
レイカは羽根のように軽かった。
彼女を手に抱いたのは、あれで二度目だ。
一度目は必死にしがみついてきて、それが猫のようで愛らしく、重さなど気にする余裕もなかった。
二度目は、自分の腕の中で眠っていた。少し赤く腫れた目元と、頬に残った涙の跡を愛おしく思ったものだ。東棟になど戻さず、このまま腕の中に閉じ込めて、彼女が目覚めるその瞬間まで寄り添っていたかった。
「腹の中に子がなあ……」
昨日の彼女の反応を考えると、おそらくほぼ間違いはない。
しかし幸いにも、灰墨以外レイカが身ごもっていることは誰にも知られていなかった。
彼女が身ごもっていると知ってから、しばらく東棟へは足が遠のいた。どう接したら良いのか分からず、頭もぐちゃぐちゃで、彼女を見たら思ってもないことを口走ってしまいそうだったから。
嘘を吐かないと誓ってくれたのにと憎む気持ちと、それでも彼女には傍にいてほしいと渇望する気持ちとが何度も衝突して、この先どうすればいいのか、ずっと答えが出せないままでいた。
しかし、突然『気になって』と言ってレイカが部屋にやって来た。
正直、嬉しかった。彼女が自分を気に掛けて会いたいと思ってくれたことに、震えるほどの喜びを感じた。
そんな優しい彼女が身ごもっているはずがないと、確信がほしくて様子を窺ってみたのだが、彼女の反応を目の当たりにして、頭から血の気が引いていった。
明らかに、彼女は動揺し何かを隠していた。
驚くほど頭が冷えていた。いや頭だけでなく、まるで氷塊を飲まされたように身体の真中心が痛いほどに冷たくなった。
気がついたら、自分は彼女を襲おうとしていた。このまま婚儀を待たず、自分のものにしてしまおうかとも考えていた。
しかし、彼女が倒れそうになったのを見た瞬間、そんな考えはどこかへ飛んでいった。レイカだけでなく腹の子も守らねばと思い、抱き留めていた。
「悩むだけ無駄だったな」
やはり自分は、彼女が身ごもっていても手放せないらしい。
『見ないで』と、泣きじゃくりながら哀願する彼女すら愛おしく思った。
『もう少しだけ』と抱擁を求める彼女を、誰が拒めるだろうか。
そのまま腕の中で眠ってしまった彼女の額に、密かに口づけた。本当は唇にしたかったが、婚儀まではと我慢したものだ。
今日が婚儀の前に彼女に会える最後の日だった。
本当は会いたくて堪らなかった。
しかし、運悪く玄泰やその他の里長、灰墨にまで捕まり、明日に控えた潔斎や明後日の婚儀について、段取りの確認や郷の者達への振る舞いなどを話し合っていたら、あっという間に日が傾いていた。
明日のこともあるし、きっと緊張しているだろうから、さすがに夜に訪ねるのは憚られた。次に会えるのは婚儀の時だ。
「ははっ、まったく……どれだけ彼女のことを考えているんだか」
思わず苦笑が漏れた。
会っていても離れていても、常に脳裏には彼女の姿があった。
「自分でもどうしようもないくらい、彼女に惚れているんだろうな」
たとえ嘘を吐いていようとも、その嘘ごと愛せるくらいに。
おそらくレイカの身ごもりがばれたら、里長達は新しい花御寮をと騒ぐだろう。
「奪われて堪るか」
自分から彼女を引き離そうとする者は、誰であっても許さない。
彼女以外、花御寮はありえない。
黒王は酒杯を床に置くと、障子を開けに立った。
滑りの良い障子はすーっと静かに開き、夜の虫の音を邪魔することはない。廊下に出て見上げれば、ほとんどまん丸の月が夜闇に浮かんでいた。
次に会えるのは婚儀の日。
「俺がほしいのは、花御寮じゃなくて彼女なんだ」