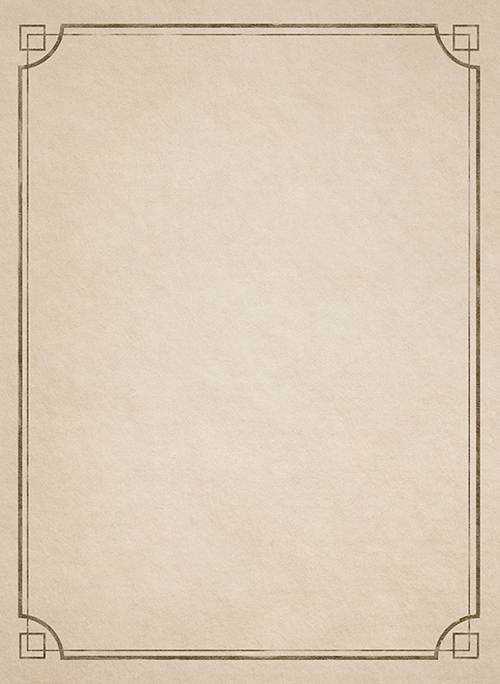姉と話していて、それがいいと思った。だって、どうせどちらも選べないのなら、どちらも捨てたって一緒だって、そう思った。
駆け落ちなんて、出来ない。あのひとを連れていくことなんて、出来ない。あのひとはこれからのこの国に必要なひとで、私ごときが連れていっていいようなひとなんかじゃない。
だから、全部捨てて、ひとりになって。それで、もう父とも姉ともあのひととも関係のないところで、好きに生きたらいいって、そう思ったのに。
穏やかな口調でそれを止めた姉は、私の唇にそっと、人差し指を当てた。
「あのひとにね、お願いしてきたから。茜のこと、幸せにしてくださいって。……茜の、好きなひとの分まで。茜のことを幸せにしてください、って」
「お姉、ちゃ」
「あのね、茜。幸せになっていいの。……求めていた幸せとは、まったく違うものかもしれないけれど。私はもう十分、あのひとに愛してもらったから。……だからね、幸せになってね、茜」
姉が、私の頬を撫でた。優しい手つきに、ひゅっと胸の奥が冷える。
だって、私が幸せになったって、姉は。
待ってお姉ちゃん、と声が漏れる。違うの茜、と間髪入れずにねじ込んできた姉が、本当に違うの、と重ねて続けた。
「いなくならないよ、茜。私は別に、いなくなったりしないから、大丈夫。……私もね、別の家に嫁ぐの。あのひとが、せめて私が幸せになれますようにって、……だったら、私がそのままあのひとの傍にいたって、いいようにしてくれたらよかったのに……」
零れ落ちた言葉は、本音。
慰めの言葉一つ欠けられない自分が、ひどく悔しい。それでも、私たちはやっぱり、この人生から降りることを許されていないのだと、強く実感してしまった。
すべてを捨てててくれたら。そうしたら、私たちだってすべてを捨てることができるのに。
それを許してはくれない。どこまでも、彼らは私たちのことを心配して、私たちのことを想って行動してくれる。
そして、それが分かっているから、私はまだ、父に嫁ぎ先を告げられてからあのひとに会っていない。
知っているだろう、と思う。もうあのひとは知っているだろう。私があのひとでない誰かに嫁ぐことも、その嫁ぎ先も。本当は私から伝えるべきだったのに、私はそれから逃げて、家に閉じこもったままだった。