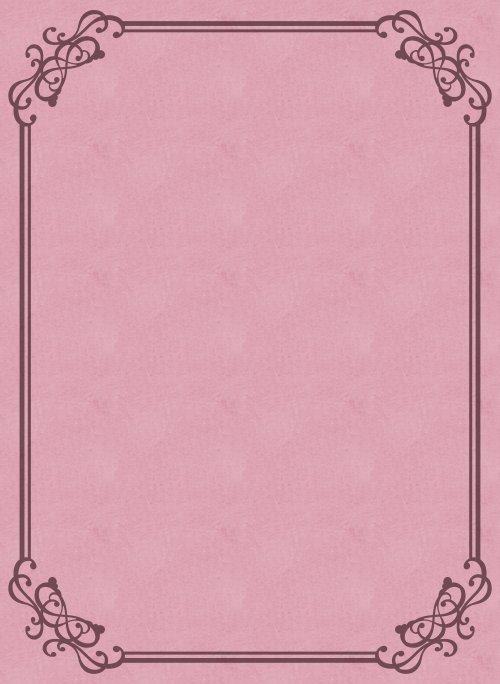大切なヒトをなくしたとき、大切なものをなくしたとき、落ち込み、塞ぎ込んでしまうのはどうしたって仕方がないことだと思う。実際、僕が今そうだった。僕は亡くなった父からもらったギターを無くしてしまった。あんな大きいもの、一体どうやったら無くなるのか不思議で仕方ないが、でも無くなってしまった。母も知らないという。とても悲しい。そんな、僕にとっては大きな出来事でも、誰かにとっては些細な出来事でしかない日常であることが、実は最も悲しいのかもしれない。
そんなある日、裏山で不思議な生き物を僕は見つけた。二頭身くらいの手のひらサイズの小さな生き物。小さな手と小さな足があって、腰が少し太って丸くなっていて前身緑で、卵の殻を被ったような格好をしている。
なんだ、あれ。
ちなみに裏山とは、中学校の街とは反対側の裏側にある山のことである。父を亡くし、母の手一つで育てられている僕は、学校が終わるとよく遊びに行っていたのであった。
そこで見つけたその小さな不思議な生き物は、なにか急いでいるようだった。影に隠れて様子を見ていると、やがて水の溜まっている洗面器ほどの大きさの桶に辿り着き、縁《ふち》に立ってそして飛び込んだ。びっくりして急いで近づき、その桶を覗いてみるとそこにはもう何もいなかった。
消えてしまった。
不思議に、不可思議に思って手を顎に当ててしばらく覗き込んでいると、その時、バランスを崩してしまった。そう、僕も桶に顔を突っ込んてしまったのである。ばしゃばしゃと音を立てて突っ込み、そして同時に吸い込まれるような感覚が。真っ暗な闇の中に放り出され、全身の感覚がなくなったと思ったら、次の瞬間には地面に転がっていた。
気がついたその世界はどこか別世界であった。
人間の世界ではない、そういう気がした。
あの不思議な生き物がたくさんいた。二頭身であることに変わりはないけど、大きさが違う。だいたい手のひらサイズだったのが、今は僕と同じ大きさのように見える。僕が小さくなったのか、彼らが大きくなったのか。どちらにしてもファンタジーな世界に来てしまったのは間違いがないようであった。
僕は冷静であった。不思議な生き物を見つけたときも、この世界に来たときも努めて冷静であった。取り乱したりすることはない。驚くこともない。いや、驚くべきことが起こっているのはまさにその通りなのだが、声を出したり、騒いだりすることはないということだ。そんなのはみっともない。見るに耐えない。恥ずかしい。羞恥の極みである。
大切な人をなくしてから、僕はずっとこうだった。どこか遠くから自分を見ているというか、感情の起伏がないというか、子供にしては大人びているというか、悪くいえば気取っているように見えるのかもしれない。それは全て自覚していたし、理解したうえで自分だと思って過ごしてきた。
だからこうしてファンタジーな世界に足を踏み入れてしまっても、なんとかなるだろうと、どこか楽観的な思いであるのもまた、自分自身である。
僕は先ほど見かけた不思議な生き物を見つけた。近づいて行って背中を掴み、ぐいっと引き寄せた。
「突然ですまない。君を追いかけてここまで来た。ここはどこなのか教えてくれるか」
「なんだ、お前。人間か? 珍しいな」
「驚きはしないんだな」
「ああ、たまに紛れ込んでくるのを見かける。お前も迷い込んだのか?」
「まあ、そんなところだ」
人間の言葉、日本語が通じるのはやはり人間世界を行き来していたからだろうか。
「ここは俺たち『カプ』の世界。人間が捨てたものを拾ってきては、それで家を作ったり、使ったりして生活している。こんなんでいいか? ちょっと急いでるんだ」
「急いでるところ悪いけど、でもそれって泥棒ってことだよね?」
「泥棒じゃない。捨てられたものを拾っているだけだ」
「でも法律だと……」
「人間の法律なんか知るか。それは人間にでも当てはめていろ。俺たちには関係ないことだよ、そんなことは」
「わかったよ。教えてくれてありがとう」
「おう、じゃあな」
「ちなみにどこ行くの?」
「国王様のコンサートだ。広場であるんだよ」
「僕も行ってもいいかな」
「良いんじゃないか、別に。無料で誰でも観覧歓迎って書いてあったしな」
「ありがとう」
こうして僕は『カプ』の世界の広場へ向かう事になった。
そんなある日、裏山で不思議な生き物を僕は見つけた。二頭身くらいの手のひらサイズの小さな生き物。小さな手と小さな足があって、腰が少し太って丸くなっていて前身緑で、卵の殻を被ったような格好をしている。
なんだ、あれ。
ちなみに裏山とは、中学校の街とは反対側の裏側にある山のことである。父を亡くし、母の手一つで育てられている僕は、学校が終わるとよく遊びに行っていたのであった。
そこで見つけたその小さな不思議な生き物は、なにか急いでいるようだった。影に隠れて様子を見ていると、やがて水の溜まっている洗面器ほどの大きさの桶に辿り着き、縁《ふち》に立ってそして飛び込んだ。びっくりして急いで近づき、その桶を覗いてみるとそこにはもう何もいなかった。
消えてしまった。
不思議に、不可思議に思って手を顎に当ててしばらく覗き込んでいると、その時、バランスを崩してしまった。そう、僕も桶に顔を突っ込んてしまったのである。ばしゃばしゃと音を立てて突っ込み、そして同時に吸い込まれるような感覚が。真っ暗な闇の中に放り出され、全身の感覚がなくなったと思ったら、次の瞬間には地面に転がっていた。
気がついたその世界はどこか別世界であった。
人間の世界ではない、そういう気がした。
あの不思議な生き物がたくさんいた。二頭身であることに変わりはないけど、大きさが違う。だいたい手のひらサイズだったのが、今は僕と同じ大きさのように見える。僕が小さくなったのか、彼らが大きくなったのか。どちらにしてもファンタジーな世界に来てしまったのは間違いがないようであった。
僕は冷静であった。不思議な生き物を見つけたときも、この世界に来たときも努めて冷静であった。取り乱したりすることはない。驚くこともない。いや、驚くべきことが起こっているのはまさにその通りなのだが、声を出したり、騒いだりすることはないということだ。そんなのはみっともない。見るに耐えない。恥ずかしい。羞恥の極みである。
大切な人をなくしてから、僕はずっとこうだった。どこか遠くから自分を見ているというか、感情の起伏がないというか、子供にしては大人びているというか、悪くいえば気取っているように見えるのかもしれない。それは全て自覚していたし、理解したうえで自分だと思って過ごしてきた。
だからこうしてファンタジーな世界に足を踏み入れてしまっても、なんとかなるだろうと、どこか楽観的な思いであるのもまた、自分自身である。
僕は先ほど見かけた不思議な生き物を見つけた。近づいて行って背中を掴み、ぐいっと引き寄せた。
「突然ですまない。君を追いかけてここまで来た。ここはどこなのか教えてくれるか」
「なんだ、お前。人間か? 珍しいな」
「驚きはしないんだな」
「ああ、たまに紛れ込んでくるのを見かける。お前も迷い込んだのか?」
「まあ、そんなところだ」
人間の言葉、日本語が通じるのはやはり人間世界を行き来していたからだろうか。
「ここは俺たち『カプ』の世界。人間が捨てたものを拾ってきては、それで家を作ったり、使ったりして生活している。こんなんでいいか? ちょっと急いでるんだ」
「急いでるところ悪いけど、でもそれって泥棒ってことだよね?」
「泥棒じゃない。捨てられたものを拾っているだけだ」
「でも法律だと……」
「人間の法律なんか知るか。それは人間にでも当てはめていろ。俺たちには関係ないことだよ、そんなことは」
「わかったよ。教えてくれてありがとう」
「おう、じゃあな」
「ちなみにどこ行くの?」
「国王様のコンサートだ。広場であるんだよ」
「僕も行ってもいいかな」
「良いんじゃないか、別に。無料で誰でも観覧歓迎って書いてあったしな」
「ありがとう」
こうして僕は『カプ』の世界の広場へ向かう事になった。