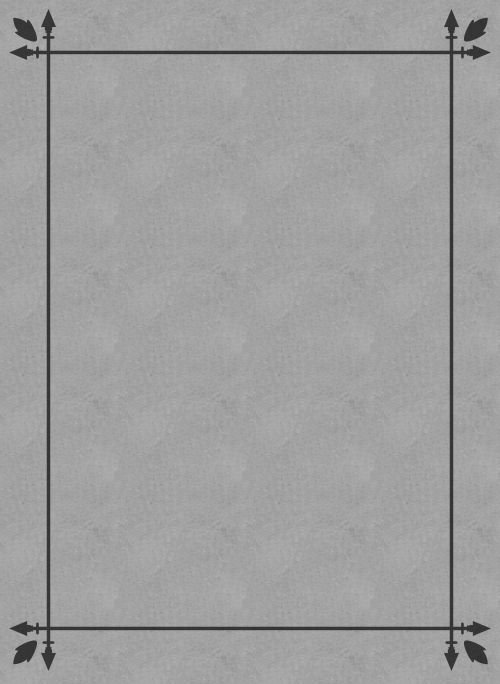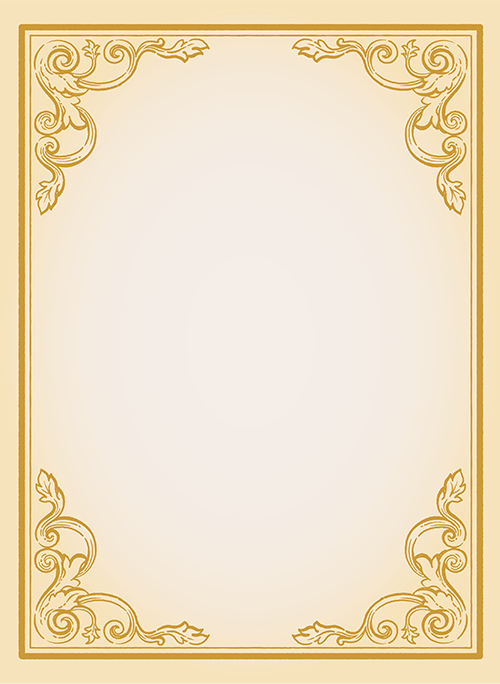「……なんで?」
アモルの問いが部屋に響く。
シオンの横にいるのは、普通の衣服に身を包んだラヴ。
『なんで?』とは『なんでここに?』といったところだろうか。
「アモル、この子、誰?」
シオンが不機嫌そうにアモルを睨みながら聞く。
シオンとしては、幼なじみの自分以外にこんな可愛い子がいるなんて聞いていない、といったところだ。
「アモルを助けたって言ってるんだけど……」
現実世界のこととはいえ、アモルがラヴに助けてもらったのは間違いない。
「えっと、まあそんなところ……かな?」
アモルはベッドから起き上がると、素早くラヴに近づき。
「ごめん、シオン! ちょっと二人だけで話させてね!」
そう言って、ラヴの手を引きながら外に出ていく。
「なんなの、いったい……」
不満そうにシオンはアモルを見送った。
「で、なんでここに?」
「なんでって、話の続きをしにきたの」
「話って……」
アモルも、転移させてくれた礼は言わなくてはいけない、とは思っていた。
だが、他に話があるのかと疑問に思う。
「契約の話の続き!」
「契約って……あのキス? まだ何かあるの?」
ラヴは勢いよく頷くと説明を始めた。
「あのね。異世界に送るために契約したんだけど、タダじゃないの」
「えっ」
そんなの聞いてないとばかりにアモルはラヴを見る。
「安心して! 悪いことにはならないから!
アモルにはね、わたしのお手伝いをしてほしいの」
「手伝い?」
「そう! 正確には、わたしが女神見習いからランクアップするための協力!」
それくらいなら……とアモルは「わかったよ」と頷いた。
「で、なにをすればいいの?」
「それは――」
ラヴはすっと近づくとアモルに再び口づけした。
「っ!? なになに!?」
動揺するアモルに、ラヴは顔を赤く染めながら言う。
「アモルには『愛』を集めてほしいの」
「愛……?」
「言ったと思うけど、わたしは『愛』と『生命』の女神……の見習い!
わたしの契約者として、アモルには愛を集めてほしいの」
「でも愛って、具体的には?」
問うアモルに、ラヴは手を大きく回しながら言った。
「わかりやすく言うと、ハーレムを築くってこと!」
その答えにアモルは咳き込んだ。
「ハ、ハーレムって……」
「愛を集めるの! それくらいしなきゃ! 話終わり! それじゃあ――」
ラヴはアモルを回らせ、シオンの家に向ける。
「まずはあの子の愛を手に入れておいで!」
そう言ってアモルの背中を勢いよく押した。
「あら、アモル、おかえりなさい」
シオンの母、アモルにとっても育ての親が笑顔で出迎える。
「アモルも隅に置けないわね。いつあんな可愛い子と知り合ったの?」
「ははは……」
苦笑でごまかしつつ、アモルは本題に入る。
「あの、シオンは……?」
「ああ、部屋に戻ってるはずだよ」
それを聞くと、アモルは急いでシオンの部屋に向かう。
「シオン。いるよね?」
アモルがノックしながら部屋内に呼びかける。しかし返事はない。
「シオン? 入るよ」
アモルが部屋を開けると、そこには枕で顔を隠すシオンの姿が。
「シオン? あの、さっきの子、ラヴって言うんだけど、話終わったから……」
「……キス」
「え?」
シオンが枕をどけて顔を見せる。
その表情は、怒りとも、何か恥ずかしいとも、言える赤さで染まっている。
「さっきの子。ラヴ?とキスしてた」
「見てたの? えっと、あれは……あいたっ!?」
アモルの顔に枕が直撃する。
「アモルのバカ! エッチ! スケベ! すけこまし!」
「ちょっ、シオン、話を聞いて。あとすけこましってどこで覚え……。痛い痛い!」
落ち着くまでアモルはシオンに物をぶつけられまくっていた。
「というわけで、あの子は女神様なんです。ボクを助けてくれました。それ以上はありません」
「……」
シオンの前で正座しながらアモルは事情を説明した。
もちろん、転移してきた、などは言わなかったが。
「……嘘っぽい」
「……だよね」
アモル自身もそう思っている。
女神だのハーレムだの信じられないだろう。
「でも……」
「うん?」
シオンはアモルに笑顔を向けて言った。
「アモルは嘘はつかないってわかってるから」
その笑顔にアモルはドキッとする。
転移で記憶が混ざっているとはいえ、幼なじみの少女の可愛い笑顔だ。
まだ少年のアモルはドキドキするしかない。
「でも!」
急にシオンが睨みながら叫んだ。
「あの子が神様でもいいし、ハーレム?を作ってもいいけど――」
シオンはまだハーレムの意味がよくわかっていない。
が、顔が赤くなりながらシオンは言葉を続けた。
「アモルは渡さないからね!」
そう言うと、シオンは布団に潜って隠れてしまった。
恥ずかしすぎて出てこれないのは、アモルにもわかった。
「あらあら」
部屋の戸の前でシオンの母が笑顔で様子を見ていたのは、アモルもシオンも気づいていなかった。
アモルの問いが部屋に響く。
シオンの横にいるのは、普通の衣服に身を包んだラヴ。
『なんで?』とは『なんでここに?』といったところだろうか。
「アモル、この子、誰?」
シオンが不機嫌そうにアモルを睨みながら聞く。
シオンとしては、幼なじみの自分以外にこんな可愛い子がいるなんて聞いていない、といったところだ。
「アモルを助けたって言ってるんだけど……」
現実世界のこととはいえ、アモルがラヴに助けてもらったのは間違いない。
「えっと、まあそんなところ……かな?」
アモルはベッドから起き上がると、素早くラヴに近づき。
「ごめん、シオン! ちょっと二人だけで話させてね!」
そう言って、ラヴの手を引きながら外に出ていく。
「なんなの、いったい……」
不満そうにシオンはアモルを見送った。
「で、なんでここに?」
「なんでって、話の続きをしにきたの」
「話って……」
アモルも、転移させてくれた礼は言わなくてはいけない、とは思っていた。
だが、他に話があるのかと疑問に思う。
「契約の話の続き!」
「契約って……あのキス? まだ何かあるの?」
ラヴは勢いよく頷くと説明を始めた。
「あのね。異世界に送るために契約したんだけど、タダじゃないの」
「えっ」
そんなの聞いてないとばかりにアモルはラヴを見る。
「安心して! 悪いことにはならないから!
アモルにはね、わたしのお手伝いをしてほしいの」
「手伝い?」
「そう! 正確には、わたしが女神見習いからランクアップするための協力!」
それくらいなら……とアモルは「わかったよ」と頷いた。
「で、なにをすればいいの?」
「それは――」
ラヴはすっと近づくとアモルに再び口づけした。
「っ!? なになに!?」
動揺するアモルに、ラヴは顔を赤く染めながら言う。
「アモルには『愛』を集めてほしいの」
「愛……?」
「言ったと思うけど、わたしは『愛』と『生命』の女神……の見習い!
わたしの契約者として、アモルには愛を集めてほしいの」
「でも愛って、具体的には?」
問うアモルに、ラヴは手を大きく回しながら言った。
「わかりやすく言うと、ハーレムを築くってこと!」
その答えにアモルは咳き込んだ。
「ハ、ハーレムって……」
「愛を集めるの! それくらいしなきゃ! 話終わり! それじゃあ――」
ラヴはアモルを回らせ、シオンの家に向ける。
「まずはあの子の愛を手に入れておいで!」
そう言ってアモルの背中を勢いよく押した。
「あら、アモル、おかえりなさい」
シオンの母、アモルにとっても育ての親が笑顔で出迎える。
「アモルも隅に置けないわね。いつあんな可愛い子と知り合ったの?」
「ははは……」
苦笑でごまかしつつ、アモルは本題に入る。
「あの、シオンは……?」
「ああ、部屋に戻ってるはずだよ」
それを聞くと、アモルは急いでシオンの部屋に向かう。
「シオン。いるよね?」
アモルがノックしながら部屋内に呼びかける。しかし返事はない。
「シオン? 入るよ」
アモルが部屋を開けると、そこには枕で顔を隠すシオンの姿が。
「シオン? あの、さっきの子、ラヴって言うんだけど、話終わったから……」
「……キス」
「え?」
シオンが枕をどけて顔を見せる。
その表情は、怒りとも、何か恥ずかしいとも、言える赤さで染まっている。
「さっきの子。ラヴ?とキスしてた」
「見てたの? えっと、あれは……あいたっ!?」
アモルの顔に枕が直撃する。
「アモルのバカ! エッチ! スケベ! すけこまし!」
「ちょっ、シオン、話を聞いて。あとすけこましってどこで覚え……。痛い痛い!」
落ち着くまでアモルはシオンに物をぶつけられまくっていた。
「というわけで、あの子は女神様なんです。ボクを助けてくれました。それ以上はありません」
「……」
シオンの前で正座しながらアモルは事情を説明した。
もちろん、転移してきた、などは言わなかったが。
「……嘘っぽい」
「……だよね」
アモル自身もそう思っている。
女神だのハーレムだの信じられないだろう。
「でも……」
「うん?」
シオンはアモルに笑顔を向けて言った。
「アモルは嘘はつかないってわかってるから」
その笑顔にアモルはドキッとする。
転移で記憶が混ざっているとはいえ、幼なじみの少女の可愛い笑顔だ。
まだ少年のアモルはドキドキするしかない。
「でも!」
急にシオンが睨みながら叫んだ。
「あの子が神様でもいいし、ハーレム?を作ってもいいけど――」
シオンはまだハーレムの意味がよくわかっていない。
が、顔が赤くなりながらシオンは言葉を続けた。
「アモルは渡さないからね!」
そう言うと、シオンは布団に潜って隠れてしまった。
恥ずかしすぎて出てこれないのは、アモルにもわかった。
「あらあら」
部屋の戸の前でシオンの母が笑顔で様子を見ていたのは、アモルもシオンも気づいていなかった。