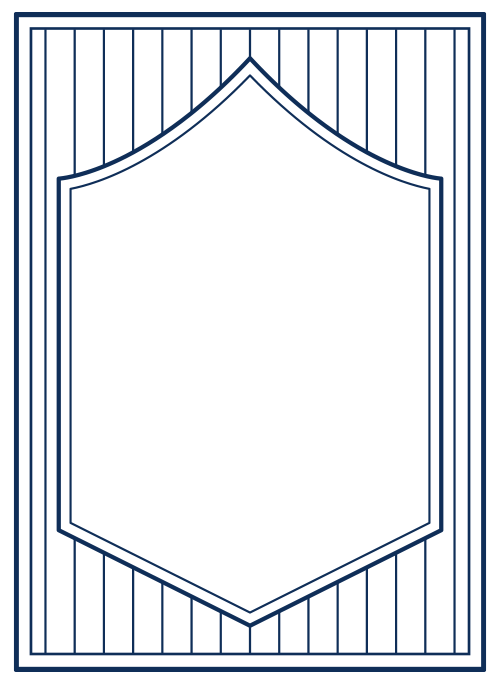一
マイラは唇を噛み締めた。
ようやくラースに近付けたと思ったのに。
ラースの側にいたかったからここへ来たのに。
こんな事なら上級神官の試験など受けなければ良かった。
明日にはタグラへと向かわなければならない。
ミラのせいで……。
ミラさえいなければ……。
そう思った時、向こうからミラが来るのが見えた。
ミラはいつものようにマイラを無視して擦れ違った。
神殿での上下関係は絶対である。
上級神官のミラはマイラを無視する事が出来るが中級神官のマイラはミラに挨拶をしないわけにはいかない。
マイラはミラに頭を下げてから、
「キシャル……様」
ミラに声を掛けた。
ミラはちょっと迷った様子を見せてから振り返った。
「なに?」
カイルとミラへの面会は必ず神殿長かラースを通す事……。
「あなたでなければ倒せない魔物がいると……」
「どこ?」
「ロークの……」
ミラが弾かれたように顔を上げた。
「ありがと!」
ミラが駆け出す。
多分、裏から抜け出してロークへ向かうのだろう。
仮に神殿を追い出されても構わない。
どうせ明日にはタグラへ行くのだ。
ここでなければどこでも同じだ。
神殿じゃなくても……。
マイラは拳を握り締めた。
ミラが神殿の窓を乗り越えようとした時、
「どこに行くんだい?」
聞き覚えのある声に思わず身を竦ませた。
ミラが慌てて振り返る。
「ラース! これは……」
柱の影から出てきたのはウセルだった。
「なんだ。脅かさないでよ」
ウセルに背を向けると再び窓枠に手を掛けた。
「こらこら」
ウセルは苦笑しながらミラを窓から引き離した。
「離してよ」
「お姫様がいなくなったらまた大騒ぎになるだろ」
「私はお姫様じゃないわよ! 魔物が暴れてるの。行かなきゃ」
「君じゃなくてもいいだろ」
「ダメなの。これは私じゃないと」
「今回に限って君じゃなきゃいけない理由は?」
「よく分かんないけど……多分、アイオンと同じヤツだと思う」
「その通り。だからこそ君が行っちゃいけないんだよ。ロークの魔物は俺が倒す」
ウセルはそう言うと神殿の奥に目を向けた。
「俺はこの為に戻ってきたんだ。運命の環を断ち切るためにね」
「運命の……環?」
「そ。運命とか宿命とかってのは嫌いなんだが……自由にしてやるよ。君も坊やも、ガブリエラもラースも……皆」
「ガブリエラも?」
「ああ。早くしてやらないと、あいつ、婚期を逃しちゃうからな」
「ガブリエラと結婚するの?」
意外そうな顔をしたミラの頭にウセルが手を置いた。
優しくミラの頭を撫でる。
「ガブリエラがどっちを選ぶかなんて聞くまでもないだろ。残念だけどな」
「…………」
「じゃ、大人しく待ってろよ」
そう言うとウセルは窓枠に足を掛けた。
「お前は抜け出す必要ないんだから出口から出なさい」
「ラース! いつの間に……」
ウセルが顔を顰めた。
「ミラ。ウセルを裏口に案内してあげなさい」
「いらねーよ」
ウセルは手を振ると窓から飛び降りた。
そのまま振り向きもせずに神殿から遠ざかっていく。
ミラは窓からウセルを見送った。
そしてウセルの姿が見えなくなるとラースの方を振り返った。
自分より優に頭一つは高いラースの顔を見上げる。
「今の、どういう意味?」
「君には君がすべき事があるように、私にもなすべき事があると言う事だよ」
困惑して首を傾げたミラに微笑みかけるとラースは背を向けた。
そのまま執務室へ向かおうとした時、廊下を走る足音が聞こえてきた。
白い聖衣を着た人間が神殿の外へ駆け出していく。
ラースが眉を顰めた。
「あれは、ここの神官じゃない……」
よその神殿の神官は来たという報告は受けていない。
その時、後ろから足音が聞こえてきてミラとラースは振り向いた。
ガブリエラが駆けてくる。
「ラース! 神殿長が襲撃されて……!」
ガブリエラが真っ青な顔で叫んだ。
「カイルは!?」
「今呼びにいかせてる」
ラースは最後まで聞く前に神殿の奥に向かって駆け出した。
ミラとガブリエラも後に続く。
綺麗に整頓された神殿長の書斎。
その部屋の床に神殿長は目を閉じて横たわっていた。
左胸が血で染まっている。
白い床の血溜まりが徐々に広がっていく。
白い聖衣に広がる真紅の染み。
足元に転がる血に濡れた短刀。
既に息絶えているのは一目瞭然だった。
神官長が傍らに膝を突いている。
カイルも既に来ていた。
隣の部屋から中級神官達が不安そうな顔で覗き込んでいる。
「神官長、神殿長は……」
中級神官の一人が訊ねた。
「私達が四人掛かりで回復魔法を掛ければ助かる」
ラースの言葉にミラは弾かれたように顔を上げた。
「ラース……!」
言い掛けたミラを遮るように肩に手が置かれる。
振り返るとガブリエラが目顔で黙っているようにと言っていた。
「神官長は不審者の捜索の指揮をお願いします」
ラースがそう言うと神官長は立ち上がって戸口に向かった。
「彼らは集中する必要がある。お前達は神殿内に不審者がいないか隈なく見て回りなさい」
「はい」
返事をした中級神官達に続いて神官長も部屋を出て扉を閉めた。
二
「ラース、どういう事?」
「今、説明するわ。ちょっと待っててくれる?」
ガブリエラが答えた。
「カイル。やってくれるね」
ラースの言葉にカイルはミラを一瞥してから、
「はい」
カイルは頷いた。
不審そうなミラの前でラースが聖句を唱え始める。
回復魔法ではない。
神の力を借りて結界を張る魔法だ。
神、それも最高神の力を借りて造る何人たりとも覗く事の不可能な強力な結界。
そこまでして隠さなければならない事を今からするのだ。
ラースが結界を張り終えた。
周囲が白いもので囲まれて外が見えなくなった。
続いてガブリエラが同じ聖句を唱え始める。
ミラが目を見張った。
「どういう……!?」
「静かに」
ラースが遮った。
ミラは信じられない思いでラースを見上げた。
最高神以外は神といえども覗けないほど強力な結界の内側に同じものを張っても意味がない。
最高神以外は覗けない。
逆に言えば何重に張ろうと最高神には隠す事が出来ない。
となれば二重にする意味はただ一つ。
これからカイルがする事をミラに見せないようにする為に張っているのだ。
カイルと神殿長のいる辺りが白く霞み始める。
カイルは次第に濃くなっていく靄の向こうにいるミラを見ていた。
が、最後の瞬間カイルは視線を逸らせた。
カイルの姿は完全に見えなくなってしまった。
「もういいんでしょ。説明して」
カイルが見えなくなるなりミラはラースの方を向いた。
「そうだな、どうせ暫くはする事がないからな」
ラースはそう言うとソファに腰を下ろした。
ミラもその隣に座る。
「私がいつも言っている事を覚えているね」
「魔法は想像力だって言うヤツ?」
「そう。聖句というのは魔法で起こす現象を想像させるためにある」
「知ってるわよ」
「なら、もう一つの役割は? 私が君に聖句を教えなかったのは何も面倒だからじゃないんだ」
ミラは黙ってラースを見詰めた。
「聖句は想像力を補うためにある。けれど反面で抑制もしているんだ」
「想像力を?」
「そう。膝丈ほどって言ってる時に天高く聳えるものを想像したりするかい?」
「いないとは言い切れないと思うけど」
「そのために最初に実演して見せるんだ。そうする事で教わった人間は皆同じようなものを出すようになる」
「なんで?」
「魔法を制御出来るのは術者の魔力と良心だけだからね。心理的な制限を掛けてるんだよ」
「でも慣れちゃえば黙ってても使えるでしょ」
「それまでにはもっと沢山の抑制が掛かる。その最たるものが死者の蘇生だ」
ミラの視線は引き付けられるように結界へ向けられた。
「死者を生き返らせる事は出来ない。そう思い込ませる事でやらせないようにしてるんだ」
「でも、出来ないって言われたら逆にやってみたくなる人だっているんじゃない?」
「勿論だ。だから長い年月を掛けて死者を生き返らせる事が出来のは化け物だけだと思い込ませてきた。魔法を使えない人達にもね」
そうだっけ? という表情のミラにラースは思わず溜息を吐いた。
「人間は仲間外れを極端に恐れるものだ。除け者にされる危険を冒してまでやろうとするものは少ない」
「少ない?」
「全く無くすのは無理だから。それに禁止されてなくても相当な魔力がなければ出来ない。私だってそれだけの力は無い」
ミラがガブリエラに目を向けると「ご同様」と言うように肩を竦めた。
「ただ、この手の心理的な抑制というのは固定観念のない子供には利かないんだ」
「子供なら出来るって事?」
「それだけの魔力を持ってる者は滅多にいないし、持っていても制御は難しい。扱えるようにする為の訓練を受ければその過程で『やってはいけない』『出来ない』と教え込まれるわけだし」
不意にミラが目を見張った。
ミラの目には半透明の神殿長が宙を漂いながら結界へと向かっている姿が映っていた。
「見えるのか?」
「うん」
ミラの視線がそのまま結界へと移動するとガブリエラが魔法を解いた。
目隠しの靄が晴れると床に横たわっていた神殿長がカイルの手を借りて起き上がったところだった。
ミラはたった今、透き通って浮いている神殿長を見た。
生き返った神殿長が信じられなくて呆気に取られる。
「手間取っちゃってすみませんでした」
カイルはミラを見ないようにしながら言った。
ラースは知っている。
ガブリエラも。
だがミラはこの事を知ったらどう思うだろう。
ミラの態度がどう変わるかが気になって、なかなか集中出来なかったのだ。
「まさか、わしに使われるとは思わなかったよ」
神殿長が死ぬ前と変わらない様子で言った。
「今あなたに死なれたらカイルを庇える人がいなくなってしまいますから」
「生き返らせるのってラースやガブリエラにも出来ないのよね?」
「わしも出来ん。中央神殿にもいるかどうか」
ミラは神殿長からラース、ガブリエラと視線を移していき、最後にカイルで止まった。
二人の目が合う。
「すっごーい! あんた役立たずじゃなかったのね」
はしゃぎながら力一杯カイルの背を叩いた。
カイルが痛さで顔を顰める。
「君にだけは言われたくなかったよ、その台詞」
「褒めたのよ!」
「どこがだよ!」
そう言いながらも安心して泣きそうになるのを堪えるのがやっとだった。
禁断の魔法を使った事で嫌われるかもしれないと危惧していたのだ。
ラースが結界を解くと神殿長は汚れた聖衣を着替えに行った。
「でもラースはまだ隠してる事があるはずよ」
ミラは今度は誤魔化されるもんか、という決意の表情を浮かべている。
「そうだね。そろそろ話した方が良さそうだ」
ラースはそう言うとカイルとミラを真っ直ぐに見据えた。
「アスラル教の教典とハイラル教の聖典は読んだね」
「はい」
「どっちも無い」
「どっちも!? アスラル教の教典も読んでないの!?」
カイルが驚いてミラを見た。
「そうよ」
「どういうつもりだよ! 神官が教典読んだ事ないなんて!」
「読みたくないからに決まってるでしょ!」
「ズルいぞ!」
「あんたも読みたくないなら読まなきゃ良かったじゃない!」
「そういうわけにはいかないだろ!」
「はい、そこまで」
ラースが二人の間に割って入った。
「喧嘩はしない約束だったはずだが」
「喧嘩じゃないわ、口論よ」
「なら口論も禁止だ」
「じゃあ、お喋り。お喋りも出来ないんじゃ仲良くも出来ないわよね」
どうだ、という表情でミラが言い返した。
「誰だ、ミラにこんな知恵つけたのは」
ラースが思い切り渋い顔でカイルとガブリエラを睨んだ。
「わたしじゃないわよ」
ガブリエラが両手を軽く挙げた。
「元からですよ」
カイルが冷めた口調で答えた。
ミラはバカでは無い。
知識が乏しいだけで頭は回るのだ。
三
「まあいい。とにかく、カイルは薄々気付いてるんだろう」
「何に?」
ミラが首を傾げてカイルを見た。
「アスラル教もハイラル教の一つ……じゃないかと思うんですけど」
「バカ言ってんじゃないわよ。多神教と一神教の違いくらい私にだって分かるわよ」
「教典と聖典読めよ。そうすれば分かるから」
「冗談でしょ」
カイルは思わず溜息を吐いた。
確かにミラとは言い争うだけ無駄だ。
「ハイラルの言っていた事と、アスラル教の教えが似てるんだよ」
カイルが言った。
「ハイラル教の前身であるキルケイス教の正典に入ってる『良い王様』の話が、ハイラル教の聖典に無いっていうのが象徴的だと思わないか?」
「良い王様って神様になろうとしたっていうあれ?」
全く知らないわけではないらしい。
尤も、一般的なお伽話として子供に話す類の伝説だから、そこだけ聞いたのかもしれないが。
昔、良い王様がいた。
善政を敷いて国を治め、全ての国民は幸せに暮らしていた。
しかし周りの国々の政治は腐敗し国民は不幸だった。
王様は他の国の人達も幸せにしようと戦争を起こして周りの国を侵略していった。
他国民を自国民にして救おうとしたのである。
けれど一国の王としてでは自ずと限界がある。
そこで王様は神になりたいと願った。
だが神になりたいという不遜な願いに天罰が下り王様は地獄に落とされた。
「ハイラルは一見宗教活動のような事をしていたが実際は思想家だ。ハイラルがしたかったのは布教活動ではなく困っている人達の救済だ」
それもあの世ではなく、この世を住み易くする事で人々を救おうとしたのだ。
けれど大勢の人に支持されるようになるにつれハイラルを危険視する者が出てきた。
「人を救う事の何が危ないの?」
「ハイラルが訴えていたの不正を正す事だ。他人を搾取する事で利益を得ている人間に取っては邪魔だったんだ。だから処刑されてしまった」
ラースはそこで言葉を切ると改めてカイルとミラを見詰め直した。
「それからだ。ハイラルの教えが慈愛から呪いへと変わったのは」
「呪い?」
「そう。終末思想が出てきたのはハイラルが処刑された後だ。異教徒を悪魔と決め付けて殺すようになったのも」
「それと王様となんの関係があるの?」
ミラが質問すると、ラースは訊ねるようにカイルに顔を向けた。
「ハイラルが神になりたいと願ったんですか?」
実際、今のハイラルは神と同等の扱いを受けている。
「処刑される時、それらしい事を叫んだと言われている。公開処刑だから大勢の人間が聞いていたんだが……目撃証言というのは当てにならないからな。十人いれば十通りの証言が出てくるものだ」
ラースは大昔の、それも隣の大陸で使われていた言葉を呟いた。
神よ。
この世の全てのものを捧げます。
代わりにこの世の全てをお与え下さい。
「神との契約には代償が必要だ。人が神になるにはどれくらいの代償が必要だと思う?」
「異教徒全員の命?」
ミラが訊ねた。
「全ての人間の命だ。終末が訪れればハイラル教徒も死ぬから」
「本当にハイラルはそんな事を望んだんですか?」
「契約自体は確かに存在する」
契約……。
一瞬、鼓動が止まった。
ヘメラでの事が甦る。
「ただハイラル教ではこう教えている」
神よ
私がこの世の全ての罪を償います。
代わりにこの世の人の全ての罪をお許し下さい。
「悪い事した人、許しちゃっていいの?」
「ハイラル教の罪って言うのはそう言う罪とは違うんだよ」
「じゃあ、何?」
「人間は生まれてきた時から罪を背負ってる事になってるんだ」
「なんで?」
カイルは溜息を吐いた。
「さすがにそれは自分で読んで」
「イヤ」
カイルは頭痛がしてきた。
ハイラル教では全ての人間は生まれた時から罪を背負っている。
『原罪』と呼ばれるものだ。
最初の人間が神の教えに背いた罪を子々孫々まで背負わされている。
それがハイラル教の『原罪』でありハイラル教徒になる事で『贖罪』つまり神からの救済を得られるのだ。
「ただ契約をしたのが本当にハイラル本人かどうかまでは分からない」
「本人じゃないってどういう……」
「ねぇ、それ、今の話とどこで繋がるの?」
ミラがじれったそうにカイルの問いを遮った。
カイルが睨んだがミラは知らん顔で明後日の方を向いてしまった。
ラースが苦笑する。
「ミラ、あと少しだから我慢してくれ」
退屈そうなミラと、ラースの子供をあやすような態度。
ミラの指導をしなければならないラースの苦労が忍ばれる。
カイルはラースに同情しながら同じ質問を繰り返した。
「処刑前のハイラルと処刑後のハイラルは別人だという説がある。だから呼び方も違う」
「生前、生後?」
「先在と後在!」
カイルはついキツい声で言ってしまった。
ミラが横目で睨んできたがラースの手前、何も言わなかった。
処刑前を『先在』、処刑後に復活したハイラルを『後在』と呼ぶのだ。
「そう、先在と後在は別人だったのではないかと考える説がある。実際、生き返ったハイラルに会ったエリシャが逃げている」
「エリシャってどのエリシャですか?」
ハイラル教にはエリシャという名の聖人は何人かいる。
最も有名なのがハイラルを産んだ聖母で次が直弟子の聖女エリシャである。
その二人以外のエリシャは聖人と読んで区別している。
「聖女だ。聖女は復活したハイラルと会った後、資料からは姿を消している。後在は女性蔑視が激しかったから聖女は無視されただけ、という可能性もあるが」
ラースはそこで一旦言葉を切った。
「聖女は弟子と言われているが本当は恋人だったんだ。ハイラル教の資料にはほとんど出てこないが二人の間には子供もいた。その子を連れてこの大陸に逃げてきたんだ」
「それでアスラル教を造ったんですか?」
「造った、というか、組織化したんだ。大地母神や自然を神とする信仰自体は文明が出来る前からあったから。ただ村ごとに独立していて横の繋がりがなかったし、神々の名前もそれぞれ違っていた。それを一つの組織にしたのが聖女とその子供だ」
四
聖女は自然信仰をアスラル教として一つにまとめ神官達に厳しい掟を定めた。
信者には特に決まりがないのも、神官には厳しい戒律があるのもハイラルの教えに基づいているのだとすれば辻褄が合う。
先在のハイラルがやろうとしていたのは困っている人に助けの手を差し伸べる事で見返りは求めていない。
アスラル教の神官も頼まれて何かしたとしても報酬は受け取らない。
神官には叶えられないような願いは神に頼む事になるから神への捧げ物は必要だがそれを受け取るのは神であってアスラル教団ではない。
だから神殿の壁画や彫刻が捧げ物になり得るのだ。
そしてもう一つ、ハイラルがしていたのが堕落した神官達の糾弾だった。
アスラル教が神官に厳しい戒律を課しているのもそれ故だろう。
その代わり神官を辞めるのは簡単だ。
辞めた後でなら例え犯罪を犯そうとアスラル教は咎めない。
そういうものの取り締まりは国の管轄になるからだ。
「どうして一つにする必要があったと思う?」
「契約を取り消すためですか?」
「神との契約を撤回する事は出来ない。人間にそれだけの力はない」
「じゃあ、なんで私達が狙われるの?」
「契約はまだ施工されてない――つまり始まってないからだ。ハイラル教徒は契約の施行によりこの世界に神の国が訪れると信じている」
「そう言えばそんなこと言ってたけど……ホントは違うって事?」
「神の国と言っても実際はティルグの事だ。この世界とティルグの間にある壁を消して一つの世界に戻すのが目的なんだ」
ティルグは破壊神でもある光明神が支配する世界だ。
壁が無くなり一つの世界に戻ればこの世界のものは全て破壊される。
向こうの住人にとってどうなのか分からないが、少なくともこちらの世界の人間にとっての理想郷とはほど遠い世界になるはずだ。
「その話と私とどういう関係があるの?」
「君とカイルが契約を遂行する〝約束の子〟なんだよ。聖女はハイラル教が世界を支配するのを阻みたかったんだ」
ハイラル教の終末思想に染まった人間ばかりになれば契約の遂行者が世界の破滅を望んでしまうかもしれない。
アスラル教は約束の子が生まれる土地が終末思想に染まらないように守っているのだ。
約束の子がハイラルの終末思想に染まりさえしなければそれでいいから信者に干渉しないし、アスラル教側も頼まれない限り何もしない。
信者にうるさいことを言うと反発を生んで逆効果になりかねない。
原始的な自然信仰のままなのもそのためだろう。
元々宗教と呼べるようなものではないのだ。
「なんで二人なの? 契約したのがハイラル一人なら遂行者だって一人なんじゃないの?」
「先在が聖女との間に子供を作ったように後在も子供を残したんだろう。預言者の子孫は二系列あるんだよ」
ラースがそう言った時、戸を叩く音がした。
「神殿長が戻られました」
中級神官の言葉にラースは頷いた。
「分かった。続きは執務室でしよう」
考えてみれば四人はまだ神殿長の書斎にいたのである。
「じゃあ、私は隣で待ってる」
隣というの神殿長の書斎の隣ではなく、執務室の隣の部屋である。
来客が来た時のための応接室があるのだ。
「ミラ!」
カイルがミラを止めようとすると、
「いいんだ、カイル」
ラースが制止した。
「なんなら続きは今度にするかい? 元々ミラが言い出した事だし」
カイルの不満げな顔を見たラースが言い添えた。
「いえ……」
言いながらも声が不機嫌になるのは隠せなかった。
ミラは知らん顔でさっさと行ってしまった。
「あの……」
「なんだい?」
「ミラの魔法は教えればもっと伸びるんじゃないかと思うんですけど」
「分かってる。ただ……」
そこまで言った時、新しい聖衣に着替えた神殿長が入ってきた。
カイル達は神殿長に一礼すると執務室へ向かった。
カイル達が執務室に入っていくと神官長が長椅子で休んでいた。
「神官長、侵入者は捕まりましたか?」
「いや。神殿長を殺……重傷を負わせる事が出来る者を中級神官に深追いさせるわけにもいかんからな」
「あの、神殿長を刺したのは僕達を狙ってきた連中ですか?」
神官長の躊躇いが無言の肯定だった。
ラースがカイルの肩に優しく手を置いた。
「アスラル教にだって敵がいないわけじゃない。異教徒というだけで狙われる理由になるんだ」
「まあ、そういう事だ」
神官長はラースに同意すると部屋を出ていった。
「話の続……」
ラースが言い掛けた瞬間、轟音と、耳をつんざくような甲高い鳴き声がして壁と天井が崩れてきた。
「な……!」
咄嗟に障壁を張る。
天井と壁の一部が崩れ青い空が見えた。
空に真っ赤な鳥ともドラゴンともつかないものが浮かんでいた。
ヘデトセス!?
幻獣と呼ばれる魔物だ。
その翼は広げると町の端から端までを太陽から隠してしまうと言われるほど大きい。
鱗の生えた鳥とトカゲの合いの子のような魔物だ。
幻獣と言われるくらいだから当然伝説上の生き物だと思っていた。
ヘデトセスを見たラースが応接室に向かって駆け出す。
カイルも後に続いた。
「ミラ!」
応接室に入るとミラが目を丸くしてヘデトセスを見上げていた。
ラースが聖句を呟く。
ヘデトセスが消えた。
「ミラ、私がいつも言ってる事を覚えているか?」
「魔法は想像」
「もう一つは?」
「室内でものを考えたり想像したりしてはいけない」
「その通り。忘れてたわけじゃないなら今のはわざとか?」
「退屈だったからそれを見てただけよ」
ミラが絵を指した。
絵の中のヘデトセスは今見たやつとそっくりだった。
この絵は実物を見て描いたのか……。
「退屈だったら規則書を読みなさい。神殿の決まりを一つでもいいから覚えてくれ」
ミラは何やら小声で言っていたが反論はしなかった。
そのままどこへともなく行ってしまった。
マイラは唇を噛み締めた。
ようやくラースに近付けたと思ったのに。
ラースの側にいたかったからここへ来たのに。
こんな事なら上級神官の試験など受けなければ良かった。
明日にはタグラへと向かわなければならない。
ミラのせいで……。
ミラさえいなければ……。
そう思った時、向こうからミラが来るのが見えた。
ミラはいつものようにマイラを無視して擦れ違った。
神殿での上下関係は絶対である。
上級神官のミラはマイラを無視する事が出来るが中級神官のマイラはミラに挨拶をしないわけにはいかない。
マイラはミラに頭を下げてから、
「キシャル……様」
ミラに声を掛けた。
ミラはちょっと迷った様子を見せてから振り返った。
「なに?」
カイルとミラへの面会は必ず神殿長かラースを通す事……。
「あなたでなければ倒せない魔物がいると……」
「どこ?」
「ロークの……」
ミラが弾かれたように顔を上げた。
「ありがと!」
ミラが駆け出す。
多分、裏から抜け出してロークへ向かうのだろう。
仮に神殿を追い出されても構わない。
どうせ明日にはタグラへ行くのだ。
ここでなければどこでも同じだ。
神殿じゃなくても……。
マイラは拳を握り締めた。
ミラが神殿の窓を乗り越えようとした時、
「どこに行くんだい?」
聞き覚えのある声に思わず身を竦ませた。
ミラが慌てて振り返る。
「ラース! これは……」
柱の影から出てきたのはウセルだった。
「なんだ。脅かさないでよ」
ウセルに背を向けると再び窓枠に手を掛けた。
「こらこら」
ウセルは苦笑しながらミラを窓から引き離した。
「離してよ」
「お姫様がいなくなったらまた大騒ぎになるだろ」
「私はお姫様じゃないわよ! 魔物が暴れてるの。行かなきゃ」
「君じゃなくてもいいだろ」
「ダメなの。これは私じゃないと」
「今回に限って君じゃなきゃいけない理由は?」
「よく分かんないけど……多分、アイオンと同じヤツだと思う」
「その通り。だからこそ君が行っちゃいけないんだよ。ロークの魔物は俺が倒す」
ウセルはそう言うと神殿の奥に目を向けた。
「俺はこの為に戻ってきたんだ。運命の環を断ち切るためにね」
「運命の……環?」
「そ。運命とか宿命とかってのは嫌いなんだが……自由にしてやるよ。君も坊やも、ガブリエラもラースも……皆」
「ガブリエラも?」
「ああ。早くしてやらないと、あいつ、婚期を逃しちゃうからな」
「ガブリエラと結婚するの?」
意外そうな顔をしたミラの頭にウセルが手を置いた。
優しくミラの頭を撫でる。
「ガブリエラがどっちを選ぶかなんて聞くまでもないだろ。残念だけどな」
「…………」
「じゃ、大人しく待ってろよ」
そう言うとウセルは窓枠に足を掛けた。
「お前は抜け出す必要ないんだから出口から出なさい」
「ラース! いつの間に……」
ウセルが顔を顰めた。
「ミラ。ウセルを裏口に案内してあげなさい」
「いらねーよ」
ウセルは手を振ると窓から飛び降りた。
そのまま振り向きもせずに神殿から遠ざかっていく。
ミラは窓からウセルを見送った。
そしてウセルの姿が見えなくなるとラースの方を振り返った。
自分より優に頭一つは高いラースの顔を見上げる。
「今の、どういう意味?」
「君には君がすべき事があるように、私にもなすべき事があると言う事だよ」
困惑して首を傾げたミラに微笑みかけるとラースは背を向けた。
そのまま執務室へ向かおうとした時、廊下を走る足音が聞こえてきた。
白い聖衣を着た人間が神殿の外へ駆け出していく。
ラースが眉を顰めた。
「あれは、ここの神官じゃない……」
よその神殿の神官は来たという報告は受けていない。
その時、後ろから足音が聞こえてきてミラとラースは振り向いた。
ガブリエラが駆けてくる。
「ラース! 神殿長が襲撃されて……!」
ガブリエラが真っ青な顔で叫んだ。
「カイルは!?」
「今呼びにいかせてる」
ラースは最後まで聞く前に神殿の奥に向かって駆け出した。
ミラとガブリエラも後に続く。
綺麗に整頓された神殿長の書斎。
その部屋の床に神殿長は目を閉じて横たわっていた。
左胸が血で染まっている。
白い床の血溜まりが徐々に広がっていく。
白い聖衣に広がる真紅の染み。
足元に転がる血に濡れた短刀。
既に息絶えているのは一目瞭然だった。
神官長が傍らに膝を突いている。
カイルも既に来ていた。
隣の部屋から中級神官達が不安そうな顔で覗き込んでいる。
「神官長、神殿長は……」
中級神官の一人が訊ねた。
「私達が四人掛かりで回復魔法を掛ければ助かる」
ラースの言葉にミラは弾かれたように顔を上げた。
「ラース……!」
言い掛けたミラを遮るように肩に手が置かれる。
振り返るとガブリエラが目顔で黙っているようにと言っていた。
「神官長は不審者の捜索の指揮をお願いします」
ラースがそう言うと神官長は立ち上がって戸口に向かった。
「彼らは集中する必要がある。お前達は神殿内に不審者がいないか隈なく見て回りなさい」
「はい」
返事をした中級神官達に続いて神官長も部屋を出て扉を閉めた。
二
「ラース、どういう事?」
「今、説明するわ。ちょっと待っててくれる?」
ガブリエラが答えた。
「カイル。やってくれるね」
ラースの言葉にカイルはミラを一瞥してから、
「はい」
カイルは頷いた。
不審そうなミラの前でラースが聖句を唱え始める。
回復魔法ではない。
神の力を借りて結界を張る魔法だ。
神、それも最高神の力を借りて造る何人たりとも覗く事の不可能な強力な結界。
そこまでして隠さなければならない事を今からするのだ。
ラースが結界を張り終えた。
周囲が白いもので囲まれて外が見えなくなった。
続いてガブリエラが同じ聖句を唱え始める。
ミラが目を見張った。
「どういう……!?」
「静かに」
ラースが遮った。
ミラは信じられない思いでラースを見上げた。
最高神以外は神といえども覗けないほど強力な結界の内側に同じものを張っても意味がない。
最高神以外は覗けない。
逆に言えば何重に張ろうと最高神には隠す事が出来ない。
となれば二重にする意味はただ一つ。
これからカイルがする事をミラに見せないようにする為に張っているのだ。
カイルと神殿長のいる辺りが白く霞み始める。
カイルは次第に濃くなっていく靄の向こうにいるミラを見ていた。
が、最後の瞬間カイルは視線を逸らせた。
カイルの姿は完全に見えなくなってしまった。
「もういいんでしょ。説明して」
カイルが見えなくなるなりミラはラースの方を向いた。
「そうだな、どうせ暫くはする事がないからな」
ラースはそう言うとソファに腰を下ろした。
ミラもその隣に座る。
「私がいつも言っている事を覚えているね」
「魔法は想像力だって言うヤツ?」
「そう。聖句というのは魔法で起こす現象を想像させるためにある」
「知ってるわよ」
「なら、もう一つの役割は? 私が君に聖句を教えなかったのは何も面倒だからじゃないんだ」
ミラは黙ってラースを見詰めた。
「聖句は想像力を補うためにある。けれど反面で抑制もしているんだ」
「想像力を?」
「そう。膝丈ほどって言ってる時に天高く聳えるものを想像したりするかい?」
「いないとは言い切れないと思うけど」
「そのために最初に実演して見せるんだ。そうする事で教わった人間は皆同じようなものを出すようになる」
「なんで?」
「魔法を制御出来るのは術者の魔力と良心だけだからね。心理的な制限を掛けてるんだよ」
「でも慣れちゃえば黙ってても使えるでしょ」
「それまでにはもっと沢山の抑制が掛かる。その最たるものが死者の蘇生だ」
ミラの視線は引き付けられるように結界へ向けられた。
「死者を生き返らせる事は出来ない。そう思い込ませる事でやらせないようにしてるんだ」
「でも、出来ないって言われたら逆にやってみたくなる人だっているんじゃない?」
「勿論だ。だから長い年月を掛けて死者を生き返らせる事が出来のは化け物だけだと思い込ませてきた。魔法を使えない人達にもね」
そうだっけ? という表情のミラにラースは思わず溜息を吐いた。
「人間は仲間外れを極端に恐れるものだ。除け者にされる危険を冒してまでやろうとするものは少ない」
「少ない?」
「全く無くすのは無理だから。それに禁止されてなくても相当な魔力がなければ出来ない。私だってそれだけの力は無い」
ミラがガブリエラに目を向けると「ご同様」と言うように肩を竦めた。
「ただ、この手の心理的な抑制というのは固定観念のない子供には利かないんだ」
「子供なら出来るって事?」
「それだけの魔力を持ってる者は滅多にいないし、持っていても制御は難しい。扱えるようにする為の訓練を受ければその過程で『やってはいけない』『出来ない』と教え込まれるわけだし」
不意にミラが目を見張った。
ミラの目には半透明の神殿長が宙を漂いながら結界へと向かっている姿が映っていた。
「見えるのか?」
「うん」
ミラの視線がそのまま結界へと移動するとガブリエラが魔法を解いた。
目隠しの靄が晴れると床に横たわっていた神殿長がカイルの手を借りて起き上がったところだった。
ミラはたった今、透き通って浮いている神殿長を見た。
生き返った神殿長が信じられなくて呆気に取られる。
「手間取っちゃってすみませんでした」
カイルはミラを見ないようにしながら言った。
ラースは知っている。
ガブリエラも。
だがミラはこの事を知ったらどう思うだろう。
ミラの態度がどう変わるかが気になって、なかなか集中出来なかったのだ。
「まさか、わしに使われるとは思わなかったよ」
神殿長が死ぬ前と変わらない様子で言った。
「今あなたに死なれたらカイルを庇える人がいなくなってしまいますから」
「生き返らせるのってラースやガブリエラにも出来ないのよね?」
「わしも出来ん。中央神殿にもいるかどうか」
ミラは神殿長からラース、ガブリエラと視線を移していき、最後にカイルで止まった。
二人の目が合う。
「すっごーい! あんた役立たずじゃなかったのね」
はしゃぎながら力一杯カイルの背を叩いた。
カイルが痛さで顔を顰める。
「君にだけは言われたくなかったよ、その台詞」
「褒めたのよ!」
「どこがだよ!」
そう言いながらも安心して泣きそうになるのを堪えるのがやっとだった。
禁断の魔法を使った事で嫌われるかもしれないと危惧していたのだ。
ラースが結界を解くと神殿長は汚れた聖衣を着替えに行った。
「でもラースはまだ隠してる事があるはずよ」
ミラは今度は誤魔化されるもんか、という決意の表情を浮かべている。
「そうだね。そろそろ話した方が良さそうだ」
ラースはそう言うとカイルとミラを真っ直ぐに見据えた。
「アスラル教の教典とハイラル教の聖典は読んだね」
「はい」
「どっちも無い」
「どっちも!? アスラル教の教典も読んでないの!?」
カイルが驚いてミラを見た。
「そうよ」
「どういうつもりだよ! 神官が教典読んだ事ないなんて!」
「読みたくないからに決まってるでしょ!」
「ズルいぞ!」
「あんたも読みたくないなら読まなきゃ良かったじゃない!」
「そういうわけにはいかないだろ!」
「はい、そこまで」
ラースが二人の間に割って入った。
「喧嘩はしない約束だったはずだが」
「喧嘩じゃないわ、口論よ」
「なら口論も禁止だ」
「じゃあ、お喋り。お喋りも出来ないんじゃ仲良くも出来ないわよね」
どうだ、という表情でミラが言い返した。
「誰だ、ミラにこんな知恵つけたのは」
ラースが思い切り渋い顔でカイルとガブリエラを睨んだ。
「わたしじゃないわよ」
ガブリエラが両手を軽く挙げた。
「元からですよ」
カイルが冷めた口調で答えた。
ミラはバカでは無い。
知識が乏しいだけで頭は回るのだ。
三
「まあいい。とにかく、カイルは薄々気付いてるんだろう」
「何に?」
ミラが首を傾げてカイルを見た。
「アスラル教もハイラル教の一つ……じゃないかと思うんですけど」
「バカ言ってんじゃないわよ。多神教と一神教の違いくらい私にだって分かるわよ」
「教典と聖典読めよ。そうすれば分かるから」
「冗談でしょ」
カイルは思わず溜息を吐いた。
確かにミラとは言い争うだけ無駄だ。
「ハイラルの言っていた事と、アスラル教の教えが似てるんだよ」
カイルが言った。
「ハイラル教の前身であるキルケイス教の正典に入ってる『良い王様』の話が、ハイラル教の聖典に無いっていうのが象徴的だと思わないか?」
「良い王様って神様になろうとしたっていうあれ?」
全く知らないわけではないらしい。
尤も、一般的なお伽話として子供に話す類の伝説だから、そこだけ聞いたのかもしれないが。
昔、良い王様がいた。
善政を敷いて国を治め、全ての国民は幸せに暮らしていた。
しかし周りの国々の政治は腐敗し国民は不幸だった。
王様は他の国の人達も幸せにしようと戦争を起こして周りの国を侵略していった。
他国民を自国民にして救おうとしたのである。
けれど一国の王としてでは自ずと限界がある。
そこで王様は神になりたいと願った。
だが神になりたいという不遜な願いに天罰が下り王様は地獄に落とされた。
「ハイラルは一見宗教活動のような事をしていたが実際は思想家だ。ハイラルがしたかったのは布教活動ではなく困っている人達の救済だ」
それもあの世ではなく、この世を住み易くする事で人々を救おうとしたのだ。
けれど大勢の人に支持されるようになるにつれハイラルを危険視する者が出てきた。
「人を救う事の何が危ないの?」
「ハイラルが訴えていたの不正を正す事だ。他人を搾取する事で利益を得ている人間に取っては邪魔だったんだ。だから処刑されてしまった」
ラースはそこで言葉を切ると改めてカイルとミラを見詰め直した。
「それからだ。ハイラルの教えが慈愛から呪いへと変わったのは」
「呪い?」
「そう。終末思想が出てきたのはハイラルが処刑された後だ。異教徒を悪魔と決め付けて殺すようになったのも」
「それと王様となんの関係があるの?」
ミラが質問すると、ラースは訊ねるようにカイルに顔を向けた。
「ハイラルが神になりたいと願ったんですか?」
実際、今のハイラルは神と同等の扱いを受けている。
「処刑される時、それらしい事を叫んだと言われている。公開処刑だから大勢の人間が聞いていたんだが……目撃証言というのは当てにならないからな。十人いれば十通りの証言が出てくるものだ」
ラースは大昔の、それも隣の大陸で使われていた言葉を呟いた。
神よ。
この世の全てのものを捧げます。
代わりにこの世の全てをお与え下さい。
「神との契約には代償が必要だ。人が神になるにはどれくらいの代償が必要だと思う?」
「異教徒全員の命?」
ミラが訊ねた。
「全ての人間の命だ。終末が訪れればハイラル教徒も死ぬから」
「本当にハイラルはそんな事を望んだんですか?」
「契約自体は確かに存在する」
契約……。
一瞬、鼓動が止まった。
ヘメラでの事が甦る。
「ただハイラル教ではこう教えている」
神よ
私がこの世の全ての罪を償います。
代わりにこの世の人の全ての罪をお許し下さい。
「悪い事した人、許しちゃっていいの?」
「ハイラル教の罪って言うのはそう言う罪とは違うんだよ」
「じゃあ、何?」
「人間は生まれてきた時から罪を背負ってる事になってるんだ」
「なんで?」
カイルは溜息を吐いた。
「さすがにそれは自分で読んで」
「イヤ」
カイルは頭痛がしてきた。
ハイラル教では全ての人間は生まれた時から罪を背負っている。
『原罪』と呼ばれるものだ。
最初の人間が神の教えに背いた罪を子々孫々まで背負わされている。
それがハイラル教の『原罪』でありハイラル教徒になる事で『贖罪』つまり神からの救済を得られるのだ。
「ただ契約をしたのが本当にハイラル本人かどうかまでは分からない」
「本人じゃないってどういう……」
「ねぇ、それ、今の話とどこで繋がるの?」
ミラがじれったそうにカイルの問いを遮った。
カイルが睨んだがミラは知らん顔で明後日の方を向いてしまった。
ラースが苦笑する。
「ミラ、あと少しだから我慢してくれ」
退屈そうなミラと、ラースの子供をあやすような態度。
ミラの指導をしなければならないラースの苦労が忍ばれる。
カイルはラースに同情しながら同じ質問を繰り返した。
「処刑前のハイラルと処刑後のハイラルは別人だという説がある。だから呼び方も違う」
「生前、生後?」
「先在と後在!」
カイルはついキツい声で言ってしまった。
ミラが横目で睨んできたがラースの手前、何も言わなかった。
処刑前を『先在』、処刑後に復活したハイラルを『後在』と呼ぶのだ。
「そう、先在と後在は別人だったのではないかと考える説がある。実際、生き返ったハイラルに会ったエリシャが逃げている」
「エリシャってどのエリシャですか?」
ハイラル教にはエリシャという名の聖人は何人かいる。
最も有名なのがハイラルを産んだ聖母で次が直弟子の聖女エリシャである。
その二人以外のエリシャは聖人と読んで区別している。
「聖女だ。聖女は復活したハイラルと会った後、資料からは姿を消している。後在は女性蔑視が激しかったから聖女は無視されただけ、という可能性もあるが」
ラースはそこで一旦言葉を切った。
「聖女は弟子と言われているが本当は恋人だったんだ。ハイラル教の資料にはほとんど出てこないが二人の間には子供もいた。その子を連れてこの大陸に逃げてきたんだ」
「それでアスラル教を造ったんですか?」
「造った、というか、組織化したんだ。大地母神や自然を神とする信仰自体は文明が出来る前からあったから。ただ村ごとに独立していて横の繋がりがなかったし、神々の名前もそれぞれ違っていた。それを一つの組織にしたのが聖女とその子供だ」
四
聖女は自然信仰をアスラル教として一つにまとめ神官達に厳しい掟を定めた。
信者には特に決まりがないのも、神官には厳しい戒律があるのもハイラルの教えに基づいているのだとすれば辻褄が合う。
先在のハイラルがやろうとしていたのは困っている人に助けの手を差し伸べる事で見返りは求めていない。
アスラル教の神官も頼まれて何かしたとしても報酬は受け取らない。
神官には叶えられないような願いは神に頼む事になるから神への捧げ物は必要だがそれを受け取るのは神であってアスラル教団ではない。
だから神殿の壁画や彫刻が捧げ物になり得るのだ。
そしてもう一つ、ハイラルがしていたのが堕落した神官達の糾弾だった。
アスラル教が神官に厳しい戒律を課しているのもそれ故だろう。
その代わり神官を辞めるのは簡単だ。
辞めた後でなら例え犯罪を犯そうとアスラル教は咎めない。
そういうものの取り締まりは国の管轄になるからだ。
「どうして一つにする必要があったと思う?」
「契約を取り消すためですか?」
「神との契約を撤回する事は出来ない。人間にそれだけの力はない」
「じゃあ、なんで私達が狙われるの?」
「契約はまだ施工されてない――つまり始まってないからだ。ハイラル教徒は契約の施行によりこの世界に神の国が訪れると信じている」
「そう言えばそんなこと言ってたけど……ホントは違うって事?」
「神の国と言っても実際はティルグの事だ。この世界とティルグの間にある壁を消して一つの世界に戻すのが目的なんだ」
ティルグは破壊神でもある光明神が支配する世界だ。
壁が無くなり一つの世界に戻ればこの世界のものは全て破壊される。
向こうの住人にとってどうなのか分からないが、少なくともこちらの世界の人間にとっての理想郷とはほど遠い世界になるはずだ。
「その話と私とどういう関係があるの?」
「君とカイルが契約を遂行する〝約束の子〟なんだよ。聖女はハイラル教が世界を支配するのを阻みたかったんだ」
ハイラル教の終末思想に染まった人間ばかりになれば契約の遂行者が世界の破滅を望んでしまうかもしれない。
アスラル教は約束の子が生まれる土地が終末思想に染まらないように守っているのだ。
約束の子がハイラルの終末思想に染まりさえしなければそれでいいから信者に干渉しないし、アスラル教側も頼まれない限り何もしない。
信者にうるさいことを言うと反発を生んで逆効果になりかねない。
原始的な自然信仰のままなのもそのためだろう。
元々宗教と呼べるようなものではないのだ。
「なんで二人なの? 契約したのがハイラル一人なら遂行者だって一人なんじゃないの?」
「先在が聖女との間に子供を作ったように後在も子供を残したんだろう。預言者の子孫は二系列あるんだよ」
ラースがそう言った時、戸を叩く音がした。
「神殿長が戻られました」
中級神官の言葉にラースは頷いた。
「分かった。続きは執務室でしよう」
考えてみれば四人はまだ神殿長の書斎にいたのである。
「じゃあ、私は隣で待ってる」
隣というの神殿長の書斎の隣ではなく、執務室の隣の部屋である。
来客が来た時のための応接室があるのだ。
「ミラ!」
カイルがミラを止めようとすると、
「いいんだ、カイル」
ラースが制止した。
「なんなら続きは今度にするかい? 元々ミラが言い出した事だし」
カイルの不満げな顔を見たラースが言い添えた。
「いえ……」
言いながらも声が不機嫌になるのは隠せなかった。
ミラは知らん顔でさっさと行ってしまった。
「あの……」
「なんだい?」
「ミラの魔法は教えればもっと伸びるんじゃないかと思うんですけど」
「分かってる。ただ……」
そこまで言った時、新しい聖衣に着替えた神殿長が入ってきた。
カイル達は神殿長に一礼すると執務室へ向かった。
カイル達が執務室に入っていくと神官長が長椅子で休んでいた。
「神官長、侵入者は捕まりましたか?」
「いや。神殿長を殺……重傷を負わせる事が出来る者を中級神官に深追いさせるわけにもいかんからな」
「あの、神殿長を刺したのは僕達を狙ってきた連中ですか?」
神官長の躊躇いが無言の肯定だった。
ラースがカイルの肩に優しく手を置いた。
「アスラル教にだって敵がいないわけじゃない。異教徒というだけで狙われる理由になるんだ」
「まあ、そういう事だ」
神官長はラースに同意すると部屋を出ていった。
「話の続……」
ラースが言い掛けた瞬間、轟音と、耳をつんざくような甲高い鳴き声がして壁と天井が崩れてきた。
「な……!」
咄嗟に障壁を張る。
天井と壁の一部が崩れ青い空が見えた。
空に真っ赤な鳥ともドラゴンともつかないものが浮かんでいた。
ヘデトセス!?
幻獣と呼ばれる魔物だ。
その翼は広げると町の端から端までを太陽から隠してしまうと言われるほど大きい。
鱗の生えた鳥とトカゲの合いの子のような魔物だ。
幻獣と言われるくらいだから当然伝説上の生き物だと思っていた。
ヘデトセスを見たラースが応接室に向かって駆け出す。
カイルも後に続いた。
「ミラ!」
応接室に入るとミラが目を丸くしてヘデトセスを見上げていた。
ラースが聖句を呟く。
ヘデトセスが消えた。
「ミラ、私がいつも言ってる事を覚えているか?」
「魔法は想像」
「もう一つは?」
「室内でものを考えたり想像したりしてはいけない」
「その通り。忘れてたわけじゃないなら今のはわざとか?」
「退屈だったからそれを見てただけよ」
ミラが絵を指した。
絵の中のヘデトセスは今見たやつとそっくりだった。
この絵は実物を見て描いたのか……。
「退屈だったら規則書を読みなさい。神殿の決まりを一つでもいいから覚えてくれ」
ミラは何やら小声で言っていたが反論はしなかった。
そのままどこへともなく行ってしまった。