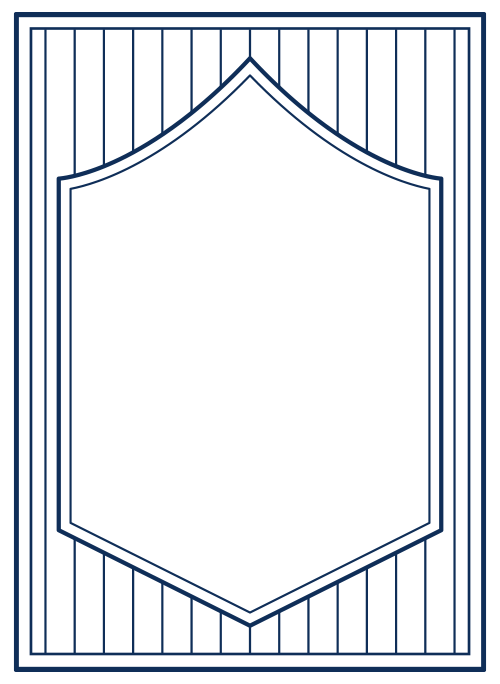一
「理由は分からないけど、ティルグとこちらを遮る壁に亀裂が生じたんだ。それであいつがこちらに来た。起きるはずのない地震は空間の歪みのせいだと思う」
以前ラースが言っていた『空間の振動』とはそれだろう。
裂け目が閉じようとするときに大地が――というより空間が揺れるのだ。
「じゃあ、あいつが消えちゃったのは……」
「さっきの地震で亀裂が閉じちゃったんだろ。一時的にだと思うけど」
向こうの者をこちらに来させない為の壁を無理にこじ開けているに違いない。
基本的には開いてないものだから閉じてしまうのだ。
「そっか」
ミラは納得したように頷いた。
「ね、セルケト教もハイラル教もアスラル教もないところで、ここから一番近いとこってどこ?」
「この大陸の西の果て辺りはもしかしたら……」
「それ、ここからどのくらい?」
「歩いて一年か一年半くらい」
ミラはうんざりしたような顔になった。
「じゃ、ここから一番近い海は?」
「南に十日くらい」
「そこから隣の大陸までは?」
「二十日くらいじゃない?」
「じゃあ、そっちね。行きましょ」
ミラが歩き出す。
「……どこに行くの?」
「隣の大陸に決まってるでしょ。もう上級試験終わってるし、今頃マイラが私の部屋でふんぞり返ってるはずだもん」
「隣の大陸なんて言葉も習慣も、何もかも違うんだぞ」
「なんとかなるわよ」
ミラはカイルの腕を掴んで引っ張っていこうとした。
その手を静かに外す。
「僕は嫌だ」
「殺されるかもしれないんでしょ!」
「君を助けるための囮になってくれたカイルを殺したりはしないよ」
穏やかな声と共にラースが森の中から現れた。
ラースはカイルとミラのぼろぼろの服を見ると眉を顰めた。
「遅くなってしまったようだね。すまなかった」
「ラース! どうしてここに……」
ミラがカイルを庇うように前に立った。
「魔法で僕達の位置を知るくらい、ラースなら簡単だろ」
カイルがそう言うとミラが振り返って睨み付けてきた。
「あんた、それが分かってたからここでぐずぐずしてたのね!」
「当然だろ」
「サッイテー!」
「なんとでも言えよ」
「言うわよ。バカ。間抜け。意地悪。陰険。陰湿、偏屈……」
「そこまで言う事ないだろ!」
「なんとでも言えって言ったじゃない!」
「それなら僕だって言わせてもらうけどな……!」
「よしなさい、カイル」
ラースが穏やかにカイルの肩に手を掛けた。
ミラはカイルに舌を出してみせると先に行ってしまった。
カイルが口を開こうとするとラースの手に力が籠もった。
カイルは不満を隠そうともせずにラースを見上げた。
「女性との口喧嘩はするだけ無駄だ。敵いっこないから止めときなさい」
「ラースが言い負かせない相手がいるとは思えませんけど」
「言い負かされた時より言い負かした時の方が始末が悪いんだ。泣いたり拗ねたり聞こえよがしに嫌みを言い続けたり……」
「経験があるような口振りですけど……」
「私がガブリエラの言う事を聞かされた事はあっても、ガブリエラが私の頼みを聞いてくれた事は無い」
ミラはそのガブリエラと仲がいいのである。
カイルは溜息を吐いた。
「じゃあ、当分、機嫌は直りそうにないですね」
「それはどうかな。帰るまで覚えてられないだろう」
ラースがミラに聞こえないように低い声で言った。
その時、前を歩いていたミラが振り返った。
「ラース、私、どうしても帰らなきゃダメ?」
「他に行く当てがあるのかい」
「マイラ……」
「彼女はタグラへの転属が決まった」
「タグラ?」
「元々ケナイの人間はタグラの神殿に入るものだから。帰ってきてくれるね」
ミラはカイルに目を向けた。
「僕は帰るよ。君も魔術師になるにしても、もう少し魔法が上達してからでも遅くないんじゃない?」
「悪かったわね!」
ミラはカイルを睨み付けた。
レラス神殿に帰ると、ラースが約束した通りカイルもミラもお咎めなしだった。
あれだけ大騒ぎしたのが嘘のようだ。
窓から差し込む朝日が眩しい。
カイルは執務室で資料の整理をしていた。
これでいつも通り……。
そう思った瞬間、扉が乱暴に開かれてミラが入ってきた。
「ミラ、もう少し静かに……」
「ちょっと来て!」
ミラはカイルの腕を掴むと引き摺るようにして歩き出した。
「なんだよ」
「大事な用があるのよ!」
「ミラの『大事』は碌な事が……」
カイルは腕を振り払おうとしたが、
「いいから!」
ミラは離そうとしなかった。
二
白い石に青みがかった影が落ちる廊下を足早に通り過ぎていく。
長い廊下の端まで行くと見覚えのある階段を下り始めた。
「どこ行くの?」
ミラはその問いに行動で答えた。
着いた先はカイルが一度、ミラは抜け穴を何度も作れるくらい入った事のある部屋だった。
ミラはカイルと部屋へ入ると扉を閉めようとした。
「ちょっと待って!」
カイルは慌ててミラの横を擦り抜けると戸を開いた。
「何すんのよ」
「それはこっちの台詞だよ! こんなとこで二人きりになるのはマズいだろ!」
「他の人に聞かれたら困るのよ。二人きりじゃない方がマズいでしょ」
「どうして執務室じゃダメなんだよ」
「いつラースやガブリエラが来るか分からないじゃない」
「これ以上、君の悪巧みに付き合うのはごめんだよ」
「違うわよ!」
「じゃあ何?」
「聞かれたくないんだってば」
ミラがじれったそうに言った。
「二人切りになるのなんてこれが初めてじゃないでしょ! そこ閉めてよ!」
「場所を考えろって言ってんだよ! こんな個室で……」
カイルはベッドを一瞥した。
「執務室だって個室じゃない!」
「なに言って……」
最後まで言う前にようやく思い当たった。
思わずミラを凝視してしまう。
神官というのはあくまで希望者がなるものだ。
少なくともアスラル教は。
子供の頃に神殿に入る者もいるがそれは例外で大抵は早くて十代後半、人によっては人生も後半になり経験も豊富になってから入ってくる者も多い。
ハイラル教などは孤児を神官にする事があるがアスラル教では自立出来るようになるまで面倒を見るだけで神官見習いにはしない。
アスラル教の神官は魔法が使えないとなれないというのもあるが。
アスラル神官は通常の社会で普通の人間関係を経験してきた者達だから当然、神官といえども自由時間はその手の話に花が咲くのだが……。
女性神官達はそういう話をしないのか?
ミラが神殿へ来たのは最近で、カイルよりずっと遅い。
それまで村にいたのだし女性は意外とあけすけな話をすると聞いている。
もっとも神殿に来る前も神官と大して変わりない生活をしていたようだが。
まさか未だに子供は結婚した夫婦が神殿へ行って貰ってくる、なんて話を信じてるんじゃ……。
「早くしてよ」
「とにかく出よう。話なら外で聞くよ」
「なんでここじゃダメなのよ」
「それはラー……ガブリエラに聞いて」
ミラは「もぉ!」とかなんとか言いながら随いてきた。
カイルは神殿の裏口から外へ出た。
神殿から少し離れた場所まで行ったところで立ち止まる。
「ほら、ここなら他の人には聞こえないし、誰もこっそり近付くことは出来ないからいいだろ」
ミラはしばらく不服そうに辺りを見回していた。
それからようやく切り出した。
「マイラのこと聞いた?」
「タグラへ行くって話ならとっくに聞いてただろ」
「それよ」
「どれ?」
「マイラは上級神官になったのよ。おかしいと思わない?」
「何が?」
「上級神官になれたって事は私より上って判断されたんでしょ。なら、なんで私を落としてマイラをここのキシャルにしないの?」
「そうなったら君は出ていくだろ」
「当たり前じゃない。けど、なんでそれがマズいの? おかしくない?」
「君、今まで自分の前任者の事は変だと思ってなかったの?」
「どういう事?」
「君と僕の前任者も中級神官に落とされたわけじゃないんだよ」
「そうなの?」
その問いにカイルはミラが来た時の事を思い出した。
そういえばミラの前任者はミラが来た時には既にいなかった。
だからミラは会ったことがない。
「僕らの前任者は中央神殿へ異動になったんだよ。正確には戻ったんだと思う」
「戻った?」
「うん。多分ずっと前からレラスのキシャルは君って決まってたんだ」
ラースがずっとミラに来るように勧めていたというのはそういう事だろう。
最初から席が用意されていたのだ。
「なんで?」
「そんなの知らないよ」
そう答えるとミラは考え込んでしまった。
その時、
「アンシャル様、キシャル様。セネフィシャル様がお呼びです」
やってきた中級神官が告げた。
「用って何?」
ラースの待っていた執務室へ入るなりミラが口を開いた。
「実は魔物退治に行ってほしいんだ」
ラースは言い辛そうに切り出した。
ミラは待ってましたとばかりに胸を張った。
「任せてよ。簡単に片付けてみせるわ。場所はどこ?」
ラースはすぐには答えずにカイルに目を向けた。
ミラの実力に関しては心配してないらしい。
「ヘメラなんだ」
カイルは目を見張った。
「まさか、あいつですか?」
「いや、関係ない。出たのはシドルだ」
シドルというのは二階建ての家くらいの大きさをした翼の生えた蛙(みたいなヤツ)である。
「知らないとこだけど、案内してくれる人がいるんでしょ」
「カイル、行ってくれるかい?」
「お目付役なんか必要ないわよ!」
「分かってる。シドル退治は君にやってもらう。ただカイルは道を知ってるし……」
「上級神官を道案内だけに使うなんて随分贅沢じゃない」
「向こうがカイルを名指ししてきたんだ」
カイルは思わず息を飲んだ。
ラースが、すまなそうな顔でカイルに向き直った。
「行ってくれるか?」
「はい」
これは仕事だ。
神官の勤めなのだ。
そう自分に言い聞かせても頭に浮かぶのは石をぶつけられた、こめかみの疼きと、あからさまな悪意を向けられた時に感じた胸を抉られるような心の痛みだった。
ラースの顔を見れば心配してくれているのは明らかだった。
とはいえ魔物退治を断る訳にもいかない。
神官の指名くらいなら突っ撥ねる事も可能だろうが。
シドル退治など本来は上級神官が出向くほどではない。
「そうと決まったら早く行きましょ」
ミラはそう言って戸口へ向き掛けた。
「待ちなさい」
「まだなんかあんの?」
「ちゃんと仕度をしてから行きなさい」
ヘメラは朝晩は冷え込むし、ミラは事情を知らないから食事をご馳走になるつもりだ。
報酬は受け取らないとは言っても食事くらい許される。
勿論、本来は無償でやる事だから食事など出さなくても構わない。
正直、食事を出してくれるかどうかは甚だ怪しい。
しかしミラは、
「冗談でしょ。魔物退治すんのよ。食事くらい出してくれるわよ」
と言って弁当を持とうとしなかった。
そのためカイルが二人分持つ羽目になった。
ヘメラへ着いたのは昼頃だった。
村の入り口で一瞬、足が竦んだ。
暴力よりも他人から向けられる悪意が怖かった。
カイルが足を止めた事に気付いたミラが眉を顰めて振り返った。
「どうかしたの?」
カイルが答えようとした時、村長がやってきた。
「よくいらしてくださいました」
村長は卑屈とも言えるほど低姿勢だった。
カイルが治療のためにここへ来てた頃だってこれほどではなかった。
他の家より大きくて手入れが行き届いている村長の家に案内され、応接間で昼食を出された。
ミラがほら見ろ、といわんばかりの表情をカイルに向ける。
それには気付かない振りで料理を食べ始めた。
三
昼食後、二人はシドル退治のため村の出口へと向かっていた。
その時、向こうから歩いてくるのが誰か気付いて思わず足を止める。
向こうも立ち止まると媚びるような笑みを浮かべた。
アリシア……。
どういう顔をすればいいのか分からなくて目を逸らした。
「カイル、久しぶりね。元気だった?」
「……はい」
「魔物退治してくれるんですってね。助かるわ」
その言葉に喉に何かがつかえたような気がした。
何も言えず、ただ下唇を噛んで俯いた。
「期待してるわ。お願いね」
「……はい」
「帰りはうちに寄ってね。前みたいにお茶を用意するから」
それだけ言うとカイルの答えを待たずに行ってしまった。
「今の誰? 綺麗な人じゃない」
ミラが揶揄うようにカイルを肘で突いた。
「アリシアって言ってこの村の薬師なんだ」
「ひょっとして初恋の人とか」
「……うん、憧れてたよ。友達って言える人はアリシアだけだったから」
「友達? そういう感じには見えなかったわよ」
ミラは首を傾げてからカイルの顔を覗き込んできた。
「ここへ来る事が決まってからずっと様子がおかしかったけど、なんかあったの? あんたが魔物を倒したのってここなんでしょ。だったら英雄じゃない。なんでもっと堂々としてないの?」
「気付いてないの?」
「え?」
「僕らはその英雄なのに村長以外誰も出迎えにこなかっただろ。おかしいとは思わなかった?」
「農作業とか……」
言いながら辺りを見回したミラは驚いたような顔で口を噤んだ。
二人に視線を注いでいる無数の瞳に気付いたからだろう。
窓から、戸口の隙間から、物陰から、こちらを見詰めている村人達。
ミラはカイルの袖を掴んで足を早めた。
村から離れるなり立ち止まるとカイルの方を向いた。
「何あれ! どういう事!?」
カイルは昔、魔物を倒した時の経緯を話した。
石をぶつけられた事は伏せて。
「信じらんない! どういう神経してんの!」
「しょうがないよ。アリシアは……」
「誰があんな女の話してるのよ!」
「じゃあ、村の人達?」
「あの村には私の知り合いなんて一人もいないわよ!」
「僕の何が悪いんだよ!」
「なんで怒んないのよ!」
「怒ってどうにかなるわけ? 仕事だよ、これ」
「私達が来る必要なんかなかったでしょ! シドルくらい、ちょっと力のある中級神官が何人かいれば済むもの」
「ごめん。付き合わせちゃって」
「そんなこと言ってんじゃないわよ!」
ミラは怒ったように言うと山に向かって歩きだした。
ミラは倒木を見付けると疲れたように座り込んだ。
「ちょっとぉ! どうして魔物退治っていつもこうなわけ?」
「え?」
少し先を行っていたカイルは立ち止まって振り返った。
「村が襲われるんなら、あの家で待ってた方が良かったんじゃない?」
「村には来てないよ。壊れてる家なんか無かっただろ」
「ならシドルに豊作にしてくれるように頼めば良いじゃない」
「関係ない旅人が犠牲になっちゃうんだぞ」
おそらくシドルは人を襲うだけで豊作にしたりというような事はしないか出来ないのだろう。
そもそも豊作にしてくれる魔物というのも初耳だったし、その後も聞いた事がない。
あれは特別だったのだ。
ミラは座り込んだまま動かない。
カイルは溜息を吐いて倒木の折れたところに目を止めた。
樹の裂け目が真新しい。
「ミラ」
「なによ」
「近いよ。油断しないで」
言い終わる前に何かが飛んできた。
とっさにミラを押し倒しながら障壁を張った。
二人がもつれ合って地面に転がる。
金属質の輝きを放つ巨大な棘のようなものが立て続けに障壁に当たって跳ね返された。
カイルは眉を顰めた。
シドルがこんなの飛ばすなんて聞いてない……。
樹が倒れる音が近付いてくる。
が、本体は樹々に遮られて見えない。
にも関わらず視線を感じて空を見上げた。
梢の上から三つの目がこちらを見下ろしてきた。
シドルじゃない!
これはローゲスダスだ。
首が背の高い樹よりも更に長い、身体中棘だらけの蛙みたいな魔物である。
身体に生えている棘を飛ばして敵を攻撃するのだ。
「出たわね! 一発で片付けるわよ」
その言葉にカイルは慌てて、
「森の中で火炎系はダメだってば!」
と制止した。
「分かったわよ」
空が光ったかと思うと幾筋もの稲妻が大地に突き刺さった。
ローゲスダスが雷に斬り裂かれる。
一瞬遅れで大気を引き裂く轟音が圧力のように押し寄せてきた。
空気と共鳴して大地までが振動している。
カイルは耳を塞ぎながら障壁の強度を高めた。
二人の周りに雷に貫かれた樹が倒れてくる。
ったく、後先考えないんだから……。
最後に千切れたローゲスダスの首が障壁にぶつかって二人の脇に転がった。
ミラは胸を張って何か言った。
しかし、さっきの雷鳴のせいでまだ聴力が回復していなかった。
ミラも気付いたらしく口を噤んだ。
が、すぐにカイルが未だに張ったままの障壁を手で叩きながら口を動かした。
「障壁を消せ」
とでも言っているのだろう。
カイルは黙って首を振った。
ミラが怒ったように何か言った。
ようやく少しだけ聞き取れるようになった。
どうしてよ、とかなんとか言ったらしい。
「今のはシドルじゃないよ。あれはローゲスダスだ」
「名前間違えただけでしょ。魔物の名前を知ってる人なんてそう多くないわよ」
それはそうなのだが……。
不意に風を切る音が聞こえた。
と、思った時、障壁に何かが弾かれた。
ミラが樹々を倒して歩きやすくなったところから今度こそシドルが姿を現した。
「何匹来たって同じよ」
「悪いけど、今のと同じのはやめて」
「ならどうすんのよ」
「水で出来たすっごく大きい竜巻、想像してみて」
ミラは静かに目を閉じた。
近くに川でもあったのだろう。
樹々の向こうで水が巻き上がり、カイル達の方へと向かってきた。
四
「自分を攻撃してどうすんだよ! 敵はあっちだろ!」
「見えないのよ!」
「目を瞑れとは言ってないぞ!」
ミラは目を開けると真っ先にカイルを睨んだ。
水柱が消えた。
かと思うとシドルの前に現れた。
渦巻く水がシドルを巻き込んで空へと舞い上がる。
「あ、終わらせる時は周りに水撒いて」
カイルが言った。
まさかとは思うがさっき雷を受けて倒れた樹が山火事の原因になったりしたら目も当てられない。
ミラは言われたとおり攻撃を終えると水を辺りに散らした。
水流が収まった途端シドルの叫び声が聞こえてきた。
右の翼はちぎれ、左もぼろぼろだった。
しかし身体中から血を流してはいるもののどれも軽傷ばかりである。
「それなら……!」
辺りに風の唸る音が満ち、目に見えない無数の刃がシドルを襲った。
雷と水の攻撃にかろうじて耐え残った大木が細切れになって辺りに散らばる。
けれどシドルには効いていなかった。
たまに、まぐれで攻撃が傷に当たったときだけ吠える程度だった。
ミラが目を見張って攻撃を止めた。
シドルが今度は自分の番とばかりにこちらに舌を伸ばしてくる。
カイルの障壁に弾かれてはいるが間近で見るシドルの舌はなかなか気持ち悪かった。
「ちょっと、シドルって魔法耐性あった?」
「無いよ。君がさっき言ったろ。中級神官でなんとかなる程度だって。これは特別だよ」
「どうすんのよ」
カイルはしばし考え込んだ。
小さな突起が無数に付いている舌が障壁にぶつかる度に水袋を叩き付けたような音がして不快感を煽る。
考えあぐねている時、いきなりシドルが弾けた。
文字どおり、内側から爆発でもしたように粉々になって辺りに四散したのである。
辺りに飛び散った肉塊はかなり気持ちが悪かった。
「ーーーーー!」
ミラが声にならない悲鳴を上げてカイルに抱き付いてきた。
柔らかいミラの身体の感触にカイルの方が動転して真っ赤になった。
「ちょ、ちょっと、ミラ」
「気持ち悪い~!」
「ミラ、離せよ!」
カイルが慌ててミラを離そうとした時、
「いくら倒しても無駄だ」
聞き覚えのある冷たい声にカイルとミラが同時に振り返る。
いつの間にか背後に自称天使シーアスが立っていた。
カイルはミラが身体を強ばらせた隙に強引に押し退けた。
が、ミラはカイルの背に隠れるようにしながら身体を押し付けてくる。
「無駄って言うのはどういう事だ」
ミラを気にしないようにしながらシーアスに訊ねた。
「ここは三ヶ月前お前が封印を解いた場所だ」
目印のない山の中である。
正確な場所など覚えてなかったが黙っていた。
「封印って封印獣と関係があるのか?」
「あれは封印であり鍵でもあった」
シーアスはカイルの質問に答えず続けた。
「封印獣が向こうとこちらの通路を塞いでたんだ。それをお前が開いてくれたお陰で千年ぶりにこっちに来られたよ」
「教えてくれるなんて随分親切じゃないか」
「彼女にはね」
ミラがカイルに更に密着してきた。
カイルが肩を竦める。
「ミラ、地震」
ミラはすぐに意味を悟った。
次の瞬間、突き上げるような震動が襲ってきた。
カイルとミラが地面に投げ出される。
二人は倒れたまま地面にしがみつく。
シーアスが顔を顰めた。
「まだ子供だからって舐めてたようだな」
言い終える前に姿が消えていた。
「もう止めていい?」
「うん、大丈夫だと思う」
地震が止み、安堵の息を吐いた時、
「こんなのは一時しのぎだ」
シーアスの声が響いてきた。
ミラが慌ててカイルにしがみつく。
カイルはそれを強引に引き離した。
「もう大丈夫だよ」
「また会えるのを楽しみにしてるよ」
最後の台詞はミラに向けられたものだ。
ミラの顔が引き攣る。
ミラを怖がらせられるなんて一体どんな事をしたのか気になるが、まずはここを離れる事にした。
たまたま二人のいたところが街道の近くだったこともあり、村に寄らずに帰る事にした。
「村長に何か言わなくていいの?」
「お礼を貰えるわけじゃないし、僕らが報告するのはラースの方だろ」
ミラもカイルの話を聞いて以来ヘメラにはあまりいい印象を持ってないらしく異議はないようだった。
マイラは神殿の廊下を歩いていた。
廊下の端で言い争う声が聞こえる。
見ると居住区への入り口のところで男が下級神官に食い下がっていた。
「どうかしたの?」
下級神官の困りきった様子にマイラは声をかけた。
「マイラ様」
「マイラ? ミラじゃないのか。ミラって人に会わせてくれ」
「ミラ……」
マイラは名前を呼び捨てにしかけて下級神官に気付いた。
「キシャル様に何か?」
声がキツくなるのまでは抑えられなかった。
カイルとミラがハイラル教徒に攫われて以来、二人への面会の取り次ぎは必ず神殿長かラースに報告するようにと言う厳命が下っている。
「化け物が出て困ってるんだよ」
「それなら私が……」
「ミラかカイルが来れば大人しくなるって言われたんだ。その二人じゃないとダメだって」
「魔物のいる場所は?」
「ロークだよ。ロークの山に……」
「分かりました。伝えておきます」
マイラはそう言うと背を向けた。
「早くしてくれないと……」
男の声が遠ざかる。
ミラ……。
いつだってミラは特別扱いだった。
ケナイの村長も周囲の村の人達も。
マイラの家族でさえマイラよりミラを大事にしていて自分は蔑ろにされていた。
ラースも同じだ。
確かにマイラに魔法の才能があるのを見出してくれたのはラースだった。
村に来る度に魔法を教えてくれたのも。
けれどラースの目当てはあくまでミラだった。
マイラに会いに来てくれた事は一度も無い。
神官になるように勧めてくれた事も。
しかしミラは村から出してもらえなかった。
マイラはレラス神殿に入りやっとの思いで中級神官になったと思ったらラースがミラを連れてきた。
ケナイの人達の話では、ラースはミラを捕まえに来た警備兵に対して脅迫まがいの事まで言って助けたという。
そしてミラはここであっさり上級神官になってしまった。
マイラの方はと言えば、ようやく昇格試験の申請が通ったと思ったらタグラで受けるように言われた。
その時はミラとカイルが行方不明だったからだと思っていた。
試験は上の階級の神官との対決だから相手がいなければ出来ないからだ。
タグラで試験を受けて合格し「やっとミラを追い越した」「ようやくミラに勝った」そう思った。
だがマイラはタグラの上級神官になったと告げられた。
ミラを中級神官に落とさない為なのは聞くまでもない。
元々マイラは替え玉だったのだ。
マイラが偽物だと言う事も、本物がミラだという事もバレてしまった。
カイルやガブリエラに勝てるだけの実力はないしミラは落とされないとなればレラスの上級神官の座に空きはない。
「理由は分からないけど、ティルグとこちらを遮る壁に亀裂が生じたんだ。それであいつがこちらに来た。起きるはずのない地震は空間の歪みのせいだと思う」
以前ラースが言っていた『空間の振動』とはそれだろう。
裂け目が閉じようとするときに大地が――というより空間が揺れるのだ。
「じゃあ、あいつが消えちゃったのは……」
「さっきの地震で亀裂が閉じちゃったんだろ。一時的にだと思うけど」
向こうの者をこちらに来させない為の壁を無理にこじ開けているに違いない。
基本的には開いてないものだから閉じてしまうのだ。
「そっか」
ミラは納得したように頷いた。
「ね、セルケト教もハイラル教もアスラル教もないところで、ここから一番近いとこってどこ?」
「この大陸の西の果て辺りはもしかしたら……」
「それ、ここからどのくらい?」
「歩いて一年か一年半くらい」
ミラはうんざりしたような顔になった。
「じゃ、ここから一番近い海は?」
「南に十日くらい」
「そこから隣の大陸までは?」
「二十日くらいじゃない?」
「じゃあ、そっちね。行きましょ」
ミラが歩き出す。
「……どこに行くの?」
「隣の大陸に決まってるでしょ。もう上級試験終わってるし、今頃マイラが私の部屋でふんぞり返ってるはずだもん」
「隣の大陸なんて言葉も習慣も、何もかも違うんだぞ」
「なんとかなるわよ」
ミラはカイルの腕を掴んで引っ張っていこうとした。
その手を静かに外す。
「僕は嫌だ」
「殺されるかもしれないんでしょ!」
「君を助けるための囮になってくれたカイルを殺したりはしないよ」
穏やかな声と共にラースが森の中から現れた。
ラースはカイルとミラのぼろぼろの服を見ると眉を顰めた。
「遅くなってしまったようだね。すまなかった」
「ラース! どうしてここに……」
ミラがカイルを庇うように前に立った。
「魔法で僕達の位置を知るくらい、ラースなら簡単だろ」
カイルがそう言うとミラが振り返って睨み付けてきた。
「あんた、それが分かってたからここでぐずぐずしてたのね!」
「当然だろ」
「サッイテー!」
「なんとでも言えよ」
「言うわよ。バカ。間抜け。意地悪。陰険。陰湿、偏屈……」
「そこまで言う事ないだろ!」
「なんとでも言えって言ったじゃない!」
「それなら僕だって言わせてもらうけどな……!」
「よしなさい、カイル」
ラースが穏やかにカイルの肩に手を掛けた。
ミラはカイルに舌を出してみせると先に行ってしまった。
カイルが口を開こうとするとラースの手に力が籠もった。
カイルは不満を隠そうともせずにラースを見上げた。
「女性との口喧嘩はするだけ無駄だ。敵いっこないから止めときなさい」
「ラースが言い負かせない相手がいるとは思えませんけど」
「言い負かされた時より言い負かした時の方が始末が悪いんだ。泣いたり拗ねたり聞こえよがしに嫌みを言い続けたり……」
「経験があるような口振りですけど……」
「私がガブリエラの言う事を聞かされた事はあっても、ガブリエラが私の頼みを聞いてくれた事は無い」
ミラはそのガブリエラと仲がいいのである。
カイルは溜息を吐いた。
「じゃあ、当分、機嫌は直りそうにないですね」
「それはどうかな。帰るまで覚えてられないだろう」
ラースがミラに聞こえないように低い声で言った。
その時、前を歩いていたミラが振り返った。
「ラース、私、どうしても帰らなきゃダメ?」
「他に行く当てがあるのかい」
「マイラ……」
「彼女はタグラへの転属が決まった」
「タグラ?」
「元々ケナイの人間はタグラの神殿に入るものだから。帰ってきてくれるね」
ミラはカイルに目を向けた。
「僕は帰るよ。君も魔術師になるにしても、もう少し魔法が上達してからでも遅くないんじゃない?」
「悪かったわね!」
ミラはカイルを睨み付けた。
レラス神殿に帰ると、ラースが約束した通りカイルもミラもお咎めなしだった。
あれだけ大騒ぎしたのが嘘のようだ。
窓から差し込む朝日が眩しい。
カイルは執務室で資料の整理をしていた。
これでいつも通り……。
そう思った瞬間、扉が乱暴に開かれてミラが入ってきた。
「ミラ、もう少し静かに……」
「ちょっと来て!」
ミラはカイルの腕を掴むと引き摺るようにして歩き出した。
「なんだよ」
「大事な用があるのよ!」
「ミラの『大事』は碌な事が……」
カイルは腕を振り払おうとしたが、
「いいから!」
ミラは離そうとしなかった。
二
白い石に青みがかった影が落ちる廊下を足早に通り過ぎていく。
長い廊下の端まで行くと見覚えのある階段を下り始めた。
「どこ行くの?」
ミラはその問いに行動で答えた。
着いた先はカイルが一度、ミラは抜け穴を何度も作れるくらい入った事のある部屋だった。
ミラはカイルと部屋へ入ると扉を閉めようとした。
「ちょっと待って!」
カイルは慌ててミラの横を擦り抜けると戸を開いた。
「何すんのよ」
「それはこっちの台詞だよ! こんなとこで二人きりになるのはマズいだろ!」
「他の人に聞かれたら困るのよ。二人きりじゃない方がマズいでしょ」
「どうして執務室じゃダメなんだよ」
「いつラースやガブリエラが来るか分からないじゃない」
「これ以上、君の悪巧みに付き合うのはごめんだよ」
「違うわよ!」
「じゃあ何?」
「聞かれたくないんだってば」
ミラがじれったそうに言った。
「二人切りになるのなんてこれが初めてじゃないでしょ! そこ閉めてよ!」
「場所を考えろって言ってんだよ! こんな個室で……」
カイルはベッドを一瞥した。
「執務室だって個室じゃない!」
「なに言って……」
最後まで言う前にようやく思い当たった。
思わずミラを凝視してしまう。
神官というのはあくまで希望者がなるものだ。
少なくともアスラル教は。
子供の頃に神殿に入る者もいるがそれは例外で大抵は早くて十代後半、人によっては人生も後半になり経験も豊富になってから入ってくる者も多い。
ハイラル教などは孤児を神官にする事があるがアスラル教では自立出来るようになるまで面倒を見るだけで神官見習いにはしない。
アスラル教の神官は魔法が使えないとなれないというのもあるが。
アスラル神官は通常の社会で普通の人間関係を経験してきた者達だから当然、神官といえども自由時間はその手の話に花が咲くのだが……。
女性神官達はそういう話をしないのか?
ミラが神殿へ来たのは最近で、カイルよりずっと遅い。
それまで村にいたのだし女性は意外とあけすけな話をすると聞いている。
もっとも神殿に来る前も神官と大して変わりない生活をしていたようだが。
まさか未だに子供は結婚した夫婦が神殿へ行って貰ってくる、なんて話を信じてるんじゃ……。
「早くしてよ」
「とにかく出よう。話なら外で聞くよ」
「なんでここじゃダメなのよ」
「それはラー……ガブリエラに聞いて」
ミラは「もぉ!」とかなんとか言いながら随いてきた。
カイルは神殿の裏口から外へ出た。
神殿から少し離れた場所まで行ったところで立ち止まる。
「ほら、ここなら他の人には聞こえないし、誰もこっそり近付くことは出来ないからいいだろ」
ミラはしばらく不服そうに辺りを見回していた。
それからようやく切り出した。
「マイラのこと聞いた?」
「タグラへ行くって話ならとっくに聞いてただろ」
「それよ」
「どれ?」
「マイラは上級神官になったのよ。おかしいと思わない?」
「何が?」
「上級神官になれたって事は私より上って判断されたんでしょ。なら、なんで私を落としてマイラをここのキシャルにしないの?」
「そうなったら君は出ていくだろ」
「当たり前じゃない。けど、なんでそれがマズいの? おかしくない?」
「君、今まで自分の前任者の事は変だと思ってなかったの?」
「どういう事?」
「君と僕の前任者も中級神官に落とされたわけじゃないんだよ」
「そうなの?」
その問いにカイルはミラが来た時の事を思い出した。
そういえばミラの前任者はミラが来た時には既にいなかった。
だからミラは会ったことがない。
「僕らの前任者は中央神殿へ異動になったんだよ。正確には戻ったんだと思う」
「戻った?」
「うん。多分ずっと前からレラスのキシャルは君って決まってたんだ」
ラースがずっとミラに来るように勧めていたというのはそういう事だろう。
最初から席が用意されていたのだ。
「なんで?」
「そんなの知らないよ」
そう答えるとミラは考え込んでしまった。
その時、
「アンシャル様、キシャル様。セネフィシャル様がお呼びです」
やってきた中級神官が告げた。
「用って何?」
ラースの待っていた執務室へ入るなりミラが口を開いた。
「実は魔物退治に行ってほしいんだ」
ラースは言い辛そうに切り出した。
ミラは待ってましたとばかりに胸を張った。
「任せてよ。簡単に片付けてみせるわ。場所はどこ?」
ラースはすぐには答えずにカイルに目を向けた。
ミラの実力に関しては心配してないらしい。
「ヘメラなんだ」
カイルは目を見張った。
「まさか、あいつですか?」
「いや、関係ない。出たのはシドルだ」
シドルというのは二階建ての家くらいの大きさをした翼の生えた蛙(みたいなヤツ)である。
「知らないとこだけど、案内してくれる人がいるんでしょ」
「カイル、行ってくれるかい?」
「お目付役なんか必要ないわよ!」
「分かってる。シドル退治は君にやってもらう。ただカイルは道を知ってるし……」
「上級神官を道案内だけに使うなんて随分贅沢じゃない」
「向こうがカイルを名指ししてきたんだ」
カイルは思わず息を飲んだ。
ラースが、すまなそうな顔でカイルに向き直った。
「行ってくれるか?」
「はい」
これは仕事だ。
神官の勤めなのだ。
そう自分に言い聞かせても頭に浮かぶのは石をぶつけられた、こめかみの疼きと、あからさまな悪意を向けられた時に感じた胸を抉られるような心の痛みだった。
ラースの顔を見れば心配してくれているのは明らかだった。
とはいえ魔物退治を断る訳にもいかない。
神官の指名くらいなら突っ撥ねる事も可能だろうが。
シドル退治など本来は上級神官が出向くほどではない。
「そうと決まったら早く行きましょ」
ミラはそう言って戸口へ向き掛けた。
「待ちなさい」
「まだなんかあんの?」
「ちゃんと仕度をしてから行きなさい」
ヘメラは朝晩は冷え込むし、ミラは事情を知らないから食事をご馳走になるつもりだ。
報酬は受け取らないとは言っても食事くらい許される。
勿論、本来は無償でやる事だから食事など出さなくても構わない。
正直、食事を出してくれるかどうかは甚だ怪しい。
しかしミラは、
「冗談でしょ。魔物退治すんのよ。食事くらい出してくれるわよ」
と言って弁当を持とうとしなかった。
そのためカイルが二人分持つ羽目になった。
ヘメラへ着いたのは昼頃だった。
村の入り口で一瞬、足が竦んだ。
暴力よりも他人から向けられる悪意が怖かった。
カイルが足を止めた事に気付いたミラが眉を顰めて振り返った。
「どうかしたの?」
カイルが答えようとした時、村長がやってきた。
「よくいらしてくださいました」
村長は卑屈とも言えるほど低姿勢だった。
カイルが治療のためにここへ来てた頃だってこれほどではなかった。
他の家より大きくて手入れが行き届いている村長の家に案内され、応接間で昼食を出された。
ミラがほら見ろ、といわんばかりの表情をカイルに向ける。
それには気付かない振りで料理を食べ始めた。
三
昼食後、二人はシドル退治のため村の出口へと向かっていた。
その時、向こうから歩いてくるのが誰か気付いて思わず足を止める。
向こうも立ち止まると媚びるような笑みを浮かべた。
アリシア……。
どういう顔をすればいいのか分からなくて目を逸らした。
「カイル、久しぶりね。元気だった?」
「……はい」
「魔物退治してくれるんですってね。助かるわ」
その言葉に喉に何かがつかえたような気がした。
何も言えず、ただ下唇を噛んで俯いた。
「期待してるわ。お願いね」
「……はい」
「帰りはうちに寄ってね。前みたいにお茶を用意するから」
それだけ言うとカイルの答えを待たずに行ってしまった。
「今の誰? 綺麗な人じゃない」
ミラが揶揄うようにカイルを肘で突いた。
「アリシアって言ってこの村の薬師なんだ」
「ひょっとして初恋の人とか」
「……うん、憧れてたよ。友達って言える人はアリシアだけだったから」
「友達? そういう感じには見えなかったわよ」
ミラは首を傾げてからカイルの顔を覗き込んできた。
「ここへ来る事が決まってからずっと様子がおかしかったけど、なんかあったの? あんたが魔物を倒したのってここなんでしょ。だったら英雄じゃない。なんでもっと堂々としてないの?」
「気付いてないの?」
「え?」
「僕らはその英雄なのに村長以外誰も出迎えにこなかっただろ。おかしいとは思わなかった?」
「農作業とか……」
言いながら辺りを見回したミラは驚いたような顔で口を噤んだ。
二人に視線を注いでいる無数の瞳に気付いたからだろう。
窓から、戸口の隙間から、物陰から、こちらを見詰めている村人達。
ミラはカイルの袖を掴んで足を早めた。
村から離れるなり立ち止まるとカイルの方を向いた。
「何あれ! どういう事!?」
カイルは昔、魔物を倒した時の経緯を話した。
石をぶつけられた事は伏せて。
「信じらんない! どういう神経してんの!」
「しょうがないよ。アリシアは……」
「誰があんな女の話してるのよ!」
「じゃあ、村の人達?」
「あの村には私の知り合いなんて一人もいないわよ!」
「僕の何が悪いんだよ!」
「なんで怒んないのよ!」
「怒ってどうにかなるわけ? 仕事だよ、これ」
「私達が来る必要なんかなかったでしょ! シドルくらい、ちょっと力のある中級神官が何人かいれば済むもの」
「ごめん。付き合わせちゃって」
「そんなこと言ってんじゃないわよ!」
ミラは怒ったように言うと山に向かって歩きだした。
ミラは倒木を見付けると疲れたように座り込んだ。
「ちょっとぉ! どうして魔物退治っていつもこうなわけ?」
「え?」
少し先を行っていたカイルは立ち止まって振り返った。
「村が襲われるんなら、あの家で待ってた方が良かったんじゃない?」
「村には来てないよ。壊れてる家なんか無かっただろ」
「ならシドルに豊作にしてくれるように頼めば良いじゃない」
「関係ない旅人が犠牲になっちゃうんだぞ」
おそらくシドルは人を襲うだけで豊作にしたりというような事はしないか出来ないのだろう。
そもそも豊作にしてくれる魔物というのも初耳だったし、その後も聞いた事がない。
あれは特別だったのだ。
ミラは座り込んだまま動かない。
カイルは溜息を吐いて倒木の折れたところに目を止めた。
樹の裂け目が真新しい。
「ミラ」
「なによ」
「近いよ。油断しないで」
言い終わる前に何かが飛んできた。
とっさにミラを押し倒しながら障壁を張った。
二人がもつれ合って地面に転がる。
金属質の輝きを放つ巨大な棘のようなものが立て続けに障壁に当たって跳ね返された。
カイルは眉を顰めた。
シドルがこんなの飛ばすなんて聞いてない……。
樹が倒れる音が近付いてくる。
が、本体は樹々に遮られて見えない。
にも関わらず視線を感じて空を見上げた。
梢の上から三つの目がこちらを見下ろしてきた。
シドルじゃない!
これはローゲスダスだ。
首が背の高い樹よりも更に長い、身体中棘だらけの蛙みたいな魔物である。
身体に生えている棘を飛ばして敵を攻撃するのだ。
「出たわね! 一発で片付けるわよ」
その言葉にカイルは慌てて、
「森の中で火炎系はダメだってば!」
と制止した。
「分かったわよ」
空が光ったかと思うと幾筋もの稲妻が大地に突き刺さった。
ローゲスダスが雷に斬り裂かれる。
一瞬遅れで大気を引き裂く轟音が圧力のように押し寄せてきた。
空気と共鳴して大地までが振動している。
カイルは耳を塞ぎながら障壁の強度を高めた。
二人の周りに雷に貫かれた樹が倒れてくる。
ったく、後先考えないんだから……。
最後に千切れたローゲスダスの首が障壁にぶつかって二人の脇に転がった。
ミラは胸を張って何か言った。
しかし、さっきの雷鳴のせいでまだ聴力が回復していなかった。
ミラも気付いたらしく口を噤んだ。
が、すぐにカイルが未だに張ったままの障壁を手で叩きながら口を動かした。
「障壁を消せ」
とでも言っているのだろう。
カイルは黙って首を振った。
ミラが怒ったように何か言った。
ようやく少しだけ聞き取れるようになった。
どうしてよ、とかなんとか言ったらしい。
「今のはシドルじゃないよ。あれはローゲスダスだ」
「名前間違えただけでしょ。魔物の名前を知ってる人なんてそう多くないわよ」
それはそうなのだが……。
不意に風を切る音が聞こえた。
と、思った時、障壁に何かが弾かれた。
ミラが樹々を倒して歩きやすくなったところから今度こそシドルが姿を現した。
「何匹来たって同じよ」
「悪いけど、今のと同じのはやめて」
「ならどうすんのよ」
「水で出来たすっごく大きい竜巻、想像してみて」
ミラは静かに目を閉じた。
近くに川でもあったのだろう。
樹々の向こうで水が巻き上がり、カイル達の方へと向かってきた。
四
「自分を攻撃してどうすんだよ! 敵はあっちだろ!」
「見えないのよ!」
「目を瞑れとは言ってないぞ!」
ミラは目を開けると真っ先にカイルを睨んだ。
水柱が消えた。
かと思うとシドルの前に現れた。
渦巻く水がシドルを巻き込んで空へと舞い上がる。
「あ、終わらせる時は周りに水撒いて」
カイルが言った。
まさかとは思うがさっき雷を受けて倒れた樹が山火事の原因になったりしたら目も当てられない。
ミラは言われたとおり攻撃を終えると水を辺りに散らした。
水流が収まった途端シドルの叫び声が聞こえてきた。
右の翼はちぎれ、左もぼろぼろだった。
しかし身体中から血を流してはいるもののどれも軽傷ばかりである。
「それなら……!」
辺りに風の唸る音が満ち、目に見えない無数の刃がシドルを襲った。
雷と水の攻撃にかろうじて耐え残った大木が細切れになって辺りに散らばる。
けれどシドルには効いていなかった。
たまに、まぐれで攻撃が傷に当たったときだけ吠える程度だった。
ミラが目を見張って攻撃を止めた。
シドルが今度は自分の番とばかりにこちらに舌を伸ばしてくる。
カイルの障壁に弾かれてはいるが間近で見るシドルの舌はなかなか気持ち悪かった。
「ちょっと、シドルって魔法耐性あった?」
「無いよ。君がさっき言ったろ。中級神官でなんとかなる程度だって。これは特別だよ」
「どうすんのよ」
カイルはしばし考え込んだ。
小さな突起が無数に付いている舌が障壁にぶつかる度に水袋を叩き付けたような音がして不快感を煽る。
考えあぐねている時、いきなりシドルが弾けた。
文字どおり、内側から爆発でもしたように粉々になって辺りに四散したのである。
辺りに飛び散った肉塊はかなり気持ちが悪かった。
「ーーーーー!」
ミラが声にならない悲鳴を上げてカイルに抱き付いてきた。
柔らかいミラの身体の感触にカイルの方が動転して真っ赤になった。
「ちょ、ちょっと、ミラ」
「気持ち悪い~!」
「ミラ、離せよ!」
カイルが慌ててミラを離そうとした時、
「いくら倒しても無駄だ」
聞き覚えのある冷たい声にカイルとミラが同時に振り返る。
いつの間にか背後に自称天使シーアスが立っていた。
カイルはミラが身体を強ばらせた隙に強引に押し退けた。
が、ミラはカイルの背に隠れるようにしながら身体を押し付けてくる。
「無駄って言うのはどういう事だ」
ミラを気にしないようにしながらシーアスに訊ねた。
「ここは三ヶ月前お前が封印を解いた場所だ」
目印のない山の中である。
正確な場所など覚えてなかったが黙っていた。
「封印って封印獣と関係があるのか?」
「あれは封印であり鍵でもあった」
シーアスはカイルの質問に答えず続けた。
「封印獣が向こうとこちらの通路を塞いでたんだ。それをお前が開いてくれたお陰で千年ぶりにこっちに来られたよ」
「教えてくれるなんて随分親切じゃないか」
「彼女にはね」
ミラがカイルに更に密着してきた。
カイルが肩を竦める。
「ミラ、地震」
ミラはすぐに意味を悟った。
次の瞬間、突き上げるような震動が襲ってきた。
カイルとミラが地面に投げ出される。
二人は倒れたまま地面にしがみつく。
シーアスが顔を顰めた。
「まだ子供だからって舐めてたようだな」
言い終える前に姿が消えていた。
「もう止めていい?」
「うん、大丈夫だと思う」
地震が止み、安堵の息を吐いた時、
「こんなのは一時しのぎだ」
シーアスの声が響いてきた。
ミラが慌ててカイルにしがみつく。
カイルはそれを強引に引き離した。
「もう大丈夫だよ」
「また会えるのを楽しみにしてるよ」
最後の台詞はミラに向けられたものだ。
ミラの顔が引き攣る。
ミラを怖がらせられるなんて一体どんな事をしたのか気になるが、まずはここを離れる事にした。
たまたま二人のいたところが街道の近くだったこともあり、村に寄らずに帰る事にした。
「村長に何か言わなくていいの?」
「お礼を貰えるわけじゃないし、僕らが報告するのはラースの方だろ」
ミラもカイルの話を聞いて以来ヘメラにはあまりいい印象を持ってないらしく異議はないようだった。
マイラは神殿の廊下を歩いていた。
廊下の端で言い争う声が聞こえる。
見ると居住区への入り口のところで男が下級神官に食い下がっていた。
「どうかしたの?」
下級神官の困りきった様子にマイラは声をかけた。
「マイラ様」
「マイラ? ミラじゃないのか。ミラって人に会わせてくれ」
「ミラ……」
マイラは名前を呼び捨てにしかけて下級神官に気付いた。
「キシャル様に何か?」
声がキツくなるのまでは抑えられなかった。
カイルとミラがハイラル教徒に攫われて以来、二人への面会の取り次ぎは必ず神殿長かラースに報告するようにと言う厳命が下っている。
「化け物が出て困ってるんだよ」
「それなら私が……」
「ミラかカイルが来れば大人しくなるって言われたんだ。その二人じゃないとダメだって」
「魔物のいる場所は?」
「ロークだよ。ロークの山に……」
「分かりました。伝えておきます」
マイラはそう言うと背を向けた。
「早くしてくれないと……」
男の声が遠ざかる。
ミラ……。
いつだってミラは特別扱いだった。
ケナイの村長も周囲の村の人達も。
マイラの家族でさえマイラよりミラを大事にしていて自分は蔑ろにされていた。
ラースも同じだ。
確かにマイラに魔法の才能があるのを見出してくれたのはラースだった。
村に来る度に魔法を教えてくれたのも。
けれどラースの目当てはあくまでミラだった。
マイラに会いに来てくれた事は一度も無い。
神官になるように勧めてくれた事も。
しかしミラは村から出してもらえなかった。
マイラはレラス神殿に入りやっとの思いで中級神官になったと思ったらラースがミラを連れてきた。
ケナイの人達の話では、ラースはミラを捕まえに来た警備兵に対して脅迫まがいの事まで言って助けたという。
そしてミラはここであっさり上級神官になってしまった。
マイラの方はと言えば、ようやく昇格試験の申請が通ったと思ったらタグラで受けるように言われた。
その時はミラとカイルが行方不明だったからだと思っていた。
試験は上の階級の神官との対決だから相手がいなければ出来ないからだ。
タグラで試験を受けて合格し「やっとミラを追い越した」「ようやくミラに勝った」そう思った。
だがマイラはタグラの上級神官になったと告げられた。
ミラを中級神官に落とさない為なのは聞くまでもない。
元々マイラは替え玉だったのだ。
マイラが偽物だと言う事も、本物がミラだという事もバレてしまった。
カイルやガブリエラに勝てるだけの実力はないしミラは落とされないとなればレラスの上級神官の座に空きはない。