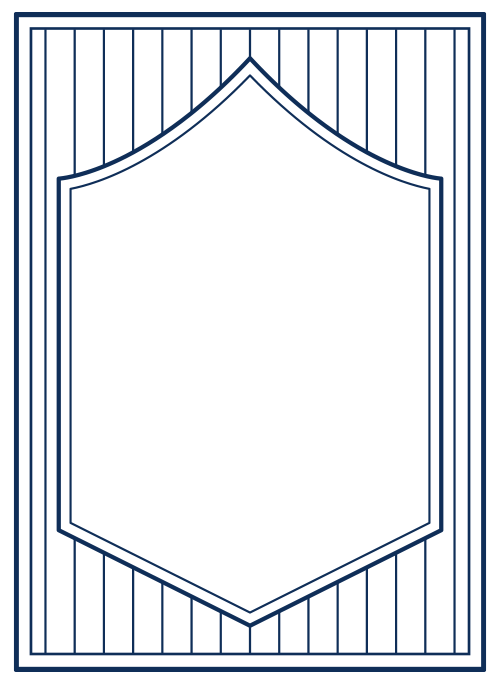一
ベッドに浅く腰掛けたカイルはさっきのラースの言葉を思い返す。
魔法は願望の具現化……。
無論、魔力が無い人間はいくら願っても実現しない。
この世には魔力を持った人間と持ってない人間がいる。
カイルがそのどちらに入るのかは微妙なところだ。
カイルの場合、回復と障壁は自分の魔力を使ってない。
回復魔法も魔法には代わりはないから普通は術者の魔力によって実現する。
だがカイルの使っている力は自分のものではない。
その力がどこからくるのかは分からない。
ミラではないが「お祈りすると誰かがやってくれる」のだ。
ただ回復と障壁以外の神聖魔法、例えば人を眠らせる魔法などは別である。
これは神殿で教わるまで使えなかったし、出来るようになるまでに何年も掛かった。
だから神聖魔法だけは自分の魔力を使っているらしい。
らしい、と言うのは魔力があるなら種類を問わず使えるはずだがカイルに出来るのは人を傷付けない魔法だけだからだ。
攻撃魔法は初歩的なものですら一切使えない。
離れた相手に掛けた事ないんだけど……。
カイルはベッドに座ったまま静かに眼を閉じた。
心の中で聖句を唱えながら見張りが眠る事を願う。
五回ほど唱えたところでようやく扉の外で人が倒れる音がした。
足音を忍ばせて扉に近付く。
静かに覗き窓を開けると見張りは二人とも熟睡していた。
カイルは溜息を吐くと窓に向かった。
布をなるべく丁寧に壁から破り取る。
本当は必要ないのだが発案者にやれと言われている。
いかにも窓から抜け出した――といっても格子があるから無理な事は一目瞭然なのだが――ように細工をするとベッドの下に潜り込んだ。
音を立てないように静かにベッドの下の床板を外す。
そこには縦穴が空いていた。
穴の底にはカイルが四ん這いになってようやく通り抜けられるだけの横穴が続いている。
カイルは縦穴に降りると床板を元通りに嵌め直した。
これも必ずやるように言われている事の一つだ。
「最初、机の下に抜け穴造った時は壁板嵌めるの忘れてバレちゃったのよね」
と言っていた。
床板を戻すと中は真っ暗になった。
そうか、ミラは魔法で明かりが出せるから……。
ここで魔法の練習している暇はない。
一本道なのだから道なりに行けばいいのだ。
カイルは真っ暗な横穴を進み始めた。
「じゃあ、あんた、無断で神殿抜けだしたの!」
「うん、だからラースにも言えなくて……あの部屋、筆記具なかったから書き置きも出来なかったし。ごめん」
「そんなのはどうでもいいけど……なんで抜け出したりしたのよ!」
「それ、君にだけは言われたくないよ」
「なに言ってんのよ! 閉じこめられたのはあんたが捕まったら困るからでしょ!」
「そうだったらしいね」
部屋の中に視線を彷徨わせる。
最後にまた椅子の男に行き着いた。
「ね、帰ったらどうなると思う?」
ミラが訊ねた。
「どっちが?」
「あんたが!」
「君はあの部屋に入れられたこと何回ある?」
「つまり、レラスに帰っても酷い目に遭うのは同じなわけね」
素直に騙されるのはラースの時だけらしい。
それとも学習したのか……。
「だからってハイラル教に改宗する気はないよ」
「当たり前でしょ!」
「じゃあ、どうするの?」
「逃げるの!」
「どこから? どこへ?」
「こっからどっかへよ!」
「どうやって?」
「それなのよね」
ミラが肩を落とした。
それからカイルの耳に口を寄せた。
「あいつには私の魔法、効かないのよ」
「ふぅん」
あいつなら効かなくてもおかしくはない。
あれは人間の姿をしているがこの世界の者ではない。
「護衛してあげてるんだからせめて知恵ぐらい出してよ」
「いつから僕の護衛になったんだよ」
「バカね、なんの為にラースがあんたと私を仲良くさせようとしたと思ってるのよ。あんたの護衛のためでしょ」
「僕は君の見張りの為だと思ってたけど」
「なんで私に見張りが必要なのよ!」
「教えてもらわなきゃ分かんないわけ?」
ミラが腹立たしげに睨んできた。
「とにかく……」
ミラが言い掛けた時、カートが見張りを連れて入ってきた。
「もういいですかな」
カートの言葉に椅子の男は黙って肩を竦めただけだった。
「約束の子が来たからにはもうこの娘は必要ないでしょう」
「ミラを帰してくれるの?」
「なわけないでしょ」
ミラが冷たく言った。
この数日間の会話を聞いていれば本命が手に入った後の運命は明らかだ。
「バカだな。この娘がいなくなったら、そいつに言う事を聞かせられなくなるだろう」
「しかし邪魔になります」
「邪魔しないように離しておけばいいのさ。俺が預かっといてやるよ」
「嫌よ!」
ミラが悲鳴に近い声を上げた。
真っ青な顔が思い切り引き攣っていた。
表情からするとカートも同じ思いらしかった。
ミラはカートに突進した。
カートが思わず身を引く。
ミラはカートの手を掴んで握り締めた。
「私の命がある限り、あんた達の邪魔をしまくってやるわ。だからさっさと殺して」
「ミラ! なに言ってるんだよ! 折角助けに来たんだぞ!」
「捕まってるヤツがなに偉そうなこと言ってんのよ!」
「そんな言い方ないだろ!」
「あんたは私がこいつらに捕まった後、何があったか知らないからそんなこと言えんのよ!」
「何がって……やっぱり何かされたの!?」
「されそうになったって言ったでしょ!」
ミラは必死の形相でカートの手を握っていた。
「お願い! あんたも聖職者なら情けってもんがあるでしょ! 一思いに殺して!」
どうやら早くここから逃げ出さないとミラは碌な目に遭わないようだ。
二
不意にシーアスの顔が厳しくなった。
窓ガラスが微かに鳴る。
次の瞬間、建物が揺れ始めた。
大した揺れではない。
だがミラは眉を顰めていた。
シーアスが顔を歪める。
「くそ! また……!」
最後まで言う前にシーアスの姿は消えていた。
カイルはミラの方を振り向いた。
「今の、君がやったの?」
何かに気を取られていた様子だったミラが我に返った。
「まさか。あれ、あいつの力よ。ただの虚仮威しで姿が見えなくなるだけなのか、それともどっかに行ってるのかは分かんないけど」
カイルは気配を探るように中に視線を彷徨わせた。
「どこかに行った方みたいだね」
気配がなくなっている。
「この地震、人為的に起こされたもの?」
ミラが首を振った。
地震を起こせるのは相当な魔力を持つ者だけである。
ミラなら簡単だろうが。
揺れはすぐに収まったがシーアスは戻ってこなかった。
「あいつさえいなければこっちのもんよ」
「あいつ、何者なの?」
「天使だって言ってたけど、どう思う?」
「人間じゃないのは気付いてるんだろ」
「うん。でもホントに天使なの?」
「堕ちた方のね」
カイルの言葉にカート達が動揺した。
悪魔とは堕ちた天使の事だ。
シーアスが堕天使だとしたらカート達にとって彼は異教徒同様、敵である。
「堕ちたって?」
ミラが首を傾げた時、轟音と共に建物が大きく揺れた。
全員が床に投げ出される。
「きゃ……!」「わっ!」
壁にひびが入り天井からゴミとも破片ともつかない物が落ちてくる。
今度は地震ではない。
何者かが建物に攻撃を仕掛けてきたのだ。
「何事だ!」
「アスラル教のやつらか!」
「なわけないでしょ!」
アスラルの神官が警告も無しに攻撃をしてくるはずがない。
カイルとミラを助けに来たのなら尚更だ。
再度、何かが建物にぶつかるような大きな音がした。
振動と壁が割れる音や家具がぶつかりあう音、それに叫び声が続く。
建物が揺れ、壁の亀裂が大きくなり天井が落ちてくる。
カイルはミラを庇うのがやっとだった。
肩や背中に天井や壁の破片がぶつかってくる。
男達も必死で床にへばりついていた。
激しい揺れと耳をつんざくような音が続きその度に建物が崩れていく。
不意に音が止んだ。
「来る!」
ミラが叫んだ。
咄嗟の事でカイルは自分の周りに障壁を張るのがやっとだった。
最後の攻撃で残っていた建物は全て消し飛ばされた。
カイルも障壁ごと吹っ飛ばされそうだった。
辛うじてその場に踏み留まれた有り様だ。
風圧とも衝撃波ともつかないものが止んだ時、建物は瓦礫さえ碌に残っていなかった。
家の周囲に生えていた樹々まで薙ぎ倒されている。
「信じらんない! この私を捕まえとくのに自称天使以外に魔法使えるヤツがいなかったわけ!?」
「ハイラル教は魔法禁止だから」
一応神官の中には特別に使う事を許可された者もいるようだがそれ以外の者が使う事は許されない。
魔法は聖人が行う〝奇蹟〟とされているからだ。
ミラが拳を握り締める。
建物に何人のハイラル教徒がいたのかは知らないがカイルが目にしただけでも十人近くいた。
だが今ここにいるのはカイルとミラの二人だけだ。
遮る物が無くなった二人の前方に立っていたのはオレンジ色の布を纏った男だった。
オレンジ色の敷布を被っているような、だらしなさと紙一重の長い聖衣。
セルケト教の神官だ。
「貴様らが〝破壊神の使い〟か」
「その言葉そっくり返すわよ」
ミラの声が怒りで震えている。
二人の周囲、僅かに残った瓦礫の下にはさっきまで人間だったものの一部が見えていた。
血の臭いがしないのはそれすらも吹き飛ばされてしまったのだろう。
たとえ虫の息でも生きている者が何人いるか……。
「この世界を破壊神の手に渡すわけにはいかん。死ね!」
言い終わると同時にセルケト教徒の放った衝撃波が襲ってきた。
カイルとミラがそれぞれ障壁を張って防ぐ。
しかしセルケト神官の攻撃は障壁を突き抜けてきた。
腕や足に次々と傷が出来ていく。
そんなバカな……!
カイルの魔法障壁は他の神官の障壁とは違う。
障壁ごと弾き飛ばされる事はあっても攻撃が突き抜けてしまう事のない〝貫けない盾〟のはずだ。
周りに残っていた瓦礫が後ろへ飛ばされていく。
背後で樹が倒れる音がした。
カイルの頬が抉られ生暖かいものが流れていく。
打ち身と切り傷でそこら中が痛い。
服も破れているはずだ。
「この!」
ミラは大人しく身を守っていたりしなかった。
攻撃を障壁で防ぎながら火球を二発、三発と立て続けに放った。
だがセルケト神官は炎の球を苦もなく跳ね返してしまった。
こちらが完全に防ぎ切れていない事を考えればかなり実力があると言う事だ。
唯一の救いは向こうは魔法を放ち続けられないという点か。
定期的に攻撃が途切れる。
人の魔力は体力と同じで有限だからだ。
人間が全力疾走をいつまでも続けられないのと同様、魔法を放ち続ける事も出来ない。
でなければとっくに二人ともやられていただろう。
向こうの攻撃が止んだ途端、セルケト教徒を炎が包んだ。
が、一瞬にして散らされてしまった。
掠り傷一つ負った様子はない。
平然とした様子で攻撃を再開してきた。
三
「きゃ……!」
振り返るとミラが地面に叩き付けられていた。
同時に攻撃が止んだ。
「ミラ!」
急いで駆け寄るとミラを抱き起こした。
ミラの服の前面が真紅に染まっている。
右頬にも顎の近くから額まで穿たれたような傷が付いていた。
「ミラ、大丈夫!?」
「平気よ」
ミラは不機嫌そうな声で答えると自力で半身を起こした。
見ると背中も血塗れだった。
衝撃波が貫通したのだ。
服の腹部に空いた大きな穴と身体の前面を真っ赤に染めた鮮血が傷の酷さを物語っていた。
よく即死しなかったものだ。
カイルが回復魔法を掛けるまでもなく腹部の傷は治っていた。
ケガをした直後、意識を失う直前の一瞬に回復魔法を掛けたのだろう。
図らずも「重傷でも意識があれば自分で治せる」を実践する羽目になったのだ。
カイルは地面に付いた手で硬い土を力一杯握りしめた。
小石で爪が割れるのが分かった。
こんな理不尽な目に遭っても何も出来ないなんて……。
自分には止めさせる事もやり返す事も出来ない。
悔しさで拳が震えた。
「ちょっと」
ミラがカイルを突いた。
「来るわよ」
カイルは顔を上げると障壁を張った。
想定内とはいえミラは防御が得意ではない。
そうと分かった今、ミラも一緒に守らなければならない。
直後に衝撃波が襲ってきた。
カイルは攻撃を防ぎながらミラの顔の傷に回復魔法を掛けた。
「同時に出来るの?」
「君は出来ないの?」
「うん、神聖魔法は同時には使えない」
つまりケガを治しているところを狙われたらやられてしまうのか……。
ミラにも障壁張っておいて良かった……。
「君と同じで回復魔法と障壁は『お祈りすると誰かがやってくれる』んでね」
「……っ痛!」
ミラが顔を顰めた。
治したばかりの顔にまた傷が出来ていた。
「どうしてこっちの攻撃は利かないのにあいつの攻撃は防げないのよ! あんた、あいつの魔法を跳ね返したりとかは出来ないの?」
「攻撃は一切ダメ」
「もぉ! なんなのよ、あいつの力は」
「向こうのは僕らの魔法より発達してるみたいだね」
「つまり向こうの魔法は願望の具現化じゃないって事?」
「それは基礎の基礎。それを更に発展させて複雑な形で実現したのが向こうの魔法なんだと思う」
「なんでそんな事すんの?」
「現にこっちより強いだろ」
ミラが「やなヤツ」とかなんとか言いながら顔を顰めた。
「なんとかしなきゃ。これじゃ、まだ生きてる人がいたとしても助けられないわよ」
そうは言われてもカイルに出来るのは障壁を張りながらミラと自分に回復魔法を掛ける事だけだ。
向こうと違ってカイルの障壁と回復魔法はいつまででも使い続けられるが攻撃が貫通してくる。
万が一即死するような攻撃が当たったらそこで終わりだ。
「どうしてこういう時に自称天使がいないのよ! あいつがいればハイラル教の連中だって無事だったかもしれないのに!」
「それはどうかな」
天使は天使でも堕天使だ。
ハイラル教徒を利用しているだけだから守ったりはしないだろう。
ミラは暫く考え込んでいたがやがてセルケト教徒の方を向いた。
「仕方ないわね。あんまり人には使いたくなかったんだけど、テル・シュトラを……」
「ダメだよ」
「他に効きそうなの無いわよ。この前のイス・レズルは大きすぎてあんなちっちゃい的に当てられるかどうか分かんないし」
あれは生えてきたのではなく落ちてきたのか……。
大地系の魔法はその名の通り地面から出てくるものなのだが。
「正確にはイス・レズルじゃないけど……テル・シュトラはハイラル教の人達に止めを刺しちゃうよ」
まだ生きてる人がいたら、だけど。
カイルは言葉に出さずに付け加えた。
「なら、どうするのよ」
「一度見れば真似できるんだろ。あいつと同じ魔法なら多分」
「そっか」
「ちょっと待った」
早速やり返そうとしたミラを止めた。
「なんで止めんの?」
「この程度じゃ無理だよ」
「じゃあ、どうしろって……」
「一度だけ」
カイルは低い声で呟いた。
「え……?」
「一度だけなら、あいつの最大の攻撃を防げると思う」
「それで?」
「二発目が来る前に同じ魔法でやり返して」
「分かった」
ミラが真剣な顔で頷いた。
カイルはセルケト教徒の攻撃が止んだのを見計らって怒鳴った。
「そんな攻撃いくらやっても無駄だ!」
「そうは思えないが」
セルケト教徒がバカにしたように嗤った。
確かに服はぼろぼろで身体は傷だらけだ。
この状態で言っても説得力に欠けるだろう。
しかし、ここで挫けるわけにはいかない。
「現に僕達は無事じゃないか」
「いつまで保つかな」
「僕達はこれでも上級神官だ。あんたの最大の技にだってやられない自信あるけど?」
カイルは笑みを浮かべた。
不敵に見える事を祈りながら。
「強がりを」
「なら試してみろよ。通用しないって証明してやるから」
「いいだろう。あの世で後悔するんだな!」
セルケト教徒が指で宙に図形を描きながら呪文を唱え始めた。
「あいつ、何やってんの?」
「印を切りながら呪文を唱えてるんだよ」
「何の為に?」
「聖句と同じ。魔法を出す為の準備みたいなものだよ」
「面倒くさそ。魔法教わったのがアスラル教で良かったわ」
「そんな事はどうでもいいから、あいつの技ちゃんと見てろよ」
「大丈夫よ。あんたと同じでね」
ミラが胸を張った。
「ありがと」
カイルはちょっと笑ってみせた。
本当はそれほど自信があったわけではない。
さっきまでの攻撃だって完全には防げていなかったのだ。
けれど、これでやらないわけにはいかなくなった。
ミラさえ守れれば……。
カイルは深呼吸をすると障壁を張った。
一拍遅れて炎の奔流が圧力となって二人を襲った。
「く……!」
後ろに押されそうになるのをなんとか堪える。
倒れてしまったら自分もミラもそれまでだ。
必死で圧力に対抗していたが少しずつ後ろに押されていく。
顔の前で交差した腕が熱のせいで激痛がする。
袖が燃えて灰になる。
ミラも両手で顔を庇っていたが無事なようだった。
だがやはり完全には防げていない。
時折貫通した攻撃でケガをしている。
カイルも今だけは回復魔法を掛けている余裕はなかった。
腕の感覚が無くなる。
炭化するのではないかと思ったが仮に焼け落ちてしまってもカイルは欠損した部位の再生も可能だから命と意識さえあればなんとかなる。
セルケト教徒はホントに最大の技を放ってくれたらしい。
今までよりも短い時間で攻撃が止んだ。
カイルは思わず安堵の息を漏らした。
身体中の力を使い果たした気がする。
膝を突きたかったがここで弱みを見せるわけにはいかない。
目を見張っているセルケト教徒に笑ってみせた。
「この! ならば今一度……!」
「遅い!」
印を切ったり呪文を唱えたりしない分ミラの方が早い。
驚愕しているセルケト教徒に圧力を伴った炎が襲いかかった。
四
炎が消えた時、セルケト教徒は後方の焦げた樹にもたれて立っていた。
傷一つ負っていない。
「嘘……あれでもダメだったの!?」
ミラの声が動揺している。
カイルも一瞬緊張した。
すぐに障壁を張れるように身構える。
だがセルケト教徒は微動だにしない。
様子を窺っていたカイルは身体の力を抜いた。
「どうなってるの?」
「君の勝ち」
「でも……」
「魔法そのものは防がれちゃったけど……防ぐので力を使い果たしちゃったんだよ。魔力の過剰な放出による心停止ってとこかな」
おそらくミラの放った魔法の方が遥かに威力が強かったのだろう。
ミラの魔法がカイルの回復を司る力と同じだとすれば、ミラは自らの魔力は使ってない。
自分の力でなければ身体に負担が掛からないから幾らでも威力を上げられるし際限なく打ち続けられる。
有限である普通の魔力とは違う力なのだ。
「死んじゃったの?」
ミラが青ざめた顔で唇を震わせる。
カイルはミラの肩に手を置いた。
「誰か生きてる人がいるかもしれない。探してみよう」
「……うん」
周囲の木々は薙ぎ倒されていたものの離れた場所の樹は無事だった。
その為、瓦礫も犠牲者も樹に引っ掛かってあまり遠くへは飛ばされなかったのだ。
障壁を張れるミラやカイルでさえケガをしたのだから魔法の使えない者があれだけの攻撃を受けて生きていられるわけがない。
とりあえず犠牲者を埋葬しようという事になった。
しかし遺体は全てばらばらになっていて正確な犠牲者の数が分からない。
ミラは当然ながらハイラル教徒達の人数も顔も覚えていなかった。
ミラに分かったのは一度に目にした最大の人数は人質を抜かして六人。
それに人質の二人を加えて八人。
つまりそれ以下ではない。
カイルが一番沢山見たのはここに着いたときで八人くらい。
その他に複数の人の話し声がしたから人質を含めれば十人は越えていただろう。
仕方なく全員同じ場所に埋める事にした。
ただ流石にセルケト教徒とは一緒に入りたくないだろう、という事で意見が一致した。
セルケト教徒の分は隣に別の穴に埋める事にした。
「でも、こいつだけが一人で他は全員一緒ってなんか特別扱いみたいで腹立つわね」
とは言え手足を別々に埋められもそれはそれで嫌だろう。
「うーん」
カイルは考え込んだ。
その時、建物の瓦礫が目に止まった。
「棺……」
「え?」
「棺、作ろうか。リース達とハイラル教徒の分だけ。全員一緒は同じだけど」
「私、棺なんて見た事ないから作れないわよ」
「僕が作るよ」
カイルは瓦礫の中から材料を集めた。
カイルが棺を作っている間、ミラは墓穴を掘った。
といってもミラは魔法だからすぐに終わったが。
「あんた、そういうの得意よね」
ミラが棺を作っているカイルを眺めながら言った。
「え?」
「執務室の扉に付けた花瓶とか壊れた棚の修理とか全部あんたがやったんだって?」
「うん」
「好きなの?」
「何が?」
「大工仕事」
カイルは思わず手を止めて釘に目を落とした。
そんなの、考えた事も無かった。
けれど、やっている時は楽しいのも確かだった。
カイルはなんと答えればいいのか分からないまま作業を続けた。
ミラもしつこく訊ねようとはしなかった。
暫く経ってから、
「……僕の村にムノーガっていうお爺さんがいたんだ」
カイルがぽつりと言った。
「知ってる。昔、船大工やってた人でしょ」
そうだ、村にいた頃は暇さえあればそのお爺さんの仕事を見ていたっけ。
昔の話を聞くのが楽しくて……。
「……その人に教わったんだ」
「ふぅん」
棺が出来るとそれに犠牲者を収めて穴に入れ土を被せた。
「お墓の上を歩かれたらイヤよね? 上に何か置いた方がいいと思う?」
一応棺や遺体の分だけ土が盛り上がっているが、それは遺体が腐敗して土に戻ったら平らになってしまう。
「ハイラル教は木や石の棒を立てるんだけど……ケナイはどうしてた?」
カイルのいたラウル村の墓は盛り土をするだけだった。
「土を盛ってたと思うけど……」
ミラが首を傾げた。
何しろミラがいる限り寿命以外で死ぬ事はまず無かったのだ。
大して大勢いる訳でもない上にミラが生まれるまでは長生きする人間は滅多にいなかった。
老衰以外の死因が無いのに年寄りが殆どいなかったのだから当然葬式に立ち会った事は無いし村の中で大事にされていたから外にある墓を見る機会も無い。
「両方やっとく?」
「そうね」
ミラは同意してからセルケト教徒の墓を指した。
「こっちは?」
「セルケト教徒は分からないよ」
「この前、調べたって言ってたじゃない」
「埋葬方法調べたわけじゃないよ」
この辺にはセルケト教徒はいない。
二人ともセルケト教徒の墓を見た事が無かった。
「とりあえず板を立てとけばいいんじゃないかな」
「そうね」
二人は盛り土をしてからハイラル教徒とセルケト教徒の分の板を立てた。
「あの世ってホントにあったのね」
「なんでそう思うの?」
「あいつが天使だって言うのがホントなら、あの世があるって事でしょ」
「天使も悪魔もあの世に住んでるわけじゃないよ。天使がいるのは天界、悪魔がいるのは地獄、死んだ人が逝くのは冥界。ハイラル教で悪魔が住んでる世界(地獄)はアスラル教のティルグの事だし」
ミラは混乱したように首を傾げた。
「じゃあ、あいつはどこから来たの?」
「言ったろ。ティルグの住人だよ」
カイルは少し躊躇ってから付け加えた。
「アイオンで魔物を倒した時に見た世界。多分あれがティルグだよ」
ミラは分かっているのかいないのか不思議そうな顔でカイルを見ている。
この様子ではティルグの事も覚えてないのかもしれない。
ラースから教わっていないはずは無いのだが……。
本当にミラがバカではないのか自信が無くなってきた。
ティルグというのは空間の壁で遮られたもう一つの世界である。
その昔、混沌から大地母神が生まれ、続いて天空大神が生まれた。
大地母神と天空大神との間に最初に出来たのが光明神と海洋神である。
海洋神の性格は穏やかだったが光明神は凄まじい熱と光であらゆるものを破壊した。
光明神のもたらした破壊により世界は壊滅した。
折角創った世界を壊された大地母神は世界を二つに分けた。
一つは大地母神アスラルの治める穏やかな世界。
もう一つが破壊神となった光明神の治める破壊に満ちた世界――ティルグ――である。
光明神を向こうの世界に追いやってしまったのでこちらの世界には光が無くなった。
そこで光明神の比較的穏やかな性格の子供の一柱をこちらに呼び、太陽神にしてこの世界に昼を創った。
魔物というのは破壊神の世界からやってくるのだ。
「覚えてる?」
カイルは恐る恐る訊ねた。
ミラは何も言わずに肩を竦めた。
ラースの胃は穴だらけかもしれない……。
カイルは密かにラースに同情しながら説明を続けた。
ベッドに浅く腰掛けたカイルはさっきのラースの言葉を思い返す。
魔法は願望の具現化……。
無論、魔力が無い人間はいくら願っても実現しない。
この世には魔力を持った人間と持ってない人間がいる。
カイルがそのどちらに入るのかは微妙なところだ。
カイルの場合、回復と障壁は自分の魔力を使ってない。
回復魔法も魔法には代わりはないから普通は術者の魔力によって実現する。
だがカイルの使っている力は自分のものではない。
その力がどこからくるのかは分からない。
ミラではないが「お祈りすると誰かがやってくれる」のだ。
ただ回復と障壁以外の神聖魔法、例えば人を眠らせる魔法などは別である。
これは神殿で教わるまで使えなかったし、出来るようになるまでに何年も掛かった。
だから神聖魔法だけは自分の魔力を使っているらしい。
らしい、と言うのは魔力があるなら種類を問わず使えるはずだがカイルに出来るのは人を傷付けない魔法だけだからだ。
攻撃魔法は初歩的なものですら一切使えない。
離れた相手に掛けた事ないんだけど……。
カイルはベッドに座ったまま静かに眼を閉じた。
心の中で聖句を唱えながら見張りが眠る事を願う。
五回ほど唱えたところでようやく扉の外で人が倒れる音がした。
足音を忍ばせて扉に近付く。
静かに覗き窓を開けると見張りは二人とも熟睡していた。
カイルは溜息を吐くと窓に向かった。
布をなるべく丁寧に壁から破り取る。
本当は必要ないのだが発案者にやれと言われている。
いかにも窓から抜け出した――といっても格子があるから無理な事は一目瞭然なのだが――ように細工をするとベッドの下に潜り込んだ。
音を立てないように静かにベッドの下の床板を外す。
そこには縦穴が空いていた。
穴の底にはカイルが四ん這いになってようやく通り抜けられるだけの横穴が続いている。
カイルは縦穴に降りると床板を元通りに嵌め直した。
これも必ずやるように言われている事の一つだ。
「最初、机の下に抜け穴造った時は壁板嵌めるの忘れてバレちゃったのよね」
と言っていた。
床板を戻すと中は真っ暗になった。
そうか、ミラは魔法で明かりが出せるから……。
ここで魔法の練習している暇はない。
一本道なのだから道なりに行けばいいのだ。
カイルは真っ暗な横穴を進み始めた。
「じゃあ、あんた、無断で神殿抜けだしたの!」
「うん、だからラースにも言えなくて……あの部屋、筆記具なかったから書き置きも出来なかったし。ごめん」
「そんなのはどうでもいいけど……なんで抜け出したりしたのよ!」
「それ、君にだけは言われたくないよ」
「なに言ってんのよ! 閉じこめられたのはあんたが捕まったら困るからでしょ!」
「そうだったらしいね」
部屋の中に視線を彷徨わせる。
最後にまた椅子の男に行き着いた。
「ね、帰ったらどうなると思う?」
ミラが訊ねた。
「どっちが?」
「あんたが!」
「君はあの部屋に入れられたこと何回ある?」
「つまり、レラスに帰っても酷い目に遭うのは同じなわけね」
素直に騙されるのはラースの時だけらしい。
それとも学習したのか……。
「だからってハイラル教に改宗する気はないよ」
「当たり前でしょ!」
「じゃあ、どうするの?」
「逃げるの!」
「どこから? どこへ?」
「こっからどっかへよ!」
「どうやって?」
「それなのよね」
ミラが肩を落とした。
それからカイルの耳に口を寄せた。
「あいつには私の魔法、効かないのよ」
「ふぅん」
あいつなら効かなくてもおかしくはない。
あれは人間の姿をしているがこの世界の者ではない。
「護衛してあげてるんだからせめて知恵ぐらい出してよ」
「いつから僕の護衛になったんだよ」
「バカね、なんの為にラースがあんたと私を仲良くさせようとしたと思ってるのよ。あんたの護衛のためでしょ」
「僕は君の見張りの為だと思ってたけど」
「なんで私に見張りが必要なのよ!」
「教えてもらわなきゃ分かんないわけ?」
ミラが腹立たしげに睨んできた。
「とにかく……」
ミラが言い掛けた時、カートが見張りを連れて入ってきた。
「もういいですかな」
カートの言葉に椅子の男は黙って肩を竦めただけだった。
「約束の子が来たからにはもうこの娘は必要ないでしょう」
「ミラを帰してくれるの?」
「なわけないでしょ」
ミラが冷たく言った。
この数日間の会話を聞いていれば本命が手に入った後の運命は明らかだ。
「バカだな。この娘がいなくなったら、そいつに言う事を聞かせられなくなるだろう」
「しかし邪魔になります」
「邪魔しないように離しておけばいいのさ。俺が預かっといてやるよ」
「嫌よ!」
ミラが悲鳴に近い声を上げた。
真っ青な顔が思い切り引き攣っていた。
表情からするとカートも同じ思いらしかった。
ミラはカートに突進した。
カートが思わず身を引く。
ミラはカートの手を掴んで握り締めた。
「私の命がある限り、あんた達の邪魔をしまくってやるわ。だからさっさと殺して」
「ミラ! なに言ってるんだよ! 折角助けに来たんだぞ!」
「捕まってるヤツがなに偉そうなこと言ってんのよ!」
「そんな言い方ないだろ!」
「あんたは私がこいつらに捕まった後、何があったか知らないからそんなこと言えんのよ!」
「何がって……やっぱり何かされたの!?」
「されそうになったって言ったでしょ!」
ミラは必死の形相でカートの手を握っていた。
「お願い! あんたも聖職者なら情けってもんがあるでしょ! 一思いに殺して!」
どうやら早くここから逃げ出さないとミラは碌な目に遭わないようだ。
二
不意にシーアスの顔が厳しくなった。
窓ガラスが微かに鳴る。
次の瞬間、建物が揺れ始めた。
大した揺れではない。
だがミラは眉を顰めていた。
シーアスが顔を歪める。
「くそ! また……!」
最後まで言う前にシーアスの姿は消えていた。
カイルはミラの方を振り向いた。
「今の、君がやったの?」
何かに気を取られていた様子だったミラが我に返った。
「まさか。あれ、あいつの力よ。ただの虚仮威しで姿が見えなくなるだけなのか、それともどっかに行ってるのかは分かんないけど」
カイルは気配を探るように中に視線を彷徨わせた。
「どこかに行った方みたいだね」
気配がなくなっている。
「この地震、人為的に起こされたもの?」
ミラが首を振った。
地震を起こせるのは相当な魔力を持つ者だけである。
ミラなら簡単だろうが。
揺れはすぐに収まったがシーアスは戻ってこなかった。
「あいつさえいなければこっちのもんよ」
「あいつ、何者なの?」
「天使だって言ってたけど、どう思う?」
「人間じゃないのは気付いてるんだろ」
「うん。でもホントに天使なの?」
「堕ちた方のね」
カイルの言葉にカート達が動揺した。
悪魔とは堕ちた天使の事だ。
シーアスが堕天使だとしたらカート達にとって彼は異教徒同様、敵である。
「堕ちたって?」
ミラが首を傾げた時、轟音と共に建物が大きく揺れた。
全員が床に投げ出される。
「きゃ……!」「わっ!」
壁にひびが入り天井からゴミとも破片ともつかない物が落ちてくる。
今度は地震ではない。
何者かが建物に攻撃を仕掛けてきたのだ。
「何事だ!」
「アスラル教のやつらか!」
「なわけないでしょ!」
アスラルの神官が警告も無しに攻撃をしてくるはずがない。
カイルとミラを助けに来たのなら尚更だ。
再度、何かが建物にぶつかるような大きな音がした。
振動と壁が割れる音や家具がぶつかりあう音、それに叫び声が続く。
建物が揺れ、壁の亀裂が大きくなり天井が落ちてくる。
カイルはミラを庇うのがやっとだった。
肩や背中に天井や壁の破片がぶつかってくる。
男達も必死で床にへばりついていた。
激しい揺れと耳をつんざくような音が続きその度に建物が崩れていく。
不意に音が止んだ。
「来る!」
ミラが叫んだ。
咄嗟の事でカイルは自分の周りに障壁を張るのがやっとだった。
最後の攻撃で残っていた建物は全て消し飛ばされた。
カイルも障壁ごと吹っ飛ばされそうだった。
辛うじてその場に踏み留まれた有り様だ。
風圧とも衝撃波ともつかないものが止んだ時、建物は瓦礫さえ碌に残っていなかった。
家の周囲に生えていた樹々まで薙ぎ倒されている。
「信じらんない! この私を捕まえとくのに自称天使以外に魔法使えるヤツがいなかったわけ!?」
「ハイラル教は魔法禁止だから」
一応神官の中には特別に使う事を許可された者もいるようだがそれ以外の者が使う事は許されない。
魔法は聖人が行う〝奇蹟〟とされているからだ。
ミラが拳を握り締める。
建物に何人のハイラル教徒がいたのかは知らないがカイルが目にしただけでも十人近くいた。
だが今ここにいるのはカイルとミラの二人だけだ。
遮る物が無くなった二人の前方に立っていたのはオレンジ色の布を纏った男だった。
オレンジ色の敷布を被っているような、だらしなさと紙一重の長い聖衣。
セルケト教の神官だ。
「貴様らが〝破壊神の使い〟か」
「その言葉そっくり返すわよ」
ミラの声が怒りで震えている。
二人の周囲、僅かに残った瓦礫の下にはさっきまで人間だったものの一部が見えていた。
血の臭いがしないのはそれすらも吹き飛ばされてしまったのだろう。
たとえ虫の息でも生きている者が何人いるか……。
「この世界を破壊神の手に渡すわけにはいかん。死ね!」
言い終わると同時にセルケト教徒の放った衝撃波が襲ってきた。
カイルとミラがそれぞれ障壁を張って防ぐ。
しかしセルケト神官の攻撃は障壁を突き抜けてきた。
腕や足に次々と傷が出来ていく。
そんなバカな……!
カイルの魔法障壁は他の神官の障壁とは違う。
障壁ごと弾き飛ばされる事はあっても攻撃が突き抜けてしまう事のない〝貫けない盾〟のはずだ。
周りに残っていた瓦礫が後ろへ飛ばされていく。
背後で樹が倒れる音がした。
カイルの頬が抉られ生暖かいものが流れていく。
打ち身と切り傷でそこら中が痛い。
服も破れているはずだ。
「この!」
ミラは大人しく身を守っていたりしなかった。
攻撃を障壁で防ぎながら火球を二発、三発と立て続けに放った。
だがセルケト神官は炎の球を苦もなく跳ね返してしまった。
こちらが完全に防ぎ切れていない事を考えればかなり実力があると言う事だ。
唯一の救いは向こうは魔法を放ち続けられないという点か。
定期的に攻撃が途切れる。
人の魔力は体力と同じで有限だからだ。
人間が全力疾走をいつまでも続けられないのと同様、魔法を放ち続ける事も出来ない。
でなければとっくに二人ともやられていただろう。
向こうの攻撃が止んだ途端、セルケト教徒を炎が包んだ。
が、一瞬にして散らされてしまった。
掠り傷一つ負った様子はない。
平然とした様子で攻撃を再開してきた。
三
「きゃ……!」
振り返るとミラが地面に叩き付けられていた。
同時に攻撃が止んだ。
「ミラ!」
急いで駆け寄るとミラを抱き起こした。
ミラの服の前面が真紅に染まっている。
右頬にも顎の近くから額まで穿たれたような傷が付いていた。
「ミラ、大丈夫!?」
「平気よ」
ミラは不機嫌そうな声で答えると自力で半身を起こした。
見ると背中も血塗れだった。
衝撃波が貫通したのだ。
服の腹部に空いた大きな穴と身体の前面を真っ赤に染めた鮮血が傷の酷さを物語っていた。
よく即死しなかったものだ。
カイルが回復魔法を掛けるまでもなく腹部の傷は治っていた。
ケガをした直後、意識を失う直前の一瞬に回復魔法を掛けたのだろう。
図らずも「重傷でも意識があれば自分で治せる」を実践する羽目になったのだ。
カイルは地面に付いた手で硬い土を力一杯握りしめた。
小石で爪が割れるのが分かった。
こんな理不尽な目に遭っても何も出来ないなんて……。
自分には止めさせる事もやり返す事も出来ない。
悔しさで拳が震えた。
「ちょっと」
ミラがカイルを突いた。
「来るわよ」
カイルは顔を上げると障壁を張った。
想定内とはいえミラは防御が得意ではない。
そうと分かった今、ミラも一緒に守らなければならない。
直後に衝撃波が襲ってきた。
カイルは攻撃を防ぎながらミラの顔の傷に回復魔法を掛けた。
「同時に出来るの?」
「君は出来ないの?」
「うん、神聖魔法は同時には使えない」
つまりケガを治しているところを狙われたらやられてしまうのか……。
ミラにも障壁張っておいて良かった……。
「君と同じで回復魔法と障壁は『お祈りすると誰かがやってくれる』んでね」
「……っ痛!」
ミラが顔を顰めた。
治したばかりの顔にまた傷が出来ていた。
「どうしてこっちの攻撃は利かないのにあいつの攻撃は防げないのよ! あんた、あいつの魔法を跳ね返したりとかは出来ないの?」
「攻撃は一切ダメ」
「もぉ! なんなのよ、あいつの力は」
「向こうのは僕らの魔法より発達してるみたいだね」
「つまり向こうの魔法は願望の具現化じゃないって事?」
「それは基礎の基礎。それを更に発展させて複雑な形で実現したのが向こうの魔法なんだと思う」
「なんでそんな事すんの?」
「現にこっちより強いだろ」
ミラが「やなヤツ」とかなんとか言いながら顔を顰めた。
「なんとかしなきゃ。これじゃ、まだ生きてる人がいたとしても助けられないわよ」
そうは言われてもカイルに出来るのは障壁を張りながらミラと自分に回復魔法を掛ける事だけだ。
向こうと違ってカイルの障壁と回復魔法はいつまででも使い続けられるが攻撃が貫通してくる。
万が一即死するような攻撃が当たったらそこで終わりだ。
「どうしてこういう時に自称天使がいないのよ! あいつがいればハイラル教の連中だって無事だったかもしれないのに!」
「それはどうかな」
天使は天使でも堕天使だ。
ハイラル教徒を利用しているだけだから守ったりはしないだろう。
ミラは暫く考え込んでいたがやがてセルケト教徒の方を向いた。
「仕方ないわね。あんまり人には使いたくなかったんだけど、テル・シュトラを……」
「ダメだよ」
「他に効きそうなの無いわよ。この前のイス・レズルは大きすぎてあんなちっちゃい的に当てられるかどうか分かんないし」
あれは生えてきたのではなく落ちてきたのか……。
大地系の魔法はその名の通り地面から出てくるものなのだが。
「正確にはイス・レズルじゃないけど……テル・シュトラはハイラル教の人達に止めを刺しちゃうよ」
まだ生きてる人がいたら、だけど。
カイルは言葉に出さずに付け加えた。
「なら、どうするのよ」
「一度見れば真似できるんだろ。あいつと同じ魔法なら多分」
「そっか」
「ちょっと待った」
早速やり返そうとしたミラを止めた。
「なんで止めんの?」
「この程度じゃ無理だよ」
「じゃあ、どうしろって……」
「一度だけ」
カイルは低い声で呟いた。
「え……?」
「一度だけなら、あいつの最大の攻撃を防げると思う」
「それで?」
「二発目が来る前に同じ魔法でやり返して」
「分かった」
ミラが真剣な顔で頷いた。
カイルはセルケト教徒の攻撃が止んだのを見計らって怒鳴った。
「そんな攻撃いくらやっても無駄だ!」
「そうは思えないが」
セルケト教徒がバカにしたように嗤った。
確かに服はぼろぼろで身体は傷だらけだ。
この状態で言っても説得力に欠けるだろう。
しかし、ここで挫けるわけにはいかない。
「現に僕達は無事じゃないか」
「いつまで保つかな」
「僕達はこれでも上級神官だ。あんたの最大の技にだってやられない自信あるけど?」
カイルは笑みを浮かべた。
不敵に見える事を祈りながら。
「強がりを」
「なら試してみろよ。通用しないって証明してやるから」
「いいだろう。あの世で後悔するんだな!」
セルケト教徒が指で宙に図形を描きながら呪文を唱え始めた。
「あいつ、何やってんの?」
「印を切りながら呪文を唱えてるんだよ」
「何の為に?」
「聖句と同じ。魔法を出す為の準備みたいなものだよ」
「面倒くさそ。魔法教わったのがアスラル教で良かったわ」
「そんな事はどうでもいいから、あいつの技ちゃんと見てろよ」
「大丈夫よ。あんたと同じでね」
ミラが胸を張った。
「ありがと」
カイルはちょっと笑ってみせた。
本当はそれほど自信があったわけではない。
さっきまでの攻撃だって完全には防げていなかったのだ。
けれど、これでやらないわけにはいかなくなった。
ミラさえ守れれば……。
カイルは深呼吸をすると障壁を張った。
一拍遅れて炎の奔流が圧力となって二人を襲った。
「く……!」
後ろに押されそうになるのをなんとか堪える。
倒れてしまったら自分もミラもそれまでだ。
必死で圧力に対抗していたが少しずつ後ろに押されていく。
顔の前で交差した腕が熱のせいで激痛がする。
袖が燃えて灰になる。
ミラも両手で顔を庇っていたが無事なようだった。
だがやはり完全には防げていない。
時折貫通した攻撃でケガをしている。
カイルも今だけは回復魔法を掛けている余裕はなかった。
腕の感覚が無くなる。
炭化するのではないかと思ったが仮に焼け落ちてしまってもカイルは欠損した部位の再生も可能だから命と意識さえあればなんとかなる。
セルケト教徒はホントに最大の技を放ってくれたらしい。
今までよりも短い時間で攻撃が止んだ。
カイルは思わず安堵の息を漏らした。
身体中の力を使い果たした気がする。
膝を突きたかったがここで弱みを見せるわけにはいかない。
目を見張っているセルケト教徒に笑ってみせた。
「この! ならば今一度……!」
「遅い!」
印を切ったり呪文を唱えたりしない分ミラの方が早い。
驚愕しているセルケト教徒に圧力を伴った炎が襲いかかった。
四
炎が消えた時、セルケト教徒は後方の焦げた樹にもたれて立っていた。
傷一つ負っていない。
「嘘……あれでもダメだったの!?」
ミラの声が動揺している。
カイルも一瞬緊張した。
すぐに障壁を張れるように身構える。
だがセルケト教徒は微動だにしない。
様子を窺っていたカイルは身体の力を抜いた。
「どうなってるの?」
「君の勝ち」
「でも……」
「魔法そのものは防がれちゃったけど……防ぐので力を使い果たしちゃったんだよ。魔力の過剰な放出による心停止ってとこかな」
おそらくミラの放った魔法の方が遥かに威力が強かったのだろう。
ミラの魔法がカイルの回復を司る力と同じだとすれば、ミラは自らの魔力は使ってない。
自分の力でなければ身体に負担が掛からないから幾らでも威力を上げられるし際限なく打ち続けられる。
有限である普通の魔力とは違う力なのだ。
「死んじゃったの?」
ミラが青ざめた顔で唇を震わせる。
カイルはミラの肩に手を置いた。
「誰か生きてる人がいるかもしれない。探してみよう」
「……うん」
周囲の木々は薙ぎ倒されていたものの離れた場所の樹は無事だった。
その為、瓦礫も犠牲者も樹に引っ掛かってあまり遠くへは飛ばされなかったのだ。
障壁を張れるミラやカイルでさえケガをしたのだから魔法の使えない者があれだけの攻撃を受けて生きていられるわけがない。
とりあえず犠牲者を埋葬しようという事になった。
しかし遺体は全てばらばらになっていて正確な犠牲者の数が分からない。
ミラは当然ながらハイラル教徒達の人数も顔も覚えていなかった。
ミラに分かったのは一度に目にした最大の人数は人質を抜かして六人。
それに人質の二人を加えて八人。
つまりそれ以下ではない。
カイルが一番沢山見たのはここに着いたときで八人くらい。
その他に複数の人の話し声がしたから人質を含めれば十人は越えていただろう。
仕方なく全員同じ場所に埋める事にした。
ただ流石にセルケト教徒とは一緒に入りたくないだろう、という事で意見が一致した。
セルケト教徒の分は隣に別の穴に埋める事にした。
「でも、こいつだけが一人で他は全員一緒ってなんか特別扱いみたいで腹立つわね」
とは言え手足を別々に埋められもそれはそれで嫌だろう。
「うーん」
カイルは考え込んだ。
その時、建物の瓦礫が目に止まった。
「棺……」
「え?」
「棺、作ろうか。リース達とハイラル教徒の分だけ。全員一緒は同じだけど」
「私、棺なんて見た事ないから作れないわよ」
「僕が作るよ」
カイルは瓦礫の中から材料を集めた。
カイルが棺を作っている間、ミラは墓穴を掘った。
といってもミラは魔法だからすぐに終わったが。
「あんた、そういうの得意よね」
ミラが棺を作っているカイルを眺めながら言った。
「え?」
「執務室の扉に付けた花瓶とか壊れた棚の修理とか全部あんたがやったんだって?」
「うん」
「好きなの?」
「何が?」
「大工仕事」
カイルは思わず手を止めて釘に目を落とした。
そんなの、考えた事も無かった。
けれど、やっている時は楽しいのも確かだった。
カイルはなんと答えればいいのか分からないまま作業を続けた。
ミラもしつこく訊ねようとはしなかった。
暫く経ってから、
「……僕の村にムノーガっていうお爺さんがいたんだ」
カイルがぽつりと言った。
「知ってる。昔、船大工やってた人でしょ」
そうだ、村にいた頃は暇さえあればそのお爺さんの仕事を見ていたっけ。
昔の話を聞くのが楽しくて……。
「……その人に教わったんだ」
「ふぅん」
棺が出来るとそれに犠牲者を収めて穴に入れ土を被せた。
「お墓の上を歩かれたらイヤよね? 上に何か置いた方がいいと思う?」
一応棺や遺体の分だけ土が盛り上がっているが、それは遺体が腐敗して土に戻ったら平らになってしまう。
「ハイラル教は木や石の棒を立てるんだけど……ケナイはどうしてた?」
カイルのいたラウル村の墓は盛り土をするだけだった。
「土を盛ってたと思うけど……」
ミラが首を傾げた。
何しろミラがいる限り寿命以外で死ぬ事はまず無かったのだ。
大して大勢いる訳でもない上にミラが生まれるまでは長生きする人間は滅多にいなかった。
老衰以外の死因が無いのに年寄りが殆どいなかったのだから当然葬式に立ち会った事は無いし村の中で大事にされていたから外にある墓を見る機会も無い。
「両方やっとく?」
「そうね」
ミラは同意してからセルケト教徒の墓を指した。
「こっちは?」
「セルケト教徒は分からないよ」
「この前、調べたって言ってたじゃない」
「埋葬方法調べたわけじゃないよ」
この辺にはセルケト教徒はいない。
二人ともセルケト教徒の墓を見た事が無かった。
「とりあえず板を立てとけばいいんじゃないかな」
「そうね」
二人は盛り土をしてからハイラル教徒とセルケト教徒の分の板を立てた。
「あの世ってホントにあったのね」
「なんでそう思うの?」
「あいつが天使だって言うのがホントなら、あの世があるって事でしょ」
「天使も悪魔もあの世に住んでるわけじゃないよ。天使がいるのは天界、悪魔がいるのは地獄、死んだ人が逝くのは冥界。ハイラル教で悪魔が住んでる世界(地獄)はアスラル教のティルグの事だし」
ミラは混乱したように首を傾げた。
「じゃあ、あいつはどこから来たの?」
「言ったろ。ティルグの住人だよ」
カイルは少し躊躇ってから付け加えた。
「アイオンで魔物を倒した時に見た世界。多分あれがティルグだよ」
ミラは分かっているのかいないのか不思議そうな顔でカイルを見ている。
この様子ではティルグの事も覚えてないのかもしれない。
ラースから教わっていないはずは無いのだが……。
本当にミラがバカではないのか自信が無くなってきた。
ティルグというのは空間の壁で遮られたもう一つの世界である。
その昔、混沌から大地母神が生まれ、続いて天空大神が生まれた。
大地母神と天空大神との間に最初に出来たのが光明神と海洋神である。
海洋神の性格は穏やかだったが光明神は凄まじい熱と光であらゆるものを破壊した。
光明神のもたらした破壊により世界は壊滅した。
折角創った世界を壊された大地母神は世界を二つに分けた。
一つは大地母神アスラルの治める穏やかな世界。
もう一つが破壊神となった光明神の治める破壊に満ちた世界――ティルグ――である。
光明神を向こうの世界に追いやってしまったのでこちらの世界には光が無くなった。
そこで光明神の比較的穏やかな性格の子供の一柱をこちらに呼び、太陽神にしてこの世界に昼を創った。
魔物というのは破壊神の世界からやってくるのだ。
「覚えてる?」
カイルは恐る恐る訊ねた。
ミラは何も言わずに肩を竦めた。
ラースの胃は穴だらけかもしれない……。
カイルは密かにラースに同情しながら説明を続けた。