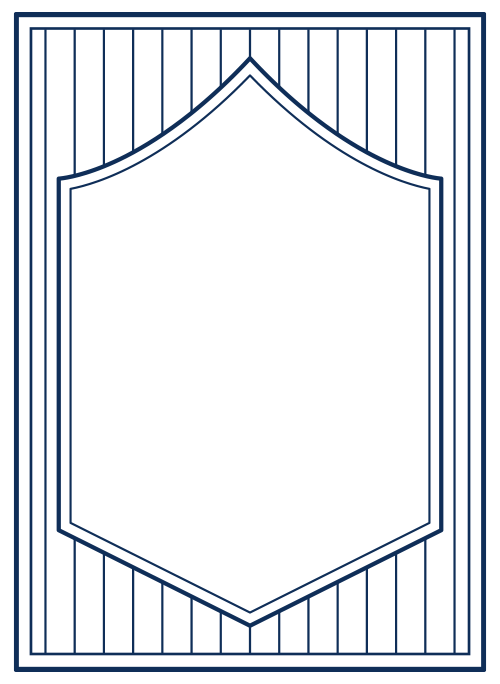一
空間が揺れると言うより捩れるような感じだった。
何かが軋むような音が聞こえた気がした。
身体ごと捻られているようで胃の中のものが逆流しそうになる。
思わず前屈みになったカイルはミラの背に頭をぶつけてしまった。
顔を上げるとミラが青ざめた顔をしていた。
「これ、なに?」
苦しそうな声だ。
ミラも同じなのか?
その時、ミラがいきなりカイルの腕を掴んだ。
「ちょっと、あれ!」
ミラが空を指した。
樹が全て倒れて見晴らしが良くなった視界に青空が広がっている。
青空が裂け、その向こうに違う空間があった。
赤い空と黒い大地。
黒い影は異形の建物なのか、それとも林立する岩なのか……。
それが見えていたのはほんの一瞬だった。
だが幻覚などではない。
あれは確かに存在する。
「あれ……なんなの?」
ミラがカイルの腕を痛いくらいに強く握っていた。
声が震えているのはミラにも分かったからだろう。
あれは自分達がやった事だ。
カイル達は何か恐ろしい事をしてしまったのだ。
不意にまた声が聞こえてきた。
『……約束の子は大地に十字の杭を突き立て邪魔する者を抑えた。
もはや何人たりとも止めること能わず。
ただ……』
「うるさいわね!」
ミラが苛立たしげに魔物の屍骸を睨んだ。
「ミラ! 火事になるだろ!」
カイルが慌てて制止する。
ミラが得意な攻撃魔法が火炎系のものだと分かった以上、可燃物に囲まれている場所でそう簡単に使わせるわけにはいかない。
カイルはミラが出した大地の剣を見上げた。
十字の杭……。
確かに鍔がある為そう見えなくもない。
「もう消しちゃっても大丈夫よね」
ミラが言った。
だが消えなかった。
「嘘……。どうして?」
ミラは目を瞑ったり手を振ったりして消そうと試みる。
しかし、いくらやっても消えなかった。
「……どうして消えないの?」
ミラが怯えた声で呟く。
その時、倒木を飛び越えてさっきの男がやってきた。
落ち着いて見ても、やはりかなり怪しい。
しかし一応命の恩人だ。
「有難うございました」
カイルは頭を下げた。
「お陰で助かったわ」
ミラも笑顔で礼を言った。
「なーに言ってんだよ。倒したのはそっちだろ。俺はおまけおまけ。だから俺の事は誰にも内緒な」
ますます怪しい。
男はカイルとミラの泥だらけになった外套を見下ろした。
外套の止め金を見ると、
「アスラル教の神官か。顔を隠しておいて正解だったぜ」
男は低い声で呟いた。
汚れが目立つ色なので一般人はわざわざ白く染めた布で作った服は着ない。
富裕層以外で白を身に着けるのは神官くらいだ。
そしてアスラル教の場合、上級神官はそれぞれに対応した神徒(この場合は鳥)を象った止め金を肩の辺りに付けている。
カイルはミラを男から離れた場所へ引っ張っていった。
「何?」
「あの人、変だよ」
「どこが?」
「あの格好見ておかしいと思わないの? 顔隠してるし」
「きっと火傷か傷痕でもあるのよ」
「そんなのアスラル神殿に行けば治してもらえるだろ」
「宗教が違うんでしょ」
「少しは警戒する気ないの?」
「あんた、いちいち細かいわよ」
「ま、とにかく帰ろうぜ」
男が二人に声を掛けてきた。
「これだけの力があるなら送る必要は無さそうだけどな」
男がそう言って周囲を見回す。
いつの間にか土の剣は消えていた。
辺りの木々は薙ぎ倒され遠くまで見通せるようになってしまっている。
「俺は、クナート。吟遊詩人なんだ」
一瞬だが名前を言う前に間があった。
偽名か……。
そもそも吟遊詩人と言いながら楽器らしいものは持っていない。
でもクナートってどこかで聞いた気が……。
「私はミラ」
「……カイルです」
カイルとしては一緒に帰りたくはなかったのだがミラは気を許してしまったようだ。
名前はマズい、なんて言ってたくせにあっさり教えてしまっている。
……ったく!
折角魔物を倒しても、これじゃ全然気が抜けないじゃないか。
カイルは苛立たしい思いでミラを睨んだ。
魔物はなんとか倒したんですが、その後で誘拐されてしまいました、なんてラースに報告する羽目にでもなったら……。
カイルは頭を抱えた。
ミラの方はクナートと話し込んでいた。
どうしてこんな怪しげなヤツを信用出来るんだよ……。
確かにクナートの声はどこか信用させるような響きがある。
人を安心させる何かがあるのだ。
というか、どこかで聞いたような気が……。
「吟遊詩人なら、なんで楽器持ってないんですか?」
ミラの親しげな様子に、つい意地悪な質問をしてしまう。
「別に楽器なんかなくたっていいじゃない。歌うんだから」
「楽器は必要ないんだ」
クナートは手近な草を摘んだ。
それから布の下の口に草を当てると吹き始めた。
とても草笛とは思えない澄んだ音色が流れ出す。
二
思わず聴き惚れてしまってから、
「すっごーい! 上手~!」
はしゃぎ声で我に返った。
「それでどうやって歌うんですか?」
カイルの問いにクナートが苦笑しながら草笛を止めた。
「あんた、揚げ足取りしか出来ないわけ?」
「ホントのこと言っただけだろ」
「なに言って……」
「まぁまぁ」
クナートが二人の間に入った。
既に布で口を覆い直している。
「このくらい賢くなきゃお姫様の騎士は勤まらないだろ」
「こいつは騎士じゃなくて神官よ」
クナートはそれには答えなかった。
覆面の向こうで笑っていたのかもしれない。
来た時のように歩き回らなくて済む分、帰りの方が早いかと思ったのだが、そうはいかなかった。
魔物のせいで地形が変わってしまっていたからだ。
木々は倒れ、魔物が埋まっていた場所には大きな穴が空いていたり逆に土砂で盛り上がっていたり。
倒木をよじ登ったり隙間を通り抜けたりして三人はようやく町の近くまで辿り着いた。
カイルもミラも泥だらけだった。
その上、顔も手足も擦り傷だらけだ。
こんな状態でも無事に帰したと言えるだろうか……。
町に入ろうとしたところでクナートが足を止めた。
「あれ、どこの坊さんだ?」
言いながら既に物陰に隠れている。
ミラも子犬のようにクナートに随いていく。
仕方なくカイルも続いた。
物陰から町の真ん中の広場のようなところを覗くと白い外套を来た人間が数人立っている。
「アスラル教? でも、レラスの神官じゃないわね」
アスラル神官なのにレラス神殿から来たのではないとなると……。
「僕だ」
「え?」
「多分、中央神殿から来たんだと思う」
「中央神殿? なんでそんなとこから……」
「僕も訳ありの口なんだ。ちょっとあって……レラス神殿に身柄を預けられてたっていうか……きっと二日続けて無断で外出しちゃったから……」
「中央神殿に連れてかれたらどうなるの?」
「処刑される……と思う。良くて死ぬまでどこかに閉じ込められるか……」
ミラが呆れたようにカイルを見た。
「あんた、一体何やったのよ!」
カイルは答えられなかった。
数ヶ月前のアリシアの嫌悪の表情が、七年前の父の顔と重なる。
教えたらきっとミラも……。
「信じらんない! 優等生面して偉そうに説教しといて自分は人に言えないような事してたなんて!」
カイルは黙って俯いていた。
「なんで随いてきたのよ!」
「君に何かあったらラースが心配するだろ」
「人の事より自分の心配しなさいよ!」
ミラはカイルを怒鳴り付けるとクナートの方を向いた。
「私が行って話してくる。それでダメだったら逃げるしかないわね」
「逃げるって、そんな事したらラースが……!」
「あんたが逃げたからってラースは殺されたりしないわよ!」
「行く当てあるの?」
「無い」
ミラの即答にカイルは眩暈を覚えた。
「俺、あるぜ」
「ホント!? 良かった」
「冗談だろ!」
こんな怪しい人間を信用出来るわけない。
しかしカイルの言葉は無視された。
「とにかく行ってみる」
ミラはそう言うとクナートに顔を向けて、
「こいつ見張ってて。私が合図したらこいつ連れて逃げて」
と言った。
「あいよ」
「逆らうようなら殴ってでも止めて。殺さない程度になら何したっていいわ」
「ミラ!」
ミラは真顔だった。
クナートも異を唱える気配はない。
自分の顔から血の気が引くのが分かった。
「私は息がありさえすればどんな重傷でも治せるし、こいつだって意識があれば自分で治せるんだから遠慮なくやって」
「りょーかい」
ミラが行ってしまうとクナートがカイルの方を向いた。
「悪いな。可愛い女の子と可愛い男の子、どっちの頼みを優先するか、言うまでもないよな」
考えようによってはまともといえなくもない。
が、やはり怪しい。
「ま、そういうわけだから仲良くしようぜ。俺も子供に手を出したくはないし」
クナートが明るい口調で言った。
吟遊詩人などと言っていたがどう見ても戦士だ。
命令されれば殺しだって躊躇わずにやるだろう。
いくら治せると言っても痛みを感じないわけではないのだ。
カイルは攻撃魔法が使えないし腕力だって無い。
せいぜい障壁で身を守ることくらいしか出来ないのだ。
喧嘩といえるようなものはミラとの口論くらいしかした事がない。
考えてみたら本当に役立たずだな……。
神聖魔法以外の魔法に関しては神官候補生にも敵わない。
というか神官候補生になる資格さえない。
自分に出来る事は何も無い。
ただの役立たずだ。
なのに上級神官だなんて……。
「おい、あいつらアスラルの神官じゃねーぞ」
カイルの物思いはクナートの声で破られた。
顔を上げるとミラが男達に両脇から腕を掴まれている。
白い外套の下に紫色の聖衣と下履きが見えた。
あれは……!
ミラは男達の方へ向かって歩きながら、なんと言い訳しようか考えていた。
中央神殿と言えばアスラル教の全神殿を統括する神殿だ。
そこから来たとなれば当然ラースどころか神殿長より偉い。
下手に怒らせたらカイルやミラだけではなくラース達も危うくなる。
言うべき言葉を何も思い付かないまま男達の前まで来てしまった。
「あの……」
男達はいきなりミラを取り囲んだかと思うと腕を掴んだ。
男の白い外套の下に見えたのはアスラル教の白い聖衣ではなかった。
ミラは目を見張った。
赤みの強い紫色の聖衣と黒に近い色の下履き。
ハイラル教の神官!?
「もう一人はどこだ?」
「なに言ってんのよ! 放しなさいよ!」
ミラは男達の腕を振り払おうと藻掻いた。
だが腕力だけなら大人の男の方が強い。
「もう一人いるだろう」
男が重ねて言った。
三
「この……!」
ミラが魔法を使おうとした時、
「その手を離してもらいましょうか」
後ろから穏やかな声がした。
「ラース!」
ラースを見た男達が怯んだ。
ミラは男達の腕を振りほどいた。
「彼女はうちの神官です。用があるなら神殿長に話を通していただきましょう」
ラースの声はあくまでも静かだった。
男達は目顔でどうするか相談しているようだ。
ラースとミラの二人を相手に出来るだけの力量があるかどうか考えていたのかもしれない。
結論は出たようだ。
男達は何も言わずに引き上げていった。
聖職者だけあって悪役のような捨て台詞は吐かなかった。
「ふふんだ! 一昨日おいで」
ミラが男達の後ろ姿に舌を出した。
「ミラ! ラース!」
その時、カイルが駆け寄ってきた。
その後ろからクナートが気乗りしない様子で随いてくる。
「カイル。ミラ」
ラースが静かに二人に向き直った。
「すみませんでした」
カイルが頭を下げた。
「ラース、これは私が……」
「話は神殿で聞く」
「その方が良さそうだな。連中が助っ人連れてくる前に……」
クナートが明後日の方向を向きながら、くぐもった声で言った。
声色を変えている。
「当然、君も一緒に護衛してくれるんだろうね、ウセル」
「お、俺はクナ……」
「今回の事もお前の差し金だろう」
「人聞きの悪いこと言うな!」
「じゃあ、この二人に大地系の魔法を使えなんて言ってないな」
「言った」
「申し開きは神殿長の前でしてもらおう」
「俺は神官じゃねーぞ!」
ラースはウセルの抗議を無視して背を向けた。
「行くぞ」
ラースの言葉にウセルが深い溜息を吐く。
カイルが見ているとウセルと目が合った。
「言っとくけどクナートってのは偽名じゃねーぞ」
「じゃあ、名字があるの!?」
ミラがカイルの脇からウセルを覗き込んだ。
庶民には名字がない。
あるとしたら王侯貴族と言う事だ。
「いや、村の名前だよ」
庶民は同名の別人がいたりして区別が必要な時だけ「何とか村の某」と名乗る。
村の名前……。
道理で聞いた事があると思った。
名乗るときに言うとはいえ村の名前が偽名でないかどうかは際どいところだが。
ウセルは「折角顔隠してたのに」とかなんとか言いながら顔に巻いていた布を取った。
「嘘! ラースにそっくり……」
ミラが声を上げた。
驚いた様子でウセルを見ている。
ウセルはラースを精悍にしたような面立ちだった。
普段は顔を隠してないのだろう。
肌は日に焼けて褐色だった。
「ラースの……弟? お兄さん?」
ミラがウセルの顔を見詰めながら訊ねた。
「あいつの偉そうな態度見りゃ分かるだろ。ま、双子だからあんまし関係ないけどな」
「ラースって双子だったんだ」
ミラがウセルに色々聞き始める。
楽しそうな様子のミラをカイルは冷めた目で見ていた。
ラースと同じ顔ってだけで……。
声に聞き覚えがあるはずだ。
ラースに似てる。
その時、前を歩いていたラースが振り返った。
「ミラ、すまないがウセルと話があるんだ」
「はーい」
「ウセル」
ラースがウセルを促した。
「分かったよ」
ウセルは返事をしてからミラとカイルに顔を寄せた。
「お前らレラスの神官だって言ってたよな」
「そうよ」
「ひょっとしてガブリエラも?」
「ガブリエラの事、知ってるの?」
「ウセル、何をしている」
「へいへい」
ウセルは叱られに行く子供のような表情でラースの方へと向かっていった。
「精悍なラースの顔って変な感じ」
「……ミラってラースの言う事は素直に聞くんだね」
カイルの言葉にミラは軽く肩を竦めた。
「ラースは特別だもん」
「どうして?」
「ケナイ山の話、聞いてるでしょ。山が吹き飛んだ巻き添えをくって村がいくつも無くなっちゃったって」
「うん」
「あれの犯人、私なの」
カイルは呆れてミラの顔を見た。
「つまんない冗談言うなよ。言いたくないなら無理に言わなくていいから」
「何よ。私には出来ないと思ってんの?」
「出来る出来ないは関係ないだろ」
「なんで?」
「魔法は術者の望んだことの具現化だぞ。望まない事は起きないんだよ」
「ケナイ山が無くなればいいって思わなかったってどうして言い切れるのよ」
「仮にケナイ山を吹き飛ばす事を望んだとしても、村が無くなればいいと思ってなければ村は無事なはずだ」
「村を消そうと思えば消せたって事じゃない」
「君がそんなこと考えるわけないだろ」
短い付き合いでもミラが人助けが好きで、他人に害意は向けないことくらいは分かった。
「どうして分かるのよ」
「分かるよ。それくらい」
「断言出来る?」
「出来るよ。なんならアスラル神に誓ってもいいけど?」
アスラル教の神官が『アスラル神に誓う』と言うのは本気で命を掛けるという意味である。
アスラル教の神官がアスラル神に誓った事を違えた場合、殺しても殺人罪に問われない。
だからアスラル神官は「神に誓う」という言葉はまず口にしない。
それくらい重い意味を持っているのだ。
ミラはしばらく黙って歩いていた。
「それでも、犯人は私よ……やってないけど」
それから低い声で呟いた。
カイルはなんと言えばいいのか分からなかったので黙っていた。
「あれ、魔物がやったの」
そう言われてみればケナイ山が吹き飛んだ日、さっきと同じ感じが……。
「山に魔物が埋まってたの。それが出てきて近くの村は全部……。私が行った時にはもうどの村も無くなってた」
そうだ!
山のように大きな魔物。
さっき引っ掛かったのはそれだったんだ。
あの魔物も山に埋まっていた。
あれと同じならば、やはりミラがやったのではない。
ミラは遠くを見るように空を仰いだ。
「私は魔物を倒しただけだけど、警備兵が来て犯人を出せって言って……あの時、あの辺りで魔法が使えたのは私だけだったから……」
「でも……魔物がやったんだろ。だったら死体が……」
「跡形も残って無かったのよ」
力が強すぎるのも考えものだ……。
「他の人からは私が魔法でやったようにしか見えなかったんでしょ。生き残ってた人もいなかったし」
「君がそんな事する理由ないじゃないか」
「それでも……誰も信じてくれなかった。ラース以外は」
ミラの声は沈んでいた。
いつもの元気が無い。
嘘ではないという事か……。
「警備兵に連れてかれそうになったところをラースが助けてくれたの」
嘘を言っているようには見えなかったものの、完全に信じる事も出来ないでいた。
ケナイ村の人間がミラをあっさり渡すとは思えなかったからだ。
四
なんと言おうかと考えていた時、微かな振動を感じたような気がした。
一拍おいて地面が揺れ始めた。
大地が海になってしまったかのように波打ち始める。
ラースとウセルはなんとか立っていたがカイルとミラは姿勢を崩した。
「うわ!」「きゃ!」
二人が転び掛ける。
ウセルは迷わずミラを抱き留めようとした。
が、カイルもミラを支えようとして手を伸ばしていた。
「うわ!」
カイルとミラは二人してウセルの方へ倒れ込んだ。
激しい揺れの最中、二人同時には支えきれずウセルも後ろへ引っくり返った。
揺れはすぐに収まった。
樹々の枝に僅かに余韻を残すのみだ。
「もしかして、また魔物が……」
カイルは心配になって辺りを見回した。
「違うわ。今のはただの地震よ。だけど、ホントは起きるはずないのに……」
地面に手を付いていたミラが眉を顰めた。
「誰かが起こしたの?」
カイルの問いにミラが首を振る。
「人が引き起こしたものじゃないけど、起きるはずもないのに……」
いつも強気なミラが不安そうな表情を浮かべていた。
「分かんない……どうしてこんな地震が起きたの?」
「……空間の振動だ」
ラースが静かに言った。
その言葉にミラは当惑したような顔でラースを見上げる。
ラースはそれ以上は何も言わずにミラに手を差し出した。
ミラがラースの手を借りて立ち上がる。
先を越されたウセルが悔しそうに指を鳴らしてからカイルが起きるのに手を貸した。
神殿へ帰ったカイルとミラは上級神官用の居間でラースにがっちりと説教された。
ウセルは神殿長の部屋へ行かされた。
「二人とも十日間の謹慎だ。自室と執務室以外への出入り禁止。いいね」
「食事は?」
ミラが訊ねた。
食堂と女性神官の居住区はかなり離れている。
食堂へ行けるとなれば実質的に神殿内は自由に歩けると言う事だ。
当然、神殿も簡単に抜け出せる。
「部屋へ持って行かせる」
ミラが残念そうな表情で溜息を吐いた。
「二人とも、部屋に戻りなさい」
「は~い。それじゃ……」
「待って」
カイルはミラを引き留めるとラースの顔を見上げた。
「ラース、あの魔物の事なんですけど……」
「どうかしたか?」
「倒れた後に教典の文句みたいなのを言ったんです」
カイルはミラの方を向いた。
「あれ、終末節だったよね?」
「お利口さんのあんたが言うならそうなんでしょ」
ミラがどうでも良さそうに答える。
カイルは「お利口さん」の部分が癇に障ったが言い返すのはやめておいた。
「そうか」
ラースは落ち着いた顔で頷いた。
驚いている様子は無い。
「あれ、倒しちゃいけなかったんですか?」
「いずれ誰かが倒していた。それが君達だっただけだよ」
「でも、あれはただの魔物じゃありませんよね。あれも、ヘメラのヤツも。あれはなんなんですか?」
ラースはしばらく黙ってカイルを見詰めていた。
やがて、
「封印獣の話は知ってるね」
と言った。
封印獣というのは教典の最初の方に出てくる神話である。
はるか昔、地上を七匹の強大な魔物が暴れ回っていた。
その魔物達が暴れ回っていたせいで地上のものは悉く破壊された。
見兼ねた大地母神が槍で魔物達を貫いて動きを止め、天空大神が自分の羽でそれらを覆った。
そして封印獣達は大きな山になった。
というのが封印獣の神話である。
「あれが封印獣なんですか?」
「あの部屋に資料がある。鍵は開けておくから後は自分で調べなさい」
ラースは部屋の隅の扉を指した。
いつも鍵が掛かっていた扉だ。
「あそこって資料室だったんだ。開いてるとこ見た事ないから掃除用具入れだと思ってた」
ミラがカイルの思いを代弁した。
ミラと同じこと考えてたなんて……。
カイルはちょっと複雑な気分になった。
謹慎期間、カイルは資料室に篭もって過ごした。
当然ながらミラは資料室に入ろうとする素振りすら見せなかった。
だが流石のミラも今回は神殿の中で大人しくしていた。
あれからすぐラースは中央神殿へ行ってしまったのだ。
理由は教えてもらえなかったがあの魔物のせいだという事くらいは見当が付いた。
ミラもそれが分かったからこそ大人しく謹慎していたのだろう。
ラースは三日ほどで戻ってきた。
ミラは勉強こそしてないものの、執務室でガブリエラとお喋りしたり仕事を手伝ったりして一日を過ごしていた。
七日目の朝、カイルが資料室から出てきたとき執務室にはミラしかいなかった。
「ラースとガブリエラは?」
「出掛けたわよ」
「そう。ちょっといい?」
「いいけど……あんた埃だらけよ。ずっとそん中にいたわけ?」
「うん」
「きったないわねぇ。お風呂入って綺麗にしてきなさいよ」
ミラに言われて自分の身体を見下ろしてみた。
確かに埃にまみれて白いはずの聖衣が灰色と茶色のまだらになっている。
「着替えてくるまでこの部屋の椅子に座っちゃダメ。敷物が汚れるでしょ」
「分かったよ」
仕方なく執務室から出ると自室へ向かった。
ミラの事だからどこかへ行ってしまっているかもしれないな……。
着替えながらそう思った。
だが執務室へ戻ってみるとミラは待っていてくれた。
「で? 話って?」
「封印獣の事、ちょっと引っ掛かる事があって調べてみたんだ」
「引っ掛かる? 何が?」
「場所が違うんだよ。僕らが倒した連中と神話の地名が。それにケナイとアイオンのは山くらいの大きさがあったけど、ヘメラのはそんなに大きなヤツじゃなかったんだ。死霊だったし」
「だから?」
「あれは封印獣じゃないんだよ」
「なに言ってんのよ。ラースが嘘吐くわけないでしょ。神官は嘘吐いちゃいけないの、忘れたの?」
ミラにだけは言われたくない台詞だ。
自分は詐欺まがいのこと平気で言うくせに……。
けど、神官の誓い、一応覚えてたんだな……。
アスラル教は信者には干渉しないが神官にはかなり厳しい規律を設けている。
神官になる時、誓わされる事の一つが「嘘を吐かない」である。
「嘘は吐いてないだろ」
「今、あれは封印獣じゃないって言ったじゃない。けどラースは封印獣だって……」
「言ってないよ」
「言ったわよ」
「言ってない。知ってるかって聞いただけだろ。僕があれがそうなのかって訊ねた時も返事はしなかったし」
「じゃあ、なんでラースは封印獣の話なんかしたのよ」
「あれが封印獣だって錯覚させるためだよ。ホントの事を教えたくない時によく使う手だよ」
「それで? 違ったらなんかマズい事でもあるの?」
ミラを話し相手に選んだのは失敗だったのかも……。
カイルは白い目でミラを見た。
とはいえ他に話せるような相手はいない。
ミラはバカではない。
悪知恵は働くのだから頭の回転は速い方だろう。
関心がある事に対しては。
興味がある事と無い事に対しての落差が大きいのだ。
「あの教典の文句、気にならないわけ?」
ミラは何も言わずに肩を竦めた。
興味がなければこうして大人しく話を聞いていたりはしないだろう。
気にならないわけではないがわざわざ調べようとも思わない、といったところか。
「あのさ、あの部屋の中の本、見た?」
「埃と蜘蛛の巣だらけの部屋の中に入って? 冗談でしょ」
思わず溜息が漏れる。
猫に話しているのと何が違うのか……。
一瞬、話を打ち切ろうかと思った。
だが、苦労して調べた事を話したい、という欲求の方が勝った。
何しろ長時間同じ姿勢でいたため死にそうなほど肩も腰も背中も痛い。
本の読み過ぎで頭痛も酷い。
そこまでして調べた事を自分の胸にしまっておくだけ、というのは嫌だったのだ。
「この部屋もだけどさ、ハイラル教の本、多いと思わない?」
「そう言われてみればそうかもね」
ミラはおざなりに部屋を見渡した。
「その次に多いのがセルケト教の本でしょ。他の教団も含めて魔物を片っ端から調べてみたんだ」
空間が揺れると言うより捩れるような感じだった。
何かが軋むような音が聞こえた気がした。
身体ごと捻られているようで胃の中のものが逆流しそうになる。
思わず前屈みになったカイルはミラの背に頭をぶつけてしまった。
顔を上げるとミラが青ざめた顔をしていた。
「これ、なに?」
苦しそうな声だ。
ミラも同じなのか?
その時、ミラがいきなりカイルの腕を掴んだ。
「ちょっと、あれ!」
ミラが空を指した。
樹が全て倒れて見晴らしが良くなった視界に青空が広がっている。
青空が裂け、その向こうに違う空間があった。
赤い空と黒い大地。
黒い影は異形の建物なのか、それとも林立する岩なのか……。
それが見えていたのはほんの一瞬だった。
だが幻覚などではない。
あれは確かに存在する。
「あれ……なんなの?」
ミラがカイルの腕を痛いくらいに強く握っていた。
声が震えているのはミラにも分かったからだろう。
あれは自分達がやった事だ。
カイル達は何か恐ろしい事をしてしまったのだ。
不意にまた声が聞こえてきた。
『……約束の子は大地に十字の杭を突き立て邪魔する者を抑えた。
もはや何人たりとも止めること能わず。
ただ……』
「うるさいわね!」
ミラが苛立たしげに魔物の屍骸を睨んだ。
「ミラ! 火事になるだろ!」
カイルが慌てて制止する。
ミラが得意な攻撃魔法が火炎系のものだと分かった以上、可燃物に囲まれている場所でそう簡単に使わせるわけにはいかない。
カイルはミラが出した大地の剣を見上げた。
十字の杭……。
確かに鍔がある為そう見えなくもない。
「もう消しちゃっても大丈夫よね」
ミラが言った。
だが消えなかった。
「嘘……。どうして?」
ミラは目を瞑ったり手を振ったりして消そうと試みる。
しかし、いくらやっても消えなかった。
「……どうして消えないの?」
ミラが怯えた声で呟く。
その時、倒木を飛び越えてさっきの男がやってきた。
落ち着いて見ても、やはりかなり怪しい。
しかし一応命の恩人だ。
「有難うございました」
カイルは頭を下げた。
「お陰で助かったわ」
ミラも笑顔で礼を言った。
「なーに言ってんだよ。倒したのはそっちだろ。俺はおまけおまけ。だから俺の事は誰にも内緒な」
ますます怪しい。
男はカイルとミラの泥だらけになった外套を見下ろした。
外套の止め金を見ると、
「アスラル教の神官か。顔を隠しておいて正解だったぜ」
男は低い声で呟いた。
汚れが目立つ色なので一般人はわざわざ白く染めた布で作った服は着ない。
富裕層以外で白を身に着けるのは神官くらいだ。
そしてアスラル教の場合、上級神官はそれぞれに対応した神徒(この場合は鳥)を象った止め金を肩の辺りに付けている。
カイルはミラを男から離れた場所へ引っ張っていった。
「何?」
「あの人、変だよ」
「どこが?」
「あの格好見ておかしいと思わないの? 顔隠してるし」
「きっと火傷か傷痕でもあるのよ」
「そんなのアスラル神殿に行けば治してもらえるだろ」
「宗教が違うんでしょ」
「少しは警戒する気ないの?」
「あんた、いちいち細かいわよ」
「ま、とにかく帰ろうぜ」
男が二人に声を掛けてきた。
「これだけの力があるなら送る必要は無さそうだけどな」
男がそう言って周囲を見回す。
いつの間にか土の剣は消えていた。
辺りの木々は薙ぎ倒され遠くまで見通せるようになってしまっている。
「俺は、クナート。吟遊詩人なんだ」
一瞬だが名前を言う前に間があった。
偽名か……。
そもそも吟遊詩人と言いながら楽器らしいものは持っていない。
でもクナートってどこかで聞いた気が……。
「私はミラ」
「……カイルです」
カイルとしては一緒に帰りたくはなかったのだがミラは気を許してしまったようだ。
名前はマズい、なんて言ってたくせにあっさり教えてしまっている。
……ったく!
折角魔物を倒しても、これじゃ全然気が抜けないじゃないか。
カイルは苛立たしい思いでミラを睨んだ。
魔物はなんとか倒したんですが、その後で誘拐されてしまいました、なんてラースに報告する羽目にでもなったら……。
カイルは頭を抱えた。
ミラの方はクナートと話し込んでいた。
どうしてこんな怪しげなヤツを信用出来るんだよ……。
確かにクナートの声はどこか信用させるような響きがある。
人を安心させる何かがあるのだ。
というか、どこかで聞いたような気が……。
「吟遊詩人なら、なんで楽器持ってないんですか?」
ミラの親しげな様子に、つい意地悪な質問をしてしまう。
「別に楽器なんかなくたっていいじゃない。歌うんだから」
「楽器は必要ないんだ」
クナートは手近な草を摘んだ。
それから布の下の口に草を当てると吹き始めた。
とても草笛とは思えない澄んだ音色が流れ出す。
二
思わず聴き惚れてしまってから、
「すっごーい! 上手~!」
はしゃぎ声で我に返った。
「それでどうやって歌うんですか?」
カイルの問いにクナートが苦笑しながら草笛を止めた。
「あんた、揚げ足取りしか出来ないわけ?」
「ホントのこと言っただけだろ」
「なに言って……」
「まぁまぁ」
クナートが二人の間に入った。
既に布で口を覆い直している。
「このくらい賢くなきゃお姫様の騎士は勤まらないだろ」
「こいつは騎士じゃなくて神官よ」
クナートはそれには答えなかった。
覆面の向こうで笑っていたのかもしれない。
来た時のように歩き回らなくて済む分、帰りの方が早いかと思ったのだが、そうはいかなかった。
魔物のせいで地形が変わってしまっていたからだ。
木々は倒れ、魔物が埋まっていた場所には大きな穴が空いていたり逆に土砂で盛り上がっていたり。
倒木をよじ登ったり隙間を通り抜けたりして三人はようやく町の近くまで辿り着いた。
カイルもミラも泥だらけだった。
その上、顔も手足も擦り傷だらけだ。
こんな状態でも無事に帰したと言えるだろうか……。
町に入ろうとしたところでクナートが足を止めた。
「あれ、どこの坊さんだ?」
言いながら既に物陰に隠れている。
ミラも子犬のようにクナートに随いていく。
仕方なくカイルも続いた。
物陰から町の真ん中の広場のようなところを覗くと白い外套を来た人間が数人立っている。
「アスラル教? でも、レラスの神官じゃないわね」
アスラル神官なのにレラス神殿から来たのではないとなると……。
「僕だ」
「え?」
「多分、中央神殿から来たんだと思う」
「中央神殿? なんでそんなとこから……」
「僕も訳ありの口なんだ。ちょっとあって……レラス神殿に身柄を預けられてたっていうか……きっと二日続けて無断で外出しちゃったから……」
「中央神殿に連れてかれたらどうなるの?」
「処刑される……と思う。良くて死ぬまでどこかに閉じ込められるか……」
ミラが呆れたようにカイルを見た。
「あんた、一体何やったのよ!」
カイルは答えられなかった。
数ヶ月前のアリシアの嫌悪の表情が、七年前の父の顔と重なる。
教えたらきっとミラも……。
「信じらんない! 優等生面して偉そうに説教しといて自分は人に言えないような事してたなんて!」
カイルは黙って俯いていた。
「なんで随いてきたのよ!」
「君に何かあったらラースが心配するだろ」
「人の事より自分の心配しなさいよ!」
ミラはカイルを怒鳴り付けるとクナートの方を向いた。
「私が行って話してくる。それでダメだったら逃げるしかないわね」
「逃げるって、そんな事したらラースが……!」
「あんたが逃げたからってラースは殺されたりしないわよ!」
「行く当てあるの?」
「無い」
ミラの即答にカイルは眩暈を覚えた。
「俺、あるぜ」
「ホント!? 良かった」
「冗談だろ!」
こんな怪しい人間を信用出来るわけない。
しかしカイルの言葉は無視された。
「とにかく行ってみる」
ミラはそう言うとクナートに顔を向けて、
「こいつ見張ってて。私が合図したらこいつ連れて逃げて」
と言った。
「あいよ」
「逆らうようなら殴ってでも止めて。殺さない程度になら何したっていいわ」
「ミラ!」
ミラは真顔だった。
クナートも異を唱える気配はない。
自分の顔から血の気が引くのが分かった。
「私は息がありさえすればどんな重傷でも治せるし、こいつだって意識があれば自分で治せるんだから遠慮なくやって」
「りょーかい」
ミラが行ってしまうとクナートがカイルの方を向いた。
「悪いな。可愛い女の子と可愛い男の子、どっちの頼みを優先するか、言うまでもないよな」
考えようによってはまともといえなくもない。
が、やはり怪しい。
「ま、そういうわけだから仲良くしようぜ。俺も子供に手を出したくはないし」
クナートが明るい口調で言った。
吟遊詩人などと言っていたがどう見ても戦士だ。
命令されれば殺しだって躊躇わずにやるだろう。
いくら治せると言っても痛みを感じないわけではないのだ。
カイルは攻撃魔法が使えないし腕力だって無い。
せいぜい障壁で身を守ることくらいしか出来ないのだ。
喧嘩といえるようなものはミラとの口論くらいしかした事がない。
考えてみたら本当に役立たずだな……。
神聖魔法以外の魔法に関しては神官候補生にも敵わない。
というか神官候補生になる資格さえない。
自分に出来る事は何も無い。
ただの役立たずだ。
なのに上級神官だなんて……。
「おい、あいつらアスラルの神官じゃねーぞ」
カイルの物思いはクナートの声で破られた。
顔を上げるとミラが男達に両脇から腕を掴まれている。
白い外套の下に紫色の聖衣と下履きが見えた。
あれは……!
ミラは男達の方へ向かって歩きながら、なんと言い訳しようか考えていた。
中央神殿と言えばアスラル教の全神殿を統括する神殿だ。
そこから来たとなれば当然ラースどころか神殿長より偉い。
下手に怒らせたらカイルやミラだけではなくラース達も危うくなる。
言うべき言葉を何も思い付かないまま男達の前まで来てしまった。
「あの……」
男達はいきなりミラを取り囲んだかと思うと腕を掴んだ。
男の白い外套の下に見えたのはアスラル教の白い聖衣ではなかった。
ミラは目を見張った。
赤みの強い紫色の聖衣と黒に近い色の下履き。
ハイラル教の神官!?
「もう一人はどこだ?」
「なに言ってんのよ! 放しなさいよ!」
ミラは男達の腕を振り払おうと藻掻いた。
だが腕力だけなら大人の男の方が強い。
「もう一人いるだろう」
男が重ねて言った。
三
「この……!」
ミラが魔法を使おうとした時、
「その手を離してもらいましょうか」
後ろから穏やかな声がした。
「ラース!」
ラースを見た男達が怯んだ。
ミラは男達の腕を振りほどいた。
「彼女はうちの神官です。用があるなら神殿長に話を通していただきましょう」
ラースの声はあくまでも静かだった。
男達は目顔でどうするか相談しているようだ。
ラースとミラの二人を相手に出来るだけの力量があるかどうか考えていたのかもしれない。
結論は出たようだ。
男達は何も言わずに引き上げていった。
聖職者だけあって悪役のような捨て台詞は吐かなかった。
「ふふんだ! 一昨日おいで」
ミラが男達の後ろ姿に舌を出した。
「ミラ! ラース!」
その時、カイルが駆け寄ってきた。
その後ろからクナートが気乗りしない様子で随いてくる。
「カイル。ミラ」
ラースが静かに二人に向き直った。
「すみませんでした」
カイルが頭を下げた。
「ラース、これは私が……」
「話は神殿で聞く」
「その方が良さそうだな。連中が助っ人連れてくる前に……」
クナートが明後日の方向を向きながら、くぐもった声で言った。
声色を変えている。
「当然、君も一緒に護衛してくれるんだろうね、ウセル」
「お、俺はクナ……」
「今回の事もお前の差し金だろう」
「人聞きの悪いこと言うな!」
「じゃあ、この二人に大地系の魔法を使えなんて言ってないな」
「言った」
「申し開きは神殿長の前でしてもらおう」
「俺は神官じゃねーぞ!」
ラースはウセルの抗議を無視して背を向けた。
「行くぞ」
ラースの言葉にウセルが深い溜息を吐く。
カイルが見ているとウセルと目が合った。
「言っとくけどクナートってのは偽名じゃねーぞ」
「じゃあ、名字があるの!?」
ミラがカイルの脇からウセルを覗き込んだ。
庶民には名字がない。
あるとしたら王侯貴族と言う事だ。
「いや、村の名前だよ」
庶民は同名の別人がいたりして区別が必要な時だけ「何とか村の某」と名乗る。
村の名前……。
道理で聞いた事があると思った。
名乗るときに言うとはいえ村の名前が偽名でないかどうかは際どいところだが。
ウセルは「折角顔隠してたのに」とかなんとか言いながら顔に巻いていた布を取った。
「嘘! ラースにそっくり……」
ミラが声を上げた。
驚いた様子でウセルを見ている。
ウセルはラースを精悍にしたような面立ちだった。
普段は顔を隠してないのだろう。
肌は日に焼けて褐色だった。
「ラースの……弟? お兄さん?」
ミラがウセルの顔を見詰めながら訊ねた。
「あいつの偉そうな態度見りゃ分かるだろ。ま、双子だからあんまし関係ないけどな」
「ラースって双子だったんだ」
ミラがウセルに色々聞き始める。
楽しそうな様子のミラをカイルは冷めた目で見ていた。
ラースと同じ顔ってだけで……。
声に聞き覚えがあるはずだ。
ラースに似てる。
その時、前を歩いていたラースが振り返った。
「ミラ、すまないがウセルと話があるんだ」
「はーい」
「ウセル」
ラースがウセルを促した。
「分かったよ」
ウセルは返事をしてからミラとカイルに顔を寄せた。
「お前らレラスの神官だって言ってたよな」
「そうよ」
「ひょっとしてガブリエラも?」
「ガブリエラの事、知ってるの?」
「ウセル、何をしている」
「へいへい」
ウセルは叱られに行く子供のような表情でラースの方へと向かっていった。
「精悍なラースの顔って変な感じ」
「……ミラってラースの言う事は素直に聞くんだね」
カイルの言葉にミラは軽く肩を竦めた。
「ラースは特別だもん」
「どうして?」
「ケナイ山の話、聞いてるでしょ。山が吹き飛んだ巻き添えをくって村がいくつも無くなっちゃったって」
「うん」
「あれの犯人、私なの」
カイルは呆れてミラの顔を見た。
「つまんない冗談言うなよ。言いたくないなら無理に言わなくていいから」
「何よ。私には出来ないと思ってんの?」
「出来る出来ないは関係ないだろ」
「なんで?」
「魔法は術者の望んだことの具現化だぞ。望まない事は起きないんだよ」
「ケナイ山が無くなればいいって思わなかったってどうして言い切れるのよ」
「仮にケナイ山を吹き飛ばす事を望んだとしても、村が無くなればいいと思ってなければ村は無事なはずだ」
「村を消そうと思えば消せたって事じゃない」
「君がそんなこと考えるわけないだろ」
短い付き合いでもミラが人助けが好きで、他人に害意は向けないことくらいは分かった。
「どうして分かるのよ」
「分かるよ。それくらい」
「断言出来る?」
「出来るよ。なんならアスラル神に誓ってもいいけど?」
アスラル教の神官が『アスラル神に誓う』と言うのは本気で命を掛けるという意味である。
アスラル教の神官がアスラル神に誓った事を違えた場合、殺しても殺人罪に問われない。
だからアスラル神官は「神に誓う」という言葉はまず口にしない。
それくらい重い意味を持っているのだ。
ミラはしばらく黙って歩いていた。
「それでも、犯人は私よ……やってないけど」
それから低い声で呟いた。
カイルはなんと言えばいいのか分からなかったので黙っていた。
「あれ、魔物がやったの」
そう言われてみればケナイ山が吹き飛んだ日、さっきと同じ感じが……。
「山に魔物が埋まってたの。それが出てきて近くの村は全部……。私が行った時にはもうどの村も無くなってた」
そうだ!
山のように大きな魔物。
さっき引っ掛かったのはそれだったんだ。
あの魔物も山に埋まっていた。
あれと同じならば、やはりミラがやったのではない。
ミラは遠くを見るように空を仰いだ。
「私は魔物を倒しただけだけど、警備兵が来て犯人を出せって言って……あの時、あの辺りで魔法が使えたのは私だけだったから……」
「でも……魔物がやったんだろ。だったら死体が……」
「跡形も残って無かったのよ」
力が強すぎるのも考えものだ……。
「他の人からは私が魔法でやったようにしか見えなかったんでしょ。生き残ってた人もいなかったし」
「君がそんな事する理由ないじゃないか」
「それでも……誰も信じてくれなかった。ラース以外は」
ミラの声は沈んでいた。
いつもの元気が無い。
嘘ではないという事か……。
「警備兵に連れてかれそうになったところをラースが助けてくれたの」
嘘を言っているようには見えなかったものの、完全に信じる事も出来ないでいた。
ケナイ村の人間がミラをあっさり渡すとは思えなかったからだ。
四
なんと言おうかと考えていた時、微かな振動を感じたような気がした。
一拍おいて地面が揺れ始めた。
大地が海になってしまったかのように波打ち始める。
ラースとウセルはなんとか立っていたがカイルとミラは姿勢を崩した。
「うわ!」「きゃ!」
二人が転び掛ける。
ウセルは迷わずミラを抱き留めようとした。
が、カイルもミラを支えようとして手を伸ばしていた。
「うわ!」
カイルとミラは二人してウセルの方へ倒れ込んだ。
激しい揺れの最中、二人同時には支えきれずウセルも後ろへ引っくり返った。
揺れはすぐに収まった。
樹々の枝に僅かに余韻を残すのみだ。
「もしかして、また魔物が……」
カイルは心配になって辺りを見回した。
「違うわ。今のはただの地震よ。だけど、ホントは起きるはずないのに……」
地面に手を付いていたミラが眉を顰めた。
「誰かが起こしたの?」
カイルの問いにミラが首を振る。
「人が引き起こしたものじゃないけど、起きるはずもないのに……」
いつも強気なミラが不安そうな表情を浮かべていた。
「分かんない……どうしてこんな地震が起きたの?」
「……空間の振動だ」
ラースが静かに言った。
その言葉にミラは当惑したような顔でラースを見上げる。
ラースはそれ以上は何も言わずにミラに手を差し出した。
ミラがラースの手を借りて立ち上がる。
先を越されたウセルが悔しそうに指を鳴らしてからカイルが起きるのに手を貸した。
神殿へ帰ったカイルとミラは上級神官用の居間でラースにがっちりと説教された。
ウセルは神殿長の部屋へ行かされた。
「二人とも十日間の謹慎だ。自室と執務室以外への出入り禁止。いいね」
「食事は?」
ミラが訊ねた。
食堂と女性神官の居住区はかなり離れている。
食堂へ行けるとなれば実質的に神殿内は自由に歩けると言う事だ。
当然、神殿も簡単に抜け出せる。
「部屋へ持って行かせる」
ミラが残念そうな表情で溜息を吐いた。
「二人とも、部屋に戻りなさい」
「は~い。それじゃ……」
「待って」
カイルはミラを引き留めるとラースの顔を見上げた。
「ラース、あの魔物の事なんですけど……」
「どうかしたか?」
「倒れた後に教典の文句みたいなのを言ったんです」
カイルはミラの方を向いた。
「あれ、終末節だったよね?」
「お利口さんのあんたが言うならそうなんでしょ」
ミラがどうでも良さそうに答える。
カイルは「お利口さん」の部分が癇に障ったが言い返すのはやめておいた。
「そうか」
ラースは落ち着いた顔で頷いた。
驚いている様子は無い。
「あれ、倒しちゃいけなかったんですか?」
「いずれ誰かが倒していた。それが君達だっただけだよ」
「でも、あれはただの魔物じゃありませんよね。あれも、ヘメラのヤツも。あれはなんなんですか?」
ラースはしばらく黙ってカイルを見詰めていた。
やがて、
「封印獣の話は知ってるね」
と言った。
封印獣というのは教典の最初の方に出てくる神話である。
はるか昔、地上を七匹の強大な魔物が暴れ回っていた。
その魔物達が暴れ回っていたせいで地上のものは悉く破壊された。
見兼ねた大地母神が槍で魔物達を貫いて動きを止め、天空大神が自分の羽でそれらを覆った。
そして封印獣達は大きな山になった。
というのが封印獣の神話である。
「あれが封印獣なんですか?」
「あの部屋に資料がある。鍵は開けておくから後は自分で調べなさい」
ラースは部屋の隅の扉を指した。
いつも鍵が掛かっていた扉だ。
「あそこって資料室だったんだ。開いてるとこ見た事ないから掃除用具入れだと思ってた」
ミラがカイルの思いを代弁した。
ミラと同じこと考えてたなんて……。
カイルはちょっと複雑な気分になった。
謹慎期間、カイルは資料室に篭もって過ごした。
当然ながらミラは資料室に入ろうとする素振りすら見せなかった。
だが流石のミラも今回は神殿の中で大人しくしていた。
あれからすぐラースは中央神殿へ行ってしまったのだ。
理由は教えてもらえなかったがあの魔物のせいだという事くらいは見当が付いた。
ミラもそれが分かったからこそ大人しく謹慎していたのだろう。
ラースは三日ほどで戻ってきた。
ミラは勉強こそしてないものの、執務室でガブリエラとお喋りしたり仕事を手伝ったりして一日を過ごしていた。
七日目の朝、カイルが資料室から出てきたとき執務室にはミラしかいなかった。
「ラースとガブリエラは?」
「出掛けたわよ」
「そう。ちょっといい?」
「いいけど……あんた埃だらけよ。ずっとそん中にいたわけ?」
「うん」
「きったないわねぇ。お風呂入って綺麗にしてきなさいよ」
ミラに言われて自分の身体を見下ろしてみた。
確かに埃にまみれて白いはずの聖衣が灰色と茶色のまだらになっている。
「着替えてくるまでこの部屋の椅子に座っちゃダメ。敷物が汚れるでしょ」
「分かったよ」
仕方なく執務室から出ると自室へ向かった。
ミラの事だからどこかへ行ってしまっているかもしれないな……。
着替えながらそう思った。
だが執務室へ戻ってみるとミラは待っていてくれた。
「で? 話って?」
「封印獣の事、ちょっと引っ掛かる事があって調べてみたんだ」
「引っ掛かる? 何が?」
「場所が違うんだよ。僕らが倒した連中と神話の地名が。それにケナイとアイオンのは山くらいの大きさがあったけど、ヘメラのはそんなに大きなヤツじゃなかったんだ。死霊だったし」
「だから?」
「あれは封印獣じゃないんだよ」
「なに言ってんのよ。ラースが嘘吐くわけないでしょ。神官は嘘吐いちゃいけないの、忘れたの?」
ミラにだけは言われたくない台詞だ。
自分は詐欺まがいのこと平気で言うくせに……。
けど、神官の誓い、一応覚えてたんだな……。
アスラル教は信者には干渉しないが神官にはかなり厳しい規律を設けている。
神官になる時、誓わされる事の一つが「嘘を吐かない」である。
「嘘は吐いてないだろ」
「今、あれは封印獣じゃないって言ったじゃない。けどラースは封印獣だって……」
「言ってないよ」
「言ったわよ」
「言ってない。知ってるかって聞いただけだろ。僕があれがそうなのかって訊ねた時も返事はしなかったし」
「じゃあ、なんでラースは封印獣の話なんかしたのよ」
「あれが封印獣だって錯覚させるためだよ。ホントの事を教えたくない時によく使う手だよ」
「それで? 違ったらなんかマズい事でもあるの?」
ミラを話し相手に選んだのは失敗だったのかも……。
カイルは白い目でミラを見た。
とはいえ他に話せるような相手はいない。
ミラはバカではない。
悪知恵は働くのだから頭の回転は速い方だろう。
関心がある事に対しては。
興味がある事と無い事に対しての落差が大きいのだ。
「あの教典の文句、気にならないわけ?」
ミラは何も言わずに肩を竦めた。
興味がなければこうして大人しく話を聞いていたりはしないだろう。
気にならないわけではないがわざわざ調べようとも思わない、といったところか。
「あのさ、あの部屋の中の本、見た?」
「埃と蜘蛛の巣だらけの部屋の中に入って? 冗談でしょ」
思わず溜息が漏れる。
猫に話しているのと何が違うのか……。
一瞬、話を打ち切ろうかと思った。
だが、苦労して調べた事を話したい、という欲求の方が勝った。
何しろ長時間同じ姿勢でいたため死にそうなほど肩も腰も背中も痛い。
本の読み過ぎで頭痛も酷い。
そこまでして調べた事を自分の胸にしまっておくだけ、というのは嫌だったのだ。
「この部屋もだけどさ、ハイラル教の本、多いと思わない?」
「そう言われてみればそうかもね」
ミラはおざなりに部屋を見渡した。
「その次に多いのがセルケト教の本でしょ。他の教団も含めて魔物を片っ端から調べてみたんだ」