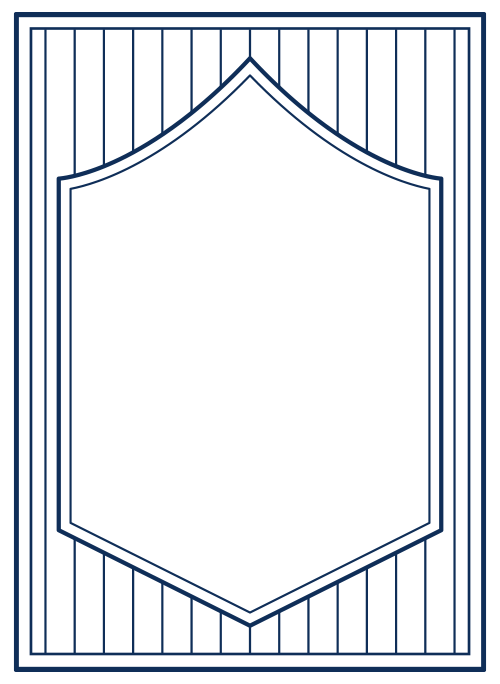一
眩しい光が徐々に収まっていった。
光の中から森の樹々が姿を現し始める。
樹々の間に少年が立っていた。
顔を背けて腕で光を遮り、目をきつく閉じていた。
膝までの長さの飾り気のない白い聖衣が風に揺れている。
ベルトには鳥の模様が彫られていた。
アスラル教の神官の紋章である。
レラスにあるアスラル神殿の中で最年少の下級神官であるカイルだった。
下級とは言えまだ十五歳にも関わらず既に神官であるというのはかなり若い。
普通、神官候補生から下級神官になれるのは早くても二十代だ。
魔物を退治した。
倒すことが出来た。
死霊だから除霊しただけ、と言うのは取り敢えずおいておこう。
安堵の溜息を吐いた時、辺りに鐘の音が鳴り響いた。
地響きを思わせる低い音が樹々を震わせ周囲に木霊する。
カイルは驚いて辺りを見回した。
ここは山の中だ。
鐘など近くにはない。
見ると、とっくに消えているはずの光が球体になってカイルの目の前に浮かんでいた。
鐘の音は光の中から聞こえてくる。
カイルは思わずその球体を凝視した。
光の中から鐘の音と共に声が響いてくる。
『……を指し示した。
其は七つの封印を施された神と約束の子との契約の証。
約束の子が作り出した白い光が闇のように辺りを覆い隠す時、封印は解かれ……』
低く、それでいてよく通る声。
「これは……教典?」
魔物が教典を?
そんなはずは……。
『……と共に目覚めの鐘が鳴り響き、封印は永き眠りより解き放たれる。
今、此処に神と約束の子との契約の序次が始まる……』
「違う、みたいだけど……」
教典に載っている文章とは少し食い違いがある。
魔物の言葉が終わり光も消えた。
一体なんだったんだろう。
ただの魔物じゃなかったのか?
不安を拭いきれないものの時間も気になる。
カイルは踵を返すと麓の村へと向かった。
カイルは足早に山を下っていった。
勝手な行動を取ったことでラースに叱られるかもしれない。
けどアリシアはきっと喜んでくれるはずだ。
アリシアというのはこの山の麓にあるヘメラ村の薬師の見習いである。今年十七歳になった。
綺麗な容姿にも関わらず気さくな性格のため皆から好かれている。
ヘメラ村は山に囲まれた盆地にある。
全戸併せて五十戸あるかないだ。
どの家も板の壁に漆喰を塗った板葺きの屋根の単純な作りである。
屋根の上には温度対策のため枯れ草を載せていた。
簡素な作りの家が集まっている向こうに畑や果樹園が見える。
この村には薬師しかいない。
そのため薬師の手に負えない病人やケガ人がいる時はレラスの神殿に神官の派遣を要請している。
薬師で対処出来ないような者は下級神官でも治せない重症者が多い。
だから本来ならこの手の訪問に下級神官が同行することはないのだがカイルだけは別だった。
異例の若さと特別扱い。
カイルに対する他の神官の風当たりは強かった。
意地悪をされたりするわけではない。
しかし親しくしてくれる者もいない。
影口を言われているのも知っている。
神官同士の楽しそうなお喋りもカイルには縁がない。
普段、声を掛けてくれるのは上級神官のラースとガブリエラくらいだ。
上級神官を神聖名ではなく名前で呼ぶ。
本来なら上級神官同士でなければ許されない事を許されているのもカイルが妬まれる原因の一つだ。
ただラースとガブリエラは上司であって友達ではない。
唯一友達と言える相手がアリシアだった。
アリシアはいつも優しい。
ラースやガブリエラは忙しいから雑談はほとんど出来ない。
お喋りが出来るのはアリシアくらいなのだ。
村へ来るといつも帰る前にお茶を入れてくれて美味しい手作りお菓子も出してくれる。
そして二人で他愛ないお喋りをする。
ここへは要請があった時しか来られない。
病人やケガ人が出るのを願うのは良くないことなのだが、それでもこの村で神官が必要になれば良いのに、と、つい思ってしまう。
この村へくるのがカイルの唯一の楽しみなのだ。
二
「お兄さんが?」
問い返したカイルにアリシアが目に涙を浮かべて頷く。
治療を終えた後、カイルはアリシアの家でお茶を飲んでいた。
アリシアにいつものような元気がないので尋ねてみると、兄が魔物に殺されたと告げられたのだ。
なんと言って慰めればいいのか分からなかった。
アリシアは父親と友達も魔物に殺されたと聞いている。
魔物は全くいなくなる事もないが、どこにでもいるというわけでもない。
たまに現れても大抵はすぐに誰かが退治してしまうから滅多に出会す事は無い。
だが、この村の近くに住む魔物は大昔から退治されないままだった。
いる事は分かっているのに何故か退治されていないのだ。
「父さんもあいつに殺されて今度は兄さんまで……あんなヤツ、いなくなっちゃえばいいのに!」
アリシアが顔を覆って泣き始めると母親が飛んできた。
「アリシア……すみませんね、見苦しいところをお見せしてしまいまして……」
「いえ……」
「ほら、アリシア。あっちへ行って顔を洗ってきなさい」
アリシアは母親に追い立てられるようにしてい部屋を出ていった。
その場に一人取り残されたカイルはアリシアの家を出た。
そして誰にも内緒で山へ来たのだ。
なんとか魔物を退治することが出来た。それも一人で。
早くアリシアに報告したい。
逸る気持ちに山を下るカイルの足は次第に速くなっていった。
山を下りきった時には駆け足になっていた。
村の入口でアリシアの姿を見付けると、
「アリシア!」
カイルは頬を上気させて駆け寄った。
「カイル! どこに行ってたの? 心配したのよ」
「ごめん。山へ行ってたんだ」
「山? 魔物がいて危ないのに……」
「そいつを倒しに行ってきたんだ」
「倒しにって……退治しちゃったの!?」
「うん!」
「なんて事するのよ!」
いきなり怒鳴りつけられたカイルは面食らった。
「アリシアが、あんな奴いなくなればって……」
カイルは狼狽えながら答えた。
「あたしはそんなこと頼んでないわ!」
「でも……」
「あれはこの村の守り神なのよ!」
「え……?」
「あたしが頼んだわけじゃないんだから……あたしのせいにしないでよ!」
アリシアはそれだけ言うと逃げるように駆けていってしまった。
嫌悪と恐怖の表情を浮かべ、カイルの方が魔物であるかのようなアリシアの眼差し。
とんでもない事をしてしまったのか?
怖くてその場から動けなかった。
またラースに迷惑を掛けてしまったのだろうか。
ラースにも愛想を尽かされてしまうかもしれない。
もしかしたら今度こそ……。
「カイル」
不意に背後からラースの声がした。
カイルは振り向くと恐る恐るラースを見上げた。
落ち着いた静かな物腰と、貴族の出身ではないかと思わせるような気品のある整った顔立ち。
ラースは優しい面差しの青年で穏やかな性格のため神殿中の神官達から慕われている。
カイルは子供の頃、ラースに命を救われた。
そしてラースが上級神官をしていたレラスの神殿に引き取られて神官見習いになった。
カイルは神官見習いになるための条件を満たしていないから本来なら神殿内の施設で育てられるところなのだが特例として神官見習いにしてもらうことが出来た。
おそらくラースが手を打ってくれたのだろう。
ラースに恩返しをしたい。
役に立ちたい。
認めてもらいたい。
その一心で必死に魔法の修行をしてきて、ようやく下級神官になれたのだが……。
「どうした? 急にいなくなるから……」
「ラース……」
カイルは俯いて拳を握った。
それから覚悟を決めて顔を上げるとラースに事情を話した。
「そうか」
ラースは落ち着き払ったまま頷いた。
「そいつは何か言わなかったか?」
その問いにカイルは動揺を隠せなかった。
唇が震え思わず眼を伏せてしまう。
ラースはカイルの肩に優しく手を置いた。
「分かった。もういい、帰ろう」
ラースはそう言うと歩き出した。
カイルが歩いていると突如こめかみに衝撃を受けてよろめいた。
ラースは、すかさずカイルを支えると辺りに視線を走らせた。
カイルが地面に目を落とすと赤い染みの付いた石が落ちていた。
こめかみの辺りが疼き生暖かいものが頬を伝って滴り落ちた。
敵意を向けられるのはこれが初めてではない。
傷の痛みには耐えられる。
けれど胸の痛みには慣れる事が出来なかった。
ヘメラは山間の盆地にあるため、どこへ行くにも一旦山を登らなければならない。
人の出入りが少ないので街道までは獣道ではないかと思えるほど道幅が狭いところを通る。
道を覆い隠すように小枝が張り出している。
神殿へ帰り着く頃にはいつも髪には葉が絡まり、顔は擦り傷だらけ、外套は緑の染みや鉤裂きが出来ていた。
「僕、いけない事しちゃったんですか?」
カイルは思い切って訊ねた。
「我々があいつを放置していたのは何もアスラル教の教えがあるからじゃないんだ」
ラースが落ち着いた声で答えた。
アスラル教では生き物はすべて平等である。
猫が鼠を食べ、人間が動物の肉を食べるのが悪い事でないのと同様に魔物が人を食べるのも悪い事とは見做さない。
ただし牛が狼に抵抗して返り討ちにする事があるように、人間も大人しく魔物にやられる必要はない。
食べるのと同じように反撃も認められているのだ。
だから退治は禁止されていない。
依頼があれば神官が退治に出向く。
そもそもアスラル教はいくつもある宗教のうちの一つでしかない。
他所の宗教の信者や無神論者がアスラル教の教えに従う必要はない。
これはあくまでアスラル教団内での話だ。
「あの村では、あいつが人を食うのを黙認する代わりに毎年豊作にしてもらってた。それで退治させてもらえなかったんだ」
「じゃあ、やっぱり退治しちゃいけなかったんですか?」
「人の命と引き替えに豊作にしてもらうのは正しい事か?」
「神に祈願する時も捧げ物をしますけど……」
「それは自分の財産だ。あの村の人間が襲われるのは他所者が犠牲にならなかった年だけなんだ。村の人間は魔物がいる場所には近寄らないから」
「…………」
「過去には親切や腕試しで退治しに行った者達がいたんだ」
「それなら、なんで……」
カイルが神官になれたのは事情があったからで魔物退治に関しては下級神官どころか神官見習いにすら及ばない。
カイルに倒せるものに負けるような弱い者が退治に行くとは思えない。
「村に魔物の場所を聞きに行ったとき薬を盛られたりして妨害されたらしい。全員あれの餌にされた」
ラースの厳しい表情が、あの村のやり方を快く思っていない事を物語っていた。
ラースがいつもあの村に行くのを渋っていたのはこういう理由だったようだ。
「済んだ事を気にする必要はない」
ラースは穏やかにそう言った。
三
山を越え、道が緩やかになる頃、周りの樹々はまばらになり鳥の声も山とは違う種類のものに変わる。
視界が開け、地平線まで続く草の海が風にそよぐ。
山脈の麓にあるレラスのアスラル神殿は新緑の森を背景に白く輝いていた。
かなり大きな建物なのだが周囲にほとんど木が生えていないのと、空と接するほど高くて東西にどこまでも続く壮麗な山脈の前では小さく見える。
建物自体は大きいが教義で質素を旨としているため造りは簡素だ。
それでも白亜造りの太い柱や高い天井には堂々とした威厳があった。
一歩間違えれば味もそっけもなくなりそうなところを柱や壁の彫刻や壁画が救っている。
これらは神に祈願したい事はあるが捧げるものがない、という芸術家の手になるものが多い。
だから彫刻や壁画などの様式は様々で統一性がない。
彫刻や壁画の維持管理や修復なども捧げ物がないという者がやっていた。
祈願のために奉納した物を受け取るのは神であって教団ではないから金である必要はないのだ。
正面を入ってすぐの広間が祭壇のある祈祷所である。
誰でも出入り自由だ。
祈願の儀式も神官抜きでやりたければ勝手にやれる。
なんなら異教徒が使っても文句は言わない。
神官に対する規律は厳しいが、神官以外の者に対しては信者だろうが異教徒だろうが完全な不干渉を貫いていた。
神官達は祭壇の奥にある通路の先にある居住区に住んでいる。
神殿の内部の静寂を秘めた冷気がここは神聖な場所であることを告げていた。
一ヶ月後、カイルは上級神官になっていた。
アスラル教の神官というのは魔法で人を助けられる人間しかなれない。
そのため上の階級に上がるには昇格試験を受ける必要があるし途中を飛ばして上級になる事も出来ない。
ところがカイルは本来受けるべき試験を受けないまま上級になっていた。
本来なら中級で学ぶべき事を学んでいない。
その為、中級神官の分と上級神官の勉強をまとめてやっていた。
勉強は仕事の合間にやらなければならない。
仕事といっても下級神官を指導する事は出来ないが。
いくら神官とはいえ子供の指導を素直に聞けるほど人間が出来ている者は少ないからだ。
その日、カイルはラースやガブリエラと共に上級神官の執務室にいた。
ガブリエラは長く伸ばした栗色の巻き毛を一つに結んで背中に垂らしている。
優しげで整った顔立ちの女性だ。
いつも落ち着いていて優美なので皆から好意を持たれている。
ラースやガブリエラもカイル同様、上級神官としては異例の若さだった。
もちろんカイルと違って実力は伴っているが。
執務室は大して広くない上に壁のほとんどを本棚が占拠して上級神官用の図書室と化していた。
以前は飾り気のない殺風景な部屋だったらしい。
本棚以外には実用一点張りのテーブルくらいしかなかった。
貴重な書物が置いてあるからという理由で飲食はおろか、水の入った花瓶を置く事すら禁止されている。
だがガブリエラは扉に花瓶を取り付けさせ乾燥した花を飾っていた。
木製の固く座り心地の悪い椅子にもガブリエラが造った可愛い刺繍が施された敷物が置かれている。
ラースは苦笑しただけで何も言わなかったそうだが他の二人の上級神官は明らかに居心地悪そうだった。
元々この部屋に来る事の少なかった神殿長は全く来なくなったらしい。
ガブリエラはテーブルにも可愛い模様の布を掛けようとしたがラース以外の上級神官達の反対にあって断念したそうだ。
ガブリエラがいない時に年配の上級神官は「これだから女の子は……」とかなんとか言っていた。
ガブリエラはラースと同い年だからもう二十代半ばだ。
女の子、という年齢ではない。
だが初老の上級神官から見れば女の子ということになるのだろう。
扉の脇には上級神官の白い外套が四着掛かっていた。
神殿長と神官長のものはそれぞれの執務室に置いてある。
その日、カイルは執務室でガブリエラに勉強を教わっており、ラースは何かの書類を書いていた。
ガブリエラの指摘で文字を目で追っていた時、背筋に悪寒が走った。
一瞬遅れてラースとガブリエラも顔を上げた。
カイルは反射的に立ち上がっていた。
そのまま部屋を飛び出し、食堂へ駆け込んだ。
神官達が一斉にカイルの方を向いた。
何事かとこちらへ視線を向けてくる神官達を無視して窓へ駆け寄る。
嫌な感じはますます強くなっていた。
「ダメだ!」
カイルが叫ぶのと同時に空気が震え空間が揺れた。
山の稜線に閃光が走り、わずかに遅れて地面が振動する。
誰かの、あるいは何かの思念が叩き付けるようにカイルを襲った。
訳の分からない強力な意志。
身体を貫く精神波に思わずよろめいた。
一瞬、誰かの哄笑が聞こえたような気がした。
倒れ掛けたカイルを後ろに来ていたラースが受け止める。
周りを見るとラースも神官達も何ともなさそうな顔をしていた。
青ざめて額に汗を浮かべているのはカイルだけだ。
「ラース」
「ケナイか」
「え? 見えるんですか?」
カイルは思わず外に目を向けた。
ケナイはここから歩いて五日は掛かるし間に山脈があるから肉眼では見えないはずだ。
「見る必要はないのよ。知っているから」
カイルの問いにガブリエラが答えた。
まるで意味が分からなかったが二人ともそれ以上は教えてくれなかった。
「行ってくる」
ラースはそれだけ言うと食堂から出ていってしまった。
二日後、その日は昼だというのに外は薄暗く、神殿内では明かりを灯していた。
空を灰色の物が覆っている。
雲ではない。
陽光を遮っているのは上空に巻き上げられた塵である。
空からは土や小石が雨のように降ってきている。
二日経ち、空高く舞い上がった小石などがようやく地上へ戻ってき始めたのだ。
あのとき何があったのかは分からない。
だが閃光と、振動や衝撃波から考えて大爆発が起きて大量の土砂が吹き飛んだのだろう。
「ケナイ山が崩れて村がいくつか埋まったってホントか?」
外を眺めていたカイルは人の声で我に返った。
「崩れたんじゃないよ。消し飛んだらしい」
「セネフィシャル様が帰ってくれば詳しい話が聞けるかもな」
セネフィシャルというのはラースの神聖名だ。
上級神官には神聖名が与えられる。
要は肩書きだ。
「でもさ……」
神官達は話しながら通り過ぎていった。
ケナイ……。
四
ケナイ山は山脈から半島のように突き出している大きな山だった。
その山の麓にはケナイ村がある。
ケナイ村はカイルが生まれたラウル村の近くだ。
まだ村にいた頃、何度かケナイ村に行った事がある。
カイルは物心が付いた頃には既に回復魔法が使えた。
教えてくれる者がいないにも関わらず魔法が使えるというのはかなり珍しい。
特にそれが小さな子供となると尚更だ。
近くに神殿が無く、医者もいない村で回復魔法が使えたカイルは大事にされていた。
同じようにケナイ村にもカイルと同い年で魔法が使える子がいた。
魔法……と言っていいのかどうかはよく分からないが。
彼女が祈ると日照りの村に雨が振り、雨が続いて困っている村の雨が止み、農作物が虫の被害に遭っている村から虫がいなくなったらしい。
らしい、と言うのは実際に見る事が出来るほど近い場所ではその手の災害は起きなかったので噂でしか知らないからだ。
ケナイ村周辺は祈るまでもなく豊穣が約束されていた。
日照りも水害もなく、魔物の姿も見掛けなくなり流行病も起きない。
近隣の村も恩恵を受けていた。
カイルの住んでいたラウル村も例外ではない。
あの子が生まれる二年くらい前からあの辺りは凶作にならなくなった。
適度に雨が降り、硬かった大地は何時の間にか柔らかくなり土壌が豊かになっていたらしい。
裕福とまではいかなくても食うに困る事はなくなった。
「お前は、あと半年早く生まれてたら口減らしのために殺されてたかもしれないんだよ」
母はよくそう言っていた。
彼女はそれくらい神聖な存在であり〝アスラル神の化身〟などと言われてすごく大切にされていた。
話をした事は無かったけれど綺麗な子だったのは覚えている。
華奢で、ちょっと現実離れした透明感のある容姿の子だった。
朝日を受けて光る硝子細工の花といったところだろうか。
それも夏に咲く大輪のものではなく、早春に森の中でひっそりと咲く小さく可憐な花だ。
あの子は大丈夫だったかな……。
無くなってしまった村がケナイ村でなければいい、なんて考えるのはいけない事だろうか。
けど……。
ケナイ山まではここから歩いて五日は掛かる。
それほど遠くで起きた爆発の閃光と振動がここまで到達したのだとしたら周囲は相当な衝撃波に襲われたはずだ。
近くの村は無事では済まなかっただろう。
数日後、カイルが神殿の廊下を歩いていると、
「カイル」
ガブリエラに声を掛けられた。
「なんですか?」
「いらっしゃい。会わせたい人がいるの」
ガブリエラの後に随いて神殿長の部屋へ入るとラースの隣に少女が立っていた。
ケナイ村のあの子だった。
「カイル、ミラだ」
一ヶ月後。
神殿の脇に火柱が上がった。
雲まで焼き付きそうなほど高く上がった太い火柱は始まりと同様に突然消える。
神殿の外で下級神官達が魔術の練習をしていた。
今のは中級神官が下級神官に手本を見せたのだ。
窓にもたれたカイルはその様子を漫然と眺めていた。
ここは廊下の端に近い場所である。
林立する柱の位置関係のせいか廊下を通る人達からの死角になりやすいのだ。
誰かが話し掛けてくるわけではないが人の眼に晒されるのはわずらわしい。
何より、こんな所でぼんやりしている姿を見られたら何を言われるか……。
完全に死角になっているわけではないから誰にも見られないと言うわけではないが。
「……って言えばさぁ、ケナイ山の話……」
すぐ側で話し声がした。
見ると下級神官が何人か窓際に集まって女性神官の練習を眺めている。
カイルはともかく彼らは見付かったら怒られるので窓辺に身を隠すようにして見ていた。
「ああ、キシャル様がやったんだって?」
キシャルというのはケナイ村にいたあの子の神聖名である。
上級神官以外の者は上級神官を神聖名で呼ばなければならない。
神官見習いどころか下級神官すら経ずにいきなり上級神官になるというのはカイルの飛び級も霞む特別扱いである。
確かに神の化身と言われていただけあって魔法の力は相当なものなのだが。
「ホントなのか? それ」
「お尋ね者らしいぜ。だから名前も変えたって」
ミラはケナイ村にいたときマイラと呼ばれていた。
だが今ここでマイラと呼ばれているのは大分前にケナイから来た中級神官の少女だった。
今のマイラは子供の頃から修行を積んでいたので中級神官になったのは順当だ。
「そんなのがなんでここにいるんだよ」
「さあな。けどミラ様って神殿長に贔屓されてるから」
「やりたい放題だもんな」
ミラは仕事もせずに毎日のように無断で外出しており、中級、下級神官や神官見習達から反感を買っていた。
しかし注意するべき上級神官達はミラの事を黙認している。
「中級神官の一人が見掛ねて神殿長に直訴したらしいぜ。けど、ミラ様の事は口出し無用って取り合ってもらえなかったって」
窓の外に炎の球が浮かんだ。
一抱え以上ありそうな大きな球は、急速に収縮していった。
限界まで小さくなった球が眩しい光を放って爆発した。
火炎系最強の攻撃魔法テル・シュトラ。
本来ならその熱により辺りのものは全て溶けてしまう。
だが、これは練習なので周りに障壁が張ってある。
熱や爆風が外に漏れる事はない。
「さすが、マイラ様だな」
マイラもカイルと同い年で今年十五歳。
カイルはもうすぐ十六になるが。
この神殿は他の神殿と較べてかなり平均年齢が低い。
一度その事をラースに訊ねてみたら、
「この辺は魔法に長けた者が多いんだろう」
という答えが返ってきた。
けど、中級神官の一人はグース村から来たって言ってたよな……。
グースならイラシの神殿の方が近い。
他にも遠い所から来ている者が何人かいる。
そして遠くから来ているのは全て若年者だ。
その中で一番若いのがカイル、ミラ、マイラである。
ミラが上級神官になるのと時を同じくしてマイラは中級神官になった。
マイラの場合そろそろ中級神官になるだろうと言われていたから妥当なのだが、一つ不審な点があるとすれば中級神官になるための試験の時期がいつもとは違った事だろうか。
中級、上級の神官の数は決まっていて上の階級に上がるためには試験がある。
上の階級の神官と魔法対決して、勝った方が昇格し、負けた方が降格する。
しかしマイラが中級神官になった時は違った。
中級神官は誰一人降格せず、その中の一人が中央神殿に行ってしまったのだ。
中央神殿というのはアスラル教を統括する神殿で特に魔法に長けた者が揃っている。
カイルとミラが上級神官になった時もそうだった。
上級神官は中級神官に降格せず中央神殿に異動になったのだ。
それ以前にミラとカイルは昇格試験を受けていないが。
カイルが廊下を歩いていると神官長が大声で怒鳴っているのが聞こえてきた。
「ミラ! どこへ行く!」
「どこだっていいでしょ!」
「仕事をしなさい!」
「冗談じゃないわよ!」
「ミラ!」
ミラと神官長の怒鳴りあいが廊下に響きわたっていた。
これが硝子の花の正体である。
カイルの幻想はガブリエラに引き合わされた直後、粉々に砕かれた。
それはもう一欠片の破片すらも残さず塵となって消えた。
幻想とは壊れるためにあるのだ。
元々こっちが勝手に想像してただけだけど……。
幼さが残っているものの可憐で整った顔立ち。
ガブリエラはもう大人で「美人」だから可愛いという点ではミラは間違いなくこの神殿で一番の美少女だ。
だが見た目は可愛いのに性格は最悪だった。
眩しい光が徐々に収まっていった。
光の中から森の樹々が姿を現し始める。
樹々の間に少年が立っていた。
顔を背けて腕で光を遮り、目をきつく閉じていた。
膝までの長さの飾り気のない白い聖衣が風に揺れている。
ベルトには鳥の模様が彫られていた。
アスラル教の神官の紋章である。
レラスにあるアスラル神殿の中で最年少の下級神官であるカイルだった。
下級とは言えまだ十五歳にも関わらず既に神官であるというのはかなり若い。
普通、神官候補生から下級神官になれるのは早くても二十代だ。
魔物を退治した。
倒すことが出来た。
死霊だから除霊しただけ、と言うのは取り敢えずおいておこう。
安堵の溜息を吐いた時、辺りに鐘の音が鳴り響いた。
地響きを思わせる低い音が樹々を震わせ周囲に木霊する。
カイルは驚いて辺りを見回した。
ここは山の中だ。
鐘など近くにはない。
見ると、とっくに消えているはずの光が球体になってカイルの目の前に浮かんでいた。
鐘の音は光の中から聞こえてくる。
カイルは思わずその球体を凝視した。
光の中から鐘の音と共に声が響いてくる。
『……を指し示した。
其は七つの封印を施された神と約束の子との契約の証。
約束の子が作り出した白い光が闇のように辺りを覆い隠す時、封印は解かれ……』
低く、それでいてよく通る声。
「これは……教典?」
魔物が教典を?
そんなはずは……。
『……と共に目覚めの鐘が鳴り響き、封印は永き眠りより解き放たれる。
今、此処に神と約束の子との契約の序次が始まる……』
「違う、みたいだけど……」
教典に載っている文章とは少し食い違いがある。
魔物の言葉が終わり光も消えた。
一体なんだったんだろう。
ただの魔物じゃなかったのか?
不安を拭いきれないものの時間も気になる。
カイルは踵を返すと麓の村へと向かった。
カイルは足早に山を下っていった。
勝手な行動を取ったことでラースに叱られるかもしれない。
けどアリシアはきっと喜んでくれるはずだ。
アリシアというのはこの山の麓にあるヘメラ村の薬師の見習いである。今年十七歳になった。
綺麗な容姿にも関わらず気さくな性格のため皆から好かれている。
ヘメラ村は山に囲まれた盆地にある。
全戸併せて五十戸あるかないだ。
どの家も板の壁に漆喰を塗った板葺きの屋根の単純な作りである。
屋根の上には温度対策のため枯れ草を載せていた。
簡素な作りの家が集まっている向こうに畑や果樹園が見える。
この村には薬師しかいない。
そのため薬師の手に負えない病人やケガ人がいる時はレラスの神殿に神官の派遣を要請している。
薬師で対処出来ないような者は下級神官でも治せない重症者が多い。
だから本来ならこの手の訪問に下級神官が同行することはないのだがカイルだけは別だった。
異例の若さと特別扱い。
カイルに対する他の神官の風当たりは強かった。
意地悪をされたりするわけではない。
しかし親しくしてくれる者もいない。
影口を言われているのも知っている。
神官同士の楽しそうなお喋りもカイルには縁がない。
普段、声を掛けてくれるのは上級神官のラースとガブリエラくらいだ。
上級神官を神聖名ではなく名前で呼ぶ。
本来なら上級神官同士でなければ許されない事を許されているのもカイルが妬まれる原因の一つだ。
ただラースとガブリエラは上司であって友達ではない。
唯一友達と言える相手がアリシアだった。
アリシアはいつも優しい。
ラースやガブリエラは忙しいから雑談はほとんど出来ない。
お喋りが出来るのはアリシアくらいなのだ。
村へ来るといつも帰る前にお茶を入れてくれて美味しい手作りお菓子も出してくれる。
そして二人で他愛ないお喋りをする。
ここへは要請があった時しか来られない。
病人やケガ人が出るのを願うのは良くないことなのだが、それでもこの村で神官が必要になれば良いのに、と、つい思ってしまう。
この村へくるのがカイルの唯一の楽しみなのだ。
二
「お兄さんが?」
問い返したカイルにアリシアが目に涙を浮かべて頷く。
治療を終えた後、カイルはアリシアの家でお茶を飲んでいた。
アリシアにいつものような元気がないので尋ねてみると、兄が魔物に殺されたと告げられたのだ。
なんと言って慰めればいいのか分からなかった。
アリシアは父親と友達も魔物に殺されたと聞いている。
魔物は全くいなくなる事もないが、どこにでもいるというわけでもない。
たまに現れても大抵はすぐに誰かが退治してしまうから滅多に出会す事は無い。
だが、この村の近くに住む魔物は大昔から退治されないままだった。
いる事は分かっているのに何故か退治されていないのだ。
「父さんもあいつに殺されて今度は兄さんまで……あんなヤツ、いなくなっちゃえばいいのに!」
アリシアが顔を覆って泣き始めると母親が飛んできた。
「アリシア……すみませんね、見苦しいところをお見せしてしまいまして……」
「いえ……」
「ほら、アリシア。あっちへ行って顔を洗ってきなさい」
アリシアは母親に追い立てられるようにしてい部屋を出ていった。
その場に一人取り残されたカイルはアリシアの家を出た。
そして誰にも内緒で山へ来たのだ。
なんとか魔物を退治することが出来た。それも一人で。
早くアリシアに報告したい。
逸る気持ちに山を下るカイルの足は次第に速くなっていった。
山を下りきった時には駆け足になっていた。
村の入口でアリシアの姿を見付けると、
「アリシア!」
カイルは頬を上気させて駆け寄った。
「カイル! どこに行ってたの? 心配したのよ」
「ごめん。山へ行ってたんだ」
「山? 魔物がいて危ないのに……」
「そいつを倒しに行ってきたんだ」
「倒しにって……退治しちゃったの!?」
「うん!」
「なんて事するのよ!」
いきなり怒鳴りつけられたカイルは面食らった。
「アリシアが、あんな奴いなくなればって……」
カイルは狼狽えながら答えた。
「あたしはそんなこと頼んでないわ!」
「でも……」
「あれはこの村の守り神なのよ!」
「え……?」
「あたしが頼んだわけじゃないんだから……あたしのせいにしないでよ!」
アリシアはそれだけ言うと逃げるように駆けていってしまった。
嫌悪と恐怖の表情を浮かべ、カイルの方が魔物であるかのようなアリシアの眼差し。
とんでもない事をしてしまったのか?
怖くてその場から動けなかった。
またラースに迷惑を掛けてしまったのだろうか。
ラースにも愛想を尽かされてしまうかもしれない。
もしかしたら今度こそ……。
「カイル」
不意に背後からラースの声がした。
カイルは振り向くと恐る恐るラースを見上げた。
落ち着いた静かな物腰と、貴族の出身ではないかと思わせるような気品のある整った顔立ち。
ラースは優しい面差しの青年で穏やかな性格のため神殿中の神官達から慕われている。
カイルは子供の頃、ラースに命を救われた。
そしてラースが上級神官をしていたレラスの神殿に引き取られて神官見習いになった。
カイルは神官見習いになるための条件を満たしていないから本来なら神殿内の施設で育てられるところなのだが特例として神官見習いにしてもらうことが出来た。
おそらくラースが手を打ってくれたのだろう。
ラースに恩返しをしたい。
役に立ちたい。
認めてもらいたい。
その一心で必死に魔法の修行をしてきて、ようやく下級神官になれたのだが……。
「どうした? 急にいなくなるから……」
「ラース……」
カイルは俯いて拳を握った。
それから覚悟を決めて顔を上げるとラースに事情を話した。
「そうか」
ラースは落ち着き払ったまま頷いた。
「そいつは何か言わなかったか?」
その問いにカイルは動揺を隠せなかった。
唇が震え思わず眼を伏せてしまう。
ラースはカイルの肩に優しく手を置いた。
「分かった。もういい、帰ろう」
ラースはそう言うと歩き出した。
カイルが歩いていると突如こめかみに衝撃を受けてよろめいた。
ラースは、すかさずカイルを支えると辺りに視線を走らせた。
カイルが地面に目を落とすと赤い染みの付いた石が落ちていた。
こめかみの辺りが疼き生暖かいものが頬を伝って滴り落ちた。
敵意を向けられるのはこれが初めてではない。
傷の痛みには耐えられる。
けれど胸の痛みには慣れる事が出来なかった。
ヘメラは山間の盆地にあるため、どこへ行くにも一旦山を登らなければならない。
人の出入りが少ないので街道までは獣道ではないかと思えるほど道幅が狭いところを通る。
道を覆い隠すように小枝が張り出している。
神殿へ帰り着く頃にはいつも髪には葉が絡まり、顔は擦り傷だらけ、外套は緑の染みや鉤裂きが出来ていた。
「僕、いけない事しちゃったんですか?」
カイルは思い切って訊ねた。
「我々があいつを放置していたのは何もアスラル教の教えがあるからじゃないんだ」
ラースが落ち着いた声で答えた。
アスラル教では生き物はすべて平等である。
猫が鼠を食べ、人間が動物の肉を食べるのが悪い事でないのと同様に魔物が人を食べるのも悪い事とは見做さない。
ただし牛が狼に抵抗して返り討ちにする事があるように、人間も大人しく魔物にやられる必要はない。
食べるのと同じように反撃も認められているのだ。
だから退治は禁止されていない。
依頼があれば神官が退治に出向く。
そもそもアスラル教はいくつもある宗教のうちの一つでしかない。
他所の宗教の信者や無神論者がアスラル教の教えに従う必要はない。
これはあくまでアスラル教団内での話だ。
「あの村では、あいつが人を食うのを黙認する代わりに毎年豊作にしてもらってた。それで退治させてもらえなかったんだ」
「じゃあ、やっぱり退治しちゃいけなかったんですか?」
「人の命と引き替えに豊作にしてもらうのは正しい事か?」
「神に祈願する時も捧げ物をしますけど……」
「それは自分の財産だ。あの村の人間が襲われるのは他所者が犠牲にならなかった年だけなんだ。村の人間は魔物がいる場所には近寄らないから」
「…………」
「過去には親切や腕試しで退治しに行った者達がいたんだ」
「それなら、なんで……」
カイルが神官になれたのは事情があったからで魔物退治に関しては下級神官どころか神官見習いにすら及ばない。
カイルに倒せるものに負けるような弱い者が退治に行くとは思えない。
「村に魔物の場所を聞きに行ったとき薬を盛られたりして妨害されたらしい。全員あれの餌にされた」
ラースの厳しい表情が、あの村のやり方を快く思っていない事を物語っていた。
ラースがいつもあの村に行くのを渋っていたのはこういう理由だったようだ。
「済んだ事を気にする必要はない」
ラースは穏やかにそう言った。
三
山を越え、道が緩やかになる頃、周りの樹々はまばらになり鳥の声も山とは違う種類のものに変わる。
視界が開け、地平線まで続く草の海が風にそよぐ。
山脈の麓にあるレラスのアスラル神殿は新緑の森を背景に白く輝いていた。
かなり大きな建物なのだが周囲にほとんど木が生えていないのと、空と接するほど高くて東西にどこまでも続く壮麗な山脈の前では小さく見える。
建物自体は大きいが教義で質素を旨としているため造りは簡素だ。
それでも白亜造りの太い柱や高い天井には堂々とした威厳があった。
一歩間違えれば味もそっけもなくなりそうなところを柱や壁の彫刻や壁画が救っている。
これらは神に祈願したい事はあるが捧げるものがない、という芸術家の手になるものが多い。
だから彫刻や壁画などの様式は様々で統一性がない。
彫刻や壁画の維持管理や修復なども捧げ物がないという者がやっていた。
祈願のために奉納した物を受け取るのは神であって教団ではないから金である必要はないのだ。
正面を入ってすぐの広間が祭壇のある祈祷所である。
誰でも出入り自由だ。
祈願の儀式も神官抜きでやりたければ勝手にやれる。
なんなら異教徒が使っても文句は言わない。
神官に対する規律は厳しいが、神官以外の者に対しては信者だろうが異教徒だろうが完全な不干渉を貫いていた。
神官達は祭壇の奥にある通路の先にある居住区に住んでいる。
神殿の内部の静寂を秘めた冷気がここは神聖な場所であることを告げていた。
一ヶ月後、カイルは上級神官になっていた。
アスラル教の神官というのは魔法で人を助けられる人間しかなれない。
そのため上の階級に上がるには昇格試験を受ける必要があるし途中を飛ばして上級になる事も出来ない。
ところがカイルは本来受けるべき試験を受けないまま上級になっていた。
本来なら中級で学ぶべき事を学んでいない。
その為、中級神官の分と上級神官の勉強をまとめてやっていた。
勉強は仕事の合間にやらなければならない。
仕事といっても下級神官を指導する事は出来ないが。
いくら神官とはいえ子供の指導を素直に聞けるほど人間が出来ている者は少ないからだ。
その日、カイルはラースやガブリエラと共に上級神官の執務室にいた。
ガブリエラは長く伸ばした栗色の巻き毛を一つに結んで背中に垂らしている。
優しげで整った顔立ちの女性だ。
いつも落ち着いていて優美なので皆から好意を持たれている。
ラースやガブリエラもカイル同様、上級神官としては異例の若さだった。
もちろんカイルと違って実力は伴っているが。
執務室は大して広くない上に壁のほとんどを本棚が占拠して上級神官用の図書室と化していた。
以前は飾り気のない殺風景な部屋だったらしい。
本棚以外には実用一点張りのテーブルくらいしかなかった。
貴重な書物が置いてあるからという理由で飲食はおろか、水の入った花瓶を置く事すら禁止されている。
だがガブリエラは扉に花瓶を取り付けさせ乾燥した花を飾っていた。
木製の固く座り心地の悪い椅子にもガブリエラが造った可愛い刺繍が施された敷物が置かれている。
ラースは苦笑しただけで何も言わなかったそうだが他の二人の上級神官は明らかに居心地悪そうだった。
元々この部屋に来る事の少なかった神殿長は全く来なくなったらしい。
ガブリエラはテーブルにも可愛い模様の布を掛けようとしたがラース以外の上級神官達の反対にあって断念したそうだ。
ガブリエラがいない時に年配の上級神官は「これだから女の子は……」とかなんとか言っていた。
ガブリエラはラースと同い年だからもう二十代半ばだ。
女の子、という年齢ではない。
だが初老の上級神官から見れば女の子ということになるのだろう。
扉の脇には上級神官の白い外套が四着掛かっていた。
神殿長と神官長のものはそれぞれの執務室に置いてある。
その日、カイルは執務室でガブリエラに勉強を教わっており、ラースは何かの書類を書いていた。
ガブリエラの指摘で文字を目で追っていた時、背筋に悪寒が走った。
一瞬遅れてラースとガブリエラも顔を上げた。
カイルは反射的に立ち上がっていた。
そのまま部屋を飛び出し、食堂へ駆け込んだ。
神官達が一斉にカイルの方を向いた。
何事かとこちらへ視線を向けてくる神官達を無視して窓へ駆け寄る。
嫌な感じはますます強くなっていた。
「ダメだ!」
カイルが叫ぶのと同時に空気が震え空間が揺れた。
山の稜線に閃光が走り、わずかに遅れて地面が振動する。
誰かの、あるいは何かの思念が叩き付けるようにカイルを襲った。
訳の分からない強力な意志。
身体を貫く精神波に思わずよろめいた。
一瞬、誰かの哄笑が聞こえたような気がした。
倒れ掛けたカイルを後ろに来ていたラースが受け止める。
周りを見るとラースも神官達も何ともなさそうな顔をしていた。
青ざめて額に汗を浮かべているのはカイルだけだ。
「ラース」
「ケナイか」
「え? 見えるんですか?」
カイルは思わず外に目を向けた。
ケナイはここから歩いて五日は掛かるし間に山脈があるから肉眼では見えないはずだ。
「見る必要はないのよ。知っているから」
カイルの問いにガブリエラが答えた。
まるで意味が分からなかったが二人ともそれ以上は教えてくれなかった。
「行ってくる」
ラースはそれだけ言うと食堂から出ていってしまった。
二日後、その日は昼だというのに外は薄暗く、神殿内では明かりを灯していた。
空を灰色の物が覆っている。
雲ではない。
陽光を遮っているのは上空に巻き上げられた塵である。
空からは土や小石が雨のように降ってきている。
二日経ち、空高く舞い上がった小石などがようやく地上へ戻ってき始めたのだ。
あのとき何があったのかは分からない。
だが閃光と、振動や衝撃波から考えて大爆発が起きて大量の土砂が吹き飛んだのだろう。
「ケナイ山が崩れて村がいくつか埋まったってホントか?」
外を眺めていたカイルは人の声で我に返った。
「崩れたんじゃないよ。消し飛んだらしい」
「セネフィシャル様が帰ってくれば詳しい話が聞けるかもな」
セネフィシャルというのはラースの神聖名だ。
上級神官には神聖名が与えられる。
要は肩書きだ。
「でもさ……」
神官達は話しながら通り過ぎていった。
ケナイ……。
四
ケナイ山は山脈から半島のように突き出している大きな山だった。
その山の麓にはケナイ村がある。
ケナイ村はカイルが生まれたラウル村の近くだ。
まだ村にいた頃、何度かケナイ村に行った事がある。
カイルは物心が付いた頃には既に回復魔法が使えた。
教えてくれる者がいないにも関わらず魔法が使えるというのはかなり珍しい。
特にそれが小さな子供となると尚更だ。
近くに神殿が無く、医者もいない村で回復魔法が使えたカイルは大事にされていた。
同じようにケナイ村にもカイルと同い年で魔法が使える子がいた。
魔法……と言っていいのかどうかはよく分からないが。
彼女が祈ると日照りの村に雨が振り、雨が続いて困っている村の雨が止み、農作物が虫の被害に遭っている村から虫がいなくなったらしい。
らしい、と言うのは実際に見る事が出来るほど近い場所ではその手の災害は起きなかったので噂でしか知らないからだ。
ケナイ村周辺は祈るまでもなく豊穣が約束されていた。
日照りも水害もなく、魔物の姿も見掛けなくなり流行病も起きない。
近隣の村も恩恵を受けていた。
カイルの住んでいたラウル村も例外ではない。
あの子が生まれる二年くらい前からあの辺りは凶作にならなくなった。
適度に雨が降り、硬かった大地は何時の間にか柔らかくなり土壌が豊かになっていたらしい。
裕福とまではいかなくても食うに困る事はなくなった。
「お前は、あと半年早く生まれてたら口減らしのために殺されてたかもしれないんだよ」
母はよくそう言っていた。
彼女はそれくらい神聖な存在であり〝アスラル神の化身〟などと言われてすごく大切にされていた。
話をした事は無かったけれど綺麗な子だったのは覚えている。
華奢で、ちょっと現実離れした透明感のある容姿の子だった。
朝日を受けて光る硝子細工の花といったところだろうか。
それも夏に咲く大輪のものではなく、早春に森の中でひっそりと咲く小さく可憐な花だ。
あの子は大丈夫だったかな……。
無くなってしまった村がケナイ村でなければいい、なんて考えるのはいけない事だろうか。
けど……。
ケナイ山まではここから歩いて五日は掛かる。
それほど遠くで起きた爆発の閃光と振動がここまで到達したのだとしたら周囲は相当な衝撃波に襲われたはずだ。
近くの村は無事では済まなかっただろう。
数日後、カイルが神殿の廊下を歩いていると、
「カイル」
ガブリエラに声を掛けられた。
「なんですか?」
「いらっしゃい。会わせたい人がいるの」
ガブリエラの後に随いて神殿長の部屋へ入るとラースの隣に少女が立っていた。
ケナイ村のあの子だった。
「カイル、ミラだ」
一ヶ月後。
神殿の脇に火柱が上がった。
雲まで焼き付きそうなほど高く上がった太い火柱は始まりと同様に突然消える。
神殿の外で下級神官達が魔術の練習をしていた。
今のは中級神官が下級神官に手本を見せたのだ。
窓にもたれたカイルはその様子を漫然と眺めていた。
ここは廊下の端に近い場所である。
林立する柱の位置関係のせいか廊下を通る人達からの死角になりやすいのだ。
誰かが話し掛けてくるわけではないが人の眼に晒されるのはわずらわしい。
何より、こんな所でぼんやりしている姿を見られたら何を言われるか……。
完全に死角になっているわけではないから誰にも見られないと言うわけではないが。
「……って言えばさぁ、ケナイ山の話……」
すぐ側で話し声がした。
見ると下級神官が何人か窓際に集まって女性神官の練習を眺めている。
カイルはともかく彼らは見付かったら怒られるので窓辺に身を隠すようにして見ていた。
「ああ、キシャル様がやったんだって?」
キシャルというのはケナイ村にいたあの子の神聖名である。
上級神官以外の者は上級神官を神聖名で呼ばなければならない。
神官見習いどころか下級神官すら経ずにいきなり上級神官になるというのはカイルの飛び級も霞む特別扱いである。
確かに神の化身と言われていただけあって魔法の力は相当なものなのだが。
「ホントなのか? それ」
「お尋ね者らしいぜ。だから名前も変えたって」
ミラはケナイ村にいたときマイラと呼ばれていた。
だが今ここでマイラと呼ばれているのは大分前にケナイから来た中級神官の少女だった。
今のマイラは子供の頃から修行を積んでいたので中級神官になったのは順当だ。
「そんなのがなんでここにいるんだよ」
「さあな。けどミラ様って神殿長に贔屓されてるから」
「やりたい放題だもんな」
ミラは仕事もせずに毎日のように無断で外出しており、中級、下級神官や神官見習達から反感を買っていた。
しかし注意するべき上級神官達はミラの事を黙認している。
「中級神官の一人が見掛ねて神殿長に直訴したらしいぜ。けど、ミラ様の事は口出し無用って取り合ってもらえなかったって」
窓の外に炎の球が浮かんだ。
一抱え以上ありそうな大きな球は、急速に収縮していった。
限界まで小さくなった球が眩しい光を放って爆発した。
火炎系最強の攻撃魔法テル・シュトラ。
本来ならその熱により辺りのものは全て溶けてしまう。
だが、これは練習なので周りに障壁が張ってある。
熱や爆風が外に漏れる事はない。
「さすが、マイラ様だな」
マイラもカイルと同い年で今年十五歳。
カイルはもうすぐ十六になるが。
この神殿は他の神殿と較べてかなり平均年齢が低い。
一度その事をラースに訊ねてみたら、
「この辺は魔法に長けた者が多いんだろう」
という答えが返ってきた。
けど、中級神官の一人はグース村から来たって言ってたよな……。
グースならイラシの神殿の方が近い。
他にも遠い所から来ている者が何人かいる。
そして遠くから来ているのは全て若年者だ。
その中で一番若いのがカイル、ミラ、マイラである。
ミラが上級神官になるのと時を同じくしてマイラは中級神官になった。
マイラの場合そろそろ中級神官になるだろうと言われていたから妥当なのだが、一つ不審な点があるとすれば中級神官になるための試験の時期がいつもとは違った事だろうか。
中級、上級の神官の数は決まっていて上の階級に上がるためには試験がある。
上の階級の神官と魔法対決して、勝った方が昇格し、負けた方が降格する。
しかしマイラが中級神官になった時は違った。
中級神官は誰一人降格せず、その中の一人が中央神殿に行ってしまったのだ。
中央神殿というのはアスラル教を統括する神殿で特に魔法に長けた者が揃っている。
カイルとミラが上級神官になった時もそうだった。
上級神官は中級神官に降格せず中央神殿に異動になったのだ。
それ以前にミラとカイルは昇格試験を受けていないが。
カイルが廊下を歩いていると神官長が大声で怒鳴っているのが聞こえてきた。
「ミラ! どこへ行く!」
「どこだっていいでしょ!」
「仕事をしなさい!」
「冗談じゃないわよ!」
「ミラ!」
ミラと神官長の怒鳴りあいが廊下に響きわたっていた。
これが硝子の花の正体である。
カイルの幻想はガブリエラに引き合わされた直後、粉々に砕かれた。
それはもう一欠片の破片すらも残さず塵となって消えた。
幻想とは壊れるためにあるのだ。
元々こっちが勝手に想像してただけだけど……。
幼さが残っているものの可憐で整った顔立ち。
ガブリエラはもう大人で「美人」だから可愛いという点ではミラは間違いなくこの神殿で一番の美少女だ。
だが見た目は可愛いのに性格は最悪だった。