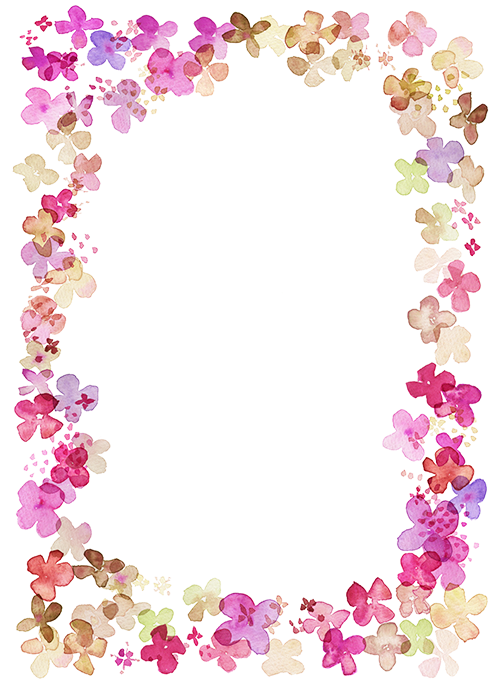ティエンは言葉通り、三日間あれこれと私の世話を焼いてくれた。食事を作ってくれたり、布団を干してくれたり、途中からは私もすっかり頼っていた。
しなやかな鞭のような後ろ姿を見ていると、亡くなった両親のことを思い出した。その力強い背中は両親とはまるで違うのに、ずっと側にいた人をみつめているような安心感があった。
そういえば彼の作るコンソメスープは、母が作ってくれた味と同じだ。それに気づいた頃には、私の具合は良くなり、彼は伯父の元に帰る日になっていた。
空港のロビーで、ティエンは私を振り向いた。
「体はもう大丈夫ですか?」
「はい。せめて見送りくらいはさせてください」
私は深く頭を下げて、彼を見上げる。
「ティエンさん、本当にありがとうございました。お礼の手紙を書きましたので、伯父にも渡してくれますか?」
「ええ……」
手紙を渡すと、ティエンはふいに黙った。
時刻はそろそろ夕暮れ時で、空を赤い陽が飾っている。
その最中で、ティエンは腕を伸ばして私を引き寄せた。
「……ティエンさん」
次の瞬間、私は彼の腕の中にいた。
「ごめんなさい。若い女性にすることではないとわかっているのですが」
温かくて、大きな腕の中だった。そこはずっと私が馴染んだ匂いがした。
ティエンはどこか切ないような声で言う。
「いつでも呼んでください。助けに行きますから。また手紙も書いてください」
私は彼の肩越しに月を仰いで、ああ、やっぱりそうなのだと思った。
空に月が上がり始めるのが、奇妙にゆっくりと見えた。輝かしい金色の光を瞳に映して、体の感覚が鈍くなる。
落ちるように意識を失う直前、ティエンの輪郭が揺らめいたのが見えた。
実は気づいていたことが一つある。
伯父は、本当はいないということ。
両親が亡くなる前も、その後も、私は一度も伯父の姿を見たことがなかった。
学校の書類を整えるため戸籍を取り寄せたことがあったけれど、父にも母にも兄弟はいなかった。
でも怖いとか、嫌だとか、そんなことは思ったことがなかった。
私が両親と暮らした家に手紙を出すと、必ず返ってくる手紙。いつも私を心配して、私の成長を喜んでくれた「誰か」。
それが伯父でなかったとして、一体何がいけないというのだろう?
目覚めると、自室の布団の中だった。カーテンが開いていて、少し欠けた月が見える。
私はため息をついて言葉を口にする。
「ごめんなさい。倒れたりして」
「いいえ。それくらい、月華さんは月に影響されやすいんですよ」
風で舞い上がるカーテンを背に、枕元にティエンが座っていた。
私は困りながら問いかける。
「大丈夫ですか? 飛行機、行ってしまいましたか?」
「それでよかったんです」
ティエンの輪郭がまた揺れた。彼の声も少し、震えているようだった。
「月華さんに隠し事をし続けるよりは、その方がよかった」
私は起き上がって、彼を見上げる。
手を伸ばして彼の手を取ると、彼はびくりと緊張した。
「……天駆(ティエン・クー)」
そう呼びかけると、彼は目を見張る。
「忘れていてごめんなさい。家族で暮らしていた頃は、ずっとあなたのことをそう呼んでいたのに」
私は彼の手に頭をつけて、そのぬくもりに涙を落とす。
「ありがとう。両親が亡くなった後も私の側にいてくれて。手紙を送ってくれて。今まで気づかなくてごめんなさい」
彼は私の涙を拭って、首を横に振った。
ゆらりとティエンの輪郭が乱れた。
月明かりを浴びて、姿が変わっていく。黒い服は黒い毛皮に、すっと通る鼻筋は突き出た鼻に、その金色の瞳だけはそのままに。
「これが、私が伯父になりきれなかった理由です。私は月灯りを浴びると、時々姿を変えてしまう」
それは私のよく知る天駆だった。黒毛の立派な体躯で、お行儀よく座っている。
「人の姿になったり、犬の姿になったり。中途半端な魔法でしょう?」
天駆はもどかしそうに顔を伏せる。
「今回は三日間しか人になれなかった。いつも月華さんの助けになれたらいいのに」
彼が沈痛な面持ちになったのを見て、私は苦笑する。
「私だって月の満ち欠けに左右されている人間の一人です。人が操れない不思議な力だってあるのでしょう」
私は腕を広げて、今度は私から天駆を抱きしめる。
「月華さん?」
「それより大事なことをあなたに言っておかなければ。……私にとってあなたは」
温かなその体を抱きしめられる。その喜びが、触れたところから伝わればいい。
「家族であり、私をいつも守ってくれる騎士で」
顔を上げて、私は笑う。
「奇跡そのものだと思っています」
その首に頬を寄せて、私はぎゅっと彼を抱きしめた。
天駆は私の頬に、とんとんと二回自らの頬を当てた。私が泣いているとき、笑っているとき、彼を抱きしめると、いつも彼はその仕草をした。
どういう意味なのだろうと私が首を傾げると、天駆は優しい声で答えた。
「はい。私のお姫様」
月明かりが降り注ぐ。
それは私と彼を変えてしまうもの。けれど私たちをつないでくれた奇跡の光。
愛犬と魔法にかかった日常は、きっと永く続いていく。
しなやかな鞭のような後ろ姿を見ていると、亡くなった両親のことを思い出した。その力強い背中は両親とはまるで違うのに、ずっと側にいた人をみつめているような安心感があった。
そういえば彼の作るコンソメスープは、母が作ってくれた味と同じだ。それに気づいた頃には、私の具合は良くなり、彼は伯父の元に帰る日になっていた。
空港のロビーで、ティエンは私を振り向いた。
「体はもう大丈夫ですか?」
「はい。せめて見送りくらいはさせてください」
私は深く頭を下げて、彼を見上げる。
「ティエンさん、本当にありがとうございました。お礼の手紙を書きましたので、伯父にも渡してくれますか?」
「ええ……」
手紙を渡すと、ティエンはふいに黙った。
時刻はそろそろ夕暮れ時で、空を赤い陽が飾っている。
その最中で、ティエンは腕を伸ばして私を引き寄せた。
「……ティエンさん」
次の瞬間、私は彼の腕の中にいた。
「ごめんなさい。若い女性にすることではないとわかっているのですが」
温かくて、大きな腕の中だった。そこはずっと私が馴染んだ匂いがした。
ティエンはどこか切ないような声で言う。
「いつでも呼んでください。助けに行きますから。また手紙も書いてください」
私は彼の肩越しに月を仰いで、ああ、やっぱりそうなのだと思った。
空に月が上がり始めるのが、奇妙にゆっくりと見えた。輝かしい金色の光を瞳に映して、体の感覚が鈍くなる。
落ちるように意識を失う直前、ティエンの輪郭が揺らめいたのが見えた。
実は気づいていたことが一つある。
伯父は、本当はいないということ。
両親が亡くなる前も、その後も、私は一度も伯父の姿を見たことがなかった。
学校の書類を整えるため戸籍を取り寄せたことがあったけれど、父にも母にも兄弟はいなかった。
でも怖いとか、嫌だとか、そんなことは思ったことがなかった。
私が両親と暮らした家に手紙を出すと、必ず返ってくる手紙。いつも私を心配して、私の成長を喜んでくれた「誰か」。
それが伯父でなかったとして、一体何がいけないというのだろう?
目覚めると、自室の布団の中だった。カーテンが開いていて、少し欠けた月が見える。
私はため息をついて言葉を口にする。
「ごめんなさい。倒れたりして」
「いいえ。それくらい、月華さんは月に影響されやすいんですよ」
風で舞い上がるカーテンを背に、枕元にティエンが座っていた。
私は困りながら問いかける。
「大丈夫ですか? 飛行機、行ってしまいましたか?」
「それでよかったんです」
ティエンの輪郭がまた揺れた。彼の声も少し、震えているようだった。
「月華さんに隠し事をし続けるよりは、その方がよかった」
私は起き上がって、彼を見上げる。
手を伸ばして彼の手を取ると、彼はびくりと緊張した。
「……天駆(ティエン・クー)」
そう呼びかけると、彼は目を見張る。
「忘れていてごめんなさい。家族で暮らしていた頃は、ずっとあなたのことをそう呼んでいたのに」
私は彼の手に頭をつけて、そのぬくもりに涙を落とす。
「ありがとう。両親が亡くなった後も私の側にいてくれて。手紙を送ってくれて。今まで気づかなくてごめんなさい」
彼は私の涙を拭って、首を横に振った。
ゆらりとティエンの輪郭が乱れた。
月明かりを浴びて、姿が変わっていく。黒い服は黒い毛皮に、すっと通る鼻筋は突き出た鼻に、その金色の瞳だけはそのままに。
「これが、私が伯父になりきれなかった理由です。私は月灯りを浴びると、時々姿を変えてしまう」
それは私のよく知る天駆だった。黒毛の立派な体躯で、お行儀よく座っている。
「人の姿になったり、犬の姿になったり。中途半端な魔法でしょう?」
天駆はもどかしそうに顔を伏せる。
「今回は三日間しか人になれなかった。いつも月華さんの助けになれたらいいのに」
彼が沈痛な面持ちになったのを見て、私は苦笑する。
「私だって月の満ち欠けに左右されている人間の一人です。人が操れない不思議な力だってあるのでしょう」
私は腕を広げて、今度は私から天駆を抱きしめる。
「月華さん?」
「それより大事なことをあなたに言っておかなければ。……私にとってあなたは」
温かなその体を抱きしめられる。その喜びが、触れたところから伝わればいい。
「家族であり、私をいつも守ってくれる騎士で」
顔を上げて、私は笑う。
「奇跡そのものだと思っています」
その首に頬を寄せて、私はぎゅっと彼を抱きしめた。
天駆は私の頬に、とんとんと二回自らの頬を当てた。私が泣いているとき、笑っているとき、彼を抱きしめると、いつも彼はその仕草をした。
どういう意味なのだろうと私が首を傾げると、天駆は優しい声で答えた。
「はい。私のお姫様」
月明かりが降り注ぐ。
それは私と彼を変えてしまうもの。けれど私たちをつないでくれた奇跡の光。
愛犬と魔法にかかった日常は、きっと永く続いていく。