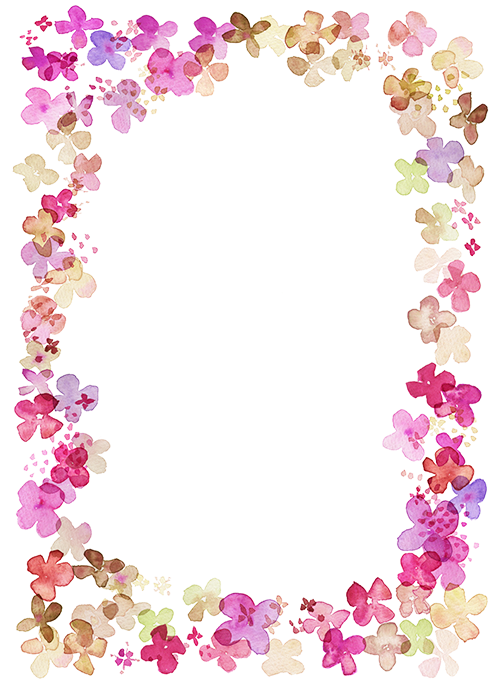子どもの頃の夢を見ていて、コンソメの湯気の匂いで目を覚ました。
野菜を切る規則正しい音、トースターの電動音、冷蔵庫を閉じる音に囲まれていた。いつもの何気ない音たちが、寝ぼけた頭を揺さぶる。
まだ眠っていたいなと思うのも、いつものこと。でも学校に行かなければいけない。そのためには自分で支度をしないと、誰も代わりはしてくれない。
「……え」
そこまで考えたとき、頭の後ろから叩かれたような違和感を抱く。
このアパートには私と愛犬しか住んでいない。
……誰が、朝ごはんを作っているの?
緊張に体を固くしながら起き上がると、私はパジャマのまま布団から抜け出る。
寝室兼居間のすぐ隣がキッチンだ。音を立てないよう、壁に身を寄せながら恐る恐る目をのぞかせる。
私がのぞき見たキッチンには、見知らぬ男がいた。
背が高くて、肩幅が広い男だった。黒いタートルセーターの上からでもわかる、鍛え抜かれた鞭のような体をしていた。
どうしようと爆発しそうな頭で考える。
こちらに背を向けているから、まだ気づかれてはいない。でも玄関に辿りつくまでに追いつかれてしまったら、力では敵わない。
とっさにいつも心に思うのは、一緒に暮らしている愛犬のことだった。
高校二年生になる私より大きな体を持つ、ごわごわした黒毛の雑種犬、天駆。朝起きたときから側にいてくれて、帰って来たら玄関まで飛んできてくれる。噛んだり吠えたりもしない、とても賢い子だ。
でもだからこそ一番に気づかなければいけなかった。いつも一緒に眠るはずの天駆が、朝起きたときに側にいなかった。
「……天駆」
不安で、怖くて、半分泣き声で、私は思わず天駆を呼んでしまった。
もちろんそんな不用意なことをしたら男の人は気づく。男の人が振り向くところが見えて、私は目をぎゅっとつぶった。
私の馬鹿。なんてことしたの、もうだめ。
真っ暗になった視界の中で、天駆の優しい金色の瞳が見えた気がした。
「はい?」
耳を打った低い返事に、私は硬直した。
私は「天駆」と呼んだはずだった。天駆は犬で、そしてもちろん人の声で返事はしない。
でも違う。今この家には、もう一人いる。
恐る恐る目を開いて、キッチンにいる男を見上げた。
私はそのとき、初めて振り向いた彼の顔を見た。精悍な眉の下にすっと通った鼻筋をしていて、硬い感じの黒髪、浅黒い肌の色をしていた。
少し金色に見える淡い茶色の瞳をした彼は……私と目が合うと、困ったように笑った。
「ごめんなさい。あの、突然のことで驚かれたでしょう」
彼は私より一歩離れたところで膝をつくと、とても低いけれど穏やかな声で話し掛けてきた。
「私、ティエンと申します。伯父様から頼まれて、昨夜こちらに参りました」
「伯父さんが?」
「手紙を預かっています」
よく見ると彼はエプロンをしていて、クマのプリントされたかわいい格好だった。拍子抜けした私は、一瞬まじまじと彼を見上げてしまった。
彼はエプロンの前ポケットから手紙を取り出して、私に差し出した。
『――月華さんへ。
月華さんが日本で一人暮らしを始めてから、もう五年になりますね。
月華さんは生理がひどく、月に一度は寝込むでしょう?
一人だとゆっくり休めないと、心配になって家人をよこすことにしました。
ティエンはひととおりのことはできますので、頼ってください。 伯父より』
手紙は確かに、月に一度欠かさず送られてくる伯父の筆跡だった。
読み終わった私は、ティエンを見上げて首を横に振る。
「大丈夫ですよ、ティエンさん。生理くらいで大げさです」
「いいえ」
ティエンは膝をついたまま、首を横に振る。
「昨日も下校途中でうずくまってしまったでしょう? 具合が悪いときは無理をしてはいけませんよ」
「い、いいんですってば!」
私はそんなところを見られていたと気づいて、恥ずかしさに真っ赤になる。
「私は一人でちゃんとやれます! 伯父にもそう伝えてください!」
思わず怒ってしまってから、私は息が切れてうつむいた。
お腹が引き裂かれるように痛くて、体から力が抜けていってしまう。
どうにも私は生理がひどい。医者にもかかったけど、良くはならなかった。生理用品を使っていても、服を汚してしまうくらいだった。
自分一人でしっかりやりたいのに、しっかりできない自分が情けない。
じわりと目がにじんだとき、空気が動いた。
「あ」
「あなたが覚えていない頃から」
ティエンはひょいと私を子どもみたいに抱えて、ぽんぽんと頭をなでる。
「ずっと、あなたは私のお姫様なのです」
頬に触れた肩の温もりがなんだか懐かしくて、とっさに抵抗できなかった。
ティエンは私を布団のところまで抱えていって降ろすと、慈しむような目で見下ろして言った。
「じきに朝食ができますよ。もう少し待っていてください」
「あ、あの!」
キッチンに入っていこうとする彼を呼びとめて、私はごくんと喉を鳴らす。
「天駆はどこにいったのですか?」
彼は安心させるように笑って答える。
「大丈夫。……じきに戻りますよ」
彼はそう言って、キッチンに戻っていく。
私はその後ろ姿を見ながら、今しがた感じたぬくもりを思い起こしていた。
野菜を切る規則正しい音、トースターの電動音、冷蔵庫を閉じる音に囲まれていた。いつもの何気ない音たちが、寝ぼけた頭を揺さぶる。
まだ眠っていたいなと思うのも、いつものこと。でも学校に行かなければいけない。そのためには自分で支度をしないと、誰も代わりはしてくれない。
「……え」
そこまで考えたとき、頭の後ろから叩かれたような違和感を抱く。
このアパートには私と愛犬しか住んでいない。
……誰が、朝ごはんを作っているの?
緊張に体を固くしながら起き上がると、私はパジャマのまま布団から抜け出る。
寝室兼居間のすぐ隣がキッチンだ。音を立てないよう、壁に身を寄せながら恐る恐る目をのぞかせる。
私がのぞき見たキッチンには、見知らぬ男がいた。
背が高くて、肩幅が広い男だった。黒いタートルセーターの上からでもわかる、鍛え抜かれた鞭のような体をしていた。
どうしようと爆発しそうな頭で考える。
こちらに背を向けているから、まだ気づかれてはいない。でも玄関に辿りつくまでに追いつかれてしまったら、力では敵わない。
とっさにいつも心に思うのは、一緒に暮らしている愛犬のことだった。
高校二年生になる私より大きな体を持つ、ごわごわした黒毛の雑種犬、天駆。朝起きたときから側にいてくれて、帰って来たら玄関まで飛んできてくれる。噛んだり吠えたりもしない、とても賢い子だ。
でもだからこそ一番に気づかなければいけなかった。いつも一緒に眠るはずの天駆が、朝起きたときに側にいなかった。
「……天駆」
不安で、怖くて、半分泣き声で、私は思わず天駆を呼んでしまった。
もちろんそんな不用意なことをしたら男の人は気づく。男の人が振り向くところが見えて、私は目をぎゅっとつぶった。
私の馬鹿。なんてことしたの、もうだめ。
真っ暗になった視界の中で、天駆の優しい金色の瞳が見えた気がした。
「はい?」
耳を打った低い返事に、私は硬直した。
私は「天駆」と呼んだはずだった。天駆は犬で、そしてもちろん人の声で返事はしない。
でも違う。今この家には、もう一人いる。
恐る恐る目を開いて、キッチンにいる男を見上げた。
私はそのとき、初めて振り向いた彼の顔を見た。精悍な眉の下にすっと通った鼻筋をしていて、硬い感じの黒髪、浅黒い肌の色をしていた。
少し金色に見える淡い茶色の瞳をした彼は……私と目が合うと、困ったように笑った。
「ごめんなさい。あの、突然のことで驚かれたでしょう」
彼は私より一歩離れたところで膝をつくと、とても低いけれど穏やかな声で話し掛けてきた。
「私、ティエンと申します。伯父様から頼まれて、昨夜こちらに参りました」
「伯父さんが?」
「手紙を預かっています」
よく見ると彼はエプロンをしていて、クマのプリントされたかわいい格好だった。拍子抜けした私は、一瞬まじまじと彼を見上げてしまった。
彼はエプロンの前ポケットから手紙を取り出して、私に差し出した。
『――月華さんへ。
月華さんが日本で一人暮らしを始めてから、もう五年になりますね。
月華さんは生理がひどく、月に一度は寝込むでしょう?
一人だとゆっくり休めないと、心配になって家人をよこすことにしました。
ティエンはひととおりのことはできますので、頼ってください。 伯父より』
手紙は確かに、月に一度欠かさず送られてくる伯父の筆跡だった。
読み終わった私は、ティエンを見上げて首を横に振る。
「大丈夫ですよ、ティエンさん。生理くらいで大げさです」
「いいえ」
ティエンは膝をついたまま、首を横に振る。
「昨日も下校途中でうずくまってしまったでしょう? 具合が悪いときは無理をしてはいけませんよ」
「い、いいんですってば!」
私はそんなところを見られていたと気づいて、恥ずかしさに真っ赤になる。
「私は一人でちゃんとやれます! 伯父にもそう伝えてください!」
思わず怒ってしまってから、私は息が切れてうつむいた。
お腹が引き裂かれるように痛くて、体から力が抜けていってしまう。
どうにも私は生理がひどい。医者にもかかったけど、良くはならなかった。生理用品を使っていても、服を汚してしまうくらいだった。
自分一人でしっかりやりたいのに、しっかりできない自分が情けない。
じわりと目がにじんだとき、空気が動いた。
「あ」
「あなたが覚えていない頃から」
ティエンはひょいと私を子どもみたいに抱えて、ぽんぽんと頭をなでる。
「ずっと、あなたは私のお姫様なのです」
頬に触れた肩の温もりがなんだか懐かしくて、とっさに抵抗できなかった。
ティエンは私を布団のところまで抱えていって降ろすと、慈しむような目で見下ろして言った。
「じきに朝食ができますよ。もう少し待っていてください」
「あ、あの!」
キッチンに入っていこうとする彼を呼びとめて、私はごくんと喉を鳴らす。
「天駆はどこにいったのですか?」
彼は安心させるように笑って答える。
「大丈夫。……じきに戻りますよ」
彼はそう言って、キッチンに戻っていく。
私はその後ろ姿を見ながら、今しがた感じたぬくもりを思い起こしていた。